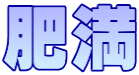 |
肥満抑制たんぱく質を発見 東京大の宮崎徹教授らのチームは肥満の原因となる「脂肪細胞」がためこむ脂肪を溶かす作用のあるたんぱく質を発見した。このたんぱく質を体内で作れないようにしたマウスは肥満になったが、逆に与えると肥満が改善された。人間でも同様の働きがあると考えられ、肥満症の治療薬開発などにつながる可能性がある。脂肪を溶かすことが分かったたんぱく質は、体内の免疫細胞で作られる血液中に含まれる「AIM」である。AIMを作れないように操作したマウスは脂肪細胞内に通常よりも多くの脂肪を蓄積して、正常なマウスと比べて体重が1.5〜2倍になった。しかし、このマウスにAIMを注射すると正常なレベルまで体重が減ったという。AIMは人間の体内にもあることが、すでに分かっている。肥満の人は、多くの脂肪を体内の脂肪細胞内にためこんで細胞が肥大化している。肥満が進むとAIMの血中濃度が高まって脂肪細胞の中に取り込まれ、細胞に蓄積された脂肪を溶かしていく。肥満が進んだときに体がAIMをたくさん作り、それ以上太らないようにする役割を担っていると考えられるという。AIMは脂肪細胞のみに作用するので副作用の心配も少なく、肥満症の治療薬開発につながる可能性があると研究グループではみている。(平成22年6月9日 日本経済新聞) 太り気味、やせ形より7年長生き 40歳時点の体格によってその後の余命に大きな差があり、太り気味の人が最も長命であることが、厚生労働省の研究班(研究代表者=辻一郎東北大教授)の大規模調査で分かった。最も短命なのはやせた人で、太り気味の人より6〜7歳早く死ぬという、衝撃的な結果になった。「メタボ」対策が世の中を席巻する中、行きすぎたダイエットにも警鐘を鳴らすものといえそうだ。研究では、宮城県内の40歳以上の住民約5万人を対象に12年間、健康状態などを調査した。過去の体格も調べ、体の太さの指標となるBMI(ボディー・マス・インデックス)ごとに40歳時点の平均余命を分析した結果、普通体重(BMIが18.5以上25未満)が男性39.94年、女性47.97年なのに対し、太り気味(同25以上30未満)は男性が41.64年、女性が48.05年と長命だった。しかし、さらに太って「肥満」(同30以上)に分類された人は男性が39.41年、女性が46.02年だった。一方、やせた人(同18.5未満)は男性34.54年、女性41.79年にとどまった。病気でやせている例などを統計から排除しても傾向は変わらなかった。やせた人に喫煙者が多いほか、やせていると感染症にかかりやすいという説もあり、様々な原因が考えられるという。体格と寿命の因果関係は、はっきり分かっていない。このため、太り気味の人が長命という今回の結果について、研究を担当した東北大の栗山進一准教授は「無理に太れば寿命が延びるというものではない」とくぎを刺す。同じ研究で、医療費の負担は太っているほど重くなることも分かった。肥満の人が40歳以降にかかる医療費の総額は男性が平均1521万円、女性が同1860万円。 どちらもやせた人の1.3倍かかっていたという。太っていると、生活習慣病などで治療が長期にわたる例が多く、高額な医療費がかかる脳卒中などを発症する頻度も高い可能性があるという。(平成21年6月10日 読売新聞) 体力、50歳は死亡率の指標 心筋梗塞などリスク低下 50歳のとき、速足(時速6.4キロ程度)での歩行に相当する身体活動が無理なくできる体力があれば、心筋梗塞などで死亡する危険性が低くなることを、筑波大の研究チームが突き止めた。20日発行の米医師会誌(JAMA)に発表した。同大の児玉暁研究員(内分泌代謝学)は「体力の有無が、将来の心筋梗塞などの発症や死亡の危険性を予測する指標として使えるかもしれない」と話している。研究チームは、日米欧で発表された心筋梗塞など冠動脈疾患の発症のほか、運動や死亡のデータが含まれる論文計1万679本、計10万2980人分のデータを解析。論文での追跡期間は1〜26年で、対象者の体力と、期間中の冠動脈疾患による死亡、それ以外の死亡を調べた。50歳の男性を体力が普通の群(時速6.4〜7.8キロ程度で歩行できる)、低い群(普通群以下)、高い群(時速7.9キロ程度以上で歩行できる)の3つに分けて比較したところ、低い群の冠動脈疾患による死亡率は普通群の1.4倍、高い群の1.47倍になった。すべての死亡率でも、低い群は普通群の1.7倍、高い群の 1.56倍と高くなった。普通群と高い群はほとんど差がなく、少なくとも普通群程度の体力があることが、冠動脈疾患や死亡の危険性を減らす可能性があるとみられる。40歳、60歳で比較しても、体力のある方が死亡や心筋梗塞などの危険性が低かった。女性の場合は、男性の約8割の体力で同様の結果が出た。曽根博仁・筑波大教授は「定期的な運動をすることによって寿命が延びるというデータはないものの、体力の有無が死亡率に影響を与えることが明らかになった」と話している。(平成21年5月21日 毎日新聞) お酢飲んでメタボ解消 酢を飲み続けると内臓脂肪が減ることを、ミツカン中央研究所(愛知県半田市)が成人対象の実験で確認した。長崎市で開かれる日本栄養・食糧学会で21日、発表する。実験は、肥満度を示す体格指数(BMI)が25〜30の「軽度肥満」に該当する成人男女175人(うち女性64人、平均44.1歳)を対象に実施。過度の運動を避けてもらうほかは通常の生活を送り、リンゴ酢を配合した飲料を1日2回、12週間飲み続けてもらった。腹部のコンピューター断層撮影(CT)画像による内臓脂肪面積の変化や体重などの変化を比較。データが得られた155人を分析したところ、1日30ミリリットル(酢酸量1500ミリグラム)摂取した群は内臓脂肪面積が平均約6.72平方センチ減り、腹囲は同1.85センチ減少。15ミリリットル(同750ミリグラム)摂取した群も減少した。酢を含まない飲み物を飲んだ群には変化が見られなかった。また、酢を摂取した群は、血中1デシリットルあたりの中性脂肪が28.2〜42ミリグラム減った。研究チームはこれまでに、酢の主成分である酢酸が脂肪の合成を抑え、燃焼を促進することを動物実験で確かめている。(平成21年5月15日 毎日新聞) 肝がんリスク、肥満は2倍超 厚生労働省研究班は高血糖や肥満などメタボリック症候群の関連要因を抱えている人について、肝臓がんにかかるリスクが2倍以上に高まるとの大規模疫学調査の結果を発表した。肝がんは大半が肝炎ウイルスに感染して発症するが、生活習慣に気をつければ発症を回避できる可能性があるという。井上真奈美・国立がんセンター室長が、40−69歳の男女1万7590人を13年間追跡調査。 期間中に102人が肝がんにかかった。調査開始時点の健診結果をもとに、血圧や血糖値、中性脂肪、体格指数(BMI)などのメタボリック関連要因が、肝がんリスクと関連するか調べた。高血糖(1デシリットル当たり140ミリグラム以上、または空腹時で同100ミリグラム以上)のグループは、そうでないグループと比較し、肝がんになるリスクが1.75倍になった。また肥満度を示すBMIが25以上の人は、そうでない人と比べて肝がんリスクが2.22倍になった。(平成21年3月10日 日本経済新聞) 太り過ぎでがん危険高まる 世界がん研究基金は太り過ぎが少なくとも6種類のがんを引き起こす危険性があると発表した。研究者は、がんの危険性を下げるためには体格指数「BMI」は25未満が望ましいとの考えを示した。報告書は1960年代以降の7000件以上の研究結果を分析。太り過ぎと、食道がんや膵臓がん、腎臓がんなどの間には明確な関連があると結論付けた。報告書は、わずかな体重超過でもがんの危険性が高まると警告。ベーコンなどの加工肉は腸がんの危険性が高まるため避けるべきだとし、食べる量は牛肉などの赤肉を週500グラム以内にすべきだと勧告している。ファストフードや甘い飲料、過度のアルコールも勧めないとしている。(平成19年11月1日 中国新聞) 早食いの子、肥満度が高い 食べ物を早食いする子供は、ゆっくり食べる子供に比べて肥満度が高いことが、東京歯科大とライオン歯科衛生研究所の共同研究で明らかになった。研究グループは5年前、早食いするサラリーマンほど肥満度が高いとする調査結果を公表していたが、小学生でも同様の傾向があることが浮き彫りになった。調査は食生活が激変しているとされる沖縄県八重山地区の小学5年生256人(男子137人、女子119人)を対象に、食生活など生活習慣を尋ねるとともに、身長と体重を測定。子供の肥満度の指標であるローレル指数(標準は116〜144)を使って、双方の関係を調べた。その結果、他人よりも食べるのが「はやい」と答えた子供の肥満度は平均141で、標準でも太り気味に近かった。一方、「ゆっくり」と答えた子供は平均125だった。また、一口で食べる量が「多い」と答えた子供の肥満度は平均139で、「少ない」と答えた子供の平均129よりも高かった。 反対に、「おやつの回数」や「夜食の有無」「運動する頻度」といった、一般には肥満との関連が指摘されている生活習慣は、今回の調査では、関連性がみられなかった。同大千葉病院の石井拓男病院長(社会歯科学)は「ゆっくりとよくかんで食べるといった、正しい食習慣を早くから身につけさせることが必要だ」と話している。(平成18年10月7日 読売新聞) 抗肥満物質、食欲抑制のたんぱく質発見 群馬大大学院の森昌朋教授らの研究グループは、摂食やエネルギー代謝を制御する脳の視床下部に直接働きかけて食欲を抑制するたんぱく質「ネスファチン1」を発見した。動物実験で既に、皮下脂肪型と内臓脂肪型の両方の肥満の解消効果を実証しており、「メタボリック・シンドローム解消の切り札として、できるだけ早く臨床での使用を目指す。正常体重の人の場合、脂肪細胞が分泌するたんぱく質「レプチン」の食欲抑制作用から肥満になりにくい。だが、肥満状態の人には、レプチンが作用しないことは以前から知られていた。森教授らは、脂肪細胞だけでなく、脳細胞で分泌する九つのたんぱく質から、レプチンと同様に視床下部に作用して食欲を抑制させる別のたんぱく質があることを発見し、「ネスファチン1」と名付けた。レプチンの作用しない肥満状態のネズミの脳髄液中にネスファチン1を注射して実験したところ、投与しないネズミと比べ、1日の摂食量は約30%減少、11日後の皮下脂肪は約20%、内臓脂肪は約30%減少させることが確認された。 今後、臨床使用までに、毒性実験など人体への副作用の有無を解明するなど課題は残っている。森教授は「同様の作用をするたんぱく質はこれまでにも数種類発見されているが、レプチンと同等の食欲抑制作用を有するものは、ネスファチン1だけ」と話している。(平成18年10月2日 毎日新聞) 拒食症の小児患者26人死亡 病院の小児科を受診した拒食症(神経性無食欲症)の患者が昨年は944人おり、過去に衰弱や自殺などで26人が死亡している。調査を担当した宮本信也筑波大教授は「かなり多く驚いた。受診者数も多いと言える。 予防のための健康教育が必要だ」としている。拒食症は、重度の体重減少に、体重が増えることへの恐怖などの精神症状が伴い、小学生の患者など低年齢化が進んでいるという。調査は、総合病院など小児科医を育成するための小児科研修病院569施設を対象に実施、294施設が回答した。昨年受診した拒食症患者は、初診が358人、再診が586人の計944人だった。「これまでに拒食症の死亡例の経験がある」と答えたのは24施設で、計26人。死因は衰弱や致命的な不整脈、心不全、自殺などだった。また、低身長や脳の委縮などの後遺症の恐れもある初潮前の女児患者は、過去に386人が確認された。病院側が苦慮している点は、鼻に入れた管や点滴による強制栄養療法を実施するかどうかの判断や、患者が隠れて嘔吐するなどの問題行動であることも分かった。今回の調査では、受診者、死亡者の年齢や性別は調べておらず、学会は発症のきっかけや治療経過、死亡の詳細について2次調査を近く始める。(平成18年9月19日 中国新聞) 「胆汁酸」やせる効果 肝臓でつくられ、食事のときに腸に流れ出る胆汁の成分が、エネルギーの消費を活発にさせる働きを持っているという研究結果を、仏ルイ・パスツール大の渡辺光博研究員らが動物実験などで示し、英科学誌ネイチャー電子版で発表した。新しいやせ薬の開発につながる可能性も考えられる。渡辺さんらが注目したのは胆汁の主な成分である胆汁酸。脂肪分の多いエサと一緒にマウスに与えると、与えないマウスと比べて体重の増加が抑えられた。体の組織を比較すると、褐色脂肪でエネルギーを盛んに消費していた。遺伝子操作したマウスなどを使ってさらに分析すると、胆汁酸は褐色脂肪細胞の中にある酵素に働きかけるなどして、エネルギー消費などにかかわるホルモンの働きを活発にしていた。人の筋肉の培養細胞で調べると同じ働きが見られた。 胆汁酸はコレステロールを材料につくられ、小腸で脂肪を吸収する働きを助けている。胆汁酸そのものを人が摂取すると、悪玉コレステロールの値が上がってしまうので、直接、薬にするのは難しいが、渡辺さんは「胆汁酸と同じような働きをする物質を特定できれば、肥満を防ぐ薬につながる可能性がある」と話す。(平成18年1月13日 朝日新聞) 女性の足、太くていい 心臓病にならないためには、減量はしても足は細くしない方がいい。筑波大人間総合科学研究科の大蔵講師らが成人女性を対象に行った健康調査で、そんな結果が出た。腹部の内臓脂肪とは違い、足にある脂肪には心臓病を防ぐ働きがあるらしい。肥満気味の女性のための減量プログラムに参加した128人を対象に、体重や血圧、総コレステロール値などのほか、X線を使った装置で胴体や腕、足の体脂肪量の変化を調べた。減量は食事のカロリーを制限したうえ、有酸素運動を週に3回するなどした。14週間後、参加者の体重は平均で8キログラムほど減った。うち7キロ近くは体脂肪だった。血圧や中性脂肪の値など、心臓病のリスクを予測する指標は、胴体の脂肪がたくさん減るほど改善した。ところが、ももやふくらはぎなど足全体の脂肪については、少ししか減らない人の方がより改善する傾向だった。足の脂肪は平均2.1キロ減っていたが、例えば、脂肪の減り方が30グラム少ないと、最低血圧(拡張期血圧)が1ミリHg(ミリ水銀柱)低くなる計算だという。足の脂肪から、動脈硬化などを防ぐホルモンが出ている可能性が考えられている。大蔵さんは「内臓脂肪を落とすことが大切。健康の面からは『足やせ』はしない方がよさそうです」という。(平成17年12月12日 朝日新聞) 内臓脂肪症候群、日本人の8% 動脈硬化などにつながるとされる状態「メタボリックシンドローム」(内臓脂肪症候群)になっている人は、20歳以上の日本人の約8%を占めると推定され、小食や運動、禁煙、趣味によるストレス解消など健康的な生活習慣を多く持つ人ほどこの状態に陥る率は低いことが、東京慈恵会医大(東京都港区)健康医学センターの和田高士センター長らの研究で分かった。 大阪市で開催中の日本脈管学会で2日に発表する。メタボリックシンドロームは、男性はウエスト85センチ以上、女性は90センチ以上で、さらに(1)中性脂肪などの異常(2)高血圧(3)高血糖−−のうち2項目以上を満たす状態だ。それぞれの異常は軽くても、重なることで動脈硬化を起こしやすくなるという。和田センター長らは、00年1月から04年12月までの5年間に、同大で人間ドックを受けた男女計2万2892人について、メタボリックシンドロームだったかを調べた。 同時に「禁煙」「過食をしない」「飲酒は日に1合以下」「週に1回以上運動する」「仕事をしない日が月に6日以上ある」「打ち込める趣味がある」の6項目の「よい生活習慣」について、それぞれ実行しているかどうかをアンケートした。日本人の年齢分布などを考慮して結果を分析すると、メタボリックシンドロームの人は、成人男性の14%、成人女性の2.9%、平均では8.4%と推定された。「よい習慣」の実行数別にみると、受診者のうち、一つも実行していない人は、シンドロームに陥っている率が約21%に達した。しかし、実行数が一つ増えるごとに、率は2ポイント余り低下し、六つとも実行している人は7.2%だった。和田センター長は「メタボリックシンドロームは、生活習慣の改善でかなり防げる。高血圧など個々の異常を薬に頼って治す前に、複数の異常の共通原因となる生活習慣を変えてほしい」と話している。(平成17年12月2日 毎日新聞) 食欲抑制ホルモン、ラットの胃で発見 食欲を抑制する作用がある新たなホルモンを米スタンフォード大のチームがラットの胃で発見、「オブスタチン」と名付け、11日付の米科学誌サイエンスに発表した。オブスタチンは、日本で発見された食欲促進ホルモン「グレリン」ともとになる遺伝子が共通なのに、機能はほぼ正反対。こうした例は非常に珍しい。二つのホルモンの役割を解明することで、先進各国で深刻な問題になっている肥満の治療薬開発につながる可能性がある。チームはグレリンの遺伝子や、グレリンのもとになる前駆体のアミノ酸配列を、人間やマウスなど約10の哺乳(ほにゅう)類について調べ、同じ遺伝子からグレリンとは別のタンパク質がつくられている可能性が高いと予測。そしてラットの胃から予測通りにオブスタチンを発見した。合成したオブスタチンをラットに注射したところ、餌を食べる量が減ったうえ、消化にも時間がかかり、体重増加のスピードが鈍くなった。人間でも同様の効果があるかどうかの確認はこれからだという。(平成17年11月12日 毎日新聞) グレープフルーツの香りで脂肪燃焼 グレープフルーツの香りをかぐことで脂肪が燃焼されることが、大阪大蛋白質研究所の研究で裏付けられ、13日、札幌市で開催されている日本肥満学会で発表された。これまでもグレープフルーツの香りにダイエット効果があるといわれてきたが、科学的な証拠はなかった。一方、ラベンダーの香りは正反対の作用を及ぼし、脂肪を蓄積させることも、同じ研究で明らかになった。永井教授らは、グレープフルーツから抽出した精油を10分間、実験用ラットにかがせた。その結果、脂肪が分解され血中のグリセロール濃度が2倍以上になった。また、体温が上昇し脂肪が燃焼されていることが分かった。同時に、交感神経の活動が弱まり食欲を低下させ、においをかいだラットはかいでないラットと比べ、体重が約5%減った。永井教授は「体温が上がることなどは人間でも分かっている。ただ、体内時計が乱れると効果がなくなるので、規則正しい生活を送ることが大切。またかぐ量にも注意する必要がある」と話している。(平成17年10月13日 産経新聞) やせ、肥満より死亡率高い 日本人の中高年では、男女ともにやせた人の方が肥満や標準体格の人より死亡率が高いとする結果を、鈴木庄亮群馬産業保健推進センター所長や群馬大学医学部のグループが約1万1000人を対象にした調査でまとめ、31日発行の日本疫学会誌に発表した。男性については同様の結果を厚生労働省研究班が2002年に発表しているが、今回は女性でも同じ傾向がみられた。若い女性でやせた人が増えていることから、鈴木所長は「栄養が足りなければ感染症に対する抵抗力が減る。将来に備えてバランスの良い食事を心がけ、やせ過ぎに注意してほしい」と話している。1993年に群馬県内の40−60代の男女に身長、体重、生活習慣などを尋ね、以後7年間追跡して死亡率を調べた。体重(キロ)を身長(メートル)の2乗で割った体格指数(BMI)が標準的(22−24・9)な人に比べ、やせとされる18・5未満の人は、死亡率が男性で2・59倍、女性では2・93倍高かった。 BMI28以上の肥満の男性は1・63倍、女性は2・71倍で、男女ともにやせの死亡率の方が肥満を上回った。がんや循環器疾患などの死因別に見た場合や喫煙者を除いた場合でも、同様の傾向を示した。 02年の厚労省国民栄養調査によると、20−30代の女性でBMIが18・5未満の人の割合は、この20年で約2倍になっている。(平成17年5月31日 産経新聞) 心筋梗塞、ウエストに注目 内臓脂肪のたまり具合をウエストサイズで判断する診断基準を、日本動脈硬化学会や日本糖尿病学会など8学会がまとめた。男性は85センチ、女性は90センチ以上だと「要注意」だという。大阪市で開催中の日本内科学会で8日、公表された。 脂肪のたまり方には皮下脂肪型と内臓脂肪型がある。内臓脂肪がたまると血糖や血圧、中性脂肪などが正常より高めになる。糖尿病や高血圧と診断されるほどではなくても、複数重なると動脈硬化が進行し、心筋梗塞につながることがわかり、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)と呼ばれるようになった。だが、内臓脂肪の量はX線CT(コンピューター断層撮影)写真を撮らないとわからず、明確な診断基準がなかった。 今回まとまった診断基準は、「要注意」のウエストサイズで、(1)中性脂肪が150ミリグラム以上(血清0.1リットル中)またはHDLコレステロールが40ミリグラム未満(同)(2)最大血圧が130以上または最小血圧が85以上(3)空腹時血糖値が110ミリグラム以上(血漿(けっしょう)0.1リットル中)――の3項目のうち2項目以上に当てはまるとメタボリックシンドロームとした。 食事に気を付け、運動を心がけるなど生活習慣を改善すれば、心筋梗塞の危険性は減らせるという。 基準づくりの中心となった住友病院(大阪市)の松沢佑次病院長は「血糖や血圧などが少し高いだけだと放置していた人を見つけ出し、生活習慣の改善につなげるのが大切だ」と話している。 (平成17年4月8日 朝日新聞) 肥満防止のたんぱく質発見 肥満を防ぐのに役立ちそうなたんぱく質を、慶応大学と山之内製薬の共同研究グループが発見し、21日付の米科学誌ネイチャー・メディシン電子版に発表した。糖尿病を防ぐ作用もあり、将来のやせ薬や血糖を下げる薬の開発につながる可能性があるという。 このたんぱく質は、血管が新たに伸びるのを促す因子として、同グループが人間の血液中にあることを03年に見つけ、AGFと名付けたもの。 AGFを作れないようにしたマウスに普通にえさを与えると、生後半年で通常マウスの約2倍の体重になり、内臓脂肪も著しく増えた。血糖値の調節もうまくできなくなり、糖尿病のような状態に陥った。 逆にAGFを多くつくれるマウスは、体重は通常の4分の3程度の「やせ」になり、解剖すると内臓脂肪が少なかった。さらに、高カロリー食を与えても肥満や糖尿病にならなかった。 AGFの働きは、肥満にかかわる従来知られている生理活性物質とは違うことも確認された。グループの尾池雄一・慶応大講師は「AGFそのものを人間に投与できる段階ではないが、詳しく作用を解明し、将来の治療薬の開発につなげたい」といっている。(平成17年3月21日 朝日新聞) 肥満の人は歯周病にご注意 肥満者は歯周病に約1.5倍かかりやすい。こんな結果を大阪府立看護大の吉田幸恵教授や今木雅英教授らの研究グループがまとめた。 歯周病の危険因子は加齢、糖尿病、喫煙習慣などが知られる。研究グループは、大阪府内の事業所に勤める「糖尿病ではない」20〜59歳の男性1470人について調べた。体重(キロ)を身長(メートル)で2回割ったBMI(体格指標)が18.5未満の人を低体重者、25以上を肥満者、その間を普通体重者とし、唾液(だえき)中の血液濃度で歯周病を判定した。その結果、肥満者(388人)で16.75%、普通体重者(1033人)で11.52%がかかっていた。年齢や喫煙習慣を考慮すると、肥満者は歯周病に普通体重者より1.49倍かかりやすくなり、統計的に明確な差があった。年代ごとにみても、肥満者の罹患(りかん)率が上昇した。脂肪から分泌する物質が骨を壊すなどして歯周病につながる、と考えられ、吉田さんは「肥満が歯周病の危険因子の一つである可能性が見いだされた」といっている。(平成17年1月19日 朝日新聞) 睡眠不足は肥満のもと 米研究「危険、最大7割増も」 睡眠時間が短い人ほど太る傾向が強く、最大で73%も肥満の危険が増す。そんな研究結果を米コロンビア大のチームがまとめ、18日まで開かれていた北米肥満学会で発表した。米政府の健康栄養調査に参加した1万8000人(32〜59歳)のデータを分析。睡眠が7〜9時間の人に比べ、4時間以下しか眠らない人は73%も肥満の危険度が高かった。 睡眠5時間程度の人でも50%、6時間程度では23%、それぞれ太りやすかった。 睡眠不足だと、体内で食欲を抑える物質レプチンが減り、逆に、高める物質グレリンが増えるとされる。 起きている時間が長ければ食べ物を口にする機会も多く、こうした体内状態が食べ物の摂取を促進するらしい。起きている時間が長いと消費カロリーも多いものの、摂取が消費を上回っている実態が、今回の大人数のデータから浮かび上がった。 研究チームは「生物は食物の豊富な夏季に栄養を蓄え、冬に備える。睡眠時間が短い人の体は、夜が短い夏と同様の状態が続くので太りやすい」と見ている。(平成16年11月19日 朝日新聞) リンゴのポリフェノール、筋力増強や脂肪減少の効果 アサヒビールと日本体育大学大学院の中島寛之教授らの共同研究で、リンゴから抽出されるリンゴポリフェノールに筋力を増し、内臓の脂肪を減らす働きがあることが明らかになった。 赤ワインや黒豆などに含まれるポリフェノールは老化やがんの要因とされる活性酸素を除去する働きが知られているが、筋力増強や脂肪減少などの効果が明らかになったのは初めてという。 アサヒは、年内にも人を対象とした実験で効果を確かめ、早ければ2005年にもサプリメントや飲料などでの商品化を目指す。リンゴのポリフェノールは果肉にもあるが、特に皮の部分に多く含まれているという。アサヒと中島教授らは、リンゴポリフェノールを5%混ぜた固形エサを3週間与えたマウスと、普通の固形エサを与えたマウスを比較した。その結果、ポリフェノール入りを食べたマウスは、普通のエサのマウスより筋力が16%高く、内臓脂肪は27%少なかったという。 アサヒは、ポリフェノールに内臓脂肪の分解を助ける働きがあるとしているが、筋力アップのメカニズムは、よく分かっておらず、今後の研究課題という。 アサヒは「筋力アップや体脂肪率抑制が必要な運動選手に効果が期待できる」としている。(平成16年10月4日 読売新聞) 早食い、「肥満の元」 国立健康・栄養研究所などの研究グループが全国の女子大生を対象に実施した大規模調査で、早食いの人ほど太っている傾向があることが明らかになった。とても速く食べる人は、とても遅く食べる人より平均5キロ以上、体重が重かった。「早食いは肥満の元」という言い伝えが実証される結果となった。調査は97年に全国22大学の18歳の女子大生を対象に実施した。食べる速さのほか、身長・体重、食事の内容、生活習慣について聞いた。回答した1744人のうち、摂取カロリーが過多や過少な人、生活習慣についての回答が不十分な人を除く1695人分のデータを数年がかりで解析した。食べる速さは「とても遅い」「比較的遅い」「普通」「比較的速い」「とても速い」の5段階で、自己申告してもらった。申告の確からしさを調べるため、1大学(222人)で友人にも評価してもらったところ、9割以上が本人の申告とほぼ一致した。解析の結果、身長と食べる速さとの相関関係がなかった一方、「とても速い」と答えた人の平均体重は55・4キロ、「とても遅い」は49・6キロで、5・8キロの差があった。体重(キロ)を身長(メートル)の2乗で割った体格指数BMIは「とても速い」が22・0、「とても遅い」が19・6で、ゆっくり食べる人ほどやせている傾向があった。1日当たりの摂取カロリーは早食いの人ほど多く、摂取カロリー当たりの食物繊維の量は遅食いの人ほど多かった。また、早食いの人ほどダイエットに取り組んだ経験のある割合が高かった。運動習慣やたばこなどの生活習慣と食べる速度との関連はなかった。 研究は「生活習慣や運動量などのばらつきが少ない」との理由から女子大生を対象にした。 同研究所の佐々木敏・栄養所要量企画・運営リーダーは、遅食いの人ほど食物繊維の摂取量が多いことに注目し、「早食いの人たちは、食物繊維の少ない速く食べやすい食事をしているため、満腹感を感じる前に必要以上に食べてしまうのではないか」と話している。(平成16年8月23日 毎日新聞) 朝食をとった方がやせる 「朝食をきちんととった方がやせる」といわれる。米厚生省は88〜94年、朝食をとっているかどうかと、朝食の品目について、1万6000人以上を対象に調査した。 その結果、肥満度の判定に使う体重(キロ)を身長(メートル)の2乗で割った体格指数「BMI」は、朝食をとっていない人の方が高い傾向になった。食事内容では、朝食で穀類・米を中心にとっている人のBMIが最も低かった。従来の和食の朝食は「理想の朝食」といえそうだ。シリアル類、果物・野菜を中心にとっている人のBMIも、朝食をとっていない人より低かった一方、乳製品や肉・卵が中心の人のBMIは、朝食をとっていない人より高かった。ニュージーランドなどの研究者の論文によると、食事回数と体重に明確な関係はなかった。国立健康・栄養研究所の佐々木敏・栄養所要量策定企画・運営担当リーダーは「食事をいつ、何回食べるかよりも、何をどれくらいの量食べるかが大切だ。 摂取エネルギーも、1週間単位くらいで過不足なくとることを心がけてほしい」と話す。寝る前の食事については、「夜は消化機能をつかさどる副交感神経が優位に働くため、食べたものの吸収が高まり、肥満につながる」との説がある。しかし、米国の研究チームは昨年、サルを使った実験で、食事をとる時間と体重増に相関関係はなかったと発表した。「摂取するエネルギー量が問題であり、寝る前に食べると太るというのは伝説にすぎない」としている。(平成16年8月7日 毎日新聞) 肥満に関与のホルモンを発見 大阪大学未来医療センターの下村伊一郎教授らは肥満に関与するとみられるホルモンを見つけた。肥満は糖尿病や動脈硬化の一因になるが、このホルモンの血中濃度を調整する物質が見つかれば、糖尿病などの治療薬になる可能性があるという。体の運動や姿勢を保つのに使う骨格筋という筋肉が分泌するホルモン「ムスクリン」が、肥満にかかわることを突き止めた。骨格筋には体内の糖分を調節する働きがあるため、肥満に関係があると想定。肥満したネズミを調べたところ、骨格筋からムスクリンが多く分泌されていた。 ムスクリンの量が多いほど、血液中の糖を分解するインスリンの機能が低下する可能性があることも実験で判明。 薬物でムスクリンの量を抑えれば、肥満を予防でき、糖尿病などの発症も未然に防げるという。(平成16年5月10日 日本経済新聞) リンゴ食べれば太らない リンゴに含まれるポリフェノールに、脂肪が体内に蓄積されるのを抑える効果があることが、アサヒビールと弘前大の長田恭一助教授のグループの共同研究で明らかになった。これまで報告されていた、がんなどの予防効果に加え、生活習慣病の予防にも期待できるという。28日から始まる日本農芸化学会(広島市)で発表される。研究では、ラットを6匹ずつのグループに分け、それぞれ普通のエサ、高脂肪のエサ、リンゴポリフェノールを配合した高脂肪のエサなどを、量に差が出ないように10週間与え、観察した。内臓の脂肪の重さを比べたところ、高脂肪のエサを与えられたラットは、普通のエサを与えられたものより9割近く増えたのに対し、リンゴポリフェノールを加えたエサを食べたラットは5割程度の増加にとどまった。脂肪を燃焼する肝臓内の酵素が活発になる一方、脂肪を合成する酵素の働きが低下したという。長田助教授は「生活習慣病の予防に有望なことが解明されつつあり、人間への応用も期待できる」と話す。アサヒビールはリンゴから抽出したポリフェノールを清涼飲料やあめ、化粧品などの原料として95年に商品化。今後商品を増やすことを検討している。(平成16年3月26日 朝日新聞) 危険な肥満の徴候はBMIよりウエストサイズ 高血圧、高脂血症、メタボリックシンドロームの予知因子としては、BMIよりも腹囲(ウエストサイズ)の方が優れているとする解析を、カナダQueen's大学のIanJanssen氏らがAmerican Journal of Clinical Nutrition誌2004年3月1日号で報告した。米国の横断調査「NHANES III」を解析した結果だ。NHANES(全米健康・栄養調査)IIIは1988年から1994年にかけて行われた3万3199例に対する横断調査だが、今回Janssen氏らは、そのうち、ウエストサイズと代謝の各種指標が記録された、17歳以上でBMI18.5〜34.9の1万4924例を対象に、高血圧、高脂血症、メタボリックシンドロームの有症率と、BMI、ウエストサイズの関連性を検討した。 高血圧の定義は米国の高血圧ガイドラインであるJNC7、高脂血症とメタボリックシンドロームの定義は、米国の脂質管理ガイドラインのATP IIIに従った。まず、BMIが18.5〜24.9を「正常体重」、25〜29.9を「太り過ぎ(過体重)」、30.0〜34.9を「クラス1肥満」として上記疾患の有症率を比較すると、正常体重群に比べて太り過ぎ群とクラス1肥満群では、高血圧、高コレステロール血症、低HDLコレステロール血症、高トリグリセライド(TG)血症の有症率が、男女を問わず有意に多かったが、高LDLコレステロール血症は女性でのみ有意に多かった。これは年齢、人種、喫煙、アルコール摂取と経済的状況で補正した結果だが、これに加えてウエストサイズで補正すると、太り過ぎと男性の高TG血症、同女性の高コレステロール血症以外は、正常体重群に比べて有意な増加を示さなかった。 次に、BMIとウエストサイズが上記疾患の予知因子となっているかどうか、ロジスティック回帰分析を行った。BMI、ウエストサイズとも、それぞれ単独では有意な予知因子だったが、BMIとウエストサイズを同時に変数とすると、ウエストサイズは、男性の高コレステロール血症、高 LDLコレステロール血症以外、すべての疾患に対して有意な予知因子だったのに対し、BMIが有意な予知因子となっていたのは男性の高血圧だけだった。 すなわち、BMIを基準とした正常体重、太り過ぎ、クラス1肥満のどれに属していても、ウエストサイズが同じであれば、男性の高血圧、高コレステロール血症、高LDLコレステロール血症以外のリスクは同等ということになる。 J anssen氏らは、ウエストサイズを用いたリスクの層別化とその有用性の検証が必要だとしている。(平成16年3月8日medwave) WHOが肥満の定義めぐり新勧告 世界保健機関(WHO)専門家会議はこのほど、肥満の国際分類に関する新たな勧告を取りまとめ、Lancet誌1月10日号で発表した。体格指数(BMI)が25以上を過体重、30以上を肥満とする国際分類に変更の必要はないものの、アジア諸国では「より低いカットオフ値」が適切な場合もあると結論。国によっては国際基準とは異なる分類値を用いてもよいとした。専門家会議では、ピマ・インディアンや台湾人、在米日本人などでは、BMIが比較的低いのに2型糖尿病などの発症率が高いと報告されている点に着目。 アジア人の疫学データを解析し、心血管疾患のリスクが高まるBMIカットオフ値を検討した。その結果、BMIが同じでも、アジア人では白人より体脂肪率が高い傾向があることが判明。香港やシンガポールでは、心血管疾患リスクがやや高まる「過体重」のカットオフ値がBMI22〜23、ハイリスクとなる「肥満」のカットオフ値がBMI27程度とみなせることがわかった。ただし今回の検討では、例えば日本人の「過体重」カットオフ値はBMI24〜25、「肥満」はBMI29〜30となり、WHOの国際分類基準とほぼ同じ水準となった。つまり、アジアでも国によりカットオフ値が異なることが示唆され、「一律引き下げ」を支持するだけのデータはないことも判明した。以上から専門家会議は、現行の国際分類を、現時点で変更する必要はないと結論。ただし、アジア諸国では、公衆衛生的・政策的な必要性に応じ、WHOの国際分類に含まれないカットオフ値を用いてもよいと勧告している。わが国では日本肥満学会が、BMI25以上を「肥満」、BMI25以上で2型糖尿病など肥満関連疾患がある場合や内臓脂肪が多い場合などを「肥満症」と定義しており、「肥満症」に対する治療ガイドラインの策定を進めている。日本独自のエビデンスに支持されたガイドラインだが、世界に向けた情報発信も一層必要な時代が来たと言えそうだ。平成16年1月13日medwave) ミカンの内皮に減量効果? 温州ミカンやイヨカンの果肉を包む内皮に、脂肪を分解し、体内への吸収も抑える働きがあることがわかったと、ポンジュースを製造しているえひめ飲料(松山市)と愛媛大総合科学研究支援センターの辻田隆広助教授が8日、発表した。 両者の共同研究によるもので、えひめ飲料は「ダイエットにもつながる」として、内皮を使った商品開発を目指している。脂肪は消化酵素を使って分解され、体内に吸収される。試験管に内皮を入れ消化酵素の働きを調べたところ、内皮を多く入れた方が働きが弱まることが確認できた。 内皮に含まれる食物繊維の一種、ペクチンが作用している可能性があるという。 ラットの脂肪細胞を入れた試験管実験では、内皮の抽出液を加えると脂肪の分解が進むことがわかった。皮下脂肪よりも内臓脂肪への効果が高かったという。 えひめ飲料はジュースを搾る際に出るかすに内皮が多く含まれていることに着目。 内皮だけを取り出す技術を開発した。 今後、加工した内皮をジュースやパンなどに交ぜた商品の開発にも乗り出す。(平成15年10月8日 朝日新聞) 結腸がん、肥満女性は「死亡リスクが高い」 女性は肥満の度合いが高いほど、結腸がんで死亡する危険性が高くなるとの疫学調査結果を、名古屋大大学院の玉腰浩司講師(公衆衛生学)らがまとめた。一方、男性では、肥満と結腸がんとの間に明確な相関関係はみられなかった。25日から名古屋市で開催される日本癌(がん)学会で発表する。調査には国内の24研究機関が参加した。1988〜90年に40〜79歳だった全国の男女約10万人の身長、体重などを調べ、対象者を99年まで追跡した。その間に結腸がんで死亡した249人を特定し、肥満の判定基準(BMI)との関係を分析した。BMIは体重(キロ)を身長(メートル)の2乗で割った数値で、22が「標準」、25以上が「肥満」、18.5未満が「やせ」と判定される。分析の結果、BMIが28以上の女性は、BMIが20以上22未満の女性に比べ結腸がんで死亡する危険性が3・41倍になっていた。26以上28未満の場合も同2.27倍、24以上26未満の場合も同2.23倍になった。20歳のころにBMIが高かった女性や、20歳を過ぎてからBMIが大きく増加した女性も結腸がんで死亡する危険性が高まるとの結果も出た。食生活の欧米化が結腸がんの増加につながっているとされるが、玉腰講師は「女性だけがこのような結果になった理由はよく分からない。 これからの研究課題だ」と話している。(平成15年9月24日 毎日新聞) 日本の子供 米並み肥満 日本の子供たちは、米国の子供たち並みに太ってきており、心臓病や糖尿病になる危険が増えている米疾病対策センター(CDC)が、こんな調査結果をまとめた。 調べたシファン・ダイ研究員は「日本の子も食事や運動に注意する必要がある」と警告している。 調査は、新潟県新発田市の7―15歳の子供369人(男子199人、女子170人)を対象に、1991年―95年に行われた。その結果、血液中の総コレステロールは、男子が1デシ・リットルあたり平均約167ミリ・グラム、女子が同173ミリ・グラムで、米国の白人の子供に比べてやや高かった。 皮下脂肪の厚さや、身長と体重から計算される肥満度は、米国の子供と同程度だった。 ダイ研究員によると、過去の調査では、日本の子の肥満度は米国の子に比べて格段に低かった。 今回の調査も、日本では米国より心臓病患者が少ない理由を、子供の時期から探るのが目的だったが、逆に日本の子供の肥満傾向が明らかになってしまったという。(平成15年6月14日読売新聞) 特殊たんぱく質、血糖値を下げ、脂肪を燃焼 血糖値を下げ、脂肪を燃焼させる特殊なたんぱく質を、東京大大学院の門脇孝・助教授や山内敏正医師(糖尿病代謝内科学)らの研究グループが発見し、12日発行の英科学誌「ネイチャー」に発表した。 運動しなくても、飲むだけで糖尿病を治療できる新薬開発につながると期待される。 過食による肥満や運動不足などが原因となる糖尿病は、2型糖尿病といわれる。 血糖値を下げるインスリンホルモンがうまく機能しなくなり、血糖値が高くなる。 糖尿病患者を対象にしたこれまでの研究で、脂肪細胞から分泌される「アディポネクチン」というホルモンに、インスリンの働きを高め、脂肪酸の燃焼を促進する作用があることが分かっていた。 研究グループは、今回、アディポネクチンと結びついて働くたんぱく質を人とマウスの筋肉や肝臓で調べ、2種類の特定に成功した。 いずれも細胞の表面にある受容体たんぱくで、このたんぱく質を活性化できれば、糖尿病の改善につながる。 門脇助教授は「糖尿病の治療には食事制限や運動が必要だが、肥満の人はひざに負担がかかるため運動が難しい。今回の研究は、つらい運動をしなくても治療が可能な薬の開発に役立つ」と話す。(平成15年6月1日 毎日新聞) TVよく見る人ほど肥満、視聴時間が増えるほど危険度も高く テレビの視聴時間が長い女性ほど、肥満や糖尿病になる危険度が増すことが、米ハーバード大の研究チームが約5万人に行った調査でわかり、米国医師会雑誌に掲載された。 テレビを見ながら菓子をつまんでいると太る、とよく言われるが、大規模な調査で裏付けられたのは初めて。 約5万人の女性看護師のうち、6年間の調査期間中に肥満になったのは約3700人。 テレビを見る時間が週1時間未満で肥満になる危険度を1・0とすると、週に2―5時間の人は1・23、6―20時間で1・42、21―40時間は1・68、40時間以上のグループでは2・0となり、視聴時間が増えるほど危険度も高くなった。 年齢、喫煙、飲酒、食事など肥満に影響を与える他要因を考慮すると、1日当たりの視聴時間が2時間増えるごとに危険度は23%アップすることがわかった。 糖尿病が発症する危険度も視聴時間が増えるとともに高くなった。 原因について研究チームは、視聴時間が長いほど、体を動かさないためエネルギー消費が減り、食べ物のコマーシャルなどの影響でさらに食べる量が増えるためではないかと見ている。(平成15年5月6日 読売新聞) 子ども肥満原因、3歳時の生活慣習 子どもの肥満は、3歳時の生活習慣の乱れが原因――そんな研究結果を、富山医科薬科大などの研究チームがまとめた。子どもたち約1万人を7年間追跡調査して分かった。小児肥満は、大人になってからの心疾患や高血圧の原因とされ、関根道和・同大講師は「乳児からの予防策が大切なことを裏付けた」と話している。 調査は、富山県内の1989―90年生まれの約1万人を対象に、3歳時、小学1年時、4年時の3回にわたり体格測定を行い、同時に子どもたちの両親に生活習慣、家庭環境についてアンケートを実施。国際的な基準で「肥満」とされた子、そうでない子の両グループのデータを比較した。 すると、3歳時に「朝食を時々食べる」「おやつの時間を決めていない」と答えたグループは、「朝食を毎日食べる」「おやつの時間を決めている」グループより、小学4年時に肥満になる例が1・2―1・8倍多かった。また、3歳時に、睡眠時間が11時間以上だったグループに比べ、9時間未満のグループは、肥満が約1・5倍多くなり、睡眠量が少ないと肥満になりやすいことも判明。国民栄養調査(97年)によると、小中学生の約10・7%が肥満で、78年の7・2%から増加傾向にある。(平成15年2月1日 読売新聞) 男性の肥満者は20年前の約1.5倍に、40歳未満の女性はやせている人が増加 厚生労働省は12月11日、「2001年国民栄養調査結果」の概要を公表した(2001年11月に1万2481人(男性5852人、女性6629人)を対象に調査)。体脂肪指数(BMI)が25以上の肥満者の割合は、20歳以上の男性では、いずれの年代でも20年前の1.5倍前後増えていた。年代別の肥満者の割合は、20歳代は18.1%、30歳代は29.0%、40歳代は31.8%、50歳代は31.6%、60歳代は31.3%、70歳以上は21.0%だった。一方、女性では、60歳未満のいずれの年代も、肥満者の割合は20年前より低くなっていた。BMIが18.5未満の低体重(やせ)の人の割合は、男性はいずれの年代も1割未満で、20年前と比べるとわずかに減っていた。しかし、女性は20歳代と30歳代で低体重者が大きく増えていた。20歳代は20.0%、30歳代は16.0%で、それぞれ20年前の1.6倍、2.0倍だった。また、エネルギー摂取量に占める脂質からのエネルギー割合である、脂質エネルギー費については、若いほど高くなる傾向がみられた。全体では25.2%で、20歳から49歳は成人の適正比率である25%を上回っていた。栄養素ごとの摂取量をみると、所要量より少なかったのは25栄養素のうち、カルシウム、鉄、亜鉛、銅、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンEの7栄養素だった。ビタミン・ミネラルの服用理由は「病気の予防・健康増進」が6割錠剤やカプセル、顆粒、ドリンク状のビタミンやミネラルを飲んでいる人の割合は、男性が17.0%、女性が23.6%だった。その理由を尋ねると(複数回答)、男性は、「病気の予防・健康増進」(61.9%)、「不足している栄養成分の補給」(33.9%)、「老化防止」(10.4%)、「病気の治療」(9.2%)の順に多かった。一方、女性は、「病気の予防・健康増進」(57.2%)、「不足している栄養成分の補給」(38.3%)、「美容」(17.1%)、「老化防止」(14.3%)、「病気の治療」(12.3%)となり、男性ではほとんどいない「美容」を理由として挙げる人が増える。摂取している栄養素については、男女で異なっていた。男性だと上位は、ビタミンB1(35.0%)、ビタミンB2(29.8%)、ビタミンC(29.5%)であり、女性だと、ビタミンC(36.6%)、ビタミンE(32.9%)、ビタミンB1(29.6%)となる。このほか、欠食習慣などについても調査しており、普段から欠食習慣がある人は男女とも20歳代が最も多く、男性は46.3%、女性は34.7%だった。(平成14年12月13日medwave) 3歳で肥満だった子供の3割は20歳でも肥満 肥満の3歳児の3割は、20歳になっても肥満のまま−−。これは、20年間の追跡調査の結果、明らかになったもので、石川県立総合看護専門学校保健学科の塚田久恵氏らが10月25日、日本公衆衛生学会のポスターセッション「母子保健・学校保健」で発表した。乳幼児期から肥満に注意する必要性を再認識させるデータだ。塚田氏らは、成年健康調査(石川県在住の20歳の人を対象に実施)を受診した1965年〜1974年に生まれた人のうち、3カ月児、12カ月児、3歳児における乳幼児健診のすべてのデータとの関連が確認できた2314人(男性1080人、女性1234人)のデータを基に分析した。このように、数多くの同一人物のデータを使って、乳幼児期と成人期における肥満の関係を明らかにしたデータは珍しい。なお、肥満度の判定基準には、3カ月、12カ月、3歳の時は乳幼児においてよく使われるカウプ指数(=体重[g])÷身長[cm]2×10)を用い、3カ月と12カ月では20以上を、3歳では18以上を、それぞれ肥満とした。また、20歳の時は体脂肪指数(=体重[kg]÷身長[m]2;BMI)を用い、日本肥満学会の判定基準に従い25以上を肥満とした。2000人以上のデータを解析した結果、20歳におけるBMIは3カ月、12カ月、3歳時点でのいずれのカウプ指数との間に相関関係を、男女ともに示した。最も相関係数が高かったのはともに3歳で、男性が0.33、女性が0.42だった(ともにp<0.001)。そこで、3歳の時点におけるカウプ指数別に、20歳で肥満だった人の割合を調べてみた結果、カウプ指数が小さくなるほど、肥満者の割合は少なくなる傾向にあることが判明した。カウプ指数が18以上だった子供(肥満の3歳児)は、20歳の時点で男性は29.1%、女性は29.5%が肥満であった。一方、カウプ指数が15未満だった子供のうち、20歳の時点での肥満者は男性が4.6%、女性が1.0%に過ぎず、肥満者の割合はカウプ指数18以上の場合のそれぞれ6分の1、30分の1だった。しかし、3歳の時点で肥満であっても、20歳になると、7割は肥満ではなかったとも言えるわけだ。塚田氏は、「3歳で肥満だと20歳でも肥満になりやすいと言い過ぎると、過度の摂食制限などにつながる心配もあり、必要以上に強調するのは避けるべき。一方で、肥満につながりやすいという事実を、留意しておいてもらう必要もあるだろう」と語った。また、今後の研究課題として、学校でのデータ(6歳から18歳までのデータ)を含めた解析や、乳幼児健診・相談時における効果的な介入指導のあり方などを挙げていた。(平成14年10月28日medwave) 満腹ホルモン発見、肥満防止薬の期待も 肥満防止の切り札になるかもしれない「満腹ホルモン」を、英インペリアル・カレッジのスティーブン・ブルーム博士らのグループが見つけた。このホルモンを注射された人たちは、注射を受けていない人たちより食事の量が3割少なく、食欲の抑制効果は最長で12時間続いたという。8日発行の英科学誌ネイチャーに論文が掲載される。 この物質はアミノ酸がつながった「ペプチドYY3−36」と呼ばれるもの。存在は知られていたが、食欲抑制ホルモンとしての作用を持つことは、今回明らかになった。 食事をすると腸の内壁にある細胞で作られ、これが血流によって脳の視床下部に達すると、食欲のスイッチを入れる神経の働きを抑えるらしい。 このホルモンと作用の似た薬を食前に服用すれば、食欲が減退して体重の増加を抑えられるはず、と研究グループは期待している。(平成14年8月8日 朝日新聞) 抗酸化ダイエット、「肥満で高血圧」の人には特にお薦め 肥満で血圧が高い人が、野菜や果物などを豊富に含む食事を取ると、血中の抗酸化活性が高まり、血圧も下がる−−。ブラジルSao Paulo大学心臓研究所のH. F. Lopes氏(写真)らの研究によるもので、6月25日のポスターセッションで発表した。肥満の人は高血圧になりやすく、心臓病のリスクも高いことが知られている。それでは、肥満の人とやせている人とでは、体重以外に何が違うのか。こう考えたLopes氏らは、肥満で高血圧の人と、やせていて血圧も正常な人をそれぞれ12人ずつ集め、様々な検査を行った。すると、肥満で高血圧の人では、血中の抗酸化活性がかなり低いことが判明。そこでLopes氏らは、野菜や果物を多く含む「高抗酸化食」と、飽和脂肪酸などを多く含む「低抗酸化食」を4週間ずつ食べてもらい、検査値がどのように変わるかを調べた。その結果、高抗酸化食を食べた期間に、肥満で高血圧の人では血圧が低下。最高血圧(収縮期血圧)、最低血圧(拡張期血圧)のいずれも、およそ10mmHgずつ下がった。血中抗酸化活性も、高抗酸化食を食べた期間ではやせて正常血圧の人と同じくらいまで上がった。一方、やせて正常血圧の人では、高抗酸化食を食べた場合でも、血圧や抗酸化活性は変わらなかった。Lopes氏は「野菜や果物は“健康に良い”とされる食品だが、理論的な根拠はこれまではっきりしていなかった。今回の研究で、肥満の人では体の抗酸化活性が低く、それが食事で改善されることがわかった」と強調。「特に肥満と高血圧のどちらもある人では、抗酸化ダイエットは予想以上の効果があるだろう」と述べた。(平成14年6月26日medwave) 太るホルモン解明、予防薬・治療に期待 体に脂肪がたまって肥満になるのに十二指腸から出るホルモンが重要な役目を果たしていることを京都大の研究グループが解明した。このホルモンの働きを抑える動物実験をしたところ、脂肪が多い餌を与えても体重がほとんど増えなかった。肥満の予防や治療薬の開発に役立ちそうだ。17日付の米医学誌ネイチャーメディシン(オンライン版)で発表する。研究をしたのは京大医学部の清野裕教授と山田祐一郎・助教授ら。肥満は体の中の脂肪細胞に余分に脂肪がため込まれて起こる。清野教授らは、食事後に主に脂肪の刺激で十二指腸から出るホルモン「GIP」に注目。脂肪細胞の表面でGIPと結合し、刺激を細胞内に伝えるたんぱく質「GIP受容体」がないマウスを使い、肥満になるかどうか実験した。まず、普通のマウスに餌の全カロリーのうち脂肪分が45%の高脂肪食を与えた場合と、同13%の通常食を与えた場合を比べた。50週間飼うと、高脂肪食の方が通常食より体重が約35%多く、肥満になった。次に、GIP受容体がないマウスで比べると、餌の違いで体重差が出ず、高脂肪食でも肥満にならなかった。脂肪細胞の性質などを調べたところ、GIP受容体がGIPと結合すると、血液中の脂肪をとり込みやすくする酵素が出ることなどが分かった。また、GIP受容体がないマウスは、高脂肪食を与えられた直後から普通のマウスより脂肪を多く消費する傾向があった。山田助教授は「これまでの肥満治療薬は食欲を抑える薬。GIPの働きを抑える薬なら、脂肪の蓄積という肥満の源を解決することが期待できる」と話している。(平成14年6月17日 朝日新聞) 太りすぎの人は、体重が軽い人に比べて2.5倍死亡率が高い 交通事故にあった時、太りすぎの人は、体重が軽い人に比べて死亡する確率がかなり高い――米ワシントン州で最近起きた交通事故統計を分析したところ、こんな結果が出た。調査した医師は「事故の衝撃テストに肥満体のダミー(人形)を導入し、早急に原因究明すべきだ」と提言している。 シアトルの負傷予防研究センターの医師らが、同州で交通事故に巻き込まれた2万6000人について調べた。体重が100キロ以上の人の死亡率は、60キロ以下の2・5倍にのぼったという。 また、肥満の度合いを数値化したBMI(体格指数)で比べても、指数が35―39もある太りすぎの人は、指数20前後のやせている人と比べ、2倍以上死亡しやすかった。なぜ肥満の人が死亡しやすいのか。シートベルトが体にめり込んで機能しない、一般車の内部が肥満体に合った設計になっていないなどの原因が疑われるが、よくわかっていない。 調査を報じた英科学誌ニューサイエンティストによると、米国では、衝撃テスト用に子どものダミーが最近導入されたが、肥満体のダミーは使われていない。(平成14年5月6日 読売新聞) ごく軽い運動でレプチン感受性が改善 軽いウオーキングを1週間続けるだけで、満腹感をコントロールするホルモン「レプチン」のレベルが大幅に低下することが報告された。米国Tennesee大学のNobukoHongu氏らのグループが、4月22日のポスターセッションで発表した。試験に参加したのは、特に運動習慣がない23人の健康な成人(男5人、女18人、18〜54歳で平均28.7歳)。平均体脂肪指数(BMI)は25.7±1.0と太めの人が多い。歩数計をつけて1回20分以上のウオーキングを1日に2〜3回、1週間行い、前後の血中レプチン濃度を調べた。事前のチェックから、被験者の体重、BMI、体脂肪率、血中中性脂肪とレプチン濃度は強く相関していることがわかった。つまり、肥満で中性脂肪が高いような人ほど、レプチン濃度も高い傾向があった。試験の結果、レプチン濃度は、26±2ng/mlから11±3ng/mlへと減少した。なお1日歩数は事前に7437±706歩だったところ、試験期間中は11469±805に増加していた。体重や体脂肪率は有意に変化していない。レプチンは満腹刺激を司るホルモンで、これが欠損したネズミが際限なく食べて太ることから発見された。肥満者ではレプチン濃度が高まっていることが多いため、肥満の原因として「満腹シグナル伝達系の障害によるレプチン感受性の低下」が考えられている。Hongu氏は、今回のレプチン減少結果と肥満の関係はまだ未解明としながらも、「ごく軽い運動でレプチン感受性が改善できた可能性がある」と話している。(平成14年4月24日 medwave) |
| たはら整形外科 最新の医療情報 |