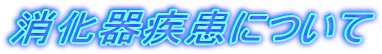 |
潰瘍性大腸炎、抗生物質で新療法 腸管の慢性的な炎症で、血便や腹痛が続く難病「潰瘍性大腸炎」の治療で、抗生物質3剤を2週間服用するATM療法を行うと、半数の患者の症状が著しく改善することが、慈恵医大柏病院消化器・肝臓内科の大草敏史教授らの研究で分かった。潰瘍性大腸炎は、若い世代で発症者が増え、国内患者数10万人。原因不明で特効薬がなく、ステロイドなどで免疫力を抑える。ATM療法は、特定の腸内細菌がこの病気を引き起こすとの考えに基づき、アモキシシリンなどの抗生物質3剤で細菌をたたく治療法。使用中の治療薬に、2週間加えて服用する。研究では、ATMを加える組と偽薬を加える組の改善度を比較。血便や下痢が日に何度もあるような中等症以上の患者(116人)では、ATMの組の49%が3か月後に腸管の炎症が消えたり、軽症になったりした。偽薬の組は22%だった。ステロイドを止めると症状が悪化する患者にATMを行うと、1年後には35%がステロイドを止められた。(平成22年6月3日 読売新聞) 糖尿病の一種、原因にピロリ菌 胃潰瘍などを引き起こすヘリコバクター・ピロリ菌が、糖尿病の一種「B型インスリン抵抗症」の原因になることを、東北大創生応用医学研究センターの片桐秀樹教授らが突き止めた。患者からピロリ菌を除菌したところ糖尿病が完治した。B型インスリン抵抗症は、患者の免疫機能がインスリンの働きを妨げる糖尿病。数千人から数万人に1人が発症する比較的珍しいタイプで、通常の糖尿病治療はほとんど効果がない。片桐教授らは、B型インスリン抵抗症の患者が血小板減少症にかかっていたため調べたところ、ピロリ菌感染が判明。昨年3月に血小板減少症に対する治療として、抗生物質による除菌を実施すると、糖尿病も治癒し、現在まで再発せず完治したという。片桐教授は「ピロリ菌が、患者の免疫に何らかの悪影響を与えることで、糖尿病の一因になったようだ。除菌は根治療法として期待できる」と話している。(平成21年7月30日 読売新聞) 体内「泳ぐ」内視鏡開発 遠隔操作で、胃の中を自由に動かせる自走式の「泳ぐ」カプセル内視鏡の開発に、龍谷大と大阪医科大が3日までに成功した。長さ48ミリのカプセルに付いた磁石とヒレで、撮影したい場所に移動させることができる。 小型電池を内蔵したカプセル内視鏡は、チューブ式の内視鏡の検査で患者が感じる痛みを軽減するため、これまでも活用されているが、自由に動かせず、長時間の検査もできなかった。龍谷大理工学部の大塚尚武教授の研究グループは、体外から遠隔操作できる駆動装置を開発。電池ではなく装置が発生させる磁場でカプセルの磁石を振動させ、魚のようにヒレを動かし、体内を自走できるようにした。ジョイスティックで上下左右の操作もできる。 グループは犬の胃の中での撮影に成功。1年以内に臨床実験を行うことを目指している。大塚教授は「電池が切れて到達できなかった大腸の検査や、検査中に再度確認したい位置に戻って見ることもできるようになるのでは」と期待する。(平成21年7月3日 中国新聞) ピロリ菌、全員除菌を 胃がん予防のため、胃の粘膜に細菌ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)がいる人は全員、薬で除菌することを勧める新指針を日本ヘリコバクター学会が発表した。新指針では、ピロリ菌が胃粘膜にいる状態を「ヘリコバクター・ピロリ感染症」と位置づけ。除菌は胃潰瘍の治療や胃がん予防に役立つなど、「強い科学的根拠があり、強く勧められる」とした。除菌の効果については、浅香正博・北海道大教授らが昨年、国内患者を対象とした臨床研究をもとに「除菌すれば胃がんの発生が3分の1になる」と英医学誌で発表。これを受け同学会で指針改定を検討していた。現在、除菌が保険適用されるのは、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の患者。日本では約5000万人がピロリ菌の感染者といわれる。除菌には通常、抗菌剤など3種類の薬を1週間のむ。(平成21年1月23日 朝日新聞) 胃がん、染色し部位浮き上がらせる 色素に酢(酢酸)を混ぜ、胃がん部位を浮き上がらせる検診技術を岡山大学病院光学医療診療部の河原祥朗助教らが発見、日本消化器内視鏡学会の英文誌「DigestiveEndoscopy(消化器内視鏡)」に発表した。胃がんの正確な診断や早期発見につながる手法として期待されている。胃がんの治療は近年、患者の負担が少ない内視鏡手術が発達。患部の根元に薬剤を注入し、がんを持ち上げて切り取る「内視鏡的粘膜下層剥離(はくり)術」が普及し、内視鏡で切除可能な胃がんは直径約2センチから10センチ以上になった。一方、通常胃がんの診断には、インジゴカルミンという青色の着色料で胃内部を染め、凸状になった患部を浮き上がらせる手法が用いられる。しかし、胃壁は元々起伏があるためがんと見分けがつきにくく、正診率は約70%という。取り残しは再発につながるため、がん部位を正確に把握するための検出技術が求められていた。河原助教らは胃の細胞は粘液で胃酸から身を守り、がん細胞は粘液をつくる力を失う点に着目。内視鏡検診時は胃の中が空で胃酸、胃粘液とも分泌されないため、検診時にインジゴカルミン溶液に0.6〜0.8%の酢酸を混ぜることで胃を刺激し、粘液を分泌させた。その結果、着色料は正常組織の粘液と結合して青く染まり、胃がん部分だけが浮き上がって正診率は90%以上に向上したという。河原助教らは既に日本の特許を取得し、科学技術振興機構の支援を受けて海外でも特許を出願する予定。河原助教は「特殊な機器が不要で、低コストで正確な診断ができるようになった」と話している。(平成21年1月14日 毎日新聞) カプセル内視鏡の製造販売承認を取得 オリンパスメディカルシステムズは、口から飲み込んで使う小腸用のカプセル内視鏡システムで厚生労働省から製造販売承認を取得したと発表した。カプセル内視鏡の承認取得は2社目で、国産製品は初めて。オリンパスは国内市場が100億円規模に膨らむとみて、従来のチューブ型内視鏡とあわせ需要獲得を目指す。発売時期や価格は未定としている。カプセル内視鏡は外径11ミリメートルで長さ26ミリメートル。CCD(電荷結合素子)カメラや無線通信機能を内蔵し、胃や小腸のぜん動運動に乗って移動しながら1秒間に2枚ずつ撮影。画像は患者が装着した受信装置に順次送られる仕組み。8時間で約6万枚を撮った後、体外に排出される。(平成20年9月11日 日経産業新聞) 胃がん、大動脈リンパ切除は無益 標準的な胃がん手術で行われるリンパ節切除に加え、大動脈周辺のリンパ節まで切除する拡大手術を行っても、患者の生存率がほとんど向上しないとする臨床試験結果を、国内のがん臨床医グループが7日までにまとめ、米医学誌ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに発表した。国内では進行性の胃がんの患部と、転移の恐れがある胃の周辺や胃につながる血管周辺のリンパ節を切除する手術が標準。場合によって大動脈周辺まで切除範囲を広げることもあるが、こうした手術は無益との証拠が示された形だ。この結果を受け日本胃癌学会も治療ガイドラインを改訂した。研究代表者の笹子三津留兵庫医大教授は「今後は手術に伴う無益な患者の負担を避けるようになるだろう」と話している。グループは1995−2001年、全国24病院で胃がん患者523人の同意を得て臨床試験を実施。標準的な手術を受けた患者と、加えて大動脈周辺のリンパ節切除を受けた患者の5年後の生存率を比べると、前者が69.2%、後者が70.3%と変わらなかった。再発の度合いにも目立った差はなかった。(平成20年8月7日 中国新聞) がんワクチン臨床研究、6割に効果 膵臓・大腸がんなど 膵臓がんなどを対象に全国10ヵ所以上の大学病院で行われている、がんワクチン臨床研究の中間的な解析が明らかになった。従来の治療が効かなかった患者約80人の6割強で、がんの縮小や、一定期間悪化しないなどの効果があった。対象は食道がん、膵臓がん、大腸がん、膀胱がんなど10種以上で、国内過去最大規模。研究を重ね、新薬の承認申請を目指した治験に入る。 がんワクチンを注射した82人について解析。進行・再発で標準的な治療法が無効だった大腸がんで、27人中15人にがんの縮小やそれ以上進行しない効果があった。膀胱がんでは6人中3人でがんの縮小が認められた。膵臓がんでは抗がん剤との併用で利用したが、患者27人中18人で何らかの効果がみられた。82人の経過をみると50人でがんの縮小や、進行しない効果が認められた。注射した部分が腫れたり硬くなったりする副作用はあったが、重い副作用はなかったという。がんワクチンは、がんに対する免疫反応を特に強め、やっつけるのが狙い。中村教授らが人の全遺伝情報を調べ、がん細胞で活動しながら、正常細胞ではほとんど働いていない遺伝子をみつけた。その中から強い免疫反応を引き起こす17の抗原を特定し、複数のがんワクチンを作った。がんワクチンは副作用が少なく通院治療ができるうえ、最近の抗がん剤より費用が低いと期待されている。開発は米国などが先行し、前立腺がんでは年内にも承認される見通し。(平成20年7月16日 朝日新聞) ベータカロテン不足で胃がんリスク2倍に 厚生労働省研究班は、ニンジンやカボチャといった緑黄色野菜に多く含まれる「ベータカロテン」が足りないと胃がんにかかるリスクが約2倍になるとの疫学研究結果を発表した。男性の方が女性よりも不足しがちで、「喫煙や飲酒の習慣がある人は、野菜や果物を積極的に取るようにしてほしい」としている。全国の40―69歳の男女約3万7000人を対象に、10年前後の追跡期間中に胃がんにかかった511人と、そうでない511人を比較分析した。調査開始時の血中ベータカロテン濃度をもとに4グループに分け、胃がんの発症リスクとの関連を調べた。ベータカロテン濃度が最も低いグループは、ほかの3グループと比べ胃がんリスクが約2倍だった。必要量を満たしていれば、多く取っても胃がんリスクは下がらないことも分かった。(平成20年7月17日 日本経済新聞) NK細胞で移植後の肝がん防ぐ 正常な肝臓にある強い抗がん作用を持つナチュラルキラー細胞(NK細胞)を培養・投与することで、肝臓がんで臓器移植を受けた後の患者で、再び肝がんができるのを防ぐことに、広島大の大段秀樹教授らが成功した。肝臓がん患者に移植を行った後、体内に残るがん細胞で、移植した肝臓に再びがんができる場合がある。大段教授らは2年前、移植用の肝臓に通した後の保存液から、強い抗がん作用を持つNK細胞を発見。2日間培養し、肝臓がんを殺す能力を高めたNK細胞の投与を移植患者に始めた。その結果、2000〜2006年に移植を受け、NK細胞を投与されなかった患者42人のうち4人に再びがんができたが、細胞を投与した14人には現在、がんはできていない。培養したNK細胞の表面には、肝臓がんを殺す働きを持つたんぱく質が多数生成されるという。また、肝臓がん患者の7割以上がC型肝炎だが、培養したNK細胞は肝炎ウイルスの増殖を抑えるインターフェロンを作り出す働きも持つ。大段教授らが移植後の患者にNK細胞を投与したところ、何もしない場合と比べ、ウイルスの量を一時100分の1まで減らすことが出来たという。(平成20年6月1日 読売新聞) 胃がん早期診断技術、「がん」部位だけ赤に着色 岡山大学の河原祥朗・助教らのチームは、胃がんを正確に診断できる新技術を開発した。がんの部分だけ赤く染められる色素を内視鏡で胃の内部に噴射する。小さな早期がんも見逃さずに発見できるほか、手術時に切除すべき範囲が明確に分かる。減少傾向にあるとはいえ年間5万人が命を落とす胃がん。診断・治療の両面で大きな威力を発揮しそうだ。胃がんの診断では、内視鏡を使うことが多い。胃をのぞくだけではなく「インジゴカルミン」という色素を胃壁に噴射、凹凸を目立たせてからがんを探す手法が普及している。ただ、表面が平たんながんを見つけにくいなど限界もある。(平成20年2月29日 日本経済新聞) 胆石の病歴、胆道がんになる確率2.5倍 胆石を患ったことがある人は、そうでない人に比べて胆道がんになる危険性が2〜3倍に高まることが、厚生労働省の研究班の大規模調査で分かった。また、胆道がんの一種の肝外胆管がんは、体格指数(BMI)が27以上の人は、23未満の人に比べて1.8倍も発症の恐れが高いなど、太っているほど危険性が高まることも分かった。BMIは体重を身長で2回割り算して算出する。調査は、当初40〜69歳だった秋田、茨城県などの男女10万人を10年以上にわたり追跡調査。この間に235人が胆道がんと診断され、内訳は胆のうがんが93人、肝外胆管がんが142人だった。こうした患者と、胆石の病歴、肥満などとの関連を調べたところ、胆石の病歴を持つ人は、2.5倍ほど胆道がんになる確率が高く、特に女性では3.2倍高まることが判明。胆のうがんは3.1倍、肝外胆管がんは2.1倍、それぞれ危険性が高まっていた。胆石が胆道がんになる危険性を高める一因だという指摘は以前からあったが、大規模調査で確かめたのは初めて。(平成20年1月11日 読売新聞) ピロリ菌から発がんたんぱく質 人の胃にすみ着くピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)がつくるたんぱく質にがんを引き起こす働きのあることを、北海道大遺伝子病制御研究所の畠山昌則教授らのグループがマウスの実験で明らかにした。今週の米科学アカデミー紀要電子版に発表する。胃がんなどを起こす仕組みの解明につながる成果だ。ピロリ菌が胃の粘膜の細胞にくっつくとCag(キャグ)Aというたんぱく質を細胞内に打ち込むことが知られている。畠山さんらはCagAを作るピロリ菌の遺伝子を取り出してマウスの受精卵に組み込み、全身の細胞にCagAが入るとどうなるかを調べた。すると、約200匹のマウスの半数以上は生後3カ月までに胃の粘膜の細胞が異常増殖して胃壁が厚くなり、その後約20匹で胃にポリープができた。さらに1年半以内に2匹が胃がん、4匹が小腸がんを発症。白血病になったマウスも17匹いた。これまでの細胞レベルでの研究で、CagAが細胞内で別のSHP-2というたんぱく質と結びつくと細胞のがん化が起きることを突き止めていたため、SHP-2と結合しないように細工したCagAをつくらせてみると、マウスはがんにならなかったという。畠山さんは「CagAががんを起こすことが、個体レベルで証明できた。将来、CagAとSHP-2との相互作用を妨げる薬の開発ができるかもしれない」という。(平成20年1月8日 朝日新聞) ピロリ菌、先祖は深海底の微生物 ゲノム解析で判明 胃かいようや慢性胃炎の原因となる細菌の一種「ヘリコバクター・ピロリ」(ピロリ菌)の祖先が、深海底に広く分布する微生物であることを、海洋研究開発機構の研究グループがゲノム解析によって突き止めた。これらの細菌が人の体に住み着くようになった進化の過程解明につながるという。研究グループは沖縄本島の北西約200キロ、水深約1000メートルの海底から熱水が噴出する場所で、「イプシロンプロテオバクテリア」と呼ばれる微生物2種を採取。ヒトの1000分の1以下の小さなゲノムに、それぞれ2466個、1857個の遺伝子が見つかった。解析の結果、ピロリ菌には残がいしかない、二酸化炭素から有機物を作り出す遺伝子を、微生物は完全な形で持っていた。この微生物は世界各地の熱水噴出域で見つかっている。光合成ができない暗黒で高圧の厳しい環境下でも、熱水中の水素や硫化水素をエネルギー源とし、二酸化炭素から有機物を合成する。グループの中川聡研究員は「環境変化が激しい胃の中にすむピロリ菌とこの微生物は、厳しい環境下で生きる戦略が似ている」と話している。(平成19年7月3日 毎日新聞) 飲酒ですぐ赤くなる人、食道がんにご用心 世界保健機関(WHO)は、アルコールと癌の因果関係についての見解を発表した。飲酒で顔が赤くなりやすい人の食道がんの発症率は、赤くならない人に比べて最大で12倍。エタノール(アルコール)は、癌を引き起こす元凶と指摘。アルコールの分解過程で重要な役割を果たすアルデヒド分解酵素の一部が欠損し、働きの悪い人は、飲酒量に比例して食道癌になる危険が高まり、酵素が正常な人の最大12倍になるとした。20年前、飲酒との関係を認定したのは食道がんと肝臓癌など限られたが、今回は乳癌、大腸癌との間にも「因果関係があるのは確実」とした。アルコールを毎日50グラム(ビール大瓶2本程度)摂取した人の乳癌発症率は、飲まない人の1・5倍。大腸癌の発症率も飲酒しない人の1・4倍になるという。(平成19年4月2日 読売新聞) 内視鏡で1ミリの食道がんも発見 昭和大学横浜市北部病院の井上晴洋助教授らは、早期発見が難しいとされる食道がんを直径1ミリの初期段階で見つけることができる手法を開発した。病巣部を拡大して見る内視鏡を使い、がんになると特徴的に表れる毛細血管の形状変化を観察、がんかどうか判別する。食道がんは進行してから見つかることが多いが、早期発見できれば治るケースが大幅に増える。食道がんは食道の内面を覆う粘膜の表面にある上皮から発生する。 上皮には先端部がループ状になった毛細血管がいくつもある。井上助教授は食道がんの病変部を詳しく観察し、がんが発生すると同時に、毛細血管の形状が微妙に変化することを突き止めた。がんの進行度に応じて、血管が特徴ある形を示すことも分かった。(平成18年10月3日 日本経済新聞) 大腸ポリープ、和食で発生率が2〜3割減少 肉をなるべく魚に替え植物油の摂取量を減らし、旧来の和食を食べるよう指導を受けた人は、そうでない人に比べ、大腸ポリープの発生率が2〜3割程度減ることが、名古屋市立大の徳留信寛教授らの研究で分かった。 食事改善の効果が出るには2年程度かかり、徳留教授は「継続した取り組みが大切」と訴えている。横浜市で開催中の日本癌学会で28日に発表した。徳留教授らは96年から04年までに、同大で大腸ポリープを切除された50代から70代までの男女計206人を、くじで二つに分けた。片方の104人には、肉はなるべく魚に替える、てんぷらなどの揚げ物を避けるなどの指導を3カ月おきに繰り返した。残りの102人には食事の脂肪を減らすよう一般的な指導をした。最初の指導から2年後に検査すると、一般的指導のグループでは検査を受けた74人中27人(36%)にポリープが再発していたが、魚を多く食べるなどの指導を受けたグループでは91人中26人(29%)にとどまった。検査を受けなかった人も含めて推計すると、魚食などでポリープが2〜3割減らせたとの結論が出た。ポリープを調べると、一般的指導の方が、悪性度が高くがんに近いポリープの割合が高かった。ただ、1年後の検査ではポリープの率に差がなかった。大腸がんの多くはポリープからできるため、徳留教授は「適度な運動と食事改善で、大腸がんを半減できるのではないか」と話している。(平成18年9月29日 毎日新聞) カルシウム多量に取ると大腸がんリスク3割減 牛乳や小魚に含まれるカルシウムを毎日たくさん取ると、大腸がんになる危険性が約30%低下することが九州大学と国立国際医療センター研究所の大規模な疫学調査で分かった。大腸がんは欧米型の食生活が浸透し国内でも患者が急増、毎年約9万人が発病し、約4万人が死亡する。がんの部位別死亡数で見ると女性でトップ、男性だと第4 位。明確な予防効果が確認された食物はこれまでなかった。調査は2000年から03年にかけ、福岡市と近郊にある8病院に入院中の大腸がん患者840人と同地域で暮らす健康な住民833人を対象に実施した。普段食べている食品の種類と量を聞き取り、カルシウムやそのほかの栄養素の摂取量と大腸がんとの関係を調べた。(平成18年9月23日 日本経済新聞) 便のDNA検査で大腸がん発見、確率8割 大腸などの消化管の壁からはがれ、便に含まれる細胞のDNAを調べることで、がんを効率よく発見する方法を松原長秀岡山大助手らが開発した。松原助手によると、米国の統計では、現在の便潜血反応検査で見つかる大腸がんは最大2割程度。この方法は8割程度になると期待できるという。松原助手らは、大腸など消化器がんの患者らの細胞を調べ、がん細胞では遺伝子に特定の分子がくっつくメチル化という現象が起きていることを突き止めた。大腸がんの場合は、6カ所でメチル化が起きているケースが多かった。(平成18年9月16日 日本経済新聞) メタボリックで胃がんリスク高まる 内臓の周りに脂肪がたまる内臓脂肪症候群(メタボリック・シンドローム)に陥ると、動脈硬化や糖尿病だけでなく、胃がんのリスクも高まることが、東大腫瘍外科の北山丈二講師らの研究でわかった。肥満解消が、がんの予防や再発防止にもつながる可能性を示す成果と言えそう。北山講師らの研究チームは、脂肪細胞から分泌される「アディポネクチン」というホルモンに着目した。脂肪の燃焼を助ける働きなどをするが、内臓脂肪症候群になると、分泌量が減り、血液中の濃度が下がる。チームが突き止めたのは、アディポネクチンに強力な抗がん作用があること。ヒトの胃がん細胞を移植したマウスにこのホルモンを投与すると、腫瘍が最大で9割も減少した。さらに、胃がん患者75人の血液中のアディポネクチン濃度を調べたところ、がんの進行した患者ほど濃度が低かった。このホルモンは、胃がん細胞と結合しやすい構造をしており、結合したがん細胞を殺す働きがあるとみられる。抗がん作用は、血液1ミリ・リットルあたりの量が0・03ミリ・グラムを超えると強まる。内臓脂肪症候群の人の濃度は、その5分の1〜6分の1という。がん増加原因として、脂肪の過剰摂取が挙げられるが、がんを引き起こす仕組みは十分に解明されていない。(平成18年9月19日 読売新聞) 胃がん、リンパ節広く取る手術と標準手術に差なし 進行胃がんの治療で、胃の周囲のリンパ節を広く切り取る「拡大手術」と、一定範囲の切除にとどめる標準的な手術(D2郭清)では、治療効果にほとんど差がないという結果を、日本の国立がんセンターがまとめた。報告した同センター中央病院の笹子三津留・副院長は「リンパ節を多くとったことで、患者の状態を悪化させている可能性もあるのではないか。標準治療はD2郭清と考えるべきだ」と話した。 同センター中央病院など全国の24医療機関が共同で調べた。がんの進行度(4段階)が2〜4の進行胃がん患者で、95〜01年に拡大手術をした260人と、D2郭清をした263人について、治療効果を比べた。その結果、3年生存率はともに76%。5年生存率は拡大手術が70%、標準的な手術は69%で、ほとんど差はなく、「延命上の利点はない」(笹子副院長)としている。 日本胃癌(がん)学会の治療ガイドラインは、進行度2〜3の患者については基本的に「胃の3分の2以上の切除とD2郭清」を標準治療とし、拡大手術の実施は、がんの転移が進んだ進行度4の患者などに限っている。(平成18年6月7日 朝日新聞) カプセル内視鏡画像 カプセル内視鏡をのみ込んで撮影した胃や十二指腸、小腸、大腸など消化管の画像を短時間で再生、診断する方法を八木康史大阪大教授(視覚情報処理学)らが開発した。カプセルが滞留しているときは高速、一気に動いた場合は低速で再生し、無駄な時間を省くと同時に見落としをなくすことができるという。八木教授によると、カプセル内視鏡は約8時間かけて体内で1秒間に2枚ずつ、計約6万枚の画像を撮影し、体外に排出される。現在、診断する医師は画像の早送りと巻き戻しを繰り返し、約2時間かけて、がんやかいようなど異常がないかを判断している。(平成18年1月31日 中国新聞) 人工食道、ぜん動運動が可能 食べ物を胃に送る蠕動運動が可能な人工食道の開発に、病態計測制御分野が専門の山家智之・東北大加齢医学研究所教授らの研究グループが成功した。内視鏡での手術が可能になるため患者への負担が軽く、食道がん患者への治療法として5年以内の実用化を目指す。同グループは24日、特許庁に特許申請した。山家教授らは、熱を加えると縮まる形状記憶合金の輪を利用。食道のぜん動運動の仕組みを参考に、この輪を1センチ間隔に配列し、規則的に縮めたり緩めたりすることで、食べ物が一定方向に進むようにした。輪を温めるための磁気コイル(長さ約5センチ)を胃の中に置き、外部から別の磁気コイルを当ててエネルギーを供給。輪は新たに開発したポリビニールアルコール(PVA)の管にくくりつけた。PVAの摩擦係数は通常の人工臓器用シリコンの1割で、食べ物をスムーズに送ることが可能だ。さらに、人工食道を設置するため食道を広げるステント(管)も、外から電磁気を当てると温まる素材を開発。温めることで、熱に弱いがん細胞を殺すことができ、治療につながるという。 食道がんは国内で年間1万人がかかるとされている。胸や腹を開くなど大掛かりな手術が必要で、切除できない場合は食べ物を飲み込めるよう金属製ステントを設置する治療をしてきたが、不都合も少なくなかった。山家教授は「胆道や尿道、大動脈などの手術への応用も考えていきたい」と話している。(平成17年11月25日 毎日新聞) ブロッコリーの新芽で胃がん予防 ブロッコリーの新芽に、胃がんの原因と注目されるヘリコバクター・ピロリ菌を殺傷し、胃炎を抑える効果があることを、筑波大の研究グループが突き止めた。米国で開催中の米がん学会主催の国際会議で2日発表する。 同大の谷中昭典講師らは、ピロリ菌に感染している50人を2つのグループに分け、一方にはブロッコリーの新芽を、残り一方には、アルファルファのもやしを、それぞれ毎日約70グラムずつ、2か月間、食べ続けてもらった。成分で見ると新芽、もやしは、ほぼ同じだが、ブロッコリーの新芽には、スルフォラファンという成分(抗酸化物質)が多く含まれる。実験前後で、ピロリ菌の活性の強さを比較したところ、新芽を食べたグループは、活性が約30%〜60%減少。さらに、胃炎も抑えられた。もやしを食べたグループは、こうした変化は見られなかった。マウスでは確認されていたが、人間で確認されたのは初めて。谷中講師は「スルフォラファンは、特にブロッコリーの新芽に大量に含まれる。ピロリ菌を除菌しなくても、胃炎を抑え、胃がんを予防できる可能性がある」と話している。(平成17年11月1日 読売新聞) 胃酸の逆流が不眠症の原因に 米国の多くの不眠症患者は、その原因として胃食道逆流症(GERD)を疑われることが、医学誌「Alimentary Pharmacology and Therapeutics」9月号に掲載された新たな研究で明らかにされた。米ジェファーソン大学医学部(フィラデルフィア)の研究者らは、医学的な原因を特定することができない睡眠障害がみられる患者16例を対象として、睡眠の状態を観察した。全例とも、過去にGERDと診断されたことも治療を受けたこともなかった。このうち8例には日中に酸逆流の症状が認められ、残る8例には何ら認められなかった。症状のみられる患者に2〜3週間にわたって、酸分泌を抑制する薬剤であるプロトンポンプ阻害薬オメプラゾール20mgを1日2回服用させた。その結果、重度の睡眠障害に酸逆流が伴う患者のうち、6例に著しい治療効果が認められ、残る2例では効果は認められたものの、その程度はそれほど高くなった。同大内科教授で消化器病学部長のAnthony DiMarino博士は、「これまでGERDと診断されたことのない患者でも、睡眠障害と酸逆流との間に何らかの関係が存在する可能性が示された。 この結果に基づいて、安眠を得るために睡眠薬を服用する前に、家庭医や胃腸病専門医を受診してGERDかどうかの診断を仰ぐ必要がある」と述べている。(平成17年10月21日 日本経済新聞) 膵臓のたんぱく質がインスリン分泌抑制 群馬大生体調節研究所は11日、独立行政法人理化学研究所と協力し、膵臓のβ細胞内にあるたんぱく質「グラニュフィリン」が、糖尿病の原因となるインスリン分泌量を抑制していることを突き止めたと発表した。今後、さらに仕組みの解明を進め、グラニュフィリンに着目した糖尿病の新たな治療法につなげたいとしている。同大研究所の泉哲郎教授らによると、同大研究所は1999年、インスリン分泌にかかわっている可能性のある物質としてグラニュフィリンを発見。マウス実験で、グラニュフィリンがないとインスリンの分泌量が多くなることを確認したという。今回の研究は、米国の学術誌「ジャーナル・オブ・セル・バイオロジー」の10月10日号に掲載された。糖尿病はインスリン不足などから、血糖値が高くなり様々な合併症を伴う。治療にはインスリン注射や、インスリン分泌を促進する薬の服用などがある。(平成17年10月12日 読売新聞) 抗がん剤投与量200分の1に、胃がん治療で新技術 愛知県がんセンターは、胃がんに投与する抗がん剤の量を200分の1に減らせる新技術を開発した。薬の入った微小カプセルを体内に入れ、がん細胞だけに効率よく作用させる。動物実験段階だが、少量の薬でもがん細胞が小さくなった。抗がん剤を減らすことができれば副作用を緩和できる可能性がある。3年後をメドに臨床研究を目指す。研究成果は14日、札幌市で始まった日本癌(がん)学会で発表した。新技術は胃がん患者の中でも転移した患者や再発した患者を想定している。同センター研究所の池原譲主任研究員らは、胃がんの抗がん剤を大きさ1マイクロ(マイクロは100万分の1)メートルの特殊なカプセルに封入し、体内に入れると免疫細胞が取り込むように工夫した。免疫細胞は胃の中のがん細胞に集まるが、その際に抗がん剤がカプセルから飛び出す仕組みになっている。(平成17年9月15日 日本経済新聞) インスリン注射不要に 糖尿病の新治療法を目指して、インスリンを分泌するヒトの膵臓(すいぞう)の細胞を大量に作る技術開発に岡山大などのグループが成功した。マウスを使った実験で効果も確かめ、この細胞を利用した患者の体内に植え込む人工膵臓の開発も進めている。25日付の米科学誌ネイチャー・バイオテクノロジー電子版で発表する。 開発したのは同大医学部の田中紀章教授、小林直哉助手らを中心とする日米などの国際研究グループ。 膵臓のβ(ベータ)細胞はインスリンを分泌し血糖値を下げている。β細胞が破壊されたり、その働きが悪くなったりした糖尿病患者は、毎日、インスリン注射をしている。β細胞を作って患者に移植できれば、注射が不要となる利点がある。グループはヒトのβ細胞に、寿命をのばす遺伝子組み換え操作をして大量に増殖させた。ただ無限に増えるとがん細胞になる恐れがあるので、寿命をのばす遺伝子を後で取り除く操作もした。 増やしたβ細胞がインスリンを作ることを確かめた上で、糖尿病のマウスに移植すると、ぶどう糖を与えた後の血糖値を健康なマウスと同レベルにできた。移植しなかった糖尿病マウスは血糖値が高いままで、実験開始10週後までに死んだが、移植したマウスは30週以上生きた。 これまでヒトβ細胞の大量増殖は困難とされてきた。β細胞を含む膵島を提供者から移植する手術も試みられているが、実施例は少ない。 田中教授らは、増やしたβ細胞を小さな容器に入れて体内に植え込む人工膵臓を開発中だ。 効果や安全性の確認に課題はあるが、1〜2年後をめどに完成させて動物実験を進め、将来的な糖尿病患者への応用を目指す。(平成17年9月26日 朝日新聞 血液で膵臓がんを早期発見 国立がんセンターは、血液1滴で膵臓(すいぞう)がんを発見できる診断法を開発した。精度は90%以上で、従来難しかった早期がんも見つけることができる。膵臓がんは発見、治療が難しいが、この診断法で早期発見すれば手術治療も可能となる。10月から全国規模で臨床研究を始める予定で、14日から札幌市で始まる日本癌(がん)学会で発表する。同センター研究所は、ノーベル化学賞を受賞した田中耕一島津製作所フェローらが開発した高精度のたんぱく質解析技術を応用。膵臓がん患者の血液を調べたところ、4種類のたんぱく質の量が微妙に変化していることを突き止め、がん診断の指標にした。 78人から採血して調べた結果、大きさが2センチ以下の早期がんも含め90%以上の高精度で膵臓がんかどうかを判別できた。腫瘍(しゅよう)マーカーと呼ぶ既存の診断法を組み合わせると100%になった。(平成17年9月14日 日本経済新聞) 胃のピロリ菌退治で「前がん状態」改善 胃がんの「前がん状態」でも、胃の中のピロリ菌を除菌すると、進行を抑え、状態を改善する効果がある。そんな研究結果を、厚生労働省研究班がまとめ、1日、岡山市で開催中の日本ヘリコバクター学会で発表する。主任研究者の斉藤大三・国立がんセンター中央病院内視鏡部長は「胃がん予防を考えると、慢性胃炎が進んだ人も除菌した方がいいかも知れない」という。 研究対象は96〜04年に登録された全国20〜59歳のピロリ菌感染者で4年以上経過した392人。胃がんへ進む前の状態と考えられている萎縮(いしゅく)性胃炎や腸上皮化生(じょうひかせい)(胃の粘膜の変性)など慢性胃炎になった患者について、抗生物質を飲んで除菌するグループと、除菌しないグループに無作為に分け、平均5.3年にわたって症状を追跡した。患部の細胞を採取して調べた結果、胃の下部の萎縮性胃炎で状態が改善した割合は、除菌しなかった116人で17人(15%)に対して、除菌した116人では72人(62%)だった。 胃の上部や中部の萎縮性胃炎、腸上皮化生を含め、すべて除菌した人の方が29〜47ポイント改善率が高かった。効果は性別や年齢層に関係なく見られた。 ピロリ菌に感染すると胃の粘膜が傷つけられ、慢性胃炎になり、さらに胃の粘膜が薄くなる萎縮性胃炎、さらに腸上皮化生になる。 これが続くと胃がんを発生しやすい。 こうした筋書きが動物実験や過去の疫学調査から示唆されてきており、ピロリ菌を除菌すると胃がんの発症率が3分の1以下になるとする研究結果もあった。「ピロリ菌元凶説」はかなり広まっているが、科学的根拠は必ずしも十分ではなかった。 今回の研究は最終的な胃がんの発生頻度まで調べたものではないが、前がん状態でもピロリ菌除菌が胃がんへの進行抑制効果を持つらしいことを厳密な研究で裏付けた点で画期的だ。 研究班は今後、除菌の効果がいつごろから現れるか解析を進めるとしている。また、研究で除菌しなかった人について、希望に応じて除菌することも検討している。 ピロリ菌は日本では国民の約半数が感染しており、特に50歳以上の感染率は約6割とされる。 除菌は、胃酸の分泌を抑える薬と2種類の抗生物質の計3種類の薬を、朝晩に1週間続けて飲むのが標準的だ。胃潰瘍(かいよう)や十二指腸潰瘍の治療などでは公的な医療保険が適用されている。 ただ、逆流性食道炎などの副作用も報告されている。(平成17年7月1日 朝日新聞) 胃がん、ピロリ菌が作り出す毒素が原因 ヘリコバクター・ピロリ菌が胃がんや胃かいようを起こす仕組みを畠山昌則・北海道大教授(分子腫瘍学)の研究グループが初めて突き止めた。ピロリ菌が作り出す毒素が原因で、予防や治療につながる新薬開発に役立ちそうだ。20日の米科学アカデミー紀要(電子版)で発表した。ピロリ菌は大きさ約3ミクロンで胃だけに存在する。胃がんや胃炎の原因とされるが、その仕組みは謎だった。研究グループは、ピロリ菌が出す「CagA」と「VacA」と呼ばれる2種類の毒性たんぱく質に着目。胃の細胞を取り出し、この二つの毒性たんぱく質を注入した。その結果、「CagA」の働きが活発になると、遺伝子の活動をコントロールする「NFAT」と呼ばれる別のたんぱく質の働きが活性化し、細胞が異常分化・増殖を始めた。「VacA」の働きが活発になると、「NFAT」の働きが弱まり、細胞の活動が抑えられた。細胞はがんでは異常増殖し、かいようでは死ぬ。このため、毒性たんぱく質の活動が変化することで、胃がんや胃かいようを引き起こすことが実験から示唆された。日本人の半数がピロリ菌を保有しているとされる。年間約10万人が胃がんを発症し、約5万人が死亡している。畠山教授は「抗生物質でピロリ菌を除去すれば、胃がんや胃かいようを防げるのではないか」と話す。(平成17年6月22日 毎日新聞) にんにく、大腸ポリープの成長を抑制 にんにくに含まれる成分に、大腸にできたポリープの成長を抑える効果のあることが、広島大の田中信治助教授(分子病態制御内科学)らの研究で分かった。 大腸ポリープは直径1センチを超すとがん細胞に移行するとされており、にんにくが、がん抑制に結びつく可能性があるという。 米国で開かれた国際にんにくシンポジウムで発表された。 大腸ポリープは通常、1センチ以上になると切除するが、1センチ未満の場合には経過を観察することが多い。 研究は内視鏡検査で大腸にポリープが見つかり、経過観察中の12人の同意を得て実施。 にんにくを油の中で2年間熟成させて抽出したエキスを、1日当たり2.4ミリリットル飲む8人(A群)と、0.16ミリリットル飲む4人(B群)に分けた。 1年後に比べると、A群では5人でポリープの数が減り、直径の平均値も1ミリ以上減った。 B群では数が減った人はなく、直径の平均値も何もせず経過観察だけの人と同レベルの3ミリ以上増えていた。いずれも統計的に有意な差があった。 にんにくには、抗がん作用を持つたんぱく質が含まれていることが知られている。田中助教授は「熟成中に有用成分ができるので、にんにくをそのまま食べるより効果は高くなるが、にんにくがおおむね大腸がんの抑制に効果があることが示された」と話している。(平成17年4月14日 毎日新聞) 胃がんの内視鏡治療、取り残し6% 内視鏡による早期胃がん切除が広まる中、消化管内視鏡治療研究会は10日、患者の6%でがんの取り残しや再発があり、2%では胃に穴があく問題が起きているとする調査結果を発表した。23施設を対象にした調査の途中集計だが、こうした実態が定量的に明らかになったのは初めて。日本胃癌(がん)学会は今回の結果も参考に、来春から大規模な全国調査を実施する計画だ。 同研究会代表世話人の斉藤大三・国立がんセンター中央病院内視鏡部長らが、国立がんセンターや神戸大付属病院など23施設で00〜01年に治療を受けた2288症例を分析して分かった。男女比は3対1、平均年齢は69歳。 ただ、約3分の1の施設が未回答。また再発した時期が確認できていないなどの限界がある。斉藤さんは「数字が独り歩きしては困るが、大体の傾向はつかめた。 回答を促し、来春までには正確な数字を出したい」と話している。 胃がんの内視鏡治療では、内視鏡でがんを見ながら、先端の器具で胃表面のがんを切除する。開腹して胃を切除する必要がないため体への負担が小さい一方、視野が悪い中で治療するため高い技術が要求される。 普及するにつれ、不完全な治療や、胃に穴があくなどの合併症が問題になり、内視鏡治療の適応範囲の見直しや、手がける医師の限定などが課題になっている。(平成16年7月11日 朝日新聞) 牛乳に大腸がん危険低下の効果 牛乳やカルシウムには大腸がんの危険を低下させる効果があることが分かったと、米ハーバード大などのグループが7日付の米国立がん研究所雑誌に発表した。欧米5カ国で行われた10の疫学調査(計約53万人が参加)のデータを分析した結果、1日当たり500グラム(200ccのコップ約2杯半)の牛乳を飲むと、大腸がんの危険が12%減少することが明らかになったという。カルシウムの大腸がん予防効果は動物実験では指摘されていたが、人への効果が大規模調査で判明したのは初めて。調査は主に1980年代に行われ、6−16年にわたって追跡。牛乳とヨーグルト、チーズの摂取と大腸がんの関係を調べたところ、ヨーグルトでも予防効果を示す傾向がみられたが、統計データで予防効果が確認されたのは牛乳のみだった。カルシウムについては、摂取量が1日1000ミリグラム以上になると、それ以下の場合に比べ女性は15%、男性は10%、大腸がんの発生が減るとしている。(平成16年7月7日 産経新聞) すい臓がん治療「血管移植」に効果 すい臓がんの再発を防ぐため、患部とともにすい臓を貫通する主要な動脈と静脈を摘出し、そこに太ももの血管を移植する方法が有効であることを、金沢大大学院医学系研究科の三輪晃一教授(消化器外科)のグループが初めて確認した。 10月に開かれる米国外科学会で発表される。再発確率が9割以上とされるすい臓がんの根治に道を開くものとして注目を集めそうだ。 三輪教授によると、この治療法が有効なのは、十二指腸に近い「すい頭」と呼ばれる部分のがん。すい臓がん患者の7割以上がこのタイプだという。手術ですい頭を切除する治療法が一般的だが、三輪教授らが再発例を分析したところ、すい頭近くを通る上腸間膜動脈と静脈に付着したがん細胞を除去しきれないことが再発の原因であることが突き止められた。 新たな治療法は、すい頭部の切除と同時に、この2本の血管の一部も切除し、代わりに患者自身の太ももの血管を移植するというもの。 太ももの血管は、一定の太さがあって移植に適しており、血管移植手術に広く用いられている。 初めて手術に成功した2002年1月以来、これまでに13例の手術を行い、うち6例は再発がなく、仕事に復帰した患者もいるという。残り7例は、すでに他臓器に転移するなどしていたケースだったが、すい頭の切除跡でのがん再発は見られなかった。 三輪教授は「これまで外科的な治療が難しかった進行がんも、手術による治療が可能となり、患者の福音となるはずだ」と話している。 すい臓がん:初期に自覚症状がなく、早期発見が難しいことから、5年生存率は5―3%。厚生労働省の統計によると、すい臓がんの死亡者数は2002年に約2万人と、食生活の変化によって30年前に比べて3倍以上に増加、がんによる死因の6位にある。(平成16年6月13日 読売新聞) 潰瘍性大腸炎、抗生物質の治療法 若い世代に増えている潰瘍性大腸炎に3種類の抗生物質を投与する治療法が有効なことを、順天堂大学の佐藤信紘教授(消化器内科)らが確かめた。胃潰瘍治療でのピロリ菌除菌をヒントにしており、米ニューオーリンズで開かれている米国消化器病学会で、18日発表する。潰瘍性大腸炎は大腸のあちこちに炎症が起き、腹痛や下痢、出血を繰り返す。全国に7万人を超える患者がいると推定されている。免疫異常が原因の一つとされ、ステロイド剤投与が主な治療法となっている。同大の大草敏史講師は免疫異常を起こす最初の引き金が腸内の細菌だと考え、患者の腸の粘膜から20種の細菌を取り出した。このうちの一種「フソバクテリウム」がつくる毒素(高濃度の酪酸)をマウスの腸に注入すると、潰瘍性大腸炎と同じような潰瘍と炎症を起こすことが分かった。 大草さんは胃潰瘍を引き起こすピロリ菌の除菌と同様の治療が有効ではないかと考え、同大治験審査委員会の承認と患者の同意を得て臨床試験を実施した。潰瘍性大腸炎の患者20人を、フソバクテリウムに有効な抗生物質3種を2週間飲む群と飲まない群の2グループに分け、投与後3カ月と1年で比較した。飲んだ群は血便がなくなり、下痢の回数が減った。内視鏡検査でも潰瘍がなくなるなど炎症が改善した。これに対し、飲まなかった群に大きな変化はなかった。1年後の追跡調査では、飲まなかった群の半数で潰瘍性大腸炎が再発、飲んだ群の再発者は1人だった。大草さんは「ピロリ菌除菌は治療法として確立しており、この治療法も新しい治療法として期待できる」と話している。(平成16年5月18日 毎日新聞) 初期大腸がん、8割判定可能・がんセンターが新技術 国立がんセンターは大腸がんを高い精度で発見できる新しい検診技術を開発した。便に混ざった細胞を調べてがん遺伝子の有無を判定する。大腸がんは早期発見が難しいが、新手法を使えば初期がんの約8割を見つけられるという。今夏に大規模な評価試験を実施し、日立製作所と組んで来年にも実用化する。大腸がんは食生活の変化で患者数が急増。国内で年間約3万8000人が死亡し、がんの中では肺がん、胃がんに次いで多い。便に付着した血液(潜血)で判定する検査法があるが、初期がんや大腸の奥深くのがんは発見が難しかった。 開発した手法は約10グラムの大便を採取し、腸内ではがれ落ちた細胞を特殊な微粒子やフィルターなどでふるい分ける。この細胞の遺伝子を装置内で増殖させ、悪性腫瘍(しゅよう)に特有の遺伝子の有無を調べる。 同センター研究所支所がん治療開発部の松村保広部長らが開発した。(平成16年4月21日 日本経済新聞) ココアがピロリ菌を抑制する 冬の温か飲料の一つ、ココアの人気が徐々に高まっている。胃潰瘍(かいよう)や胃癌の原因になるピロリ菌を減らし、整腸作用もあることが明らかになり、健康増進効果のある飲料として消費者に認知が広まっているためだ。そのココアに、毒性の強いピロリ菌の活動を抑制する作用があることが新たにわかった。 ピロリ菌は、VacAと呼ばれるたんぱく質の毒素を出し、胃の細胞に空胞を作って、細胞を死滅させる。実は、ひと口にピロリ菌といってもいろいろな株があり、このVacAをたくさん作る株ほど、毒性が強いことがわかってきた。杏林大学医学部の神谷茂教授は森永製菓と共同で、VacAをたくさん作り出す毒性の強いピロリ菌を研究。この毒性の強いピロリ菌にココアを0.06%の濃度で加えると、VacAを作る働きが抑えられることがわかった。 ちなみに0.06%という濃度は、通常のココアの飲用濃度である3.5%に比べると60分の1に相当する。「まだ研究の初期段階だが、ココアを飲むことで毒性の強いピロリ菌の活動を抑制する作用を期待できると考えてよいだろう」(神谷氏)。この効用は、2003年12月2日に東京都内で開かれた報道関係者向けセミナー「ヘリコバクターピロリに対するカカオの効果 最新情報」で発表された。 これとは別に、ピロリ菌対策のヨーグルトとして人気の明治乳業「明治プロビオ LG21」の乳酸菌であるLG21乳酸菌が、ピロリ菌の活動を抑える新たなメカニズムも明らかになってきた。ピロリ菌は、胃粘膜の上皮細胞に付着すると、ピロリ菌の細胞膜からタイプ4分泌装置という針のようなものを胃の上皮細胞に突き刺し、毒素を上皮細胞内に送り込むことが知られている。このタイプ4分泌装置でピロリ菌が上皮細胞を突き刺すのを、LG21乳酸菌が抑制することがわかったのだ。東海大学医学部教授の古賀泰裕氏が明治乳業と共同で、このメカニズムを見い出し、2003年9月上旬にスウェーデン・ストックホルムで開かれた第16回欧州ヘリコバクター研究グループ国際ワークショップのサテライト・シンポジウムの招へい講演で発表したもの。 医療機関で行われているピロリ除菌は年々、除菌成功率が低下している。耐性菌が登場しているからだ。医療機関ではピロリ菌を除去するために、胃酸の分泌を抑制するプロトンポンプ阻害薬1種と、抗生物質2種の計3剤を併用している。3剤の一つであるクラリスロマイシンという抗生物質が効きやすい通常のピロリ菌であれば、除菌成功率は8割ほどと、かなり高い。 ところが、クラリスロマイシンに耐性がある(死滅しにくい)ピロリ菌株が胃に棲息(せいそく)している場合には、除菌成功率は4〜2割程度に下がることがわかってきた。抗生物質は使えば使うほど耐性菌が出やすくなることはよく知られているが、ピロリ菌についても同じことが起こっているのだ。医薬品だけに頼らず、ココアやヨーグルトといった身近な食品でピロリ菌に対抗していく動きは今後、より重要度を増していくだろう。(平成15年12月5日Med Wave) 大腸ポリープ、染色体異常が原因 大腸に多数のポリープ(突起)ができて、がんにつながる病気が、腸の細胞の染色体に関係する遺伝子の異常で起きることがわかった。京都大医学研究科の武藤(たけとう)誠教授や大学院生の青木耕史さんらのグループが動物実験で突き止め、17日付の米科学誌ネイチャー・ジェネティクス電子版で発表する。がんの予防法開発などに役立つ可能性があるという。 大腸に数百から数千のポリープができ、がん化する病気「家族性大腸ポリポーシス」(FAP)は1万7000人に1人発症するとされる。 武藤教授らは腸の細胞ができる時に重要な役割を果たす遺伝子「Cdx2」と、がん抑制遺伝子「Apc」に注目した。二つの遺伝子の働きを抑制したネズミの大腸を調べると、生後10週間で80個以上のポリープが発生し、FAPと同じ症状になっていた。ポリープの細胞では染色体の異常が通常より10倍多かった。 Cdx2は細胞分裂にも関係することもわかった。この遺伝子が働かないと細胞分裂時に染色体がきちんとできず、他のさまざまな遺伝子に影響が出る。Apcの異常が加わると、ポリープの大量発生やがん化につながると考えられる。 武藤教授は「口の中のポリープががん化するかどうかは染色体異常と関係あるという報告もある。将来は、染色体異常で大腸ポリープのがん化を見きわめられるようにしたい」と話している。(平成15年11月17日 朝日新聞) ピロリ菌除菌で胃がん発症率3分の1 胃潰瘍(かいよう)を起こすとされる細菌、ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)を薬で除菌すると、胃がんになるリスクが3分の1になるという調査結果を浅香正博・北海道大教授(消化器内科学)らがまとめた。感染者約3400人を調べた結果で、除菌による胃がんの予防効果が明らかになった。27日まで名古屋市で開かれた日本癌(がん)学会で発表した。 同大学や東北大、信州大など全国23の医療施設が協力し、ピロリ菌感染者で除菌をしていない1233人と、除菌した2186人について、5年以上にわたって胃がん発症の有無を調べた。 その結果、除菌していない人では3.5%(43人)が胃がんになった。一方、除菌した人で胃がんになったのは1.1%(23人)で、除菌によって胃がんの発症が3分の1以下に抑えられた。ピロリ菌は胃の粘膜に感染し、炎症や潰瘍につながる。胃潰瘍の治療では、薬による除菌が普及している。しかし、除菌で胃がん発症を予防できるかどうかはまだ明らかになっていなかった。 胃がんはがんの死因の第2位で、01年には約5万人が死亡した。 浅香教授は「食生活などの生活習慣を改めるとともに除菌をすることで、胃がんの7、8割を抑えられる可能性がでてきた」と話している。(平成15年9月28日 朝日新聞 食品をとる形でピロリ菌駆除、抗生物質いらず 胃に住みつき、胃かいようの原因となるピロリ菌を効果的に除去する抗体を、ニワトリの卵を使って作り出すことに、松下記念病院(大阪府守口市)の山根哲郎外科部長と韓国・高麗大大学院の金武祚(キムムジョ)生命工学院教授の共同研究グループが成功した。 この抗体は、粉末や液体として保存でき、ヨーグルトに添加して継続的に摂取した結果、菌の数が半減したという。 山根外科部長らは、鳥類の抗体は主に卵黄に含まれていることに着目。 ピロリ菌の抗原をニワトリに注射したところ、3か月後、抗体を含む卵を産むようになった。 この卵黄を遠心分離器にかけて抗体成分だけ取り出し、液体や粉末に加工した。 この抗体を含む卵黄液2グラムをヨーグルト120グラムに混ぜ、韓国と日本の計約120人に1日2回、3か月間摂取してもらった。 その結果、平均してピロリ菌が半減、10分の1に減った人もいた。厚生労働省の研究班長として胃かいよう治療の診療指針をまとめた菅野健太郎自治医大教授は「抗生物質には副作用もあり、体質的に治療できない人もいる。食品をとる形での菌駆除が確立すれば、素晴らしい」としている。[抗体] 体内に侵入した細菌やウイルスといった病原体(抗原)を無毒化するため、血液中に作られる特殊なたんぱく質。哺乳(ほにゅう)類は母乳、鳥類は主に卵黄に含まれており、親から子へ受け継がれる。(平成15年6月28日読売新聞) 赤血球肥大で食道がんの危険 貧血の指標として健康診断の検査項目にも入っている「赤血球のサイズ」が一定以上に大きくなると、食道がんのリスクが4倍近く高まることを、国立療養所久里浜病院や国立保健科学院などの研究チームが突き止めた。 アルコール依存症患者での調査だが、一般の人でも、食道がんになりやすいかどうかを知る手がかりになると期待される。 同病院の横山顕医長らは、アルコール依存症患者を治療中、食道がんのなりやすさに違いがあることに注目。 がんになった50人と、ならなかった203人の過去の様々な検査項目を比較。 平均赤血球容積(MCV、基準値83―100)が106以上になると、それより低い人に比べ3・7倍も食道がんになりやすかった。横山医長らは、赤血球肥大の背景に栄養状態の悪さがあり、赤血球の正常な成熟に必要なビタミン(葉酸)が不足しているのではないかと見ている。(平成15年6月3日 読売新聞) 末期大腸がん患者を大幅延命 がんの増殖に必要な新しい血管の発生を抑える新薬で、末期大腸がんの大幅な延命を図ることに、米企業が成功し、1日、シカゴで開かれた米がん治療学会で発表した。この薬は、バイオ企業「ジェネンテック」社が開発したアバスチン。 新しい血管を作る体内物質の働きを抑える。がん細胞は、自分専用の新たな血管を作って、増殖に必要な酸素や養分を引き込んでおり、新薬によって兵糧攻めとなる。米デューク大などが行った臨床試験には、再発、転移した大腸がんの末期患者925人が参加。 このうち約半数は標準の抗がん剤治療法を受け、平均生存期間が16か月だったが、新薬も併用した残り半数の患者は20か月に延びた。 高血圧などの副作用が出るが、通常の抗がん剤に比べると極めて軽いという。 同社は近くこの新薬を米食品医薬品局(FDA)に承認申請する予定で、認められれば、血管新生を抑える抗がん剤では初の実用化。 試験を担当した医師は「他のがんにも応用できる可能性があり、がん治療の新たな領域を開く薬だ」と期待している。(平成15年6月2日 読売新聞) ピロリ菌で胃かいよう発症、仕組み解明 胃の中に生息するバクテリア「ヘリコバクター・ピロリ」によって胃かいようが発症する仕組みを、岡崎国立共同研究機構の野田昌晴教授らが解明、24日付の英科学誌「ネイチャー・ジェネティクス」オンライン版に発表した。 ピロリ菌によって起こる胃かいようの予防や、治療の手がかりになりそうだ。 同グループは、脳や神経細胞の表面に多く見られる「PtprZ」というたんぱく質が、ピロリ菌の出す毒素と結合するという報告を手がかりに、遺伝子組み換え技術でPtprZを持たないマウスを作った。このマウスに毒素を投与したところ、正常なマウスでは胃かいようが発症するのに、組み換えマウスは症状が出なかった。一方、胃かいようの別の原因であるアルコールを投与すると、組み換えマウスも正常マウスも同じように発症した。胃の細胞を観察すると、PtprZを持つ細胞は同菌の毒素によって細胞同士の接着力が低下して胃の表面から脱落、強い酸性の消化液から胃壁を守れなくなり、胃かいようになると結論した。 ピロリ菌は胃かいよう発症原因の1つで、胃がんとの関係も疑われている。(平成15年2月24日 読売新聞) ピロリ菌のヒトへの感染、ゴキブリが媒介 胃がんの引き金とされるピロリ菌は、ゴキブリを媒介にして人から人へと感染している可能性があることが、京都府立医大の今村重義医師らの研究でわかった。日本人の半数が感染者というピロリ菌だが、その感染ルートについては、排せつ物から口に入るという大筋がわかっているほかは、詳しくはわかっていなかった。 今村医師らは、あらかじめ雑菌を取り除いたゴキブリ20匹に、ピロリ菌の入ったエサを与え、フンの中にピロリ菌が排せつされるかどうか調べた。その結果、翌日のフンには増殖能力が十分あるピロリ菌が含まれており、3日後のフンの中でもピロリ菌は生き続けていることがわかった。1週間後まではピロリ菌の遺伝子が含まれるフンを排せつし続けた。 下水道など汚物のある場所にいたゴキブリが台所などでフンをすると、ピロリ菌が食材などに付着し、人間の体内に入る恐れがあるわけだ。今村医師は「ピロリ菌は加熱調理すれば死ぬ。生で食べる材料はきちんと洗うこと。台所や調理場も常に清潔にしておく必要がある」と指摘している。(平成14年11月20日 読売新聞) 胃や腸の潰瘍を骨髄細胞が修復 胃や腸が炎症や潰瘍を起こすと細胞を修復するために骨髄細胞が使われる−−。東京医科歯科大学の渡辺守教授(消化器内科)らの研究グループが26日付のネイチャーメディシン(オンライン版)にこんな内容の論文を掲載する。白血病の治療で行われる骨髄移植が潰瘍性大腸炎など難病治療にも役立つと研究グループはみている。 胃や腸などの表面にある細胞(上皮細胞)は通常、消化管にある幹細胞からつくられる。研究グループが白血病で骨髄移植を受けた女性の予後チェックのために上皮細胞を調べたところ、性染色体はXYで男性のものだった。骨髄の提供者が男性だったことから、骨髄細胞から上皮細胞がつくられたことがわかった。 さらに、移植の副作用で胃腸で潰瘍ができている患者の上皮細胞を調べたところ、提供者の骨髄細胞からつくられた上皮細胞が通常より50〜100倍増えていることもわかった。同グループは上皮細胞が壊れると骨髄細胞が修復に動き出すと結論づけている。渡辺教授は「潰瘍性大腸炎やベーチェット病、クローン病などの難病に、骨髄移植が使える可能性がある」と話している。(平成14年8月26日 朝日新聞) Hp除菌療法にオメプラゾールの効能追加で通知 厚生労働省は、胃潰瘍及び十二指腸潰瘍のヘリコバクター・ピロリ除菌療法(3剤併用療法)に用いるプロトンポンプ阻害剤に、新たにオメプラゾールが効能追加されたことから、同製剤の用法・用量、個別銘柄とその組み合わせに関する保険局医療課長通知を13日付けで関係者に発出した。用法・用量は通常、成人にはオメプラゾール1回20mg、アモキシシリン1回75mg(力価)、クラリスロマイシン1回400mgの3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。個別銘柄としては、オメプラゾールはオメプラール錠10、同20(アストラゼネカ)、オメプラゾン錠10mg、同20mg(三菱ウェルファーマ)の4品目。クラリスロマイシンはクラリシッド錠200mg(ダイナボット)、クラリス錠200(大正製薬)の2品目。アモキシシリンはアモキシシリンカプセル「トーワ」(東和薬品)、サワシリンカプセル、同錠250(昭和薬品化工)、パセトシンカプセル、同錠250(協和発酵工業)の5品目。なお、他の薬剤や組み合わせの使用は、保険給付の対象とはならない。(平成14年5月28日 薬事日報) ピロリ菌退治にブロッコリー効果 野菜のブロッコリーに含まれる物質に、胃潰瘍(かいよう)や胃がんの主な原因と疑われるヘリコバクター・ピロリ菌を殺す作用があることを、米ジョンズホプキンズ大と仏科学研究センターのグループが突き止め、米科学アカデミー紀要28日号に発表した。スルフォラファンと呼ばれる化学物質で、ブロッコリー、とくに新芽のブロッコリーに多く含まれる。ピロリ菌を殺す作用は体外の実験で確かめられたもので、ブロッコリーをどの程度の量食べれば胃の中の菌がなくなるかなどは、今後の課題という。研究チームによると、ピロリ菌はアジアや中南米、アフリカなどの一部地域では8割以上の人たちの胃で見つかる。日本でも成人の保有率は5割を超えるとされ、とくに中高年者でその割合が高い。抗生物質による除菌も試みられているが、抗生物質が入手しにくい国々があるうえ、有用な菌まで殺してしまう問題点が指摘されている。(平成14年5月28日 朝日新聞) |
| たはら整形外科 最新の医療情報 |