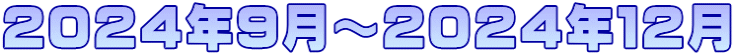 |
| 社会保障、過去最大38兆円 社会保障費は過去最大を更新し38兆2778億円となった。高齢化による伸びは6500億円程度を見込んでいたが、薬価の引き下げなどで1千億円余り圧縮し、5585億円増とした。医療費の支払いを一定にとどめる「高額療養費制度」を見直し、約200億円を削減。自己負担の上限を2025年8月から平均年収区分(約370万~770万円)で10%引き上げ、公的医療保険からの給付を抑える。薬価は市場価格に近づけて引き下げ、648億円減らす。これまで一律に適用していた引き下げルールを見直し、新薬(先発医薬品)などの価格を下がりにくくした。公的年金の支給額は、賃金の伸びを基準に1・9%上がる見通しで、2200億円程度増える。総額は13兆6916億円となる。支給額の伸びは物価や賃金の上昇より抑制する仕組みがあるため、実質では0・4%分減る。生活保護費は物価高に配慮するため、1人当たり月千円の特例加算を25年10月から1500円に増額。20億円を上積みした。実際に増額されるのは、受給世帯の約6割に当たる94万世帯となる。介護給付費は、介護人材の確保や施設整備の事業費などとして0・2%増の3兆7274億円を計上した。(2024年12月27日 共同通信社) 介護施設での高齢者虐待、前年度の31%増 2023年度に介護職員から虐待を受けたと確認された高齢者は計2335人(前年度比31.2%増)。うち約7割の人が要介護度3以上だった。5人の死亡が確認された。最も多かったのは「身体的虐待」で51.3%、次いで「心理的虐待」が24.3%、「介護等放棄」が22.3%だった。施設別では、特別養護老人ホームが352件(31.3%)で最も多く、有料老人ホームが315件(28.0%)、グループホーム156件(13.9%)と続いた。(2024年12月27日朝日新聞) 東京科学大病院が心臓移植 東京科学大病院が心臓移植の実施を目指して、2025年1月に「移植医療部」を立ち上げる。心臓移植を担う医療機関は全国で12施設にとどまり、同院は一部の医療機関に偏っている負担の解消を目的に掲げている。審査で許可が下りれば、早ければ2026年度に始める。開始する初年度は12件、翌年度以降は24件程度を目標に体制を拡充させていく考えだ。日本では脳死の人からの臓器提供が少なく、移植を受けるまでの待機期間は平均で数年に及ぶ。心臓移植では、登録できる年齢が60歳未満から65歳未満に引き上げられたこともあり、12年に約200人だった希望者は、今年11月末時点で824人にまで増えた。平均待機期間も23年末時点で約3年11カ月になっている。一方、臓器提供の意思や希望があっても、移植を担う医療機関が人員不足などを理由に辞退する事例もある。関連学会の調査によると、医療機関が心臓移植を辞退した事例は2023年に16件あり、うち15件が東大病院、1件が国立循環器病研究センターだった。2023年にあった115件の心臓移植のうち、32件が国立循環器病研究センター、25件が東大病院で実施されており、この2施設で半数を占める。(2024年12月26日朝日新聞) 「高額療養費制度」見直し 厚生労働省は医療費が高額になった場合に患者の負担を抑える「高額療養費制度」の見直しを発表した。2025年8月~2027年8月に、3回に分けて自己負担の上限額を引き上げる。平均的な年収とされる約510万~約650万円の場合、上限の基準額は現行の月約8万円から約11万3000円に増える。上限額は現在、年収に応じ、70歳未満で5段階、70歳以上で6段階にそれぞれ分けられている。2025年8月に現行の年収区分のまま、上限額を2,7~15%引き上げる。2026年8月からは年収区分を70歳未満で13段階、70歳以上で14段階に増やし、2027年8月からと併せて上限額を引き上げる。引き上げ幅は負担能力に応じて設定される。70歳未満の上限の基準額は、年収約650万~約770万円の場合、月約8万円から約5万8000円増の約13万8000円となる一方、年収約370万~約510万円では月約8万円から約8000円の増額にとどまる。自己負担の上限額引き上げには現役世代を中心に保険料負担を軽減する狙いがあり、厚労省の試算によると、1人当たりの保険料は年額1100~5000円軽減する。高額療養費制度の利用件数は高齢化の進展や医療の高度化で増加傾向にあり、21年度は6198万件に上っている。(2024年12月25日読売新聞) 厚労省が医師偏在総合対策を策定 不足地域で手当増額支援など 医師が都市部など特定の地域に集中し、地方で不足している「偏在」を是正するため、厚生労働省は、不足する地域で働く医師の手当てを増額する支援などを盛り込んだ対策パッケージを策定した。令和8年度の施行を目指す。施行後5年をめどに効果を検証する。対策パッケージでは、人口減少よりも医療機関が減るスピードが速い地域などを「重点医師偏在対策支援区域」と定義した。都道府県が重点区域を選定し、診療所を開業する際の設備費用を補助するほか、現地で働く医師や派遣される医師への手当ての増額といった経済的インセンティブを設ける。手当て増額の財源は医療保険料から充当し、加入者の負担が増えないようにする。健康保険組合連合会(健保連)など保険者が対策の実施状況や効果を確認できる枠組みもつくる。一方、外来の医師が過度に多い地域では、新規開業希望者に対し、都道府県が在宅医療や救急医療など地域で不足する医療を提供するように要請し、正当な理由なく従わない場合は勧告や医療機関名の公表ができるようにする。保険医療機関の指定期間を6年から3年などへの短縮、補助金の不交付などの措置もとるとした。このほか中堅・シニア層の医師などと医師が不足している地域の医療機関とのマッチング機能の支援や、都道府県と大学病院などの連携パートナーシップ協定締結を推進する。(2024年12月25日産経新聞) 2022年「健康寿命」 健康上の問題で日常生活を制限されずに過ごせる「健康寿命」について、厚生労働省が2022年の推計値を公表した。男性は72・57歳、女性は75・45歳。健康寿命は3年に1回、国民生活基礎調査で「健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」の質問に「ある」と答えた人を「不健康」と定義し、厚労省の研究班が算出している。都道府県別では、男女ともに静岡が最も健康寿命が長く、男性は73・75歳、女性は76・68歳だった。厚労省は、2040年までに健康寿命を男性で75・14歳以上、女性で77・79歳以上に延ばすことを目標とし、介護が必要になる前段階の「フレイル」や認知症の予防対策を進めている。(2024年12月24日朝日新聞) 帯状疱疹ワクチン、来年度から定期接種へ 痛みを伴う水ぶくれが皮膚に現れる帯状疱疹を予防するワクチンについて65歳の人を対象に、2025年度から定期接種にする方針を了承した。定期接種になれば、費用の一部が公費で助成される。経過措置として、最初の5年間は66歳以上の人も対象に加える。帯状疱疹は、水ぼうそう(水痘)を起こすウイルスが原因となる。水ぼうそうが治った後もウイルスが神経に潜伏し、免疫の働きが落ちると、再び活性化して帯状疱疹を起こす。80歳までに3人に1人が経験すると推定されている。帯状疱疹、痛みで寝たきりもある。若い世代にも急増。発症すると、神経に沿って、皮膚に刺すような痛みや水ぶくれ、腫れが生じる。10~50%の患者は、数カ月から数年にわたって神経痛が残る。帯状疱疹を防ぐワクチンは接種が1回ですむ「生ワクチン」と、2回接種が必要な「組み換えワクチン」の2種類が承認されている。全額自己負担の任意接種では、原則50歳以上の人が対象になっており、免疫不全などの発症リスクが高い人は18歳以上なら接種できる。自治体によっては、任意接種の費用を一部助成している。一方、公費助成される定期接種は65歳の人が対象になる。帯状疱疹は50歳ごろから急増し、70代が最も多い。厚労省は「70歳ごろに最も免疫が得られるようにする」と説明している。また、特に発症リスクが高いHIVによる免疫不全がある60~64歳も、定期接種の対象とする。すでに65歳を超えている人も定期接種の機会が得られるよう、25~29年度は66歳以上も対象とする。ただ、希望者が殺到してワクチン供給が不安定になるのを避けるため、29年度まで毎年度、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人だけを対象にする。101歳以上の人は、25年度に限って対象とし、26年度以降は対象から外す。(2024年12月19日朝日新聞) 国立がん研究センターに京都大が新拠点、免疫療法 画期的ながん治療法の開発を目指し、京都大は来年4月、国立がん研究センター(東京都中央区)内に新拠点を開設する。京大の最先端の基礎研究の成果を、国内で最もがん治療の実績が豊富な国立がん研究センター内に新拠点を開設し、治験を加速させる狙い。同センター内に大学の出先機関ができるのは初となる。京大は、がん免疫療法の開発に貢献した 本庶佑特別教授がノーベル生理学・医学賞を受賞するなど、基礎研究に定評がある。こうした成果の実用化を促すため、2020年4月、本庶氏をトップとする「がん免疫総合研究センター」を設立するなど、がん治療の進歩に注力している。だが、学内の京大病院はがん治療に特化した病院ではなく、単独で治験を行う場合、患者の募集や企業など関係機関との調整に時間を要し、治験開始まで1年以上かかるのが課題だ。一方、国立がん研究センターでは、治験開始までの準備を半年以内に完結し、スムーズに患者を募集するノウハウが確立。患者から採取したがん組織や血液などの検体、臨床データを多数保有し、研究段階の治療法の有効性を事前に調べる体制も整っている。日本が世界のがん治療をリードするには、基礎研究の成果を迅速に治験につなげる必要がある。そこで京大と同センターは来年4月、共同治験の実施拠点として、京大の研究室を同センター内に開設することを決めた。(2024年12月17日読売新聞) 高額療養、月8千円上げへ 厚生労働省は、医療費の支払いを一定に抑える「高額療養費制度」、平均的な年収区分としている約370万~770万円の場合、自己負担の上限月額を約8千円引き上げ、約8万8千円とする方向で調整に入った。上げ幅は10%。引き上げは2025年夏以降の見込み。医療費が膨らむ中、患者の支払いを増やして医療保険からの給付を抑え、主に現役世代が担う保険料負担を軽減する狙い。上げ幅は年収に応じて増減させ、住民税非課税の場合は2・7%にとどめる。収入が高い区分は最大15%とする。70歳以上で年収約370万円を下回る人が外来受診すると、自己負担額がさらに低くなる「特例」の上限月額は2千円引き上げて1万~2万円とする。対象となる年収も見直す方針。高額療養費制度の上限月額は年収や年齢によって異なり、医療費に応じて上乗せされるケースもある。年収約370万~770万円の場合、現行では1世帯当たり1カ月約8万円。過去約10年間の平均給与の伸びを踏まえ、10%引き上げて約8万8千円とする。住民税非課税の場合、現行の上限額は1万5千~3万5400円。負担が急激に増えないよう、上げ幅を年金の伸び率とそろえて2・7%とする。これより年収区分が高く約370万円までなら現行の上限額は5万7600円。上げ幅は5%にとどめる。年収約770万~1160万円の上げ幅は12・5%、年収約1160万円を上回る場合は15%とする。25年夏以降に引き上げた後、26年度中には年収区分を細分化する見通し。(2024年12月17日共同通信社) ※高額療養費制度 病気やけがの治療費の自己負担は原則1~3割だが、重くなり過ぎないよう1カ月当たりの支払いを一定にとどめる仕組み。上限額を超えた部分を公的医療保険から給付する。セーフティーネットの役割がある。上限額は年齢や年収によって異なる。長期療養の負担を抑えるため、直近12カ月以内に3回利用すると、4回目からは上限額が下がる。 世界で年間約700万人が脳卒中により死亡、増加傾向にあり 気候変動と食生活の悪化によって、世界の脳卒中の発症率と死亡率が劇的に上昇していることが、オークランド工科大学(ニュージーランド)のグループによる研究で示された。詳細は「The Lancet Neurology」に掲載された。2021年には、脳卒中の既往歴がある人の数は9380万人、脳卒中の新規発症者数は1190万人、脳卒中による死者数は730万人であり、世界の死因としては心筋梗塞、新型コロナウイルス感染症に次いで第3位であったという。論文の共著者は、「脳卒中の84%は23の修正可能なリスク因子に関連しており、次世代の脳卒中リスクの状況を変える大きなチャンスはある」と述べている。脳卒中のリスク因子は、大気汚染、過体重、高血圧、喫煙、運動不足などなどであり、研究グループは、これらのリスク因子はコントロール可能であると指摘している。さらに気温の上昇は、もう1つの脳卒中のリスク因子である大気汚染の悪化を意味していると説明する。汚染された空気を吸い込むことは、喫煙と同程度のリスクをもたらすと考えられているという。世界のあらゆる脳卒中に関連した死亡や障害の5割が出血性脳卒中に起因するという。(2024年12月15日M3.com) 15年後に高齢者救急75%増 85歳以上の高齢者が増加する2040年に向けて、厚生労働省は、高齢者の救急医療や在宅医療を担う医療機関を把握する方針を決めた。高齢者の救急搬送や在宅医療の需要は今後、大幅に増えるとみられており、対応できる医療機関が地域にどれだけあるか可視化することで、必要な医療を確保するねらいがある。2027年度から順次取り組みを始める「新しい地域医療構想」の概要案に方針を盛り込み、専門家検討会が案を了承した。高齢者は、10日間ほど入院してベッドで安静に過ごすと、足の筋力が15%ほど落ちるとされる。病気は治っても、日常生活の動作(ADL)が低下して退院後の生活に支障をきたすことになり、入院早期からのリハビリが重要になる。だが、国内の医療機関には、「急性期」のベッドが多く、リハビリなどで退院を支援する「回復期」のベッドが不足している。一方で、厚労省の予測では、15年後の2040年には85歳以上の高齢者の救急搬送が75%増加する。退院患者の受け皿になる在宅医療の需要も62%増える見込みだ。このため、高齢患者の急増に対応できる医療体制づくりが、喫緊の課題になっている。厚労省の新たな地域医療構想では、「治す」病院と「治し支える」病院に大きく区別する方針だ。治す病院では、医師を集約して、重症の患者や高度な手術が必要な患者の治療に専念する。治し支える病院は、一般の地域医療を担いつつ、高齢者の救急と早期リハビリなどを担う。(2024年12月11朝日新聞) 医師確保、強い開業規制は見送り 厚生労働省は医師の偏在を是正する新たな対策の具体案を専門家検討会に示した。これまでのへき地の偏在対策に加え、都道府県が重点的に医師確保の対策を支援する区域を設定し、その区域に派遣される医師や医療機関への経済的な支援を2026年度から本格的に始める。医師数は全体としては増えているものの、地域偏在が加速し、都市部の診療所に若い医師が集中する傾向にある。地方では医師の高齢化が進み、2022年時点で診療所が無い市区町村が77ある。仮に、今の診療所の医師が80歳で引退し、その地域で新たに開業する医師がいなければ、2040年には244市区町村まで増える見込みだ。厚労省の案では、都道府県は26年度に「医師偏在是正プラン」を策定することとする。重点的に支援する区域や必要な医師数を検討し、その区域に派遣される医師や勤務する医師への手当を増額したり、診療所の承継や開業を支援したりする。(2024年12月10日朝日新聞) 帯状疱疹ワクチン、高齢者対象、2025年度から定期接種へ ウイルスがもとで発疹や痛みが生じる帯状疱疹のワクチンについて、来年4月から高齢者を対象に定期接種化する最終調整に入った。65歳以降、5歳刻みで接種を受けられるようにする。接種費用の一部を公費負担とし、自己負担の軽減を図る。帯状疱疹ワクチンはこれまで、全額自己負担となる任意接種扱い。決められた回数の接種を受けると、4万~1万円ほどかかる。独自に助成をする自治体が増えているが、地域格差が指摘されていた。厚労省は、高齢者が対象のインフルエンザや新型コロナのワクチンなどと同じ、予防接種法に基づく定期接種のうちB類と呼ばれる区分に位置づける方針。専門家による議論を経て、来年度予算案に関連経費を盛り込む。帯状疱疹は、水ぼうそうにかかった後、体の中に潜伏を続けるウイルスが原因となる。加齢や疲労などによる免疫力の低下で発症する。発症する人の割合は、50代から高くなり、70代でピークになる。(2024年12月6日毎日新聞) CKDステージ3への尿酸降下薬、進展抑制か 高尿酸血症は慢性腎臓病(CKD)患者で高頻度にみられる。高尿酸血症を有するCKD患者に対する尿酸低下療法については、『高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン』では、腎機能を抑制する目的に尿酸降下薬を用いることが条件付きで推奨されている。また、『エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023』ではCKD患者に対する尿酸低下療法について、腎機能悪化を抑制する可能性があり、行うことを考慮してもよいとされている。中国・中南大学の研究グループは英国のデータベースを用いて、痛風を有するCKDステージ3の患者への尿酸低下療法について、血清尿酸値6.0mg/dL未満達成の有無別に腎機能への影響を検討した。その結果、血清尿酸値6.0mg/dL未満達成群は、非達成群と比較して腎機能障害の進展が増加せず、むしろ抑制される可能性が示された。本研究の対象は40~89歳の痛風を有するCKDステージ3で、尿酸降下薬による治療を受けた患者1万4,792例であった。(2024年12月4日ケアネット) 肥満治療薬「ゼップバウンド」を承認 厚生労働省の専門家部会は、肥満症治療薬「ゼップバウンド」について、製造販売の承認を了承した。2月に肥満症としては約30年ぶりの新薬が発売されており、治療の選択肢が広がることになる。ゼップバウンドは注射薬で、食欲を抑え、体重減少の効果がある。肥満症と診断され、高血圧や脂質異常症の持病があるなど、一定の条件を満たす患者が対象となる。日本人を対象とした臨床試験では、高用量での投与を週1回、72週続けたグループの体重が平均22・7%減少した。同じ成分の薬を2型糖尿病の治療薬としてすでに販売している(2024年12月3日読売新聞) 安楽死「先駆」の国オランダ、全死者の5.4% 2001年に国として初めて法制化したオランダでは、安楽死がなされた事後にも厳格な審査がある。2023年の全死者数に占める安楽死の割合は5・4%。オランダの安楽死要件の一つ「絶望的で耐え難い苦しみ」は、身体的か精神的かは問われないが、実施事例はがんなど身体的症状が多く、2023年も全体の88・7%を占める。他方、同年の認知症の比率は全体の3・7%に過ぎないが、件数は336件で、2013年(97件)の3・5倍に増えた。また、今年2月には12歳以上だった対象年齢を1歳以上に引き下げたほか、「人生を終えた」と感じる75歳以上なら健康でも安楽死を認めるべきだとの意見が出てくるなど、対象拡大を求める動きが顕在化している。日本には、安楽死も、終末期に延命治療を行わず自然な最期を迎える「尊厳死」も、認める法律はない。尊厳死を巡っては、厚生労働省が2019年に初のガイドラインを提示。患者の意志決定を原則に掲げたが、治療中止要件の具体的内容には踏み込まなかった。2024年には超党派議員連盟が、終末期患者の意志に基づけば延命処置を中止しても医師は責任に問われないとする尊厳死法案をまとめたが、反対の声が相次ぎ提出を断念。議連は修正法案の提出を目指しているが、先行きは不透明だ。(2024年11月30日産経新聞) マイナ保険証、電子カルテを病院間で共有へ 政府は、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」を利用する患者の電子カルテ情報について、医療機関同士で共有する新システムの運用を2025年度に始める方針を固めた。既存のシステムでは確認できない過去の検査結果など詳細な情報を把握できるようになる。医療の安全性の向上や効率化につなげる狙いがある。新システムは「電子カルテ情報共有サービス」で、厚生労働省所管の法人が管理する。各医療機関から電子カルテに記録された病名やアレルギー、感染症と生活習慣病の検査や健診結果、処方薬の情報が集まり、データベースに蓄積される。データの保存期間は3か月~5年間となる。全国の医療機関がデータを閲覧するためには、患者の同意を得る必要がある。新システムの導入で、救急患者の症状とデータをつきあわせて診断したり、初診患者の検査結果を、過去の数値と比べて病状の変化をみたりすることが可能になる。アレルギー情報は安全な薬の処方に役立つ。(2024年11月29日読売新聞) ドラッグロス解消へ新薬スピード承認 厚生労働省はがんや難病などの患者に薬を迅速に届けるため、効果が予測できる段階で製造販売を承認する新制度を導入する方針を決めた。承認後に効果が確認できない場合は取り消しを可能とする。欧米で承認された薬が日本で使えない「ドラッグロス」の解消策で、来年の通常国会に医薬品医療機器法の改正案の提出を目指す。新制度は、命に関わる重い病気や、有効な治療がない、患者が少なく臨床試験に時間がかかるなどのケースが対象となる。中間段階までのデータで効果を予測でき、患者が使う利点が大きいと判断された場合に承認する。安全対策のため医療機関や医師の条件を定める。(2024年11月28日読売新聞) 遺伝子組み換え「スギ花粉米」で花粉症治療薬 実用化へ研究加速 スギ花粉症の症状をコメで和らげる研究が実用化へ動き出した。茨城県つくば市の水田で、今年産のコメ約440キロが収穫された。このコメは、キタアケという品種のイネの遺伝子を組み換えて作った「スギ花粉米」だ。花粉症は、体に入ってきた花粉成分に免疫が過剰反応して起きるアレルギー症状だ。スギ花粉米は、コメの中に改変した花粉成分(スギ花粉アレルゲン)の一部を作り、その有効成分を継続的に摂取することで症状を抑えると考えられている。農研機構で開発が始まったのは2000年。03年には今年収穫したものと同様のスギ花粉米が実った。当初は食品として流通させることを目指していたが、治療効果への期待から、医薬品開発を念頭にマウスを使った動物実験などを重ねた。13~18年には、農研機構と共同研究をしていた東京慈恵会医科大(東京都港区)が、少数の被験者にスギ花粉米を食べてもらう方法で、人に対する有効性を確かめる臨床研究を進めた。農水省内に設けられた官民連携検討会は今年6月の中間とりまとめで、スギ花粉米から有効成分を抽出した粉末を薬剤として利用し、花粉症の根治が期待できる治療薬の実用化を目指すこととした。(2024年11月28日朝日新聞) ヒトに移植できるよう遺伝子を改変したブタの腎臓をサルに移植 明治大発のベンチャー企業の研究チームは、ヒトに移植できるよう遺伝子を改変したブタの腎臓をサルに移植することに成功したと発表した。ヒトに移植可能な臓器を使った異種移植は国内で初めて。種を越えて組織や臓器を移植する異種移植を巡っては、米国や中国で、遺伝子改変されたブタの心臓や腎臓がすでにヒトに移植され機能することが確認されている。今回は、腎臓一つを両方の腎臓を摘出した雄のカニクイザルに移植した。すると体内で腎臓への血流が確認され、排尿も正常だった。今後は半年程度、経過を観察する。チームは2025年までデータを集め、ヒトへの研究に進みたいと話した。(2024年11月25日毎日新聞) 診療所の美容外科が急増、3年間で4割増 2023年に美容外科が2016施設となり、3年間で4割増えたことが厚生労働省の医療施設調査でわかった。ほかの診療科よりも増え方が際立っており、美容医療の需要の伸びなどが影響しているとみられる。一方、少子化が進むなかで、小児科や産婦人科の診療所は減っている。診療科でみると、美容外科は2023年の調査では612施設も増えている。美容外科と領域が近い形成外科の診療所も15.0%増えて2491施設になった。このほか、腎臓内科や糖尿病内科がそれぞれ10%以上増えており、生活習慣病への対応に力を入れている診療所が多いとみられる。一方、少子化の影響で、小児科は5.4%減、産婦人科・産科は1.6%減だった。(2024年11月22日朝日新聞)) 除細動器での心肺蘇生、1分の遅れが大きな影響 除細動器による初回電気ショックを待つ時間が1分増えるごとに、心停止から生き延びる確率が6%低下することが、アムステルダム大学医療センターの研究で明らかになった。この研究の詳細は、「Circulation」に掲載された。目撃者がいる状態で院外心停止を起こした患者3,723人を対象に、初回電気ショックが与えられるまでの時間と除細動成功率との関係について検討した。患者は、最初に記録された心電図リズムで心室細動(VF)が確認されていた。初回電気ショックまでの遅延は、緊急通報からいずれかの除細動器による最初の電気ショックまでの時間と定義された。その結果、除細動成功率は、心停止から最初の電気ショックまでの時間が6分未満の場合では93%であった。緊急通報からVFが続く時間が1分増えるごとに、VFが停止しない確率が6%上昇した。(2024年11月19日HealthDay News) 体が硬いと死亡リスク高い 関節が動きにくく体が硬い人は、柔軟な人より死亡リスクが高いとの研究結果を、ブラジルなどの国際チームがスポーツ医学専門誌に発表した。46~65歳の男女約3100人に、膝や肩など7関節の可動域の広さをみる計20種類の動作をしてもらい、柔軟性を点数化した。男女別に点数の高さで3群に分けた上で、平均13年近く追跡した。その結果、男女とも点数が低く体が硬い群は、点数が高く柔軟な群に比べ死亡リスクが高く、女性は4・78倍、男性は1・87倍だった。今回柔軟性を評価したのは、特別な運動などをする前だったため、チームは「訓練で体の柔軟性を高めると長生きできるかどうかの研究が必要だ」としている。(2024年11月19日共同通信社) 高額療養費の上限、7~16%増調整 政府は医療費が高額になった患者の自己負担を一定額に抑える「高額療養費制度」の上限額の引き上げ幅に7~16%を軸として調整に入った。上限額は1カ月当たりで世帯ごとに設けられ、現在8万円程度の場合、単純計算で約6千~1万3千円増える。2025年度から開始する。医療費の膨張を抑え、現役世代を中心とした保険料の負担を軽減するのが狙い。関係者が14日、明らかにした。上限額は年収によって異なる。住民税非課税など所得が平均より低い人向けには、引き上げ幅を小さくすることも検討する。2026年度には年収区分を細分化し、高所得者はより高い上限額とする見込み。今後、詳細を詰める。現在の上限は、年収約370万~770万円の場合は8万円程度。7~16%引き上げると、8万6千~9万3千円程度となる。上限額が17万円程度となる年収約770万~1160万円の場合、約1万2千~2万7千円増えて18万2千~19万7千円程度となる。(2024年11月14日共同通信社) 美容医療に流れ込む若手医師 美容医療のトラブルが相次ぐ一方、医療界は、若手医師の美容医療への流出という問題に直面している。今や、診療所に勤務する美容外科医の半数は、20~30代の医師だ。「直美(ちょくび)」の増加だ。直美とは、医学部を卒業し、2年間の臨床研修を終えて間もない駆け出しの医師が、美容医療に進むことを指す。開業医が主に所属する日本美容外科学会によると、2014年に400人弱だった正会員数は、24年に1600人を超した。最近では新規入会者の3人に1人が直美だ。美容医療では、夜間や土日の急な呼び出しはほぼなく、医師1年目から2千万円以上の収入が見込める。(2024年11月14日朝日新聞) どんな血液型でも大丈夫な人工血液 常温で保存でき、どんな血液型の人にでも使える人工血液の実用化が見えてきた。奈良県立医科大学が廃棄予定の血液製剤から作製に成功するなど、国内で成果が出始めている。将来の献血者不足が懸念される中、事故や災害、テロ発生時の緊急輸血、離島医療などの切り札として期待されている。献血された血液をもとに作られた血液製剤のうち、有効期限が過ぎた赤血球から酸素を運ぶヘモグロビンだけを取り出し、これを人工的な膜で包んだものだ。日本赤十字社によると、献血された血液の保存期間は赤血球が冷蔵で28日、血小板が20~24度で4日、血漿が冷凍で約1年と限られ、医療機関への供給量は期間内で調整されている。作製された「人工赤血球」は常温で約2年保存できる。血液型に関係なく投与でき、感染症の恐れがなく、血圧上昇などの副作用も抑えられたという。同大は来春から人に投与する治験を始め、2030年の実用化を目指す。実用化を急ぐ背景には献血者不足への懸念がある。少子高齢化により、日赤の推計では35年度に献血者が約46万人足りなくなるとされている。(2024年11月9日読売新聞) 糖尿病治療のSGLT2阻害薬、肥満でないと効果が薄い 糖尿病治療でこの10年ほどで広く使われるようになった「SGLT2阻害薬」について、肥満でない患者では、脳卒中や心筋梗塞などの発症を抑える効果が統計上、確認できなかったと、京都大や米ハーバード大など国際共同研究チームが医学専門誌に発表した。全国健康保険協会の約28万人分のデータを分析した。SGLT2阻害薬は糖分を尿から出すことを促し血糖を下げる比較的新しいタイプの薬で、日本では2014年から使われている。ほかの治療薬に比べて脳卒中や心筋梗塞などを予防する効果が数多く示され、いまでは第一選択薬の一つとして広く利用されている。ただ、過去の大規模な臨床研究は、体格指数のBMI 30を超えるような肥満の糖尿病患者を対象としていて、日本に多いBMIが25未満の患者に対しても有効なのかは科学的な証拠が十分でなかった。研究チームは協会けんぽのデータベースを使い、2015~21年度にかけて、2型糖尿病で、SGLT2阻害薬を使っている患者のグループと、糖尿病治療で日本で最も利用されているDPP4阻害薬を使っている患者グループの計約28万人を平均27.5カ月追跡し、死亡もしくは脳卒中と心筋梗塞、心不全を発症した割合を比べた。二つの患者グループは同数で、年齢や性別、喫煙歴、BMI、血糖値などで偏りを出ないようにして選んだ。BMIが25未満の肥満でない患者は全体の約3割を占めた。その結果、全体では8165人が死亡もしくは脳卒中と心筋梗塞、心不全を発症。SGLT2阻害薬を使った患者はDPP4阻害薬の患者に比べ死亡・発症を8%ほど減らす効果が認められた。だが、BMIによって大きくわかれ、25以上では効果があり、BMIが増加するにつれて効果も高くなったが、25未満では効果は統計上は認められなかった。(2024年11月7日朝日新聞) 男性もHPVワクチンでがん予防を 子宮頸がんの原因で知られるヒトパピローマウイルス(HPV)は、男性でも肛門がんや、のどの中咽頭がんを引き起こすことがある。日本ではウイルス感染を防ぐHPVワクチンの定期接種は女性だけが対象。ところが最近、一部の自治体が男性にも接種費用の助成を始めた。HPVは性別に関係なく8割近くの人が感染するといわれる身近なウイルス。男性がワクチン接種する目的は、自分自身と将来のパートナーを守るため。HPVは男女を問わず、肛門がんや中咽頭がん、性感染症の尖圭コンジローマなどの原因ともなる。特に中咽頭がんは、女性より男性に多い。HPVは性交渉で男女が互いにうつし合って広がる。そのため海外では欧米を中心に40カ国以上で、女性だけでなく男性にも公費接種が行われているという。男性への公費接種が定着しているオーストラリアや英国では、集団免疫の効果が表れ、全体的なHPV感染率が下がってきている。日本ではHPVワクチンの公費による定期接種は小学6年~高校1年の女性だけが対象だ。男性にも任意で接種できるワクチンがあるが、3回の接種費用は5万~6万円にのぼる。(2024年11月7日産経新聞) 網膜シート移植でサルの黄斑円孔を視力改善 目の網膜の中心部が欠けて視力が低下する病気黄斑円孔を発症したサルに、様々な細胞に変化できる人の胚性幹細胞(ES細胞)から作った網膜シートを移植すると視力が改善したと、神戸市立神戸アイセンター病院などの研究チームが発表した。iPS細胞(人工多能性幹細胞)でも可能といい、論文が国際科学誌に掲載された。黄斑円孔は加齢などが原因で、視細胞が密集する黄斑部に穴ができる。50歳以上の0・1~0・3%程度で生じ、男性より女性に多いとされる。研究センターは、人のES細胞から網膜のもとになる組織を作り、直径約1ミリ、厚さ約0・1ミリのシート状に切り出した。この網膜シート1枚を、特殊な注射針を使って黄斑円孔のサルの眼球に入れ、穴があいた部分を埋めるように移植した。シートは円孔の周りの網膜とつながった。半年後、画面に映し出された画像をこのサルに見せると、視線が正しく画像の方を向く回数が増え、視力の改善がうかがえた。チームは、ES細胞と性質が似ているiPS細胞でも治療は可能としている(2024年11月6日読売新聞) 痛風発作、世界262万人の遺伝子を解析 激しい関節痛を起こす痛風。世界の約262万人の遺伝子を解析した結果、痛風の起こりやすさと関連する遺伝子の領域が、377カ所あることを国際的な研究チームが特定した。このうち149カ所は、今回新たに見つかったという。防衛医科大や米アラバマ大など18カ国によるチームが、研究成果を科学誌に発表した。痛風は、世界でも患者が増え続けている激痛を伴う関節炎だ。血液中の尿酸値が高い「高尿酸血症」の状態が続いたあと、尿酸の結晶に対する免疫反応が起こって、激しい「痛風発作」が起こる。日本では130万人を超える患者がいて、予備軍はその10倍ほどいるとされる。痛風はかつて「ぜいたく病」とも言われ、栄養価の高い食事をしている、太った、成人男性に多いというイメージをもたれてきた。ところが、近年の研究で、生活習慣だけでなく遺伝子の個人差も、発症に大きく関連することがわかっている。例えば、尿酸値が高くなる原因には「尿酸をつくり過ぎるタイプ」と「尿酸の排出がうまくいかないタイプ」があり、尿酸の輸送に関わる遺伝子の変異が大きく影響していることがわかっている。こうした遺伝子をターゲットにした治療薬が、実際の診療で使われている。研究チームは、ヨーロッパ系、東アジア系、ラテン系、アフリカ系という四つの人種集団について、痛風の人(約12万人)と、痛風ではない人(約250万人)の遺伝子をゲノムワイド解析(GWAS)という手法で調べた。特定の病気などと関連する遺伝子の場所を、網羅的に調べる手法だ。その結果、痛風の発症と関連のある遺伝子領域377カ所を同定。その中には、従来知られていた、尿酸の輸送に関わる領域などの他に、「炎症の起こりやすさ」に関連する領域が含まれることを、今回新たにつきとめた。論文は、科学誌ネイチャー・ジェネティクスに掲載された(2024年11月1日朝日新聞) 美容医療で合併症対応や医師流出 年100人単位で美容外科医師が増加「大学一つ分」 社会保障審議会医療部会は10月30日、厚生労働省から「美容医療の適切な実施に関する検討会」での検討状況について議論した。委員からは自由診療の美容医療で合併症が起きた場合の治療を医療機関が行わざるを得ないことや、それが保険診療で行われている疑いの他、医師が美容医療に流れることによる医師需給への悪影響など、様々な懸念が提示された。外国で美容医療を受けて帰国した後に何らかの症状が出て日本でかかっても、どういう手技をされたかわからず対応できない事例の報告もある。国内の美容医療の内容の透明化を図り、正しく利用者が選択できる環境を整備することが必要だ。また外科系の医師や看護師を病院で確保することが難しくなっている理由の一つに美容医療への流出があるとの見方を示し、営利目的で医師をやることには規制が必要だと指摘。自由診療で生じた合併症に対しては自由診療となり、保険適用とならないことを国民に周知することも求めた。全日本病院協会は、臨床研修修了後、すぐに美容医療に進む医師(直美と言われる医師)がいる現状を問題視した。また、合併症の対応については、自由診療の後始末を保険診療でやって保険財政を圧迫するのはおかしいと強調。日本医療法人協会も、近年は1年に100人単位で美容外科診療所の従事医師数が増えていることについて、「100人単位だと大学一つ分で、医師需給の問題だ。厚労省はしっかり考えているか」と質問。医事課長は、医師需給に関して診療科の偏在が議題となっていることから、「美容外科など特定の診療科に行ってしまうのは好ましいとは思わない。全体で若い医師が真に希望する診療科を選択していただけるような環境を整えるのが大事だ」と述べた。(2024年10月31日m3.com) 医療費、月1000万円以上は2156人 1か月の医療費が1000万円以上かかった人は2023年度に延べ2156人となり、9年連続で過去最多を更新したとする調査結果を健康保険組合連合会(健保連)が発表した。過去10年で約7倍に増加している。2023年度の最高額は1億7815万円で、14人が1億円を超えていた。いずれも全身の筋力が徐々に衰える難病「脊髄性筋萎縮症」の患者で、薬価が約1億6708万円の治療薬ゾルゲンスマを使用していた。医療費が高額となった上位100位までの主な疾患を過去10年間で比較すると、2014年度は心臓病などの循環器系疾患や血友病が7割に上ったのに対し、2023年度はがんが同程度を占めた。近年は白血病やリンパ腫などの高額な新薬に公的医療保険が認められ、使用が広がっていることが要因という。患者の自己負担は、高額な治療を受けた場合でも、高額療養費制度などを利用すると月に数十万円以下に軽減されることが多く、残りは各健保や健保連が負担する。(2024年10月29日読売新聞) 鼻にスプレーするインフルワクチン 日本で初となる鼻に噴霧するスプレータイプのインフルエンザワクチンの接種が、10月から始まった。注射の痛みが苦手な子どもには朗報だが、ウイルスを弱めた生ワクチンを使うため、接種を注意すべき場合もある。新しいワクチンは、フルミストで2~18歳が対象。左右の鼻腔の中に1回ずつスプレーで噴霧する。米国では2003年から接種が始まり、これまでに36の国と地域で承認されている。従来のインフルエンザワクチンは、感染力を失わせたウイルスからつくる「不活化ワクチン」だったが、フルミストは症状が出ないよう毒性を弱めたウイルスからつくる「生ワクチン」。鼻の粘膜に噴霧することで、感染した時と同じ仕組みで免疫が得られる。従来の不活化ワクチンと比べて、効果に明確な差はないとしている。フルミストは注射が苦手な子などに有効な選択肢になる。不活化ワクチンの場合は13歳未満は2回注射が必要だが、経鼻ワクチンは年齢にかかわらず1回となる。ただ、経鼻ワクチンは、妊婦や免疫不全の人には使えない。生ワクチンのため、接種するとインフルエンザにかかってしまうおそれがある。また、ぜんそくの子も注意が必要だ。(2024年10月25日朝日新聞) 心臓移植は60歳未満で余命1カ月の患者最優先 厚生労働省は心臓移植を希望して待機する患者のうち、余命が1カ月以内と予測される60歳未満の人を最優先に臓器をあっせんする方針を決めた。現在は選定に当たり患者の容体が悪化した場合などの医学的な緊急性は考慮されておらず、移植できずに死亡するケースがあった。最優先枠を設けることで、待機中の死亡を減らすことを目指す。有識者委員会で了承された。現行の基準は、血液型や体重などが適合するかどうかに加え、人工心臓を装着する患者らを優先。こうした条件や治療状況が同じ場合は待機期間が長い患者を優先する。医療技術の進歩で現在約7割の患者が同じ優先枠で待機する一方で、より切迫した緊急性は考慮されないため、病状が悪化しても順位は変わらない。日本心臓移植学会によると、他の待機患者への影響を減らすため、各医療機関が利用できる最優先枠は前年の移植件数の20%程度とする見込み。(2024年10月23日産経新聞) パーキンソン病患者の大腸に腸内細菌移植 順天堂大学などの研究グループは、パーキンソン病患者の大腸に腸内細菌を移植する、国内初の臨床研究を始めた。年内にも移植を実施する。パーキンソン病は、腸内環境の違いによって薬の効き目が変わる可能性が報告されており、病態の解明や治療効果の改善につながるかが注目される。パーキンソン病は、脳内の情報伝達物質「ドーパミン」を出す神経細胞が減少し、体が震えたり、姿勢を保つのが難しくなったりする難病。脳内でドーパミンに変わる治療薬が使われているが、効果に個人差があり、長い期間飲み続けると効果が薄れるなどの課題があった。順天堂大のグループは、パーキンソン病患者は健康な人に比べ腸内細菌の多様性が失われている傾向があることに着目した。計画では抗菌薬で腸内環境をリセットした上で、健康な人の便から抽出した腸内細菌の溶液を大腸内視鏡を使って移植する。患者は治療薬を続け、約8週間後に運動機能の効果などを検証する。パーキンソン病の推計患者数は約29万人で、発症年齢は50~65歳が多い。神経細胞に異常なたんぱく質がたまるのが原因とみられるが、詳しい仕組みは不明だ。(2024年10月21日読売新聞) ゲノム編集ベビー法規制 ゲノム編集技術を使って人の受精卵や精子、卵子などの遺伝子を狙い通りに改変し、子を誕生させる研究や治療を取り締まる法案について、厚生労働省が早期の国会提出を目指し、調整を始め2025年までをめどに提出する方針。ゲノム編集は「クリスパー・キャス9」という簡単で効率的な手法で利用が急速に広がった。ただゲノム編集で受精卵を改変すると望み通りの特徴を持つ子ども「デザイナーベビー」の誕生につながるとの懸念が根強い。欧州などでは罰則付きの法規制が整備されている。法案では受精卵、精子や卵子の他、遺伝情報を持つRNAへの改変などを規制する方針。現在ゲノム編集で遺伝子改変した受精卵を人の子宮に戻す研究は禁止し、生まれつきの病気や体外受精などの不妊治療に関する基礎研究に限って容認している。ただ違反しても罰則はなく、医療として行われた場合にも取り締まることができない。中国の研究者がエイズウイルス(HIV)に感染しないようゲノム編集した受精卵から双子が生まれたと報告。安全性や倫理的な問題が解決していないとして国際的に非難が殺到した。これを受けて専門家らによる内閣府の生命倫理専門調査会は19年、適切な法規制の検討を関係省庁に求めた。しかし、技術が進展しており、難病治療への期待の声もあった。慎重な検討が必要として法案提出は先送りされていた。 ※ゲノム編集 生き物の細胞の中にあり、生命の設計図であるDNAの配列を狙い通りに改変する技術。現在広く使われている手法は「クリスパー・キャス9」と呼ばれ、DNAの特定の部分に結合する分子と、そこを切断するはさみ役の酵素で構成する。特定の遺伝子を失わせたり加えたりすることで、性質を変えることができる。この手法を用いて肉厚にしたマダイや健康成分を多くしたトマトなどが実用化されている。(2024年10月15日共同通信社) 糖尿病薬で老化細胞を除去 加齢に伴い蓄積する老化細胞を薬で除去することを狙う国内初の臨床研究計画を、順天堂大の研究チームが倫理委員会に提出した。承認されれば2025年度にも患者への投与を始める。体内に蓄積した老化細胞は、炎症を起こす物質を出し続け、加齢に伴う病気を引き起こすと考えられている。このチームは「SGLT2阻害薬」という既存の糖尿病治療薬に、老化細胞を除去する働きがあるとみている。一部の老化細胞の表面には免疫の攻撃を逃れるたんぱく質がある。チームは、太らせたマウスにSGLT2阻害薬を投与する実験を実施。薬がこのたんぱく質の分解を促進し、免疫によって老化細胞の除去が進んだことを確認した。マウスの内臓脂肪にたまった老化細胞が減り、動脈硬化などの状態に改善がみられ、早老症マウスの寿命も延びていた。(2024年10月15日毎日新聞) 尿中マイクロRNAによる膵がん早期発見 川崎医科大学はCraif株式会社との共同研究により、尿中マイクロRNAを利用した膵がんの早期発見に関する成果を、2024年米国癌学会(AACR) Pancreatic Cancerで発表した。非侵襲的に採取できる尿中マイクロRNAを用いる手法が検証された。膵がんは、5年生存率が約10%と非常に低く、早期発見が患者の生存率を大幅に向上させる可能性がある。しかし、現行の検査方法では初期段階での膵がんの検出が難しいのが現状だ。今回の研究では、2型糖尿病や慢性膵炎、膵嚢胞などの膵がんリスクが高い患者から採取した尿を用い、マイクロRNAの解析を通じて膵がんを早期に診断する技術を開発した。この手法により、膵がんのステージIも含む症例を高精度で識別できることが確認された。尿中マイクロRNAの利点として、簡便なサンプリングが可能である点が挙げられる。また、この研究では、機械学習を活用した分類器の開発が進められ、リスクの高い患者のモニタリングに有効な手段となる可能性が示された。この技術は、膵がんの早期発見のための重要な一歩となると期待されている。マイクロRNAは、生体機能を調整する小さなRNAで、膵がんの発見に限らず多くの疾患の早期診断に役立つとされている。その重要性が認められ、2024年のノーベル生理学・医学賞もマイクロRNAの発見に関連して授与された。(2024年10月11日m3.com) 先発薬の処方を希望なら自己負担増 ジェネリック医薬品(後発薬)がある特許切れの先発薬の処方を患者が希望した場合の自己負担額が今月、引き上げられた。厚生労働省が導入した新制度で、安価な後発薬の使用を促し、医療費を抑制する狙い。この制度では、後発薬の発売から5年以上たった先発薬か、後発薬の使用割合が50%以上の先発薬が対象。約1100品目が該当する。該当する先発薬と後発薬の価格差の25%が医療保険適用外となり、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額に上乗せされる。自治体から小児医療費の助成を受けている患者も、保険適用外分の支払いが生じるようになった。(2024年10月8日読売新聞)) 市販薬「オーバードーズ」は2割 若者を中心に市販薬のオーバードーズ(過剰摂取)による健康被害が問題となる中、全国の薬局やドラッグストアの2割が、乱用の恐れがある市販薬を複数個販売する際、法令で定めた購入目的などを確認していないとする調査結果を厚生労働省がまとめた。厚労省は確認の徹底を求め、対策の強化を図る方針だ。厚労省は依存性のある6成分を含む風邪薬などの市販薬について、医薬品医療機器法の省令などで販売する数や方法を規制している。1人原則1個とし、複数個を購入する人には理由を確かめる。中高生ら若年者は個数を問わず氏名と年齢の確認も義務付けている。調査は2023年11月~2024年3月に実施。全国の薬局やドラッグストアなど1256店で対象の市販薬の複数個購入を試み対応を調べた。その結果、240店(19%)では質問などを受けず購入できた。インターネット販売についても調べると、140サイトのうち25サイト(18%)では確認がなく複数購入できた。オーバードーズにより意識がもうろうとしたり、呼吸が苦しくなったりして救急搬送される事例が各地で報告されている。厚労省は、乱用の恐れがある市販薬について20歳未満には、容量の大きな製品や複数個の販売を禁じるなどの新たな規制を検討している。(2024年10月7日読売新聞) レプリコンワクチン、コロナ接種で世界初実用化 新型コロナウイルスワクチンの定期接種で、「レプリコンワクチン」と呼ばれる新しいタイプのワクチンが使われている。ワクチンに含まれるメッセンジャーRNA(mRNA)が接種後に細胞内で複製されるもので、感染を抑える抗体の量(中和抗体価)を長く維持できる可能性がある。このワクチンは製薬メーカー「Meiji Seika ファルマ」が供給と販売をしている。接種すると、ウイルスから体を守るための抗体ができる仕組みは、これまで使われてきたファイザーやモデルナのmRNAワクチンと同じだ。加えて、レプリコンワクチンのmRNAには、mRNA自体を複製する酵素(レプリカーゼ)を作る設計もある。この酵素が働き細胞内でmRNAが複製されるため、mRNAの接種量は従来のものと比べて6分の1から10分の1ほどとなっている。薬の承認審査をした医薬品医療機器総合機構(PMDA)の審査報告書によると、デルタ株流行下のベトナムで約1万6000人を対象にした初回接種(1回目と2回目の接種)の臨床試験(治験)では、発症を約57%抑える効果と、重症化を約95%抑える効果が確認された。追加接種として約800人を対象にした国内の治験では、中和抗体価が、ファイザー製に劣らないことが確認された。また、追加接種から3カ月後のオミクロン株に対する中和抗体価は、ファイザー製に比べて高い傾向がみられた。ただ、こうした抗体価の差がどの程度、発症や重症化予防の効果につながるかについては、審査報告書は「現時点では不明だ」としている。安全性については治験では、接種後は痛みや発熱などの軽度や中等度の症状が多かった。審査報告書では、従来のmRNAワクチンと大きく変わらないと判断された。(2024年10月3日毎日新聞)) 緊急避妊薬、処方箋なしで購入可能な薬局 望まない妊娠を防ぐ緊急避妊薬(アフターピル)について、医師の処方箋なしで販売できる薬局を約340か所に増やすことが、日本薬剤師会への取材で分かった。9月下旬以降、当初の145か所から順次追加しており、専用サイトのリストには2日現在、311か所が掲載されている。緊急避妊薬は避妊を失敗したり性暴力を受けたりした女性が使用する。性行為から72時間以内に服用すると、妊娠を約8割防げる。日本薬剤師会は、昨年11月から全国145の薬局で適切に販売できるかを調査しているが、数の少なさや地域的な偏りから利用しにくいとの指摘が出ていた。(2024年10月3日読売新聞)) 病院検索 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/kinkyu-hinin.html 重症の糖尿病患者にiPS細胞による膵島細胞シート移植 iPS細胞(人工多能性幹細胞)を用いて 膵臓すいぞう の細胞が正常に働かない重症の1型糖尿病を治療する治験について来年1月に開始すると発表した。対象となるのは血糖値を下げるインスリンが出なくなり、「 膵島すいとう移植」の適応となる20歳以上65歳未満の患者3人。計画では健康な人のiPS細胞から数センチ四方の膵島細胞のシートを作って患者の腹部の皮下に複数枚を移植し、5年間経過を観察して安全性などを確認する。来年1月に患者の登録を始め、2月に1例目の移植を行うとしている。参加を希望する患者からの問い合わせは、京大病院のホームページで受け付ける。(2024年10月2日読売新聞)) 薬剤耐性に起因する死者数、2050年までに3900万人以上 微生物に対して抗菌薬が効かなくなる薬剤耐性が健康上にもたらす脅威が増大している。グローバル研究プロジェクトは2050年までに3900万人に上るとの予測が示され、The Lancetに掲載された。薬剤耐性は、すでに世界規模の健康問題として広く認識されており、その影響は今後数十年でさらに大きくなると予想されている。今回、報告された新たな研究では、204の国と地域のあらゆる年齢の人を対象に11種類の感染症に関連する死者数が推定された。推定は1990年から2021年までの病院の退院データ、死因データ、抗菌薬使用調査など、さまざまな情報源からの5億2000万件の個人記録に基づいて算出された。2025年から2050年までの間の累計死者数は薬剤耐性を直接原因とする死者数が3900万人以上、薬剤耐性関連の死者数で1億6900万人以上に上ると推定された。さらに、子どもの薬剤耐性による死者数は今後も減少し続ける一方で、70歳以上での死亡者数は2050年までに146%増加する可能性があると予測された。(2024年10月1日HealthDay News) コロナワクチン、10月から高齢者ら向け定期接種 高齢者を対象にした新型コロナウイルスワクチンの定期接種が10月1日から始まる。費用の一部は原則自己負担となり、オミクロン株の亜系統「JN.1」系統に対応した5種類のワクチンが使われる。今年度からは個人の重症化予防を目的とし、インフルエンザワクチンと同様に、主に高齢者が対象の秋冬の定期接種となった。10月1日から来年3月末までが接種期間となる。対象者は、(1)65歳以上(2)心臓や呼吸器疾患、免疫不全などの重い基礎疾患がある60~64歳。接種回数は年1回で、費用は自治体によって異なるが、3千円程度となる場合が多く、独自の助成で無料で受けられる自治体もある。定期接種の対象外の人は任意接種となり、全額を自己負担する。医療機関によるが、ワクチンの価格と接種費を合わせて1万5千円程度が見込まれる。(2024年9月27朝日新聞) 血液がん遺伝子検査実用化 国立がん研究センターと大塚製薬などは白血病やリンパ腫などの血液のがんを対象に開発した、400以上の遺伝子異常を網羅的に調べる「がん遺伝子パネル検査」が販売承認を受けたと発表した。血液がんでの承認は国内で初めて。今後保険適用される見通し。がんに関わる遺伝子の異常をまとめて調べる遺伝子検査は、固形がんを対象とした複数がすでに保険適用となっている。一方血液がんは原因となる遺伝子が固形がんと異なり、種類も多いため、検査の開発が遅れていた。検査機器は「ヘムサイト」で厚生労働省が19日付で承認した。患者の血液や骨髄液などから452の遺伝子をまとめて解析。血液がんは原因遺伝子ごとに病名が分かれているため、結果を診断や治療の選択に使う。白血病で骨髄移植をするかどうかや、治療の強さを決める際の判断材料にも有用という。血液がんは年間5万~6万人が罹患する。種類は200を超え、特に小児がんでは4割を占める。(2024年9月27日共同通信社) 緊急避妊薬を処方箋なしで試験販売 全国284薬局 望まない妊娠を防ぐため性交後に服用する緊急避妊薬(ノルレボ錠とジェネリック医薬品のレボノルゲストレル錠)を、処方箋なしで試験販売する薬局が全国計284店に増えたことが日本薬剤師会などへの取材で分かった。これまで145店だった。さらに増える見通し。緊急避妊薬は性交後72時間以内に飲むと妊娠を高確率で回避できる。試験販売は昨年11月から、日本薬剤師会が厚生労働省の委託を受けて調査研究として実施。対象は16歳以上の女性で、事前の電話相談や薬剤師の面前での服用が求められる。公式ウェブサイトで試験販売の薬局を公開している。https://www.pharmacy-ec-trial.jp(2024年9月26日産経新聞) 経口中絶薬、無床診療所への拡大、再審議 人工妊娠中絶のための飲み薬について、厚生労働省は一定の条件を満たせば外来での使用を可能とする方針を了承した。入院ベッドのない無床診療所での使用については準備が整っていないとし再度審議する。この薬は、妊娠9週0日までの妊婦が対象の経口薬「メフィーゴパック」。使用中に大量出血のおそれもあるため、承認時に適切な使用体制が確立されるまで入院可能な医療機関で使用し2剤目の使用後は院内待機を求める通知を出していた。こども家庭庁の研究班が昨年435件を調査し、重篤な合併症はなかったと結論づけたことをふまえ、通知の改正に向けた議論が進んでいた。今後、2剤目の使用後は医療機関から16キロ以内などの条件を満たせば帰宅できるようになる。一方、使用できるのは引き続き入院可能な医療機関に限られる。関係者によると、調査対象期間外で重篤な有害事象が複数確認されたため、日本産婦人科医会から無床診療所への使用拡大について慎重な対応を求める声が上がっていた。(2024年9月25日朝日新聞)) アルツハイマー病治療薬(ドナネマブ)を承認 厚生労働省はアルツハイマー病治療薬ドナネマブを承認した。原因物質を脳内から除去するタイプではレカネマブに次いで2剤目となる。薬価の審議を経て11月にも保険適用される見通しだ。ドナネマブは患者の脳内に蓄積する異常なたんぱく質「アミロイド βベータ (Aβ)」の塊を取り除き、病気の進行抑制を狙う。対象は、認知症の前段階となる軽度認知障害(MCI)を含むアルツハイマー病の早期患者で、点滴で月1回、最長1年半投与する。1年をめどに検査し、Aβの塊が消えたことが確認できれば、投与をやめられる。(2024年9月24日読売新聞)) HPV感染と男性の生殖機能 HPV(ヒトパピローマウイルス)は、ほぼ全例(95%)の子宮頸がんの原因であることから、これまで女性の健康問題と考えられてきた。しかし男性にもHPVを恐れる理由と予防接種を受けるべき理由のあることが新たな研究で明らかになった。男性が高リスク型のHPVに感染すると生殖機能が障害される可能性のあることが示されたのだ。国立コルドバ大学化学学部よるこの研究結果は「Frontiers in Cellular and Infection Microbiology」に掲載された。HPVは高リスク型と低リスク型に分類され、高リスク型は子宮頸がんや陰茎がん、肛門がんなどのリスクを上昇させる。米疾病対策センター(CDC)は性的に活発になってウイルスに曝露するリスクが高まる前にHPVワクチンを接種すると効果が高いことから、9~14歳の小児へのワクチン接種を推奨している。しかし、男子でのワクチン接種率は女子よりも低く、2022年の米国での接種率は女子で約65%であったのに対し男子では約61%にとどまっていたという。この研究では、205人の男性(年齢中央値35歳)を対象に、生殖器系での高リスク型または低リスク型HPV感染と精液の質、酸化ストレス、炎症との関連が検討された。精液サンプルを調べたところ、19.0%でHPV感染が確認された。陽性サンプルからHPVの遺伝子型を割り出すことができた74.0%は少なくとも1種類の高リスク型HPVに感染していることが確認された。高リスク型HPV感染者では低リスク型HPV感染者や対照と比べて、精子のアポトーシスや壊死が有意に多く、活性酸素種(ROS)陽性精子の割合も高いことが確認された。また、高リスク型HPV感染者では対照と比べて精液中の白血球と炎症性サイトカイン(IL-6およびIL-1β)レベルが低いことも観察された。高リスク型HPVに感染した男性は、酸化ストレスと尿生殖器の局所的な免疫反応の低下により、死滅する精子が増加することが示された。この結果は、これらの男性では生殖機能が障害を受けている可能性があることを示唆される。(2024年9月23日HealthDay News) 臓器移植見送りが2023年、509人 脳死者からの臓器を移植する施設が、人員や病床の不足などを理由に臓器の受け入れを断念している問題で、移植を見送られた患者が2023年だけでのべ509人いたことが、厚生労働省による初の実態調査でわかった。臓器のあっせん順位は、日本臓器移植ネットワーク(JOT)が、脳死者からの臓器提供例が出る度、臓器別の待機患者リストから、待機期間や重症度などを踏まえて決める。上位の患者から順に登録先の移植施設に連絡し、受け入れを要請する。施設は辞退する場合、理由も返答する。今回の調査は、JOTが23年にあっせんした心臓、肺、肝臓、膵臓、腎臓、小腸の記録を全て確認。同年に脳死判定を受けた131人の831の臓器のうち、あっせんしたものの、最終的に移植が成立しなかった192の臓器(心臓6、肺25、肝臓9、膵臓45、腎臓8、小腸99)の経過を追った。192臓器のあっせんで、移植が見送られた患者はのべ3706人。このうち509人が人員や病床が確保できないなど院内態勢が整わないことが理由となった。内訳は多い順に肺364人、膵臓55人、心臓53人、小腸17人、肝臓15人、腎臓5人だった。(2024年9月21日読売新聞) がん治療薬オプジーボの10年 オプジーボが発売から10年を迎えた。画期的な治療アプローチで多くの患者に福音となったが、高額薬として知られ、患者負担の重さや厳しい医療財政が壁となり度重なる薬価の引き下げに直面した。ただ薬価の問題は製薬会社の経営に直結し新薬の開発余力にも影響するだけに、高額薬の在り方を巡る議論に一石を投じる形となった。オプジーボは、ノーベル生理学・医学賞を受賞した本庶佑京大特別教授の研究成果を基に開発された。従来の抗がん剤などと異なり、自己の免疫を利用してがんを攻撃するのが特長だ。2014年に皮膚がんの一種メラノーマの治療薬として発売されて以降、肺がんや胃がんなど13のがんに対象が拡大。投与患者数は推定約19万人に上る。ただオプジーボは極めて高額の薬として知られ、肺がん治療では当初、年約3500万円かかるとされていた。患者の自己負担そのものは高額療養費制度など公的保険でカバーされため、国民の医療費全体は膨張し財政を圧迫する。このためオプジーボの薬価は普及に伴い6度にわたり引き下げられ、現在は5分の1以下になっている。最近でも、認知症治療薬レカネマブなど高額薬の登場が相次ぐ。厚生労働省によると2021年度の国民医療費は45兆円を超えて過去最大となり、翌年度以降の概算額も増え続けている。命に値段は付けられないが、保険料や患者の自己負担以外の公費投入は17兆円に達し、膨張には限度があるのも実情だ。(2024年9月17日 共同通信社) 自己増幅型の新型コロナワクチン承認 厚生労働省の専門家部会は、製薬会社MeijiSeikaファルマが開発した、新型コロナウイルスのオミクロン株の新系統JN・1に対応したワクチン「コスタイベ」の製造販売の承認を了承した。遺伝物質mRNAワクチンを改良した新しいタイプで、少量の接種で効果が長く続く特性がある。このワクチンのタイプは自己増幅型と呼ばれ、接種からしばらくの間ウイルスの働きを抑える中和抗体の産生につながるmRNAが体内で増える。このため接種量は従来の6分の1~20分の1で済むという。約830人を対象に行った臨床試験では、接種後1か月時点で血液中の中和抗体量は接種前の8倍、半年時点では同4倍だった。海外製の承認済みワクチンと比べて高く、副反応の頻度には違いがみられなかった。承認されれば、来月に始まる定期接種用も含めて約430万回分が供給される予定だ。(2024年9月13日読売新聞) 肺炎球菌ワクチン接種の高齢者では認知症減少 新潟大学は約1万人の高齢者を3年半追跡し、肺炎球菌ワクチンを接種していた人では接種しなかった人と比べ認知症が23%少なかったことを明らかにしたと発表した。研究グループは、心臓病などの認知症のリスクを上げる病気だけでなく、社会経済的状況やフレイルが認知症に影響している可能性を取り除いた上で、インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンのどちらが認知症減少と関係するのかを調べた。ワクチン接種歴・認知症発症の関係、認知症に影響する要素除いて2013年に65歳以上で要介護認定を受けていない約1万人の高齢者を対象に、認知症の発症に影響する可能性がある年齢、性別、教育歴、婚姻状況、家族構成、喫煙、飲酒、高、中、低強度の運動の頻度、BMI(30以上か否か)、心臓病、高血圧、糖尿病、耳の病気、呼吸器の病気、老年うつ、フレイル、肺炎およびインフルエンザの罹患歴、ワクチン接種歴、社会的つながり(社会参加、社会的結束、相談できる人がいるかなど)について調査した。2016年には肺炎球菌ワクチンおよびインフルエンザワクチン接種に関して調査した。肺炎球菌ワクチンまたはインフルエンザワクチン接種後に認知症が減少したのかについては、ワクチン接種以外の認知症発症に関係する要因の影響を統計学的方法で取り除いた上で、ワクチンを接種したグループと接種していないグループの間で認知症発症に差があるかを計算した。肺炎球菌ワクチン接種で認知症が23%減少、インフルエンザワクチン接種は有意差なしであった。(2024年9月10日m3.com) 着床前診断の拡大議論も 重い遺伝性の病気が子供に伝わらないよう、体外受精した受精卵の遺伝子を調べる「着床前診断」を巡り、日本産科婦人科学会は来年4月にも倫理審議会を開き、対象疾患の拡大も含めて議論する方針を示した。学会は従来、成人までに亡くなったり、日常生活を著しく損なったりする可能性がある重い遺伝性の病気に限って着床前診断を認めてきた。2022年に対象を拡大。成人以降に発症する病気や、生命に直接影響を及ぼすことは少ないが身体の機能を失う病気に関しても検査を行えるようにした。この日の会見では「重い病気」という定義の見直しは大切なことだと述べた。(2024年9月7日産経新聞) 細胞シート製品化へ 難治性皮膚潰瘍治療に 山口大とセントラル硝子は、患者以外の健康な人から採取した細胞を培養して作る細胞シートを共同開発し、2030年の発売を目指すと発表した。細胞シートは、皮膚の真皮にある繊維芽細胞を培養したもので、実用化されれば初めてのタイプの再生医療製品となる。重症の糖尿病患者らの皮膚に、細菌が感染するなどして起きる難治性皮膚潰瘍の治療に用いられる。これまでの研究により、患部に移植したシートから成長因子が分泌され、組織の再生を促すことを確認した。製品化に向けては、シートを作る繊維芽細胞を、歯科医療で親知らずを抜いた際の歯肉から採取する。1回の採取で、数百万枚のシート(直径3センチの円状)が作れる。ウイルス検査などをして、健常であることを確認したドナーから提供を受けるとしている。さらに、細胞シートを凍結保管する技術を確立。従来の細胞シートを凍結後に解凍した場合、多くの細胞が死滅していたが、繊維芽細胞を使った今回のシートは2年間凍結して解凍した場合でも、細胞の70%以上の生存率を実現。製品化に向けて、在庫を確保し、製品を柔軟に提供することが可能になった。また、開発担当者は「肺がんや食道がんなどの手術の際に縫合部に移植して、合併症を防ぐ効果があることを確認したい」と語った。(2024年9月6日毎日新聞) 75歳医療費3割負担拡大、検討加速へ 政府の高齢化対策の中長期指針「高齢社会対策大綱」の改定案が判明した。75歳以上(後期高齢者)の医療費窓口負担が3割となる人の対象範囲拡大を検討すると明記した。現在75歳以上の窓口負担は原則1割で一定の所得があれば2割、現役並みの所得があれば3割となっている。2028年度までに「現役並み所得」の判断基準を見直すかどうか協議する。 転移リンパ節に直接抗がん剤投与 岩手医大と東北大のチームは、頭頸部がん患者を対象にがん細胞が転移した頸部リンパ節に抗がん剤を直接投与する臨床研究を始めた。全身投与に比べて量を少なくでき副作用を抑えられるという。頭頸部がんは首や顎、口の中、喉などにできるがんの総称。チームによると、リンパ節転移が見つかった場合、5年生存率は30~70%まで低下するため早期治療が必要となる。抗がん剤治療は静脈に注入する全身投与が主流だが、転移リンパ節内は血流が良くないため薬剤が十分に行き渡らず、治療効果は高くない。臨床研究では、超音波画像で部位を確認しながら、浸透圧を調整した抗がん剤を皮膚の上から注射器で直接注入。7日後にリンパ節を摘出し、がん細胞がなくなっているかを確かめる。今回はステージ3と4の進行がん患者が対象。世界初の手法といい、効果を確かめられれば、将来的には乳がんなどへの適用拡大も目指す。(2024年9月4日産経新聞) 新たな熱中症の重症度 日本救急医学会は熱中症の診療指針を9年ぶりに改訂した。これまで3分類していた重症度に新たに最重症群の「4度」を設けた。深部体温(体の中心部の体温)が40度以上で意思疎通が難しい重篤な患者とし、医療機関で速やかに体を冷やす集中治療の必要があるとしている。4月29日~8月25日に熱中症で救急搬送された人は8万3238人に上る。また、年間1千人超が熱中症で亡くなっている。従来の指針の重症度の3分類は、体温などにかかわらず、めまいや立ちくらみがある状態を「1度」、頭痛や嘔吐(おうと)があると「2度」、意識障害などがあれば「3度」と定義していた。1度は体の表面の冷却や水分・塩分の補給など現場での処置。2度以上は医療機関を受診。3度は入院が必要としていた。学会は熱中症患者2500人超のデータを分析。深部体温が40度以上で意思疎通が取れない患者の死亡率は23.5%と、それ以外の患者の6.4%と比べて高かった。新たな指針では、深部体温が40度以上で意思疎通が取れない患者を最重症群の「4度」とし、早急に体を冷やす「アクティブクーリング」などの治療を推奨する。(2024年9月2日朝日新聞) 体外受精で生まれた子どもは9人に1人 日本産科婦人科学会は、2022年に国内で実施された体外受精で生まれた子どもが、前年より7409人増の7万7206人で過去最多を更新したとする調査結果を発表した。生まれてきた子の9人に1人に相当する。治療を受けた女性の年齢は42歳が最も多かった。2020年4月に体外受精が42歳を上限に公的医療保険の適用となり、駆け込みで治療を始めたケースがあったとみられる。発表によると、国内で生まれた体外受精児は1983年の1例目から累計で91万8312人となった。2020年に治療を受けた件数を女性の年齢別にみると、42歳(4万6095件)、39歳(4万3750件)、40歳(4万2903件)の順に多かった。(2024年9月2日読売新聞)) 肺炎球菌ワクチン「プレベナー20」 高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者における肺炎球菌(血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、8、9V、10A、11A、12F、14、15B、18C、19A、19F、22F、23F及び33F)による感染症の予防に肺炎球菌ワクチン「プレベナー20(R)水性懸濁注」(沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン)承認した。本剤は従来の沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン「プレベナー13(R)」に7血清型を加えたことにより、さらに広範な血清型による肺炎球菌感染症を予防することが期待される。なお、プレベナー20の発売日は8月30日でプレベナー13は今後市場から引き上げ、9月30日をもって販売を終了する。(2024年9月2日ケアネット) 1型糖尿病患者にiPS細胞から作る膵島細胞を移植…インスリン注射不要に 膵臓の細胞が正常に働かない重症の1型糖尿病について京都大病院がiPS細胞(人工多能性幹細胞)から作った細胞のシートを患者に移植する治験を来年にも実施する計画であることが、京大関係者らへの取材でわかった。有効性が確認されれば注射治療が継続的に必要な患者の負担を軽減する効果が期待できるという。2030年以降の実用化を目指す。 1型糖尿病の患者は通常、インスリン製剤を毎日数回、腹部に自分で注射する必要がある。国内では、亡くなった人の膵臓からインスリンを出す膵島細胞を取り出し、重症患者に移植する「膵島移植」が2020年から公的医療保険の対象になっているが、日本膵・膵島移植学会によると、ドナー不足などから保険適用後に実施されたのは10人以下にとどまっている。そこで京大などは、iPS細胞から膵島を作製してシート状にする技術を開発し、京大病院での治験実施を計画。計画では、健康な人のiPS細胞から膵島細胞の塊を作り、これらを集めて数センチ四方のシート状にする。これを複数枚、患者の腹部の皮下に移植する。治験の対象は、20歳以上65歳未満の患者3人の予定で、1年以上かけて安全性を確認する。シートが血糖値の変化に応じてインスリンを放出することで、注射をしなくても血糖値を安定させる効果が期待できるという。(2024年9月2日読売新聞) ◆ 1型糖尿病 膵臓の組織中に島のように点在しインスリンを分泌している膵島の細胞が壊れ、血糖値を制御できなくなる病気。若い人が発症することが多く、国内には推計で10万~14万人の患者がいる。中高年に多く生活習慣が発症に影響する2型糖尿病とは異なるが、いずれも腎臓の機能低下や網膜症、神経障害など様々な合併症が起きやすい。 健康保険証廃止12月2日まで3カ月 公的医療保険で受診時に使う現行の健康保険証は廃止期限(12月2日)まで残り3カ月となった。政府はマイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせたマイナ保険証への一本化を目指し普及を呼びかけるものの、利用率は低迷が続く。健康保険証は廃止期限以降、新規発行されなくなる。発行済みの保険証は猶予期間があり期限後も最長1年間(2025年12月1日まで)は使用できる。マイナ保険証を利用していない人全員に対しては、保険証代わりに使える「資格確認書」が届く。申請不要で、自治体や勤務先の健康保険組合などが24年12月以降に順次発送、有効期限は最長5年となる。マイナ保険証の7月の利用率は11・13%。(2024年9月1日産経新聞) |
| たはら整形外科 |