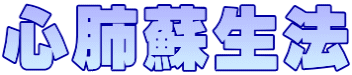 |
|
| 世界標準心肺蘇生法とは | |
| 呼吸が停止すると、数分以内に心臓も停止し、生命の危機をもたらします。呼吸停止後、2分以内に心肺蘇生を行うと救命率は90%です。しかし、3分後では75%となり、4分後では50%で、5分後では25%となり、10分後には救命率は限りなく0%に近くなります。従って、数分以内に適切な心肺蘇生が行われるかどうかが、生死の分かれ目となります。 しかし、最近まで標準化された適切な心肺蘇生法はなく、個々の病院で、それぞれの心肺蘇生法が行われているのが現状です。2005年度にアメリカ心臓病学会より、多施設でのデーターを基に、標準化された心肺蘇生法が発表されました。以後、現在ではこのガイドラインに沿った心肺蘇生法が、国際的なスタンダード蘇生法として推奨されています。 その世界標準心肺蘇生法とは、一般市民が行うことのできるBLS(Basic Life Support、一次救命処置)と、医療従事者が行うACLS(Advanced Cardiovasular Life Support、二次救命処置)とに分かれます。 |
|
| BLS(Basic Life Support) | |
| BLSとは、一般市民が行う事ができる蘇生法で、救急車が到着するまでに医療器具を用い無いで行う心肺蘇生法です。もし、現場が病院内であれば、蘇生器具が届くまでに行う蘇生法という事になります。BLSは以下の手順(1〜7)に則って行われます。 | |
| 1 意識状態の確認 2 119番・救急隊への通報 3 気道確保(Airway) 4 呼吸の確認 5 人工呼吸(Breathing) 6 循環サインの確認 7 心臓マッサージ(Circulation) 以上の処置にて脈拍や呼吸が確認されれば、回復体位をとり、救急隊や医師の到着を待ちます。 |
|
| 実際の状況に沿った手順 |
|
| 倒れている患者がいると、まず肩を叩いたり、揺すったり、声をかけたりして、刺激に対する反応を観察し、意識の状態をチェックします。意識がないと、直ちに119番へ通報して救急車を呼び、人手を集め、救急隊が到着するまで心肺蘇生を開始します。(もし現場が病院内であれば、直ちにバックマスクや除細動器などを手配します)。 まず、気道を確保し(口や鼻から肺までの空気の通り道を開ける事を気道確保と言います。あご先挙上法で行います、すなわち、下顎を挙上し、頭部を後方へ反らします)、次に、呼吸状態を観察します(胸や腹の動きを見て、呼吸音を聞いて、吐息を感じて、呼吸をチェックします)。呼吸がなければ、直ちに人工呼吸を開始します(ハンカチなどを口に当てて、mouth to mouth の人工呼吸を行います。その際、下顎を少し持ち上げ、鼻をつまみ、胸が少し持ち上がる程度に2回ほど息を吹き込みます)。 次に循環の状態を観察します(息があるか、咳をしているか、体の動きがあるか、頚動脈の拍動があるか)。これらのサインがなければ、心停止と判断し、心臓マッサージを開始します(マッサージの部位は乳頭と乳頭の間で、1分間に100回の速さで、圧迫は強く、胸を3〜5cm程度押し込む程度で行ないます)。2回の人工呼吸と30回の心臓マッサージを交互に繰り返し、これらを5サイクル(2分間)行い、呼吸や脈拍をチェックします。 この時点で、呼吸や脈拍が確認できなければ、救急車や蘇生器具が届くまでひたすら心肺蘇生を行います。呼吸と脈拍が確認できれば、回復体位(昏睡体位)をとり救急隊の到着を待ちます。 |
|
| ACLS(Advanced Cardiaovasvular Life Support) | |
| ACLSはBLS(人工呼吸や心臓マッサージなど)を行っても、呼吸や脈拍が確認されない場合に行われ、医師や看護師が除細動器や薬剤を用いて行う心肺蘇生法です。 ACLSは世界の蘇生に関するデーターを基に作成された最も効果的な蘇生法です。ACLSは数名でチームを組み行われます。すなわち、チームリーダーの基に、モニターの管理や除細動器の管理、呼吸の管理、血管確保、心臓マッサージなどの担当に分かれて作業する事になります。 蘇生に必要な器具が到着すると、心臓マッサージを継続しながら呼吸管理を行い(バックマスクでリザーバーバックを付けて100%酸素で行います)、心臓の状態をモニターでチェックし、VF(心室細動)/VT(無脈性心室性頻拍)か、Asystole(心電図で脈がフラットになる場合)やPEA(pulseless electrical activity 無脈性電気活動でVF/VT以外の場合)か、を判断します。 |
|
| ■VF(心室細動)/pulselessVT(無脈性心室頻拍)の場合 | |
| 心停止の状態で、モニターでVFやVTを認めれば、直ちに除細動を行います。まず、除細動は200Jから開始し、脈が現れなければ、さらに300J、360Jと放電を繰り返します。 除細動を行っても脈が再開しなければ、直ちに気管内挿管(挿管に30秒以上を要する場合には、無理に気管内挿管を行わず、バックマスクによる換気を継続します)と、血管確保(肘正中静脈より血管を確保し、生食かリンゲル液でルート確保)を行い、ボスミン1A(1mg)を投与します。この際、生食20mlにてボスミンを後押し、上腕を10秒間挙上します(早く薬液を心臓へ到達させるために行います)。その間、人工呼吸と心臓マッサージは継続します。ボスミン1A(1mg)で効果がなければ、さらに、5分間隔でボスミン1Aを繰り返し投与します。 これらにて脈が再開しなければ、再び360Jで除細動を試みます。必要に応じて、リドカインやアトロピン、メイロンなどの薬剤を投与します。もし、これらにて蘇生効果が無ければCCUへ転送します。(VF/VTによる心停止は迅速な除細動によって救命される可能性が高く、発症直後であれば救命率は90%で、1分遅れるごとに7〜10%づつ低下します。病院内であれば3分以内に、病院外であれば5分以内の除細動が推奨されます) |
|
| ■Asystole(心静止)/PEAの(無脈性電気活動)場合 | |
| Asystoleは心静止の状態で、モニターでは完全なフラット波形を呈します。PEA(pulseless electrical activity、無脈性電気活動)とは、VFやVT、Asystole以外の波形で脈が触れないものをいいます。 モニターでAsystoleやPEAと判断されると、除細動の適応はありません。直ちに気管内挿管と血管確保を行い、ボスミン1A(1mg)の投与を行い、人工呼吸と心臓マッサージを継続します。ボスミン1A(1mg)で効果なければ、さらに、5分間隔に繰り返し、ボスミン投与を行います。必要に応じて、リドカインやアトロピン、メイロンなどの薬剤を投与します。これらの処置をsinus rhythmになるまで行います。もし、途中でVFかVTになると除細動を行います。何の反応も無ければ、救急車の到着を待って総合病院へ搬送します。 尚、最近では一般市民にも簡単な操作で除細動が行えるAED(automated external defibrillator ・自動体外式除細動器で、音声誘導で簡単)が開発され、いろんな公共の場で、いつでも使用出来るように配置されております。日本では平成16年7月から一般市民でもAED使用が可能となりました。 現在、一日に約100人程度が心臓突然死(大半が心室細動)で亡くなられています。例え、AEDを使用しても、10分過ぎると、まず助けられません。そのため、数多くの場所にAEDを配置していただき、ためらわず、迅速にAEDを使用しましょう。
|