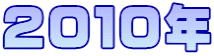
|
自閉症は遺伝子のコピーミスからか? 新生児100人に1人の割合で生じるとされる脳の機能障害「自閉症スペクトラム」が、複数の遺伝子のコピーミスから起きる可能性があることが、英オックスフォード大などの研究で分かった。自閉症スペクトラムは、他者とのコミュニケーションや社会性の発達に遅れが見られる。自閉症のほか、知的障害がなく特異な才能を発揮する「アスペルガー症候群」なども含み、症状の多様さから「スペクトラム(連続体)」と呼ばれる。チームはヨーロッパ人の患者996人と健康な1287人のゲノム(全遺伝情報)を比較。その結果、父と母から一つずつ受け継ぐべき遺伝子が一つ足りなかったり、三つになるコピーミスが健康な人より平均19%多く、健康な人ではめったに起きない遺伝子で起きていた。コピーミスは「コピー数多型」と呼ばれ、健康な人では病気のかかりやすさや薬の効き方の個人差として表れる。チームは、鍵となる遺伝子の複数のコピーミスが発症につながるとみている。(平成22年6月10日 毎日新聞) 肥満抑制たんぱく質を発見 東京大の宮崎徹教授らのチームは肥満の原因となる「脂肪細胞」がためこむ脂肪を溶かす作用のあるたんぱく質を発見した。このたんぱく質を体内で作れないようにしたマウスは肥満になったが、逆に与えると肥満が改善された。人間でも同様の働きがあると考えられ、肥満症の治療薬開発などにつながる可能性がある。脂肪を溶かすことが分かったたんぱく質は、体内の免疫細胞で作られる血液中に含まれる「AIM」である。AIMを作れないように操作したマウスは脂肪細胞内に通常よりも多くの脂肪を蓄積して、正常なマウスと比べて体重が1.5〜2倍になった。しかし、このマウスにAIMを注射すると正常なレベルまで体重が減ったという。AIMは人間の体内にもあることが、すでに分かっている。肥満の人は、多くの脂肪を体内の脂肪細胞内にためこんで細胞が肥大化している。肥満が進むとAIMの血中濃度が高まって脂肪細胞の中に取り込まれ、細胞に蓄積された脂肪を溶かしていく。肥満が進んだときに体がAIMをたくさん作り、それ以上太らないようにする役割を担っていると考えられるという。AIMは脂肪細胞のみに作用するので副作用の心配も少なく、肥満症の治療薬開発につながる可能性があると研究グループではみている。(平成22年6月9日 日本経済新聞) 骨折、早く治す注射 骨折した患部に細胞増殖を促すたんぱく質を注入すると、治癒を大幅に早める効果があることを、東大病院のグループが確かめた。すねの骨折では治療期間が約4週間短縮された。実用化すれば、松葉づえが必要な期間を短くでき、糖尿病などが原因で骨折が治りにくくなっている人の治療にも役立ちそうだ。同病院整形外科・脊椎外科の中村耕三教授らは、骨や皮膚の細胞を増殖させるFGF―2というたんぱく質を利用。国内48施設の協力で、治療に時間がかかる、すねの骨を骨折した直後の患者71人を対象に、FGF―2を患部に注射した47人と、注射しなかった24人とで効果を比較した。その結果、FGF―2を注入した患者は14週間で半数が治癒し、24週間後に治りきらなかったのは1人だけだった。一方、注入しなかった患者のうち半数は治るまで18週間かかり、24週間後も4人が完治しなかった。グループの川口浩准教授は「骨折が治りにくい人は繰り返し折れたり、骨が変形したりしやすい。今後、最終的な臨床試験を実施し、早期の実用化を目指したい」と話している。(平成22年6月9日 読売新聞) 統合失調症示す血中物質を突き止めた 統合失調症の患者の約4割で、血液中の「ペントシジン」という物質の濃度が高くなっていることを、東京都精神医学総合研究所と東北大学の研究チームが突き止めた。この病気は原因不明で、発症を示す物質の発見は世界初。関連するビタミンの低下も患者の約2割で確かめており、血液検査による診断や発症予防、早期の治療開始が可能になりそうだ。統合失調症は、幻覚や妄想が生じて思考が混乱したり、感情が不安定になったりする病気である。国内には100万人弱の患者がいて、10〜30歳ごろに発症する。発症は症状が出るまでわからない。原因は脳内の神経伝達物質ドーパミンの過剰放出とする説もあるが、ドーパミンを抑える抗精神病薬が効かない患者もいる。同研究所の糸川昌成研究員らは、統合失調症の患者45人の血液を解析。うち21人でアミノ酸の仲間であるペントシジンの血中濃度が、健康な人より平均1・7倍高く、高い患者ほど抗精神病薬が効きにくいことを発見した。このうち11人は、ペントシジンなどを体外に排出するビタミンB6化合物の血中濃度が5分の1に下がっていた。ビタミンB6化合物は現在、米国で糖尿病合併症の治療薬として臨床試験中で、糸川さんは「統合失調症の新薬としても期待できる」と話している。(平成22年6月8日 読売新聞) アレルギー抑制分子を発見 ぜんそくやアトピー性皮膚炎、花粉症などアレルギー症状を抑える分子を、渋谷彰・筑波大教授(免疫学)らが発見した。この分子の働きを強めることができれば、さまざまなアレルギーに共通する薬の開発につながる可能性がある。アレルギーは、花粉や食べ物などに含まれる特定の物質「抗原」が体内に侵入し、肥満細胞が反応、炎症を起こすヒスタミンなどの化学物質が過剰に放出されて起きる。これらの化学物質の働きを抑える薬はあるが、完全に抑えるのは難しい。そこで、研究チームは化学物質を出させない方法を探った。その結果、肥満細胞の表面にある特定の分子を刺激すると、化学物質の量が、刺激なしに比べて半分程度に減ることを突き止めた。また、この分子を持たないマウスを作ると、通常のマウスより激しいアレルギー反応が起きた。この分子は花粉など抗原の種類に関係なく、アレルギー反応を抑えることも分かり、研究チームは「アラジン1」と命名。人にもアラジン1が存在することを確認した。日本では国民の3割が何らかのアレルギーを持つと言われる。渋谷教授は「アラジン1の働きを高めることによって、アレルギーを効果的に抑制できる」と話す。(平成22年6月7日 毎日新聞) がん発見技術を開発 群馬大の竹内利行らの研究グループは、有機物を使った発光技術「有機EL」(エレクトロ・ルミネッセンス)に用いられる素材を使って、がん組織を可視化する技術を開発したと発表した。マウス実験では直径2ミリのがんも検知しており、早期発見に役立つことが期待される。この素材は「イリジウム錯体」という化合物で、低酸素状態で光を当てられると発光する特性をもつ。研究グループは、がん組織は酸素の補給が不足し、低酸素状態になっていることに着目。イリジウム錯体の活用を試みた。実験では、がんを移植したマウスに、イリジウム錯体の水溶液を静脈から注入。その5分後から、がん細胞に届いたイリジウム錯体の発光が確認され、がんの場所を特定できた。当初は、臓器などの表面から深さ4ミリまでのがんしか検知できなかったが、イリジウム錯体を改良して深くまで到達する長波長の光に反応するようにし、表面から1センチまでのがんを調べられるようにした。理論上は、2センチ程度まで可能になるという。胃や大腸のがん、乳がんやぼうこうがんなど、部位の表面や近くにできるがんの発見に役立つ。エックス線や磁気で調べるよりも検出機器が安価なため、検査を低コスト化するという利点もある。(平成22年6月4日 読売新聞) 放射線治療、誤差1ミリ 山形大医学部は、国内最高精度のがんの放射線治療装置を導入。既存の装置では放射線照射の誤差が最大で10ミリ程度あったが、最新設備ではほぼ1ミリ単位で立体的にがん組織に照射可能で国内でも4、5台しか導入されていない。肺の中皮腫など疾患部分の形状が複雑でこれまで放射線治療が難しかったがんにも対応できるようになり、同大がん臨床センターは「放射線治療の需要が高まる中、東北のがん診療拠点の役割を果たしたい」としている。新たに導入するのは、米・独社製の「強度変調放射線治療(IMRT)装置」と、患部の位置を正確に測定する「イメージガイド」を組み合わせた設備。国の助成を受け、約12億円かけて周辺機器と治療室を整備する。最新のIMRTは、2方向から600万〜1000万ボルトのX線を当て、誤差2・5ミリレベルで複雑な3次元の立体形状に照射することが可能。新型イメージガイドは、呼吸による患部の動き(位相)も想定しIMRTの照射に合わせるように台が微妙に動くことで、照射精度が飛躍的に高まる。2つの装置を組み合わせることで、精度の誤差は1ミリ程度にまで向上した。これまでは、皮膚に印を付けて放射線を当てる治療法で最大10ミリ程度の誤差があり、がんの周辺の正常な細胞や組織を傷付ける恐れがある場合は、外科的手術や設備の整った他県の病院に依頼するなどしてきたという。また、横隔膜の周辺に湾曲した形で広がる中皮腫や、頭蓋骨に沿った骨転移など、がんが正常組織を取り囲むように位置する場合、十分量の照射をすることは事実上不可能だったが、対応できるようになる。新設備では、事前に撮影したMRIやCTの画像をもとに10〜20時間かけて治療プログラムを組むが、手術時間は10〜15分程度で済み、患者の負担も大きく軽減されるという。付属病院2階に治療室を設け、試験運用を経て早ければ7月中に稼働させる。同大がん臨床センターによると、全国で放射線治療を受ける新規がん患者は、1990年に年間約5万人だったが、近年は20万人を超える。局所治療効果が高く臓器の温存が可能なことや、2008年4月から、IMRTが保険診療となったことも要因。同センターは、「患者にとってより安心できる治療法を追求していきたい」としている。IMRT がん組織の機能を低下、停止させる放射線治療機器。周囲への副作用を減らすため、がんの形状に合わせて様々な角度から立体的に放射線を照射する。イメージガイド 患部に弱いX線などを当てて3次元で正確な位置を計測する。(平成22年6月4日 読売新聞) 酒かす成分、肝臓保護 かす汁など冬の家庭料理で親しまれている酒かすに含まれる成分が、肝臓を保護する効果があるという研究結果を、月桂冠総合研究所がマウスを使った実験で明らかにした。酒かすをそのまま食べただけでは効果は限定的とみられるが、酒かすの利用法で選択肢が広がるとして、月桂冠は今後、成分を機能性食品などとして商品化することを検討するとしている。強い酸化力をもつ「活性酸素」が体内で増えると、臓器が傷つくなどして、様々な病気を引き起こす。特に肝臓は血液にのって活性酸素や過酸化脂質が集まりやすく、酸化を防ぐことが重要だと考えられている。同研究所は、日本酒を製造する過程で副産物としてできる酒かすの約6割を占めるたんぱく質に注目。これを酵素で分解してペプチドと呼ばれる断片にし、その働きを調べたところ、肝臓内で活性酸素を防御する働きがあるグルタチオンという物質と同様の酸化抑制作用があることを確認した。さらに、マウスの腹部に肝障害を引き起こす薬剤を一定期間、注射し続け、その間、グループごとに様々な餌をやる実験を実施。その結果、肝障害の指標となるGOTとGPTの数値について、普通の餌を食べさせた場合を100とすると、断片の入った餌をやったグループでは、それぞれ39と26だった。一方、酒かすをそのまま食べさせた場合は、普通の餌より両方の数値とも低かったが、断片入りの餌ほどには効果が出なかった。このことから、酒かすに含まれる成分に肝機能保護や肝障害予防の効果があると結論づけた。(平成22年6月4日 読売新聞) 血流の始まりは酵素、血栓症予防に期待も 脊椎動物で血液循環が始まる仕組みを、瀬原淳子・京都大教授(発生生物学)らが解明した。血流が始まる端緒は心臓の拍動ではなく、血管の内壁につながった赤血球が、はさみ役の酵素で切られ、流れ出すという。この酵素は人の血液細胞に存在し、脳梗塞など血栓症の予防や治療に役立つ可能性がある。研究チームはゼブラフィッシュの受精卵を使い、赤血球の循環が始まる様子を世界で初めて撮影した。それによると、血管の外で作られた赤血球は血管内に移動して内壁に接着。血液を全身に送り出すポンプとなる心臓の拍動が始まっても1時間以上もとどまった後、一気に流れ出すことが分かった。また、赤血球を血管内壁と接着させるたんぱく質を分解する酵素「ADAM8」が働かないように操作すると、赤血球はいつまでも血管内にとどまった。将来、ADAM8の働きをあらかじめ調べたり、制御できれば血栓が生じるのを予測したり、防ぐことも期待できるという。瀬原教授は「血液循環の始まりは心臓の拍動という受け身な要素が大きいと考えられていた。赤血球が血管の状態を察知して、循環を始める時期を決めているのではないか」と話す。(平成22年6月4日毎日新聞) 潰瘍性大腸炎、抗生物質で新療法 腸管の慢性的な炎症で、血便や腹痛が続く難病「潰瘍性大腸炎」の治療で、抗生物質3剤を2週間服用するATM療法を行うと、半数の患者の症状が著しく改善することが、慈恵医大柏病院消化器・肝臓内科の大草敏史教授らの研究で分かった。潰瘍性大腸炎は、若い世代で発症者が増え、国内患者数10万人。原因不明で特効薬がなく、ステロイドなどで免疫力を抑える。ATM療法は、特定の腸内細菌がこの病気を引き起こすとの考えに基づき、アモキシシリンなどの抗生物質3剤で細菌をたたく治療法。使用中の治療薬に、2週間加えて服用する。研究では、ATMを加える組と偽薬を加える組の改善度を比較。血便や下痢が日に何度もあるような中等症以上の患者(116人)では、ATMの組の49%が3か月後に腸管の炎症が消えたり、軽症になったりした。偽薬の組は22%だった。ステロイドを止めると症状が悪化する患者にATMを行うと、1年後には35%がステロイドを止められた。(平成22年6月3日 読売新聞) 脳の情報やりとりの様子撮影 記憶をつかさどる脳の海馬の神経細胞が協調して働く様子を高速で撮影することに、東京大学の池谷裕二准教授らが世界で初めて成功した。記憶や精神疾患の解明につながる成果。脳の活動を調べるには、血流の変化を連続的にとらえるfMRI(機能的磁気共鳴画像)があるが、撮影できるのはせいぜい約1ミリ・メートル四方。細かく見るため顕微鏡を使っても1秒間に数十枚撮影が限界だった。研究チームはレーザーを使った顕微鏡とカメラを組み合わせ、1秒間に2000枚撮影できる装置を開発。ラットの海馬の神経細胞が活動時に光を出すよう処理した上で、約0・3ミリ・メートル四方の神経細胞100〜200個それぞれが出す光の変化を撮影。100分の1秒という短時間に、信号が伝わる様子を追跡できた。(平成22年6月3日 読売新聞) 梅干しにインフル抑制効果 和歌山県立医科大の宇都宮洋才准教授と、国立和歌山高専の奥野祥治助教が、梅干しから抽出された新発見の化合物から、インフルエンザウイルスの増殖を抑える効果があることを確認したと発表した。今回、見つかったのはポリフェノールの一種「エポキシリオニレシノール」。新型インフルエンザと同じ「H1N1型」のウイルスに感染させた培養細胞に新化合物のエキスを加え、約7時間後、化合物を加えなかった培養細胞と比較した結果、ウイルスの量が約10分の1になった。1日に梅干し5個分の化合物を摂取すれば、インフルエンザにかかりにくくなる効果が見込めるという。今後は、「エポキシリオニレシノール」に、親しみやすい愛称をつけ、商標登録することも検討。サプリメントの成分として売り出すことや、梅に、含有量を表示して販売促進にも活用できる可能性が出てきた。(平成22年6月2日 読売新聞) iPSで免疫力強化、皮膚がんマウス大幅に延命 iPS細胞(新型万能細胞)を使って免疫力を高め、皮膚がんのマウスを大幅に延命させることに、理化学研究所が成功した。人に応用できれば、がんの新しい治療法になりそうだ。免疫細胞の一種である「ナチュラルキラーT細胞(NKT細胞)」に着目し、マウスの脾臓からNKT細胞を集めてiPS細胞に変え、体外で培養して約1万倍に増やした後に、そのほとんどをNKT細胞に戻すことに成功した。こうして増やしたNKT細胞を、悪性黒色腫というがんを移植したマウスに注射すると、通常は1か月程度で死ぬマウスが半年後まで生存した。 (平成22年6月2日 読売新聞) ALS、新たな原因遺伝子発見 筋肉が次第に動かなくなる神経の難病、筋萎縮(いしゅく)性側索硬化症(ALS)の新たな原因遺伝子を広島大、徳島大などの研究チームが発見し、英科学誌「ネイチャー」に発表した。ALSは年間10万人あたり2人程度の患者が報告され、9割は原因がはっきりしない孤発性、残りが遺伝性だ。研究チームは原因遺伝子を探るため、遺伝性のALS患者に着目した。父由来と母由来の遺伝子に同じ変異がある場合に発症する可能性を考え、近親婚の両親を持つ患者6人の遺伝情報を調べた。その結果、半数の3人が、緑内障の原因遺伝子「OPTN」に変異を持っていた。OPTNはがんや炎症に関与するたんぱく質が過剰に働くのを抑える役目がある。変異によってこの機能が失われ、運動神経に影響を与えたと推定された。広島大の川上秀史教授(分子疫学)は「孤発性の患者でも、この遺伝子が作るたんぱく質に異常が見られることから、この遺伝子は発症に関与していると思う」と話す。(平成22年6月1日 毎日新聞) B型肝炎、父子感染にも注意 父親からB型肝炎に感染する乳幼児がいることが、大阪大などの調査でわかり、専門家が注意を呼びかけている。母子感染に比べ、父子感染はあまり知られておらず、食べ物の口移しなどで知らぬ間に感染しているようだ。祖父母や兄弟を介したとみられる例もあり、専門家は「家族で検査を受けて感染者がいれば、ワクチンで乳幼児への感染を防いで」と呼びかけている。 B型肝炎は血液や体液を通じて感染する。唾液中のウイルスは少ないが、食べ物の口移しなどを通じて、子どもに感染する可能性がある。大人が感染しても一過性で終わることが多いが、乳幼児がかかると、慢性化して肝硬変や肝がんに進みかねない。(平成22年年5月27日 朝日新聞) 犬・猫の細菌で感染症、死亡例も 犬や猫の口の中にいる細菌に、2002年から14人が感染、発症し、うち6人が死亡していることが、国立感染症研究所のまとめでわかった。「カプノサイトファーガ感染症」と呼ばれるが、実態がよくわかっていない。見逃されている患者も多いとみられる。この細菌には、ひとが犬や猫にかまれたり、ひっかかれたり、傷口をなめられたりすると、極めてまれに感染、発熱や腹痛、吐き気などの症状が出る。発症すると血圧が急に下がり、血中で菌が増え、敗血症で亡くなることがある。高齢で免疫機能が低下した人、ステロイド剤で膠原病や腎炎などの治療をしている人などは注意が必要だ。抗生剤で治療できる。ただ、感染力はかなり弱く、犬と猫をさわった後はよく手を洗い、口移しでえさを与えるなどしなければ、まず感染の心配はない。かまれるなどして、発熱した場合、医師に相談することも必要だ。(平成22年5月24日 朝日新聞) |