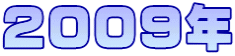
|
10分の運動で頭スッキリ 筑波大によると、これまで長時間の適度な運動が脳を活性化させることは「常識」として知られていたが、短時間でも脳が活性化することが科学的に裏付けられたのは初めて。同大の征矢英昭教授は「メタボ対策だけでなく、健康な人でも昼休みにちょっとした運動をすることで集中力が高まる」と話している。征矢教授によると、研究は19〜24歳の男女計20人を対象に実施。50%の力で自転車をこぐ「中強度」の運動を10分間した後、脳の活動を画像化する装置で測定すると、全員で左脳の前頭前野の一部の血流が増加し、情報処理などの能力が向上したという。(平成21年12月22日 中国新聞) 第3の治療薬ペラミビル 厚生労働省は新型インフルエンザ対策として、タミフル、リレンザに続く第3のインフルエンザ治療薬「ペラミビル」(商品名・ラピアクタ)を1月にも承認する方針を決めた。タミフル耐性の新型インフルエンザウイルスが出現しており、医療現場での治療薬選択の幅を広げるのが狙い。ペラミビルは点滴注射薬で経口や吸入で服用するタミフルなどと異なり、人工呼吸器で管理されたり、意識不明の状態に陥ったりした重症患者に使いやすいとされる。(平成21年12月19日 読売新聞) 消化器系がんを血液検査で検出 金沢大医薬保健研究域の金子周一教授らは血液中に含まれる遺伝子を調べることによって胃や大腸など消化器系のがんを発見できる検査方法を開発したと発表した。血中の特定たんぱく質を調べる現行検査に比べ精度が高く、健常者の健康診断などで実施すれば、がんの早期発見につながるという。研究チームはヒトの遺伝子のうち約1800の異常が消化器がんと関係があることを突き止めたとしているが、どの遺伝子を検査しているか現時点では明らかにしていない。53人の消化器がん患者と健常者から採血して遺伝子を調べたところ、約9割の確率でがん患者と健常者を判別できた。がんの部位が胃・大腸か、膵臓(すいぞう)かも、約7割の確率で特定できたという。現行検査は「腫瘍(しゅよう)マーカー」と呼ばれる血中の特定たんぱく質でがんの兆候をとらえるが、がんを発見できる確率はあまり高くない。(平成21年11月20日 日本経済新聞) 新型インフル、ワクチン副作用は1万人に1人 世界保健機関(WHO)は新型インフルエンザ用ワクチンの接種による副作用の発生率は1万人に1人(0.01%)程度との調査結果を発表した。副作用は発熱や頭痛、倦怠(けんたい)感などで、通常は48時間以内に回復しているという。WHOはワクチンの安全性について「60年以上使われてきた季節性インフルエンザ用ワクチンと同程度で、非常に高い」と強調した。ただ、調査結果では副作用が発生した20人のうち1人は死亡したり、重症化したりしているという。死亡例についてWHOは「これまでの報告ではワクチンは直接の原因ではない」としており、もともと別の疾患を持っていた可能性があるという。WHOによると、ワクチンはこれまでに全世界で8000万回分が出荷され、すでに6500万回分が接種された。(平成21年11月20日 日本経済新聞) 花粉症のもと食べれば症状和らぐ 花粉症を引き起こすのは花粉に含まれる抗原と呼ばれる物質。これが体に入ると免疫反応が過剰になって鼻水やくしゃみが出たり、目がかゆくなったりする。都は抗原を体内に取り込んで体を慣らし、免疫反応を抑える「減感作療法」の一つとして、日本医科大と共同で06年夏から実験を始めた。花粉症の症状がある142人の舌の下に、スギ花粉の抗原を含ませた約1センチ角のパン片を置いて投与するもので、期間は2年間。1日1回2分間で最初は毎日投与し、次第に濃度を濃くして回数を減らした。その結果、100人の症状が改善した。花粉飛散期に常に鼻が詰まっていた重症者は28%から4%に激減。ほとんど症状が出ない人は逆に5%から20%に増えた。今年の都内の花粉飛散量は06年比で約6倍だったので、都は「効果は飛散量に左右されない」としている。同様の研究で、100人以上の患者データを同時に集めた実験は国内で初めてという。都は「今回の方法なら自宅で簡単にできる」と期待する。だが、治療に使う抗原は、薬事法に基づく承認が必要になった場合、治験などに数年かかる可能性がある。都は、パン片の代わりにトローチなどへの改良も検討し、早期の実用化に向けて国や製薬会社へ働きかけを進めるという。(平成21年11月4日 朝日新聞) 痛風の原因遺伝子突き止める 激しい関節痛を伴う生活習慣病、痛風の主要な原因となる遺伝子の変異を、防衛医科大や東京大、東京薬科大など11機関のチームが突きとめた。患者の8割がこの変異を持ち、ない人に比べて26倍痛風になりやすい変異もあった。個人差に応じた予防や治療法の開発につながるという。痛風は血液中の尿酸の濃度が高い状態が続いて起こる。07年の国民生活基礎調査によると、痛風で通院している人は約85万人。関節などに尿酸が結晶化してたまり、炎症が起こって痛みを生じる。まれな先天性の代謝異常で起きる場合を除き、多くは原因が不明だった。チームが見つけたのは、腎臓や腸管から尿酸を体外へ排出する働きをもつと考えられる「ABCG2」という遺伝子。この遺伝子の配列のうち、尿酸が排出されにくくなる変異を5ヵ所突きとめた。痛風患者を含む尿酸値の高い人と正常値の人計1千人以上の男性を対象に、変異の様子を調査。5つの変異のうち重要な変異は2ヵ所で、患者の8割がどちらかの変異を持っていた。変異の組み合わせによって、尿酸の排出機能が4分の1以下に減る患者が1割おり、全く変異を持たない人よりも26倍痛風になりやすいことも分かった。松尾洋孝・防衛医科大助教は「遺伝子変異があれば必ず痛風になるわけではないが、2つの変異があるかどうかで、なりやすさが分かる。リスクの高い人は食事療法をするなど、早期の予防や治療に役立てることができる」と話している。(平成21年11月5日 朝日新聞) ロタウイルス向けワクチン グラクソスミスクラインは幼児の胃腸炎を引き起こすロタウイルスの感染を予防するワクチンを年内にも日本で承認申請する。実用化すれば同ウイルス向けでは日本初のワクチン。日本では感染症の対策に治療薬の普及が先行しているが、新型インフルエンザの流行でワクチンの重要性が見直されている。主力のワクチンを相次いで日本に投入し、今後の市場拡大に備える。 年内にも承認申請を目指すのは「ロタリックス」。幼児が感染すると激しい下痢や脱水症状を起こすロタウイルスへの感染を予防する。世界100ヵ国以上で承認を受けている。日本では年内に投入する子宮頸癌向けとともに同社の主力ワクチン。 (平成21年11月3日 日本経済新聞) 早期腎臓病に高脂血症薬が有効 東北大の阿部高明教授と慶応義塾大の曽我朋義教授らは、悪化すると人工透析が必要になる慢性腎臓病の早期治療に、高脂血症の治療で広く使われている薬「スタチン」が有効であるとの研究結果をまとめた。ラットの実験で働きが弱くなった腎臓が回復することを確かめた。東北大医学部付属病院で患者を対象に有効性を見極める臨床研究を始めた。腎臓のほとんどを摘出して血中の不要物質を尿に送り出す働きを弱めたラットでスタチンの効果を調べた。スタチンを投与した5匹は投与しなかった5匹に比べ体内に残る不要物質の量が平均して半分以下になり、腎臓がより働いていた。不要物質は毒性があり、体内に長い間たまり続けると腎臓の機能が弱まる。慢性腎臓病の患者は国内で1330万人と推計され、悪化して人工透析を受ける患者も増加の一途で27万人いるとされる。阿部教授は「腎臓病の早期患者では副作用は起きにくく、症状の悪化予防に効果が期待できそうだ」と話している。(平成21年10月30日 日本経済新聞) 高脂血症薬でインフル患者の死亡率低下 高脂血症の治療薬として広く使われているスタチンがインフルエンザ重症患者の死亡率をほぼ半減させることが、オレゴン州など米10州の保健当局の研究チームによる疫学調査でわかった。当地で開かれている米感染症学会で30日、発表された。発表によると、07〜08年、10州の成人計2800人の季節性インフルエンザ入院患者を調査。入院中か退院から30日以内の死亡率は、入院中にスタチンの投与を受けていた人は2.1%、受けていなかった人は3.2%だった。投与を受けていた人は、より高齢で心臓病などの病気にかかっている傾向があるにもかかわらず、死亡率が半分近くになっていたことから研究チームは「スタチン投与は死亡率の低下と関係がある」と結論づけた。スタチンには血中コレステロール値を下げる働きのほか、免疫抑制の効果もある。インフルエンザは、患者の免疫系がウイルス感染に過剰反応して重症化することがわかっており、スタチンはこれを防いでいるらしい。またスタチン投与を受けていた敗血症や肺炎の患者の死亡率が低い傾向も知られていた。今回の調査は季節性インフルエンザに関するもので、新型の豚インフルエンザについては調べていない。しかし研究チームは新型の豚インフルエンザにも同じ仕組みで効果があると期待している。スタチンは遠藤章・東京農工大名誉教授が発見。さまざまな商品名で、高脂血症や心筋梗塞(こうそく)、脳卒中などの治療・予防薬として広く使われている。発表したオレゴン州保健局のメレディス・バンデミーアさんは「抗ウイルス薬のタミフルに比べると、特に後発薬スタチンは安い。治療効果が実証されれば、途上国でのインフルエンザ対策に役立つのではないか」と話した。(平成21年10月31日 朝日新聞) インフルワクチン、新型・季節性の同時接種 新型の豚インフルエンザの国内産ワクチンと、季節性インフルのワクチンとの同時接種について、厚生労働省の薬事食品衛生審議会安全対策調査会は安全面で問題がないことを確認した。今後、医療現場に周知する。また、同調査会は、妊婦への新型ワクチンの接種について、改めて安全性を検討。「接種しても子どもの先天異常の発生率は上がらない」とする季節性ワクチンの海外の研究報告や国内で1千人を超す妊婦への季節性ワクチンの接種経験から最終的に「問題ない」と判断した。インフルワクチンの医療機関向けの注意書き「添付文書」に「原則、妊婦へは接種しない」とあるため、今後これを削除する。また、一部の国内産の新型ワクチンに添加されている保存剤「チメロサール」について、季節性ワクチンでの使用実績などをもとに「使用に問題ない」とした。一方、厚労省は新型インフルワクチンの副反応をできるだけ早く把握するため、19日から始まる医療従事者の接種対象者のうち2万人を追跡調査し、11月下旬までに結果を公表する。全体で30万人程度が接種した時点で、まれな副反応の頻度を確認し、死亡など重い事例には専門チームを派遣して調べるという。調査会では、新型インフルの重症化予防策として注目されている成人の肺炎球菌ワクチンについても、医師の判断のもとで、新型インフルワクチンとの同時接種や、2回目以後の接種ができることを確認した。国内産の新型インフルのワクチンは19日から、医療従事者を対象にした接種が始まる。妊婦については、11月半ばから実施される予定。(平成21年10月19日 朝日新聞) 肺炎球菌ワクチンの再接種 厚生労働省は肺炎の重症化を予防する肺炎球菌ワクチンについて、1回目の接種から5年程度経ていれば再接種を認めることを決めた。新型インフルエンザに感染した65歳以上の高齢者が重篤な肺炎を併発することを防ぐ効果も期待される。同ワクチンは従来、再接種すると強い副作用が出るとして、接種は一生に1度とされていた。 だが、同ワクチンの効果は5年以上たつと低下する。海外などで4年以上の間隔を置けば、再接種は問題ないとの報告が出され、現在では欧米の多くの国で再接種が認められている。(平成21年10月19日読売新聞) 子宮頸がんワクチン年内にも発売 厚生労働省は子宮頸がんを予防するワクチン「サーバリックス」の製造販売を承認した。製造元のグラクソ・スミスクライン社は、年内にも同ワクチンを発売する。子宮頸がんワクチンの承認は国内初。子宮頸がんの主な原因であるヒトパピローマウイルス(HPV)のうち、7割を占める2種類のウイルス感染を防ぐことができると期待されている。ただ、ワクチンは3回の接種が必要で、費用は4万〜6万円程度かかる見込み。(平成21年10月17日読売新聞) 生活習慣病・がん、皮膚のガスから診断 キャノン国立循環器病センター研究所の共同チームは、皮膚から出る微量ガスを調べて病気を診断する新型装置の開発に着手した。皮膚表面に当ててガスを検出・分析するもので、血液検査のように痛みを伴わない。3年後をメドに試作装置を完成させ、糖尿病をはじめとする生活習慣病やがんの早期発見などに役立つ医療機器を目指す。病気によっては特有の微量成分が皮膚などから放出されている。糖尿病だと、皮膚からのガスにアセトンという物質が1PPM(PPMは100万分の1)ほど含まれるほか、乳がんや頭けい部がんの患部からは、ジメチルトリスルフィドという物質が出ることが分かってきた。このため、嗅覚(きゅうかく)が優れる犬を使い、がんを発見しようという試みもあるという。(平成21年10月17日 日本経済新聞) 脳の血流で認知症を早期診断 京都府立医科大は物忘れなどが起こる認知症の早期診断を一般向けに始めると発表した。近赤外光を頭に当てて脳表面近くの血流を調べる測定装置を使い、患者の血流量の変化を調べる。発症前でも早期に発見できれば、生活習慣改善や治療に取り組み認知症進行を遅らせられると期待している。早期診断を始めるのは京都府立医大の中川正法教授ら。近赤外線分光法と呼ぶ方法で、多数のセンサーが付いた専用器具を頭に載せるだけで簡単に血流の変化が分かる。1分間に動物や野菜の名前をできるだけ多く言ってもらい、その間の血流変化から、脳の前頭葉がどの程度活発に働いているかを判定する。認知症では脳の神経活動の反応が遅くなり血流量の増加ペースも鈍くなるので、そうした変化をとらえる。記憶障害の有無を調べるテストや磁気共鳴画像装置(MRI)で脳の画像を調べる検査などが普及しているが、ある程度症状が進んでいないと把握は難しく、新しい検査法を加えて総合的に診断する。週1回、1人を2時間かけて診断する。(平成21年10月15日 日本経済新聞) タミフル耐性ウイルスを検出 厚生労働省と札幌市は新型インフルエンザに感染した札幌市内に住む10代の女性から、治療薬タミフルに耐性を持つウイルスを検出したと発表した。耐性ウイルスは国内では8例目の検出だが、タミフルを服用していない患者からの検出は国内では初めて。人から人に感染する耐性ウイルスの可能性もある。女性は8月に発症し、治療薬リレンザを投与され回復。今月6日に国立感染症研究所の調査でタミフル耐性ウイルスと判明した。厚労省は「今後、周辺に感染の広がりがあるか注視する必要がある」としている。(平成21年10月8日読売新聞) インフルワクチン「強毒性」の開発加速 海外製薬会社が相次いで、現在流行中の新型インフルエンザより毒性の強いH5N1型に対するワクチンの開発に日本で取り組みはじめた。米バクスター・インターナショナルが日本で臨床試験(治験)を年内にも始めるほか、英グラクソスミスクラインは年末をめどに日本で承認を申請する。鳥インフルエンザから発生したH5N1型は致死率が高いだけに、万一の流行に備え対応を急ぐ。バクスターはベトナムで得たウイルスをもとに開発したH5N1型向けのワクチンの治験に乗り出す。100人以上の健康な日本人を対象に接種し、安全性や有効性を確かめる。同社はサルの腎臓から得た細胞を使ってウイルスを増殖させ、ワクチンを製造する。 (平成21年10月5日 日本経済新聞) 歯磨きでがんリスク3割減 1日2回以上歯を磨く人が口の中や食道のがんになる危険性は、1回の人より3割低いとの研究結果を、愛知県がんセンター研究所(名古屋市)がまとめた。全く磨かない人の危険性は、1回の人の1.8倍だった。約3800人を対象とした疫学調査の結果で、歯磨き習慣と発がんの関連を示す報告は国内初という。横浜市で10月1日から開催される日本癌学会で発表する。同研究所疫学予防部の松尾恵太郎室長は「口やのどには発がん物質とされるアセトアルデヒドを作る細菌がいる。歯磨きで細菌や発がん物質が洗い流されるので、少なくとも朝と夜に磨けば、がん予防に役立つ」と話している。同センターを受診した人の中から、口の中やのどなどの頭頸部がんと食道がんの患者計961人と、がんでない2883人に、歯磨きや喫煙、飲酒などの習慣を聞いた。年齢は20〜79歳で平均は61歳。解析した結果、2回以上磨く人は1回の人に比べ、がんになる危険性が約29%低く、全く磨かない人の危険性は2回以上磨く人の2.5倍だった。喫煙や飲酒をする人だけの解析でも同様の結果で、歯磨き習慣がないことが、ほかの危険因子と関係なく、独立したがんの危険因子であることを強く示すものだという。 アルツハイマーは睡眠不足から 睡眠不足がアルツハイマー病を引き起こす可能性があるとの研究結果を、米ワシントン大などの研究チームが発表した。物忘れがひどくなるアルツハイマー病は、脳内にアミロイドベータ(Aβ)という異常なたんぱく質が蓄積するのが原因と考えられている。研究チームは、遺伝子操作でアルツハイマー病にかかりやすくしたマウスの脳内を観察。Aβが起きている時に増え、睡眠中に減ることに気づいた。さらに西野精治・スタンフォード大教授らが、起きている時間が長いマウスではAβの蓄積が進むことを確認。不眠症の治療薬を与えるとAβの蓄積は大幅に減った。研究チームは「十分な睡眠を取ればアルツハイマーの発症が遅れるかもしれない。慢性的な睡眠障害のある人が、高齢になって発症しやすいかどうかも調べる必要がある」としている。(平成21年9月25日 読売新聞) 新型インフル、国民の大半「抗体なし」 国立感染症研究所は新型インフルエンザウイルスに対し、1930年代以降に生まれた80歳未満の国民のほとんどは抗体を持たないとする調査結果を発表した。1917年以前に生まれた高齢者は半数が抗体を持っていたが、1920年代に生まれた人は2割にとどまった。ほとんどの国民は抗体を持っていないことが改めて確認された。調査は感染研が過去約30年にわたり約15万人分の血清を集めた「国内血清銀行」から931の検体を使って実施。新型に対する抗体があるかどうか調べた。スペイン風邪と呼ばれる新型インフルエンザが18年以降に世界的に流行したが、感染研によると、それより前に生まれた92歳以上の高齢者は50〜60%が今回の新型インフルエンザの抗体を保有していた。(平成21年9月25日 日本経済新聞) 脳の「海馬」、形成に関与する遺伝子を発見 名古屋大学大学院医学系研究科の高橋雅英教授と同大高等研究院の榎本篤講師らのグループが、記憶や学習にかかわる脳の一部「海馬」の形成に重要な役割を果たしている遺伝子を発見した。海馬はてんかんや統合失調症などとの関連が指摘されており、高橋教授は「精神・神経疾患が発症する仕組みの解明に役立つのでは」と話している。海馬形成への関与が見つかった遺伝子は、「ガーディン」と呼ばれるたんぱく質。高橋教授らはガーディンのないマウスを作成して海馬を観察した。通常一列に並ぶはずの未熟な神経細胞が位置に異常を起こしたことから、ガーディンが新生した神経細胞の位置決定を制御していることを突き止めた。さらに、同様の位置異常が統合失調症の原因遺伝子とされる「DISC1」の量を低下させた場合でも報告されていることから、ガーディンとDISC1が協調的に働いている可能性を検討。両者が細胞内にあっても結合していないと位置異常が起きるため、2つの遺伝子の結合が海馬の神経回路の形成に重要であると結論付けた。(平成21年9月24日 毎日新聞) C型肝炎治療効果、遺伝子の違いで差 C型肝炎の治療が効くか効かないかは、人の遺伝子のわずかな違いが要因の一つになっていることが、国立国際医療センターの溝上雅史肝炎・免疫研究センター長と名古屋市立大の田中靖人准教授らのグループの研究でわかった。C型肝炎はウイルスが原因の病気で、日本人に最も多いタイプでは治療薬「インターフェロン」と抗ウイルス剤「リバビリン」の併用療法が有効とされている。しかし、約20%の患者は効きづらく、治療を受けてみないと効果がわからなかった。このため、効きづらい患者は、月数万円の薬代が無駄になったり、発熱やうつ病などの副作用が出かねない危険を抱えながら治療を続けなければならなかった。近く数千円の遺伝子検査キットが開発できるといい、治療前に血液を検査することにより、こうした問題を避けられるという。85〜95%の確率で、事前に薬が効くかどうかの見極めができるとしている。薬が効かないのは、C型肝炎ウイルスの遺伝子変異が要因との研究がすでにあったが、約400人の患者の血液を調べたところ、DNAにある個人ごとのわずかな違い(遺伝子多型)が特定の領域にある人は、ない人と比べ、薬が30倍効きにくかった。(平成21年9月14日 朝日新聞) インフルエンザ、ウイルス検出の高精度試薬開発 富士フイルムは14日、インフルエンザウイルスの検出の精度を大幅に高める試薬の開発に成功したと発表した。従来の検査方法に比べ、100分の1のウイルス量でも検出できる。インフルエンザ感染の初期段階でも感染の有無を特定できるため、早期の治療で重症化を防ぐ効果が期待できる。今後、病院での臨床試験などを経て、11年秋の商品化を目指す。医療機関での簡易的なインフルエンザの検査では、ウイルスに反応して色が変わる試薬が使われているが、感染したばかりでウイルスが少量の場合には、色が変わりにくい。富士フイルムは、従来の試薬に独自開発の還元剤を混ぜることで、ウイルスへの反応を増幅した。写真現像に使う技術を応用したという。(平成21年9月15日 毎日新聞) 新型インフルエンザの予防接種 厚生労働省は新型インフルエンザワクチン接種の具体的な方法を公表した。1人2回、医療機関に予約して接種することを原則とし、必要な自己負担は計6000〜8000円程度とみられる。「医療従事者」「妊婦」「基礎疾患のある人」など優先順位の高いグループから順に、ワクチンが確保でき次第、接種を始めるとした。今回の接種は予防接種法に基づかない任意接種の扱いで、国は接種の勧奨はしない。生活保護世帯などの低所得者の負担軽減策として自治体が助成するよう、国が補助金を出す。国産と輸入ワクチンで費用に格差が生じないよう、出荷時に国が価格調整をするという。接種は、(1)実施を希望する医療機関(2)市町村が選定した医療機関が実施、厚労省と委託契約を結ぶ。都道府県は10月中旬までに医療機関をリスト化しワクチン配分量を決める。医療機関での接種が原則だが、医師が出向いての集団接種も認める。医療機関で接種を受ける人には、母子健康手帳や保険証などの提示を求める。基礎疾患がある人は、かかりつけの医療機関での接種が望ましいが、別の医療機関で受ける場合は、主治医に「優先接種対象者証明書」を発行してもらう。新型インフルエンザは国民の大半に基礎免疫がないため2回の接種が必要で、3〜4週間の間隔を空けると効果が高いとされる。各グループの接種期間は1ヵ月半程度などを目安とする。副作用被害は医療機関から国に直接報告させ、速やかに公表するとした。(平成21年9月9日 毎日新聞) 新型インフルワクチン、1回接種で8割に免疫 スイスの大手製薬企業「ノバルティス」は英国で実施した新型インフルエンザワクチンの臨床試験で、有効性と安全性が確認されたと発表した。治験は18〜50歳の健康な100人を対象に実施。間隔を置いて2回接種することで90%以上の人に免疫がついたという。1回接種でも80%に効果があった。同社の日本法人は、同じワクチンを使った日本国内での治験を今月中にも始める。20歳以上の成人200人と生後6ヵ月〜19歳の120人に2回接種する計画。同社のワクチンには日本で使用経験のない免疫を強める添加物が入っている。(平成21年9月4日 読売新聞) 子宮頸がんワクチン 厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の部会は子宮頸がんを予防するワクチン「サーバリックス」の承認を了承した。10月に正式承認される見通し。このワクチンはオーストラリアなど95ヵ国で承認されているが、国内で子宮頸がんワクチンが承認されるのは初めて。2007年9月にグラクソ・スミスクライン社が承認申請していたもので、10歳以上の女性が接種対象となる。子宮頸がんは、性的接触によって感染するヒトパピローマウイルス(HPV)が主な原因とされている。今回のワクチンを感染前に接種すれば、子宮頸がんの原因の7割を占める2種類のHPVの感染が予防できると期待される。国内では毎年約7000人が子宮頸がんになり、約2500人が死亡している。特に20〜30歳代の若い女性で増えつつある。(平成21年9月1日読売新聞) 血圧高いと物忘れしやすい傾向 血圧が高い中高年は、脳に何らかの損傷を受けて物忘れしやすい傾向にあることが米アラバマ大バーミングハム校の研究でわかった。高血圧は脳卒中や心臓病などの危険を増すことが知られているが、認知症予備群も生み出していることになる。研究チームは、脳卒中を起こしたことがない45歳以上の米国人約2万人の血圧データと、「今日は何日ですか?」といった認知機能テストの結果を分析。高血圧は「最高血圧140ミリHg以上か最低血圧90ミリHg以上、あるいは高血圧の薬を服用している」と定義されるが、最低血圧が10ミリHg上がるたびに、認知機能に障害が出る危険が7%ずつ上がることがわかった。過去の実験研究では、最低血圧が高いと脳の細動脈が弱くなって神経細胞が損傷を受けることがわかっている。チームは「高血圧を治療することで、認知機能障害を防げる可能性がある」としている。今回の研究では、最高血圧と認知機能の間には関連は見られなかった。高齢者には高血圧と認知症が多くみられることから、関連があると考えられてきたが、これまで明確な結論は出ていなかった。(平成21年8月30日 朝日新聞) 1遺伝子だけでiPS細胞 様々な細胞に変化する人の新型万能細胞(iPS細胞)を1個の遺伝子を導入するだけで作ることに、独マックスプランク分子医薬研究所などのチームが成功した。使う遺伝子が少ないほど、がん化の危険性を減らせるため、安全な再生医療につながると期待される。研究チームは、材料に中絶胎児の神経幹細胞を選択。この細胞に、京都大学の山中伸弥教授がiPS細胞の作製に使った4個の遺伝子のうち、がん化の恐れの少ない遺伝子1個を導入した。その結果、10〜11週間後にiPS細胞ができ、筋肉や神経の細胞に変化することが確認できた。国立成育医療センターの阿久津英憲室長は「細胞の種類によって、iPS細胞の作りやすさが違うことが分かった。安全性の高い再生医療への応用に近づく」と話している。(平成21年8月29日 読売新聞) 寝る子は育つ、睡眠中も脳は学習 成績を上げるためにはよく寝ること。そんな教訓が得られそうな実験結果を、渡辺武郎・米ボストン大教授らのグループが発表した。学習中に活動する脳の領域が睡眠中にも活動しており、その活動が活発なほど学習効果が高い傾向があることを、機能的磁気共鳴画像(fMRI)で脳の活動の様子を調べて確認した。学習後に寝るほうが学習効果が高まるといわれているが、その仕組みはよくわかっていない。そこで、グループは、7人の被験者に、複雑な画像を素早く識別する訓練をしてもらった。訓練中は、脳の視覚情報を処理する特定の場所が活動する。学習した後、fMRIの中で寝てもらったところ、その場所が活発に活動することがわかった。寝ないで同じ訓練をすると識別の正答率は上がらなかったが、寝た後は正答率が上がった。睡眠中の活動が活発な人ほど、睡眠後の正答率が上がる傾向があることも明らかになった。睡眠中に学習した脳活動を繰り返して、脳の中に学習内容を「固定」していると推定されるという。「睡眠によって疲れがとれるから学習効果が高まるように見えるという考えもあったが、脳が活動して、学習を固定化していることがわかった」と渡辺教授は話している。(平成21年8月27日 朝日新聞) 新生児・乳児にもタミフル投与 世界保健機関(WHO)は新型インフルエンザに感染した場合、持病のある人だけでなく、新生児や乳児もタミフルやリレンザを服用するべきだ、などとする治療指針を公表した。妊婦やエイズウイルス(HIV)感染者らもリスクが高く、服用が勧められている。重症の場合はタミフルが第一選択。指針作成にかかわったけいゆう病院の菅谷憲夫・小児科部長によると、重症例で治療実績があることなどが考慮されている。持病などがない人はタミフル、リレンザによる治療は必要ないとされたことに、菅谷さんは「基本的には全員の治療が望ましい」と指摘する。(平成21年8月22日 朝日新聞) 新型インフル、子供の意識障害に注意 日本小児科学会は新型インフルエンザに感染した子供の意識が低下している場合、インフルエンザ脳症を起こしている可能性があるとして注意喚起した。脳症を起こすと死亡や障害が残る恐れがあり、小児科などの受診を勧めている。強い解熱剤は症状を悪化させる場合もあることから「必ず医師に相談して使ってほしい」と求めた。厚生労働省によると、同日までに新型インフルエンザに感染して脳症を起こした子供は4〜14歳の計6人。いずれもけいれんや意識障害を起こして入院したが、死亡例は出ていない。同学会はインフルエンザ脳症の早期症状として、(1)呼びかけに答えないなど意識レベルの低下がある(2)けいれんやけいれん後の意識障害が持続する(3)意味不明の言動があるなどのいずれかの症状があった場合、医療機関を受診することを勧めている。(平成21年8月22日 日本経済新聞) タミフル、日本向けに改良 スイス製薬大手ロシュ子会社の中外製薬は10月をメドに、日本向けに改良したインフルエンザ治療薬「タミフル」を出荷する。これまでタミフルは全量を輸入し、国内では日本向けの包装などの加工だけだったが、初めて国内で製造する。高温多湿の日本に合わせて吸湿しにくいように改良した粉末タイプで、患者は水に混ぜて服用する。品質の劣化をおさえることで現在2年間の有効期限を3年間に延長する。国内で製造するのは小児や高齢者でも飲みやすいように水に混ぜて飲む粉末状の「ドライシロップ」と呼ばれるタイプ。生産能力は最大で月間50万人分。タミフルの有効成分をスイスから輸入し、日本で添加物を混ぜて製品化する。現在はドライシロップをスイスから輸入して日本で瓶詰めしているが、国産に順次切り替える。(平成21年8月22日 日本経済新聞) 新型インフルエンザ、致死率0.5% 国内でも死者が出た新型インフルエンザの致死率は、季節性インフルエンザよりも高く、1957年にアジアで流行した当時の新型インフルエンザ「アジアかぜ」並みの0.5%程度と、オランダ・ユトレヒト大の西浦博研究員らが推計した。研究チームは、米国とカナダの新型インフルエンザ流行初期に確認された確定感染者数と死亡者数から、米国の致死率は1.2%、カナダは0.18%と算定した。しかし、米国は流行当初に死者が出たため実際の致死率より高めに、カナダは発病時期不明の患者が多いため低めに計算された可能性が高く、統計学的に処理し、実際の致死率は0.5%程度と推計した。一方、季節性インフルエンザの致死率は0.1%未満。約200万人が死亡したアジアかぜの致死率は約0.5%とされており、今回の新型インフルエンザの致死率はアジアかぜ並みと結論付けた。研究チームは日本の致死率について「0.5%を下回る見込み。持病のある人が適正に治療されていることや、抗インフルエンザ薬『タミフル』が多くの症例で投与されていることが影響し低めになるのではないか」と分析する。また、西浦研究員は「冬を待たずに日本で感染者数が増大する可能性がある。季節性よりも毒性が高く、妊婦や持病のある人が数多く重症化し、相当数の死者が出ることを覚悟して準備すべきだ」と呼びかける。(平成21年8月18日 毎日新聞) パーキンソン病に遺伝子治療 パーキンソン病患者の脳にウイルスを使って遺伝子を組み込む国内初の遺伝子治療を実施している自治医科大学で、治療を行った患者6人のうち5人の運動機能が回復した。ウイルスの安全性についても確認できたという。症例が少なく、まだ一般的な治療としては使えないが、患者の生活を大きく改善する可能性をもつ成果だ。パーキンソン病は、手足にふるえなどが生じる神経難病で、国内に約12万人の患者がいる。脳の「線条体」で神経伝達物質ドーパミンが不足することが原因と考えられており、現在はドーパミンの元になる「L―ドーパ」を投与する薬物治療が主流。だが、病気が進行するとL―ドーパからドーパミンを作る酵素が不足し、薬効が低下していくことが問題だった。そこで中野今治教授らは、2007年5月から08年9月にかけて、ドーパミンを作る酵素の遺伝子を組み込んだ特殊なウイルス約3000億個を、パーキンソン病患者6人それぞれの線条体に注入した。半年後に運動機能を調べたところ、5人に改善が見られた。体を動かせなかった患者が、日常生活に支障がないまでに回復したケースもあった。(平成21年8月14日 読売新聞) リウマチ薬でがんリスク上昇 米食品医薬品局(FDA)は4日、日本でも使われている腫瘍壊死因子(TNF)阻害薬と呼ばれる新しいタイプの関節リウマチ薬について、小児、青少年が使用した場合にがんの発症リスクが上昇するとして、注意書きで、強く警告するよう製薬会社に指示した。対象は、レミケード(一般名インフリキシマブ)、エンブレル(エタネルセプト)、ヒュミラ(アダリムマブ)など5種類。関節で骨を壊すTNFというタンパク質と結合して、その働きを抑える作用があり、関節リウマチのほかクローン病、潰瘍性大腸炎などに処方される。ロイター通信によると、改善効果が高いため、米国で最も人気があるリウマチ薬となっている。同局の調査では、TNF阻害剤を使用した小児、青少年のうち48人がリンパ腫を中心とするがんを発症。2年半使用した場合、がんのリスクが高まることが分かった。(平成21年8月5日 日本経済新聞) インフル薬にお茶の力、タミフルより効果 緑茶に含まれるカテキンを加工してインフルエンザ治療薬に応用する技術を、大阪大学と横浜市衛生研究所の共同チームが開発した。季節性インフルエンザや鳥インフルエンザで効果が確認された。感染を防ぐ作用もあるため、鼻やのどに噴霧する予防薬への応用も期待できるという。開発に利用したのは、緑茶に多く含まれているエピガロカテキンガレート(EGCG)というカテキンの一種。カテキンは茶の渋み成分で、EGCGがウイルスの働きを抑えるのは以前から知られていた。だが、そのまま飲むと、体内ですぐに分解され、効果がなくなってしまう。このため、研究チームは、体内での分解、代謝を抑える作用のある脂肪酸と合成することで、EGCGが分解されずに、ウイルスの感染や増殖を抑える技術を開発した。この加工したEGCGを季節性インフルエンザや鳥インフルエンザのウイルスに混ぜ合わせて、イヌの腎臓細胞にふりかけて感染力を調べた。すると、治療薬タミフルよりも約100倍、感染を抑える効果があった。鶏の有精卵を使った増殖実験でも、何もしない卵12個では中のヒナが70時間で4割、164時間で全数が死亡したが、加工したEGCGを投与した卵12個では全数が生き残った。作用を調べると、ウイルスが細胞に侵入するのを防いだり、仮に侵入してもウイルスの遺伝子が増殖しないようにしたりしていた。主任研究者の大阪大学の開発邦宏助教が08年に特許を出願。数年内の実現を目指すという。開発さんは「緑茶を飲んでも効果はないが、開発した成分は高い効果があった。作用からみれば、新型インフルエンザにも効果が期待できる。茶葉から大量に抽出でき、安価で副作用も少ない」と話す。(平成21年7月31日 朝日新聞) タミフル、安価な合成法 岡山大大学院教育学研究科の石川彰彦准教授らのグループが、抗インフルエンザウイルス薬タミフルを安価な原料で合成する方法を開発した。タミフルの製造は植物由来の原料が使われ、供給が不安定で原料代は高騰しがち。石川准教授らは、実験室レベルで2通りの原料から合成に成功。いずれも、原料が安定して入手でき、安価なことが特徴という。タミフルは、シキミ科の植物トウシキミから抽出されるシキミ酸を原料に合成。トウシキミは主に中国で栽培されているが、天候に生産量が左右されるうえ、タミフルの需要増加により、枯渇する可能性が指摘されている。石川准教授らは、食品添加物に使われる有機化合物「D−酒石酸」と、点滴や錠剤などに使われる糖類「D―マンニトール」から、それぞれタミフルを合成する方法を開発した。石川准教授によると、シキミ酸から合成する場合と比べ、工程数は7〜9工程とほぼ変わらず、D−マンニトールの場合は原料価格が3000分の1に抑えられるという。今後は実用化に向け、合成の効率を高めるなど改良を重ねるという。タミフルは2017年ごろには特許が切れ、後発医薬品としての製造販売が可能になる。国内外で10以上のグループが、シキミ酸を用いない新規合成法の開発に取り組んでいる。(平成21年7月30日 朝日新聞) 日焼けマシン、発がんリスク最高レベル 世界保健機関(WHO)の国際がん研究機関(IARC)は、日焼けサロンやスポーツジムで使われ、人工的に紫外線を出す「日焼けマシン」の使用は発がんリスクを確実に高めるとして、発がんリスク分類でもっとも危険性の高い「グループ1」に引き上げた。IARCは、日焼けマシンと皮膚がん(メラノーマ)との関係を調べた19論文を分析。30歳未満で日焼けマシンを使った経験のある人は、使ったことのない人より75%もリスクが高いことがわかった。日焼けマシンの使用による、眼球の色素細胞にできるがんのリスクも高かった。従来、紫外線のうちB紫外線(UVB)にだけ発がん性があると考えられていたが、A紫外線(UVA)もUVBと同じように発がん性があることもわかったという。地上に降り注ぐ紫外線の95%がUVAだ。日焼けマシンは5段階の発がんリスク分類で危険性が2番目に高いグループだった。危険性が一番高いグループにはアスベストやたばこ、X線、太陽光などがある。紫外線に詳しい名古屋市立大の森田明理教授は、「黄色人種は白人に比べて紫外線によるがんのリスクは数分の1だとされるが、油断はできない。屋外で浴びる紫外線の量が、欧米の多くの都市よりもかなり多いからだ。外出のときは、皮膚が赤くなるような日焼けをしないように、日焼け止めや日傘で予防すべきだ」と警告する。(平成21年7月30日 朝日新聞) メタボ症候群、Tリンパ球が原因 内臓に脂肪がたまると、そこに体内で免疫を担う「Tリンパ球」が集まって炎症を引き起こし、高血糖などのメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)につながることを、東京大学の永井良三教授らのグループがマウスを使った実験で突き止めた。Tリンパ球の働きを抑えるメタボ治療薬の開発に道を開くと期待される。 26日発行の米科学誌ネイチャー・メディシン(電子版)に発表した。永井教授らは、高脂肪食で太ったマウスの脂肪組織に「CD8陽性T細胞」とよばれるTリンパ球が集まり、炎症を引き起こすことを確認。このTリンパ球の働きを抑えたところ、炎症が改善し、インスリンの働きもよくなって血糖値が下がった。Tリンパ球を持たないマウスに高脂肪食を与えても、炎症は起きなかった。永井教授は「Tリンパ球の働きをうまくコントロールする薬を開発できれば、メタボリックシンドロームに伴う生活習慣病などの治療に役立つだろう」と話す。(平成21年7月30日) 糖尿病の一種、原因にピロリ菌 胃潰瘍などを引き起こすヘリコバクター・ピロリ菌が、糖尿病の一種「B型インスリン抵抗症」の原因になることを、東北大創生応用医学研究センターの片桐秀樹教授らが突き止めた。患者からピロリ菌を除菌したところ糖尿病が完治した。B型インスリン抵抗症は、患者の免疫機能がインスリンの働きを妨げる糖尿病。数千人から数万人に1人が発症する比較的珍しいタイプで、通常の糖尿病治療はほとんど効果がない。片桐教授らは、B型インスリン抵抗症の患者が血小板減少症にかかっていたため調べたところ、ピロリ菌感染が判明。昨年3月に血小板減少症に対する治療として、抗生物質による除菌を実施すると、糖尿病も治癒し、現在まで再発せず完治したという。片桐教授は「ピロリ菌が、患者の免疫に何らかの悪影響を与えることで、糖尿病の一因になったようだ。除菌は根治療法として期待できる」と話している。(平成21年7月30日 読売新聞) 新型インフル、60〜80代も「抗体ない」 60歳以上の高齢者の3〜4割は新型の豚インフルエンザウイルスに対する抗体を持っていて何らかの免疫があるという調査が日米で報告されていたが、60〜80歳代には抗体がなく、安心できないことがわかった。90歳代の人には抗体があった。サルなどの動物実験で、新型インフルエンザウイルスは季節性インフルより肺など体内で広く増殖することも確かめられた。東京大医科学研究所の河岡義裕教授のチームが、新潟大や永寿総合病院、滋賀医科大などと共同で研究した。国立感染症研究所や米疾病対策センターがこれまで、60歳以上の3〜4割は、新型インフルの抗体を持っていると発表していた。河岡さんたちは、99年と今年4月に採取した250人分の血清を調べた。いずれの年でも、18〜19年に世界的大流行したスペイン風邪以前に生まれた90歳代以上の人の血清では、新型インフルへの抗体を持っている血清が多かった。一方、20年以降に生まれたそれ以下の年代の血清では、抗体がある人はほとんどいなかった。河岡さんたちは、カニクイザル6匹に新型インフルを感染させ、他の6匹には季節性インフルを感染させた後、3日後の肺や気道などのウイルス量を調べた。どちらのウイルスも鼻腔(びくう)や気道では増えていたが、新型の方が増殖量が多かった。一方、肺では、新型はあらゆる部位で増殖していたのに対し、季節性は、右肺の一部でしか増えておらず、増殖量が1万倍違うサルもいた。河岡さんは「新型インフルは季節性と同じだという人がいるが、実際は肺などでより増殖し、それが重症化につながる恐れもある。秋以降の新型インフル流行に向け油断しないで備えるべきだ」という。(平成21年7月14日 朝日新聞) うつ病、血液検査で診断 血液検査でうつ病かどうかを診断する方法を、厚生労働省の研究班が開発した。うつ病患者と健常者で白血球の遺伝子の反応が微妙に異なることを利用した。数年後の実用化を目指す。問診と併せて、数値化できる簡便な診断法が使えれば、患者の見逃しが減ると期待される。研究班は白血球の遺伝子がストレスで変化することに着目し、それをうつ病の診断に使えないか調べた。約3万個の遺伝子の中から、神経伝達や免疫などに関連する24の遺伝子が、うつ病患者と健常者で異なる働き方をすることを突き止めた。医師の面接によってうつ病と診断された17〜76歳の患者46人と健常者122人を分析した結果、うつ病患者の83%(38人)、健常者の92%(112人)で、特定の遺伝子が突き止めた通りに反応し、正しく判定できた。治療薬による影響で遺伝子が反応する可能性を除くため、うつ病の患者はまだ治療していない人を対象にした。研究班は今年から2年間、対象を増やして診断し、実用化できる精度か確かめる。うつ病以外の精神科の病気と、はっきり見分けることができるかも調べる。実用化されれば、患者から採った血液2.5ミリリットルを処理した液を、遺伝子チップという分析器具で反応させて診断できるという。厚労省の調査で、うつ病など気分障害と診断された人は、05年で92万4千人。6年で倍以上に急増している。うつ病は、医師が患者と面接し、症状から診断している。しかし、うつ病と他の病気との境目があいまいな例も多く、専門医でも診断に迷うことが少なくないという。大森教授は「血液検査による診断法が実用化されても、医師の面接による診断は必要だ。血液検査が実用化、普及すれば、一般の医師が診察する際に、これまで見過ごされてきた患者を治療に結びつけることが期待できる」と話している。(平成21年7月11日 朝日新聞) 認知症、ALSなどの原因抑える物質を発見 筋肉が動かなくなる難病である筋萎縮性側索硬化症(ALS)や、若年性認知症の治療につながる物質を、東京都精神医学総合研究所の野中隆主席研究員らの研究グループが見つけた。これまでの研究で、ALSや若年性認知症を発症した患者の脳や脊髄には、TDP43と呼ばれるたんぱく質が異常を起こして蓄積していることがわかっており、これが細胞の死滅や病気発症の原因になると見られている。研究チームは、人の神経細胞に異常なTDP43を作り出す遺伝子を組み込み、患者の細胞を再現。この細胞を使って、様々な薬の効果を確かめたところ、ロシアでアレルギーなどの治療に使われていた医薬品と、国内でも市販されている薬剤とを併用することで、細胞内に蓄積した異常たんぱく質を80%以上減らせることを突き止めた。ALSは往年のメジャーリーガー、ルー・ゲーリッグ選手が発症したことで知られる難病で、治療法はまだ開発されていない。40〜65歳で発症する若年性認知症も治療法がない。野中主席研究員は「すでにある薬を使って、ALSなどの進行を大幅に抑えることができる可能性がある。早急に治療薬開発につなげたい」と話している。(平成21年7月12日 読売新聞) カロリー制限で寿命延びる 食物から摂取するカロリーを制限すると、そうでない場合より寿命が長く、かつ健康的に過ごせるとする研究結果を米ウィスコンシン大などのチームがまとめた。アカゲザルを使って20年間にわたり実験を続けた。チームは「栄養不良にならない程度のカロリー制限が、老化を遅くすることを霊長類で示せた。人間にも同様のことが起こりうる」としている。実験は、米ウィスコンシン国立霊長類研究センターで1989年にスタート。7〜14歳のおとなのアカゲザル計76匹を半分ずつ2つのグループに分け、片方には好きなだけ餌を与え続けた。もう一方は、最初の3ヵ月で餌のカロリーを約30%減らし、その後も、このカロリー制限を維持しながら飼育した。自由に餌を食べたグループは、38匹中14匹(37%)が糖尿病やがん、心疾患、脳萎縮など加齢に関連する病気で死んだ。一方、カロリーを制限したグループで加齢に関連する病気で死んだのは5匹 (13%)。制限なしのグループの3分の1にとどまり、チームは寿命が延びたと判断した。アカゲザルの平均寿命は27歳前後で、40歳近くまで生きることもあるという。(平成21年7月10日 中国新聞) iPS細胞、肝がん細胞から作成 がん化せず肝臓細胞に再生人工多能性幹細胞(iPS細胞)を、肝臓がんの細胞から作ることに森口尚史・米ハーバード大研究員らが世界で初めて成功した。できたiPS細胞から正常な肝臓の細胞も初めて作成した。 iPS細胞はさまざまな細胞になるが、その過程でがん化するのが課題になっている。研究チームは得られた細胞の分析から、がん化を防ぐ遺伝子の働きを解明したといい、再生医療の実現に向けた一歩になると注目される。8日からスペインで始まった国際幹細胞学会で発表する。チームは肝がん細胞を作る「肝がん幹細胞」を正常な肝臓細胞に戻す方法を模索。市販のヒト肝がん幹細胞に抗がん剤など2種類の化学物質を加えると、正常の肝臓細胞になった。またこの肝臓細胞に山中伸弥・京都大教授が発見した4遺伝子のうちの2つと別の2種類の化学物質を加えるとiPS細胞に変化。正常な肝臓細胞に戻すことにも成功した。そこで、正常な肝臓細胞に分化したiPS細胞を調べたところ、がん抑制遺伝子「p21」の働きが、別のがん抑制遺伝子「p53」よりわずかに活発になっていることを突き止めた。p21を働かさせず、p53だけにして分化させると、すべて肝がん細胞になった。このため、研究チームは両遺伝子の働きのバランスが、iPS細胞のがん化を左右していると結論付けた。(平成21年7月9日 毎日新聞) iPS細胞、「全細胞、iPS化可能」 体中のほぼすべての細胞が、さまざまな細胞に分化できる万能細胞「人工多能性幹細胞(iPS細胞)」になる能力を持っているとの考察を、開発した山中伸弥・京都大教授が英科学誌ネイチャーに発表した。iPS細胞は、体細胞に4種類の遺伝子を組み込むなどの方法で作る。現状ではiPS細胞が1個できるには元になる体細胞が1000個以上必要と作成効率が低く、ごく一部が万能化するとの指摘がある。山中教授は、世界中の研究を調べ、4遺伝子の働き方などが特定の状態になるとiPS細胞ができると分析した。(平成21年7月6日 毎日新聞) 新型インフル、日本人の高齢者にも免疫 国内の高齢者の一部が新型インフルエンザ(豚インフルエンザ)への免疫を持っている可能性があることが、国立感染症研究所の調査で分かった。新型インフルエンザの感染者に高齢者が少ない原因の一つと考えられ、感染研は対象を広げて詳しく調べる方針。調査したのは、小田切孝人・インフルエンザウイルス研究センター第一室長のチーム。チームは福岡県内の医療機関から提供された60〜100歳代の高齢者30人(平均年齢83.4歳)の血液を分析。4割にあたる12人から新型インフルエンザのウイルスに反応する「抗体」が確認された。過去に、新型インフルエンザに似たウイルスに感染して、免疫を獲得した可能性があるという。新型インフルエンザの感染者は若年層に多く、米疾病対策センター(CDC)も高齢者に免疫がある可能性を示した研究結果を公表している。高齢者に免疫があると確認された場合、ワクチンの接種順位の決定にも影響するため、感染研は1000人規模の調査を行い、どの年代が抗体を保有しているか調べる。(平成21年7月6日 読売新聞) 「トロイの木馬」微小細胞でがん退治 オーストラリアの研究者らがこのほど、細菌から作った薬剤入りの微小な細胞を「トロイの木馬」として、がん細胞に直接送り込んで殺す手法を開発したと発表した。ネズミなどの動物実験では明確な効果を上げており、がん治療に新たな道を開く可能性がある。開発したのは豪バイオ技術ベンチャー、エンジェネイック社の研究者ら。薬剤入りの微小な細胞は、がん細胞がそれを取り込んでしまうよう表面が偽装されている。治療は2段階で、最初に「トロイの木馬」でがん細胞の薬に対する抵抗力を失わせ、第2波の抗がん剤で殺す。同社の研究者らは「ヒトのさまざまながん細胞を移植したネズミでの実験では、100%の生存率が得られた」と効果を強調、近く臨床試験を開始するという。今後、ヒトへの有効性や安全性が確認されれば、化学療法でがん細胞が薬剤への耐性を持つ問題を回避するとともに、副作用も軽減できると期待されている。(平成21年7月4日 朝日新聞) 体内「泳ぐ」内視鏡開発 遠隔操作で、胃の中を自由に動かせる自走式の「泳ぐ」カプセル内視鏡の開発に、龍谷大と大阪医科大が3日までに成功した。長さ48ミリのカプセルに付いた磁石とヒレで、撮影したい場所に移動させることができる。 小型電池を内蔵したカプセル内視鏡は、チューブ式の内視鏡の検査で患者が感じる痛みを軽減するため、これまでも活用されているが、自由に動かせず、長時間の検査もできなかった。龍谷大理工学部の大塚尚武教授の研究グループは、体外から遠隔操作できる駆動装置を開発。電池ではなく装置が発生させる磁場でカプセルの磁石を振動させ、魚のようにヒレを動かし、体内を自走できるようにした。ジョイスティックで上下左右の操作もできる。 グループは犬の胃の中での撮影に成功。1年以内に臨床実験を行うことを目指している。大塚教授は「電池が切れて到達できなかった大腸の検査や、検査中に再度確認したい位置に戻って見ることもできるようになるのでは」と期待する。(平成21年7月3日 中国新聞) ひとり酒、脳卒中にご用心 一人で酒を飲むより、仲間と飲む人の方が脳卒中になる危険度が低いことが、厚生労働省研究班(班長=津金昌一郎・国立がんセンター予防研究部長)の調査で分かった。研究班は、40〜69歳の男性約1万9000人を、「週1回以上話す友人の人数」や「秘密を打ち明けることのできる人の有無」などの質問を基に、社会的な支えが多い群と少ない群に分け、1993年から約10年間追跡した。調査中に836人が脳卒中や心臓病を発症。エタノール換算で週300グラム(ビール大瓶で1日2本程度)未満の飲酒の場合、社会的支えの多い群は、脳卒中の発症危険度が飲まない人の0.7〜0.8倍と低く、社会的支えの少ない群は、1.2〜1.8倍になった。週の飲酒量が300グラム以上になると、両群とも、飲まない人より脳卒中の発症危険度は高くなった。一方、心臓病の発症危険度は、社会的支えに関係なく、飲酒によって下がった。研究班の磯博康・大阪大教授は「仲間と騒いで酒を飲むと一人で飲むよりストレスを発散できていると考えられ、この結果につながったのでは」と話している。(平成21年7月2日 読売新聞) 「髪の元」細胞で神経修復 人間の髪の元になる細胞を使って、切断されたマウスの足の神経を修復することに北里大など日米の研究チームが成功した。脊髄損傷や事故で切断された手足の再生治療に応用が期待され、米専門誌に発表した。同大の天羽康之講師(皮膚科学)らは、体毛の周囲にあり、毛のほか神経や筋肉、皮膚の細胞に変化する能力を持つ「毛包幹細胞」に着目。この細胞を髪のそばから取って増やした後、マウスの末梢神経の切断部分に移植した。その結果、8週間後、切れた神経はつながり、足の付け根から電気刺激を与えると足が動いた。自然治癒にまかせたマウスに電気を流しても足は動かなかった。毛包幹細胞は、胚性幹細胞(ES細胞)や新型万能細胞(iPS細胞)に比べ変化できる器官は限られ増殖能力も低いが、人間に移植した際のがん化の危険性は少ない。(平成21年7月2日 読売新聞) 介護につながる症状、50歳以上で8割に 足腰の骨や筋肉が弱って、将来介護が必要になる運動器の障害を抱えている人は、50歳代以上で 8割を超えることが東京大の調査で分かった。自覚症状がない人も多く、放っておくと悪化する恐れがあるため研究チームは片足立ちやスクワットなどによる予防を呼び掛けている。介護が必要になる運動器の障害は、関節の軟骨がすり減って痛む「変形性膝関節症」、腰の骨同士がぶつかる「変形性腰椎症」、「骨粗鬆症」が代表的。吉村典子准教授らは、東京都板橋区と和歌山県の日高川町と太地町の住民3040人を対象にレントゲン撮影、問診などを行い、この3疾患の有症率を調べた。その結果、50歳以上でいずれかの疾患と断定された人は87%に達した。年齢別では、50歳代で 67%、70歳代は96%と加齢に伴い急増。運動の機能に影響する二つ以上の疾患を持っている人も50歳以上は51%だった。 60歳以上の発症者の内、痛みなど自覚症状のない人は約7割いた。(平成21年7月2日 読売新聞) マウスのアルツハイマー病、カフェインで改善 コーヒーなどに含まれるカフェインがアルツハイマー病の認知症状を改善するとともに、患者の脳に沈着する異常なたんぱく質が作られにくくすることを埼玉医大の森隆准教授ら日米のチームがマウスの実験で確認した。米医学誌「ジャーナル・オブ・アルツハイマーズ・ディジーズ」(電子版)で発表した。研究チームは、アルツハイマー病を発症した生後約18ヵ月の高齢モデルマウスに、人間で換算すると1日当たりコーヒー5杯に相当するカフェインを水に混ぜて1ヵ月飲ませ、認知や運動機能テストなど8項目について調べた。目的地まで迷子にならないかを調べる実験では、カフェインを飲ませたマウスはミスが減って毎回場所が変わる目的地までの到達時間も早くなり、健康なマウスと同程度の成績だった。水だけを飲んだマウスでは症状は改善しなかった。カフェインを飲ませたマウスは、記憶をつかさどる脳の海馬や大脳皮質で異常なたんぱくの沈着が減少。カフェインの投与で異常なたんぱく質を作り出す酵素の働きが抑えられることも分かった。森准教授は「人間の疫学調査などで予想されていた症状改善の仕組みが解明できた。マウスではあるが、症状の進行を抑える方法を考えるうえで有効なデータだと思う」と話している。(平成21年6月22日 朝日新聞) 免疫ブレーキ、仕組み発見 一部の細菌などに対し、抗体を作りにくくしている「免疫のブレーキ」と言える人体の仕組みを、筑波大大学院人間総合科学研究科の本多伸一郎講師と渋谷彰教授らが見つけた。「ブレーキ」を一時的に外す薬を作れば、ワクチン効果の増強などに応用できるという。15日付の米科学アカデミー紀要電子版に発表した。細菌などが人体に入ると、体内のリンパ球が「IgG抗体」を作って攻撃する。ただ、表面を「多糖類」という物質で覆われた肺炎球菌などにはIgG抗体ができにくく、ワクチンも効きにくい。だが、理由は謎だった。本多講師らは、働きがよく分からなかった別の種類の抗体「IgM抗体」に注目。リンパ球から、IgM抗体と結びつく受容体をなくしたマウスを、遺伝子操作で作った。マウスに肺炎球菌などと構造が似た化学物質を注射すると、普通のマウスの約10倍のIgG抗体ができ、化学物質を攻撃した。12週間後に再び、同じ物質を注射すると、IgG抗体の中でも攻撃力が強いものが、1度目の実験より約5割増えた。こうした実験から、IgMが多糖類に覆われた菌などへのIgG抗体の生産を抑えていると結論づけた。渋谷教授は「IgMは、免疫が過剰に働きすぎて体を傷つけるのを防いでいるのではないか。ワクチン注射の際だけIgMの働きを止める薬を作れば効果の増強につながるだろう」と話している。(平成21年6月16日 毎日新聞) 感染力増すウイルス変異か 世界に広がっている新型インフルエンザウイルス(H1N1型)の一部に、人の細胞にくっつきやすくなる原因とみられる変異が見つかったと、河岡義裕東京大医科学研究所教授らのチームが14日付の英科学誌ネイチャー(電子版)で発表した。この変異が広がると、現在より人に感染しやすくなる可能性があるという。変異は、ウイルスの表面にある「ヘマグルチニン(HA)」と呼ばれるタンパク質で見つかった。同じ変異は、アジアなどで人に感染している鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)でも報告されており、従来は結合しにくかった人の細胞にくっつきやすくなる変化に関係しているのではないかと指摘されている。河岡教授は「H1N1型は、豚のウイルスが人に感染するようになり、人への適応が進む過程にあるとみられる。この部分の変異を、注意深く監視していく必要がある」と話している。(平成21年6月15日 中国新聞) 日本脳炎、新ワクチン接種へ 日本脳炎の新たなワクチンが今月2日に発売された。日本脳炎の予防接種は、旧ワクチンの副作用被害のため2005年以来、実質的に行われなくなっていたが、4年ぶりに再開される。 日本脳炎は、ウイルスに感染した豚を刺した蚊を介し、人に感染する。発症すると、高熱、頭痛、意識障害、けいれんなどが表れ、2〜4割が死亡する。九州・沖縄、中国・四国地方を中心に、最近10年間で58人の患者が報告されている。旧ワクチンは、接種を受けた女子中学生が、脳の障害で寝たきりになるなどの重い副作用が出たことが問題となった。新ワクチンは、異なる手法で作られ、重い副作用は少ないことが期待されている。3〜7歳の間に3回と、9〜12歳の計4回の接種が必要とされるが、厚生労働省は今回、3〜7歳の3回分のみを、公費補助の対象となる「定期接種」と位置づけた。4回目についてはまだ臨床試験が行われておらず、見送られた。厚労省は、接種を受けた方がいい人として「九州・沖縄、中国・四国などに住み、接種を受けていない3〜7歳の子ども」を挙げている。ただし、今年はワクチンの生産量が少なく、市町村に対し積極的に接種を勧める通知は行わない。(平成21年6月11日 読売新聞) 太り気味、やせ形より7年長生き 40歳時点の体格によってその後の余命に大きな差があり、太り気味の人が最も長命であることが、厚生労働省の研究班(研究代表者=辻一郎東北大教授)の大規模調査で分かった。最も短命なのはやせた人で、太り気味の人より6〜7歳早く死ぬという、衝撃的な結果になった。「メタボ」対策が世の中を席巻する中、行きすぎたダイエットにも警鐘を鳴らすものといえそうだ。研究では、宮城県内の40歳以上の住民約5万人を対象に12年間、健康状態などを調査した。過去の体格も調べ、体の太さの指標となるBMI(ボディー・マス・インデックス)ごとに40歳時点の平均余命を分析した結果、普通体重(BMIが18.5以上25未満)が男性39.94年、女性47.97年なのに対し、太り気味(同25以上30未満)は男性が41.64年、女性が48.05年と長命だった。しかし、さらに太って「肥満」(同30以上)に分類された人は男性が39.41年、女性が46.02年だった。一方、やせた人(同18.5未満)は男性34.54年、女性41.79年にとどまった。病気でやせている例などを統計から排除しても傾向は変わらなかった。やせた人に喫煙者が多いほか、やせていると感染症にかかりやすいという説もあり、様々な原因が考えられるという。体格と寿命の因果関係は、はっきり分かっていない。このため、太り気味の人が長命という今回の結果について、研究を担当した東北大の栗山進一准教授は「無理に太れば寿命が延びるというものではない」とくぎを刺す。同じ研究で、医療費の負担は太っているほど重くなることも分かった。肥満の人が40歳以降にかかる医療費の総額は男性が平均1521万円、女性が同1860万円。 どちらもやせた人の1.3倍かかっていたという。太っていると、生活習慣病などで治療が長期にわたる例が多く、高額な医療費がかかる脳卒中などを発症する頻度も高い可能性があるという。(平成21年6月10日 読売新聞) アルツハイマー病関連のたんぱく質 アルツハイマー病に関係するとみられるたんぱく質を、大阪大の研究グループが新たに見つけた。このたんぱく質の量の変化を調べることで、早期診断に利用できる可能性があるという。欧州分子生物学機構の学術誌(電子版)で10日発表する。脳神経細胞が死んでいくアルツハイマー病は、体内で「アミロイドβ(ベータ)」というたんぱく質が増えて、脳に老人斑と呼ばれる特徴的な染みをつくる。脳を守る脳脊髄(せきずい)液などからこのたんぱく質の量の変化を調べ、診断につなげる研究が進んでいる。だが、多くが脳に蓄積されてしまうアミロイドβは、特に初期段階では量の変化がわかりにくく、病気の早期発見が難しいことが課題だった。阪大の大河内正康講師(精神医学)らは、脳に蓄積しない性質を持つ「APL1β」というたんぱく質が、患者の脳脊髄液にあるのを発見した。このたんぱく質の増加と病気の進行度が一致していることもわかった。さらに追跡調査で、このたんぱく質は発症の少なくとも2〜3年前から増え始めることも突き止めた。これを目印にすれば、アルツハイマー病の早期診断に使える可能性があるという。大河内さんは「脳脊髄液は腰に針を刺して採取する必要があるが、診断自体はすでに実用化できるレベルにある。早期診断が実現すれば、将来アルツハイマー病になるのを防いだり、遅らせたりする治療法の開発にもつながるはずだ」と話している。(平成21年6月10日 朝日新聞) 新型インフルエンザ、ワクチン2500万人分 厚生労働省は9日、新型インフルエンザのワクチンについて、年内に最大約2500万人分を確保できるとの試算を明らかにした。製造ラインを新型に振り向けるため、季節性インフルエンザのワクチンは、08年の約8割にあたる約4000万人分確保した段階で製造を打ち切ることになるという。新型インフルエンザ与党プロジェクトチーム座長の川崎二郎元厚労相は同省の報告を受け、国内で感染者が多い中高生ら10代と、医療関係者、妊婦や基礎疾患のある患者にワクチンを優先接種すべきだとの考えを示した。同省によると、季節性のワクチンは例年約5000万人分製造し、大半がシーズン中に消費される。次のシーズンは新型流行の恐れがあるため、既に始まっている季節性のワクチン製造を、どの時点で新型に切り替えるかが焦点になっている。試算によると、新型のワクチンを最優先にし、製造が可能になる7月中旬に切り替えた場合、12月末までに約2500万人分製造できる。季節性は約4000万人分となる。(平成21年6月10日 毎日新聞) おなかの脂肪から神経細胞 おなかの脂肪から取り出した幹細胞を脳の中に入れて神経細胞を作り出すことに、京都大学再生医科学研究所の中村達雄准教授らが動物実験で成功した。脂肪の利用は負担が少ないため、将来、脳梗塞や脳腫瘍の患者への再生医療の足がかりにしたいという。スイスの専門誌に発表する。脂肪の中には、体のさまざまな組織の細胞になりうる幹細胞が含まれていることが知られている。幹細胞そのままでは移植に使えないが、幹細胞を取り出してスポンジなどの「足場」にしみこませたものを、傷ついた組織に移植、再生をめざす研究が世界中で進んでいる。研究チームの中田顕研修員は、ラットのおなかの脂肪から幹細胞を取り出し、コラーゲンでできた数ミリ角のスポンジにしみこませた。幹細胞を大量にしみこませるために、3日間、幹細胞を培養しながら、スポンジを回転させ続ける工夫をした。このスポンジをラットの脳の中にあけた穴に移植した。1ヵ月後、幹細胞から神経細胞ができたことが確認できた。今後、この神経細胞が回路を作るか、ほかの種類の細胞が増えていないか、長期間、調べる。チームは、脳腫瘍の手術後や脳梗塞などで欠けた部分を補う治療法につなげる一歩にしたいという。(平成21年6月10日 朝日新聞) はしか 免疫ない乳児4割 はしかへの抵抗力のない乳児(6ヵ月未満)の割合がこの10年で4倍の約4割に増えたことが、国立感染症研究所の調査でわかった。免疫のない母親が増えたためとみられる。はしかによる死亡は0〜1歳児が多いが、0歳児は生ワクチンの接種ができない。専門家は、1歳以上ヘの予防接種を徹底して流行を防ぐよう呼びかけている。乳児は生まれてから半年前後、母親から受け継いだ免疫で、はしかなどの病気から守られている。免疫力の元になる母親の抗体は、胎盤を通して移る。1歳までに母親の抗体はほぼなくなり、自分の免疫で身を守るようになる。だが、母親が免疫を持たない病気には乳児も最初から免疫がない。感染研が0歳児のはしかに対する免疫保有状況を調べたところ、6ヵ月未満児で抗体がなかったのは08年度が約4割に上り、97年度の約1割の4倍に増えていた。08年度の6、7ヵ月児で抗体のない割合は74%、8、9ヵ月児では85%と月齢とともにさらに増えていた。はしかの定期予防接種は78年に始まり、その後、流行は減った。06年からは1歳と小学校入学前の1年間の計2回打つようになったが、若い母親の中には、はしかにかかったことがなく、予防接種も1回しか受けていないため、免疫がなかったり、弱かったりする人が増えているという。妊娠判明後は、胎児への影響から予防接種できない。将来、妊娠する可能性があれば、抗体がない人は、接種したほうがいいようだ。99〜02年、国内のはしか患者の約半数は2歳以下だった。生まれつき免疫のない乳児が増え、はしかが突然流行すれば、0歳児の死亡が増えるおそれがある。未成年のはしかの報告数は06年は516人まで減ったが、07年には3132人に増えた。はしかの予防接種は、弱毒化したウイルスをそのまま使う生ワクチンなので、0歳児には危険で接種できない。感染研の岡部信彦・感染症情報センター長は「1歳以上の児童や大人に2回接種を徹底することで、はしかの流行をなくすことが重要だ」と話している。(平成21年6月4日 朝日新聞) インターフェロン、肝炎治療用に造血制御の機能 白血病治療応用に期待 肝炎などの治療に使われている「1型インターフェロン(IFN)」に、赤血球や白血球など血液細胞の源である造血幹細胞の増減を制御する機能があることを、樗木俊聡・東京医科歯科大教授と佐藤卓・秋田大助教が発見した。慢性骨髄性白血病治療への応用などが期待できるという。1日付の米医学誌ネイチャー・メディシン電子版に発表した。造血幹細胞は通常、分裂しない休眠状態だが、何らかの刺激で活性化すると1個の造血幹細胞が新たな造血幹細胞1個と血液前駆細胞1個に分裂する。この前駆細胞が赤血球などの血液細胞になる。 研究チームは、1型IFNが過剰に働くマウスで、造血幹細胞の働きに異常が生じることに着目。1型IFNの分泌を誘発する薬剤をマウスに投与して調べた。その結果、薬剤を一度だけ投与すると、休眠中の造血幹細胞の働きが活発化し、前駆細胞と新たな造血幹細胞を大量に作った。だが、1日おきに3度の投与では、造血幹細胞は前駆細胞2個に分裂し、造血幹細胞の数が減った。慢性骨髄性白血病は、異常な造血幹細胞である「白血病幹細胞」が原因だ。抗がん剤治療は、増殖する白血病幹細胞を標的にするが、休眠状態でいると効果は低い。樗木教授は「治療前に1型IFNを投与し白血病幹細胞の増殖を促せば、抗がん剤の効果を高められるのではないか」と話す。(平成21年6月1日 毎日新聞) iPS細胞、がん化しにくい作製手法を開発 米ハーバード大学などの研究チームは、体のあらゆる細胞や組織になるヒトの新型万能細胞(iPS細胞)を、従来より安全に作ることに成功した。遺伝子を直接細胞に入れるとがんを引き起こす危険性が高くなるため、たんぱく質だけを使う方法で試みた。遺伝子を導入しない方法はすでに米国とドイツの研究チームがマウスの実験で成功しているが、ヒトの細胞では初めて。30日までに米科学誌「セル・ステムセル」(電子版)に発表した。研究チームは、京都大学の山中伸弥教授が最初に使った4遺伝子を、アミノ酸の一種であるアルギニンなどをくっつけて改造し、ヒトの培養細胞に入れた。こうして作ったたんぱく質は細胞膜を通り抜けやすく、ヒトの新生児の皮膚細胞からiPS細胞ができた。(平成21年5月30日 日本経済新聞) WHO、南半球の拡大警戒 新型インフルエンザ(H1N1型)の発生を、世界保健機関(WHO)が4月28日に正式認定してから1ヵ月。ウイルスは弱毒性で感染者の大半が回復している上、WHOが世界的大流行(パンデミック)宣言を先送りしたこともあって、緊迫感に包まれた世界は、ひとまず落ち着きを見せている。だが拡大は依然続いており、感染者は世界で約1万4000人に達し、死者も100人を突破。WHOは、これから冬を迎える南半球で被害が深刻化する事態を警戒している。WHOによると、感染者の多くは軽症で、入院や抗ウイルス剤による治療も不要だった。世界が備えてきた強毒性鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)の変異によるパンデミックとは大きく様相が異なる。英国や日本など発生国からの抵抗もあり、WHOは感染の地理的拡大だけでパンデミックを宣言する当初の方針を変更。ウイルスが強毒化したり、感染が南半球へ本格的に広がったりするまで宣言を先送りした。(平成¥21年5月27日 中国新聞) 抜け毛、原因にかかわる遺伝子発見 抜け毛の原因にかかわる遺伝子を国立遺伝学研究所と慶応大がマウスで見つけた。人も共通の仕組みを持つ可能性が高いという。この遺伝子がつくるたんぱく質「Sox21」は、神経細胞の発生や増殖に関係していることが知られている。遺伝研の相賀裕美子教授(発生遺伝学)と慶応大医学部の岡野栄之教授らは、生まれつきSox21遺伝子を持たないマウスを作った。このマウスは生後まもなく体毛が生えそろうが、生後15日ごろ頭部から脱毛が始まり、1週間で全身の毛が抜けた。その後は、25日周期で脱毛と発毛を繰り返した。 マウスの毛は25日周期で生え変わる。脱毛マウスも周期や発毛機能は正常だが、抜けるスピードが異常に速かった。体毛を詳しく調べたところ、毛の表面を覆い、うろこのような形で毛根とつながっているキューティクルがほとんどなかった。研究チームは、Sox21がキューティクルの材料のケラチンの生成にかかわっており、脱毛マウスはそれを持たないため抜け毛が早まると結論づけた。研究チームは人の毛髪のキューティクルにもSox21遺伝子が発現していることを確認。相賀教授は「薄毛の人はSox21遺伝子やSox21の働きに問題があると推測できる。詳しい仕組みが分かれば、治療薬開発の糸口になるかもしれない」と話す。(平成21年5月26日 毎日新聞) 日本の平均寿命83歳、首位守る 世界保健機関(WHO)が21日発表した2009年版の世界保健統計によると、07年時点の日本の平均寿命は男女平均が83歳で、193の全加盟国の中で単独首位を維持した。女性は86歳で前年と同じく首位。 一方、男性は79歳で、アイスランドに抜かれて3位に後退した。男性首位は富裕層の多いサンマリノの81歳だった。男女平均の2位はサンマリノ、スイス、イタリア、アイスランドなどの82歳で、先進国の寿命の長さが際立つ。逆に平均寿命が最も短いのは、長い内戦に苦しんだアフリカのシエラレオネで41歳。WHOが定義する貧困国の平均寿命は57歳で、富裕国の80歳に比べて23歳も短い。(平成21年5月22日 日本経済新聞) 57年以前生まれに免疫か 新型インフルで血液分析 米疾病対策センター(CDC)のジャーニガン・インフルエンザ部副部長は20日の記者会見で、1957年より前に生まれた人の一部に、新型インフルエンザに対する免疫がある可能性を指摘した。さまざまな年齢層から採取した血液の分析で、57年より前の世代の血清から、新型インフルエンザのH1N1型ウイルスに対する免疫反応を示唆する結果が得られたという。詳しくは近く公表されるCDCの週報に掲載されるという。ジャーニガン副部長によると、米国の入院患者のうち50歳以上は13%で、高齢者が重症化する傾向のある季節性インフルエンザとは特徴が異なるという。1918年から19年にかけ世界的に大流行したスペイン風邪はH1N1型で、終息後もウイルスは変異を続けた。その後、H2N2型のアジア風邪が57年に大流行したが、それまでの間に、現在の新型ウイルスと関連するH1N1型に感染した世代が存在する可能性があるとしている。季節性インフルエンザにもH1N1型ウイルス(Aソ連型)があるが、現在流行し、豚に起源がある新型のH1N1型との関連は薄いとされている。(平成21年5月22日 中国新聞) 体力、50歳は死亡率の指標 心筋梗塞などリスク低下 50歳のとき、速足(時速6.4キロ程度)での歩行に相当する身体活動が無理なくできる体力があれば、心筋梗塞などで死亡する危険性が低くなることを、筑波大の研究チームが突き止めた。20日発行の米医師会誌(JAMA)に発表した。同大の児玉暁研究員(内分泌代謝学)は「体力の有無が、将来の心筋梗塞などの発症や死亡の危険性を予測する指標として使えるかもしれない」と話している。研究チームは、日米欧で発表された心筋梗塞など冠動脈疾患の発症のほか、運動や死亡のデータが含まれる論文計1万679本、計10万2980人分のデータを解析。論文での追跡期間は1〜26年で、対象者の体力と、期間中の冠動脈疾患による死亡、それ以外の死亡を調べた。50歳の男性を体力が普通の群(時速6.4〜7.8キロ程度で歩行できる)、低い群(普通群以下)、高い群(時速7.9キロ程度以上で歩行できる)の3つに分けて比較したところ、低い群の冠動脈疾患による死亡率は普通群の1.4倍、高い群の1.47倍になった。すべての死亡率でも、低い群は普通群の1.7倍、高い群の 1.56倍と高くなった。普通群と高い群はほとんど差がなく、少なくとも普通群程度の体力があることが、冠動脈疾患や死亡の危険性を減らす可能性があるとみられる。40歳、60歳で比較しても、体力のある方が死亡や心筋梗塞などの危険性が低かった。女性の場合は、男性の約8割の体力で同様の結果が出た。曽根博仁・筑波大教授は「定期的な運動をすることによって寿命が延びるというデータはないものの、体力の有無が死亡率に影響を与えることが明らかになった」と話している。(平成21年5月21日 毎日新聞) お酢飲んでメタボ解消 酢を飲み続けると内臓脂肪が減ることを、ミツカン中央研究所(愛知県半田市)が成人対象の実験で確認した。長崎市で開かれる日本栄養・食糧学会で21日、発表する。実験は、肥満度を示す体格指数(BMI)が25〜30の「軽度肥満」に該当する成人男女175人(うち女性64人、平均44.1歳)を対象に実施。過度の運動を避けてもらうほかは通常の生活を送り、リンゴ酢を配合した飲料を1日2回、12週間飲み続けてもらった。腹部のコンピューター断層撮影(CT)画像による内臓脂肪面積の変化や体重などの変化を比較。データが得られた155人を分析したところ、1日30ミリリットル(酢酸量1500ミリグラム)摂取した群は内臓脂肪面積が平均約6.72平方センチ減り、腹囲は同1.85センチ減少。15ミリリットル(同750ミリグラム)摂取した群も減少した。酢を含まない飲み物を飲んだ群には変化が見られなかった。また、酢を摂取した群は、血中1デシリットルあたりの中性脂肪が28.2〜42ミリグラム減った。研究チームはこれまでに、酢の主成分である酢酸が脂肪の合成を抑え、燃焼を促進することを動物実験で確かめている。(平成21年5月15日 毎日新聞) 新型インフルの致死率0.4% 世界に広がっている新型インフルエンザの致死率は1957年のアジア風邪並みの約0.4%で、感染力は季節性インフルエンザよりも強いとする初期データの分析結果を、国際チームが11日、米科学誌サイエンス(電子版)に発表した。チームは、世界保健機関(WHO)の世界的大流行(パンデミック)評価に携わる英ロンドン大インペリアルカレッジなどで「20世紀に起きたパンデミックに匹敵する大流行になる可能性がある」と指摘している。チームは、旅行者を通じた世界各国への感染拡大の状況などから、4月末にメキシコで感染者は2万3000人いたと推計。当時の死者数から、感染後の致死率は約0.4%で、1918年出現のスペイン風邪(約2%)よりは低いが、アジア風邪(約0.5%)に匹敵するとした。1人から何人に感染するかを示す感染力は、1.4−1.6人と推計。季節性のインフルエンザよりは強く、1.4−2人だった過去のパンデミックの低い方に近いという。メキシコでは、1月12日ごろに最初の1人に感染し、4月末までに人から人への感染が14−73回繰り返されたと推定されるという。今回の解析では、最も早く感染が確認され、住民の半数以上が発症したベラクルス州ラグロリアが発生地になったとの説を支持する結果が得られたとしている。(平成21年5月12日 中国新聞) 抗うつ薬で攻撃性増 抗うつ薬を服用した患者に、他人に突然、暴力をふるうなど攻撃性が増す症状が表れたとの報告が約40件寄せられたため、厚生労働省は8日、「因果関係が否定できない症例がある」として、使用上の注意を改訂することを決めた。対象となるのは5製品で、うち4製品はSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害剤)。同省などは、SSRIなどの抗うつ薬を服用し、傷害など他人を傷つける行為が実際にあった35件と、傷害につながる可能性があった4件の副作用について調査した。このうち、SSRIのパキシル、デプロメール、ルボックスを服用した4件について、「他人を傷つける行為との因果関係を否定できない」と判断。SSRIのジェイゾロフトと、別の薬のトレドミンも含めた改訂を決めた。調査の結果、うつ症状やアルコール依存症などがある患者が薬を処方されたことにより、症状が進んで攻撃性が増し、傷害に結びついた疑いがあるケースが多いことも分かった。(平成21年5月9日 読売新聞) 新型インフルエンザウイルス、人・鳥・豚などの混合ウイルス 世界に拡大している新型インフルエンザウイルスは、98年に豚に流行した人型、鳥型、豚型の混合ウイルスに由来することが米コロンビア大などの分析で分かった。これに、欧州などで流行した別の豚型が交雑していた。新型ウイルスの起源と特徴が判明し、治療や今後の新型対策に役立つと期待される。インフルエンザウイルスの遺伝子には8本のRNA(リボ核酸)がある。研究チームが新型の遺伝子を解析したところ、6本が98年に北米の豚が感染した2種類のウイルス由来で、うち1種類は人型と鳥型、豚型の混合だった。一方、残りの2本は92年に欧州やアジアで流行したユーラシア型豚ウイルスに由来していた。ユーラシア型がどのような経緯で北米型と交雑したかは不明としている。インフルエンザウイルスは複数の動物に感染するが、一つの種に定着すると他の種に感染することはまれだ。しかし豚は、人と鳥型の両方のウイルスが感染する細胞を持ち、今回の新型のように重複感染して遺伝子が混合することが知られている。専門家は1918年のスペイン風邪など過去の世界的大流行(パンデミック)も、豚で豚型に人型が混合したことが原因と指摘している。(平成21年5月4日 毎日新聞) 心機能アップに筋トレ効果 腕や太ももなどの骨格筋を鍛えることで、心機能が高まることが日本女子体育大などの調査で分かった。大きな筋肉を動かすことで血液の流れがよくなり、心臓を刺激するためとみている。同大プロジェクトチームは「特に高齢者は有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせることで心機能の衰えを防止できる」と提言している。研究チームは運動による健康、体力作りのためのプログラムを作るため、骨格筋と血流の関係を分析した。小学1年生から高校3年生まで、ジュニア強化選手などさまざまな運動経験を持つ計57人(男子32人、女子25人)と、高齢者15人(平均76歳)を調査。心臓と太もも、腕の筋肉の厚さを超音波で調べ、心筋の厚さから心臓の重さを推計した。その結果、腕や太ももの筋肉が増えれば心臓も重くなる比例関係にあることが分かった。高齢者では太ももの筋肉が200立方センチの人の心臓は127グラムだが、800立方センチの人は182グラムだった。加賀谷淳子・同大名誉教授(健康・スポーツ科学)は「有酸素運動で心臓の容量が大きくなることが知られていたが、筋力トレーニングで心筋が厚くなり心機能が高まることが初めて分かった」と話している。(平成21年4月11日 毎日新聞) 国内初のがんワクチン外来 国内初の「がんワクチン外来」を開設した久留米大医学部が資料請求の受け付けを始めたところ、申し込みが殺到、受け入れ可能な患者数を超えることが予想されたため、約1時間半後に中止した。担当者は「反響があまりにも大きく、受け入れ態勢をオーバーした。治療を希望する患者に迷惑を掛けて申し訳ない」と話している。半年後に受け付けを再開する予定。めどが付き次第、大学のホームページや専用電話で案内する。大学によると、HPと自動応答による電話で受け付けをしたが、午前11時半までに1600人を超え、大学の代表電話もつながらない状態になった。第1期で受け入れられるのは約60人で、受け付けを中止した。同外来は患者の免疫特性に合わせてがんワクチンを投与する。自由診療扱いで治療費は高額だが、抗がん剤や放射線治療などに比べて体の負担が軽いという。臨床試験に当たり、治療は主治医の承諾や大学側の審査を経る必要がある。(平成21年4月1日 中国新聞) 無花粉スギ 花粉を出さない「無花粉スギ」を効率よく増やす方法を、日本製紙が開発した。苗木の生産効率が従来の約100倍に向上するという。親木と同じ形質を持つ木を育てるには、枝を土に挿して根付かせ苗木に育てる「挿し木」が使われる。スギの場合、挿し木には長さ20〜30センチの枝が必要で、その枝を採取できる親木の育成に数年かかる。同社は、森林総合研究所林木育種センターが05年に開発した無花粉スギ「爽春(そうしゅん)」を使い昨年4月から高効率栽培に取り組んだ。二酸化炭素濃度を外気の3倍程度に高めた空気を満たした室内で、2センチ程度の枝を挿し木。赤と青の光を当てながら水を与えると光合成が活発になり、8割以上が3〜4週間で根が伸び始めた。これを育てて苗木とし、採った枝を挿し木に使うことで数年のサイクルが1年未満に短縮でき、効率は100倍近くに向上するという。林木育種センターによると、無花粉スギは普通のスギよりコストがかかるが、緑化事業や生け垣などに使うことで花粉発生の抑制が期待できるという。現在、東京都や富山県など各地で無花粉スギの開発・増産の取り組みが進んでいる。(平成21年3月21日 毎日新聞) 若年性認知症、推計3万7800人 65歳未満の現役世代が発症する若年性認知症の人が全国で推計3万7800人に上ることが厚生労働省研究班の調査でわかった。若年性は働き盛りなどに発症するため、失業や経済的困難に結びつくことが多い。同省は新年度から、各地に支援担当者を配置するほか、就労支援や相談窓口の開設などに力をいれていく方針。調査は2006〜08年度に、茨城、群馬、富山、愛媛、熊本県で実施した。認知症の人が利用する可能性がある医療機関など約1万2000ヵ所に、患者の有無や病名などを尋ねたほか、介護者の家族会に生活実態などを聞いた。5県で把握された人数は、約2000人。これをもとに全国では約3万7800人と推計した。 1996年度の前回調査では、約2万5600人〜約3万7400人と推計されていた。18〜64歳の人口10万人あたりで見ると、男性が57.8人、女性が36.7人。推定発症年齢は、男性が平均51.1歳、女性が同51.6歳だった。原因は、脳血管性認知症が39.8%と最も多く、アルツハイマー病(25.4%)、頭部外傷の後遺症(7.7%)がそれに続いた。若年性認知症の人を介護する87家族に生活実態を聞いたところ、介護者の約6割が抑うつ状態と判断されたほか、約7割の家族で収入が減っていた。(平成21年3月20日 読売新聞) 肝がんリスク、肥満は2倍超 厚生労働省研究班は高血糖や肥満などメタボリック症候群の関連要因を抱えている人について、肝臓がんにかかるリスクが2倍以上に高まるとの大規模疫学調査の結果を発表した。肝がんは大半が肝炎ウイルスに感染して発症するが、生活習慣に気をつければ発症を回避できる可能性があるという。井上真奈美・国立がんセンター室長が、40−69歳の男女1万7590人を13年間追跡調査。 期間中に102人が肝がんにかかった。調査開始時点の健診結果をもとに、血圧や血糖値、中性脂肪、体格指数(BMI)などのメタボリック関連要因が、肝がんリスクと関連するか調べた。高血糖(1デシリットル当たり140ミリグラム以上、または空腹時で同100ミリグラム以上)のグループは、そうでないグループと比較し、肝がんになるリスクが1.75倍になった。また肥満度を示すBMIが25以上の人は、そうでない人と比べて肝がんリスクが2.22倍になった。(平成21年3月10日 日本経済新聞) 大豆、女性は食べ過ぎないで 大豆製品をたくさん食べる女性は、あまり食べない女性に比べて肝臓がんになる危険性が3〜4倍に高まることが、厚生労働省の研究班の大規模調査で分かった。大豆に含まれるイソフラボンは、乳がんのリスクを減らすことが知られており、研究班は「食事を通して適度に取るのがいい」としている。研究班は93年から05年まで、6府県の男女約2万人(開始時40〜69歳)の健康状態を追跡した。うち101人(男性69人、女性32人)が肝臓がんになった。アンケートで大豆食品をどれぐらい食べるかを尋ね、イソフラボンの2成分の摂取量と発症との関連を調べた。その結果、摂取量とリスクの関連が明らかになったのは女性だけで、摂取量が最も多い群(1日あたり豆腐80グラム以上、納豆3分の2パック以上)が肝臓がんになるリスクは、最も少ない群(同豆腐40グラム未満、納豆3分の1パック未満)のリスクの約3.2〜3.9倍だった。研究班の倉橋典絵・国立がんセンター予防研究部研究員によると、イソフラボンの分子構造は、女性ホルモンのエストロゲンに似ている。エストロゲンは乳がんのリスクを高める半面、肝臓がんには予防作用があり、イソフラボンの過剰摂取がこうした作用を妨げると考えられる。倉橋研究員は「肝臓がんの最大のリスク要因はB型、C型肝炎ウイルス。女性の場合、まず感染の有無を調べ、感染が分かれば大豆製品の取りすぎに注意してほしい。感染していなくても過度の取りすぎには注意が必要」と指摘する。(平成21年3月10日 毎日新聞) iPS細胞の高品質化に成功 パーキンソン病患者の皮膚からさまざまな細胞に成長する人工多能性幹細胞(iPS細胞)を高品質でつくることに、米国チームが成功した。従来の作製法と比べ、iPS細胞の性質のばらつきを抑え、がん化などの危険性も減らせるという。パーキンソン病は神経細胞が減って神経伝達物質のドーパミンが不足し、手足のふるえなどが起こる難病。米マサチューセッツ工科大などのチームは、53〜85歳の男女5人の患者の皮膚細胞に、iPS細胞をつくるのに必要な3つの遺伝子を導入した。遺伝子の導入には従来通りウイルスを使ったが、iPS細胞ができた後、特殊な酵素で導入遺伝子を取り除き、遺伝子が過剰に働かないようにする仕組みも加えた。すると、できたiPS細胞の遺伝子の働きぶりは、従来のiPS細胞より、もうひとつの万能細胞の胚(はい)性幹細胞(ES細胞)に近くなることがわかった。iPS細胞は、パーキンソン病などの難病治療に使えると期待されているが、導入遺伝子が残っていると性質がばらつくとされ、臨床応用への課題になっている。国立成育医療センター研究所の阿久津英憲室長は「技術改良が着実に進んでいる。導入遺伝子を残さない今回のような作製法は、今後の主流になる可能性がある」と話す。(平成21年3月6日 朝日新聞) 血液から新型iPS細胞できた あらゆる組織や細胞になりうる新型の万能細胞(iPS細胞)を、血液からつくることに、東京大医科学研究所の中内啓光教授らが成功した。人のiPS細胞はおもに皮膚を切り取ってつくるが、採血で可能になれば、患者の負担が軽い再生医療の実現につながる。iPS細胞は、患者の細胞からつくることができ、拒絶反応の少ない再生医療が期待される。患者の細胞はより簡単に入手できるほうがいい。皮膚の細胞は、針を使って採取するが、出血性の血液疾患の患者や子どもには向かない場合があるという。採血なら、患者、医師ともに負担が小さい。今回のiPS細胞は、山中伸弥・京都大教授らが使った4つの遺伝子を人の血液に導入して作製した。ただ血液中には、赤血球や白血球などの血液細胞以外の別の細胞も混じっており、できたiPS細胞が血液細胞がもとになったのか、はっきりしない。これを調べるため、マウスで実験をした。別のマウスの造血幹細胞を移植したマウスの血液からiPS細胞を作製し、遺伝子を調べたところ、別のマウスの遺伝子情報と一致した。血液中の造血幹細胞が変化した造血前駆細胞から作製されたとみられることが確認された。(平成21年3月5日 朝日新聞) HIV除去体外受精111組 エイズウイルス(HIV)に感染した夫の精液からウイルスを除去し、体外受精する生殖補助医療を国内で受けた夫婦が110組を超えたことが、治療の窓口を担う荻窪病院(東京都)の調査でわかった。71人の子供が生まれ、母子ともに感染例はないが、現在治療を実施している医療機関は2ヵ所だけだ。ウイルス除去技術の習得が難しいことなどが理由で、実施機関の拡大が課題になっている。治療がこれまでに実施されたのは、新潟大、慶応大、杏林大。治療法が開発された2000年から08年までに、111組の夫婦で計267回の治療が行われた。その結果、延べ59人の母親が計71人の子供を出産した。杏林大は担当医師がいなくなったため、現在は中止している。治療を待つ夫婦は現在、約80組。荻窪病院では、全国の医療機関に協力を呼びかけているが、「母子に感染したら責任を負えない」「産婦人科医が不足し新しい治療を行う余裕はない」などとして、引き受けるところはないという。同病院の花房秀次副院長は「治療法の安全性は確立したと思う。だが、医師が安全に実施するための技量を身に着けるには研修が必要で、各病院は二の足を踏んでいる」と話している。(平成21年2月28日 読売新聞) 処方薬自分で中断6割 医師から処方された薬の服用を途中でやめた経験のある人は6割を超えることが、製薬企業「ファイザー」日本法人の調査で分かった。抗菌薬(抗生物質)は、患者が自己判断で服用を中断すると薬が効きにくい耐性菌が発生する恐れもある。「自己判断で中断せず、医師の処方に従って服用してほしい」と同社は訴えている。調査は昨年11月末、インターネットを使って、全都道府県に住む成人9400人を対象に行われた。「処方薬を途中で服用するのをやめたことがあるか」の設問には、13%が「よくある」、51%が「たまにある」と答えた。理由別では「症状が改善したから」が最も多かった。「自分の判断で服用量を調節したことがあるか」という設問に対しては、3%が「よくある」、22%が「たまにある」と回答、4人に1人が自分の判断で服用量を調節していた。抗菌薬の服用を途中でやめると薬が効きにくくなる可能性があることについては、「知らない」と答えた人が52%いた。抗菌薬を処方されたことのある7326人中、40%が服用中止の経験があると回答した。(平成21年2月27日 読売新聞) 世界初、iPS細胞で新薬検査 様々な臓器や組織の細胞に変化する人間の新型万能細胞(iPS細胞)を使い、新薬の候補になる物質が心臓へ副作用を起こすかどうかを検査するサービスが、早ければ4月に始まる。実施するのはバイオベンチャー企業リプロセルで、iPS細胞を使って事業を起こすのは世界で初めて。新薬は、効能や副作用を動物実験などで確かめながら、数万種類の物質から絞り込んでいく。生死にかかわる心臓への副作用が、最終段階の臨床試験で初めて分かった場合、数十億〜数百億円に及ぶ開発費が無駄になりかねない。このため、早い段階で副作用を確かめる手法が求められていた。リプロセルは昨年、サルの胚性幹細胞(ES細胞)を利用し、心臓への副作用を検査する技術を確立。今回はこの技術を応用した。小さな電極60個を張り付けた皿に、iPS細胞から作った心筋細胞の塊(大きさ0.1〜0.3ミリ)を入れたところ、正常な心電図のパターンの検出に成功。心臓への悪影響が知られている化合物2種類をこの皿に加えたところ、不整脈のパターンを検出、副作用を確認できたという。(平成21年2月28日 読売新聞) 梅毒、患者急増 梅毒患者の報告数がここ数年、急増していることが国立感染症研究所のまとめで分かった。感染を知らず出産し、子供が先天梅毒になるケースもある。。感染研によると、梅毒患者数は抗生物質など薬剤開発により戦後減少傾向だったが、03年以降、再び増え始めた。03年に509例だった報告数は06年に600例を超え、07年737例、08年は823例と毎年100例近く増え続けている。男性では35〜39歳、女性では20〜24歳の割合が高い。20〜24歳の女性は03年15例だったのが、07年には49例と3倍以上に増えた。母子感染による先天梅毒は06年に10例、08年は7月末現在で7例報告。妊娠中に夫から感染したとみられる症例もあった。先天梅毒の子供の4割は妊娠中か生後1週間までに死亡するといい、感染症情報センターの多田有希室長は「妊婦検診を必ず受け、感染が判明したらきちんと治すことが大事だ。妊娠後期に2回目の検査もしてほしい」と警告する。梅毒は細菌「梅毒トレポネーマ」が引き起こす性感染症で、国内では99年以降、感染を確認したらすべて保健所に届けるよう義務付けている。性感染症に詳しい斎田幸次・斎田マタニティークリニック院長は「不特定多数と性行為をする風潮が原因ではないか。(感染を防ぐ)コンドームの出荷数も減少しており、感染増加との関連が示されている」と話す。(平成21年2月17日 毎日新聞) 前立腺がん、尿検査で早期発見 尿中のアミノ酸代謝物の濃度を調べることで、前立腺がんの進行状況をより正確につかめる可能性があることが、米ミシガン大学などの研究でわかった。米国立がん研究所も「がんの進行度をみる優れたマーカー(指標)になりうる」と評価している。英科学誌ネイチャーに発表した。前立腺がんの早期発見のため、いまは血液中の「前立腺特異抗原(PSA)」というたんぱく質の量を調べる方法が検診などで使われている。しかしPSA検査は、がんではないちょっとした異常にも反応したりするほか、ゆっくりと進むがんに対して過剰な手術や放射線治療をしてしまう問題も指摘されている。研究グループは、前立腺がんの患者から集めた組織、尿、血清から分離される化合物を対象にがんの指標になる物質を調査。サルコシンというアミノ酸代謝物の一種が転移性のがんに多く見られることを見いだした。サルコシンは良性の組織ではほとんど見られなかったのに対して、局所がんの42%、転移性がんでは79%で見つかった。がん細胞を使った実験ではサルコシンを加えるとがんの進行が早まった。前立腺がんが疑われる患者の尿を調べた調査では、PSA値が低いときはPSAより正確に判定できるという結果が出た。(平成21年2月16日 朝日新聞) 線維筋痛症の診療マニュアル 全身に痛みを感じる「線維筋痛症」に関する初の診療マニュアルを、厚生労働省研究班が11日公表した。患者は推定約200万人だが、医療関係者の認知度が低く、治療法も確立していない。適切な治療やケアを受けられず、うつ病や寝たきりになる人も多く、抗うつ薬投与などを盛り込む。マニュアル作成には患者も参加した。研究班は、線維筋痛症を診察する全国の医療機関の診療データなどを分析。病状や診断基準、治療法の評価などの骨格をまとめた。診断基準では、米リウマチ学会が90年に策定した基準(原因不明の全身の痛みが3ヵ月以上続き、全身18ヵ所のうち押すと11ヵ所以上で痛みがある場合)が日本人にも有効と確認。治療法は4段階で評価し、抗うつ薬投与や認知行動療法、有酸素運動は「強く勧められる」、長期安静は「勧められない」などと分類する。来月末に完成する。線維筋痛症は、一般的な痛みの原因である炎症が起きず、検査で異常を見つけられない。痛みはひどく、服が触れるだけで痛みを感じる。(平成21年2月12日 毎日新聞) 遺伝子1個使いiPS細胞 米独の研究チームが、いろいろな組織の細胞になる新型万能細胞(iPS細胞)を1個の遺伝子だけを用いて作り出した。使う遺伝子が少ないほど、がん化する危険が減るとされ、3個の遺伝子を要した京都大の山中伸弥教授らの研究をリードする成果だ。マウスを使った実験で、6日の米科学誌「セル」に発表する。ドイツのマックスプランク分子医薬研究所やボン大学、米国の民間企業などが共同で成功した。万能細胞を作る素材にはマウスの神経幹細胞を使った。この細胞では、必要な3個の遺伝子のうち1個は初めから働いている。研究チームは、残る2個のうち、発がんにつながる恐れの低い遺伝子のみを組み入れた。その結果、約4週間後にiPS細胞ができた。(平成21年2月6日 読売新聞) iPS細胞から血小板作製 様々な細胞に変化できる人の「新型万能細胞(iPS細胞)」から、血を止める役割を果たす血小板を作製することに、東京大学医科学研究所の研究チームが成功した。輸血に使われるが、保存期間が4日程度と短い血小板の大量生産につながる成果という。血小板は、がん治療中の患者の血小板生成の低下を補う目的などで輸血される。 献血で賄われるが、供給量の確保が課題になっている。他人の血小板を輸血すると免疫拒絶が起きる場合もあり、患者由来のiPS細胞からの血小板作製が期待されていた。中内啓光教授(幹細胞生物学)らは、人の皮膚から作ったiPS細胞を、増殖を助ける細胞とともに14日間培養。すると、袋状の構造物が生成され、中に血液の成分の元になる造血前駆細胞が詰まっていた。さらに、造血前駆細胞に成熟を促すたんぱく質を加えたところ、24日目に血小板が詰まった細胞ができた。中内教授は「5年後を目標に臨床治験までできるようにしたい」としている。(平成21年2月6日 読売新聞) クラゲ、「変形性関節症」治療に効果 エチゼンクラゲなどに含まれるたんぱく質「クニウムチン」が、関節の軟骨がすり減る「変形性関節症」の治療に効果があることを、東海大の佐藤正人准教授(整形外科学)らが動物実験で突き止めた。変形性関節症は加齢やけがが原因で歩行困難になる病気で、国内に約700万人の患者がいるとされる。ヒアルロン酸を関節に注射して進行を遅らせることができるが、根本的な治療法はない。クニウムチンは理化学研究所などが07年、エチゼンクラゲから見つけた。人間の胃液の主成分「ムチン」に似た構造を持つ。佐藤准教授らは、関節の軟骨の表面にもムチンがあり、変形性関節症の人はその量が少ないことに着目。変形性関節症のウサギで実験したところ、ヒアルロン酸だけを注射したウサギより、ヒアルロン酸とミズクラゲやエチゼンクラゲから採取したクニウムチンを注射した方が、軟骨の厚さの回復がよく、損傷の度合いや範囲も大きく改善した。佐藤准教授は「ヒアルロン酸がクニウムチンを包み、相乗効果によって軟骨に長くとどまるからではないか。大型の動物で安全性などを確認し、人の治療に役立てたい」と話す。(平成21年1月31日 毎日新聞) インフルエンザの万能ワクチン開発 いろいろなタイプのインフルエンザウイルスに効くワクチンを厚生労働省研究班が開発した。従来のワクチンと違い、ウイルスが変異しても効果が続くのが特徴で、動物実験で確かめた。実用化までには数年かかるとみられるが、新型インフルエンザの予防にも役立つと期待される。研究班は、国立感染症研究所、北海道大、埼玉医科大、化学メーカーの日油。通常のワクチンは、ウイルス表面をとげのように覆うたんぱく質をもとに作る。接種後、ウイルスが体内に侵入すると、抗体がとげを認識して増殖を阻止する。だが、インフルエンザは、とげの形が異なる複数のウイルスが流行することが多いうえに、頻繁にとげの形が変異するため、毎年のようにワクチンを作り直す必要があった。流行する型の予測がはずれると、ワクチン接種の効果が薄れた。研究班は、表面に比べて変異しにくいウイルス内部のたんぱく質を人工合成。それに特殊な脂質膜をくっつけてワクチンを作った。このワクチンを接種すると、免疫細胞が、ウイルスの感染した細胞を攻撃する。実験では、新型インフルエンザウイルスに変異する可能性が高い高病原性鳥インフルエンザウイルスH5N1、Aソ連型、A香港型の3種共通の内部たんぱく質を調べ、ワクチンを作製。免疫に関与する人間の遺伝子を組み入れたマウスに接種した後、ウイルス3種をマウスに感染させても症状が表れず、増殖も抑えた。ただ、これまでにないタイプのワクチンなので、人間に使って重い副作用が出ないか、慎重に確認する必要がある。同じ仕組みのワクチンを英オックスフォード大も研究中という。研究代表者の内田哲也・感染研主任研究官は「人間に有効で安全な量を調べ、一刻も早く実用化につなげたい」と話している。(平成21年1月29日 読売新聞) 「インフルエンザAソ連型」タミフル耐性が5割超 インフルエンザ治療薬「タミフル」が効かない耐性ウイルスが高頻度で検出されている「Aソ連型」が今シーズンの流行の主流になりつつあると、国立感染症研究所が27日、発表した。主流になった原因が耐性化なのかどうかは不明という。研究所は全国の医療機関に対し、「周囲で流行しているウイルスのタイプを踏まえ、治療法を選んでほしい」と呼びかけている。流行は昨年12月に始まった。今月18日までに全国776人の患者から検出されたウイルスを分析したところ、Aソ連型413人(53.2%)、A香港型281人(36.2%)、B型82人(10.6%)だった。また、23都道府県のAソ連型患者121人のウイルスを調べると、1人を除き99.1%で耐性化していた。今月16日の発表では、Aソ連型の割合は36.2%で、耐性化ウイルスが見つかったのは11道府県で、その割合は97.1%だった。治療薬にはタミフルのほかに「リレンザ」がある。ワクチンは耐性化したウイルスにも有効であることが確認されている。研究所の岡部信彦・感染症情報センター長は「今後も耐性ウイルスが広がるか見守る必要はあるが、治療に複数の選択肢を持つことが改めて重要になってきた。普段から手洗いとうがいを徹底し、感染したら十分な栄養と休息を取ってほしい」と話す。(平成21年1月28日 毎日新聞) iPS細胞から受精卵作り 産婦人科医や基礎医学などの研究者らでつくる日本生殖再生医学会は、人の皮膚などの細胞から作る人工多能性幹細胞(iPS細胞)から精子や卵子を作るだけではなく、作った精子や卵子を受精させ、着床前までの研究を認めるべきだとの見解をまとめた。見解によると、iPS細胞から精子や卵子を作り、受精させて染色体の異常が起こらないかなどを調べるため、約5日後まで成長させることを提言する。関係者は「生殖細胞を作るだけで受精させなければ、機能するかどうか分からない。不妊の原因を探るには生殖細胞が育っていく過程を調べることが重要」と話している。文部科学省の作業部会は、iPS細胞から精子や卵子を作る研究までは認める方向で議論しているが、「技術的にも倫理的にも時期尚早」として受精を認めていない。受精は命の始まりと密接にからむため、議論が多い。 同学会は、体外受精法で受精できない不妊の治療法の開発を目的にし、05年に設立された。約200人が定例の会合に参加する。昨年8月に委員会を設置し、人のiPS細胞から生殖細胞を作る研究について検討してきた。(平成21年1月28日 朝日新聞) カロリーセーブなら記憶力Up! 健康な中高年が摂取カロリーを制限すると、記憶力が向上するという実験結果を、独ミュンスター大学の研究チームが26日、米科学アカデミー電子版に発表した。やせ過ぎていない50〜79歳の男女49人を3グループに分け、19人にはカロリー摂取量をふだんより30%減らしてもらった。別の20人は認知症の予防に役立つという説のある不飽和脂肪酸の摂取をふだんより20%増量し、残る10人は従来の食生活を続けた。実験前と3ヵ月後に言葉を覚えるテストを行った結果、カロリーを抑えた19人の点数は約20%も上昇した。他の2グループは成績に変化が見られなかった。カロリー制限によって、体内の血糖値を調整するインスリンが効きやすくなった人ほど、成績の伸びが著しかった。こうした体質が、脳神経に何らかの良い影響を与えているとみられている。(平成21年1月27日 読売新聞) 抗生物質、服用中断で耐性菌生む 感染症の治療に使われる抗生物質などの抗菌薬を処方された患者の4割が、途中で治ったと思い込んで服用をやめた経験があることが、製薬会社のファイザーの調査で分かった。服用を中断すると、抗生物質が効かない耐性菌が生まれる危険があり、分析した渡辺彰・東北大教授(感染症学)は「自己判断で飲むのをやめるのは絶対に避けてほしい」と警告している。昨年10月、インターネットで各都道府県の男女100人ずつ計9400人に調査したところ、40%に抗生物質の服用中止の経験があり、うち8割以上は「症状が改善された」と自己判断していた。薬が余った場合は、中止の経験がある患者の42%が「保存しておき、同じ症状が出た時に再度使う」と答えた。中断すると、その後は薬の効きが悪くなるのを知っていたのは、半数以下の48%にとどまった。渡辺教授によると、抗生物質はむやみに服用すべきでないが、一度使ったら必要量を集中的に飲まないと、生き残った病原菌が耐性化して治療が難しくなる恐れがあるという。日本では肺炎球菌や中耳炎などを起こすインフルエンザ菌が耐性を持つ割合が急増しており、「他の先進国と比べ国民が服薬指導を守っていないことも原因の一つではないか」と話している。(平成21年1月26日 毎日新聞) ES細胞、脊髄損傷患者に注入 米バイオベンチャー企業「ジェロン」は23日、人間の胚性幹細胞(ES細胞)を応用した治療の臨床試験を、世界で初めて行うと発表した。脊髄損傷で歩けなくなった患者に、ヒトES細胞から作製した細胞を脊髄に注入、神経系細胞を再生させる。臨床試験の第1段階は今夏に開始。損傷から1〜2週間の患者8〜10人を対象に、中枢神経を保護する細胞に育つ細胞を注入する。治療の安全性を確かめるのが目的だが、マヒした感覚や運動機能の回復など、治療効果も同時に調べる。(平成21年1月24日 読売新聞) 「多発性硬化症」治療に光 手足のまひや視覚障害などが起きる神経難病「多発性硬化症」の治療のカギとなる、神経の再生不良の原因を慶応大医学部の中原仁講師らが解明、国際医学誌「ジャーナル・オブ・クリニカルインベスティゲーション」1月号に発表した。多発性硬化症は、神経を覆う「さや」が壊れ、電気信号がうまく伝わらなくなる病気。 健康な人の場合、「さや」が傷つくと、オリゴデンドロサイトという細胞が成長して、自然に傷が修復されるが、多発性硬化症では、この自然な再生がうまくできない。中原講師らが多発性硬化症の患者の脳で、オリゴデンドロサイトに成長する過程を詳しく調べたところ、その成長を妨げる「TIP30」という分子が病変部分で異常に増えていることを発見した。中原講師は「この分子を抑える薬を開発すれば治療につながる可能性がある」と話している。(平成21年1月23日 読売新聞) ピロリ菌、全員除菌を 胃がん予防のため、胃の粘膜に細菌ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)がいる人は全員、薬で除菌することを勧める新指針を日本ヘリコバクター学会が発表した。新指針では、ピロリ菌が胃粘膜にいる状態を「ヘリコバクター・ピロリ感染症」と位置づけ。除菌は胃潰瘍の治療や胃がん予防に役立つなど、「強い科学的根拠があり、強く勧められる」とした。除菌の効果については、浅香正博・北海道大教授らが昨年、国内患者を対象とした臨床研究をもとに「除菌すれば胃がんの発生が3分の1になる」と英医学誌で発表。これを受け同学会で指針改定を検討していた。現在、除菌が保険適用されるのは、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の患者。日本では約5000万人がピロリ菌の感染者といわれる。除菌には通常、抗菌剤など3種類の薬を1週間のむ。(平成21年1月23日 朝日新聞) 胃がん、染色し部位浮き上がらせる 色素に酢(酢酸)を混ぜ、胃がん部位を浮き上がらせる検診技術を岡山大学病院光学医療診療部の河原祥朗助教らが発見、日本消化器内視鏡学会の英文誌「DigestiveEndoscopy(消化器内視鏡)」に発表した。胃がんの正確な診断や早期発見につながる手法として期待されている。胃がんの治療は近年、患者の負担が少ない内視鏡手術が発達。患部の根元に薬剤を注入し、がんを持ち上げて切り取る「内視鏡的粘膜下層剥離(はくり)術」が普及し、内視鏡で切除可能な胃がんは直径約2センチから10センチ以上になった。一方、通常胃がんの診断には、インジゴカルミンという青色の着色料で胃内部を染め、凸状になった患部を浮き上がらせる手法が用いられる。しかし、胃壁は元々起伏があるためがんと見分けがつきにくく、正診率は約70%という。取り残しは再発につながるため、がん部位を正確に把握するための検出技術が求められていた。河原助教らは胃の細胞は粘液で胃酸から身を守り、がん細胞は粘液をつくる力を失う点に着目。内視鏡検診時は胃の中が空で胃酸、胃粘液とも分泌されないため、検診時にインジゴカルミン溶液に0.6〜0.8%の酢酸を混ぜることで胃を刺激し、粘液を分泌させた。その結果、着色料は正常組織の粘液と結合して青く染まり、胃がん部分だけが浮き上がって正診率は90%以上に向上したという。河原助教らは既に日本の特許を取得し、科学技術振興機構の支援を受けて海外でも特許を出願する予定。河原助教は「特殊な機器が不要で、低コストで正確な診断ができるようになった」と話している。(平成21年1月14日 毎日新聞) iPS細胞で血友病治療 新型万能細胞(iPS細胞)を成長させた細胞を肝臓に注入することによって血友病を治すことに、米ネバダがん研究所などがマウスを使った実験で成功した。血友病の根本治療につながる成果で、米科学アカデミー紀要電子版に13日掲載された。 研究チームはマウスの尾の皮膚からiPS細胞を作製。内皮の元になる細胞まで成長させたところ、血を止める成分が分泌されていることを確認。 この細胞を血友病のマウス6匹の肝臓に注入した。その結果、注入したマウスは尾を切って出血させても、人間なら20年間にあたる3ヵ月間も生きた。一方、細胞を注入しなかった血友病のマウス6匹は2〜8時間で死んだ。(平成21年1月14日 読売新聞2009・1・14) タミフル効かない耐性インフル インフルエンザ治療薬「タミフル」が効かない耐性ウイルスについて、厚生労働省は今冬、緊急の研究班を設置し、耐性ウイルスに感染した患者の全国的な実態調査に乗り出すことを決めた。欧米などで耐性ウイルスの急増が次々と報告されているが、世界最大のタミフル使用国である日本国内で耐性ウイルスが広まると医療現場が混乱する可能性があるためだ。国立感染症研究所によると、国内の耐性ウイルスの出現率は昨冬で2.8%と低いが、米国では昨冬が11%、昨年秋に実施した50試料を対象にした予備調査では98%に跳ね上がった。このため、米疾病対策センター(CDC)は先月、今冬の主流は耐性ウイルスであると判断し、薬を投与する際には、別のインフルエンザ治療薬であるリレンザなどを併用することを勧めた緊急の治療指針を発表した。欧州全体でも昨冬、調べたウイルスの20%が耐性を獲得し、ノルウェーでは67%に達している。タミフルの使用頻度が低い国でも耐性を獲得していることから、耐性ウイルスは自然発生して流行しているとみられている。新型インフルエンザへの変異が心配される高病原性鳥インフルエンザ(H5N1型)に感染した東南アジアなどの外国の患者で、タミフルを早期に服用しなかった人はすべて死亡している。このため国などは、新型インフルエンザ対策として、流通分も含め2800万人分のタミフルを備蓄している。しかし、耐性ウイルスが国内でも広まった場合、そこに人が免疫を持っていない新型インフルエンザが来襲すると、同時に感染するうちに新型インフルエンザが耐性を獲得、備蓄されているタミフルが効かないまま感染が拡大しかねない。調査は、国立国際医療センターなどが中心となり、「Aソ連型インフルエンザウイルス」の3割以上に耐性が見つかった鳥取県を含め、北海道から九州まで全国6〜7ヵ所で、流行状況を調べる。タミフル使用との因果関係や、家族内や学校内での集団感染などの患者情報も収集する。タミフル以外の薬の使用状況も調べ、研究班では新たな治療指針を作成する方針だ。国立感染症研究所によると、今冬も、宮城県や滋賀県の小学校児童から耐性ウイルスが見つかっている。厚労省は「耐性ウイルスがさらに広まったときに備え、治療薬の適切な使い方を検討したい」としている。タミフル:一般名はリン酸オセルタミビル。インフルエンザウイルスが体内で増えるのを抑え、発熱から2日以内に服用すると、高熱や筋肉痛などの症状を緩和し、発症期間を1日ほど短くする効果がある。鳥インフルエンザウイルスでも耐性を持つものが出ている。(平成21年1月13日 読売新聞) ヒアルロン酸、しわ取り、自己注射「ダメ」 インターネットで購入したヒアルロン酸を、自分で顔などに注射する行為が広がっている。10日、東京都内で開かれた日本美容外科学会で、日本医科大の百束比古教授らが自己注射による後遺症例を報告し、「素人は絶対にやめるべきだ」と呼び掛けた。ヒアルロン酸は関節や真皮に含まれ、化粧品の保湿成分として使われる。美容クリニックなどでは、しわの下に注射して目立たなくさせる美容法が提供されている。効果を持続させるには約半年ごとの注射が必要だ。神奈川県内の女性(36)は04年春ごろ、美容クリニックでこの注射を受け、口の両脇のしわに注入して約8万円払った。その後、費用がかさむため、ネットの掲示板で話題になっていた自己注射に興味を持った。クリニックで使用していたものと同じメーカーのヒアルロン酸を、香港の輸入代行業者を通して1個約2万円で2個購入。備え付けの注射器を使い、掲示板の体験談などを基に07年12月、自分のほおや目の下に注射した。「失敗しても半年で元に戻る」と考えていたが、2、3ヵ月後、注射した部分の一部が膨らみ、しこりになった。クリニックでヒアルロン酸を分解する注射を打ったがしこりはなくならず、皮下にひきつれが起きる「異物肉芽腫症」と診断された。完全に元に戻すことは難しく、女性は 「すごく後悔している」と話す。香港の業者は「日本からは月に100件ほど注文があり、ほとんどは個人だと思う。医師の処方せんに基づいて使うという前提で販売しているので、自己注射に関する質問には、医師に相談するよう勧めている」と話す。注射に使うヒアルロン酸を輸入する際には薬事法の規制を受ける。しかし、厚生労働省によると、個人が少量を自分で利用する場合は所定の手続きを経ずに入手できるという。百束教授は「ネットでは自己注射の利点ばかりが強調されるが、後遺症に加え、注射によるショック死の可能性もある。水面下にはたくさんの事故例があるのではないか」と警鐘を鳴らす。(平成21年1月11日 毎日新聞) パーキンソン病の患者からiPS細胞 様々な細胞に変化できる新型万能細胞(iPS細胞)を、日本人の家族性パーキンソン病の患者から作ることに、慶応大の岡野栄之教授らが成功し、9日、大阪・千里で開かれた講演会で発表した。発症メカニズムの解明や治療法の開発につながると期待される。パーキンソン病の原因遺伝子の一つ「PARK(パーク)2」に異常がある60歳代の患者から皮膚細胞の提供を受けた。PARK2は、脳の神経細胞が信号を伝えるシナプスという部位の働きにかかわっている。iPS細胞を神経細胞に変化させ、正常な細胞と比較しながら発症のしくみを調べる。(平成21年1月10日 読売新聞) 厚労省、薬副作用の分析を強化 最近、抗がん剤や関節リウマチなどで効き目の高い薬が登場する一方、重い副作用を伴うケースも増えているが、監視と分析の体制は欧米に比べ手薄になっていた。現在、1日当たり約130件の副作用情報が寄せられているが、処理されているのは死亡例や特に重い副作用のある同約40件にとどまる。また、対応の遅れで被害が拡大した薬害肝炎の問題を重視した。米国では医薬品の審査・安全対策に約2900人の担当者がいる。欧州連合(EU)は約440人を抱えているほか、EUを構成する各国にも400〜1100人いるという。これに対し、日本には新薬の審査担当が厚労省と同機構の計310人、副作用分析などの安全対策は計66人にとどまる。そこで、厚労省は来年度から約100人を増員し、これまで重い副作用があっても分析が後回しにされがちだった事例の迅速な対応に取り組む方針だ。(平成21年1月8日) 結核の脅威、都市に潜む 「過去の病」と思われてきた結核の感染リスクが東京や大阪など大都市で高まっている。研究機関の調査で、都市に集中する娯楽施設や24時間営業の飲食店などでの感染が判明。専門家は不特定多数が密閉空間で長時間いる施設で、複数の人に感染が広がる可能性を指摘する。治療経験のある医師や結核病床の減少も進んでおり、診療体制の維持・強化が急務になっている。東京都内のIT(情報技術)関連企業に勤めていた男性(34)は2005年5月ごろ、急に体の変調を覚えた。せきと発熱がおさまらない。かかりつけの診療所で風邪と診断され、処方薬を飲んだが、症状は改善しなかった。(平成21年1月5日 日本経済新聞) |