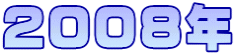
|
|---|
タミフル、10代への解禁先送り 飛び降りなどの異常行動との関連が疑われ、2007年3月から10代患者への使用が原則中止されているインフルエンザ治療薬タミフルについて、厚生労働省は今冬は中止措置を継続する方針を決めた。異常行動などを調べた厚労省研究班の大規模疫学調査の精度に限界があり「性急な判断はできない」との見方が強まった。タミフルの扱いを最終判断する同省安全対策調査会の開催は来年2月以降にずれ込む見通しで、結論まで長期化する可能性もある。(平成20年12月29日 日本経済新聞) iPS細胞で症状再現 米大チーム初成功、新薬開発に応用 神経難病の患者の皮膚からつくった新型万能細胞(iPS細胞)を神経に成長させた後、病気のため神経が死ぬのを試験管内で再現することに、米ウィスコンシン大のジェームズ・トムソン教授らのチームがに成功した。 患者由来のiPS細胞を使い、症状の再現までできたのは世界初。病気の原因解明や新薬開発などの研究で強力な武器になると期待される。チームは、運動神経が徐々に減り乳幼児期に死亡することが多い、遺伝性の重症型脊髄性筋萎縮症(SMA)の男児の皮膚からiPS細胞を作製し、運動神経に分化させた。発症していない母親の皮膚からも同様に運動神経をつくり、両方を別々に培養して細胞の状態を比較した。(平成20年12月31日 日本経済新聞) ひざ半月板、再生に道 ひざの半月板損傷を、関節部分から採取した間葉系幹細胞を移植して治すことに、東京医科歯科大などの研究チームがラットで成功した。半月板はひざの内部にあり、大腿骨とすねの骨の間でクッションの役割を担う軟骨組織。怪我や加齢で半月板を損傷した場合、半月板を切除する治療が一般的だが、関節症などを起こしやすい。チームは半月板を再生させるため、骨や軟骨になる性質がある間葉系幹細胞を使った。同細胞は骨髄から取るのが一般的だが、関節の滑膜という組織から採取した。半月板を損傷させた14匹のラットの患部に幹細胞を移植すると、約12週間で半月板と同じ性質の軟骨になった。小林英司・自治医科大教授(移植・再生医学)らが開発した、細胞を遺伝子改変によって光らせる技術で調べたところ、半月板が再生し関節を保護する様子が確認できた。また、半月板が再生した後の間葉系幹細胞は過剰に増殖する心配がないことも分かった。人工多能性幹細胞(iPS細胞)や胚(はい)性幹細胞(ES細胞)を使う再生医療では、目的の組織ができた後も増殖が止まらず、腫瘍(しゅよう)になったり、他の臓器に移動して奇形を生む恐れがあり、課題となっている。関矢一郎・東京医科歯科大准教授(軟骨再生学)は「滑膜からの幹細胞は採取しやすく取り扱いも簡単だ。数年以内にヒトでの臨床応用を始めたい」と話す。(平成20年12月28日 毎日新聞) たばこが原因で死亡、年間20万人 たばこが原因で病気になり、死亡する人は、年間20万人近くにのぼるとみられることが、厚生労働省研究班の調査でわかった。国内の4つの疫学調査データを解析した。80〜90年代に40〜79歳の男女約29万7千人に喫煙習慣などを尋ね、約10年間追跡。2万5700人が死亡していた。喫煙率は男性54%、女性8%。たばこを吸っていて病気で亡くなるリスクを、吸わない人と比べると、男性では(1)消化性潰瘍7.1倍(2)喉頭がん5.5倍(3)肺がん4.8倍(4)くも膜下出血2.3倍。女性では(1)肺がん3.9倍(2)慢性閉塞性肺疾患(COPD)3.6倍(3)心筋梗塞(こうそく)3倍(4)子宮頸がん2.3倍などだった。また、過去に喫煙歴がある人も含めると、男性のうち27.8%、女性の6.7%が、たばこに関連した病気で死亡していた。(平成20年12月22日 朝日新聞) 蛍光物質、生きたがんだけ光らせる 生きたがん細胞だけを光らせる蛍光物質を、日米の研究チームが開発した。1ミリ以下の小さながんを見つけられるうえ、がん細胞が死ぬと光が消えるため、治療効果を確認しながら手術や内視鏡治療ができるという。開発したのは、浦野泰照・東京大准教授(薬学)、小林久隆・米国立衛生研究所主任研究員ら。生きた細胞内では「リソソーム」という小器官が弱酸性、死んだ細胞では中性になることに着目。乳がん細胞に結びつきやすく、酸性のときだけ光る物質を開発した。また、マウスの肺に乳がんが転移したという条件を再現したうえで蛍光物質を注射すると、1ミリ以下の肺がんが検出され内視鏡で切除することに成功した。さらに、がんを殺すエタノールをかけたところ、約30分後に光が弱まり、がん細胞の死を確認した。米国で臨床試験の準備に入ったという。PET(陽電子放射断層撮影)など現在の画像検査では、1センチ以下のがんを見つけることや、抗がん剤の投与後の効果をすぐに確認することは難しい。浦野准教授は「他の種類のがんに結びつく蛍光物質を開発することも可能だ。小さながんを見過ごさず切除できるので、誰もが名医になれるだろう」と話す。(平成20年12月8日 毎日新聞) サルからiPS細胞作製 中国の北京大学などの研究グループは、サルから新型万能細胞(iPS細胞)を作ることに成功した。ヒト以外の霊長類でiPS細胞を作ったのは初めて。 iPS細胞を使った再生医療の実用化を後押しすると期待される。研究成果は4日付の米科学誌「セル・ステムセル」(電子版)に発表する。研究グループはアカゲザルの皮膚細胞に、京都大学の山中伸弥教授らが使った4つの遺伝子を導入してiPS細胞を作った。神経や筋肉の細胞にも分化したという。(平成20年12月4日 日本経済新聞) 骨の形成能力が1.7倍の人工骨候補材 東北大学の鈴木治教授らの研究グループは、骨の形成を促す能力が従来の約1.7倍となる人工骨の候補材料を開発し、動物実験で性能を確認した。実用化できれば、人工骨移植後の回復が早くなるなどの効果が期待できる。 開発した材料は低結晶性リン酸オクタカルシウム(OCP)。この材料は骨の成分であるヒドロキシアパタイトの前駆物質であることが知られている。 また、骨を作る骨芽細胞を活性化する作用があるとされる。(平成20年12月3日 日経産業新聞) ガラガラヘビ毒から「強力」鎮痛物質 南米産のガラガラヘビの毒から、モルヒネの数百倍の鎮痛作用がある物質を抽出して合成することに、富山大和漢医薬学総合研究所の紺野勝弘准教授らが成功した。ラットの実験では効果が3日以上持続し、飲み薬の麻酔に使える可能性があるという。ブラジルに生息するガラガラヘビは、運動神経をまひさせる猛毒で知られるが、かまれても激しい痛みを感じないという。ブラジルでは30年代に、毒を薄めて痛み止め薬として市販されていたという。紺野さんは、世界的な毒蛇の研究機関として知られるブラジルのブタンタン研究所や富山大で、ガラガラヘビの毒を分析。チームで、アミノ酸が14個つながった化合物が鎮痛物質と突き止めた。さらに、鎮痛効果を確かめるため、ラットの脚に重さをかけ、どれぐらい我慢できるか調べた。この物質を飲んだ群は飲まない群に比べ、ほぼ倍の重さの痛みに耐えることができた。その効果は、1回飲ませただけで3〜5日続いた。モルヒネで同じ効果を出すには、その数百倍の量が必要なことも分かった。モルヒネは、使う量を増やさないと効き目が悪くなることがある。一方、このヘビの毒は量を増やさなくても同じ効果が続いたという。紺野さんは「飲み薬として使えれば、普及する可能性がある。痛みを抑える仕組みを解明して、薬作りにつなげたい」と話している。(平成20年11月30日 朝日新聞) 老化、新知識得ないと物忘れが進行 新しい知識や経験を得ない単調な生活を続けると、老化による物忘れが進む可能性があることを、理化学研究所のチームがマウスを使った実験で明らかにした。好奇心旺盛な高齢者は認知症になりにくいとされるが、それが裏付けられた形だ。老化に伴って記憶が失われる物忘れは、「タウたんぱく質」と呼ばれる物質が脳の神経細胞に蓄積することが原因だ。理研脳科学総合研究センターの木村哲也・専門職研究員(神経生物学)らは、タウたんぱく質の蓄積を促す酵素に着目。これを持たないマウスを迷路などに挑戦させ、行動を観察した。 このマウスは、酵素を持たなくても道順を覚えたが、何度も試すうちに忘れてしまった。これらのことから、この酵素は新しいことを覚えるプロセスでは働かないものの、いったん固定した記憶を繰り返し使いながら再固定するのに欠かせないことが分かった。この酵素が働きすぎるとタウたんぱく質の蓄積が進んでしまうが、新しい記憶を獲得することで酵素の働きを適度に抑えれば、記憶を保ったまま脳の老化を防ぐことができるとチームは見ている。木村さんは「老化がきっかけになるアルツハイマー病の発症も遅らせられるのでは」と話す。 米オンライン科学誌「プロス・ワン」に発表した。(平成20年11月30日 毎日新聞) 便秘薬の酸化マグネシウムで2人死亡 便秘や胃炎に広く使われている医療用医薬品「酸化マグネシウム」の服用が原因とみられる副作用報告が05年4月〜今年8月に15件あり、うち2人が死亡していたことが、厚生労働省のまとめで分かった。高齢者に長期間処方しているケースも多いことから、厚労省は血液中のマグネシウム濃度の測定など十分な観察をするよう、製薬会社に使用上の注意の改訂を指示した。酸化マグネシウムは腸の中に水分を引き寄せて腸の運動や排便を助ける効果があり、各製薬会社の推計使用者は年間延べ約4500万人に上る。15件の副作用は、服用が原因で意識障害や血圧低下などにつながった可能性が否定できないケースで、全員が入院。うち認知症などの病気を持ち、他の薬と併用して長期投与を受けていた80代の女性と70代の男性が、ショック症状などを起こし死亡した。15人中13人は、服用を半年以上続けていたとみられる。酸化マグネシウムは市販薬にもある。厚労省はこの成分を含む製品を副作用の危険が最も低い3類から、薬剤師らに情報提供の努力義務が課せられる2類に引き上げることを決めた。市販薬での副作用報告は今のところないという。(平成20年8月11日 毎日新聞) 認知症、予防に頭と体の「運動」が効果 有酸素運動と知的活動を続けるとお年寄りの脳機能がアップすることが、老人総合研究所の共同研究で確認された。認知症予防のため、国内で初めて長期的な追跡研究をしたという。調査は05〜07年度の3年間、世田谷区内の高齢者134人(平均年齢72歳)を対象に実施した。研究所が用意した予防プログラムを続けてもらった後、脳の認知機能を調べる検査をし、プログラムに参加しなかった高齢者254人と比較した。プログラムは、認知症の原因とされるたんぱく質を脳内にためないようにすることなどを目的に1日30分程度有酸素運動のウオーキングを続ける。同時に、パソコンを使ってミニコミ誌を作ったり、自ら料理メニューを考案して調理するなどの知的活動を週1回、続けてもらい、認知症で低下しがちな脳の機能を刺激した。その結果を3年前と比べたところ、記憶機能はプログラムに参加しなかった高齢者が13%の改善だったのに対し、参加者は22%も良くなった。集中力などの注意機能は、非参加者で3%低下したが、参加者は7%良くなった。言語機能は非参加者の9%に対し参加者は16%、思考機能は同じく0.2%に対して、4%良くなっていた。非参加でも改善するのは、同じ問題を複数回解くからで、参加者の向上が大きかった。同研究所の矢冨直美主任研究員は「認知症予防には、知的活動と運動を習慣化し、長期間続けることが必要」と分析しており、区は今回のプログラムの内容を冊子にまとめ、地域での認知症予防に役立てる方針だ。(平成20年11月29日 毎日新聞) リンパ節注射による花粉症の免疫療法に期待 リンパ節へアレルゲンを直接注射することで、従来に比べて短期間で苦痛が少なく、かつ安全性も高い花粉症治療が実現できる可能性がスイスを中心とした研究によって示された。チューリッヒ大学病院のThomasKundig博士は「リンパ節に直接アレルゲンを注入すると効果が著しく高まり、注入するアレルゲン用量を1000分の1未満に減らすことができ、アレルギー性の副作用も軽減できる」と述べている。著者らによると、西洋化した国々に暮らす人の35%以上がアレルギー性喘息であり、アレルギー注射(allergyshot、アレルゲン特異的免疫療法 [減感作療法] )と呼ばれる皮下脂肪組織への注射が標準的な治療法である。しかし、この方法では一般に3〜5年にわたり30〜70回の注射を受ける必要があり、時間がかかる上に、注射部位の腫れから全身的反応まで、アレルギー反応が引き起こされることも多く、「この治療を受けるのはアレルギー患者の5%に満たない」とKundig氏はいう。スイスおよび米国の研究チームは、リンパ節注射の有望性を試験するため、18〜65歳の約100人を対象に研究を実施した。被験者を2群に分け、一方には3年間にわたり54回の注射をする標準的な治療を行い、もう一方には8週間で3回のリンパ節注射を実施した。その結果、いずれの治療にも同等の効果がみられたが、リンパ節治療群は従来治療群に比べて痛みが少なく、副作用の頻度も低かった。鼻の検査によりくしゃみ、鼻汁、咳および息切れなどのアレルギー症状を評価した結果、Kundig氏らは、リンパ節治療が従来の注射に比べて短期間かつ安全な治療法であると結論付けている。また、リンパ節自体には神経がないため、リンパ節注射は採血よりも痛みが少ないとされ、患者のコンプライアンス(医療従事者の指示・アドバイスに従って行動すること)にも向上がみられたという。(平成20年11月20日 日本経済新聞) がん細胞を光らせて観察 光を当てると発光する酸化亜鉛の微粒子を使い、生きた組織内でがん細胞などの観察を可能にする新たな蛍光物質を、島根大の中村守彦教授らのチームが19日までに開発した。中村教授は「将来は検診の際に蛍光物質を投与し、画像装置でがん組織を見つけるなどの応用が可能になるかもしれない」と話している。チームは、直径約10ナノメートル(ナノは10億分の1)の酸化亜鉛の微粒子を合成し特殊な処理で蛍光物質としての性質を持たせた。これを生きた細胞に取り込ませることに成功。がん細胞の膜タンパク質にくっつく抗体に結合させれば、がん細胞だけを見分けることができるという。蛍光物質には、今年のノーベル化学賞の対象になったクラゲ由来の蛍光タンパク質や別の化合物もあるが、分子が大きすぎたり、毒性があったり、生体利用の面で欠点を抱えていた。中村教授は「粒子が小さく、細胞活動を邪魔しないのも強みだ」としている。(平成20年11月19日 中国新聞) HIV、国内感染者、累計で1万人超える 厚生労働省のエイズ動向委員会は、国内のHIV感染者が累計で1万人を超えたと発表した。厚労省は「先進諸国が横ばいの中で日本の感染率上昇は目立っており、啓発が遅れている」と警戒を強めている。厚労省によると、7〜9月に報告があった新規感染者は294人で、四半期ベースでは過去最多。血液製剤で感染した薬害被害者を除く感染者は累計で1万247人(男性8305人、女性1942人)に達した。85年の最初の感染報告から5000人突破までは17年かかったが、ここ数年でペースが急激に上がり、03年1月以降の5年9ヵ月で5107人の感染者が見つかった。(平成20年11月20日 毎日新聞) 夜間の人工透析で死亡率が大幅に低下 腎疾患患者の死亡リスクが、従来の1回4時間、週3回の透析治療に比べて、夜間に1回8時間の透析を週3回行うほうが大幅に減少することが示された。報告を行ったトルコ、エーゲ大学(イズミル)腎臓病学科Ercan Ok博士によると、透析技術や医療は向上しているものの、従来の3時間、週3回の透析治療を受ける患者の死亡率は依然として受け入れ難いほど高いという。透析は腎不全患者の水分除去措置としては最も一般的な方法で、入院、外来のいずれでも実施されるが、通常は何らかの医療機関で行われる。患者の多くは、週3回、1回3〜5時間の処置を受けている。今回の研究では、従来の方法から、週3回、夜間8時間の透析に切り替えたトルコ人患者224人(平均45歳)を追跡した。研究グループによると、患者が処置を受けながら眠れるようになるまでには、通常1ヵ月の「適応期間」を要したという。1年後、夜間治療群と、従来の週3回4時間の治療を継続した同様の患者群とを比較したところ、夜間治療群は死亡率が78%低かったほか、血圧管理に顕著な改善がみられ、降圧薬の使用が3分の2減少した。また、リン酸塩濃度が正常値まで低下し、リン酸塩吸収を抑える薬剤の使用が72%減少。さらに、食欲向上、望ましい体重増加および血中蛋白濃度の増大がみられたほか、患者の多くが仕事に復帰し、業績や精神状態も改善されたと報告している。「このデータによって、医師、患者、保健当局、社会保障機関など社会全体が長時間の透析の必要性について納得してくれると期待している」とOk氏は述べている。(平成20年11月13日 日本経済新聞) 自律神経失調症 首の凝りが影響 持続的なめまいや頭痛、体調不良などを訴える自律神経失調症患者に対し、首の筋肉の凝りを解消すると、9割以上の患者で症状が治まることを、東京脳神経センターの松井孝嘉理事長(脳神経外科)が日本自律神経学会で発表した。松井理事長は、長期に症状を訴える自律神経失調症の患者は、重い頭を支える首の筋肉に痛み、硬さなどの異常が多いことに着目。2006年〜08年5月にかけて同センターに自律神経失調症で入院した265人に対し、首の筋肉の異常をなくす治療を実施したところ、92.5%が1〜3か月で治癒した。治療は、痛みや異常が首のどこにあるか36ヵ所をチェック。それに基づいて低周波治療器、温熱療法、はり・きゅう、ビタミンB群投与などを組み合わせる。外来での治療も可能だ。松井理事長は「自律神経失調症は30〜40歳代の首の細くて長い、なで肩の女性に多い。長時間のパソコン作業などは首に負担がかかるので、15分おきに休むことが大切」と話している。(平成20年11月14日 読売新聞) 花粉症、3ヵ月で改善 花粉症などのアレルギー患者に原因物質を繰り返し注射する「減感作療法」を、3ヵ月で済ませることに、チューリヒ大学病院(スイス)などの研究チームが成功した。皮下でなく、そけい部のリンパ節に注射する方法で、副作用も従来の方法より少ないという。米科学アカデミー紀要電子版に発表された。減感作療法は通常、原因物質のエキスを少量ずつ、約3年かけて注射する。研究チームは、皮下注射したエキスが体内の免疫システムをつかさどるリンパ節へは一部しか達しないことに注目。58人の花粉症患者に対し、リンパ節へ直接、1ヵ月おきに計3回だけ注射する新手法を試してみた。開始から4ヵ月後に検査したところ、アレルギー症状が劇的に緩和され、治療前に比べ平均10倍の花粉量がないと鼻炎が起きなくなっていた。効果は開始から3年後も持続していた。従来の減感作療法を行った別の54人では、じんましんなどの軽い副作用が18件、入院の必要なぜんそくの副作用が2件起きた。新手法では、軽い副作用が6件起きただけだった。(平成20年11月11日 読売新聞) 大脳皮質、ヒトのES細胞から作成 脳組織の一部で、思考や運動などを担う「大脳皮質」を、さまざまな細胞に変化できるヒトのES細胞から作ることに、理化学研究所発生・再生科学総合研究センターの永楽元次研究員と笹井芳樹グループディレクターらが成功した。胎児の段階にあたる未発達な皮質だが、単独の脳細胞でなく、数種類の細胞が数多く組み合わさった脳組織を作ったのは世界で初めて。将来は、アルツハイマー病などの解明や薬の開発、脳梗塞の後遺症軽減などにつながる可能性があるという。永楽さんたちは、約3000個のES細胞を、直径約1センチのくぼみの中で培養液に浮かせ、細胞が自然に集まって固まりを作るようにした。必要な薬品を加えるなどすると、培養開始から46日で、中心が空洞の直径2ミリの球形組織ができた。できた組織は、4種類の神経細胞がそれぞれ層を作って重なった4層構造で、受精後7〜8週の胎児の大脳皮質とそっくりだった。神経細胞同士がネットワークを作り、各細胞が連動して同時に活動することも確かめた。成人の大脳皮質は6層構造。今回の皮質は、発達過程でいえば「40〜50%程度」の段階に相当すると考えられるという。(平成20年11月6日 毎日新聞) 「梅毒」増加傾向、30代男性と20代前半女性中心 性行為により感染する「梅毒」が、30歳代男性や20歳代前半の女性を中心に増加していることが、国立感染症研究所の調べで分かった。若い女性患者の増加に伴い、胎児に感染して死産や重い後遺症を引き起こす「先天梅毒」が年間5〜10人ほど報告されており、同研究所では、コンドームの使用による予防や妊婦健診の徹底を呼びかけている。梅毒は早期発見し、治療すれば治る。しかし、放置すると、発疹などの症状を経て、感染後3〜10年でゴムのような腫瘍や神経まひなどの症状が出て、死亡する。梅毒に感染した女性が妊娠すると、血液を通じて胎児に感染する「先天梅毒」を起こし、約4割の胎児が生まれずに亡くなる。同研究所によると、梅毒の患者は2003年から増加傾向となり、509人だった03年に比べ、07年は約1.4倍の737人に増えた。今年は9月28日現在で昨年同期より102人多い614人が報告されている。(平成20年10月24日 読売新聞) 子宮頸がん、新ワクチン開発 子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスの新たなワクチンを、国立感染症研究所などが開発した。日本人は欧米人と異なるウイルスの型での感染例が多いことも確認した。欧米などで使われているワクチンは一部の型しか効かないが、新ワクチンは日本人に幅広く有効となる可能性が高い。ウイルスは遺伝子の型の違いから約100種に分類され、このうち15種類に発がん性がある。 欧米では16型と18型が発症原因の約70%を占めるが、日本の患者では16型42%、18型7%と半数にとどまる。製薬企業が厚生労働省に16型と18型に対応したワクチンの承認を申請している。研究チームは15種類に共通する構造があることに注目。この構造を作るアミノ酸配列を特定し、その特徴からワクチンを開発した。ウサギに接種し16型と18型を含む6種類で感染防止を確認した。日本人の患者の76%が6種類による感染だったことも突き止めた。 日本では毎年1万2000人以上が発症。(平成20年10月19日 毎日新聞) 糖尿病なりかけに1日7杯の緑茶で血糖値改善 緑茶を1日に7杯分ほど飲むことで、糖尿病になりかかっている人たちの血糖値が改善することが、静岡県立大などの研究でわかった。健康な人で緑茶をよく飲んでいると糖尿病になりにくいという報告はあるが、高血糖の人たちの値が下がることを確認した報告は珍しいという。血糖値が高めで、糖尿病と診断される手前の「境界型」などに該当する会社員ら60人に協力してもらった。緑茶に含まれる渋み成分のカテキンの摂取量を一定にするため、いったんいれたお茶を乾燥させるなどして実験用の粉末を作製。これを毎日、湯に溶かして飲むグループと、飲まないグループに無作為に分け、2ヵ月後の血糖値を比べた。平均的な血糖値の変化を、「Hb(ヘモグロビン)A1c」という指標でみると、緑茶粉末を飲んだ人たちは当初の6.2%が、2ヵ月後に5.9%に下がった。飲まなかった人たちは変わらなかった。 飲まなかった人たちに改めて飲んでもらうと、同じように2ヵ月間で6.1%から5.9%に下がった。一般にHbA1cが6.1%以上だと糖尿病の疑いがあるとされ、6.5%以上だと糖尿病と即断される。逆に患者の血糖値を5.8%未満に維持できれば優れた管理とされる。今回の成果は、糖尿病一歩手前の人が緑茶をたくさん飲むことで、糖尿病にならずに済んだり、発症を遅らせたりできる可能性を示した。2グループで体格や摂取エネルギーなどに差はなく、緑茶からのカテキン摂取量が血糖値に影響したらしい。1日分の緑茶粉末は一般的な濃さの緑茶で湯飲み(約100ミリリットル)約5杯分のカテキンを含み、緑茶粉末を飲んだ人では普通に飲んだ緑茶と合わせ1日に約7杯分のカテキンをとっていた。(平成20年10月4日 朝日新聞) カルシウム+ビタミンD、大腸がんのリスク低減 カルシウムとビタミンDをともに多く摂取すると、大腸がんにかかるリスクを下げる可能性があることが、九州大などの調査でわかった。古野純典・九大教授らのグループが、福岡市とその近郊に住み、大腸がんと診断された836人と、同じ年代で大腸がんではない861人から食事や生活習慣を詳しくたずね、関連を調べた。1日あたりのカルシウム摂取量が平均約700ミリグラムと最多の人たちが大腸がんになるリスクは、同400ミリグラムで最も少ない人たちと比べ、3割ほど低かった。しかし、カルシウムを多くとっても、ビタミンDをあまりとらない人では、違いははっきりしなかった。そこで、カルシウムを平均約700ミリグラムとり、かつビタミンDを多くとる人(1日10マイクログラムかそれ以上)で比べると、大腸がんリスクは、カルシウム摂取が少なくビタミンDをあまりとらない人より、6割低かった。ビタミンDはサンマやサケといった魚類やキノコ類に多い。日本人のカルシウム摂取量は1日あたり平均540ミリグラム余で不足ぎみ。ビタミンDは8マイクログラムほど。大腸がんは肥満や飲酒でリスクが高まることがわかっている。牛乳を飲んでカルシウムを多くとると、大腸がんリスクが2割ほど下がることは、欧米グループが報告している。今回の結果をまとめた溝上哲也・国立国際医療センター部長は「ビタミンDはカルシウムの吸収を助けるので、大腸がんの予防効果を高めるのかも知れない。さらに効果を調べたい」と話す。(平成20年9月22日 朝日新聞) カプセル内視鏡の製造販売承認を取得 オリンパスメディカルシステムズは、口から飲み込んで使う小腸用のカプセル内視鏡システムで厚生労働省から製造販売承認を取得したと発表した。カプセル内視鏡の承認取得は2社目で、国産製品は初めて。オリンパスは国内市場が100億円規模に膨らむとみて、従来のチューブ型内視鏡とあわせ需要獲得を目指す。発売時期や価格は未定としている。カプセル内視鏡は外径11ミリメートルで長さ26ミリメートル。CCD(電荷結合素子)カメラや無線通信機能を内蔵し、胃や小腸のぜん動運動に乗って移動しながら1秒間に2枚ずつ撮影。画像は患者が装着した受信装置に順次送られる仕組み。8時間で約6万枚を撮った後、体外に排出される。(平成20年9月11日 日経産業新聞) 老人ホーム、無届け15% 都道府県に設置の届け出をしていない有料老人ホームが全体の約15%に上ることが、総務省の行政評価で分かった。都道府県が存在を把握していない施設も見つかり、実際の無届け施設はさらに多いとみられる。こうした施設には、行政による監視が十分に行き届かないおそれがあることから、総務省は、厚生労働省に改善を勧告する。有料老人ホームは、老人福祉法で都道府県への設置届け出が義務づけられている。総務省が22都道府県を選んで調べたところ、07年4月時点で都道府県が有料老人ホームとみなしている2345施設のうち、無届けは14都道府県の353施設。東京が80、埼玉が68、神奈川58、千葉47など都市部が大半だった。一方、総務省が施設のホームページや広告などを調べたところ、都道府県が把握していない有料老人ホームが17あることもわかった。届け出がないと、施設の規模や設備、職員の配置などの情報を把握できないため、都道府県の基準を満たしていなくてもそのまま放置することになりかねない。また、入居者の虐待など問題が起きた時も対応が遅れる恐れがあるという。有料老人ホームは「入居者が10人以上で、食事を提供している」との基準が06年4月に緩和され、入居者数に関係なく食事または介護、洗濯などのサービスを提供していれば有料老人ホームとみなされるようになった。こうした小規模施設を中心に、職員数や設備が基準に満たず、満たすには費用がかかるため、届け出ない例が多いとみられる。無届け施設を巡っては、06年に千葉県で入所者をベッドに拘束して虐待していた疑いが浮上したほか、前払いした入居金を退去時に返さないといった問題が相次いでいる。無届け施設が最多だった東京都の高齢社会対策部は「基準を満たすように施設を改善し、早急に届け出をするように継続的に指導する」としている。(平成20年9月5日 朝日新聞) 子宮体がん、「毎日コーヒー」で減 コーヒーを毎日1〜2杯飲む女性は、週に2日程度しか飲まない人に比べて、子宮体がんの発症率が4割少ないことが厚生労働省研究班の大規模調査で分かった。飲む量が多いほど、発症率は低い傾向がみられた。研究班は、9府県の40〜69歳の女性約5万4000人を05年まで追跡調査。約15年間に117人が子宮体がんを発症した。コーヒー摂取量と発症率との関係を調べると、コーヒーを毎日1〜2杯飲むグループは、週2日以下しか飲まないグループに比べ、子宮体がんの発症率は4割少なかった。毎日3杯以上飲むグループは6割も少なかった。緑茶の摂取量も調べたが、発症率に関連はみられなかった。子宮の入り口にできる子宮頸がんは、ウイルス感染が原因と考えられている。一方、子宮の奥の内膜にできる子宮体がんは、女性ホルモン「エストロゲン」や血糖値を調節する「インスリン」との関連が指摘されている。担当した国立がんセンター予防研究部の島津太一研究員は「コーヒーを飲むと、エストロゲンやインスリンの濃度が下がることが知られている。この作用が発症率に影響している可能性がある」と話す。欧米ではコーヒー摂取と子宮体がんの関連がみられないとの研究が多い。その理由として、ホルモン補充療法が日本より広く行われ、コーヒーの影響が表れにくいと考えられているという。(平成20年9月2日 毎日新聞) iPS細胞 ネズミの膵臓作製 新型万能細胞(iPS細胞)を利用して、マウスの体内で膵臓を作製することに、東京大医科学研究所の中内啓光教授らが成功した。研究が進んで、糖尿病患者のiPS細胞を作製し、動物の体内で膵臓を作らせることができれば、移植医療に使える可能性もある。実験では、膵臓の形成に必要な遺伝子を持たないマウスを使った。膵臓が欠損したこのマウスの受精卵を数日間培養。胚盤胞まで育った段階で、正常な遺伝子を持つマウスから作ったiPS細胞を注入した。その後、胚盤胞を代理母の子宮に移植し、誕生したマウスを調べたところ、膵臓が出来ていた。膵臓には、インスリンを分泌するベータ細胞も含まれ、血糖値を正常に保つ機能があることを確認した。注入したiPS細胞が、欠損するはずだった膵臓を補完したとみられる。研究チームは、別の万能細胞である胚性幹細胞(ES細胞)を使い、マウスの膵臓や腎臓を作ることにも成功している。今後、サルやブタで人間の臓器が作製できるか確かめる計画だ。動物の体内で移植用の臓器を作製する試みは、難病患者に福音となる可能性がある一方、未知の感染症に侵される恐れも指摘されている。(平成20年8月31日 読売新聞) イオンで鳥インフルウイルス破壊 シャープは空気清浄機などに採用している「プラズマクラスターイオン技術」について、密閉空間にイオンを高濃度で噴射することで、浮遊する鳥インフルエンザウイルスの大部分を破壊する効果があることを実証したと発表した。世界で流行する鳥インフルエンザは、新型インフルエンザに変異して人同士で感染し爆発的に流行する可能性が高いと指摘されている。同社は今後、一段と高濃度のイオンを発生させる空気清浄機などの商品開発を進める計画。新型インフルエンザ対策の一つとなることをアピールし、家庭のほか病院や自動車メーカー、航空会社などへの販売拡大を目指す。実証実験は、ロンドン大のジョン・オックスフォード教授らと共同で、現在実用化されている製品と比べて7倍強の高濃度の酸素イオンと水素イオンを発生させて実施。10分間噴射することで、空間内のウイルスが 99.9%減少したという。プラズマクラスターイオン技術は、空気中に放出したイオンがウイルスを包み込んで分解、除去する技術。(平成20年8月27日 中国新聞) 親知らずからiPS細胞 「親知らず」の歯の細胞から、様々な細胞に変化する新型万能細胞(iPS細胞)を作製することに、産業技術総合研究所の大串始・主幹研究員らが成功した。東京大学で21日開かれたシンポジウムで発表した。歯科医院などで抜いた親知らずを集めてiPS細胞の種類を増やせば、拒絶反応のない再生医療への応用が近づくと期待される。大串研究員らは、日本人の女児(10)から抜いた親知らずの歯の細胞に、世界で初めてiPS細胞を作った京都大の山中伸弥教授が用いた3種類の遺伝子を組み入れた。約35日間培養したところ、高い増殖能力を持つiPS細胞が出現。 様々な種類の細胞に変化できる能力も確認した。(平成20年8月日22 読売新聞) ランニング、老化防ぐ ランニングの習慣に老化を遅らせる顕著な効果があることを米スタンフォード大の研究チームが突き止めた。 20年以上にわたる追跡調査の結論という。調査期間は、1984年から2005年まで。チームは、ランニングクラブに所属し、週4回程度走る男女538人(84年当時の平均年齢58歳)に毎年質問票を送り、歩行や着替えといった日常の行動能力や健康状態などを調査。走る習慣がない健康な男女423人(同62歳)も同様の方法で調べ、比較した。 その結果、走る習慣のないグループは、2003年までに34%が死亡したのに対し、習慣的に走るグループの死者は15%にとどまった。また、走るグループは、走る習慣のないグループに比べ、日常の行動能力が衰え始める時期が16年ほど遅かった。チームは「年齢を重ねても健康的に過ごすために何かひとつ選ぶとすれば、(ランニングのような)有酸素運動が最も適している」と結論づけている。(平成20年8月16日 読売新聞) 胃がん、大動脈リンパ切除は無益 標準的な胃がん手術で行われるリンパ節切除に加え、大動脈周辺のリンパ節まで切除する拡大手術を行っても、患者の生存率がほとんど向上しないとする臨床試験結果を、国内のがん臨床医グループが7日までにまとめ、米医学誌ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに発表した。国内では進行性の胃がんの患部と、転移の恐れがある胃の周辺や胃につながる血管周辺のリンパ節を切除する手術が標準。場合によって大動脈周辺まで切除範囲を広げることもあるが、こうした手術は無益との証拠が示された形だ。この結果を受け日本胃癌学会も治療ガイドラインを改訂した。研究代表者の笹子三津留兵庫医大教授は「今後は手術に伴う無益な患者の負担を避けるようになるだろう」と話している。グループは1995−2001年、全国24病院で胃がん患者523人の同意を得て臨床試験を実施。標準的な手術を受けた患者と、加えて大動脈周辺のリンパ節切除を受けた患者の5年後の生存率を比べると、前者が69.2%、後者が70.3%と変わらなかった。再発の度合いにも目立った差はなかった。(平成20年8月7日 中国新聞) ビタミンC投与でがん半減 ビタミンCをマウスに大量投与することで、がん細胞の増殖を半分に抑えることができたとの実験結果を、米国立衛生研究所(NIH)の研究チームが4日、米科学アカデミー紀要(電子版)に発表した。実験ではまず、43種類のがん細胞と5種類の通常細胞に、ビタミンC(アスコルビン酸)の溶液を加えると、通常細胞に変化はなかったが、がん細胞のうち33種類では細胞の半分以上が死滅した。次に、腹腔内にそれぞれ子宮がん、膵臓がん、脳腫瘍の細胞を植え付けたマウスに、体重1キロ当たり4グラムという大量のアスコルビン酸を毎日投与すると12−30日後に、投与しなかった場合に比べてがんの重さが41−53%に抑えられた。副作用もみられなかった。アスコルビン酸から発生した過酸化水素ががん細胞に作用したとみられるという。(平成20年8月5日 産経新聞) 難病患者からiPS細胞作製 高齢の神経難病患者の皮膚細胞からまず万能細胞(iPS細胞)を作製し、運動神経などの細胞まで作り出すことに、米ハーバード大のケビン・エガン准教授とコロンビア大の研究チームが成功した。健康な人の細胞から万能細胞を作った報告例はすでにあるが、患者の細胞を利用して万能細胞を作り出したとする論文は初めてという。病態の解明に大いに役立ちそうだ。患者は82歳と89歳の姉妹。運動神経が侵される遺伝性の筋萎縮(いしゅく)性側索硬化症(ALS)で、進行すると食べ物をのみ込んだり、手足を動かしたりしにくくなる。高齢者で遺伝子異常などを抱える患者の体細胞からでも、健康な人と同様に万能細胞ができるかどうか、そこから神経などの細胞を作製できるかは焦点の一つだった。エガン准教授らは、京都大の山中伸弥教授が開発した四つの遺伝子を皮膚細胞に組み込む方法を使って、iPS細胞を作製。さらに、受精卵から作る万能細胞(ES細胞)で開発された方法を使うことで、患者の遺伝情報を持つ運動神経(ニューロン)と中枢神経系のグリア細胞といった体細胞にまで分化させることに成功した。ALSは、発症の仕組みが分からず、まだ有効な治療法もない。これまで、病態解明や治療法の開発については、マウスやサルなどでの実験に頼らざるをえなかった。今回作製したiPS細胞は、治療法開発を視野に入れた病気の発症メカニズム解明につながる可能性がある。(平成20年8月4日 朝日新聞) 平均寿命更新、女性85.99歳・男性79.19歳 厚生労働省は2007年の日本人の平均寿命が女性85.99歳、男性79.19歳と、過去最高を更新したと発表した。女性は23年連続で長寿世界一。 前年に比べると、女性は0.18歳、男性は 0.19歳のびた。男女差は6.80歳で、前年より0.01歳縮まった。国際的に見ると、女性では、日本に次いで長寿なのは香港の85.4歳で、第3位がフランスで84.1歳だった。男性の長寿世界一はアイスランドの79.4歳で、次いで香港の79.3歳、第3位が日本だった。0歳児が将来どのような死因で死亡するかを予測する「死因別死亡確率」も公表した。男女ともに、がん、心疾患、脳血管疾患の3大死因による亡が50%を超えており、男性55.57%、女性53.02%だった。(平成20年8月1日 読売新聞) ピロリ除菌で胃がん3分の1 胃の粘膜にいる細菌ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)を薬で除菌すると、胃がん発生が3分の1になるとの研究結果を浅香正博・北海道大教授(消化器内科)らがまとめた。2日付の英医学誌ランセットで発表する。 胃がん予防目的の除菌は現在、公的医療保険の適用外。適用に向けた議論が活発化しそうだ。研究は国内51病院で実施。早期胃がん患者505人の協力を得た。内視鏡で治療した後、半分の患者に除菌の薬を飲んでもらった。半分は除菌しなかった。治療したがん以外の胃がん(2次胃がん)ができるか調べた。3年間に2次胃がんができたのは、除菌した群で9人、除菌しない群で24人。詳しく計算すると胃がんリスクは、除菌しない場合を1とすると、除菌した場合は0.34だった。効果が明らかだったため、除菌しなかった群も後ほど除菌した。これまで、除菌で「前がん状態」が改善したなどの研究結果はあったが、除菌するか否かの割り当てをくじ引きで決める「無作為化比較研究」で除菌による胃がん予防効果を示したのは世界初。初発の胃がん減少も期待できる。国内の胃がん新規患者は年約11万人、死亡は約5万人。富永祐民・愛知県がんセンター名誉総長(疫学)によると「胃がんの8割以上はピロリ菌感染が原因と考えられる」。感染率は若い世代は低いが、50歳以上は7〜8割。団塊世代ががんを発症しやすい年代に近づき、患者は増える可能性が高い。浅香教授は「除菌で胃がん発生を大幅に減らせる」と、現在は、胃潰瘍(かいよう)か十二指腸潰瘍の患者に限られている除菌の保険適用を、ピロリ菌感染者全体に広げ、胃がん予防に役立てるべきだとしている。保険適用外だと薬代と検査代で1万数千〜2万円ほど。日本ヘリコバクター学会も今回の研究結果をもとに今秋、指針を改訂し、除菌を勧める予定だ。(平成20年8月1日 朝日新聞) タミフルの異常行動 インフルエンザ治療薬「タミフル」について、厚生労働省の研究班が7月に発表した解析は誤りだとの指摘が医師たちから相次いでいる。班は「タミフルを飲んだ患者は異常行動を起こす率が飲まない患者より約1割低い」との解析結果を示したが、指摘によると「飲だ患者の方が約5割高い」のが正しい結果という。指摘しているのは、津田敏秀・岡山大教授、粂和彦・熊本大准教授、浜六郎・医薬ビジラスセンター理事長ら。調査は06年12月〜07年3月、インフルエンザで医療機関を受診した患者約1万人を対象に実施。班は「タミフル使用者」7487人のうち服用後に異常行動を起こした人を889人(11.9%)と計算。一方で「非使用者」2228人のうち、異常行動は 286人(12.8%)だったとした。しかし「非使用者」のうち99人は、実際はタミフルを飲んだが、飲む以前に異常行動を起こした患者。全く飲まなかった患者だけの人数は2129人で、異常行動は187人(8.8%)だった。(平成20年7月31日 毎日新聞) 新型インフルの被害想定 厚生労働省の新型インフルエンザ専門家会議は、東京都内で会合を開き、国内で大流行した場合の犠牲者を最大64万人としている現行の被害想定を、より高く見積もる方向で再評価することを決めた。被害想定は、治療薬の備蓄や病床数など国や都道府県の対策の根拠となるため、影響は多分野に及びそうだ。現行の想定は米国の推計モデルに基づき、発症率を人口の25%に設定。1918年に流行したスペイン風邪の致死率(2%)を参考に、最悪の場合の死者を64万人、入院200万人、病院受診2500万人と見積もっている。(平成20年7月31日 読売新聞) 新型万能細胞の研究推進へ4拠点支援 文部科学省は新型万能細胞(iPS細胞)による再生医療研究について、今後の推進方策を明らかにした。研究者の新規参入を促すため、京都大学や理化学研究所など主要な4拠点が、細胞の成長や培養の技術指導を始める。iPS細胞は神経や筋肉など様々な組織に成長でき、失われた体の機能を取り戻す再生医療の切り札と期待される。京大の山中伸弥教授が作製に成功した後、世界的に競争が激しくなっており、日本も研究者層の拡大が急務となっていた。09年度に京大、理研、慶応義塾大学、東京大学による新組織「iPS細胞技術プラットフォーム」を設ける。同プラットフォームは、細胞技術の講習会を開くなどして研究者のすそ野拡大を目指す。また難病患者の細胞からiPS細胞を作り関連の研究機関に提供したり、研究成果の比較がしやすいようにiPS細胞の標準化を進めたりする。(平成20年7月31日 日本経済新聞) 脳卒中、発症3割減 乳製品からカルシウム摂取 牛乳やチーズなどの乳製品からカルシウムを多く取る人は、ほとんど取らない人に比べて脳卒中の発症率が約3割少ないことが、厚生労働省研究班の大規模調査で明らかになった。日本人の死因3位の脳卒中予防につながる成果で、牛乳なら1日130ミリリットル前後、スライスチーズら1〜1.5枚で効果が期待できるという。研究班は、岩手、秋田、長野、沖縄の4県在住の40〜59歳の男女約4万人を、90年から12年間追跡し、食事など生活習慣と発病の関係を分析した。02年までに、1321人が脳卒中を発症。乳製品から取ったカルシウムの量で5グループに分けると、1日の摂取量が平均116ミリグラムと最も多いグループは、ほぼゼロのグループに比べて脳卒中の発症率が0.69倍にとどまった。大豆製品や野菜、魚など、乳製品以外から摂取した カルシウムでは、効果はみられなかった。研究班の磯博康・大阪大教授は「カルシウム摂取が多いと血圧が低くなるため、脳卒中予防につながったのではないか。乳製品は他の食品よりも腸での吸収率が数倍高く、効率良くカルシウムが取れたようだ」と説明する。一方、心筋こうそくなど心疾患の発症率は、カルシウム摂取の有無と関連がなかった。乳製品に多く含まれる飽和脂肪酸によって心疾患の発症率が高まり、カルシウムの効果が打ち消された結果と考えられ、乳製品の食べすぎは逆効果になる可能性が高い。また、サプリメントのカルシウムの効果は不明という。(平成20年7月29日 毎日新聞) たんぱく質を変化させインフルエンザ抑制 インフルエンザウイルスの増殖を抑えるのに重要なたんぱく質の立体構造を、横浜市大などの研究グループが突き止めた。ウイルス内にあるたんぱく質のアミノ酸を1ヵ所変えるだけで、増殖効率が大きく抑えられることも分かり、流行が懸念されている新型インフルエンザの治療薬開発につながる発見として注目されそうだ。このたんぱく質は、新型インフルエンザの最有力候補とされるH5N1型の鳥インフルエンザでも、ほぼ共通の構造をしていると考えられている。(平成20年7月28日 読売新聞) トランス脂肪酸の使用禁止 米カリフォルニア州は、トランス脂肪酸を含む食品を州内の飲食店から追放する州法案に署名し、同法が成立した。トランス脂肪酸は心疾患や脳卒中のリスクを高める恐れがあり、ニューヨーク市などが事実上禁止しているが、州レベルでは初めて。トランス脂肪酸は、植物油などを加工するときに主に生じる物質。マーガリンや揚げ物の油、菓子やパンづくりに使われるショートニングなどに含まれる。今回の州法により、同州内の飲食店は10年以降、トランス脂肪酸の削減を進め、ゼロにすることが義務付けられる。11年には、トランス脂肪酸を焼き菓子やパンなどに使うことも禁止される。トランス脂肪酸を取りすぎると血液中の悪玉コレステロール(LDL)が増えて、動脈硬化や心疾患の危険性が増す。米国では大手ファストフードチェーンが、トランス脂肪酸ゼロの食品を増やしている。日本でも低減の動きがあるが、日本人の摂取量は米国人より少ないという。(平成20年7月26日 朝日新聞) 日本脳炎、予防接種は「必要」 副作用の恐れからワクチンの接種を受ける率が激減している日本脳炎について、厚生労働省の検討会は「今後も予防接種は必要」との見解をまとめた。日本脳炎は予防接種法の対象疾病に指定され、13歳までに計4回のワクチン接種を受けるのが望ましいとされる。しかし05年に重い副作用例が報告され、接種を休止する自治体が相次いだ。一方、日本脳炎ウイルスは、西日本を中心に抗体検査陽性の豚が確認されており、このまま免疫を持つ子供が減ると、年間数人に抑えられている感染者が増える危険もある。検討会ではワクチンの供給状況を見ながら、接種対象を検討していく必要があるとの意見で一致した。(平成20年7月26日 毎日新聞) 女性医師の半数、離職経験 出産・育児との両立困難 女性医師の半数以上が、出産・育児などを理由に常勤を辞めた経験のあることが、東京医大の泉美貴准教授らの調査でわかった。辞めた時期は「卒業後10年以内」が86%に達し、常勤医として復職したのは3割にとどまる。医師不足対策の観点からも女性医師支援が必要となりそうだ。調査では、同大(新宿区)と川崎医大(岡山県倉敷市)を卒業した全女性計1423人にアンケートを送付。50%にあたる711人から回答を得た。そのうち、常勤医を辞めた経験があるのは55%。 理由は妊娠・出産が55%でトップ。育児(37%)、労働条件(33%)が次いだ。背景には24時間呼び出しがある働き方や、不規則勤務に対応した保育施設のないことを挙げる人が多かった。 辞めた時は卒後10年以内が86%。25〜29歳だった人が44%と最も多く、30〜34歳が42%だった。当時の勤め先は、6割が大学病院だった。辞めた人の86%は「子どもがいても仕事を続けるべきだ」と労働意欲は高い。一方、常勤医として復職したのは33%、非常勤が60%。5%は復職していなかった。「若い医師は当直回数なども多く、育児を理由に短時間勤務を求めると同僚に迷惑がかかる、と辞める人が多い」と泉さん。自身は39歳で病理診断部の講師だった6年前、東京医大で初めて1年間の育児休暇を取得した。「経験を積んだ後だから取れた側面もある。女性医師の離職を防ぐには、若い時期も仕事と育児と両立できる環境づくりが必要だ」と話す。(平成20年7月26日 朝日新聞) 温暖化で「腎臓結石の患者増」 地球温暖化で、腎臓結石の患者が増え、医療費がいまより25%、年間1千億円も余計にかかるとの推計を、米テキサス大が明らかにした。研究チームは「温暖化による健康への影響としては、マラリア流行のリスクり大きい」と指摘している。米科学アカデミー紀要に発表された。腎臓結石は、気温の上昇で、体の水分を大量に失って尿の濃度が上がり、カルシウムやシュウ酸などが腎臓の中で固まって発症する。日本では成人男性の11人に1人、女性の26人に1人がかかるといわれる。米国では、寒冷な北西部より暖かい南東部の方が発症する人が多い。米国の平均気温は、76〜80年に対して88〜94年が0.5度高くなる一方、腎臓結石患者の伸び率は3.6%から5.2%に増え、温暖化との関連を示した。研究チームは国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第4次報告書にもとづき、2050年に平均気温が4度上昇すると仮定。すると米国では腎臓結石にかかりやすい「危険地帯」に住む国民の割合が00年には40%だったのが、50年には56%に増え、新たに160万〜220万人の患者が生まれるとの結果が出た。研究チームは「米国だけでなく他国も同様の影響を受ける。途上国では相当な影響があるだろう」としている。(平成20年7月22日 朝日新聞) 「せっかち」「怒りっぽい」男性、心臓病リスク低い 自分の性格を「せっかち」「怒りっぽい」などと考えている日本人男性ほど、心筋梗塞になるリスクが低くなる。こんな疫学調査の結果を厚生労働省研究班がまとめた。欧米の研究では、せっかちで怒りっぽい人ほど心筋梗塞リスクが高くなることが知られている。今回の研究はその定説を覆すもので、研究班は「感情の表し方が文化によって異なることが影響しているのではないか」と分析している。大阪大学の磯博康教授が、40―69歳の男女8万6000人を対象に平均で11年半、追跡した。アンケートをもとに行動パターンで4グループに分け、心筋梗塞リスクとの関連を調べた。期間中に669人が心筋梗塞など虚血性心疾患を発症した。(平成20年7月18日 日本経済新聞) はしか予防「夏休み中に」 中1・高3で接種率3割 若年層でのはしか流行を防ぐため、今年度から新たに予防接種対象となった中学1年、高校3年世代の接種率が3割程度と伸び悩んでいる。親が病院に連れていく幼児と異なり、クラブ活動などの合間を縫っての接種となることや、周知不足が背景にあるようで、厚生労働省は文部科学省に協力を要請、学校での個別指導も依頼。専門家は「せめて夏休み中に接種して」と呼び掛けている。厚労省結核感染症課によると、現時点での正確な接種率データはないが「ワクチンメーカーの出荷数から推計すると、中1、高3生の接種率は最大でも3割程度」にとどまっているという。(平成20年7月18日 日本経済新聞) がんワクチン臨床研究、6割に効果 膵臓・大腸がんなど 膵臓がんなどを対象に全国10ヵ所以上の大学病院で行われている、がんワクチン臨床研究の中間的な解析が明らかになった。従来の治療が効かなかった患者約80人の6割強で、がんの縮小や、一定期間悪化しないなどの効果があった。対象は食道がん、膵臓がん、大腸がん、膀胱がんなど10種以上で、国内過去最大規模。研究を重ね、新薬の承認申請を目指した治験に入る。 がんワクチンを注射した82人について解析。進行・再発で標準的な治療法が無効だった大腸がんで、27人中15人にがんの縮小やそれ以上進行しない効果があった。膀胱がんでは6人中3人でがんの縮小が認められた。膵臓がんでは抗がん剤との併用で利用したが、患者27人中18人で何らかの効果がみられた。82人の経過をみると50人でがんの縮小や、進行しない効果が認められた。注射した部分が腫れたり硬くなったりする副作用はあったが、重い副作用はなかったという。がんワクチンは、がんに対する免疫反応を特に強め、やっつけるのが狙い。中村教授らが人の全遺伝情報を調べ、がん細胞で活動しながら、正常細胞ではほとんど働いていない遺伝子をみつけた。その中から強い免疫反応を引き起こす17の抗原を特定し、複数のがんワクチンを作った。がんワクチンは副作用が少なく通院治療ができるうえ、最近の抗がん剤より費用が低いと期待されている。開発は米国などが先行し、前立腺がんでは年内にも承認される見通し。(平成20年7月16日 朝日新聞) 輸入化粧クリームからステロイド 国民生活センターは16日、「ステロイドは含まない」と表示された輸入化粧クリームから、医薬品並みの濃度のステロイド成分が検出されたと発表した。連絡を受けた東京都は同日、薬事法違反にあたるとして、業者に製品の販売中止と回収を指示した。米国企業が製造、「ラバンナ」が輸入した「NOATOクリーム」で、保湿効果などをうたい通信・店頭販売されていた。6月下旬以降「6ヵ月の娘に使った。塗ってない場所の炎症まで治ったが、やめると元に戻り、塗った部分が白くまだらになった」などの相談が8件相次いだ。調べると、ステロイドの一種で最も強い塗り薬に使われるプロピオン酸クロベタゾールが検出された。このステロイドには皮膚萎縮(いしゅく)などの副作用や依存性、使用中止後にかえって症状が悪化するなどの恐れがあり、センターは「使っている場合はすぐに皮膚科医に相談してほしい」と呼びかけている。ラバンナは「ステロイドは一切含まれていない」などと宣伝していた。(平成20年7月16日 朝日新聞) ベータカロテン不足で胃がんリスク2倍に 厚生労働省研究班は、ニンジンやカボチャといった緑黄色野菜に多く含まれる「ベータカロテン」が足りないと胃がんにかかるリスクが約2倍になるとの疫学研究結果を発表した。男性の方が女性よりも不足しがちで、「喫煙や飲酒の習慣がある人は、野菜や果物を積極的に取るようにしてほしい」としている。全国の40―69歳の男女約3万7000人を対象に、10年前後の追跡期間中に胃がんにかかった511人と、そうでない511人を比較分析した。調査開始時の血中ベータカロテン濃度をもとに4グループに分け、胃がんの発症リスクとの関連を調べた。ベータカロテン濃度が最も低いグループは、ほかの3グループと比べ胃がんリスクが約2倍だった。必要量を満たしていれば、多く取っても胃がんリスクは下がらないことも分かった。(平成20年7月17日 日本経済新聞) ひざ関節症の原因遺伝子発見 理化学研究所は、ひざや手の関節に痛みを伴う変形性関節症の原因遺伝子の特定に成功した。この遺伝子が作るたんぱく質と、細胞の構造を支える別のたんぱく質との結合が弱まり、発症につながることが分かった。同関節症の新薬開発に役立つ可能性があるという。日本人のゲノム(全遺伝情報)にある塩基配列の個人差と変形性関節症との関係を調べ、発症に深く関与する未知の遺伝子「DVWA」を突き止めた。この遺伝子が特定の型の場合、日本人では発症リスクが約1.6倍になるという。(平成20年7月12日 日本経済新聞) よく動く人、がん遠ざける 仕事か余暇かにかかわらず体をよく動かす人は、そうでない人より、がんになりにくいことが厚生労働省研究班の調査で明らかになりった。男性は大腸、肝臓、膵臓のがんで、女性では胃がんでそうした傾向が目立った。詳しい原因は解明されていないが、研究班は、運動で肥満が改善されたり、免疫機能が高まったりすることなどが関係しているのではないか、と推測している。調査は、岩手から沖縄まで9府県の45−74歳の男女約8万人を約8年にわたり追跡。期間中に約4300人が何らかのがんにかかった。激しいスポーツをした時間や、歩いたり立ったりした時間、睡眠時間などをアンケートし、対象者の平均身体活動量を算出。その量の多さによって4グループに分け、がんとの関連を分析した。その結果、身体活動量が最多のグループは最少グループに比べ、がんになるリスクが男性で13%、女性で16%低かった。(平成20年7月13日 中国新聞) タミフル、「異常行動と関連検出できず」 インフルエンザ治療薬タミフルを服用した子どもに、飛び降りなどの異常行動が相次いで報告された問題で、厚生労働省の作業部会は「タミフルと異常行動との関連は検出できなかった」とする最終的な見解をまとめた。10代へのタミフル使用を原則中止している現行措置を見直す可能性がさらに強まった。ただし、今回報告された大規模疫学調査では、一部結果の精度に問題があり、追加調査が望ましいとした。作業部会には、インフルエンザと診断された17歳以下の患者9715人を対象にした大規模疫学調査と、何らかの異常行動があった患者ら597人を対象にした調査の結果が報告された。いずれもタミフルと異常行動との因果関係を示す結果は得られなかった。タミフルを巡っては、服用した子どもが建物から転落するなどして死傷する事例が続発し、厚労省は昨年3月、10代へのタミフル使用の原則中止を決定した。昨年10月から今年3月までに、タミフル服用後の新たな異常行動が31人報告され、ほかに3人が死亡している。また、作業部会では、抗インフルエンザ薬「リレンザ」でも新たに47人の異常行動が報告された。(平成20年7月11日 読売新聞) 後発薬品の品質検証へ 厚生労働省は、特許切れの有効成分を使って従来品とは別のメーカーが製造する「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」について、新たな品質検証の仕組みを導入する。従来品に劣ると指摘する研究論文を、複数の研究者による検討会で精査し、後発医薬品に問題がないかを判断する。製薬企業側に不適切なデータ取得などの不正が見つかれば、承認取り消しも視野に厳正に処分し、医療現場に広がる後発医薬品に対する不信感の一掃を狙う。後発医薬品は従来品と同じ有効成分を使うが、着色料などの添加物が違うため、品質を疑う医師や薬剤師が多い。一部の薬に対しては、「不純物が混ざっている」「効かない」などと批判する論文や症例報告も出ており、後発医薬品が市場で半分を占める米英に比べ、日本では17%(2006年度)と低迷している。厚労省は、現場の不安を解消するために、厚労省の承認審査に加えて、第三者による検証が必要と判断した。(平成20年7月9日 読売新聞) がん予防、運動が効果 こまめに体を動かしている人ほど、がんにかかりにくいことが厚生労働省研究班の大規模疫学調査でた。男性の場合、がんのリスクが最大13%、女性は同16%低かった。特に消化器系のがんは体を動かすことによる予防効果が期待できるという。研究班の井上真奈美・国立がんセンター室長が、全国の45―74歳の男女約8万人を対象に約8年にわたって追跡調査した。アンケートをもとに、通勤や仕事などで1日に体を動かしている量を算出して男女別に4グループに分類。がんになるリスクとの関係を調べた。期間中に約4300人が何らかのがんと診断された。 身体活動量の算出には「メッツ時」という単位を使った。例えば筋肉労働や激しいスポーツは4.5メッツで、1時間続けたときの活動量が4.5メッツ時になる。歩いたり立ったりしているときは2メッツ。(平成20年7月10日 日本経済新聞) 心筋梗塞、15年で2倍 都市部の中高年男性 都市部の働き盛りの男性で、心筋梗塞の発生率が80年代末からの約15年間で、2倍以上に増えたことが、大阪府立健康科学センターの疫学調査で分かった。都市部の女性や農村部の男女に増加傾向はなかった。心筋梗塞はストレスのかかる管理職に多い病気とされるが、都市部で広く中高年男性に増えている実態が浮き彫りになった。性別や居住地に応じた健康対策が求められそうだ。人口や産業形態などから都市部の代表に大阪府八尾市の一地区、農村部の代表に秋田県井川町を選び、64〜03年の40年間の住民延べ約16万人の健診データを解析した。その結果、都市部の中高年(40〜69歳)の男性で心筋梗塞を発症したのは、88〜95年の8年間で人口10万人当たり56人だったのに対し、96〜03年の8年間では2.3倍の同127人だった。この間に、心筋梗塞の危険因子の喫煙率は地域や性別などに関係なく横ばいまたは減少している。しかし、都市部の中高年男性では、別の危険因子である総コレステロール値や肥満度の目安の体格指数(BMI)が5〜7%悪化し、発症の危険性が高くなっていた。センターの北村明彦医師(循環器疫学)は「外食を取る機会の多い都市部の中高年男性は食環境の欧米化に伴い、脂肪分や高カロリーの食材を取りやすい。労働環境が厳しくなり、ストレスも高まっている」と話す。(平成20年7月6日 毎日新聞) 認知症、2035年には2倍の445万人に 全国の認知症高齢者の人数は05年の約205万人から、2035年には2.2倍にあたる約445万人になる、と厚生労働省研究班が推計を出した。増加は、埼玉県の3.1倍を筆頭に首都圏で大きく、愛知県や大阪府などでも2.5倍を超える見通しだ。在宅や病院、特別養護老人ホームなどを対象に80年代、認知症をもつ高齢者の割合を調べた実態調査を使い、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口から算定した。推計では、団塊の世代がすべて65歳以上となる2015年時点ですでに、05年の1.5倍の約302万人に上る。主な増加要因は高齢化という。ただ、算定に使った80年代調査は当時の知見から、認知症とされた人はアルツハイマー型や脳卒中後の重症患者に限られていた。その後、診断技術が向上したほか、認知症の原因となる別の病気がみつかり診断基準が明確になっている。これらを考慮すると、今回の推計より患者数は増える可能性がある。また、現在は認知症に進む前段階の「軽度認知機能障害」も診断・治療できるため、対応が必要な高齢者はさらに増えそうだ。(平成20年7月6日 朝日新聞) 高血圧死の危険、40代男性突出 厚労省が18万人調査 高血圧の40代男性が死亡する危険性は、正常な血圧の人の3.4倍に上ることが、全国13の研究グループの調査を統合した厚生労働省研究班の初めての解析でわかった。高齢男性では1.5倍前後なのと比べてはるかに高く、「高血圧は中年ほど要注意」という傾向が出た。対象は40〜90歳の男性約6万5千人、女性約11万人で、同種の国内調査では過去最大規模。70〜90年代に血圧など健康状態をみて、その後約10年追跡したところ、男性約1万人、女性約8千人が死亡。血圧と死亡の関係を調べた。高血圧と関係が深い脳血管の病気がある人は除いた。その結果、収縮期血圧120未満/拡張期血圧80未満と正常な人たちに比べ、160以上/100以上の高血圧の人たちが死亡するリスクは、男性で40代が3.4倍、50代2.2倍、60代で1.8倍、70代で1.6倍、80代で1.3倍だった。女性は40代で1.4倍、50代1.9倍、60代2.1倍、70代1.5倍、80代1.2倍。男性では若い世代ほど危険性が高くなる傾向が際だった。これらの人がもし正常血圧であれば、全体の死亡者は男性で23%、女性で18%減る計算という。140以上/90以上と軽症の高血圧でも、危険性が高まることが確認された。高血圧は塩分の多い食事や肥満、飲酒、ストレスが招きやすく、働く世代の生活習慣と関係が深い。(平成20年7月5日 朝日新聞) スイカにバイアグラ効果? 夏の味覚スイカに、性的不能治療薬「バイアグラ」に似た効果のある成分が含まれていると、米テキサスA&M大学の野菜果物改良研究所が発表した。スイカの成分「シトルリン」が体内で酵素の働きによってアルギニンというアミノ酸になり、バイアグラの主成分と同様、酸化窒素を活性化し血管を拡張、血流量を増やすという。ビム・パティル所長は「バイアグラと基本的に同じ効果だ。局所的に効くのではないかもしれないが、副作用はない」と指摘している。米農務省の研究者は「研究内容は正しいが、体内のアルギニン濃度を上げるには6切れも食べなければならない。スイカには利尿作用もあり、頻繁にトイレに行くことになるだろう」と述べている。同研究所によると、シトルリンは果実よりも皮に高濃度に含まれ、果実に多く含まれるように品種改良に取り組んでいるという。(平成20年7月4日 中国新聞) コレステロール、「悪玉」成分解明 「悪玉」と呼ばれるLDLコレステロールのうち、動脈硬化を促進するのは成分の一つの「酸化LDL」であることを、東北大の片桐秀樹教授らがマウスの実験で確かめた。酸化LDLはLDLコレステロールが酸化したもので、LDLコレステロール全体の中のごくわずかな成分。片桐教授らは、高LDLコレステロール血症のマウスの肝臓に酸化LDLを蓄積させる遺伝子を導入。血液中のLDLコレステロール全体の量はほとんど減らさずに、酸化LDLだけを3分の1程度に下げた状態を作り出した。4週間後、普通の高LDLコレステロール血症マウスは全身の動脈硬化の病変部分が実験前より約4割増加。一方、酸化LDLだけを減らしたマウスは動脈硬化がまったく悪化しなかった。また動脈硬化促進物質の過酸化脂質などの血中濃度も減少した。LDLコレステロールは細胞膜の材料などになる物質もあり、薬でLDLコレステロール全体を下げ過ぎることを懸念する専門家もいる。片桐教授は「酸化LDLだけを減少させる治療法が開発できれば、安全に動脈硬化の進行を抑制し、心筋梗塞の発症予防ができるようになる可能性がある」と話している。(平成20年7月2日 毎日新聞) 糖尿病治療に「適度な空腹」必要 生活習慣がおもな原因とされる2型糖尿病を治すには、適度な空腹が必要であることが、発症にかかわるたんぱく質の働きの解明から裏付けられた。東京大学などの研究チームによるマウスの実験で、このたんぱく質は空腹が続くと増え、血糖値を下げるインスリンの働きを仲介していることをつかんだ。東京大の窪田直人准教授らは、インスリンの働きにかかわる、IRS2というたんぱく質が肝臓にないマウスをつくり、調べた。その結果、IRS2は、肝臓が体内の脂肪などを分解して糖をつくるのを抑えるインスリンの働きを促し、空腹が続くほど増え、食後にほとんどなくなることがわかった。インスリンは、肝臓が食後に糖から脂肪をつくってためこむのを助ける働きもあり、これにはIRS1という別のたんぱく質がかかわっていた。IRS1の量はほぼ一定なので、食べ続けることで肝臓には脂肪がためこまれる。2型糖尿病患者に高血糖と脂肪肝が同時に起こる原因とみている。治療薬開発につながる成果という。共同研究者の門脇孝・東大教授は、「間食をせずに3食リズムよく食べることが大切」と話している。(平成20年7月2日 朝日新聞) タミフル効かない耐性ウイルス インフルエンザ治療薬「タミフル」が効かない耐性ウイルスは、国内で1.6%にとどまっていることが、国立感染症研究所などの緊急調査で分かった。報告書が世界保健機関(WHO)のウェブサイトに掲載された。 欧州では4分の1が耐性化するなど国際的な問題になっている。WHOなどによる国際監視体制の一環。全国76の地方衛生研究所が07年9月から08年3月までのシーズンに患者から得たインフルエンザAソ連型のウイルス1360株を集め、感染研が解析した。その結果、1.6%にあたる22株が耐性だった。このなかには、今年1月に横浜市で集団感染を起こしたウイルスも含まれている。耐性は非常に強く、普通のインフルエンザウイルスに比べ、300倍以上だった。日本は世界の生産量の7割を使うタミフル消費大国であり、耐性ウイルスが広まっているのではないかと懸念されていた。(平成20年7月1日 朝日新聞) 前立腺がん細胞増殖、遠赤外線が抑制 遠赤外線が前立腺がん細胞の増殖を抑制する効果があることを、兵庫医科大の島博基教授が突き止め発表した。遠赤外線を発する特殊加工ゴムをがん細胞の近くに置くと、がん細胞の自滅(アポトーシス)を促す遺伝子が活性化し、がん細胞が減少。抗がん剤と併用すると、がん細胞が死滅したという。ヒト前立腺がん細胞を移植したマウスをカゴに入れ、周りを大阪市の化学メーカーが開発した、微弱な遠赤外線を放射する金属などを混ぜた特殊加工ゴムで囲って、マウスのがん細胞増殖の推移を観察した。その結果、遠赤外線を当てられたマウスの体温が0.36度上がり、マウスに移植されたがん細胞内の遺伝子にあるアポトーシス回路が活性化。約70日後に、がん細胞の増殖が半分以下に抑制された。これに加え、がん増殖抑制機能があるとして米国で抗がん剤として使われている腸管内物質「酪酸ナトリウム」を3種類の前立腺がん細胞に投与したところ、いずれも死滅したという。島教授は「原理的にはすべてのがんに効果があるはず。臨床応用を進めて、治療法を確立したい」と話している。(平成20年6月27日 産経新聞) カルシウム不足の女性、腰椎骨折リスク2倍 厚生労働省研究班はカルシウムの不足している女性は腰椎を骨折するリスクが最大で2.1倍に高まるという大規模疫学調査の結果を公表した。日本人は欧米人と比べてカルシウムの摂取量が少ないといわれており、研究班は幅広い食品からの摂取を呼びかけている。研究班の中村和利・新潟大学准教授は、全国の40―69歳の男女約7万6000人を10年間にわたって追跡調査。聞き取り調査を基に食品からのカルシウム摂取量を算出し、腰椎を骨折するリスクとの関係を調べた。交通事故などによるケースを除くと、期間中に364人が骨折していた。カルシウム摂取量の多い順に4つのグループに分けると、女性の場合、最も少ないグループ(1日当たり350ミリグラム未満)は、最も多いグループ(同700ミリグラム以上)と比べて腰椎骨折のリスクが2.1倍になった。(平成20年6月26日 日本経済新聞) じゃまな脂肪で再生医療 おなかの脂肪から、様々な細胞になりうる幹細胞を取り出して心筋梗塞や肝臓病を治療することに、大阪大や国立がんセンター研究所のグループが動物実験で成功した。脂肪は採取しやすく移植時の拒絶反応も避けられる。厄介者扱いされがちな脂肪だが、再生医療に利用しようと研究が広がっている。大阪大未来医療センターの松山晃文・准教授らは、脂肪の中から心筋や肝臓、膵臓の細胞に効率よく成長する幹細胞を見つけた。この細胞を、特殊な薬剤で心筋のもとになる心筋芽細胞に変化させ、心筋梗塞のラットに移植した。治療しないと心臓の収縮率は30%に落ちたが、移植すると60%まで回復して4カ月維持した。この幹細胞から肝細胞の塊をつくり、慢性肝炎のマウスに移植すると、肝機能が改善した。膵臓のようインスリンを出す細胞もつくり、糖尿病のマウスに移植すると、3週間にわたり血糖値が下がった。同センターの澤芳樹教授は「動物実験を重ね、あらかじめ脂肪から幹細胞をとって将来に備える細胞バンクをつくりたい。テーラーメード型の再生医療が目標」という。国立がんセンター研究所の落谷孝広・がん転移研究室長らも、皮下脂肪から肝細胞をつくった。肝臓でしか合成されないたんぱく質を14種類以上検出。肝臓を傷めたマウスに注射すると、上昇した血中のアンモニア濃度が24時間後にほぼ正常に戻った。ただ、肝臓は500ほどの機能があり、すべて回復しているかどうかは分からない。メカニズムの解明もこれからだ。落谷さんは「胚性幹(ES)細胞から肝細胞をつくる効率が低いのに対し、必要な量を採取できる脂肪の利用に期待が集まっている。肝臓切除時に少量移植して機能回復を促す補助的な使い方が考えられ、数年内の臨床試験をめざしたい」と話している。(平成20年6月23日 朝日新聞) ミカン果汁で脳の老化防止? ミカン果汁が脳の老化防止に役立つ可能性があることが、静岡県立大や農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所によるマウス実験でわかった。県立大の海野けい子准教授は「果汁の成分のどこに効果があるのかはこれからの研究課題になる。人で効果があるかも試したい」としている。老化が早い系統のマウス80匹を使った。20匹ずつ4グループに分け、3.8〜38%の3段階の濃度のミカン果汁で水分補給したものと、水で水分補給したものを1年間飼育。マウスが明るい箱から暗い箱に移動すると電気ショックを与える装置で実験し、移動を避けるようになるまでにかかる時間を計って学習能力を調べた。その結果、水で育てたマウスは、平均約千秒かかったが、ミカン果汁で育てたマウスは600〜700秒で、果汁濃度が高いほど学習時間が短かった。また、老化につながる大脳の酸化を示す値も3割ほど低かった。(平成20年6月21日 朝日新聞) 寄生虫の治療薬、C型肝炎にも効果 寄生虫病の一種である住血吸虫症の治療薬が、C型肝炎にも効くことが、エジプトでの臨床試験でわかった。エジプトでは住血吸虫とC型肝炎ウイルス両方に感染する患者が多く、住血吸虫症の治療薬がC型肝炎にも効くと言われてきたが、米バイオテクノロジー企業「ロマーク研究所」の試験で裏づけられた。同社がイタリアで開かれた欧州肝臓学会で発表した。治療薬はニタゾキサニド(商品名アリニア)。住血吸虫やクリプトスポリジウムなどの寄生虫病の治療に使われている。同社のジャン・フランソア・ロシニョール博士らが、エジプトのC型肝炎患者で試験した。標準治療を受けた40人のうち、C型肝炎ウイルスが消えたのは半数の20人だったが、標準治療にニタゾキサニドを加えた28人では約8割の22人になった。ニタゾキサニドがC型肝炎ウイルスに効く理由ははっきりしていない。C型肝炎ウイルスは、日本国内でも200万人以上の感染者がいるとされ、肝臓がんの大きな原因になっている。大阪大学の林紀夫教授は「数年前からC型肝炎に効くとの報告があったが、信用されていなかった。明らかなデータが出たことで、治療法の研究が進むのではないか」と話している。(平成20年6月21日 朝日新聞) ビタミンB群多くとる人は心筋梗塞になりにくい ビタミンB群が豊富な魚や野菜などを多く食べる人は、心筋梗塞になりにくいことが、厚生労働省研究班の大規模調査で分かった。魚、野菜、米を中心にした日本食の優れた点が改めて裏付けられた。磯博康・大阪大教授らは岩手、秋田など4県の40〜59歳の男女約4万人を対象に、約11年間にわたって調査。食事内容から、ビタミンB群のビタミンB6やB12、葉酸の摂取量を算出した。その結果、B6の摂取量が多い人(1日当たり1.6ミリ・グラム)は最も少ない人(同1.3ミリ・グラム)より、心筋梗塞になる恐れが48%低かった。B12や葉酸でも、それぞれ47%、37%低下した。ただ、B群のうち1種類だけ多くても、発症の恐れは1.45〜1.74倍高く、バランスの良い食事が重要と言えそうだ。(平成20年6月6日 読売新聞) 1日1杯のワインは肝臓によい効果 1日1杯程度のワインであれば、肝臓に害がないばかりでなく、非アルコール性脂肪性肝疾患のリスクを軽減する可能性さえあることが新しい研究により示された。今回の地域集団ベースの研究は、米カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究グループによるもので、飲酒の習慣のない人7211人、1日に平均ワイン4オンス(約120ミリリットル)、ビール12オンス(約360ミリリットル)または蒸留酒1オンス(約30ミリリットル)程度の控えめな量の飲酒をする人4543人を対象に実施された。その結果、1日1杯のワインを飲む人は、飲酒しない人に比べ血液検査に基づく非アルコール性脂肪性肝疾患疑いのリスクが半分であることが判明。しかし、ビールまたは蒸留酒を控えめに飲むとした人では、非アルコール性脂肪性肝疾患疑いの比率はワインを飲む人の4倍であった。研究を行った同大学小児科部門消化器病学准教授のJeffrey Schwimmer博士は、「この結果は常識を覆すものだ」と述べている。しかし、多量のワインを摂取した場合に予防効果がさらに高まるとの証拠は示されておらず、「アルコールを飲み過ぎるリスクのある人は、ワインもそのほかの酒類の摂取も考えるべきではない」とSchwimmer氏らは強調している。この効果はワインだけにみられ、ビールや蒸留酒には認められないことから、効果がアルコールによるものなのか、それ以外の成分によるものかを見極めるためにさらに研究を重ねる必要があるという。非アルコール性脂肪性肝疾患は米国では最もよくみられる肝疾患で、4000万人を超える成人が罹患しており、患者の5%が肝硬変を発症するという。非アルコール性脂肪性肝疾患の主な危険因子は、肥満、糖尿病、中性脂肪および高血圧など。(平成20年6月5日 日本経済新聞) 40歳時点で喫煙…余命は4年短く 40歳の時に、たばこを吸っている人の平均的な余命は、吸わない人と比べて男女とも4年近く短いことが、約30万人を対象にした厚生労働省研究班の調査でわかった。結果をまとめた京都府立医科大の小笹晃太郎・准教授は「余命への影響は、実際にはもっと大きいかもしれない。さらに禁煙対策を進めていくべきだ」と指摘する。喫煙者の平均余命については、昨年、40歳時点で男性は3.5年、女性は2.2年短いという別の研究班の調査が公表されたが、対象は約1万人だった。今回は国内で進められている四つの疫学調査データを使い、90年代に40〜79歳の男女約29万7千人に喫煙習慣などをたずね、約10年間追跡した。約2万6千人が亡くなっていた。喫煙率は男性54%、女性8%だった。データから年代ごとの余命を計算すると、40歳の男性でたばこを吸う人の余命は38.5年で、吸わない人の42.4年より3.9年短かった。40歳の女性では、喫煙者が42.5年で、吸わない人の46.1年より3.6年短かった。早めに禁煙すれば、影響は少なくてすむことも確認された。喫煙者の多かった男性で比較すると、40歳の喫煙者の余命は、40代でやめる場合は42.2年、50代でやめる場合は40.1年だった。たばこの本数と余命との関係では、1日に1〜14本吸う40歳男性は38.3年、15〜24本では38.7年、25本以上では37.9年で、あまり変わらなかった。こうした調査は一般に、追跡期間が長いほど、吸う人と吸わない人の差が広がるといわれ、英国で50年間追跡した研究では両者の差が10年ほど開いた。また、吸わないという人も、実際には他人の煙にさらされる受動喫煙による健康被害で、本来よりも余命が短くなり、差が小さく見えている可能性もあるという。(平成20年6月1日 朝日新聞) NK細胞で移植後の肝がん防ぐ 正常な肝臓にある強い抗がん作用を持つナチュラルキラー細胞(NK細胞)を培養・投与することで、肝臓がんで臓器移植を受けた後の患者で、再び肝がんができるのを防ぐことに、広島大の大段秀樹教授らが成功した。肝臓がん患者に移植を行った後、体内に残るがん細胞で、移植した肝臓に再びがんができる場合がある。大段教授らは2年前、移植用の肝臓に通した後の保存液から、強い抗がん作用を持つNK細胞を発見。2日間培養し、肝臓がんを殺す能力を高めたNK細胞の投与を移植患者に始めた。その結果、2000〜2006年に移植を受け、NK細胞を投与されなかった患者42人のうち4人に再びがんができたが、細胞を投与した14人には現在、がんはできていない。培養したNK細胞の表面には、肝臓がんを殺す働きを持つたんぱく質が多数生成されるという。また、肝臓がん患者の7割以上がC型肝炎だが、培養したNK細胞は肝炎ウイルスの増殖を抑えるインターフェロンを作り出す働きも持つ。大段教授らが移植後の患者にNK細胞を投与したところ、何もしない場合と比べ、ウイルスの量を一時100分の1まで減らすことが出来たという。(平成20年6月1日 読売新聞) たばこ吸って飲酒も多いと…肺がんリスク1.7倍 たばこを吸うと肺がんになりやすくなることが知られているが、飲酒が加わるとさらに危険度が1.7倍に増大するとの調査結果を、厚生労働省研究班がまとめ発表した。飲酒によって体内で活発に働く酵素が、たばこの発がん物質を活性化していると考えられるという。全国の40―69歳の男性約4万6000人を14年間にわたって追跡調査した。喫煙者と非喫煙者に分け、飲酒と肺がんリスクとの関係を調べた。期間中に651人が肺がんを発症した。聞き取り調査をもとに飲酒量で「飲まない」「時々飲む(月に1―3回)」の2グループと、毎日飲む人については日本酒換算で「1日1合未満」「1日1―2合」「1日2―3合」「1日3合以上」の4グループ、合計6グループに分けた。喫煙者の場合、飲酒量の多い2グループは、「時々飲む」グループと比べて肺がんになるリスクが1.7倍だった。非喫煙者では、飲酒量が増えても肺がんリスクは上がらなかった。日本酒1合のアルコール量は、焼酎で0.6合、ビールで大瓶1本、ワインでグラス2杯、ウイスキーならダブルで1杯に相当する。(平成20年5月30日 日本経済新聞) 乳がん家系は前立腺に注意 リスク4倍 乳がんの多い家系に生まれた男性は前立腺がんの発症リスクが高いことをオーストラリアなどの研究チームが19日までに突き止めた。家族性乳がんのリスク因子として知られるBRCA2遺伝子の変異が前立腺がんの因子でもあることが確認でき、2つのがんの関連が初めて分かった。BRCA2遺伝子に変異を持つ男性の前立腺がん発症リスクは、変異がない男性の4倍になるという。成果は米医学誌クリニカル・キャンサー・リサーチに掲載された。家族性乳がんや卵巣がんの研究を続けてきたチームは、一部の家系では前立腺がんも多いことに気付いた。BRCA2遺伝子の変異が家族性乳がんのリスク因子となることは過去の研究で分かっており、チームは前立腺がんでもこの遺伝子変異が起こっているかどうかを調べ、確認にこぎ着けた。チームは「乳がんの多い家系に生まれた男性は検査を。BRCA2遺伝子変異による乳がんを克服した女性は、兄弟や息子に注意を呼び掛けてほしい」としている。(平成20年5月19日 中国新聞) HIV感染、過去4番目 「増加傾向は変わらず」 厚生労働省のエイズ動向委員会は、今年1月から約3カ月間に新たに報告されたHIV感染者数を過去4番目の251人と発表した。4半期ごとの新規感染者は前回報告(277人)まで3期連続で過去最高を更新しており、岩本愛吉東大医科学研究所教授は「増加傾向に変わりはない」としている。新規のエイズ患者は94人で過去9番目だった。感染者の感染経路別では、同性間性的接触が165人と最多で、このうち日本国籍の男性が159人。患者では同性間の性的接触の44人中、43人が日本国籍の男性だった。感染者、患者ともに20−50代に広がりがみられるが、感染者では特に20、30代で計170人と、全体の7割近くを占めた。(平成20年5月21日 中国新聞) 8人に1人が「うつ」 一般の人の8人に1人に、うつ病あるいはうつ状態の可能性があることが、製薬企業のファイザーのアンケート調査で分かった。うつ病・うつ状態の可能性があっても、実際に医療機関を受診した人は24%にとどまっていた。調査は昨年2月、12歳以上の男女4000人を対象に、インターネット上で実施。米国の学会が作成したうつ病のチェック項目を基に回答してもらったところ、12%にあたる 486人に、うつ病・うつ状態の可能性があった。うつ状態を感じても受診しない理由として、最も多かったのが「行く必要を感じない」(44%)で、「病院への不信感」(20%)、「周囲に知られたくない」(15%)などが続いた。受診について、63人は「家族や友人らに相談した」とし、受診率も83%と高かった。反対に「自分で判断した」423人の受診率は15%で、家族や友人の助言が、うつ病の早期治療のきっかけになっていた。(平成20年5月16日 読売新聞) バイオ人工腎により急性腎不全の死亡率が減少 急性腎不全患者の生命を救うバイオ人工腎が数年以内に実用化される可能性が、新たな臨床試験によって示された。生体細胞を利用した尿細管補助装置によって腎細胞の機能を短時間補助することにより、腎損傷による急性腎不全患者の死亡リスクが有意に減少し、腎機能の回復が加速されるという。研究を行った米ミシガン大学医学部内科教授のH. David Humes博士らは、10年以上前にこのバイオ人工腎の開発を始めた。この装置には、従来の腎透析のように血液を濾過するカートリッジが含まれ、これが尿細管補助装置につながれている。尿細管補助装置は腎近位尿細管細胞と呼ばれる腎細胞の一種で裏打ちされた中空糸でできており、この腎細胞は生命維持に必須の電解質や塩、グルコース、水を再吸収し、感染症と闘うサイトカインと呼ばれる免疫システム分子の産生をコントロールする。今回の研究では、18〜80歳の極めて重篤な状態にある患者58人を対象とした。持続的静脈-静脈血液濾過と尿細管補助装置を併用した患者では28日後の死亡率が33%であったのに対し、従来型の持続的腎補助療法(腎透析)を受けた患者では66%であった。28日目の時点で尿細管補助装置群の53%に腎機能の回復が認められた。180日間の治療後、尿細管補助装置群での死亡リスクは従来療法群の半分(50%)であった。Humes氏は、今回の結果は非常に有望だと述べている。急性腎不全の死亡率の高さ(50〜70%)には長い間変化がみられなかったが、この方法によって優れた治療法の開発が期待できるという。さらに、生体細胞を利用するこの新しい取り組みは、あらゆる分野の新しい細胞ベースの治療法や組織工学を用いた治療法の開発の可能性をもたらす。慢性腎不全患者の治療用として、装着型人工腎のような装置の開発が促進される可能性もあるという。「細胞の生命維持プロセスを利用して、疾患によって障害された部分を回復させるこの能力は、医学の将来に大きな影響をもたらすものである。このような生体細胞の利用が成功したことで、われわれの取り組みの正当性が裏付けられ、幅広い疾患において細胞治療の研究が促進されると思われる」とHumes氏は述べている。(平成20年5月8日 日本経済新聞) 椎間板ヘルニアの原因遺伝子2個 理化学研究所などの研究チームは、重い腰痛を招く「椎間板(ついかんばん)ヘルニア」にかかりやすいかどうかを決める新たな遺伝子を2個発見した。両遺伝子の個人差によって、発症リスクが約3倍に高まる。椎間板ヘルニアの治療法の開発に道を開く成果で、米科学誌に研究論文を掲載した。研究チームは、背骨の中でクッションの役割を果たしている「椎間板」に多いたんぱく質「THBS2」を作る遺伝子に注目した。椎間板ヘルニア患者と健康な人の遺伝子を解析したところ、一部の配列(塩基配列)の違いで発症リスクが約1.4倍に高まることが分かった。(平成20年5月2日 日本経済新聞) アルツハイマー、さい帯血で予防 へその緒の血液(さい帯血)を静脈に注射する手法で、アルツハイマー病の原因物質を脳内で蓄積しにくくすることに、埼玉医科大総合医療センターの森隆准教授と米国・南フロリダ大のチームが成功した。さい帯血移植は白血病などの治療に広く使われているが、高齢社会で増加しているアルツハイマー病の治療にも有効である可能性がでてきた。成果は、米医学誌「ステム・セルズ・デベロップメント」に掲載された。アルツハイマー病は、脳にアミロイドベータ(Aβ)と呼ばれるたんぱく質が異常に蓄積することで神経細胞が死に、認知障害が出る病気。そのため、Aβの蓄積を抑える薬の開発が世界中で進められている。研究チームは、生まれつきAβが蓄積しやすいマウス10匹の静脈に2〜4週間おきに人のさい帯血細胞を10万個ずつ計8回注射した。すると、さい帯血細胞を注射しなかったマウスに比べ、脳内のAβ量は約7割減少した。(平成20年4月29日 読売新聞) ALS、新たな原因遺伝子 筋肉が次第に動かなくなる難病「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」の新たな原因遺伝子を、新潟大の小野寺理准教授らが発見した。この遺伝子による「TDP43」というたんぱく質の異常が症状を引き起こすとしている。異常は約9割を占める非遺伝性ALSでもみられることから、原因究明が大幅に加速すると期待される。 ALSは遺伝性と非遺伝性があり、運動をつかさどる神経が侵され、症状が進むと自力呼吸も難しくなっていく難病。非遺伝性ALS患者の神経細胞には、TDP43というたんぱく質が蓄積することがわかっている。しかし神経細胞が侵された結果として蓄積するのか、蓄積によって神経細胞が侵されるのかは不明とされていた。小野寺准教授らは、TDP43の異常がみられる一部の遺伝性患者を研究。TDP43をつかさどる遺伝子に異常が見つかったことから、TDP43が神経細胞を侵す原因であるとした。(平成20年4月29日 毎日新聞) ジェネリック医薬品、生活保護者に安価薬 生活保護受給者に対してジェネリック(後発)医薬品の使用を事実上強制する通知を厚生労働省が自治体に出していることが明らかになった。背景に医療費抑制を迫られる"国の懐事情"があり、通知書でも「後発医薬品は安く」「医療保険財政の改善の観点から」など、お金にかかわる文言が並ぶ。一方、指導に従わない生活保護者を割り出すため、薬局に1枚100円の手数料を払ってまで処方せんを入手するとしており、なりふり構わぬ様子がうかがえる。4月1日に始まった後期高齢者(長寿)医療制度に続き、生活保護者に限定した医費抑制策は「弱者切り捨て」との批判を呼びそうだ。生活保護者については「患者負担が発生しないことから、後発医薬品を選択するインセンティブ(動機付け)が働きにくいため、必要最小限の保障を行う生活保護法の趣旨目的にかんがみ、後発の使用を求める」としている。通知によると、都道府県や政令市などが所管する福祉事務所は、診療報酬明細書(レセプト)の抽出を行ってまで、生活保護者が後発薬を使っているか確認しなければならない。そのために、調剤薬局に1枚100円の手数料を支払い、先発薬を使っている生活保護者の処方せんの写しを提出させるとまで規定していた。先発薬の使用を指示した医師に対しては「特段の理由なく(受給者が)後発薬を忌避したことが理由でないかについて確認」することも盛り込んだ。国は後発薬の使用を生活保護者だけでなく国民全体に呼びかけているが、窓口で3割負担をする患者は調剤薬局などと相談して先発薬を選ぶこともできる。しかし生活保護者は「医学的理由がない」と判断されれば、保護の停止や打ち切りにつながりかねず事実上、選択権が奪われた形だ。ある自治体の担当者は「停止や打ち切りにつながることを、どういう形で受給者に説するか慎重に検討したい」と戸惑った様子で話す。(平成20年4月27日 毎日新聞) リウマチ薬エンブレル、因果関係否定できぬ死者84人 関節リウマチ薬「エンブレル」(一般名エタネルセプト)を使用し、同薬との因果関係が否定できない死者が84人に上ると、日本リウマチ学会の特別調査委員会が21日、札幌市で開かれた同学会シンポジウムで発表した。一部の専門家からは「感染症発症の危険が高い患者などへの処方には、より注意が必要だ」という声も出ている。エンブレルは05年1月に厚生労働省の承認を受け、同3月から製造販売元ワイスが武田薬品工業と販売している。発表によると、昨年4月までに薬を使い始めた登録患者1万3894人のうち、薬との因果関係が否定できない感染症、間質性肺炎などで死亡した患者は84人だった。使用後に何らかの症状を訴えた患者は31%で、結核感染者は12人いた。エンブレルを使用する前に別の感染症にかかった経験がある患者や、ステロイド剤を併用している患者で感染症発症が高かった。一方、エンブレルの使用で、85%の患者の症状が改善した。関節リウマチ患者の死亡率は一般の1.5〜2.0倍とされるが、エンブレル使用者は1.46倍だった。臨床試験で副作用や長期使用での安全性に疑問が残ったため、厚労省は発売後一定期間、使用した患者全員を登録、追跡調査することを義務付けていた。昨年12月の両社の発表では、登録患者で薬との因果関係が否定できない死者は76人、昨年6月の登録終了後の死者は3人だった。(平成20年4月21日 毎日新聞) がん細胞、増殖加速遺伝子を解明 がん細胞がエネルギー源であるブドウ糖を取り込む一連の仕組みを、日本医科大の川内敬子助教と田中信之教授らが発見した。この仕組みを遮断する薬剤を開発すれば、「兵糧攻め」でがん細胞の増殖を抑えられることになる。研究チームは、細胞が、がん化するのを抑制する遺伝子「p53」に注目。マウスの細胞でp53を除去すると、がん化するだけでなく、別の遺伝子「NFκB」の働きが活発になっていることに気付いた。調べると、NFκBが、ブドウ糖を取り込む別のたんぱく質を増やし、がん細胞の増殖を加速させることを突き止めた。p53が働かなくなると、NFκBが活性化し、がん細胞へのエネルギー供給が進み、増殖するという流れを解明した。田中教授は「p53の機能を回復したり、NFκBの機能を抑えれば、新しいがん治療薬の開発につながるだろう」と話している。(平成20年4月21日 毎日新聞) 月経血から心筋細胞 慶応大など「幹細胞源として期待」 女性の月経血には、からだのさまざまな組織に変化する可能性がある幹細胞が豊富に含まれ、条件を整えると心臓の細胞(心筋細胞)に高い確率で変化して拍動もすることがわかった。慶応大と国立成育医療センターなどのチームが実験で示した。チームは「月経血は新しい幹細胞源として期待できる」としている。チームは、女性6人に協力してもらい、月経血をガラスの容器に採取して培養。人工的に心筋梗塞を起こしたネズミの心臓に移植したところ、症状の改善が確認された。また試験管内の分化誘導実験では、月経血に含まれる細胞の20%が心筋細胞に変わって、自ら拍動を始めた。現在、病気の治療に幹細胞を使うときは、赤ちゃんのへその緒に含まれる臍帯血や、骨髄から採ることが多い。しかし、さまざまな組織に変化できる有用な幹細胞が含まれる割合が低いうえ、目的の細胞に変化する割合も高くない。チームの実験では、心筋細胞に変化した骨髄細胞の割合は、0.3%だった。 チームの三好俊一郎・慶応大講師は「月経血は医療廃棄物で、使うことに倫理的な問題はなく、採取の際に痛みもない。将来、若いころに月経血を採って冷凍保存しておき、あとで心臓病になったときに使うことなどが考えられる」と話している。(平成20年4月17日 朝日新聞) 脳梗塞リスク、血液で簡単判別 千葉大学病院と同大学発ベンチャー企業のアミンファーマ研究所は、脳梗塞が将来起きるかどうかの危険性を血液だけで簡単に判別する技術を開発した。大型の検査装置が必要なく、検査を受ける人の負担が少ない。同大は病院で脳ドックを受ける40歳以上の男女約1000人を対象に5月から臨床研究を始める考えだ。脳梗塞の患者数は約120万人とされる。特に40歳以上の働き盛りの男女を中心に患者が増えている。ただ、多くの患者は自覚症状を感じないが将来発症する恐れがある「隠れ脳梗塞」とされ、発症前に簡単に検査する方法が求められていた。(平成20年4月18日 日本経済新聞) 治験で子どもに接種へ 新型インフル備蓄ワクチン 厚生労働省は16日、新型インフルエンザ対策として鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)から製造し、国家備蓄しているワクチンを、子どもに接種する臨床試験を今月中に始める方針を明らかにした。「プレパンデミックワクチン」と呼ばれる備蓄ワクチンは、大人のみを対象とした臨床試験で承認されたため、新たに子どもについても用法、用量を確認するのが目的。通常のインフルエンザワクチンでも大人と子どもでは用量が違う。厚労省によると、備蓄ワクチンの承認審査の段階でも、子どもについて情報収集の必要性が指摘されていた。計画によると、治験は医師主導で実施し、今年12月までに、北里研究所と阪大微生物病研究会が製造したワクチンを、6ヵ月以上20歳未満の120人に接種する。(平成20年4月17日 中国新聞) 前立腺がん、乳製品食べる男性、発症率が1.6倍 乳製品をたくさん食べる男性は、ほとんどとらない男性に比べ、前立腺がんの発症率が約1.6倍になることが、厚生労働省研究班の大規模調査で分かった。乳製品は骨粗しょう症や高血圧、大腸がんの予防に有効だとする報告も多く、研究班は「乳製品の摂取を控えた方がいいかどうかは総合的な判断が必要で、現時点での結論は出せない」としている。研究班は、95年と98年に登録した全国10府県に住む45〜74歳(登録当時)の男性約4万3000人を04年まで追跡。このうち329人が前立腺がんを発症した。牛乳やヨーグルトなど乳製品の摂取量によって4群で分析した結果、最も多い群は、ほとんどとらない群に比べ、前立腺がんの発症率が約1.6倍になった。摂取量が多いほど危険性が高まる傾向がみられた。乳製品に多く含まれるカルシウムと飽和脂肪酸は、前立腺がん発症の危険性を高める可能性のあることが報告されている。(平成20年4月16日 毎日新聞) 百日ぜき、2000年以降最多 しつこいせきが続く「百日ぜき」の患者報告が増えており、今年1―3月の累計は、比較が可能な2000年以降で最多となったことが、国立感染症研究所の16日までのまとめで分かった。特に成人患者の増加が目立ち、全体の4割近くを占めた。専門家は乳幼児期に受けたワクチンの効果が減衰したためではないかとみている。成人は典型的な発作症状がなく、見逃される例も多いとされる。感染研は「放っておくと感染を拡大させるため、激しく治りにくいせきなどの症状が出たら早く受診を」と呼び掛けている。3月30日までの約3ヵ月間に、全国約3000ヵ所の小児科から報告された患者数は計851人。この規模の調査が定着した2000年以降、最多だった同年の同じ時期までの累計(計689人)を上回った。都道府県別では千葉150人、福岡70人、大阪69人、広島58人、愛知56人など、大都市圏で多い。(平成20年4月16日 日本経済新聞) 国家公務員病欠、1位はうつなど 人事院は2006年度に1か月以上病欠した国家公務員に関する実態調査の結果を発表した。うつ病などの「精神・行動の障害」で休んだ人が63%にあたる3849人に上り、01年度の前回調査と比べ、74%の大幅増となった。人事院職員福祉課は「1人当たりの仕事量が増え、ストレスを感じる人が多いのではないか」としている。病欠者の人数は公務員数の減少で過去最少の6105人だったが、公務員全体に占める割合は2%でわずかに増えた。「精神・行動の障害」以外では「肺がんや白血病など」(604人)「循環器系の疾患」(317人)などが多かった。(平成20年4月10日 読売新聞) パーキンソン病のiPS細胞治療、ラットで成功 新型の万能細胞「人工多能性幹細胞(iPS細胞)」から作り出した神経細胞を使い、パーキンソン病のラットを治療することに、米マサチューセッツ工科大のルドルフ・ヤニッシュ教授らのグループが成功した。iPS細胞が神経病の治療に使えることを初めて示した成果。研究グループは、マウスの皮膚からiPS細胞を作り、神経伝達物質のドーパミンを分泌する細胞に分化させた。パーキンソン病を人工的に発症させたラット9匹の脳に移植したところ、8匹の症状が改善、特有の異常動作がなくなった。パーキンソン病は、ドーパミン細胞の異常で手のふるえなどが起きる難病。移植した細胞がラットの脳内に定着し、ドーパミンを正常に分泌し始めたらしい。(平成20年4月8日 読売新聞) 野生イノシシ肉がE型肝炎感染源に E型肝炎の感染源の一つが野生イノシシ肉であることが、国内で初めて遺伝子レベルで確認されていたことが分かった。全国的にE型肝炎ウイルス(HEV)感染者が急増するなか、野生イノシシの5〜10%がHEVを保有している可能性があるとされ、厚生労働省は「野生動物の肉を食べる際は十分に火を通すなど注意してほしい」と呼びかけている。HEVの感染源が遺伝子レベルで確認されたのは、05年1月に福岡県筑豊地方で夫が捕ってきた野生イノシシ肉を焼き肉にして食べた当時50代の女性。同年3月、倦怠感や食欲不振を訴えて病院に行ったところ、E型肝炎に感染した疑いがあると診断された。自宅の冷凍庫にイノシシ肉が保管してあったことから、国立感染症研究所が肉と女性の血清から検出したHEVの塩基配列を比較。配列がほぼ一致し、イノシシ肉が感染源と特定された。十分に火を通していなかったなどの理由が考えられるという。E型肝炎は従来、開発途上国を旅行した人が水などから感染するケースが多いとされてきたが、02年以降、国内での感染が疑われるケースが急増している。朝日新聞社が各都道府県などに尋ねたところ、99〜01年の3年間で全国で3件しか発生していなかったE型肝炎は02年約20件、03年約30件、06年には約70件と大幅に増加。このうち国内での感染が疑われるケースは02〜04年が20件前後、06年は44件になった。 地域的には北海道が最も多く71件。ついで東京が23件、愛知16件、神奈川13件と続いた。一方、秋田、石川、岐阜、島根、香川などでは感染の報告はなく、青森では今年2月に1件報告があった。福岡県保健環境研究所は06、07年度の2年間、県猟友会の協力を得て野生イノシシなどを対象にHEV遺伝子について調査した。07年度分は検査中だが、06年度分はイノシシ77頭のうち1割強にあたる9頭からHEV遺伝子が検出された。厚労省によると、各地の同様の調査では地域差はあるものの、野生イノシシの5〜10%からHEV遺伝子が検出されているという。イノシシ以外にも03年に兵庫県で冷凍したシカの生肉を食べた4人がHEVに感染したほか、北海道では市販の豚レバーからHEV遺伝子が検出されたケースもあるという。 感染の報告数が増えたのは、高感度なHEV遺伝子の検出法などが広まったことが背景にあるとされる。厚労省食品安全部監視安全課は(1)野生動物の肉の生食は避け、しっかり火を通す (2)生肉に触れたまな板やはしは熱湯消毒する――ことなどを呼びかけている。〈E型肝炎〉 HEVに汚染された水や食べ物から経口感染し、吐き気や食欲不振などの症状が出る。通常は一過性で慢性化しないが、まれに劇症化し死亡することがある。約100年前に英国から輸入された豚と一緒に国内に入ってきた可能性があるとの研究結果があり、シカ肉や豚レバーによる感染例や、輸血で感染した例も報告されている。加熱すると感染性を失う。(平成20年4月7日 朝日新聞) 前立腺がん、学会が集団検診のPSA検査推奨 日本泌尿器科学会は前立腺がんの集団検診として普及しつつあるPSA(前立腺特異抗原)検査を推奨するガイドラインを発表した。学会のガイドラインでは、PSA検査を積極的に実施した地域では、前立腺がんで死亡した人が予測された数の半分以下になった事例を報告した米国の最新データを紹介。「検査をすれば、明らかに転移する(悪性の)がんにかかる危険率が下がる」とした。PSA検査は採血で、前立腺がんになると増えるたんぱく質の濃度を測定する。日本では06年1月現在、全国の約4割の957市区町村が住民検診に導入している。(平成20年4月4日 毎日新聞) ミトコンドリア異常でがん悪性化 がん細胞にあるミトコンドリアの遺伝子に異常が起こると、がん細胞が悪性化し、転移しやすくなることが、筑波大、島根大、千葉県がんセンターのチームの研究でわかった。治療法開発につながると期待されている。 林純一・筑波大教授によると、細胞のエネルギーになるATP(アデノシン三リン酸)をつくるミトコンドリアの酵素に遺伝子変異があると、活性酸素が過剰にできる。マウスの肺がん細胞を使った実験で、活性酸素によって、細胞増殖を調節する物質が異常に増えることを突き止めた。酵素に変異があるがん細胞をマウスに注射すると肺に転移したが、マウスに活性酵素を抑える薬を飲ませると、転移は減った。人の乳がん細胞でも、同じ酵素に異常があると活性酸素が過剰に生み出され、悪性化することを確かめた。(平成20年4月5日 朝日新聞) 心停止、とにかく胸押して 心停止状態で倒れている成人を助けるには、胸を押し続けて圧迫するだけでも、人工呼吸を加えた方法と同じ蘇生効果があることが、日本の二つのグループの調査でわかった。調査を受けて米心臓協会(AHA)は、この「圧迫」を蘇生法として市民に勧める見解を発表。日本でも指針が見直される見通しだ。心臓発作などで倒れた場合、命を大きく左右するのは早期の心肺蘇生。蘇生法は、胸の真ん中を押す「胸骨圧迫」と人工呼吸を交互に行うのが原則で、海外でも同じ。ただ、第一発見者の多くはたまたま居合わせた人。他人に口をあわせる人工呼吸に抵抗感があるのが課題だった。ところが京都大の石見拓・助教や大阪府の救急医らの調査で、人工呼吸を省いても効果が変わらないことがわかった。調査対象は、98〜03年に心臓病で心停止して倒れたが、近くに人がいた大阪府民の事例約4900件。倒れて1年後に、後遺症なく社会復帰できた率を調べた。 すると、倒れて15分以内に救急隊が到着したケースでは、居合わせた人から基本蘇生法を受けた場合の「後遺症なし復帰率」は4.1%。胸骨圧迫のみは4.3%で、ほぼ同じ効果がみられた。首都圏の医師らの調査でも同様の傾向だった。AHAは蘇生法の国際的な指針づくりに強い影響力を持つ。子どもについては、基本の方法を勧めている。日本救急医療財団心肺蘇生法委員長の坂本哲也・帝京大教授は「手法の難しい人工呼吸を無理にするより、圧迫だけでもたくさんの人に取り組んでもらえれば、より多くの命を救える」と話す。(平成20年4月5日 朝日新聞) 受動喫煙、糖尿病リスク8割増 他人のたばこの煙にさらされる受動喫煙で、糖尿病になるリスクが8割ほど高くなることが、企業の従業員を対象とした厚生労働省研究班の調査でわかった。受動喫煙でがんやぜんそくのリスクが高まることは知られているが、糖尿病との関連を示した研究は珍しい。調査は関東、近畿、北陸地方の12の事業所に勤める19〜69歳の男女で、糖尿病でない約6500人に実施。99〜00年に職場の喫煙環境のほか、体格や運動習慣などを聞き、04年まで追跡した。この間、229人が新たに糖尿病になった。自分は吸わないが、職場でたばこの煙を浴び、とても不快に思っている人を「受動喫煙あり」と定義。喫煙歴がなく、受動喫煙もない人たちが糖尿病になるリスクを1として比較すると、受動喫煙がある人たちのリスクは1.81倍だった。肥満の有無や運動習慣など、糖尿病のかかりやすさに関連するほかの要因は影響しないように調整した。喫煙者本人ではがんや動脈硬化などのほか、糖尿病のリスクを高めることもすでに報告されているが、今回の調査では自分自身が吸っている人のリスクは1.99倍だった。喫煙で糖尿病になりやすいのは、糖を処理するインスリンをつくる膵臓(すいぞう)の働きが悪くなったり、インスリンが出ても効きにくくなったりするためと考えられている。調査をまとめた京都大の林野泰明講師(臨床疫学)は「糖尿病を防ぐ観点からも、職場の分煙環境の整備が重要。もっと大切なのは、喫煙者を一人でも減らすことです」と話す。(平成20年4月3日 朝日新聞) 血栓、防ぐ抗体を開発 血液を固まりにくくして、脳梗塞や心筋梗塞の原因となる血栓ができるのを防ぎ、一方で内出血などはあまり起こさずに済む抗体を、滋賀県立大の高山博史教授らが開発した。臨床で使えれば、副作用の少ない理想的な血栓予防薬になる可能性があるという。血栓は、血液中の血小板にコラーゲン繊維がからまり、固まりを作ってできる。しかし高山教授らは、固まりができない女性を発見。血液中から、血小板とコラーゲンの結合を妨げる抗体を見つけ、この抗体を人工的に作ることに成功した。抗体には、血小板の表面に存在しコラーゲンと結びつく「コラーゲン受容体」を、血小板の内部に引っ込めさせる働きがあった。さらに、マウスの体内に人為的に血栓を作る実験を行い、普通のマウスには血栓ができるが、同様の抗体を前もって注射したマウスにはできないことを確かめた。血小板の機能を部分的に低下させて血栓を防ぐ薬は既にあるが、副作用で脳出血など体内の出血が起きやすくなる。しかし今回の抗体を持つ患者は、脳出血などを起こさず20年間過ごしている。高山教授は「抗体を実用化すれば、脳出血などの副作用なく血栓を防ぐ薬ができるのではないか」と話している。(平成20年4月2日 毎日新聞) 医師の待機勤務に手当支給へ 独立行政法人・国立病院機構は4月から、全国146病院の医師や看護師らが緊急手術などに備えて当番制で自宅待機する場合、手当を支給することを決めた。医師は1回5千円。年間支給総額約10億円を見込む。医師不足問題で勤務医らの待遇が課題になっており、国立病院が自ら改善に乗り出した形だ。これまで「待機当番」は、各診療科の医師が順番で、夜間休日に電話が常につながるよう待機。患者の急変に応じて病院に駆けつけたり、院内にいる当直医から専門治療の相談にのったりしていた。「オンコール」と呼ばれ、無償だった。 4月からはオンコールも勤務とみなし、当番回数に応じて医師に1回5千円、看護師、臨床検査技師らに2千円を支給する。「待機中は飲酒もできず、在宅勤務をしているようなものだと、長年、対処要望が強かった」と同機構人事課。勤務医不足が社会問題化しているのを受け、初めて実施する。関東地方のある機構病院の救命救急センターでは、医師にかかる電話は1回の当番中に複数回。2回当番があれば、1度は病院に駆けつける状態という。「無償では、医師個人の意識によって対応にばらつきがあった。きちんと勤務と認められることで、責任が明確になる」と同センター長は評価している。(平成20年4月1日 朝日新聞) 肝硬変、原因細胞を抑制 札幌医大が「新薬」 肝硬変発症の原因となる異常細胞の働きを抑える方法を、札幌医大の新津洋司郎教授の研究チームが初めて開発した。国内には数十万人の肝硬変患者がいるが、有効な治療法はない。抜本的な治療につながる可能性があり、研究チームは近く臨床試験に着手する。肝臓内の血管に張り付いている正常な星細胞は、ウイルス感染などが原因で活性化星細胞(HSC)と呼ばれる異常細胞に変化する。その後、 HSCはコラーゲンを生成し、肝細胞を線維化させ、肝硬変を起こす。研究チームは、HSCにあり、コラーゲン生成に必須のたんぱく質に着目。コラーゲンの分泌量を減らすため、このたんぱく質の働きを抑える機能を持った2本鎖RNA(リボ核酸)「siRNA」を含む薬を合成し、薬にはHSCが好んで取り込むビタミンAを加えた。肝硬変を起こさせたラットを使った実験では、薬を投与しなかったラットは1カ月余りですべて死んだのに対し、投与したラットは約70日後には正常の肝臓並みに機能が回復し100%生存。コラーゲンを失ったHSCが死滅したとみられる。新津教授は「HSCが原因で発症する肺線維症や心筋梗塞などでも、同様の方法で病気の進行を抑えられた。再生医療を含め、幅広い応用が期待できる」と話している。(平成20年3月31日 毎日新聞) 百日ぜき患者倍増 激しいせきが続く百日ぜきの患者が、今年は過去10年間で最も速いペースで増加していることが、国立感染症研究所感染症情報センターの調べでわかった。国内の小児科3000か所からの報告によると、今年に入って確認された患者は664人(3月16日現在)で、昨年同期(331人)の約2倍。大人も含めた全体の患者数も急増しているとみられ、同センターでは注意を呼びかけている。百日ぜきは、春から夏にかけてが流行のシーズン。風邪に似た症状で始まり、大人の場合は長引く激しいせきのほかは、比較的症状が軽いのが特徴だ。このため、発症に気づかないケースも珍しくない。しかし、大人が感染源となって、ワクチンを接種していない乳幼児に感染すると、肺炎のほか、手足のまひ、目や耳の障害などの後遺症が残る例がある。このうち0.2〜0.6%の乳幼児は死亡するとされる。国内では、生後3か月以降に計4回のワクチン定期接種の機会があるが、ワクチン効果は年月がたつにつれ減少するため、大人がかかるケースが近年増加。現在では、小児科からの報告でも20歳以上の症例が3割以上を占める。同センターでは「乳幼児は早めにワクチンを受け、大人も、せきが長引けば病院を受診してほしい」と話している。(平成20年3月30日 読売新聞) 胸腹部大動脈瘤に筒状器具で新手術 胸から腹部にかけての大動脈が膨らむ胸腹部大動脈瘤の治療で、「ステントグラフト」という筒状の器具を瘤の中に通す新たな手術に、東京慈恵会医科大の大木隆生教授らが成功した。人工血管に置き換える従来の手術は胸から腹部を50センチほど切る必要があり、患者の負担が大きかった。今回の手術方法で、体への負担軽減と、高かった13〜20%の死亡率も低くなると期待されている。ステントグラフトは、ワイヤを筒状にし、合成繊維の布をつけた器具。これを血管代わりにして命にかかわる瘤の破裂を防ぐ。「腹部」「胸部」という限られた場所の大動脈瘤では、今回のような手術方法は行われていた。しかし、動脈瘤が両方にまたがる胸腹部大動脈瘤では技術的に難しく、国内では行われていなかった。対象患者は数百人いるとみられる。患者は東京都内の女性(49)。ふつう直径2センチほどの大動脈が太い場所で6センチに膨らんでいた。大木教授らは女性の血管の配置を詳しく調べ、胸から腹部にいたる大動脈瘤に通す長さ約30センチのステントグラフトを特注した。大動脈瘤の途中から枝分かれした腸や腎臓の動脈ともつなげられるよう工夫した。手術は今月11日。女性の脚の付け根の動脈を3センチほど切り、そこからカテーテルという細い管で瘤の中に挿入した。順調に回復している。(平成20年3月23日 朝日新聞) 小児のインフルエンザ菌、6割が抗生物質効かず 小児の髄膜炎や中耳炎の原因となるインフルエンザ菌の6割は、抗生物質の効かない耐性菌であることが、北里大北里生命科学研究所の砂川慶介教授らの全国調査でわかった。髄膜炎に関する調査は、全国約260の国公立病院を対象に2年ごとに実施しており、最新の2006年のデータでは、小児の髄膜炎患者から検出されたインフルエンザ菌のうち60%が耐性菌だった。また、27病院でつくる小児科領域耐性菌研究会が2004年、中耳炎や肺炎の原因となるインフルエンザ菌を小児患者から採取して調べたところ、やはり耐性菌が60%にのぼった。2000〜01年の前回調査に比べて倍増し、子供の中耳炎が治りにくくなっていることを示す形となった。耐性菌の広がりは、医療現場で風邪などに安易に抗生物質が多用されてきたことなどが背景とみられる。砂川教授は「抗生物質を適正に使うことや、髄膜炎を予防するワクチンの普及が必要だ」と話している。(平成20年3月21日 読売新聞) 助産所、1割廃業も お産を取り扱う全国の助産所の約1割が、4月以降に義務付けられている嘱託医療機関の確保ができず、廃業に追い込まれる可能性があることが分かった。07年4月の医療法改正で、お産を扱う助産所は、緊急搬送先確保のため嘱託の産科医と産科医療機関の届け出が義務化され、今年3月末で猶予期間が切れる。しかし厚生労働省の調査では、今月7日現在、来年度もお産を扱う予定の助産所284施設のうち、9施設は医師と医療機関の両方、18施設は医療機関が決まっていないという。また2月時点の調査では、お産を扱う予定だった助産所は297施設あり、医療機関の確保をあきらめて既に廃業したり、出産以外の保健指導などに業務を切り替えた施設もあるとみられる。助産所と医療機関との連携が進まない背景には、産科医の不足や、異常分娩(ぶんべん)を引き取ることによる訴訟リスクの懸念がある。厚労省医政局は「分娩施設がこれ以上減らないよう、嘱託医と嘱託医療機関が同一でも構わないなどの弾力的な運用で、続けられない助産所をゼロに近づけたい」としている。(平成20年3月15日 毎日新聞) 大豆食品成分、乳がんリスク抑える 大豆食品に多く含まれるイソフラボンの一種「ゲニステイン」の血中濃度が高い女性は乳がんになるリスクが最大で3分の1に下がるという調査結果を、厚生労働省研究班がまとめた。研究班の岩崎基・国立がんセンター室長は全国の40―69歳の女性2万5000人を10年半にわたって追跡調査した。この間、乳がんになった144人に、ならなかった288人を加えた計432人について、血液中のゲニステイン濃度と乳がん発症リスクとの関連を調べた。血中濃度が高い順に4つのグループに分けて乳がん発症リスクを比較すると、最も濃度が高いグループは最も低いグループの3分の1にとどまった。閉経前の女性に限ると7分の1まで低下した。最も濃度が高いグループのゲニステイン摂取量は、豆腐だと1日100グラム、納豆なら同50グラムに相当するという。(平成20年3月7日 日本経済新聞) 新型万能細胞応用 経済産業省は、さまざまな細胞に変化できる新型万能細胞(iPS細胞)の産業応用に向け、今月から産業界と大学など研究機関との間で対話の場を設けることを決めた。iPS細胞は再生医療への応用以外にも、新薬の薬効や毒性を調べる材料などとして有望視されており、製薬会社など産業界も注目している。同省は、iPS細胞の産業化でも日本が世界の主導的立場となることを目指す。産学対話では、大学などの研究機関からiPS細胞を円滑に産業界に提供する方法や知財などの取り扱いについて、両者の意見や要望を聞く。6月まで数回開催する計画で、同月に国の総合科学技術会議のiPS作業部会がまとめる研究推進策にも要望などを反映させる。(平成20年3月5日読売新聞) iPS細胞から視細胞 マウスの皮膚でつくった人工多能性幹細胞(iPS細胞)から、網膜にあって光を感じる視細胞をつくることに、理化学研究所発生・再生科学総合研究センターの高橋政代チームリーダーと京都大の山中伸弥教授らが2日までに成功した。人のiPS細胞でも同様の実験を開始。患者本人の細胞を使えば、移植しても拒絶反応が起きないメリットが期待できる。高橋リーダーは「網膜色素変性症などの再生医療実現につながる一歩だ」としている。理研はこれまで、人の胚性幹細胞(ES細胞)から視細胞を効率良くつくるのに成功している。今回は山中教授が作成したマウスのiPS細胞を使い、同様の手法で網膜の前駆細胞をつくり、さらに視細胞に分化させるのに成功した。他人の受精卵からつくられるES細胞と違い、iPS細胞には患者と同じ遺伝子を持たせることが可能で、移植時の拒絶反応が避けられる。高橋リーダーは「分化能力の点でiPS細胞とES細胞は似通っている。次は人のiPS細胞から網膜細胞づくりを試したい」としている。(平成20年3月2日中国新聞) 東大・慶大でもiPS細胞研究 さまざまな臓器・組織の細胞に変化できる新型万能細胞(iPS細胞)を早く再生医療に応用するため、文部科学省は、四つの研究機関を中心とするプロジェクトを4月に始めることを決めた。開発者である山中伸弥教授のいる京都大のほか、東京大、慶応大、理化学研究所が新たな研究拠点となる。文科省は4拠点に来年度約10億円を投入する。京大は、iPS細胞研究センターを中核として、大学病院や大阪大などとも連携。iPS細胞の基礎研究だけでなく、パーキンソン病などの治療技術の開発も推進する。東大は、4月に新設される幹細胞治療研究センターを軸に、血友病などの遺伝病患者の細胞からiPS細胞を作製し、さまざまな病気の仕組みの解明を進める。慶応大は血球の元となる細胞を豊富に含むへその緒の血液を集めて、iPS細胞を200種類作る。理化学研究所はiPS細胞から神経細胞や血球などを作製し、再生医療に使えるかを安全性も含めて検証する。(平成20年2月29日読売新聞) 胃がん早期診断技術、「がん」部位だけ赤に着色 岡山大学の河原祥朗・助教らのチームは、胃がんを正確に診断できる新技術を開発した。がんの部分だけ赤く染められる色素を内視鏡で胃の内部に噴射する。小さな早期がんも見逃さずに発見できるほか、手術時に切除すべき範囲が明確に分かる。減少傾向にあるとはいえ年間5万人が命を落とす胃がん。診断・治療の両面で大きな威力を発揮しそうだ。胃がんの診断では、内視鏡を使うことが多い。胃をのぞくだけではなく「インジゴカルミン」という色素を胃壁に噴射、凹凸を目立たせてからがんを探す手法が普及している。ただ、表面が平たんながんを見つけにくいなど限界もある。(平成20年2月29日 日本経済新聞) アルツハイマー病、たんぱく集合体が原因 大阪市立大学の森啓教授と富山貴美准教授らは、代表的な認知症であるアルツハイマー病の発症の原因は、アミロイドベータと呼ばれるたんぱく質の小さな集合体が脳の中にたまることとする研究結果をまとめた。このたんぱく質が繊維状になって脳にできる老人斑が原因とする通説を覆す成果で、新薬開発につながると期待される。25日付の米神経内科学誌(電子版)に発表した。アルツハイマー病患者の脳には、しみのような老人斑がみられる。主成分のアミロイドベータは通常は分解されるが、高齢になるとうまく分解されないケースが出てくる。老人斑がたくさんできると神経細胞が破壊され、記憶障害などが起こると考えられてきた。(平成20年2月27日 日本経済新聞) 難治性疼痛に抗うつ薬有効 異常な痛みが続く慢性の病気で、治療法がなかった「神経因性疼痛」に、既存の抗うつ薬が有効であることが、美根和典福岡大教授(心身医学)や井上和秀九州大教授(神経薬理学)らの研究で明らかになった。神経因性疼痛は痛みの直接の原因がなくなった後も激痛が続き、患者数は世界で約1500万人。開発に時間もお金もかかる新薬ではなく、既存の薬による治療に道を開く成果として注目される。治療効果が確認された抗うつ薬は「パロキセチン」(商品名パキシル)。神経細胞から放出された神経伝達物質セロトニンが再び細胞に吸収されるのを妨げる「SSRI」というタイプの薬だ。神経因性疼痛の発症メカニズムは長年の謎だったが、井上教授は2003年、脊髄にあるミクログリアという細胞の表面で情報伝達にかかわるタンパク質「P2X4」が、発症に関与していることを明らかにした。P2X4の働きを抑える薬を探し、パロキセチンの効果を発見。 神経因性疼痛の状態にしたラットに投与すると痛みが大幅に軽減することを確かめた。(平成20年2月18日 中国新聞) 新型万能細胞がん化しにくく 京都大学の山中伸弥教授らは、あらゆる細胞や組織に成長できる新型万能細胞(iPS細胞)をマウスの肝臓や胃の細胞から作ることに成功した。皮膚の細胞をもとに作ったiPS細胞よりもがん化しにくいことが分かった。研究成果をヒトのiPS細胞作りに応用して、より安全なタイプを作製できれば、損傷した臓器や神経などを回復させる再生医療の臨床応用に近づく。iPS細胞を皮膚以外の細胞から作れることを示したのは初めて。(平成20年2月15日 日本経済新聞) HIV、昨年の感染、初の1000人超(10年で2.6倍、延べ1万人目前) 07年に国内で新たにエイズウイルス(HIV)に感染した人は1048人に上り、初めて1000人を超えたことが12日、厚生労働省エイズ動向委員会の集計(速報値)で明らかになった。10年間で約2.6倍になり、延べ感染者数も9392人と08年中に1万人を突破するのが確実になっている。新規感染者は5年連続の過去最多更新で、うち93%が男性。感染経路は同性間の性的接触が約7割、異性間接触が約2割、不明が約1割。年齢別では30代が全体の4割超、20代が約3割を占めるが、伸び率が高いのは40代で、7年間で61人から192人に増えた。厚労省は「感染が拡大しているのは事実で、今後は薬物注射の乱用なども警戒する必要がある」と分析している。一方、07年の新規のエイズ患者数は400人で、前年の406人から微減した。厚労省は保健所などでのHIV検査件数が前年より約4万件多い過去最高の21万4347件に達したことを理由に「検査で発症を防げているケースもある」とみている。(平成20年2月13日 毎日新聞) 家族いても生活援助OK 厚生労働省は、家族が同居していることを理由に、介護保険で自宅にヘルパーが訪問して家事を手伝う生活援助の利用をさせないケースが相次いでいることを受け、そうした運用をしないよう、都道府県に通知した。2006年度から要介護度が軽度の人の訪問介護利用が制限されたのに伴って、利用を原則1人暮らしなどに限る市町村もでてきたが、厚労省は家族の負担を軽減するという制度本来の趣旨とは異なるとしている。訪問介護には食事や入浴などの身体介護と家事をする生活援助がある。厚労省は、2000年度の制度導入時に、生活援助の利用は「家族が障害、疾病などで、利用者や家族が家事を行うことが困難な場合」とする基準を示した。その後も基準に変更はなかったが、06年度の制度改正以降、軽度者はなるべく自分で家事をするよう国が徹底したことで、この基準を根拠に給付条件を厳しくした市町村が増えたとみられる。(平成20年2月4日 中国新聞) ES細胞、赤血球になる細胞株作成 あらゆる臓器や組織に育つ能力を持つマウスの胚(はい)性幹細胞(ES細胞)から、赤血球のもとになる細胞株を作ることに、理化学研究所の研究チームが成功した。細胞株は試験管内で長期間増殖させることができ、赤血球を効率よく大量に作ることが可能。チームは近く、ヒトの人工多能性幹細胞(iPS細胞)を使った研究を始める予定で、成功すれば、献血に頼らず、感染症の心配のない輸血が実現する。骨髄液や臍の緒の血液に含まれる血液幹細胞から赤血球を作った例はあるが、効率の悪さが実用化への課題になっていた。理研バイオリソースセンター(茨城県つくば市)の中村幸夫・細胞材料開発室長(血液学)らは、8種類のマウスES細胞と、細胞増殖作用などがある6種類のたんぱく質を使って実験した。組み合わせを変えながら63回試み、三つの組み合わせで赤血球のもとになる赤血球前駆細胞株を作ることに成功した。この株を貧血のマウスに注射すると、マウスの体内で赤血球が増加し、症状を改善できることを確認した。がん化などの問題も起きていないという。中村室長は「一日も早い臨床応用を目指したい」と話している。(平成20年2月6日 毎日新聞) 腰痛治療、自己細胞で椎間板再生 東海大の研究チームは椎間板(ついかんばん)の再生を目指す腰痛の新治療法の臨床試験研究を今春から開始すると発表した。手術で取り出した椎間板の細胞を、骨髄中の幹細胞を使い体外で活性化させてから患者に戻す方法で、世界初の試みという。研究チームは「治癒効率を高め、患者の経済的な負担も少なくできるなど、社会的意義は大きい」としている。同大の持田譲治教授(整形外科学)らは94年から、椎間板の変形を遅らせる基礎研究に取り組み、これまで不要とされてきた椎間板の髄核に、髄核を取り囲む線維輪細胞を活性化させる効果があることを突き止めた。マウスやウサギを使った動物実験で、椎間板にこの細胞を移植すると変形を抑えることが分かった。しかし、髄核細胞はそのままでは活性が低く効果は不十分。そこで、この細胞を骨髄中に含まれる幹細胞と一緒に培養し、効率よく活性化させる方法も開発。ヒトの場合、骨髄中の幹細胞と一緒に培養すると、単独培養に比べ、1細胞あたりの活性の度合いが約5倍になるという。一方、マウスにヒトの髄核細胞を移植しても、がん化などの異常は起きなかった。研究チームは東海大医学部倫理委員会の承認を得たうえ、厚生労働省からの了承も受けている。臨床試験では、椎間板の患部を切除する従来の手術で摘出した椎間板から、髄核の細胞を分離。同時に骨盤から骨髄液も採取し、幹細胞を分離して、髄核細胞と一緒に培養する。活性化した髄核細胞を、摘出手術から1週間後、ある程度変形が進んだ椎間板内に移植する。対象患者は20歳以上30歳未満の10人で、実施後3年間経過観察するという。 《腰痛と椎間板》国内の腰痛患者は800万〜1000万人といわれる。このうち約半数が椎間板の変形が原因とされる。椎間板は、背骨の一つ一つの骨の間をつなぐ軟骨状の組織。皮の厚いまんじゅうのような構造で、中心部を髄核、周囲を線維輪と呼ぶ。刺激の積み重ねや加齢により細胞や組織が傷み、飛び出した髄核が神経を圧迫するなどして、痛みやしびれを引き起こす。これまで髄核は脊椎(せきつい)発生期の遺物で、成人後は不要と考えられていた。(平成20年2月4日 毎日新聞) 難病ALS、進行関与の細胞特定 全身の運動神経が侵される難病「筋萎縮(いしゅく)性側索硬化症(ALS)」の進行に、神経細胞のネットワーク作りに重要とされるグリア細胞のうちの2種類が関係していることを、理化学研究所などのチームが突き止めた。治療法の開発につながる可能性がある。理研脳科学総合研究センターの山中宏二・ユニットリーダーらは、特定の細胞から遺伝型のALSに関係する遺伝子変異を取り除けるモデルマウスを作った。このマウスを使い、グリア細胞のうち、神経細胞を支え養う働きがあるアストロサイトから、変異型遺伝子を取り除いた。すると病気の進行が大幅に遅れた。また、傷んだ神経細胞を修復する働きがあるというミクログリアが病巣で神経細胞に障害を与えていることもわかった。ALSの進行を遅らせる有効な治療法として、この二つのグリア細胞を標的とした幹細胞治療法や薬剤の開発が考えられる。(平成20年2月4日 朝日新聞) ES細胞、網膜細胞作成に高効率で成功 あらゆる細胞になる能力を持つヒトの胚(はい)性幹細胞(ES細胞)から、目の網膜細胞を高い効率で作り出すことに、理化学研究所などのグループが成功した。病気で失われた網膜細胞を体外で再生させて移植する再生医療の実現に、大きく近づく成果。今後は、できた細胞の機能を調べるとともに、京都大で開発され、拒絶反応の問題を回避できる「人工多能性幹細胞(iPS細胞)」での応用を試みるという。光を感知する視細胞や、網膜に栄養を与える網膜色素上皮細胞が、20〜30%の効率で作れた。マウスで05年に成功した際は未知の成分を含む牛の血清などを使ったが、今回は安全性に問題のない2〜4種類の物質で成功させた。ヒトのES細胞の例は海外でわずかに報告されているが、数%の効率だった。日本に約3万人の患者がいる網膜色素変性症や、欧米で高齢者の失明原因の1位の加齢黄斑変性症は、視細胞が徐々に失われる病気で、有効な治療法はほとんど確立されていないという。理研発生・再生科学総合研究センター(神戸市)の笹井芳樹グループディレクターは「ES細胞と性質が同じiPS細胞に応用できるので、国内の研究機関に積極的に技術移転したい」と話している。(平成20年2月4日 毎日新聞) インフルエンザ、欧州でタミフル「耐性」急増・日本流入の恐れも 今シーズンのインフルエンザで、スイスのロシュ社が製造する治療薬「タミフル」の効かない耐性ウイルスが欧州で急増している。ノルウェーなど北欧を中心に、高頻度で耐性が検出された。日本に入ってきた場合、最も一般的な治療薬であるタミフルを投与しても効果が期待できないため、専門家は危機感を強めている。今年は日本を含め、世界的にAソ連型(H1N1型)のインフルエンザが流行している。欧州の国際的な感染症の動向監視ネットワーク「ユーロサーベイランス」によると、ノルウェーではAソ連型ウイルスの70%に耐性が確認。ほかにもポルトガル(33%)、フィンランド(29%)、フランス(17%)など幅広い国々で、耐性ウイルスが高頻度で検出された。(平成20年2月3日 日本経済新聞) 他人の頭皮で毛髪再生 国循センターなど研究へ 美容外科手術などであまった他人の健全な頭皮で毛の生えやすい基盤をつくり、髪の毛が少ない人の頭髪をよみがえらせる再生医療の研究を、国立循環器病センター(大阪府吹田市)、神戸大学病院、大阪工業大のグループが始める。まず人の頭皮を利用した基盤づくりの共同研究をする。他人の細胞は、拒絶反応を引き起こす。拒絶反応を避けるため、国循センターがブタの心臓弁の再生で成功している脱細胞化処理法を用いる。これは、薬品を使わずに高い水圧をかけて組織の中にある細胞を壊し、洗い流して組織の「抜け殻」を移植するもの。新たにできる組織や臓器には患者自身の細胞が入り込み、拒絶反応を起こさないという。研究は、他人の頭皮をとりだし、1万気圧の水圧を約15分間かけて細胞を壊し除去する。残ったコラーゲンなどによる1センチ四方の基盤の性質を確認する。その後、臨床研究を検討し、基盤の上に毛根を包んでいる患者の毛包(もうほう)をつけ、患者に移植。毛根づくりの指令を出す毛乳頭(もうにゅうとう)細胞を患者からとりだして新たな頭皮に育った基盤に注射し、頭髪の再生を促す。(平成20年2月1日 朝日新聞) 米がん患者2%が「CTが原因」 コンピューター断層撮影法(CT)検査の急増に伴い、検査で放射線を浴びることが原因でがんになる人は米国で将来、がん全体の2%に達する、との試算がまとまった。米コロンビア大の研究チームが米医学誌に報告した。研究チームによると、1回のCT検査で2〜3回放射線を浴び、その放射線量は 30〜90ミリ・シーベルトに達する。これは胸部エックス線撮影の最大9000倍に上る。CT検査は使い勝手が良く、米国民がCT検査で放射線を浴びる回数は、1980年の300万回から2006年の6200万回へと大幅に増えた。この影響を調べるため、研究チームは、原爆の被爆者の発がんリスクと比較した。その結果、91〜96年にはCT検査による被ばくが、米国のがん発症者の原因の0.4%にとどまっていたが、将来は1.5〜2.0%に高まるという。研究チームは「特に子供は放射線でがんが引き起こされる危険性が高く、代替策を講じて、CT検査の回数を減らすべきだ」としている。CT検査の3分の1は不要とする研究もあり、必要のない検査を受けないよう訴えている。日本の場合、がんにかかる人の3.2%は、放射線診断による被ばくが原因と推定される、との報告が、英国オックスフォード大グループの国際調査で2004年にまとまっている。日本はCTの設置台数が多く、国民が受ける検査回数が、調査対象の15か国の平均に比べ1.8倍と多いことが背景となっている。放射線を浴びると、正常細胞を傷つけることにより、がんを引き起こすとされている。(平成20年1月27日 読売新聞) 抗がん剤がリウマチに効果 抗がん剤として開発された薬が、関節リウマチ治療に効果があることを東京医科歯科大の上阪等准教授らのチームが動物実験で確認した。関節の痛みの原因となっている炎症や、細胞の異常増殖を直接抑える画期的な薬として期待される。免疫の過剰な働きによって起こる関節リウマチの薬のほとんどは免疫力を抑える治療を目指していたが、患者の病気への抵抗力を低下させるという問題があった。この薬が実用化されれば、こうした副作用を避けられる可能性があるという。関節リウマチは、関節で「サイクリン依存性キナーゼ」という物質が活性化、滑膜細胞が異常に増殖するのが主な原因。(平成20年1月26日 中国新聞) ボツリヌス毒注射の副作用で16人が死亡 美容整形にも使われるボツリヌス菌毒素の注射による副作用で、9年間に16人が死亡したと、米消費者団体「パブリック・シチズン」が発表した。ボツリヌス毒は、神経を一時的にまひさせ、筋肉を弛緩させる。筋肉が異常に緊張する病気などの治療のほか、眉間のしわを取る美容整形にも使われる。同団体は、製薬会社から米食品医薬品局(FDA)への自発的な副作用報告を分析。まひの影響で飲食物が誤って気管へ入り、肺炎を起こすといった例が、1997年11月〜2006年12月に米国内で180件あり、16人が死亡していた。 死者のうち4人は少年だった。副作用は病気治療で多いが、しわ取りでも少なくとも1人が死んでいた。(平成20年1月26日 読売新聞) ステロイド薬と抗アレルギー薬の併用で花粉症に効果 英系製薬会社のグラクソ・スミスクラインは、同社が扱うステロイド薬と抗アレルギー薬の併用治療に関する調査結果を発表した。花粉症などアレルギー性鼻炎の患者を対象に実施した。83%の患者がくしゃみや鼻水などの症状が改善し、32%の患者は症状が治まった。花粉症シーズンを迎え、医師に併用治療を提案し処方の拡大を狙う。調査は2007年1月から5月まで、約2000人の花粉症などの患者を対象に実施した。患者にステロイド薬「フルナーゼ」と抗アレルギー薬「ジルテック」の両方を投与して、症状の改善の様子を4週間観察した。(平成20年1月24日 日経産業新聞) 「iPS細胞で心筋再生」 人間の皮膚から様々な細胞に変化できる万能細胞(iPS細胞)を作製した京都大の山中伸弥教授と、筋肉から作った細胞シートで重い心臓病の治療に成功した大阪大の澤芳樹教授が、iPS細胞を使った共同研究を始めることになった。世界初の二つの成果を組み合わせ、心筋の再生医療を目指す。一方、京都大は山中教授をトップとする「iPS細胞研究センター」の設置を正式に発表し再生医療の実現に向け、万能細胞研究が大きく動き出した。澤教授らは昨年、患者の足の筋肉の細胞をもとにシートを作製。心臓移植が必要だった患者の心臓の周囲に張り付け、心機能の回復に成功した。シートは心筋にはなっていないため、iPS細胞から変化させた心筋でシートを作り、治療に生かしたい考えだ。京大の研究センターは、昨年10月に開設された「物質―細胞統合システム拠点」の一部門。教授や研究員、技術職員ら10〜20人でつくる「専任チーム」と、京大再生医科学研究所などから参画する「兼任チーム」数チームで構成される。当面は、京都市内にある民間研究施設「京都リサーチパーク」内の研究室を借り、2年後をめどに専用研究棟を建設する。iPS細胞の研究は、国内の研究者を結集したコンソーシアム(共同体)を設け、オールジャパン体制で取り組む予定で、京大のセンターがその中心になる。山中教授はこの日の記者会見で「iPS研究は10年、20年と息の長い取り組みが必要なので、若い研究者を積極的に育てたい」と語った。(平成20年1月22日 読売新聞) コーヒー、1日2杯以上で、流産の危険2倍 1日に2杯以上コーヒーを飲む妊婦は飲まない人と比べ、流産の危険が2倍になる。そんな調査結果が米国最大の会員制健康医療団体「カイザー・パーマネント」の研究チームによって明らかになった。米産婦人科ジャーナルに掲載された論文によると、研究チームは1996年10月から98年10月にかけ、同州サンフランシスコの1063人の妊婦を調査。その結果、1日にコーヒー2杯分に相当する200ミリグラムのカフェインを摂取した妊婦はカフェインを摂取ない妊婦と比べ、流産する割合が2倍に高まった。コーヒーだけでなく紅茶などを通じ、カフェインを摂取した妊婦も流産の危険が高かったことから、研究チームはカフェインが原因物質と結論付けた。カフェイン摂取は胎盤の血流減少などを引き起こし、これらが胎児に悪影響を与える可能性があるという。(平成20年1月23日 毎日新聞) エボラウイルスを無毒化 感染すると致死率が50−90%と高く、ワクチンも治療薬もないエボラ出血熱の原因であるエボラウイルスを遺伝子操作で無毒化し、実験用の特殊な人工細胞の中でしか増えないようにすることに、東京大医科学研究所の河岡義裕教授、海老原秀喜助教らが世界で初めて成功し、米科学アカデミー紀要に発表した。ウイルスの危険性が研究のネックだったが、この無毒化ウイルスを使えば、治療薬探しなどの研究が進むと期待される。 このウイルスをワクチンとして使う道も考えられるという。チームは、遺伝子からウイルスを合成する「リバースジェネティクス」という手法を使い、エボラウイルスが持つ8個の遺伝子のうち、増殖に欠かせない「VP30」という遺伝子だけを取り除いたウイルスを作製した。できたウイルスは、通常の細胞の中では増えず、毒性を発揮しないが、VP30遺伝子を組み込んだサルの細胞の中でだけ増殖。それ以外の見た目や性質は、本物のエボラウイルスと変わらず、治療薬探しなどの実験に使えることを確認した。(平成20年1月22日 中国新聞) 新型インフルエンザ対策ワクチン 新型インフルエンザの流行初期に接種する「プレパンデミックワクチン」について、厚生労働省は、備蓄計画を現在の2000万人分から3000万人分へ拡大する方針を決めた。06年度にベトナムとインドネシアのウイルス株の計1000万人分を製造(予算45億円)。07年度は、中国のウイルス株の1000万人分を3月までに製造(同43億円)し終える予定だ。新たに追加するウイルス株の種類や製造時期は未定だが、厚労省はウイルス株を多様化させる考えという。厚労省の推計では、新型インフルエンザが世界的に大流行した場合、国内で4人に1人が感染し、最大で約2500万人が医療機関を受診し、約64万人が死亡する、とされる。(平成20年1月22日 朝日新聞) ES細胞で筋ジス治療 筋肉の力が徐々に失われる遺伝性疾患の筋ジストロフィーの症状を示すマウスに、遺伝子操作した胚性幹細胞(ES細胞)を注射して、筋肉の機能を一部回復させることに成功したと、米テキサス大の研究チームが米医学誌ネイチャーメディシン電子版に発表した。筋ジストロフィーのマウスを、あらゆる細胞に分化する能力を持つES細胞の移植で治療したのは初めて。遺伝子を操作するため、すぐには人への応用はできないという。 筋ジストロフィーのうち患者の多いデュシェンヌ型は、筋細胞の形を保つタンパク質「ジストロフィン」が遺伝子変異のため作られず、筋力の低下や筋委縮が起きる。研究チームは、マウスのES細胞を培養し、筋細胞への分化を促進する遺伝子「Pax3」を人工的に導入。筋細胞になるよう分化し始めたものだけを取り出した。これを病気のマウスの大動脈に注射したところ、1カ月後には筋細胞になって筋肉に定着し、ジストロフィンも作られていた。通常のマウスほど強くないが、ある程度筋力が回復したという。ES細胞を注入する治療では、無限に増殖するがん化が懸念されるが、筋細胞に分化するものだけを厳選した結果、3カ月後にもがんは起きなかったとしている。(平成20年1月21日 中国新聞) 胆石の病歴、胆道がんになる確率2.5倍 胆石を患ったことがある人は、そうでない人に比べて胆道がんになる危険性が2〜3倍に高まることが、厚生労働省の研究班の大規模調査で分かった。また、胆道がんの一種の肝外胆管がんは、体格指数(BMI)が27以上の人は、23未満の人に比べて1.8倍も発症の恐れが高いなど、太っているほど危険性が高まることも分かった。BMIは体重を身長で2回割り算して算出する。調査は、当初40〜69歳だった秋田、茨城県などの男女10万人を10年以上にわたり追跡調査。この間に235人が胆道がんと診断され、内訳は胆のうがんが93人、肝外胆管がんが142人だった。こうした患者と、胆石の病歴、肥満などとの関連を調べたところ、胆石の病歴を持つ人は、2.5倍ほど胆道がんになる確率が高く、特に女性では3.2倍高まることが判明。胆のうがんは3.1倍、肝外胆管がんは2.1倍、それぞれ危険性が高まっていた。胆石が胆道がんになる危険性を高める一因だという指摘は以前からあったが、大規模調査で確かめたのは初めて。(平成20年1月11日 読売新聞) 万能細胞「お分けします」 理化学研究所バイオリソースセンターは3月から、京都大学の山中伸弥教授のグループがマウスの皮膚細胞から世界で初めて作製した万能細胞(マウスiPS細胞)を希望する研究者に配布する事業を始める。iPS細胞を多くの研究者に利用してもらうことで、再生医療などの研究を加速させるのが狙い。iPS細胞は、さまざまな臓器・組織の細胞に変化する万能細胞の一種。山中教授らは人間でも同様にヒトiPS細胞を作製しているが、受精卵を使わず作製できることから世界的に注目されている。特許取得の手続きも済んだことから、細胞バンク事業に実績のある同センターは京大から依頼を受けて、希望する国内外の研究者に提供することにした。 今週にもiPS細胞の培養を開始し、3月から提供を始める。費用は約100万個の細胞が入った試験管1本で実費1万2000円。提供を受けた研究者が論文を発表する場合は、京大との共同研究になる。同センターはヒトiPS細胞についても4月以降配布する予定。(平成20年1月8日 読売新聞) ピロリ菌から発がんたんぱく質 人の胃にすみ着くピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)がつくるたんぱく質にがんを引き起こす働きのあることを、北海道大遺伝子病制御研究所の畠山昌則教授らのグループがマウスの実験で明らかにした。今週の米科学アカデミー紀要電子版に発表する。胃がんなどを起こす仕組みの解明につながる成果だ。ピロリ菌が胃の粘膜の細胞にくっつくとCag(キャグ)Aというたんぱく質を細胞内に打ち込むことが知られている。畠山さんらはCagAを作るピロリ菌の遺伝子を取り出してマウスの受精卵に組み込み、全身の細胞にCagAが入るとどうなるかを調べた。すると、約200匹のマウスの半数以上は生後3カ月までに胃の粘膜の細胞が異常増殖して胃壁が厚くなり、その後約20匹で胃にポリープができた。さらに1年半以内に2匹が胃がん、4匹が小腸がんを発症。白血病になったマウスも17匹いた。これまでの細胞レベルでの研究で、CagAが細胞内で別のSHP-2というたんぱく質と結びつくと細胞のがん化が起きることを突き止めていたため、SHP-2と結合しないように細工したCagAをつくらせてみると、マウスはがんにならなかったという。畠山さんは「CagAががんを起こすことが、個体レベルで証明できた。将来、CagAとSHP-2との相互作用を妨げる薬の開発ができるかもしれない」という。(平成20年1月8日 朝日新聞) |