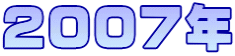
|
|---|
新型万能細胞で脊髄損傷治療 慶応大の岡野栄之教授と京都大の山中伸弥教授のチームは25日、山中教授が人の皮膚から世界で初めて作製した新型万能細胞(iPS細胞)のサルを使った治療技術の開発実験に着手、脊髄(せきずい)を損傷した患者に生かせる治療技術を2年後をめどに確立したいとの考えを発表した。 iPS細胞の研究者ら約1000人が参加して京都市内で開かれたシンポジウムで明らかにした。 研究チームは、すでにネズミのiPS細胞を神経細胞に成長させて、脊髄損傷を起こしたネズミの運動機能を一部回復することに成功。 来年から人のiPS細胞を神経細胞に成長させ、サルを使って患者に応用できる治療技術の開発に取り組む。(平成19年12月26日 日本経済新聞) 心筋こうそく患者に再生医療、幹細胞注射で血流改善 大阪大学の澤芳樹教授らは来年初めにも、心筋こうそくや狭心症など重い心臓病患者の治療に再生医療の新しい手法を応用する。詰まった血管の代わりにバイパスをつなぐ手術に合わせて、血流を改善する効果のある幹細胞を心臓に注射する。心臓病が重症化するのを防ぐ治療法として、有効性や安全性を検証する。厚生労働省のヒト幹細胞の臨床研究指針に基づき実施する。心筋こうそくや狭心症の患者は冠動脈バイパス手術を受けるケースが多いが、細い血管部分など血流の改善が難しい個所もあり、機能を十分回復できない場合もある。(平成19年12月21日 日本経済新聞) 夫の喫煙で危険性2倍 吸わない女性の肺がん 自分はたばこを吸わないのに夫が吸う女性は、夫も吸わない女性と比べ肺腺がんになる危険性が約2倍高まるとの疫学調査結果を厚生労働省研究班が発表した。夫の1日の喫煙量が20本以上だと、リスクがさらに高まるという。同センターの最新の推計値によると、2001年に肺がんを発症した女性は2万1000人あまり。 別の調査では、肺がんの女性の約70%は非喫煙者とのデータもある。調査は岩手、秋田など全国8県の40−69歳のたばこを吸わない女性約2万8000人が対象。平均13年間の追跡調査で109人が肺がんと診断された。このうち肺腺がんだったのは82人で、さらに夫が喫煙者、もしくは以前喫煙者だった女性は67人。統計学的な計算によると30人は受動喫煙がなければ肺腺がんにならずに済んだはずだという。(平成19年12月12日 中国新聞) 新型万能細胞、貧血治療に成功・米チームがマウス実験 京都大の山中伸弥教授が手法を開発した皮膚からつくる「万能細胞(iPS細胞)」を使ってマウスの貧血を治療することに、米ホワイトヘッド研究所のチームが成功、米科学誌サイエンス電子版で発表した。山中教授らが昨年6月、世界で初めてマウスのiPS細胞づくりに成功してから約1年半という短期間で、治療に役立つことを証明した。この分野の研究の競争激化があらためて示された。実験に使ったのは、赤血球が鎌の形(3日月形)に変形し、酸素運搬能が低下する「鎌状赤血球貧血」と呼ばれる病気の原因遺伝子を組み込んだマウス。しっぽから採取した皮膚細胞に計4種類の遺伝子を組み込んで、まずiPS細胞を作製した。次に、iPS細胞に含まれる貧血の原因遺伝子を、特殊な方法で正常な遺伝子に置き換え、血球などのもとになる造血幹細胞にまで成長させてマウスの体内に戻した。(平成19年12月17日 日本経済新聞) 食後の血糖管理盛り込む 世界160か国以上の医師らで構成する国際糖尿病連合は、新しい糖尿病の治療指針を発表した。糖尿病患者に、食後2時間の血糖値が140(単位・mg/dl)を下回ることを奨励している。現在は空腹時の血糖管理が重要とされ、国内でも糖尿病かどうかの判定基準の一つに、空腹時血糖の数値が使われている。しかし、血糖値は通常、2〜3時間で食前の数値に戻る。糖尿病予備軍などの場合、空腹時は正常でも、食後、極端に血糖値が上昇しているケースがあり、空腹時血糖の測定だけでは、こうした患者を見逃す可能性もある。通常、血糖値が正常な場合、食後の血糖値は140を超えることはあまりない。ガイドラインでは、血糖値を自己測定できる装置を使うなどして食後の血糖値を管理すれば、食事や運動などの治療計画に役立ち血糖値を目標内に引き下げて維持することも可能としている。(平成19年11月30日 読売新聞) 大豆に動脈硬化防止効果 大豆をたくさん食べる女性は、脳梗塞や心筋梗塞になりにくいことが、厚生労働省研究班の調査でわかった。閉経後の女性で特に顕著で、大豆に含まれるイソフラボンという物質が、女性ホルモンと同様、脳梗塞などの原因となる動脈硬化を防ぐ効果を持つらしい。研究班は、40〜59歳の男女約4万人を、1990年から13年間追跡。大豆を食べた回数、みそ汁を何杯飲んだかを記録してもらい、イソフラボンの推定摂取量を計算。多い順に5グループに分けて分析した。その結果、最もたくさん摂取した女性のグループの脳梗塞や心筋梗塞になる危険性は、最も少ないグループに比べて0.39倍と低いことがわかった。閉経後の女性に限ると、危険性は0.25倍とさらに下がった。(平成19年12月1日 読売新聞) iPS細胞、ヒトの皮膚から万能細胞 ヒトの皮膚細胞から、心筋細胞や神経細胞などさまざまな細胞に分化する能力を持つ万能細胞「人工多能性幹細胞(iPS細胞)」を作り出すことに成功した。患者自身の遺伝子を持つ細胞を作り、治療に利用することに道を開く技術。クローン胚から作る同様の能力を持つ胚性幹細胞(ES細胞)と違い、作成に未受精卵を使うなどの倫理的問題を回避できる。拒絶反応のない細胞移植治療などの再生医療や新薬開発など、幅広い応用に向けた研究が加速しそうだ。京大の山中伸弥教授と高橋和利助教らは、体細胞を胚の状態に戻し、さまざまな細胞に分化する能力をよみがえらせる「初期化」には四つの遺伝子が必要なことを発見し、昨年8月にマウスの皮膚細胞からiPS細胞を作ることに成功。これを受け、世界の研究者がヒトのiPS細胞の開発を目指し、激しい競争を繰り広げていた。山中教授らは、マウスでの4遺伝子と同様の働きをするヒトの4遺伝子を成人の皮膚細胞に導入し、ヒトのiPS細胞を開発することに成功。この細胞が容器内で拍動する心筋や神経などの各種細胞に分化することを確認した。iPS細胞をマウスに注入すると、さまざまな細胞や組織を含むこぶができ、多能性を持つことが示された。一方、ウィスコンシン大のジェームズ・トムソン教授らは、胎児や新生児の皮膚細胞から、京大チームとは異なる組み合わせの4遺伝子を使い、iPS細胞を作ることに成功した。英紙によると、世界初の体細胞クローン動物、羊のドリーを誕生させた英国のイアン・ウィルムット博士は、今回の成果を受け、ヒトクローン胚研究を断念する方針を決めたという。 クローン胚由来のES細胞より、iPS細胞の方が治療には有望と判断したためだ。一方、初期化に使う4遺伝子にはがん遺伝子も含まれ、発がんなどの危険性がある。今後は安全性の確保が研究の焦点となりそうだ。(平成19年11月21日 毎日新聞) 太り過ぎでがん危険高まる 世界がん研究基金は太り過ぎが少なくとも6種類のがんを引き起こす危険性があると発表した。研究者は、がんの危険性を下げるためには体格指数「BMI」は25未満が望ましいとの考えを示した。報告書は1960年代以降の7000件以上の研究結果を分析。太り過ぎと、食道がんや膵臓がん、腎臓がんなどの間には明確な関連があると結論付けた。報告書は、わずかな体重超過でもがんの危険性が高まると警告。ベーコンなどの加工肉は腸がんの危険性が高まるため避けるべきだとし、食べる量は牛肉などの赤肉を週500グラム以内にすべきだと勧告している。ファストフードや甘い飲料、過度のアルコールも勧めないとしている。(平成19年11月1日 中国新聞) 循環器病の発症、果物の摂取で2割減 果物をたくさん食べる人ほど脳卒中など循環器病のリスクが低くなる、という調査結果を厚生労働省研究班が発表した。岩手、秋田、長野、茨城、新潟、高知、長崎、沖縄の8県に住む男女8万人に野菜や果物の摂取量をアンケート。がんと循環器病の発症を最長7年間追跡した。国立がんセンター予防研究部長が主任研究者となった調査で、1日の摂取量で対象者を4グループに分けて発症率を比べた。果物の摂取量が最も多いグループ(平均280グラム)は、最も少ないグループ(同35グラム)より発症リスクが19%低かった。果物100グラムはみかん1個、りんご半分に相当する。たばこを吸わない人の発症率が低くなる傾向がみられ、吸う人は同じ量の果物を食べても効果が小さい可能性があるという。今回の調査では、野菜と循環器病、野菜や果物とがん全体では関連が認められなかった。坪野吉孝・東北大学公共政策大学院教授(疫学)は「これまで考えられていたほど野菜と果物の病気の予防効果ははっきりしなかったが、個別のがんでは効果が認められるものもある。健康全般に良いことには変わらない」と話している。(平成19年10月25日 朝日新聞) 妊婦喫煙で子の肥満率3倍 妊娠初期の女性が喫煙者だと、生まれた子どもが10歳になった時点で肥満になる確率が、非喫煙者に比べ約3倍高いことが山梨大医学部の山県然太朗教授らの調査で分かった。1991−97年に妊娠した山梨県の女性約1400人を追跡調査し、10歳の子ども約1000人のデータを分析した。妊婦の生活習慣が子どもの健康に与える影響についての長期的な調査は珍しい。調査によると、女性が妊娠3カ月の時点で喫煙していると、10歳となった子どもが肥満になる確率は、非喫煙の場合の2.9倍高かった。また、妊娠中に規則正しく朝食を取っていない女性の子どもも、2.4倍の高確率で肥満になっていた。肥満の判定には、肥満度を測定する国際的な指標となっている体格指数「BMI」を低年齢向けに換算して用いた。(平成19年10月24日 中国新聞) アルツハイマー病 高学歴ほど進行速く 高学歴の人ほど、アルツハイマー病による記憶能力低下は遅い時期に始まるが、いったん低下が始まると、病状の進行度は学歴の低い人に比べ速いことが、米アルバート・アインシュタイン大の研究で明らかになった。 研究チームは「高学歴の人は"認知力の蓄え"があるために、ある一定レベルまで病状が進むまで症状が見えないのでは」と指摘している。研究チームは、1980年代からニューヨーク市の高齢者488人に対し、記憶力のテストを定期的に実施。結果的にアルツハイマー病などの認知症と診断された117人について詳しく検討した。その結果、教育を受けた期間が1年長いと、記憶能力の低下が始まる時期が約2か月半遅れたが、いったん記憶障害が始まると、記憶低下の速度が教育期間1年あたり4%速まっていた。研究チームは「今回の結果は、患者の症状が速く進むかゆっくり進むかを、アドバイスするのに重要になる」としている。(平成19年10月24日 読売新聞) 膵臓がんリスク、喫煙男性は1.8倍 たばこを吸っていたり、糖尿病と診断された男性は膵臓がんのリスクが約2倍高くなることが厚生労働省研究班の大規模調査でわかった。調査は、1990年と93年に、茨城や長野、大阪など9府県に住んでいた40〜60歳代の男女約10万人が対象。喫煙や病歴、運動などについてアンケート調査を実施。その後、2002年まで膵臓がんになるリスクとの関連を調べた。その結果、喫煙していた男性は、非喫煙者に比べて、膵臓がんになるリスクが1.8倍高かった。また、過去に糖尿病と診断された男性は、そうでない男性よりも、リスクが2.1倍高かった。女性では、男性と同じ傾向が確認された。一方、膵臓がんの発症リスクを高めると考えられていた肥満のリスクは確認されなかった。運動による予防効果も認められなかった。(平成19年10月6日 読売新聞) がんワクチン「効果あり」 進行した膵臓がんや食道がんなどを対象にしたがんワクチンの臨床研究で、患者34人のうち22人に病状の悪化を防ぐ効果が確認された。日本癌学会総会で、東大医科学研究所ヒトゲノム解析センターの中村祐輔教授が発表した。目立った副作用は出ていないという。新薬として開発を進める方針だ。がんワクチンは、がん細胞に狙いを絞って免疫反応を高め、がんをやっつけようという手法。中村教授らが、正常細胞ではほとんど働かないのに、それぞれのがん細胞で特徴的に活発に働いている遺伝子を特定。その中から強い免疫反応を導くものを選び出し、複数のワクチンを作った。膵臓、食道のほか、肺、肝臓、膀胱、大腸の各がんを対象に、岩手医大や福島県立医大、山梨大、和歌山県立医大、九州大などが昨秋から順次、臨床研究を始めた。今はワクチン自体に毒性がないかどうかを確認している段階で、標準的な治療法がないと判断された患者らに説明し、同意を得て研究に参加してもらっている。9月末までに投与した患者は67人おり、このうち、計画通り投与し、3カ月以上過ぎた34人について分析した。がんが縮小したと評価された人は膵臓、膀胱、大腸の各がんだった5人。がんが大きくならずに安定していた人が17人で、計22人で効果があったと判断した。がんに対する免疫反応が高まっていることも確認され、特に比較的若い人で顕著だった。また、投与の結果、半年以上、病状が安定している患者がいた一方、効果のみられないケースもあった。グループが、がんワクチンに期待するのは、手術後の再発予防。実用化にはさらに研究を重ねる必要があるが、新薬の承認申請を目指し、臨床試験(治験)を担当する厚生労働省の関連組織と相談に入りたい考えだ。(平成19年10月5日 朝日新聞) コーヒー派に膵臓がん少ない コーヒーを1日に3杯以上飲む男性は、ほとんど飲まない男性に比べ、膵臓がんになる危険度が低いとの疫学調査結果を、厚生労働省研究班がまとめた。コーヒーは膵臓がんの危険を高めるとの調査が1981年に米国で発表されたが、異論も出てはっきりしていなかった。今回は男性だけで予防効果がある可能性が示されたが、研究班は「コーヒー以外の生活習慣や体質の影響もあるのかもしれない」としている。調査は、全国9府県の40−69歳の男女約10万人が対象。1990年から平均約11年の追跡期間中に233人が膵臓がんになった。年齢や喫煙などの影響を取り除いてコーヒー摂取量との関係を調べたところ、ほとんど飲まない男性が膵臓がんになる危険度に比べ、1日に1−2杯飲む男性の危険度はやや低く、3杯以上の男性はさらに低いとの結果で、よく飲む男性ほど危険度が下がる傾向があった。(平成19年10月5日 中国新聞) 肺がん発見率9割 血液検査で精度3倍 血液検査で肺がんを高精度で見つける新たな腫瘍マーカーの組みあわせを、東大医科学研究所ヒトゲノム解析センターが開発した。発見率は約9割で、いま診療で主に使われている3種類に比べて1.5〜3倍高いという。また、手術後の経過を予測する組織検査の組み合わせも考案しており、肺がんの早期発見や術後の治療法選択に役立ちそうだ。肺がんで死亡する人は年に5万人を超え、がんによる死亡で最も多い。早期発見が難しく、発見時にはすでに悪化していて手術不可能な例の多いことが一因という。グループは、肺がん細胞で特異的に作られるたんぱく質で、血中に分泌されているものを複数見つけた。このうち2つと、肺がんの指標として従前からあるCEAというマーカーを加えた3つの組み合わせで、肺がん患者と健康な人の血清を対象に検出精度を確かめた。その結果、肺がんの8割余りを占める非小細胞肺がんの場合、89.1%の感度で検出できることが分かった。小細胞肺がんの場合も、別の3つのマーカーの組み合わせによる血液検査で87.5%の検出率だった。さらにグループは、肺がんは同じ早期で手術をしても、経過に差があることに着目。術後5年以上追跡している約400人の患者の肺がん組織を分析し、特定のたんぱく質3つの内いくつ検出されるかで、「5年後の生存率が8割程度」と経過の良い場合から、「生存率2割程度」と悪い場合まで4段階で判別できる方法を開発した。経過が予測できれば、抗がん剤などの治療方法や開始時期の選択に役立つ。(平成19年10月4日 朝日新聞) 椎間板ヘルニア、原因遺伝子の一つを特定 国内で100万人以上が悩まされているとされる椎間板ヘルニアの原因遺伝子の一つを、理化学研究所などの研究チームが特定した。椎間板ヘルニアの発症への関与が判明した遺伝子は二つ目で、予防や治療法の開発につながると期待される。椎間板ヘルニアは、背骨の骨と骨の間でクッションの役割を果たす椎間板が変形し、神経を圧迫して腰痛や座骨神経痛を引き起こす病気。複数の遺伝子が関係するほか、後天的な要因も影響するとされている。患者と正常な人それぞれ約900人ずつの遺伝子を統計学的に調べた。その結果、COL11A1と呼ばれる遺伝子の差異によって、発症の可能性が最大1.4倍高まることが分かった。COL11A1は、椎間板を正常に保つ働きのある11型コラーゲン(繊維状たんぱく質)を作る遺伝子で、実際に患者の椎間板では11型コラーゲンが減少していることも確認した。このタイプの患者には11型コラーゲンを投与すれば治療できる可能性がある。遺伝的に椎間板ヘルニアになりやすいと分かれば、日常生活に注意することで予防にもつながる。(平成19年10月2日 毎日新聞) 救急蘇生術、人工呼吸は不要 心臓マッサージに効果あり 突然意識を失って倒れた人を蘇生させるための応急手当は、心臓マッサージだけで効果があり、従来勧められてきた人工呼吸は必要ないことが、日本救急医学会関東地方会の研究班の調査で分かった。研究班は02〜03年、関東各地の58病院と救急隊の協力を得て、そばに人がいる状態で突然心臓が止まって倒れ、救急車で病院に運ばれた18歳以上の患者4068人を調べた。そばにいた人から人工呼吸と心臓マッサージを受けた患者が712人で、心臓マッサージだけを受けた患者は439人。救急隊到着まで蘇生措置を受けなかった患者が2917人だった。倒れてから30日後の時点で、介護なしで日常生活が送れる状態に回復した割合は、両方受けた患者が4%、心臓マッサージだけの患者は6%で、人工呼吸なしでも変わらなかった。一方、蘇生措置なしの患者は2%にとどまった。患者の約9割を占めた救急隊到着時に完全に呼吸が停止していた人に限った分析では、回復率は心臓マッサージだけの患者が6%だったのに対し、両方受けた患者は3%で、心臓マッサージだけの患者の方が回復率が高いとの結果になった。また、蘇生措置の6割以上は一般の人が、残りは通りがかった医師ら医療関係者が実施したが、効果に差はなかった。人工呼吸は不要との結果について、長尾班長は「呼吸が止まっても12分程度は血液中の酸素濃度がそれほど下がらないことや、心臓マッサージの際の胸の動きで、空気が肺に送り込まれることなどが考えられる」と話している。心臓マッサージは、患者の意識がないことや呼吸が止まっていること、あえぐなど普通ではないことを確かめた後、両方の手のひらの付け根を患者の胸の中央に重ねて押す。体重をかけ深さ4〜5センチまで胸をへこませた後、力をゆるめて元に戻す。これを1分間に100回のペースで繰り返す。救急隊が来るか、AED(自動体外式除細動器)が届くか、患者の体が動くまで続ける。1人では消耗するため、2分程度をめどに交代で行うとよいという。(平成19年9月27日 毎日新聞) B型肝炎の父子感染拡大、育児参加で「触れ合い増」原因? 肝臓がんなどを招く恐れがある乳幼児期のB型肝炎ウイルス(HBV)について、母子間の感染が減る一方、父子感染の割合が高まっている。育児に父親が参加する機会が増えていることが背景とみられ、乳児期のワクチン接種など早急な対策が求められる。B型肝炎は血液や体液、唾液を介して感染し、ウイルスを持つ持続感染者(キャリア)が国内で100万人以上いる。成人の場合、感染しても多くは自然に治るが、3歳未満で感染すると、一部がキャリアになる。このため母親がキャリアの場合、1986年以降、生後すぐに子供にワクチン接種が行われ、母子感染は10分の1以下に激減した。一方、父子感染の割合は高まってきた。済生会横浜市東部病院こどもセンターの藤澤知雄部長らが、母子感染以外でキャリアとなり、防衛医大病院などを受診した子供を対象に、家族の血液検査などを実施。父子感染が原因だったのは、85年までの10年間で感染者20人のうち8人(40%)だったが、86年から昨年までは15人中11人(73%)と増えた。母親は妊娠時にB型肝炎検査を受けるが、父親は調べないため感染がわからず、子供へのワクチン接種も行われない。 藤澤部長は「父子の接触が濃厚になり、キスや食物の口移し、同じスプーンを使うことなどで感染が起きているのではないか」とみる。母子感染は胎内感染もあり、一昨年報告された全国25医療機関への調査では、小児の感染原因の3分の2を占めたが、それまであまり報告されていなかった父子感染も1割あった。父親になる20〜40歳代の0.6%はHBVキャリアとされる。(平成19年9月26日 読売新聞) 外径1.4ミリ、世界最細の治療用カテーテル 心臓の血管(冠動脈)が狭まる狭心症などの治療に用いる細い管(カテーテル)で、外径1.4ミリという世界で最も細いものを国立循環器病センターの竹下聡・心臓血管内科医長やテルモなどが開発した。従来のものより断面積が半分以下のため、より細い血管まで治療できる。挿入する皮膚部分からの出血の危険性が低くなる利点もある。冠動脈が狭まったり詰まったりすると、そこから先に血液がうまく流れず、狭心症や心筋梗塞(こうそく)の胸痛発作が起きる。この治療に、カテーテルを冠動脈に通してその部分を広げ、ステントという、金属でできた筒状器具を血管の内側に挿入する方法が広く行われている。通常、治療に使われているのは外径2.1〜2.7ミリ程度。新たに開発したカテーテルの断面積はこの半分以下のため、冠動脈の曲がった部分や細い部分まで届き、従来より治療ができる範囲が広くなる。さらに、内径2.5ミリほどの手首の動脈からのカテーテル挿入にも適している。カテーテルは従来、足の付け根にある太い動脈から入れることが多かった。だが治療後に6時間程度は安静にしなければならず、その後も再出血することが多かった。一方、動脈の細い手首部分から入れれば出血の危険性が低く、安静時間も半減できる。竹下さんは「従来のものより軟らかいので操作しづらく、医師の技術力が要求される。だが治療の質を上げ、患者の負担も減らすことができる」と話している。(平成19年9月19日 朝日新聞) 骨密度のコントロール機能を発見 食欲を抑制する働きがある脳内物質「ニューロメジンU(NMU)」が、骨密度の増減もコントロールしていることを、竹田秀・東京医科歯科大特任准教授(骨代謝)らの研究チームが発見した。新たな骨粗しょう症治療薬の開発につながる可能性がある。竹田特任准教授らは、正常なマウスとNMUを持たないマウスの骨密度を比較。NMUを持たないマウスは正常マウスより、骨密度が腰椎で約24%、脛骨で約29%高かった。NMUを持たないマウスの脳にNMUを投与すると、腰椎の骨密度は約20%減少したが、骨のもとになる「骨芽細胞」に直接NMUを投与しても変化はなかった。このため、NMUが脳の中で作用すると、骨芽細胞になんらかの信号が送られ、骨の生成が抑制されると考えられるという。骨粗しょう症患者は国内で少なくとも1100万人に上り、2050年には4500万人に達すると推測される。竹田特任准教授は「NMUが作用しないようにする薬が開発できれば、骨密度を増加させることができるのではないか」としている。(平成19年9月17日毎日新聞) 脳卒中後のスタチン中止で死亡リスク倍増 脳卒中後の患者がコレステロール降下薬スタチンの使用を中止すると、使用を続けた患者に比べ、1年以内の死亡リスクが倍増することがイタリアの研究で示された。 脳卒中後のスタチン使用の利益はこれまでにも複数の研究で示されている。例えば、先ごろ報告されたスペインの研究では、もともとスタチンを使用していた患者89人のうち、脳卒中後にスタチン治療を中断した患者では46人中27人が3カ月後に死亡するか寝たきりになったのに対して、スタチンを中断しなかった患者で同様の結果となったのは43人中16人であった。 今回のイタリアの研究は脳卒中を起こした人のうち、心疾患などの大きな疾患のない患者631人(平均70歳)を追跡したもの。退院時、全員にスタチンを含む薬剤の服用を指示したが、4年半後、38.9%がスタチン使用を中止していた。中止までの平均期間は48.6日であった。統計解析の結果、スタチン治療の中止は死亡の独立した危険因子となることが判明。中止した理由として、約4分の1の患者が消化不良などの軽い副作用を挙げたが、それ以外は特に理由はなかった。このほか、抗血栓薬(抗血小板薬)の使用中断によっても死亡リスク増大がみられることも明らかになった。高齢者は、関節などの痛みを訴えてスタチンを中止したがることが多く、薬のせいではないと納得させることが難しいという。スペインの研究は入院中の急性の影響に着目したもので、イタリアの研究は退院後に着目したものだが、いずれもスタチン治療継続の重要性を示すものだと専門家は述べている。(平成19年9月6日日本経済新聞) 骨粗しょう症のメカニズム解明 骨粗しょう症が起きるメカニズムの一端を、科学技術振興機構と東京大の研究チームが世界で初めて突き止めた。女性ホルモンが、骨を壊す細胞(破骨細胞)の"自殺"を促し、骨の量を保つ働きがあるという。閉経に伴って女性ホルモンが減った女性は、骨粗しょう症にかかりやすくなるが、女性ホルモンがどのように骨に作用するかはよくわかっていなかった。研究チームは、破骨細胞の内部にあって女性ホルモンの エストロゲンが取り付く受容体という部分に注目。雌マウスを遺伝子操作して受容体をなくすと、通常のマウスより破骨細胞が増えて骨の破壊が進み、骨量は約5%落ちた。さらにエストロゲンを投与すると、通常のマウスは破骨細胞の自殺を促すたんぱく質の量が増えたのに、エストロゲンの受容体をなくしたマウスに変化がなかった。厚生労働省の2005年10月の調査では骨粗しょう症で入院・治療している患者は推計で約45万人で、そのうち女性は約43万人。女性患者の87%が65歳以上で、閉経後の女性が圧倒的多数を占めている。破骨細胞:骨の表面にある細胞で、酸やたんぱく質を分解する酵素を出し、古くなった骨を壊す働きをする。同時に、「骨芽細胞」が新しい骨を作るため、骨は常に新陳代謝され、骨量も一定に保たれる。骨粗しょう症は、この両者のバランスが崩れて発症する。(平成19年9月7日読売新聞) 糖尿病は万病のもと アルツハイマー発症4.6倍 糖尿病やその「予備群」の人は、そうでない人よりアルツハイマー病になる危険性が4.6倍高いことが、九州大の清原裕教授(環境医学)らの研究でわかった。福岡県久山町の住民約800人を15年間、追跡して分析した。 がんや脳梗塞、心臓病も発病しやすいという。糖尿病が、失明などの合併症に加え、様々な病気の温床になることが浮かび、その対策の重要性が改めて示された。九大は久山町で1961年から住民健診をして、生活習慣や体質と病気の関係を研究。死亡した場合には解剖への協力を求めている。清原さんらは85年時点で、神経疾患などを研究する米国立衛生研究所の研究機関の基準で認知症ではないと判断した65歳以上の826人を追跡。00年までに集めたデータの解析を進めてきた。15年間に188人が認知症を発症し、うち93人がアルツハイマー病だった。画像検査のほか、死亡した145人は9割以上を解剖して確定診断をした。 同じ826人について、ブドウ糖の代謝能力である耐糖能の異常も調査。生活習慣が主な原因とされる2型糖尿病の病歴がある人らをアルツハイマー病調査と合わせて分析した。これら糖尿病やその予備群の人は、耐糖能異常のない人に比べて4.6倍、アルツハイマー病になる危険性が高かった。清原さんによると、脳にたまってアルツハイマー病を引き起こすとされる物質は、インスリン分解酵素によって分解される。耐糖能異常の人はインスリンが少ない場合が多く、分解酵素も減るので、アルツハイマー病の危険性が高まるという。 解剖などによる確定診断に基づいたアルツハイマー病研究で、これほどの規模のものは世界でも例がないという。また、別に40〜79歳の約2400人を88年から12年間追跡し、糖尿病とがん、脳梗塞などとの関係も調べた。その結果、糖尿病の人は、そうでない人よりがん死亡の危険性が3.1倍高く、脳梗塞も1.9倍、心筋梗塞など虚血性心疾患も2.1倍高かった。清原さんは「糖尿病対策がアルツハイマー病予防につながる可能性がある。国内ではここ十数年で耐糖能に異常がある人が女性で2割、男性で4割増えており、対策を急ぐ必要がある」と話す。(平成19年9月2日朝日新聞) アルツハイマー病発症 日本人女性にリスク遺伝子 日本人女性でアルツハイマー病の発症リスクを大きく左右する遺伝子を新潟大などのグループが見つけた。 国内の患者1526人とそうでない人1666人のDNA配列を比較した結果だ。75歳以上では女性の方が男性よりも発症率が高いという報告が内外であるが、その原因の解明につながる可能性がある。DNA配列には「SNP」(スニップ)と呼ばれるわずかな個人差があり、この個人差と様々な病気との関連が注目されている。 新潟大脳研究所の桑野良三・准教授らは、すでにアルツハイマー病関連遺伝子として知られているAPOE4遺伝子の影響を除いたうえで、約1200カ所の個人差を調べ、男女で発症リスクに差がある個所を探した。その結果、10番染色体にあるCTNNA3という遺伝子が浮上した。この遺伝子で特有なDNA配列を持つ女性は、アルツハイマー病の発症リスクが約2.6倍に高まることがわかった。この配列は女性患者の約3割、患者でない女性の約 2割が持っていた。男性ではこの配列による差はなかった。CTNNA3遺伝子の働きはまだわかっていない。桑野さんは「この部分の個人差とアルツハイマー病との関連は、欧米では出てこない。DNA配列の個人差と病気の関係には、アジア人特有のものも多数あると思われるので今後さらに詳しく調べたい」といっている。(平成19年9月2日朝日新聞) 新型インフル用ワクチン、販売了承 新型インフルエンザの流行に備え、国の薬事・食品衛生審議会医薬品第2部会は31日、国内2法人が製造販売を予定するワクチンについて、それぞれ「安全性や有効性に問題ない」として、基本的に了承した。年内にも厚生労働相が製造販売を承認する見通し。 海外メーカーはすでに新型インフルエンザ用ワクチンを製造しているが、これら2品目が承認されれば、初の国産ワクチンとなる。 厚生労働省は今年度、これらの国産ワクチンで1000万人分を備蓄する方針だ。(平成19年9月1日読売新聞) 高脂血症薬、アルツハイマー病のリスク下げる コレステロール値を下げる高脂血症治療薬のスタチン系薬剤には、アルツハイマー病になるリスクを下げる効果があるかもしれない。米ワシントン大グループが発表した。グループは認知能力が正常な65〜79歳の110人について、死後、脳を調べた。その結果、スタチンを飲んでいた人はそうでない人に比べて、アルツハイマー病患者の脳に特徴的な、細胞の外にたんぱく質がたまる「老人斑」や、細胞の中にたんぱく質がたまる「神経原線維変化」が少なかった。こうした変化が進むと、神経細胞が死に、記憶障害などが起こると考えられている。スタチンによる高脂血症改善が、アルツハイマー病発病のリスクを下げるという報告はこれまでもあった。スタチンは近年、血管の炎症を抑える効果が注目されており、高脂血症の予防と炎症抑制がともにアルツハイマー病の予防と関係しているのではないかとグループはみている。(平成19年8月29日 朝日新聞) C型肝炎ウイルスは中性脂肪で増殖 肝硬変や肝臓がんなどの原因となるC型肝炎ウイルス(HCV)は、細胞内の中性脂肪を利用して増殖していることを慶応大教授、分子生物学のグループが突き止めた。ウイルスが、脂肪を増やすよう働きかけていることもわかった。C型慢性肝炎患者に脂肪肝が多いことは知られているが、理由は分かっていなかった。グループは、ヒトの肝臓細胞を培養し、HCVに感染させた。観察の結果、ウイルスの「コア」と呼ばれるたんぱく質の働きで、細胞内の中性脂肪が増えることが分かった。さらに、中性脂肪の塊の膜の部分で新たなウイルスが作られることも分かった。HCV国内の感染者は約200万人。慢性肝炎になると、患者の一部は20〜30年で肝硬変や肝がんに移行する。肝がんによる年間の死者数約3万人のうち、75%近くがHCVに感染している。治療には、ウイルスを駆除するインターフェロンやリバビリンを併用するのが主流だが、長期間の治療が必要で、発熱や脱毛などの副作用があり、患者の半数程度にしか効かないとされる。下遠野名誉教授は「HCVの中性脂肪への付着をブロックできれば、これまで薬が効かなかった患者も治療できるかもしれない」と話している。(平成19年8月27日 読売新聞) がん抑制、細胞殺す"スイッチ"特定 がん抑制遺伝子の一つ「p53」が、異常をきたした細胞を自殺に導く際に不可欠なたんぱく質を、千葉大医学部や大鵬薬品工業などの研究チームが特定した。肺がんや大腸がんなど約半数の種類のがんで、p53が正常に働いていないことが分かっている。このたんぱく質の機能を詳しく調べれば、正常な細胞には影響を与えず、がん細胞だけを自殺させる新薬の開発につながる可能性がある。p53は人間のあらゆる細胞にあるが、通常はあまり働かず眠った状態にある。体内では常に、DNAが損傷を受けるなどして細胞に異常が起きているが、その細胞ではp53が活性化され、細胞を自殺に導く指令を出したり、増殖を止めて損傷修復の時間をかせぐなど、異常な細胞が増えるのを防いでいる。しかし、正常に働かない場合がある理由は謎だった。田中知明・千葉大助教(分子腫瘍学)らは、細胞の中で遺伝子が働く際、DNAと特定のたんぱく質が「クロマチン」と呼ばれる複合体を作ることに着目した。人間の肺がんの細胞のクロマチンを分析し、p53と結合する分子をすべて調べた結果、「CSE1」というたんぱく質を発見。肺がん、大腸がん、乳がんの細胞を使った実験で、p53とCSE1が結合しないと細胞の自殺が起こらないことを確認した。田中助教は「CSE1は細胞の生死を左右するスイッチ的な役割を持つたんぱく質と言える。CSE1をうまく利用し、がん細胞だけを効率的に自殺させることができれば、まったく新しいタイプの薬の開発につながる可能性がある」と話している。(平成19年8月24日 毎日新聞) 10キロ超の体重増に心疾患のリスク高まる 若いころやせていたのに、中年以降に10キロ以上太った男性は、体重が安定していた人に比べ、心筋梗塞など虚血性心疾患になる危険度が2倍高いとの疫学調査結果を、厚生労働省研究班が発表した。アジア人でこうした傾向が明らかになったのは初めて。研究班は「年齢が進んで運動をやめたり、基礎代謝が落ちたりしても若いころと同じ食習慣を続けると、心臓への負担が増える」と注意を促している。研究班は全国8県で40−69歳の男女約9万6000人を平成2年から最長で12年追跡。この間、男性の399人が虚血性心疾患になった。肥満度を表す国際的指標で、体重を身長で2度割って算出する体格指数BMIとの関係をまず調べたところ、BMI30以上(肥満)の男性は、標準的な体格(23以上25未満)の男性に比べ心疾患発症の危険度が1.8倍で、肥満と心疾患の関係がはっきりした。女性は発症者が少なく、関連は不明だった。そこで研究班は次に、男性の約半数に当たる約2万3000人を対象に、体重の増減との関係に注目して分析すると、20歳時点でBMI21.7未満とやせ形だった人で、調査時までに10キロ以上体重が増えた人は、増減が5キロ以内だった人と比べ、危険度が約2倍になることが分かった。(平成19年8月22日 産経新聞) 肥満の一部はウイルスが原因? 肥満の一部はウイルス感染によって起きるらしい。米ルイジアナ州立大のグループが発表した。肥満の人は、そうでない人に比べて、風邪や結膜炎の原因となるウイルスの仲間アデノウイルス36に感染している割合が高いとされているが、感染との因果関係ははっきりしなかった。研究グループは、美容のために行われる脂肪吸引で得られた人間の脂肪組織から、さまざまな細胞に変化する能力を持つ幹細胞を抽出。このウイルスを加えた。その結果、ウイルスを加えられた幹細胞の半分以上が脂肪細胞に変わったが、加えられなかった幹細胞で同様の変化を示したのはわずかだった。ウイルスが肥満の原因だとはっきりすれば、ワクチンが開発できそうだというが、研究グループは「すでに肥満の人には役立たないだろう」としている。アデノウイルス36は以前から、肥満との関連が疑われてきた。米ウィスコンシン大学の研究チームは00年、このウイルスに感染させたニワトリやハツカネズミが、感染させなかったものより脂肪を2倍多く蓄積した、という論文を発表している。(平成19年8月21日 朝日新聞) 乳がんリスク遺伝子診断、親族と比較 自分が遺伝的に乳がんや卵巣がんになりやすいかどうかを調べる検査が国内で受けられるようになった。国立がんセンターなどの臨床研究で、米国で普及してきた遺伝子検査の有効性が確認された。リスクが高いとわかれば検診を欠かさないなどの対策がとれる。ただ、将来の発症におびえることにもなりかねないため、精神的サポートを含めた遺伝カウンセリングが必須条件となる。両親や兄弟姉妹らの血縁者内で多く発症しているがんは「家族性腫瘍」と呼ばれる。このうち乳がんや卵巣がんの一部には、「BRCA1」「BRCA2」という遺伝子の変異が原因で起こるものがある。この遺伝子を血液から採取し、変異の有無を調べる検査は米国で約10年前から一般に行われ、のべ約100万人が受けている。変異がある人は将来、5〜8割が乳がんに、1〜3割が卵巣がんになるとされている。この検査が日本人にも有効かどうかを調べるため、国立がんセンターほか4病院(癌研有明病院、聖路加国際病院、慶応大病院、栃木県立がんセンター)が03年から臨床研究を実施。家族性の乳がん・卵巣がんが疑われた計135人のBRCA遺伝子を調べた。変異があったのは36人(27%)。血縁者の乳がんの発症年齢が若い場合に変異率が高いなど結果は米国の傾向とほぼ同じで、研究の総括責任者をつとめた栃木県立がんセンターの菅野康吉医師らは、日本人にも検査は有効と判断した。 検査を受けたい人は、まず乳がんや卵巣がんの病歴がある血縁者の情報を医療機関に提供。家族性腫瘍の疑いが強いと判断されれば受けられる。血縁者と本人のBRCA遺伝子を調べ、遺伝的な発症リスクが高いかどうか診断される。(平成19年8月20日 朝日新聞) 生体によくなじむ人工骨開発 東京大学医学部付属病院のチームが、患者の骨格にぴたりと合い、生体になじみやすい人工骨の開発に成功した。まだ強度に課題があり、力がそれほどかからないあごやほおなど顔面への利用が主だが、10人の患者に移植、いずれも組織とくっついていることが確認できた。同チームは全国10施設で臨床試験を申請、早ければ今秋にも着手する方針だ。新しい人工骨は、骨の元となるリン酸カルシウムを材料にし、水で固めて作る。 コンピューター断層撮影(CT)を元に、プリンターにも使われるインクジェット方式で粉末の材料を何層も吹き付け、移植先の骨の形状に合う人工骨を作る技術を開発した。セラミックスと違い、腕や足など力のかかる部位で使うには強度が十分でないが、形を自在に作れる上、組織ともなじみやすい。これまでの人工骨は、セラミックスが主流で生体にうまくくっつかないのが難点だった。このため、患者の腰骨などから提供された骨を削って成形していたが、微妙な形を仕上げることができず、顔面などの骨の成形はとくに難しかった。 同病院ティッシュ・エンジニアリング部副部長の鄭雄一教授は「今回の方法なら手術時間も大幅に短縮できる」と話している。(平成19年8月19日 朝日新聞) B型肝炎、父子間でも感染 B型肝炎ウイルス(HBV)感染が父子間で起きていることを、大阪府立急性期・総合医療センターと名古屋市立大の研究チームがウイルスの遺伝子解析で突き止めた。従来は出産時の母子感染が主な感染経路とされ、母親が感染者と分かった赤ちゃんにワクチンを接種する感染予防制度がある。しかし、父親が感染者の場合には、こうした制度はなく、研究チームは「父親の健診強化とワクチン接種の拡大が必要だ」と指摘している。 HBVに感染すると、急性肝炎や慢性肝炎、肝臓がんになる恐れがある。3歳ごろまでに感染すると、感染が継続しやすい。国内の感染者は100万人以上とされる。田尻仁・同センター小児科部長らは、子どもが感染しており、父親以外に周囲に感染源がない5家族について、HBVの遺伝子を調べた。その結果、子ども8人(3〜14歳)とそれぞれの父親のHBVの遺伝子配列がほぼ完全に一致し、父親が感染源と確認できた。HBVは血液や体液を介して感染する。傷口が触れるなどの濃厚な接触が、父子間で起きていたとみられる。母親は妊娠時にHBV検査を受けるのが一般的で、陽性なら、赤ちゃんにワクチン接種する。健康保険が適用され、予防効果も95%以上だ。一方、父親は子どもとの濃厚な接触の機会が少ないとされ、子どもへのワクチン接種は保険対象外だ。肝炎ウイルスに関する厚生労働省研究班代表の大戸斉・福島県立医大教授(輸血医学)は「HBV感染の1割程度は父子間ではないか。家族内に感染者がいる子どもへは、感染者によらず保険でワクチン接種できるようにすべきだ」と話す。(平成19年8月19日 毎日新聞) 大腸がん対策に"最新兵器" 大腸がん対策に、画期的な武器が現れた。ヘリカルCTで撮った映像をコンピューターで三次元に処理する「仮想内視鏡」だ。大腸がんは増加が予測される一方、検査への抵抗感などから検診の受診率が低迷している。仮想内視鏡は、検診を受ける側の抵抗感も低く、精度も高まることから、大腸がん検診の受診率アップに貢献しそうだ。実用化を進めているのは、国立がんセンターの森山紀之・がん予防・検診研究センター長ら。仮想内視鏡は、肺がん検診に使われるヘリカルCTを使い、映像をコンピューター処理することで、まるで内視鏡で腸内を診るようにチェックできる。従来の大腸内視鏡検査は、医師の技量によっては腸内を傷つけてしまったり、死角で病巣を見落としたりするケースがあるが、そうしたリスクはほぼ解消される。厚生労働省などのデータによると、大腸がんは現在、日本人のがん罹患率のトップを占めている。しかし、早期発見に有効な大腸がん検診の受診率は約18%と低迷している。便潜血の検査で陽性でも、内視鏡による精密検査を受ける率は6割にとどまる。これは検診を受ける側が、肛門から内視鏡を入れることに抵抗感が強いためだといわれている。仮想内視鏡は、外部から10秒程度撮影するだけ。集団検診でも、1人5分程度で済むとみられ、内視鏡と比べて検診の効率化も期待される。被曝(ひばく)リスクはあるが、X線撮影による大腸検査に比べると、5分の1から8分の1に抑えられる。国立がんセンターでは試験的に仮想内視鏡による検診を実施しているが、実用化に向け、来年度からは米、英、中、各国と臨床例を増やしていく。森山氏は「5ミリ程度の大腸がんを100%見つけることを目指す。実用化されれば、検診率が飛躍的に上がることが予想され、早期では治癒率の高い大腸がん対策に大きく寄与すると思われる」と話している。(平成19年8月8日 産経新聞) 大腸がん、生活習慣上の予防策を大規模調査 大腸がんと生活習慣の関係が、国立がんセンターや群馬大などでつくる厚生労働省究班の大規模調査で明らかになった。男性はビタミンB6摂取、女性は1日3杯以上のコーヒーで発症の危険性が下がり、適度な日光浴は男女とも直腸がん予防につながる可能性があるという。研究班は9府県の40〜69歳の男女約9万6000人を調査。コーヒーを1日3杯以上飲む女性は、ほとんど飲まない女性に比べ、大腸がんになる危険性が約3割低かった。粘膜を越えて進行する結腸がんに限ると、3杯以上の女性は飲まない女性より56%も低い。男性では、関連は見られなかった。一方、男性では、魚やナッツに含まれるビタミンB6が効果を示した。同様の男女約8万人を調査。1日当たりのB6摂取量で男性を4グループに分け、大腸がんとの関係を比べた。 その結果、最も摂取量が少ないグループは、他のグループより危険性が30〜40%高かった。週に日本酒約7合(エタノール換算で150グラム)以上飲む男性でも、B6摂取は効果があった。女性ではB6との関連は見られなかった。また、男女約4万人を対象に、体内のビタミンDの貯蔵量別に4グループに分け、直腸がんとの関係を調べたところ、最も少ないグループは最も多いグループに比べ、男性で約4.6倍、女性で約2.7倍も直腸がんになりやすかった。ビタミンDは紫外線によって多く合成されるため、適度な日光浴が、直腸がん予防につながる可能性があるとみられる。(平成19年8月1日 毎日新聞) インスリン脳内では「悪役」 不足すると糖尿病につながるホルモン「インスリン」が、脳内では老化の促進という"悪役"を演じていることが、米ハーバード大の実験でわかった。 脳内でインスリンを働きにくくしたマウスは、通常のマウスより18%も長生きした。 研究成果は米科学誌サイエンスに発表した。 インスリンは全身の細胞に作用して、栄養の利用などを制御する。 田口明子研究員らは、細胞がインスリンを受け取る際に働くたんぱく質を、脳内で半減させたマウスを遺伝子操作で作製。マウスは太り気味だが糖尿病にはならず、936日間生存した。通常のマウスは791日だった。 研究チームのM・ホワイト博士は「粗食や運動が長寿に良いのは、血中のインスリン量を下げる効果があるからだろう」と説明している。(平成19年7月29日 読売新聞) 平均寿命女性は22年連続世界1、男性も2位 06年の日本人の平均寿命は男性が79.00歳、女性が85.81歳で、前年よりも男性は0.44歳、女性は0.29歳延びたことが厚生労働省がまとめた簡易生命表で分かった。05年はインフルエンザが流行した影響で前年を下回ったが、06年は再び上昇傾向に転じた。厚労省は、がん、心臓病、脳血管疾患の3大疾患での治療成績の向上が貢献しており、当分寿命が延びる傾向が続くとみている。厚労省が把握する主要各国・地域の最新データと比較すると、女性は22年連続の世界一で、香港(84.6歳)、スペイン、スイス(いずれも83.9歳)、フランス(83.8歳)が続く。 男性は前年の4位からアイスランド(79.4歳)に続く2位に上がった。3位以下は香港(78.8歳)、スイス(78.7歳)、スウェーデン(78.50歳)の順。日本の場合、3大疾患で死亡する確率は男性が56.00%、女性は 53.57%。3大疾患が克服されれば、男性の平均寿命は8.31歳、女性は7.20歳延びる見込みという。(平成19年7月26日 朝日新聞) メタボリックだと、心筋梗塞などリスク2.5倍 メタボリック症候群の人はそうでない人に比べて、心筋梗塞など心臓血管系の病気になる危険性が男性で約2.5倍、女性で約1.8倍になるとの研究結果を、島袋充生・琉球大医学部講師らがまとめた。 沖縄県の約7000人を対象にした疫学調査で、島袋講師は「同症候群と心臓血管の病気との関連が裏付けられた」としている。 島袋講師らは、2003年5月から04年3月までの間に、沖縄県豊見城市の病院で人間ドックを受けた30歳以上の男女から、腹部の肥満に加え血圧、血糖値、中性脂肪のうち2つ以上が高く、同症候群の基準を満たす男性1069人、女性153人を選んだ。この人たちに今年2月以降、聞き取りやアンケートを実施。心筋梗塞や大動脈瘤などを発症した確率を調べたところ、男性では約28%で、同症候群でなかった男性に比べ約2.5倍危険だった。女性では発症率は約9%で、危険性は同症候群でない人の約1.8倍だった。(平成19年7月26日 日本経済新聞) 日本脳炎予防接種激減 幼い子、蚊に用心 厚生労働省は20日、日本脳炎の予防接種の激減により、この病気の免疫を持つ0〜4歳の子供の割合が2割以下まで低くなっているとして、子供らが日本脳炎ウイルスを媒介する蚊に刺されないよう、ホームページで注意喚起を始めた。日本脳炎はウイルスによって脳が侵される病気。ウイルスを持つ豚などの動物を刺した蚊が、人を刺すことで感染する。感染しても発症するのはまれだが、意識障害の症状を起こすと20〜40%が死に至る。回復しても半数に、知能障害や手足のマヒなど重い後遺症が残る。日本脳炎は予防接種法に基づき、定期接種の対象の感染症となっているが、同省は2005年5月に、接種後に重い副作用が出たとして、積極的な勧奨を控えるよう、市町村に勧告。希望者は接種できるが、4歳以下の接種率は06年度で30%を下回っており、免疫を持たない子供らが増えている。例年、ウイルスを持つ豚が、中・四国や九州など西日本を中心に確認されている。このため、同省は、特に西日本の豚が多い地域や蚊が発生する水田や沼の周辺では、〈1〉長袖や長ズボンの着用〈2〉防虫薬の使用――など、子供らが蚊に刺されない工夫を呼びかけている。同省は「副作用が少ない新しいワクチンの実用化には3年以上かかる。 それまでの間は、蚊に刺されないように十分注意してほしい」と話している。(平成19年7月21日 読売新聞) リンゴポリフェノールに長寿効果 リンゴから抽出される「リンゴポリフェノール」に寿命を延ばす効果があるとの研究結果を、アサヒビールと東京都老人総合研究所がまとめた。動物実験で確認したという。実験は、遺伝子組み換えにより老化の速度を速めたマウス55匹を使った。このうち32匹に、リンゴポリフェノールを0・1%配合した飲料水を飲ませ、残り23匹のマウスにはただの水を飲ませて寿命を比べた。その結果、ポリフェノール入りの飲料水を飲んだマウスの寿命はメスが平均37・90週、オスが平均28・84週で、ただの水を飲んだマウスよりメスで平均72%、オスで29%寿命が長くなった。マウスが摂取したリンゴポリフェノールは1日リンゴ0・02個〜0・04個分にあたり、人間の摂取量に換算すると1日リンゴ5〜10個分程度になる。(平成19年7月21日 読売新聞) すべての睡眠薬で、「夢遊症状」の恐れ 睡眠薬を飲んで眠った後に、本人の記憶がないまま車を運転したり徘徊したりする「夢遊症状」が出る恐れがあるとして、厚生労働省は使用上の注意を改め、注意喚起を強めるよう製薬会社に指示した。対象はマイスリー、ハルシオン、アモバンなど19品目。 米食品医薬品局(FDA)は3月、「寝ぼけた状態で車を運転したり、電話をかけたりする恐れがある」と睡眠薬13品目について警告を出した。これを受けて、厚労省も国内の睡眠薬について、製薬会社からの副作用報告を精査。同様に副作用の恐れがあるとして、添付文書に「睡眠途中に一時起床する可能性がある時は服用させない」「異常が認められたら投与を中止する」などの注意を書き加えるよう求めた。(平成19年7月13日 朝日新聞) 肺がんの引き金遺伝子を発見 肺がんの引き金となる新たな遺伝子異常を、間野博行・自治医科大教授らの研究グループが発見した。喫煙が関係しているとみられ、これまで困難だった肺がんの早期発見が可能になるだけでなく、有効な治療薬の開発などにつながる成果として注目される。喫煙歴のある62歳の男性患者の肺がん細胞から採取した多数の遺伝子を、実験用の正常細胞に組み込み、がん化した細胞から原因遺伝子を特定した。この遺伝子は、細胞の増殖を指令する遺伝子「ALK」と、細胞の形の維持などを担う遺伝子「EML4」が融合した異常型で、ALKが際限なく増殖指令を出してがんを引き起こすらしい。さらに、肺がん患者75人を検査したところ、5人の患者から融合遺伝子を検出した。そのうち4人は喫煙者。グループによると、融合遺伝子は、たんや血液1cc中に、がん細胞が10個程度含まれていれば検出が可能。顕微鏡でがん細胞を確認する従来の方法に比べ、肺がんの診断が飛躍的に早まると期待される。肺がんに関しては、EGFRという遺伝子の変異が知られており、この働きを阻害する治療薬「ゲフィチニブ」(商品名イレッサ)もある。ただ、EGFRの変異は非喫煙者の患者に多く、喫煙による肺がんに特有の遺伝子変異は不明だった。(平成19年7月12日 読売新聞) はしか対策、中1と高3を予防接種の対象に はしかの大流行を受けて、厚生労働省は9日、来年度から5年間の時限措置として、中学1年生と高校3年生を対象に、定期予防接種を追加する方針を明らかにした。ワクチン接種が1回しかなかった小学2年生以上に、高校卒業までに2回目の機会を確保する狙い。はしかの発生件数を、すべて把握するため、医師による報告を義務化するという。 この日、同省の検討会が原案を提示。同省はこれをもとに国の「はしか排除計画」を策定し、12年までに患者が出ても流行しないとされる免疫保有率95%以上を目指す。 はしかの予防接種は、昨年4月に法改正され、1歳〜7歳半の1回接種から、1歳と小学入学前の2回の定期接種に変更された。今春小学校に入学した児童は原則2回打っている。ワクチンを2回受けると、ほぼ感染の心配はないとされ、今回の大学生や高校生の流行は「1回接種で免疫が弱まった世代で起きた」などの指摘が専門家から出ていた。 原案では、来年度から5年間、中1と高3時に接種を続け、接種機会が1回だった小学2年生以上をカバーする。このほか、保護者同伴となっている要件について、小学生以上では緩和を検討したり、学校などでの集団接種も選択肢にしたりするとしている。 国、都道府県などは「はしか排除委員会」をつくり、発生動向や接種率、副作用報告などを管理。患者が出た場合、医師に保健所への届け出を義務づけ、重篤な副作用がより迅速に報告される仕組みを導入する。今後、健診時や海外旅行時に接種を証明する機会が増えることが予想されるとして、母子保健手帳から予防接種部分を独立させることも検討する。 現在の定期接種の費用は原則、市町村が負担しているが、新たな接種の負担については今後議論するという。(平成19年7月10日 朝日新聞) 国産エイズワクチン開発 日本のベンチャー企業「ディナベック」が、世界最大のエイズ予防研究機関の協力を得て、エイズワクチンを開発する。同社のワクチンは動物実験で高い効果をあげており、改良して3年後の臨床試験実施を目指す。エイズワクチンは世界中で研究開発が進んでいるが、まだ実用化されたものはない。臨床試験が始まれば、国産ワクチンでは初となる。国内で発見された「センダイウイルス」と呼ばれるウイルスに、病原体の遺伝子の一部を組み込んでワクチンを作る技術の特許を持つ。この技術を基に作るエイズワクチンは、鼻に噴霧できるため、鼻粘膜を通じ、多くの免疫細胞を活性化させる働きがあるうえに、DNAに入り込まないので人体に悪影響を及ぼさないなどの利点がある。同社が、国立感染症研究所などと共同でワクチンをサルに投与したところ、エイズウイルスのサルへの感染を阻止しただけでなく、すでに感染しているサルのウイルス増殖を抑えることができた。ディナベックに協力する「国際エイズワクチン推進構想」は、マイクロソフト社のビル・ゲイツ会長らの巨額の支援を原資に活動する機関で、ワクチンの設計から承認申請を行うまでにかかる数十億円の開発費を負担する。IAVIはタイなどで6種のエイズワクチンの臨床試験を始めているが、ディナベックのワクチンは、より長期にわたって予防効果を発揮できるとみられる。ディナベックによると、3年後に米国、アフリカなどで臨床試験を始め、8年後に実用化するのが目標。(平成19年7月7日 読売新聞) 中国産原料のせき止め薬で死者387人 中米パナマで中国産原料を含むせき止め薬の服用で死亡したとの訴えが、387人分に上っていることが分かった。犠牲者数はパナマ保健当局が現在認定している約100人を大幅に上回る可能性が出てきた。不凍液などに利用される有害物質ジエチレングリコールが中国産原料に混入し、パナマ製のせき止めシロップに使われた。事件を担当する特別検察官に387人の遺族から訴えがあったほか、153人から後遺症被害の報告が提出されているという。このせき止め薬はパナマ社会保険庁が製造し、同国の保険加入者のみが購入できる。昨年10月ごろから致死率の高い「謎の病気」として国民を脅えさせた。ジエチレングリコールは無臭でわずかに甘い。摂取すると嘔吐、頭痛などの症状が出て腎機能に障害が出る。(平成19年7月7日 毎日新聞) 生体肝移植、提供者にもリスク 国内で実施された生体肝移植で、ドナー(臓器提供者)の3.5%に再手術が必要となるなど重い合併症が出ていたことが調査で分かった。生体肝ドナーの合併症の実態が明らかになったのは初めて。同委は89〜05年に生体肝移植を実施した施設を対象にアンケートした。37施設から3005例の報告があった。重い合併症を発症したドナーは105例(3.5%)で、手術後の発症が90例、手術中17例、手術前3例。46例は再手術を受けた。この他、京都大病院で03年に1人が死亡していた。手術後の合併症の内訳は、胆汁漏れが45例、大量出血8例など。手術中では17例中16例が大量出血で、残り1例は手術で胆管を傷つけた。手術前は、注射で動脈を傷つけたケースなどだった。同研究会が04年に実施した調査では、生体肝ドナーの約4割が今後の健康に不安を感じると回答していた。清澤委員長は「施設によって手術のレベルにそれほど差があるとは思わない。生体移植はどうしてもドナーにリスクがあり、このような重い合併症が起こることもありえるということを医療者が十分に説明する必要がある」と話している。(平成19年7月7日 毎日新聞) AED使用で蘇生率7倍に 心肺停止状態となり、一般市民らからAED(自動体外式除細動器)を使った処置を受けた人の4割で蘇生につながったことが東京消防庁の昨年中の実態調査で分かった。この「心拍再開率」は、救急隊到着まで処置を受けなかった場合と比べて約7倍も高かった。AEDは04年7月の厚生労働省通知で市民の使用が認められて急速に普及しているが、同庁は「普及が進むAEDの有効性がデータから初めて裏付けられた」としている。 AEDは心臓が止まった人に電気ショックを与えて蘇生させる機器。従来は医師や救急救命士しか使うことができなかったが、医療関係者の提言もあり同省が一般市民の使用を認めた。東京消防庁によると、昨年中、一般市民の目の前で心肺停止状態になった管内の傷病者は3107人。うち41人が近くにいた人からAEDの処置を受け、17人が病院搬送前に心拍が再開した(再開率41.5%)。一方、AEDや心臓マッサージなどの心肺蘇生処置を受けなかった2193人中、心拍が再開したのは141人(同6.4%)にとどまり、心拍再開率には約7倍の開きがあった。AEDを使用しないで一般市民らが蘇生を試みたケースは873人だが、心肺再開は1割程度だった。今年になっても1〜6月だけで既に38人が一般市民らのAEDを使った処置を受け、17人が蘇生した。心拍再開率は44.7%となっている。例えば5月には電車内で60歳代の男性が倒れ、乗客の教諭や看護師らが次の停車駅に設置されたAEDで蘇生を試みて成功。3月に50歳代の男性が交通事故を起こしたケースでは、後続車の医師が心臓マッサージを行い、近くのホテル従業員が持参したAEDで心拍を回復させた。AEDは駅や空港などの公共施設を中心に普及が進んでおり、同庁管内では今年1月時点で約3500台、全国では7万台以上が設置されている。各地の消防署や日本赤十字社で使用方法を学べる救命講習が開かれている。厚生労働省は「実際にAEDを使うのはその場に居合わせた医師ら医療関係者が多く、一般市民への浸透が課題だ」としている。(平成19年7月5日 毎日新聞) 電話相談、がん患者らの心をサポート開設 がんになって気分が落ち込む、がんになった家族にどのように接すればよいかわからない、そんな悩みを抱えるがん患者や家族の相談に応じようと、日本サイコオンコロジー学会は「こころのサポートホットライン」を開設する。電話番号は03−5218−4776、03−5218−4771で、午前10時〜午後6時まで。 相談は無料。サイコオンコロジー(精神腫瘍学)は、がん患者の心理などを研究する精神医学。がん告知後の精神的サポートが重要視される中、70年代に欧米で始まった。当日は精神科医を中心に臨床心理士ら18人が相談に応じる予定。同会常任世話人の明智龍男・名古屋市立大准教授は「再発の不安など、気持ちの問題ならば何でも相談してほしい。役に立てれば今後も続けていきたい」と話している。(平成19年7月5日 毎日新聞) ピロリ菌、先祖は深海底の微生物 ゲノム解析で判明 胃かいようや慢性胃炎の原因となる細菌の一種「ヘリコバクター・ピロリ」(ピロリ菌)の祖先が、深海底に広く分布する微生物であることを、海洋研究開発機構の研究グループがゲノム解析によって突き止めた。これらの細菌が人の体に住み着くようになった進化の過程解明につながるという。研究グループは沖縄本島の北西約200キロ、水深約1000メートルの海底から熱水が噴出する場所で、「イプシロンプロテオバクテリア」と呼ばれる微生物2種を採取。ヒトの1000分の1以下の小さなゲノムに、それぞれ2466個、1857個の遺伝子が見つかった。解析の結果、ピロリ菌には残がいしかない、二酸化炭素から有機物を作り出す遺伝子を、微生物は完全な形で持っていた。この微生物は世界各地の熱水噴出域で見つかっている。光合成ができない暗黒で高圧の厳しい環境下でも、熱水中の水素や硫化水素をエネルギー源とし、二酸化炭素から有機物を合成する。グループの中川聡研究員は「環境変化が激しい胃の中にすむピロリ菌とこの微生物は、厳しい環境下で生きる戦略が似ている」と話している。(平成19年7月3日 毎日新聞) 運動時の水、がぶ飲みで低ナトリウム血症の恐れ 運動する際に水をがぶ飲みしすぎると、運動誘発性の低ナトリウム血症(EAH)におそわれかねない。米国の専門家が医学誌スポーツメディシンで、適度の水分補給を呼びかけている。運動時に水分をとりすぎて血液中の塩分濃度が下がると、けいれんや呼吸困難といったEAHの症状にみまわれるおそれがある。ジョージタウン大医療センターのジョセフ・バーバリス教授によると、ある年のボストンマラソンでは参加者の約13%がEAHになった。今年のロンドンマラソンでも 1人が死亡したという。トライアスロンや軍隊の行軍などでも報告例がある。運動を続ける時間が4時間を超えるようだと注意がいる。過去のマラソン大会の調査で、レース中に3リットル以上の水を飲んだ人がEAHになるリスクが高かったという。運動後に体重が増えれば水分の取りすぎだ。運動前後の自分の体重の変化を調べ、その量に見合った分だけ水分を補給するよう心がけるべきだとしている。05年にEAH防止指針をまとめた経験があるバーバリス教授は「水の代わりに、塩分を含むスポーツ飲料を飲めばEAHを予防できるというのは誤解。スポーツ飲料も飲み過ぎると、やはり水分を取りすぎるリスクがある」と指摘する。(平成19年7月2日 朝日新聞) 「慢性疲労症候群」の診断 原因不明の激しい疲労が半年以上も続き、通常の日常生活が送れなくなる「慢性疲労症候群(CFS)」の新しい診断指針を、日本疲労学会の委員会がまとめた。新指針では、リウマチや慢性感染症など8種類の病態でないことを確認した上で、「体を動かした後、24時間以上疲労が続く」「思考や集中力の低下」など特徴的な症状を10項目に絞り、うち5項目以上を満たすことを診断基準にした。CFS患者は10万人当たり約300人、潜在患者はその10倍との推計がある。診断がつかないまま病院を渡り歩いたり、職場で「なまけ病」とそしられたりする患者も多く、同学会は新指針でこうした問題が減るとみている。(平成19年7月1日 読売新聞) 4時間以上のフライトで血栓2倍 世界保健機関(WHO)はこのほど、「エコノミークラス症候群」について、「4時間以上動かない姿勢で飛行機や列車などに乗っていると、血栓ができる可能性が通常の約2倍に高まる」との結果を発表した。長時間同じ姿勢でいることで静脈内に血栓ができ、場合によっては肺動脈をふさいでしまうエコノミークラス症候群。 WHOは血栓ができる確率自体は低いが、長旅をする時は足の血行をよくする運動などを心がけるよう呼びかけた。さらに、短期間に4時間以上の航空便を乗り継ぐなどした場合には、血栓ができる可能性がさらに高まると警告。肥満や経口避妊薬の服用者、もともと血液疾患がある人もリスクが高いとしている。(平成19年6月30日 朝日新聞) 注射より効く「鼻」ワクチン 鼻粘膜に噴霧するだけで、インフルエンザの感染を予防できる経鼻インフルエンザワクチンを国立感染症研究所が開発した。動物実験では、皮下に注射する現在のワクチンより効果が高いことが確認され、新型インフルエンザの予防にも威力を発揮することが期待される。感染研は3年以内に、国内初の臨床試験開始を目指している。注射型ワクチンは、主に血中の免疫物質を増強するが、気道粘膜では免疫が増強されないため、ウイルス自体の感染は防げない弱点があった。その点、経鼻ワクチンは、直接、粘膜に噴霧するため、ウイルスの感染を防ぐ効果がある。しかし、ワクチンの原料となるウイルスの成分だけでは、十分な免疫を引き出すことができなかった。同研究所感染病理部の長谷川秀樹室長らは、ウイルス成分に加え、人工的に作ったRNA(リボ核酸)の2本鎖を添加したワクチンを試作。RNAの2本鎖は、ウイルス感染のシグナルになり、体内に入ると、免疫を増強する働きがある。強毒型のウイルス(H5N1型)の経鼻と注射型ワクチンをマウスに接種し、ウイルスを感染させたところ、注射型に比べ、経鼻ワクチンを接種したマウスの生存率は平均して約2倍高かった。また、経鼻ワクチンは、注射型と異なり、様々なウイルス株に効果があることがわかった。(平成19年6月30日 読売新聞) 受動喫煙、認知症の発症 他人が吸ったたばこの煙を吸わされる「受動喫煙」が長期間に及ぶと、認知症の恐れが高まるとの分析を、米カリフォルニア大が公表した。たばこを吸う人は認知症リスクが高まるとの研究はあるが、受動喫煙と認知症の関係に注目した本格調査は初めてという。同大は「受動喫煙が血管に影響を与え、発症のリスクを高めているのではないか」と推測している。認知症の主な原因には、脳こうそくなどの血管障害とアルツハイマー病がある。たばこが中枢神経系に与える影響を探る目的で調査を実施。研究に協力する65歳以上の市民3602人のうち、過去に喫煙歴や心血管疾患がない985人(66〜92歳)を6年間、追跡した。このうち、受動喫煙があった人は495人で、その期間が30年以上だと、認知症の発症率が約1.3倍になることが分かった。30年未満の人では、受動喫煙の影響を受けなかった人と発症率の差はほとんどなかった。また、30年以上の受動喫煙者のうち、脳に血液を供給する頸(けい)動脈の狭さくが見つかった人では、認知症を発症する率が約2.4倍とさらに高かった。30年未満の受動喫煙者でも約1.3倍だった。喫煙は動脈硬化の危険因子とされ、狭さくもその一種。(平成19年6月26日 毎日新聞) 鉄分過剰摂取はC型肝炎に悪影響 ウコン、クロレラなどの健康食品の一部に、表示のないまま平均摂取量を上回る鉄が含まれており、摂取していたC型慢性肝炎患者の病状改善を妨げるケースのあることが、垣内雅彦三重大准教授(肝臓内科)らの研究で分かった。鉄は健康なら過剰摂取の心配はない。だが、国内に約200万人いるC型肝炎患者の場合、肝臓に蓄積する恐れが高い。過剰な鉄は、活性酸素を作り、肝細胞を壊したり、がん化を進めたりする。垣内准教授らは、同大付属病院で治療中のC型肝炎患者が日ごろ摂取している健康食品67品について鉄含有量を調べた。その結果、クロレラ商品(錠剤)の一つでは、100グラム中138・3ミリ・グラムで、1日当たりの摂取量を計算すると11・1ミリ・グラムとなり、成人男性の1日の平均摂取量の8・1ミリ・グラムを上回った。ケール商品の一つで100グラム中127・2ミリ・グラム、マルチビタミン剤で同118・7ミリ・グラムというケースがあり、秋ウコンのある商品でも同22・4ミリ・グラムという結果が出た。垣内准教授らが目標に掲げるC型肝炎患者の鉄摂取量は「1日6ミリ・グラム以下」。健康食品11品で鉄を1日推計8・5ミリ・グラム取っていた患者は、健康食品をやめただけで肝機能の数値が改善したという。平成19年6月24日 読売新聞) 乳がん検診、発見2割 乳がん患者のうち、乳房のエックス線(マンモグラフィ)などを使った検診でがんが見つかったのは2割に過ぎず、4人に3人は、検診を受けずに自分で、しこりなどの異常に初めて気づいて病院を受診したことが、日本乳癌(がん)学会の大規模調査でわかった。自分で発見する場合、早期がんより進行している例が多く、専門家は「早期がんの発見には、マンモグラフィ検診が有効だ。乳がんの死亡率を下げるには、低迷する集団検診の受診率を上げることが不可欠」と指摘している。同学会は、乳がんの診断や治療を行う全国226か所の医療機関から、2004年度にがん登録した乳がんの新患者約1万4800人(平均年齢57歳)のデータを集計。これは全国の年間新患者数の約4割にあたる。その結果、患者が乳がんに「自分で気づいた」と答えたのが73・8%に上った。検診で見つかったのは20・4%で、このうち自覚症状が全くなかった人は、14・7%だった。直径2センチ以下の早期がんで見つかったのは45%に過ぎず、43%は2・1〜5センチに達していた。発見時にリンパ節に転移していた人も、3分の1を占めた。リンパ節に転移しない乳がんの10年後の生存率は約9割と高いが、転移をしていると7割以下に落ちるという。(平成19年6月15日 読売新聞) コレステロールは脳伝達機能を高める 血液中や肝臓で増えると厄介者扱いされるコレステロールが、脳の機能増進には欠かせないことを、産業技術総合研究所関西センターや科学技術振興機構の研究員らのグループがネズミを使った実験で明らかにした。 「アルツハイマー病の脳内では、コレステロールの合成異常がみられるという研究もあり、治療薬の開発に役立てたい」と話す。神経細胞とコレステロールの関係を探るため、ネズミの大脳皮質の神経細胞を培養し、BDNFという脳の機能増進を促すたんぱく質を加えた。すると神経細胞のコレステロールの量が増えることが分かった。また、コレステロールが増えた神経細胞を調べると、情報伝達物質を受け渡ししやすい状態になっていた。一方、コレステロールの合成を妨げる薬剤を入れると脳の情報伝達機能が抑制された。 ただし、体と脳のコレステロールは別々につくられており、血液中のコレステロール量が多ければ、脳の働きがいいというわけではないという。(平成19年6月14日 朝日新聞) 膝軟骨の人工培養技術 従来は難しかったひざ軟骨の人工培養技術を東京大学などが開発した。体内と同じ高圧環境下で培養するもので、変形性膝関節症の患者などへの再生医療に道を開くと期待される。東大では軟骨がすり減るため、膝が痛み、歩行や階段昇降が困難になる変形性膝関節症の患者を3000万人と推計している。一部の患者には、膝から採取した健康な軟骨細胞を培養した後、患部に注入する治療が試みられているが、培養中に病的なたんぱく質を持つ異常細胞ができる問題があった。牛田多加志教授は、関節内で体液の入った袋に包まれた軟骨には、歩行時に約50気圧の圧力がかかることに着目。プラスチック製の培養袋にウシの軟骨細胞を入れ、体内と同じ水圧をかけて4日間培養したところ、球状の正常軟骨(直径1ミリ)ができた。ヒトの細胞で球状軟骨を多数作り、体内の軟骨と同じ形の型に詰めて成形すれば、移植可能な人工軟骨が作れるようになるという。東大病院整形外科・脊椎外科の中村耕三教授は「減量や運動が治療の基本だが、傷んだ軟骨を再生医療で治せるようになれば治療手段が増す」としている。(平成19年6月14日 読売新聞) はしか、来年度からワクチン接種徹底 大学生や高校生を中心としたはしかの流行を受け、厚生労働省は今年の反省を踏まえ、はしかの免疫を持つ比率が低い10〜20代のワクチン接種を徹底するほか、ワクチン増産なども検討。先進国で数少ない「はしか輸出国」の汚名返上も目指す。はしか予防は就学前のワクチン接種が基本。厚労省は昨年4月、予防接種法の施行令を改正し、それまで1歳〜7歳半までの1回接種だったのを「小学校就学前の2回接種」に変えた。しかし国立感染症研究所の調査では、就学前年の児童で2回目を接種していたのは昨年10月までに29%にとどまっていた。今回、感染が広がった10〜20代は、副作用が社会問題化して94年に予防接種が義務制から任意制になった世代の先駆けだ。94〜04年の接種率は90〜95%で推移しているが、1回の接種では接種者の約5%が十分な免疫を持てない。厚労省はこの約5%と、5〜10%の未接種者が中心になり、学校などで集団感染したとみている。このため検討会では、免疫が弱い世代の予防対策として、企業や大学などが入社・入学前に接種の有無の確認を徹底することなどが可能かどうかについても検討する。また今年は自治体の一斉購入などでワクチンの在庫が全国で一時5万本まで減り、抗体の有無を調べる検査試薬はゼロにもなった。こうした事態を繰り返さないよう増産計画も検討していく。今回の流行では、はしかを抑え込んだカナダ、米国などへの「輸出」も相次いで発覚。カナダでは、東京都内の高校生1人が修学旅行中にはしかにかかり、他の生徒約120人もホテルに一時足止めされた。米国では、日本を旅行した20代の男性が帰国後に発症、2次感染の疑いもあるとして立ち回り先が公開された。(平成19年6月13日 朝日新聞) 医療機関の倒産急増 医療機関の倒産が急増している。帝国データバンクのまとめによると、法的整理による倒産件数は今年1〜5月で全国で28件に上り、01年以降で最悪のペース。06年度の診療報酬引き下げによる収入減が大きな要因で、小規模の医療機関を中心に年後半はさらに増えそうだとみている。全国の医療機関による民事再生法や破産手続きの申請など法的整理件数を調べたところ、02〜06年はほぼ横ばいだったが、今年は例年の倍近いペースで増加。01年以降で最も多かった04年(32件)を超える勢いだ。今年の28件のうち、民事再生法が8件、破産が20件。負債額5億円未満が15件と約半数を占める一方、30億円以上の倒産件数(5件)は過去6年間の合計件数にすでに並んだ。事業規模の大きい医療機関は民事再生法、診療所や歯科医院など規模の小さいところは破産を選択する傾向が強くなっているという。主な倒産原因については、診療報酬の減少による「販売不振」が7件、「設備投資の失敗」が8件と多く、「放漫経営」が3件だった。平成19年6月12日 朝日新聞) 乳癌の放射線治療期間が短縮 放射線を正確に標的に当てる強度変調放射線治療(IMRT)の利用で、1日あたりの照射線量を増やし、乳癌患者の治療期間を従来の6〜7週間からわずか4週間に短縮できるとの研究結果が米Fox Chaseフォックス・チェイス癌センターのGray Freedman博士による報告があった。少なくとも腫瘍が小さい乳癌患者では、腫瘍摘出術と放射線治療の併用で、乳房切除術と同等の生存率および治癒率を得られることが十分に裏付けられている。しかし、放射線治療には6〜7週間を要することから二の足を踏む女性が多く、期間の短縮が重要課題となっている。いくつかの研究では、体外からの照射と放射性シードの埋め込みを併用する1週間の治療について検討されているが、この治療は腫瘍の極めて小さいごく一部の患者にしか適さない。今回の研究では、乳癌の女性75人(平均52歳)を対象に、IMRTを用いて1日当たりの線量が通常より高い治療を実施し、その副作用を調べた。従来に比べて線量の総計が多くなるわけではなく、通常の6〜7週間の治療で計60Gy(グレイ、吸収線量を示す単位)を照射するのに対して、この4週間治療では56Gyだという。IMRTでは、コンピューターが制御するX線加速器を用いて腫瘍または腫瘍内の特定部位に極めて正確に放射線を照射でき、周辺組織の被曝を最小限にとどめることができる。短期の結果は良好で、従来の治療を超える副作用は出ていない。一部の患者に皮膚障害が認められたが、6週目までには治まり、治療終了から6週間後には、皮膚の外観が治療前と同じに戻った。今後、長期的な問題の有無を確認するため5年間の追跡が行われる。過去の研究から、1980年代に放射線治療を受けた女性の心疾患リスクが高いことがわかっているが、IMRTを用いれば心臓の被曝が少なくなり、リスクも軽減できるはずだという。ただし、IMRTには利用できる施設が限られるという欠点があることをFreedman氏も認めている。また他の専門家からは、今回の研究が小規模で、さらに検証する必要がある点や、長期的な毒性と再発の可能性について疑問が残る点も指摘されている(平成19年6月7日 日本経済新聞) 患者の意思あれば延命中止 死期が迫ったがん患者の延命治療中止手続きについて、厚生労働省研究班がまとめた。対象となる終末期を「余命3週間以内」と定義し、患者本人の意思を前提に中止できる医療行為の範囲を「人工呼吸器、輸血、投薬」などと明記する一方、意思確認できない場合は除外するなど慎重な判断を求めている。試案をまとめたのは初めてで、今後、医療現場の声を反映させながら内容を詰める。ただ、全国約1500の病院が回答した同研究班の調査では、がん患者への病名告知率は平均で65・7%、余命告知率は29・9%にとどまり、患者の意思確認が容易でない実情にどう向き合うかが課題となりそうだ。試案は末期がん患者の終末期を、複数の医師が繰り返し診察するなどした結果「余命3週間以内と判定されたとき」と定義。指針の目的を「終末期の患者が、尊厳ある死に至るプロセスを選択すること」とした。患者の意思確認の方法は(1)2年以内に書かれた文書(2)口頭での患者の意思表示(3)家族による患者意思の推定と同意―のいずれかとした上で、中止や差し控えの対象は「人工呼吸器、人工心肺、栄養や水分の補給、輸血、投薬などすべての治療」とした。患者の意思が確認できない場合や、認知症や知的障害で判断が困難な場合などは、対象から除外するとしている。同研究班は今後、植物状態など、がん以外の病気についても指針を検討するとしている。林班長は「がんは3人に1人が亡くなる日本人の最大の死因だが、病状の経過がある程度予測可能で、患者や家族と治療方針を検討する時間的余裕もあるケースが多い。 今回の試案を、終末期医療をめぐる議論を一歩進めるきっかけにしたい」と話している。(平成19年6月6日 中国新聞) 先天性免疫不全症、造血幹細胞移植 重症の「先天性免疫不全症」だった青森県在住の男児(4)が、弘前大付属病院で造血幹細胞移植を受け、快復した。免疫細胞の異常で生まれつき免疫力が低く、感染症を繰り返して幼児期に死亡する可能性が高い病気。症例が極めて少ないこともあり、移植の成功例は世界初という。男児のような免疫不全症が細胞内物質の「NEMO」の異常で引き起こされることは01年に解明されたばかり。日本国内で確認されている患者は10人に満たないという。伊藤悦朗教授は「過去にはこの病気であることがわからず、助からなかったケースもあっただろう。こういう病気があることと、移植で治ることが広く知られれば」と話している。男児は生後2カ月で敗血症を起こして弘前大付属病院に入院。重症の免疫不全症と診断された。2歳半ごろ、胃や腸の炎症で食事ができなくなるほど悪化。同病院の医師グループは血液を造るもとになる「造血幹細胞」を移植し、正常な免疫細胞をつくりだす効果を期待する以外、助かる方法はないと判断した。昨年1月に移植した後、男児は4カ月ほどで退院。現在は外出もできる。同病院は「造血幹細胞の定着も確認でき、経過も順調だ」としている。 造血幹細胞は大人の骨髄中にあり、赤ん坊のへその緒や母体の胎盤から採った「臍帯血」にも多く含まれる。男児への移植では、臍帯血を点滴で静脈から注入。骨髄に造血幹細胞を定着させる方法をとった。(平成19年6月1日 朝日新聞) 介護報酬不正請求 訪問介護大手のコムスンなど3社が介護報酬を不正請求していた問題で、3社の都内各自治体に対する返還額は計4億2000万円に上ることが分かった。都は昨年11月以降、3社に立ち入り検査を実施し、計約2億2000万円の不正請求を指摘。都の指導を受け、3社が都内の全事業所を自主点検した結果、不正請求の総額は約2億円膨らんだ。都によると、コムスンの返還額は約2億円。ニチイ学館は約8500万円、ジャパンケアサービスは約1億3800万円に上る。都は今年4月、常勤管理者がいると虚偽の申請をして都内3事業所の指定を受けたとして、コムスンに約4300万円の返還を請求。その後の都の調査、同社の自主点検で、散歩の付き添いなど保険対象外のサービスに介護報酬を請求していたことなども判明した。(平成19年5月30日 日本経済新聞) 善玉コレステロールを増やすには 善玉コレステロールを増やすには、少なくとも1回に30分以上、1週間で計2時間以上の運動量が必要であることが、お茶の水女子大の研究グループの調査でわかった。血液中の余分なコレステロールを回収することから「善玉」とされるHDLコレステロールは、運動によって増えるとの指摘はあったが、どの程度行うべきか明確な指標はなかった。同大生活習慣病医科学講座の児玉暁研究員と曽根博仁准教授は、ウオーキング、ジョギングなど有酸素運動によるHDLコレステロールの変化に関する25の研究論文のデータを解析した。 それによると、HDLコレステロールの上昇には、週当たり推定消費エネルギーで900キロ・カロリー、時間にして2時間以上の運動量が必要だった。一般に1時間の速歩きで300キロ・カロリー程度消費するとされる。運動1回当たりでは、30分以下ではほとんど効果がなく、以降10分増すごとにHDLコレステロールは約1・4ミリ・グラム上昇した。運動の激しさとは無関係だった。足腰を鍛えたり体脂肪を減らしたりするには、短時間の運動をこまめにすることも効果的とされるが、「HDLコレステロールの改善には、ウオーキング、水泳など30分以上のまとまった運動を週に数回行う必要があるとみられる」と曽根准教授は話している。(平成19年5月29日 読売新聞) 心筋梗塞や脳卒中、メタボじゃなくてもご用心 高血圧や高血糖といった生活習慣病の危険要因を同時に抱えると、心筋梗塞や脳卒中を起こす危険が高まるが、その程度は、太っているよりもやせている人の方が高くなりやすいことが、厚生労働省研究班の調査でわかった。来年度から、生活習慣病予防のための特定健康診査が始まるが、その柱となる「メタボリック症候群(内臓脂肪症候群)」の診断基準が、やせた人たちのリスクを見逃してしまう可能性を示したものだ。同症候群は心筋梗塞や脳卒中など循環器病とかかわりが深い。危険要因として、肥満、高血圧、高血糖、高中性脂肪、低HDLコレステロールが挙げられ、欧米では基本的に、うち三つ以上の値が一定値を超えると、「あなたはメタボ」などと診断される。日本の診断基準では特に肥満が重視されており、ウエストサイズが一定以上であることが必須条件。例えば血糖値がかなり高くても、太っていなければ同症候群には該当しないことになる。調査で、この診断基準ではそんな人たちのリスクを見落とす可能性があることがわかった。肥満の指標となるBMI(体格指数)が25以上の太った人が循環器病で死亡するリスクは、肥満でなくほかの危険要因もない人と比べると、危険要因が肥満以外に二つの場合は1.5倍。三つ以上だと2.4倍だった。一方、BMIが25未満の人で同じ比較をすると、それぞれ2倍、2.8倍となり、肥満傾向の人よりも高かった。やせた人でも、体質的に高血糖や高血圧などを起こしやすい人がおり、そういう人は太っている人よりむしろリスクが高まりやすいらしい。同症候群については、肥満でなくても糖尿病などを通して循環器病になる人が少なくない。(平成19年5月28日 朝日新聞) 医師人口比、日本、20年に最下位へ 人口1000人当たりの日本の医師数が、2020年には経済協力開発機構(OECD)加盟30カ国中最下位に転落する恐れがあることが、近藤克則・日本福祉大教授の試算で分かった。日本各地で深刻化する医師不足について、国は「医師の地域偏在が原因で、全体としては足りている」との姿勢だが、国際水準から懸け離れた医師数の少なさが浮かんだ。OECDによると、診療に従事する03年の日本の医師数は人口1000人あたり2人。OECD平均の2.9人に遠く及ばず、加盟国中27位の少なさ。一方、診療医師数の年平均増加率はメキシコ3.2%、トルコ3.5%、韓国は5.5%で、日本は1.26%と大幅に低く、OECD各国中でも最低レベルにとどまる。各国とも医療の高度化や高齢化に対応して医師数を伸ばしているが、日本は「医師が過剰になる」として、養成数を抑制する政策を続けているためだ。近藤教授は、現状の増加率が続くと仮定し、人口1000人あたりの診療医師数の変化を試算した。09年に韓国に抜かれ、19年にメキシコ、20年にはトルコにも抜かれるとの結果になった。30年には韓国6.79人、メキシコ3.51人、トルコ3.54人になるが、日本は2.80人で、20年以上たっても現在のOECD平均にすら届かない。近藤教授は「OECDは『医療費を低く抑えると、医療の質の低下を招き、人材確保も困難になる』と指摘している。 政府は医療費を抑えるため、医師数を抑え続けてきたが、もう限界だ。少ない医師数でやれるというなら、根拠や戦略を示すべきだ」と批判している。(平成19年5月28日 毎日新聞) 認知症の原因のひとつ? 異常たんぱく質の正体解明 人格が変わったり、異常行動をとったりすることが多い認知症の一種、「前頭側頭型認知症」(FTD)の原因とみられる異常たんぱく質の正体を、東京都精神医学総合研究所のグループが突き止めた。病気のメカニズムの解明や治療法開発につながる可能性がある。FTDは、65歳以下の認知症としてはアルツハイマー病に次いで多い。FTDは、脳に、タウというたんぱく質がたまるタイプと、タウ以外のたんぱく質がたまるタイプに分けられるが、タウ以外のたんぱく質の正体は分かっていなかった。長谷川成人チームリーダーと新井哲明主任研究員らは、患者の脳に異常にたまっている物質を詳しく調べ、TDP43とよばれるたんぱく質であることを突き止めた。このたんぱく質は、筋肉が次第に動かなくなる筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者の脊髄にもたまっていることを見つけた。アルツハイマー病では、アミロイドベータという異常たんぱく質がたまることが突き止められてから、これを標的とする治療法の開発が進んでいる。今回の成果も治療法の開発につながる可能性がある。貫名信行・理化学研究所脳科学総合研究センター病因遺伝子研究グループディレクターの話 ALSと認知症の仕組みがどのように関係するのか、新たな研究が発展しそうだ。(平成19年5月27日 朝日新聞) HIV感染者・エイズ発症者、昨年過去最高1358人 2006年の1年間で、エイズウイルス(HIV)に新たに感染した人とエイズを発症した患者の合計が、過去最高の1358人に上ったと、厚生労働省のエイズ動向委員会が22日発表した。 同委員会によると、昨年の感染者数は952人、患者数は406人で、いずれも過去最高。同年末までの感染者数と患者数の累計は1万2394人となった。年齢別では05年に比べ、30、40歳代の感染者数が大幅に増加。30歳代が約21%増えて390人、40歳代が約36%増の164人となった。患者数も30歳以上の中高年で増えていた。感染経路は、同性間の性的接触が768人、異性間の性的接触が363人。感染地域は、感染者の約87%(828人)、患者の約78%(315人)が国内感染と推定された。同委員会委員長の岩本愛吉・東京大医科学研究所教授は「エイズ検査の普及と、感染者の増加によって、過去最高を更新したのだろう」と話している。(平成19年5月23日 読売新聞) 抗リウマチ薬「エンブレル」副作用の発現率 抗リウマチ薬「エンブレル」(一般名:エタネルセプト)の約1万3000例を対象に市販後に行った調査の結果がまとまった。懸念された感染症の発現率は、関節リウマチ治療に用いられる「レミケード」とほぼ同様との結果だった。また、皮下注射による皮膚軟部組織での感染症も低値だった。エンブレルは、皮下注射型の完全ヒト型可溶性TNFα/LTα受容体製剤で、投与後1カ月の間に重大な問題が発生しない場合に自己注射に切り替えることができる。1328施設で1万3477例を登録、データ回収が可能であった7091例を解析した。 その結果、副作用発現率は30.64%で、重篤な副作用の発現率は5.68%。懸念された結核が0.1%の7例、結核疑いが0.04%の3例であった。そのほか、細菌性肺炎が1.35%の96例、間質性肺炎が0.62%の44例、ニューモシスチス肺炎が0.23%の16例であった。皮下注射による皮膚組織などでの感染症は0.56%の40例であった。 また、エンブレル単独投与による副作用の発現率は35.3%に対して、メトトレキサート(MTX)との併用で26.8%だった。投与法の違いによる安全性も評価。通院して投与した場合の副作用発現率は34.2%だったのに対し、自己注射に切り替えた場合は27.5%、6カ月間自己注射した場合は22.6%で、自己投与による副作用の増悪はみられなかった。今回の全症例調査終了により、エンブレルを処方できる医療機関が拡大。(平成19年5月21日 薬事日報) 亜鉛、免疫細胞の情報伝達 体内にある微量元素の亜鉛が、免疫系の細胞で情報を伝達する役割を担っていることを、理化学研究所と大阪大のチームが突き止めた。研究が進めば、新たな薬を生み出す手がかりになりそうだ。亜鉛はたんぱく質の合成や傷の治癒、抗酸化作用といった重要な働きがあり、不足すると免疫低下や発育不全などをもたらすことは昔から知られていた。しかし、他の役割についてはよくわかっていなかった。研究チームは、免疫機能に重要な役割を果たす「肥満細胞」の内部で、亜鉛がどう働いているかに注目。肥満細胞を刺激して特殊な顕微鏡で観察した結果、刺激から数分で、細胞内部の小胞体という器官のあたりから亜鉛が大量に放出されることを突き止めた。研究チームによれば、肥満細胞が活性化すると、炎症物質が放出されるが、亜鉛はこうした物質を作る遺伝子調節にかかわるとみられる。(平成19年5月15日 読売新聞) メタボと寿命の関係 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の人と、そうでない人との死亡率にほとんど差はないことが、自治医科大学の調査でわかった。内臓脂肪型肥満(腹囲が男性で85センチ以上、女性で90センチ以上)であることに加え、血液中の脂質の異常、血糖値が高い、血圧が高い、三つの危険因子のうち二つ以上に該当すると、メタボリックシンドロームと診断される。自治医大は、1992〜95年に全国2176人(男性914人、女性1262人)の健康診断データなどを追跡調査し、メタボリックシンドロームの該当者と死亡率の関連を調べた。対象者のうち、02年末までに男性が79人、女性が58人死亡。死亡者には、調査開始時点でメタボリックシンドロームに該当した男性82人中7人、女性22人中2人が含まれていた。年齢や喫煙、飲酒習慣などの影響を調整して死亡率を比較すると、メタボリックシンドロームの人の死亡率は、そうでない人の1・09倍で、統計的に意味のある差はなかった。ただ、虚血性心疾患や脳卒中など血管病による死亡率は、メタボリックシンドロームの方が約2倍高かった。全体の死亡率に差がないのは、日本人の死因1位ががんで、心疾患が欧米ほど多くないことも関係ありそうだ。もっとも、メタボリックシンドロームだと動脈硬化や糖尿病などのリスクは高まるものの、すぐに死の危険が迫ると言われていたわけではなく、石川講師は「メタボリックと診断されても恐れず、生活習慣の改善に努めればよいのでは」と話している。(平成19年5月12日 読売新聞) パーキンソン病、国内初の遺伝子治療 自治医大付属病院はパーキンソン病患者に国内で初めて遺伝子治療を行った。病気は脳内の神経伝達物質ドーパミンの減少で発病する。治療はドーパミンの生成を促す酵素の遺伝子をウイルスベクター(運び屋)に組み込み、脳内の線条体に注入した。薬物への依存度や副作用が低い治療が期待できるという。発病後約11年が経過した50代の男性患者に、「L−アミノ酸脱炭酸酵素」の遺伝子を注入した。この治療法は米国で6例実施され、重大な副作用は確認されていないという。同病院は今後、6カ月かけて安全性と効果を検証する。同病は手足の震えなどを引き起こす。進行すると転倒しやすくなり、最後には寝たきりになる。国内の推定患者数は約12万人。従来は「L−DOPA」と呼ばれる薬を服用してドーパミンに変換させる薬物療法が行われてきた。(平成19年5月7日 毎日新聞) 脳梗塞死亡リスク、緑茶1日5杯で軽減 緑茶を1日5杯以上飲むと脳梗塞の死亡リスクが男性は42%、女性は62%低下するとの研究結果を栗山進一東北大准教授(公衆衛生学)らが4日までにまとめた。栗山准教授らは1994年から宮城県内の40―79歳の男女約4万500人を追跡調査、1日に緑茶を飲む量で4グループに分け分析した。その結果、脳や心臓など循環器系の病気の死亡リスクは、緑茶を飲む量が多いほど低下。1日に1杯未満の人に比べ、5杯以上飲む人は男性は22%、女性は31%低下した。脳血管障害では男性は35%、女性は42%低下。特に脳梗塞はリスクが低かった。一方、がんによる死亡のリスクとは関連はなかった。 紅茶やウーロン茶を飲む量とこれらの病気の死亡リスクに関連はなかった。 栗山准教授は「予想以上の差があり驚く結果だ。 緑茶に含まれるカテキンなどが体に良い影響を与えている可能性がある」と話している。(平成19年5月5日 日本経済新聞) クロレラに含有「ルテイン」、認知症予防に期待 緑藻類のクロレラなどに多く含まれる成分「ルテイン」に、赤血球の老化を防ぐ効果があることが、東北大大学院農学研究科の研究で明らかになった。老化した赤血球は、アルツハイマー病患者の血中に多く存在し、脳組織に慢性的な酸素不足をもたらして症状を悪化させると考えられていることから、認知症の予防や進行防止への効果が期待される。ルテインは天然化合物カロテノイドの一種。実験で、健康な男女計6人が、ルテインが約10ミリ・グラム含まれた錠剤を1日1粒ずつ、4週間飲んだところ、赤血球に含まれるルテイン量は平均2・8倍に増加した。逆に、赤血球の老化を示す過酸化リン脂質の量は3分の1以下に減っていた。宮沢教授らはこれまでに、アルツハイマー病患者の赤血球には、健康な人の5〜6倍の過酸化リン脂質が蓄積されていることを研究で明らかにしている。過酸化リン脂質が蓄積された状態では、赤血球から酸素が離れにくくなり、脳細胞に酸素を供給する能力が低下する。その結果、認知症の進行を早めている可能性もあるという。宮沢教授は「認知症の発症や進行を予防できる可能性があり、今年中に認知症患者にルテインを投与する臨床試験を始めたい」と話している。(平成19年5月2日 読売新聞) 糖尿病患者の喫煙は腎症リスク2倍 たばこを吸う糖尿病患者は、喫煙しない患者に比べ、人工透析の原因になる糖尿病腎症の危険性が約2倍に高まることが、お茶の水女子大学の研究グループの調査でわかった。生活習慣が関係するとされる2型糖尿病の男性患者357人を、茨城県の診療所で3〜7年にわたって調べた。106人が腎症を発症したが、喫煙している患者では179人中60人が発症したのに対し、喫煙経験のない患者では104人中23人だった。過去に喫煙経験があって禁煙した患者では74人中23人が発症した。年齢や食生活などの要因を排除して解析した結果、たばこを吸っている患者が腎症を発症する危険率は、全く吸わない患者の2・1倍になった。すでにやめた患者でも1・9倍だった。1日の喫煙本数が1本増えるごとに危険率は2%上昇。喫煙年数も、1年増すごとに危険率が2%上昇した。(平成19年5月1日 読売新聞) がん細胞、0.1ミリでも光らせる物質 がん細胞に取り込まれると光り続ける蛍光物質を、米国立衛生研究所と東京大の研究チームが開発した。マウス実験では、従来の検査では見つけにくい小さながんでも強い光を発することが確認された。微小ながんを正確に見つける新しい診断薬の開発につながる可能性があるという。研究チームは、がん細胞に取り込まれると光るスイッチが入り、スイッチが入っている間は、がん細胞の中やがん細胞表面にとどまる物質の開発に取り組んだ。その結果、(1)がん細胞に取り込まれると分解されて光り始め、光ると水に溶けにくくなって細胞から排出されにくい(2)事前にがん細胞が取り込んだ酵素で処理されると光り始め、水にも溶けにくくなる (3)がん細胞表面に張り付けた結合分子と結びつくと光り始め、結合が長く続くという性質を持つ3種の蛍光物質を開発した。いずれも従来の蛍光物質に比べ光が強いという。研究チームは、マウスの腹部に多数のがん細胞を植え付け、これらの蛍光物質を散布して観察。0.8ミリ以上のがんの9割以上を見つけることができ、0.1ミリのがんまでとらえることができたという。がんの詳細な画像診断法には、がんに集まる性質を持つ造影剤を使う陽電子放射断層撮影(PET)などがある。ただ、PETで見つかるがんは現在3ミリ程度までで、解像度には限界がある。蛍光物質を使えば、微小な変化もとらえられるが、体の深い部分にあるがんの場合、蛍光物質の光は体外から確認することができない。研究チームの小林久隆・米国立衛生研究所主任研究員は「最近は内視鏡や腹腔鏡を使う検査や手術が主流になっており、それらを使って患部に近づけば、がんか否かを正確に確認できるだろう。開発した蛍光物質は、すでに眼科の検査で使われているものに近いので、新たな検査技術への活用も可能。卵巣がんの臨床研究から始め、5年程度での実用化を目指したい」と話している。(平成19年4月30日 毎日新聞) 炎症、たんぱく質で調節、ぜんそく治療に応用 炎症反応が過剰にならないよう調節する新たなメカニズムを、理化学研究所が発見した。炎症反応が過剰になることで引き起こされるぜんそくや関節リウマチの原因解明、治療法開発の手がかりになるという。人の体にウイルスや細菌が入ると、痛みや腫れ、発熱などが起きる。こうした炎症は体を元に戻そうという反応の一つだ。 しかし、炎症が続いたり強すぎると、ぜんそくなどのアレルギー疾患やリウマチなどの自己免疫疾患を発症する。炎症反応が起きるには、ウイルスなどの侵入をキャッチする免疫細胞の一つ「樹状細胞」にあるたんぱく質の活性化が不可欠。このたんぱく質が分解されると炎症反応は止まるが、メカニズムは分かっていなかった。理研の生体防御研究チームは、別の免疫細胞の中で働く「PDLIM2」と呼ばれるたんぱく質に着目した。PDLIM2をつくらせないように操作したマウスは、樹状細胞のたんぱく質が分解されず、敗血症を発症させると正常マウスに比べて死亡率が2倍高いことが分かった。これらの実験などから、PDLIM2が炎症反応を過剰にならないように抑制していると結論づけた。(平成19年4月30日 毎日新聞) 高脂血症治療薬に早起き効果 高脂血症の治療薬「フィブレート製剤」に、睡眠のリズムなどを刻む「体内時計」を調節する働きがあることを、産業技術総合研究所生物時計研究グループが突き止めた。睡眠障害を持つマウスにこの薬を飲ませたところ、いつもより早起きし、正常マウスと同じように活動することがわかった。研究チームは今後、この治療薬を飲んでいる患者に早起きの傾向があるか調べ、睡眠障害の治療薬の開発につなげていきたいとしている。 研究チームは、薬を飲む時間帯と効き方との関係をマウスを使って調べた際、薬を飲むマウスが早起きになっていることに気付いた。 薬を含むエサを食べたマウスは3時間ほど活動する時間帯が早くなり、起きる時間が遅くなる「睡眠相後退症候群」の症状を持つマウスに与えたところ、症状が改善したという。薬が体内時計を調節する仕組みは不明だが、同研究グループの大石勝隆・主任研究員は「時差ぼけの改善にも効果が期待できる」としている。(平成19年4月26日 読売新聞) 元気ない40〜50代、男性ホルモン60代より少なく 一般に年齢とともに低下するとされる男性ホルモンの量について、日本人サラリーマンを調べたところ、働き盛りの40〜50歳代の中年層で最も低下しているとの意外な結果が出た。 男性ホルモンはストレスの影響を受けやすいと言われており、調査した帝京大病院泌尿器科の安田弥子講師は、「仕事でのストレスが男性の活力を失わせているのではないか」と話す。20〜30歳代、40〜50歳代、60歳代以上の3世代に分けた健康な男性81人を対象に、活性型男性ホルモンの指標になる唾液中のテストステロンの量を測定。一日のうちでも変動が大きいことから、2時間おきに唾液を採取してもらい変化を調べた。最も高いのは20〜30歳代だったが、次いで高いはずの40〜50歳代の中年層は、半数以上が退職者の60歳代よりもむしろ低かった。男性ホルモンが年齢とともに低下することは、国内外の調査で確認されており、その"常識"を覆す結果だった。テストステロンが低下すると、性欲や性機能の減退のほか、不安や不眠、認知能力の低下といった精神症状や、肩こりや腰痛といった身体症状として表れることが多い。安田講師は、「日本人男性は、勤勉で責任感が強く、管理職である40〜50歳代では仕事のストレスも増える。疲労や抑うつ感といった心身の様々な症状に、男性ホルモンの低下が関係している可能性がある」と話している。(平成19年4月25日 読売新聞) 「高脂血症」あらため「脂質異常症」に 日本動脈硬化学会は、心筋梗塞の引き金になるとされるコレステロール・中性脂肪値の異常を診断する新しい指針を公表した。総コレステロール値を診断の基準にするのはやめ、「悪玉」とされるLDLコレステロール値などで診断するのが柱。病名は「高脂血症」から「脂質異常症」に変更する。指針の改定は5年ぶり。従来の指針では、総コレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪のいずれかが基準より高いか、「善玉」とされるHDLコレステロール値が基準より低い場合を総称して「高脂血症」と呼んできた。 しかし、善玉コレステロール値が低い場合も「高脂血症」と呼ぶのは適当でないとして、病名を変えた。 また、総コレステロール値は血清1デシリットルあたり220ミリグラム以上を「異常」としてきたが、これだと善玉コレステロールだけが多い人も治療対象になってしまう可能性があるため、診断基準から除いた。 新指針では、LDLコレステロールが140ミリグラム以上、中性脂肪が150ミリグラム以上、HDLコレステロールが40ミリグラム未満の場合を「脂質異常症」と診断する。(平成19年4月25日 朝日新聞) 赤ワインで眼病予防を期待 赤ワインなどに含まれるポリフェノールの一種、レスベラトロールに、目の血管を拡張させる機能があることを、旭川医大の研究チームが突き止めた。成人の失明原因でトップを占める糖尿病網膜症をはじめ、血流障害による病気の予防効果が期待される。研究チームは、がんの抑制効果が報告されているレスベラトロールに着目。人が赤ワイン3〜4杯を飲んだ場合の血中濃度に相当するレスベラトロール溶液を作り、ブタの網膜血管を5分間浸して血管の直径を測定したところ、通常の状態から約1・6倍にまで拡張した。同様の効果は、血中のコレステロールを低下させる「スタチン」にもあるが、スタチンが血管内皮に作用するのに対し、レスベラトロールは、血管内皮とその外側にある平滑筋(へいかつきん)の両方に作用し血管を広げていた。研究チームの長岡泰司は「人間で同様の効果が得られるかどうか確かめ、目の病気を予防する薬の開発につなげたい」と話している。(平成19年4月21日 読売新聞) ADHD発症児、母のたばこ影響か 落ち着きがないなどの症状が表れるADHD(注意欠陥・多動性障害)の子どもの場合、母親の喫煙率が同年代の女性の2倍程度高いことが、大阪府の小児科医の調査でわかった。ADHDは、生まれつきの脳の機能異常による発達障害とされ、集中力がない、衝動的な行動をするなどが特徴。治療経験の豊富な大阪府寝屋川市の小児科医院の安原昭博院長が、小児患者の母親167人に喫煙歴などをアンケートした。その結果、喫煙経験は47%にあり、妊娠時にも35%が喫煙していた。特に出産時の年齢が20〜24歳の母親では、喫煙率が88%にのぼった。一般の出生児を対象にした厚生労働省調査では、母親の喫煙率は17%、うち20〜24歳は35%で、ADHD児の母親は2倍程度高い。安原院長は「ADHDには遺伝的要因もあるが、母親の喫煙も関係があると考えられる。妊娠が分かってから禁煙したのでは遅い可能性がある」と話す。 京都市で21日開かれる子どもの防煙研究会で発表する。(平成19年4月20日 読売新聞) 海外新薬、1年半で承認 厚生労働省は患者の要望が強い新薬などを使いやすくする仕組みを整える。使用の承認に必要な治験(臨床試験)を製薬会社が素早くできるよう、複数の国で同時に効能を検証する「国際共同治験」を推進。海外で開発された薬などの承認までの期間を現在の約4年から1年半程度に短縮する。患者の選択肢を増やし、国内医薬品の質の向上につなげる。厚労省は月内に詳細を詰め、医薬品の質の向上に関する5カ年計画をまとめる方針だ。日本は新薬承認に時間がかかり、欧米で一般に使える薬が国内では使えない「ドラッグラグ(薬の時間差)」と呼ばれる問題が深刻化している。(平成19年4月19日 日本経済新聞) 肝臓がん、進行の仕組み解明 C型肝炎ウイルス(HCV)が引き起こした慢性肝炎が肝臓がんに進行する仕組みを、人やマウスの細胞を用いた実験で京都大らのグループが解明した。HCVに感染することにより、本来は免疫細胞にしか存在しない遺伝子編集酵素の一種「AID」が肝細胞に発現し、がんにかかわる遺伝子異常を継続的に引き起こすことを突き止めた。国内のHCV感染者は約200万人といわれる。HCVが引き起こす慢性肝炎は肝硬変を経て、肝がんに進行することが分かっており、肝がんの約4分の3はHCV感染が原因。HCVが未発見で対策が不十分だった時代に感染した人が、10〜40年後に発がんする例が多い。グループが行った培養細胞の実験などから、HCVに感染すると肝細胞内に発現したAIDにより、がんに関連するさまざまな遺伝子に変異が生じることが分かった。(平成19年4月12日 毎日新聞) 休肝日ないと死亡リスク増 酒を全く飲まない「休肝日」が週に2日以下と少ない男性は、3日以上ある人に比べて死亡リスクが最大で1・8倍高いとの結果を、厚労省研究班が発表した。日本酒に換算して週に13合以上と酒量が多い人は特にリスクが高かった。研究班は「こうした人はまず休肝日を作り、次に酒量を日に1−2合程度にまで減らすよう心掛けて」と呼び掛けている。研究班は、全国8地域で40−69歳の男性約4万2000人を1990年から2003年まで追跡。飲酒習慣と、病気や事故を含むすべての死亡との関係を調べた結果、酒量が多く休肝日が少ないほどリスクが高まる傾向を確認した。週に20合以上飲む人の中では、3日以上の休肝日の有無で死亡リスクに1・8倍の差があった。(平成19年4月7日 中国新聞) 心筋梗塞、お酒に効果 お酒を飲むと顔がすぐ赤くなる人でも、適度な飲酒は急性心筋梗塞を予防する効果がある。厚労省研究班が発表した。アルコールには血液を固まりにくくするなどの作用があり、適度な飲酒が心筋梗塞のリスクを減らすことは欧米の研究で知られていた。だが、日本人に多くみられる飲酒で顔が赤くなる人は、逆に飲酒で心筋梗塞になりやすいという報告もあるため、調べていた。調査は40〜69歳の男性2万3千人に、飲酒習慣や顔が赤くなるかなどを尋ね、発症率を9年間追跡した。急性心筋梗塞になったのは170人。うち39人が亡くなった。酒を飲まないグループの心筋梗塞のリスクを1とすると、1日に飲む量が「1合未満」「1〜2合」のグループのリスクは、顔が赤くなるかどうかに関係なく0.5前後だった。(平成19年4月7日 朝日新聞) 飲酒ですぐ赤くなる人、食道がんにご用心 世界保健機関(WHO)は、アルコールと癌の因果関係についての見解を発表した。飲酒で顔が赤くなりやすい人の食道がんの発症率は、赤くならない人に比べて最大で12倍。エタノール(アルコール)は、癌を引き起こす元凶と指摘。アルコールの分解過程で重要な役割を果たすアルデヒド分解酵素の一部が欠損し、働きの悪い人は、飲酒量に比例して食道癌になる危険が高まり、酵素が正常な人の最大12倍になるとした。20年前、飲酒との関係を認定したのは食道がんと肝臓癌など限られたが、今回は乳癌、大腸癌との間にも「因果関係があるのは確実」とした。アルコールを毎日50グラム(ビール大瓶2本程度)摂取した人の乳癌発症率は、飲まない人の1・5倍。大腸癌の発症率も飲酒しない人の1・4倍になるという。(平成19年4月2日 読売新聞) どんな血液型もO型に変換 AとB、AB型の赤血球をO型の赤血球に変えることのできる酵素を米ハーバード大研究チームが開発した。O型の血液は、どの血液型の患者にも輸血できるため、実用化すれば、輸血用血液の血液型の偏りを解消できる。赤血球の表面は、毛のような糖鎖で覆われている。その糖鎖の先に結合している糖の種類によって、A、B、AB型に分かれ、何もついていないのがO型。結合している糖の種類が違うと輸血時に拒否反応が起きるため、O型以外の赤血球は輸血対象が限られる。緊急時など患者の血液型が不明な時はO型を使う。研究チームは、約2500種類の細菌などから、赤血球の糖鎖から糖を分断する能力を持つ酵素を複数発見。それぞれの特徴を遺伝子レベルで調べ上げ、効率を高めた酵素を開発した。この酵素でO型以外の赤血球200ミリ・リットルを1時間処理すると、ほとんどの赤血球がO型になった。(平成19年4月2日 読売新聞) ピロリ菌、がん発症の仕組み 京都大大学院のグループは、ヘリコバクター・ピロリ菌が胃がんを発症させる仕組みを明らかにした。ピロリ菌が、胃粘膜細胞をがん化するために、通常は免疫細胞にしかない「AID」と呼ばれる酵素を利用していたことを突き止めた。細菌が原因でがんができる唯一の例。早期のピロリ菌除菌が胃がん予防に効果的だといえる」と話す。ピロリ菌は幼児時に経口感染し、胃に数十年すみ続け、慢性胃炎を起こす。日本では40代以上の7割が感染しているという。胃がんでは最も重要な発がん因子であることが判明していたが、具体的な仕組みは分かっていなかった。グループは人体の免疫機能を担うAIDが、本来は免疫細胞のBリンパ球にしかないはずなのに、慢性胃炎を起こした細胞に多く現れていることに着目。ピロリ菌を人為的に感染させた胃粘膜細胞にはAIDが多く現れ、重要ながん抑制遺伝子を変異させるなど、がん化する一連の仕組みを確認した。AIDの働きを抑制するなどの新治療法開発の道も開けそうだという。(平成19年4月2日 毎日新聞) アルツハイマー病ワクチン アルツハイマー病の原因物質アミロイドを脳から取り除くワクチンの開発を進めていた国立長寿医療センター研究所と名古屋大などのチームが、マウスを使った実験で発症後に飲むと認知能力が戻ることを確かめた。 脳炎や出血などの危険な副作用もなかった。研究チームは次の段階として、少人数の患者を対象にした臨床試験の準備を進めている。このワクチンは、病原性がないウイルスの殻にアミロイドというたんぱく質を作る遺伝子を入れてある。口から飲むと、腸の細胞がこの「偽ウイルス」に反応してリンパ球がアミロイドを攻撃する抗体を作る。この抗体が脳にたまったアミロイドにくっつき、ばらばらにして取り除く。研究チームは、月齢を重ねると必ずアルツハイマー病を発症するよう遺伝子を変化させたマウス28匹を使って、効果を試した。 アルツハイマー病を発症した生後10カ月の時点で、半数の14匹にはワクチンを飲ませ、残りには飲ませなかった。その結果、ワクチンを飲んだマウスはほぼすべて3カ月後、記憶力や学習能力など認知力を試す4種類のテストすべてで成績が発症前のレベルまで戻った。一方、ワクチンを飲まなかったマウスは全テストで成績が落ち、認知力の大半を失っていた。今回開発したワクチンは直接たんぱく質などを注射する方法ではないため安全性が高く、大量生産が可能なうえ、薬液を飲むだけで簡単という利点がある。(平成19年3月29日 朝日新聞) 療養病床削減、老人ホーム経営容認 長期入院する高齢者向けの医療施設「療養病床」の削減問題で、医療機関が療養病床を介護施設に転換する際の政府の支援策の全容が明らかになった。禁じていた医療法人の有料老人ホーム経営を認めたり、施設改修時の融資を上乗せすることなど順次実施する。政府は療養病床を11年度末までに6割削減する方針だが、計画は進んでおらず転換を促したい考えだ。厚労省は「療養病床の患者の多くは、医療を提供する必要性が低い」とみており、療養病床を老人保健施設など介護施設に転換する方針を打ち出している。医師や看護師の配置が少なくて済む介護施設に切り替え、医療費を抑制する考えだ。しかし、医療機関は転換後の経営見通しに不安を抱いており、削減は進んでいない。そこで厚労省は、支援が必要と判断。医療法人にも、療養病床の転換先となる有料老人ホームや、高齢者専用の賃貸住宅経営を認める。また、介護施設に改修すれば法人税を軽減し、医療機関と併設する場合は、診察室、階段、エレベーターなどの共用を可能にする。(平成19年3月28日 毎日新聞) 臍帯血から効率良く骨作成 赤ちゃんのへその緒や胎盤にある臍帯血から、様々な細胞に育つ可能性がある幹細胞を高い確率で取り出し、軟骨や骨を作ることに、東大医科学研究所が成功した。高齢化とともに、寝たきりの原因になる骨折や、膝が痛む変形性膝関節症などの患者が増えており、骨や関節を再生する治療につながると期待される。出産から5時間以内に採取した臍帯血から、25例中20例の高率で幹細胞を取り出すことに成功。薬剤とともに3週間培養したところ、コラーゲンなどを含む直径約3ミリの軟骨ができた。臍帯血から幹細胞を取り出したとの報告はこれまでにもあるが、実際に採取するのは極めて困難だった。軟骨細胞は骨髄や脂肪組織の幹細胞からも作れるが、臍帯血の幹細胞は、直径で骨髄の2倍近く、脂肪細胞の10倍以上大きく成長した。幹細胞などから、失われた組織や臓器を作る再生医療の研究が進んでいる。幹細胞を骨髄から採取するのは、体に大きな負担がかかるのに対し、臍帯血はこれまで廃棄してきたものを活用する利点がある。(平成19年3月27日 読売新聞) 変形性関節症の遺伝子特定 軟骨の摩耗などで関節の痛みや変形、歩行障害が起きる変形性関節症の発症に「GDF5」という遺伝子が関係していることを理化学研究所と中国・南京大などの研究チームが突き止めた。この病気の患者は日本で約1000万人にも上る。遺伝と環境要因の相互作用で発症するとされ、これまでも関係する遺伝子が見つかっているが、発症の詳しい仕組みは未解明。今回の成果は、将来の発症のしやすさの予測や、新たな治療薬開発につながるという。研究チームは、関節の形成や軟骨細胞の分化に関係するGDF5に着目し、日本人と中国人を対象に、その塩基配列を解析した。この遺伝子の働きを調整する特定部分に「チミン」という塩基を持つ日本人は、そうでない人と比べて股関節の変形性関節症に約1・8倍かかりやすいことが判明。膝でも同様で、日本人で1・3倍、中国人で1・5倍なりやすく、関節の部位や人種にかかわらず、この遺伝子が発症に関係している可能性が高いことが分かった。(平成19年3月26日 中国新聞) 脳梗塞の後遺症の程度、病院間で大きな差 脳梗塞で入院した患者の後遺症の程度は、病院によって大きく異なり、同じ病状の患者が、ある病院では自力で歩いて退院できるのに、別の病院では歩けなくなるなどの差が出ていることが、厚労働省研究班の調査で分かった。脳卒中専門の内科医が多く勤務する病院ほど後遺症が軽く、専門でない内科医が治療にあたる病院で重かった。研究班は、国立病院機構に所属する病院のうち、脳梗塞の治療に熱心な26病院を対象に、2005年から2006年にかけて入院した脳梗塞患者合計1775人について、入院時の病状や、退院時の後遺症の程度を調べた。後遺症は、国際的な尺度に従い、全く症状がない「0」から、死亡の「6」まで7段階で点数化した。最初の病状を考慮して回復の度合いを比較すると、50人以上の患者を治療した病院に限っても、最も軽い病院の患者は、最も重い病院の患者より約1.2点分、退院時の後遺症が軽かった。患者数の少ない病院も加えると、差は2・3とさらに広がった。分析すると、治療チームに脳卒中専門医が9人以上いる病院は、5人以下の病院と比べ約0.4点、後遺症が軽かった。大規模な病院でも、専門医が少なければ治療成績は上がらなかった。一方、チーム内に脳卒中が専門でない一般内科医が1人でもいると、全員が専門医である病院に比べ約0・2点分重くなった。(平成19年3月22日 毎日新聞) がんの痛み、薬剤師も管理 欧米に比べて遅れているとされる痛みの緩和ケアに薬剤師も積極的にかかわろうと、「日本緩和医療薬学会」が結成された。モルヒネなど医療用麻薬の効果的な使い方の普及に、「薬の専門家」として一役買いたい考えだ。将来的には専門薬剤師の認定制度をつくることも検討している。 緩和ケアは、患者の生活の質(QOL)を高める手段として積極的に導入する医療機関が増えており、このチームに薬剤師を加える医療機関も増えてきている。さらに自宅で療養するがん患者らの間でも緩和ケアのニーズは高まると予想される。このため保険薬局の薬剤師も、緩和ケアについて理解を深め、往診する医師や看護師らと連携する必要性が高まっている。 がんを専門とする薬剤師としては、日本病院薬剤師会が今年度から認定試験を始めた「がん専門薬剤師」制度がある。しかし、抗がん剤を専門とする薬剤師の育成が大きな目的のため、新たに発足する緩和医療薬学会は、モルヒネなどによる緩和ケアに特化した専門薬剤師の育成を目指す。(平成19年3月19日 読売新聞) 人工リンパ節、免疫力20倍 人工的に作成したリンパ節を免疫力の低下したマウスに移植し、免疫機能を正常マウスの約20倍に高めることに理化学研究所が成功した。高い免疫力は1カ月以上持続した。免疫力の強化は、エイズなどの重症感染症やがんなどの治療に有効だという。リンパ節はわきの下や頚部などにあり、ヒトの体に入ったウイルスなどの異物(抗原)が運ばれてくる組織だ。リンパ節中の免疫細胞が異物と結合すると免疫反応が始まり、異物を排除する抗体を作り出す。研究チームは、たんぱく質の一種のコラーゲンを3ミリ角のスポンジ状にし、免疫反応に重要な2種類の細胞を染み込ませた。これを正常なマウスの体内に移植すると、リンパ節に類似の組織ができた。複数の免疫細胞が本物と同じ比率で存在し、血管も形成された。この人工リンパ節を、免疫不全症を起こしているマウスに移植したところ、異物に対する血中の抗体量が正常マウスの約20倍にも高まり、1カ月以上持続した。(平成19年3月19日 毎日新聞) 骨形成に必須なたんぱく質「活性型オステオカルシン」をブタ煮骨から抽出に成功 タカラバイオ株式会社は、ブタの煮骨から骨の形成に必須なたんぱく質「活性型オステオカルシン」製造方法を世界で初めて開発しました。骨粗鬆症は、骨分解と骨形成のバランスが崩れ、相対的に骨分解が優位となり、骨量が減少し骨折が起こりやすくなる病態をさし、「寝たきり老人」増加の主な原因となっています。特に女性の場合、閉経により骨量の減少が急速に起こります。現在、日本では約1,100万人(2000年)の骨粗鬆症患者がいると推定され、70歳以上の女性では、その4割以上が骨粗鬆症の診断基準にあてはまると報告されています。「活性型オステオカルシン」は骨芽細胞により産生されるたんぱく質であり、カルシウムを骨に蓄積する機能があります。「オステオカルシン」分子内のグルタミン酸残基がγ−カルボキシグルタミン酸残基に変換されたものは「活性型オステオカルシン」と呼ばれ、活性型のみがカルシウムを骨に蓄積できることが知られています。豚煮骨由来の抽出物には、この「活性型オステオカルシン」が含まれるため、骨分解と骨形成のバランスを骨形成に期待。(平成19年3月7日 日経新聞) 介護福祉士に上級資格 厚生労働省は重度の認知症患者などを世話し、介護事業で指導的役割を担える介護福祉士の上級資格として「専門介護福祉士」制度を創設する。近く有識者会議を設置し、2007年度中にも制度の具体的な内容を決定する。「仕事がきつく、給料が安い」とされる介護福祉士は人手不足が深刻化しているため、新制度創設により、待遇改善などにつなげたい考えだ。新たな資格は、一定の実務経験や、新たな研修の履修などを要件とする方向だ。また、「認知症ケア」「事業の運営管理」など、介護の専門分野に応じた複数の資格とする方向で検討する。介護福祉士は1988年に始まった国家資格。2006年10月末現在、約54万8000人が取得している。「入浴、排せつ、食事」の身体介護が主な役割だが、現在は、認知症や障害者へのケアなど、介護ニーズが多様化している。2005年の厚労省調査によると、施設で働く介護福祉士らの平均年収は、男性が約315万円、女性が約281万円で、全労働者平均の約452万円を大きく下回る。一方で、介護職員の離職率は22・6%で、全労働者の17・5%を上回る。専門家からは「業務内容に比べて賃金水準が低い」との指摘が出ていた。新制度は、介護福祉士のキャリアアップを可能にすることにより、やりがいを感じ、給与水準を向上させることを目指している。(平成19年3月6日 読売新聞) 新薬審査を迅速化 厚生労働省は新薬の承認審査を担当する独立行政法人「医薬品医療機器総合機構」で新薬審査と臨床試験相談に当たる人員を、2009年度までの3年間に230―240人程度増やし、現在の約200人から倍増させることを決めた。 新薬の承認審査にかかる手数料の単価を引き上げ、増員の費用に充てる。審査体制を強化し、承認審査の迅速化を図る考えだ。国内では新薬が承認されるまでの時間が欧米より長く、例えば米国の平均1年に対し、日本は倍の約2年。このため欧米で承認済みの薬が国内ではなかなか使用できないのが現状で、医薬産業政策研究所の調査では、世界の売り上げ上位医薬品の約3割が日本では未承認だという。薬の承認審査に当たる人員は、2005年、米国は2200人、フランスは942人、英国は693人に対し、日本は197人と、欧米に比べ大幅に少なく、これが審査に時間がかかる要因の一つとなっている。(平成19年3月7日 日本経済新聞) 療養病床から介護施設に転換 病状が安定した高齢者が長期入院している「療養病床」を6割削減して、介護施設に転換する政策を厚生労働省が進めている。しかし、全国の病院・診療所で実際に介護施設への転換を予定している病床数は1割に満たない。6割近くが療養病床や一般患者向けの病床としての存続を望んでいる。「2011年度末までに6割削減」という国の目標との隔たりは大きく、療養病床削減で必要になる高齢者の受け皿の確保も難しい現状が浮き彫りになった。 療養病床には現在、医療保険を使って入院するベッド(25万床)と、介護保険を使うベッド(13万床)がある。計38万床のうち、厚労省は医療費抑制のため、今後5年間で23万床を削減。療養病床は病状が比較的重い患者だけを対象とする医療保険型の15万床のみとし、残る23万床は行き場がなくなる高齢者の受け皿として、老人保健施設や有料老人ホームなどへの転換を促す計画だ。厚労省は昨年7月、療養病床の軽度の患者に対する診療報酬を大幅に引き下げる一方、介護施設に移行しようとする病棟への優遇措置を設定。介護施設への転換を促そうとしたが、これまで優遇措置を利用している医療機関はほとんどない。 今秋をめどに、各都道府県は「地域ケア整備構想」を策定し、地域ごとの療養病床の転換目標を定める予定だ。 厚労省は「介護施設の整備計画などが自治体ごとに明らかになれば、転換を希望する医療機関も増えるのではないか」とするが、計画通りに転換が進むかどうかは不透明で、受け皿が不足し、高齢者が行き場を失う可能性もある。 キーワード:療養病床の削減・転換 医療サービスの必要性が必ずしも高くない高齢者が施設代わりに入院する「社会的入院」を解消するため、2006年の医療制度改革に盛り込まれた。患者を高コストの医療機関から介護施設に移すのが狙い。厚労省の試算によると、療養病床の6割削減で、医療保険給付は12年度時点で年間4000億円削減できる。患者の多くが介護施設に移るため、介護保険は1000億円増えるが、差し引き3000億円の給付抑制につながるという。(平成19年3月7日 朝日新聞) CT定期診断、肺がんの死亡率低下に無効果 肺がんの早期発見が期待されるコンピューター断層撮影法(CT)による定期診断は、肺がんによる死亡率を低下させる効果がなく、不必要で有害な医療行為にもなりかねないという調査結果を米メイヨー・クリニックなどの研究チームが発表した。研究チームは「より決定的なデータが得られるまで不必要なCTの診断を受けるべきでない」と提言している。調査は、肺がんのリスクの高い喫煙者と元喫煙者3246人を対象に、4年間、毎年1回CT診断を実施。この間、肺がんで亡くなったり、進行性の肺がんと診断された患者の割合を、過去のデータをもとに算出したCT診断を受けない場合と比較した。その結果、死亡率、進行がんに発展する率とも、診断を受けた場合と受けない場合に大差がないと判明。小さながん細胞を早期発見し、早く治療することで死亡率を引き下げるという、CT診断に本来期待される効果がほとんど得られないとわかった。研究チームは「CT診断で肺がんを早期発見することはできるが、治療しないと急速に悪化するがんは見逃している可能性がある」としている。ただ、米国では、CT診断が「がん予防に役立つ」との調査結果もあり、死亡率の集計など、この研究のデータ解釈に疑問を投げかける専門家の声も出ている。肺がんのCT診断の効果とリスクについては、米国立がん研究所などが同国とオランダで疫学調査を実施している。(平成19年3月8日 読売新聞) がん細胞、自滅させる酵素を発見 がん細胞を自滅に導く酵素を、吉田清嗣・東京医科歯科大研究チームが発見した。酵素の働きを高められれば、抗がん剤の投与量を減らして副作用を軽減する効果が期待できるという。遺伝子の本体であるDNAが紫外線や放射線などの影響で変異することで、細胞はがん化する。変異が大きいと、細胞中のp53遺伝子が働き、細胞はアポトーシスと呼ばれる自滅現象を起こす。p53は酵素の働きで活性化すると考えられていたが、その酵素が何かは特定されていなかった。研究チームは、ヒトのがん細胞を使い、p53が活性化する時にDYRK2という酵素が働いていることを突き止めた。さらに、薬剤で細胞のDNAを傷つけると、この酵素が細胞質から核の中に移動してアポトーシスが始まることを確認。酵素が働かないようにすると、アポトーシスが起きなくなることから、p53にスイッチを入れる働きを持つと断定した。吉田助教授は「抗がん剤や放射線治療は正常な細胞にもダメージを与える。DYRK2が必要な時に必要な細胞で働くよう工夫できれば、患者の負担を小さくする治療につながる」と話す。(平成19年3月9日 毎日新聞) 人工股関節、長持ち技術開発 人工股関節の摩耗を防従来の5倍以上も長持ちさせる新技術を、東京大バイオマテリアル工学の研究グループが開発した。人工股関節は、高齢者に多い変形性関節症や関節リウマチなどの病気の場合に用いられる。合金でできた脚側の球状の骨頭部を、骨盤側に埋めたポリエチレン製のカップで繰るんで関節の代わりにする仕組みで、国内では年間約10万件の手術が行われている。しかし、使っているうちに摩耗してポリエチレンの微粉末が生じ、周辺の骨を溶かすため関節が緩んでくる。痛みや歩行障害が生じるため、患者は10〜15年で取り換えなければならないという欠点があった。石原教授らは生体や水になじみやすい「リン脂質ポリマー」という新しい高分子化合物を開発してポリエチレン製カップの内壁を覆い、関節内に水の薄い膜を作ることで摩耗を防いだ。65年分の歩数に相当する6500万回の稼働テストでもほとんど摩耗がなかった。石原教授は「一度手術すれば生涯使え、患者の負担や医療費を大幅に減らせる」と話している。(平成19年3月9日 毎日新聞) アルツハイマー病発症原因 佐賀女子短大、長谷川亨教授はアルツハイマー病が高齢者に多く発症するメカニズムの一つを解明した。老化によって神経細胞の働きが抑制されると、同病を引き起こす物質「ホモシステイン酸」が脳の神経細胞死を招く働きをすることを実験で示した。教授は2005年にホモシステイン酸の有害な働きを初めて特定。今回の実験では老化との関係を分析した。老化が進み、神経細胞の働きが弱くなると、ホモシステイン酸が細胞内に有害物質を蓄積させ、別の原因物質と組み合わされることで細胞死することが分かった。若い世代では、ホモシステイン酸があっても、有害物質が蓄積されていないので、神経細胞死までは起きないという。教授によると、喪失体験やPTSD(心的外傷後ストレス障害)などの強いストレスがアルツハイマー病の危険因子とされており、ホモシステイン酸はそのようなストレスが持続的に続いた際に増える。(平成19年3月5日 毎日新聞) 「在宅」床ずれ12万人、介護背景に重症化 在宅介護を受けている人の6%が床ずれを患い、全国で少なくとも12万人にのぼると推計されることが、日本褥瘡学会の調査で明らかになった。床ずれを持つ人のうち6割は、寝たきりで全面介助が必要な患者だった。 床ずれは、寝たきりで腰骨やかかと、ひじ、肩の骨周辺の皮膚や筋肉に、体圧がかかるなどして血流が妨げられ、皮膚がただれて組織が壊死する。重症化すると、皮膚に直径十数センチの穴があくこともあり、感染を招いて敗血症など生命に危険が及ぶ恐れもある。看護師を派遣する全国約1400の訪問看護ステーションにアンケートし、4分の1の施設が回答した。それによると、訪問看護を利用していた7万3000人余のうち、6%の約4200人に床ずれがあった。そのうち43%は、皮膚に穴があくなど専門的治療が必要な重症の状態だった。床ずれ患者を5段階の要介護度別にみると、要介護5の人が59%を占め、要介護4では22%と、寝たきりかそれに近い人ほど多かった。全国では約200万人が「要介護認定」を受けて在宅で過ごしており、12万人が床ずれを持っている計算になる。(平成19年3月5日 読売新聞) 75歳以上に「かかりつけ医」 厚生労働省は75歳以上の高齢者向けに、公的な「かかりつけ医」制度を2008年をめどに創設する方向で検討に入った。特定の開業医が患者の心身の状態を普段から把握し、外来診療から在宅ケア、みとりまで対応する。患者が信頼できる医者をもつことで、入院から在宅治療への高齢者医療の転換を促し、医療費を抑制する狙いもある。厚労省は今秋までに独自の診療報酬体系の骨格をつくる予定で、すでに方針を固めている外来の「定額制」とともに、かかりつけ医の導入をその柱とする。 かかりつけ医の条件は(1)高齢者が抱える複数の疾患を総合的に診断・治療し、必要なときには心のケアも行える (2)介護保険のケアマネジャーらとも連携をとり、患者の生活に合わせた在宅療養のアドバイスができる (3)積極的な訪問診療を行う (4)痛みを緩和するケアなど末期医療に対応できる、など。 厚労省は、こうした条件を満たす医師を公的に認定。 患者の合意を得たうえで「かかりつけ医」として扱う。かかりつけ医を持つかどうかは高齢者本人の意思に任せるが、できる限り利用を勧める。かかりつけ医がいる場合でも、病院など他の医療機関も直接受診できるようにする方針だ。だが、開業医でも専門分野ごとに細分化が進んでおり、患者の心身を総合的に診断できる医師は少ないのが実情だ。このため、かかりつけ医に必要な緩和ケアなどの技能を身につけられるよう、開業医に対する研修制度も充実させる。(平成19年3月3日 朝日新聞) ビタミンC、白内障を抑える効果 日ごろの食事でビタミンCを多くとっていると白内障になる率が低いとの結果が、厚生労働省研究班の調査で出た。白内障は目の中の水晶体が酸化されて濁ることで発症するが、ビタミンCには酸化を抑える作用があり、濁りを防ぐとみられるという。研究班は95年、岩手、秋田、長野、沖縄の各県に住む男性約1万6000人と女性約1万9000人を対象に調査した。摂取量で5グループに分けて比べると、男性で最多のグループ(1日のビタミンCが約210ミリグラム前後)は、最少のグループ(同約50ミリグラム前後)に比べ、白内障にかかる率が約35%低かった。女性でも最多のグループ(同約260ミリグラム前後)の発症率は、最少のグループ(同約80ミリグラム前後)より約41%低かった。吉田助手によると、ビタミンCは、温州みかん1個に約35ミリグラム、レモン1個に約20ミリグラム含まれる。野菜ではホウレンソウやブロッコリーに多い。吉田助手は「1種類でなく、さまざまな食べ物からビタミンCをとってほしい。たばこを1本吸うと約25ミリグラムのビタミンCが破壊されるため、白内障予防には禁煙が望ましい」と話している。ビタミンCをサプリメントでとった場合の効果は、今回検証していない。海外の研究でも結論は出ていないという。(平成19年2月27日 毎日新聞) 膵臓・スキルス胃癌の治療に手がかり 抗癌剤を入れた極小カプセルと癌の血管形成を妨げる薬の併用が、難治性の膵癌やスキルス胃癌の治療に有効であることを、東京大と大阪市立大が動物実験で突き止めた。これらの癌は早期発見が難しいため、外科手術ができない場合が多く、今回の研究成果が新たな治療法に道を開くと期待される。研究チームは、抗癌剤をくるんだ直径約65ナノ・メートル(ナノは10億分の1)の球状カプセルを、大量に静脈注射する癌治療法を開発している。癌が延ばす血管には、普通の血管にはない約100ナノ・メートルのすき間がたくさん開いていて、そこから漏れた抗癌剤カプセルを、癌細胞に蓄積させ、癌をたたくやり方だ。ところが、膵臓癌やスキルス胃癌は他の癌より血管の数が少ないため、この手法ではカプセルが癌全体に行き渡らず、うまくいかなかった。このため癌の血管形成に必要な因子「TGF―β」の阻害剤をマウスにごく少量投与した結果、癌細胞の血管壁がきちんと形成されず、すき間がより大きくなった。カプセルを注射すると、血管が少なくても、癌をたたくのに十分な量のカプセルが、がん細胞内に流れ込むようになった。何もしないマウスと比べ、膵臓癌の大きさは6分の1、スキルス胃がんは半分まで小さくなった。(平成19年2月23日 読売新聞) 高身長・未出産の女性、乳がんリスク高い 日本人で乳がんのリスクが高い女性は、身長160センチ以上、出産経験がない、初潮年齢が早いなどの傾向があることが、厚生労働省研究班の約5万5000人を対象にした疫学調査でわかった。乳がんの発生には女性ホルモンの分泌が関与しているとされ、大規模な調査で裏付けられた形だ。同研究班は1990年と93年に40〜60代だった全国の女性を対象に追跡調査を実施。閉経の前か後か、体格、初潮年齢などの条件で集団に分け、2002年までに乳がんを発症した人数から、各集団の危険性を比較した。閉経後の場合、身長160センチ以上の女性は、同148センチ未満の女性に比べ、乳がんのリスクが2・4倍に高まった。また48歳未満に閉経した人に比べ、54歳以上で閉経した人のリスクは2倍になった。出産経験がない女性は、ある女性に比べ2・2倍だった。閉経前の場合、初潮年齢が16歳以上だった女性は、14歳未満だった人に比べ、リスクが約4分の1に下がった。出産経験がない閉経前の女性は、ある女性に比べて1・7倍に増えた。 (平成19年2月21日 読売新聞) よく運動する男性、大腸がんリスク3割減 男性で運動や肉体労働などで体をよく動かす人は、ほとんど体を動かさない人に比べ、大腸がんになるリスクが3割も低いことが、厚生労働省研究班の大規模な疫学調査でわかった。研究班は1995年と98年の2回、全国の45〜74歳の中高年男女約6万5000人を対象にアンケート調査を実施した。それぞれが一日に運動する時間と運動の強さを調べ、活動量を計算。活動量の差で4集団に分け、2002年まで追跡調査し、大腸がんを発症する危険度を比較した。その結果、男性では活動量が多い集団ほど大腸がんになるリスクが下がる傾向があり、激しい運動などで最も体を動かす集団は、最も体を動かさなかった集団に比べ、31%も低かった。結腸がんのリスクの差は42%もあった。体を動かすと、がんの危険因子である肥満や糖尿病の予防につながるほか、腸の発がんにかかわる生理活性物質を少なくする効果があると考えられる。(平成19年2月20日 読売新聞) 歯の再生、マウスで成功 神経も、入れ歯代替に期待 歯のもとになる組織(歯胚)から、神経や血管を含め、歯をまるごと再生させることに、東京理科大と大阪大のチームが世界で初めて成功した。マウス実験での成功率は80%と高く、将来的に入れ歯やインプラント(人工歯根)に代わる方法として期待される。さらに、開発した技術は他の臓器や器官の再生医療にも応用できるという。研究チームは胎児マウスの歯胚から両細胞を採取。それぞれの細胞に分離したうえ、寒天状のコラーゲンの中に重ねるように入れ培養したところ、高さ0.25ミリの「歯の種」ができた。これを拒絶反応を起こさない種類の大人のマウスの抜歯部に移植すると、約2カ月後には長さ4.4ミリに成長。歯の内部には血管と神経があることを確認した。抜歯部に移植を試みた22回中17回で歯が再生した。一方、マウスの毛でも同様の方法で培養し、毛の再生にも成功した。人での実施には、胎児からの歯胚入手という倫理上の課題や、別人からの移植に伴う拒絶反応の問題もある。研究チームは、患者自身の口内や頭皮から、基になる細胞を探していくという。(平成19年2月19日 毎日新聞) 健康食品の安全性のため成分届けの義務化 健康ブームを背景に多種多様な商品が出ているサプリメントなどの健康食品に関し、厚生労働省は、安全性の検討を決めた。同省では食品衛生法の改正も視野に入れており、食品に含まれる成分の届け出の義務化の是非などについて協議する。国内の市場規模は健康ブームとともに拡大し、2000年には1・3兆円あり、10年には3・2兆円に達すると見込まれる。サプリメントなどの健康食品は、製造過程で栄養成分を抽出・濃縮することが多いため、原料に含まれる微量な有害物質も同時に濃縮される恐れがあるほか、品質の低さや副作用の懸念が指摘されるものもあり、一般の食品などと比べ、安全の確保がより重要な課題となっている。昨年2月、ビールメーカー子会社が製造していたキノコの一種「アガリクス」を使った食品に、他の発がん物質による発がんを促進する作用のある成分が含まれていることが判明。また、大豆イソフラボンのような有用な成分でも、濃縮サプリメントによる過剰摂取で健康への悪影響が否定できないケースもあった。(平成19年2月12日 読売新聞) 月経血から筋ジストロフィー治療へ 女性の月経血に含まれる細胞をマウスに注射し、不足すると筋ジストロフィーを引き起こすたんぱく質を作ることに、国立成育医療センター研究所が成功した。筋ジストロフィーは、筋肉を動かすジストロフィンと呼ばれるたんぱく質の不足や異常が原因で発病する難病。 同研究所生殖医療研究部は、女性の月経血に含まれる細胞に着目、ボランティアの女性から提供を受けた月経血を、試験管の中で約3週間培養したところ、筋肉細胞を作ることに成功した。続いて「月経血に含まれる細胞を注射すれば、体内で筋肉細胞に変化するのでは」と考え、ジストロフィンを先天的に作ることのできないマウスの足に、この細胞を注射した。その結果、約3週間後にマウスの筋肉細胞と注射で移植した細胞が融合し、ジストロフィンを分泌していた。梅沢部長は「月経血に含まれる細胞は子宮内膜細胞と思われ、筋肉細胞に非常になりやすい性質を持っている。できるだけ早く筋ジストロフィーの治療に利用できるように研究を進めたい」と話している。(平成19年2月6日 読売新聞) 手術後の癌再発ワクチン 全国13の大学病院やがん専門病院などが、がんを攻撃する免疫細胞を活性化させる「がんワクチン」の臨床研究ネットワークを作った。一部で患者への接種も始まった。対象とするがんは膵臓や食道、肝臓、胃、肺、膀胱など多岐にわたる。安全性を確かめた後、手術後の再発を予防する目的で接種。数年後の実用化をめざす。 がんワクチンはこれまでいくつかの大学病院で個別に臨床研究されてきたが、これほど規模が大きく、組織だった研究は初めて。東大医科学研究所ヒトゲノム解析センターが開発した約10種のワクチンを使う。同センターは、人の遺伝情報をつぶさに調べ、正常細胞のもとではほとんど働かないのに、がん細胞の中だと活発に働く遺伝子を特定。それらを基にワクチンを作り、がんに対する免疫細胞を活性化させるかどうかを実験で検証した。 臨床研究は、まず人での安全性を調べる第1段階から始める。((平成19年2月6日 朝日新聞) 乳がんの見落とし、40代では3割ある マンモグラフィー(乳房X線撮影)を視触診と併用する乳がん検診を受けても、40代では3割近くが乳がんを見落とされている可能性があることが、厚生労働省研究班の研究でわかった。乳腺密度が濃い40代は、マンモグラフィーに腫瘍が映りにくい可能性が以前から指摘されていた。それが裏付けられた形で、研究班は、超音波を併用する検診の研究が必要だと指摘している。宮城県でマンモグラフィー併用検診を受けた延べ約11万2000人について、検診後の経過を追跡調査した。宮城は「地域がん登録」の実施県で、がんになった住民の治療や予後の情報が、県に集積されている。研究班は、検診で「陰性」とされたのに、その後、次の検診を受けるまでに乳がんが見つかった人を「見落とされた可能性がある人」と判断。検診で乳がんを発見できた人と合わせ、「乳がんがある人を、がんと正しく診断できた割合」を算出した。その結果、40代の感度は71%で、3割近くが見落とされていた可能性があったことがわかった。50代の感度は86%、60代は87%だった。 日本では、乳がんにかかる人は40代が最も多い。だが40代は乳腺密度が濃く、マンモグラフィーに腫瘍が映りにくいといわれている。一方、エコー検査は乳腺の濃さに影響されにくく、20〜40代の乳がん発見に効果が高いと期待されている。(平成19年2月5日 朝日新聞) 高脂血症の診断基準 日本動脈硬化学会は、心筋梗塞など動脈硬化性疾患の予防や治療の指標から従来の「総コレステロール」をはずし、代わりに「悪玉コレステロール」といわれるLDLコレステロールなどを判断基準とする新しい診療ガイドラインを策定した。狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などの病気を招く「高脂血症」の診断基準には、一般的に総コレステロールが使われている。02年に策定したガイドラインでも、血液1デシリットルあたり220ミリグラム以上を「高コレステロール血症」とし、心筋梗塞などを防ぐには220ミリグラム未満に抑えるよう求めてきた。しかし、「高コレステロール」の中でも、「善玉」のHDLコレステロールが多い場合にはLDLコレステロールは通常より低く、動脈硬化につながりにくい。日本人はこうしたケースが多く、総コレステロールを基準にすると、必要量以上の投薬が行われるなどの問題が分かってきた。このため、5年ぶりの改定では総コレステロールを基準から外し、高コレステロール血症は「LDLコレステロール140ミリグラム以上」とした。(平成19年2月4日 毎日新聞) 老後に夫と同居(妻の死亡確率2倍) 愛媛県総合保健協会の藤本弘一郎医長は「夫が日常生活の多くを妻に依存している高齢者が多く、肉体的にも精神的にも妻には夫の存在が負担になっている」と指摘している。 調査では、96〜98年に松山市に隣接する旧重信町(現・東温市)で、60〜84歳の男女約3100人に配偶者の有無や喫煙習慣、糖尿病や高血圧の治療歴など17項目を答えてもらった。 約5年後の01〜02年に対象者の生死を確認。調査中に死亡した男女計約200人と生存していた約2900人を比べ、配偶者の有無などが死亡に与えた影響を60〜74歳と75〜84歳(いずれも96〜98年当時)で分析した。その結果、75〜84歳では、女性は夫がいる方が、いない場合に比べて死亡リスクが2.02倍に高まった。一方、男性は妻がいる場合、いない場合に比べて0.46倍に下がっていた。60〜74歳でも同様の傾向が見られたという。 藤本医長は「夫の依存が妻に負担をかけている一方で、妻に先立たれると夫は身の回りのことを助けてくれる存在を失い、逆に死ぬ危険性が高まる。夫が家事などを覚えて自立することが大切だ」と話す。(平成19年1月29日 朝日新聞) 急性心筋梗塞に衝撃波 東北大病院は急性心筋梗塞の患者に体外から衝撃波を当て、心臓に新たな血管をつくり慢性心不全への悪化を防ぐ治療の臨床試験を2月から始めると発表した。急性心筋梗塞は、心筋に栄養を送る血管が急に詰まって一部の心筋が傷む疾患。詰まった血管を広げるカテーテル治療などで救命しても、やがて傷みが広がり慢性心不全になる。悪化を抑えるには飲み薬しかない。循環器内科の下川宏明教授らは、尿路結石破砕用の約10分の1の出力の衝撃波が、血管内皮を刺激して新たな血管づくりを促すことを確認。この治療は既に重症狭心症患者に対する臨床試験が順調に進んでおり、急性心筋梗塞患者にも適用する。成功すれば痛みや副作用がない治療が可能になる。(平成19年1月25日中国新聞) 今春の花粉は少なめ 環境省は今春のスギとヒノキの花粉飛散量について「地域により平年の20%程度から平年並み」との予測を発表した。少なめの予想で花粉症に悩む人には朗報だ。飛散開始時期も例年並みか、やや遅れる見込みだという。北海道や東北北部では平年並み、九州では平年並みか、やや少なくなる。そのほかの地域では平年を下回る見通しで、東北南部が平年の50%、関東甲信越は20―30%、北陸・東海では30―50%、近畿は40―70%、中国・四国は60―90%程度。都道府県別で最も少ないのは群馬、山梨の24%となった。(平成19年1月24日日本経済新聞) 暖冬影響? インフルエンザ流行に遅れ 暖冬の影響なのだろうか? インフルエンザの全国的流行の始まりが今冬、例年に比べて遅いことが国立感染症研究所のまとめで分かった。例年は12月の中〜下旬に患者の報告数が急増するが、今シーズンは1月中旬に入っても少ないままだ。ただし油断は禁物。同研究所感染症研究官は「患者報告数は増加傾向にある。流行は近づいている」と指摘する。予防のため、手洗いやうがいの励行を心掛けたい。インフルエンザは、国内で毎年1000万人前後がかかるとされる。38度以上の高熱や頭痛のほか、倦怠感、関節痛、筋肉痛などの全身症状が突然現れるのが特徴だ。現時点では、全国的流行の指標となる1・0人に達していない。だが、時期の遅れは必ずしも流行規模の縮小に直結しない。平成16〜17年のシーズンは、17年1月17日からの1週間が1カ所当たり2・81人で初めて1・0人を超え、流行期間が長く、最終的な推定患者数は約1770万人と過去10年で最大の流行となった。(平成19年1月25日産経新聞 DHA、脳内の神経細胞再生促進の働き 青魚に多く含まれる物質「ドコサヘキサエン酸」(DHA)に、脳内の神経細胞の再生を促進する働きがあることを、島根大医学部の研究グループが、ラット実験で確認した。認知症やアルツハイマー病などの治療に応用が期待される。生後20週の壮齢ラットに7週間、DHAを経口投与した。短期の記憶をつかさどる「海馬」の神経細胞を調べたところ、情報伝達網の広がりを示す突起状の軸索が、DHAを与えていないラットは増えなかったのに対し、与えたラットは約60%増えた。また、神経細胞へ分化する材料となる神経幹細胞をラットの脳から直接抽出してDHAを加えると、DHAを加えなかったものより、神経細胞へ分化する度合いが約1.5倍に促進されることも分かった。(平成絵19年1月12日 毎日新聞) 幹細胞で脳梗塞の新治療 札幌医大の研究グループは本人の骨髄の幹細胞を使って脳神経細胞の再生を促す国内初の脳梗塞の治療を発症後約2カ月の50代の女性に実施した。受精卵を壊してつくる胚性幹細胞(ES細胞)と比べ、倫理的に問題も少なく、拒絶反応が起きない利点がある一方、改善効果の詳しいメカニズムなど解明されていない点もある。国内の脳梗塞の発症者は年間約30万人に達していると言われており、今回の治療で期待した効果が得られるか今後の経過が注目される。治療を受けたのは昨年11月に脳梗塞を発症した北海道の女性。女性の骨盤から12月下旬に骨髄液を採取し、幹細胞を抽出した。この幹細胞を約2週間かけて培養し、細菌やウイルスに感染していないか検査した上で、12日午前に腕に点滴で投与した。拒絶反応は見られないという。脳に達した幹細胞から放出されたタンパク質の一種「サイトカイン」が血管や神経の再生を促す。回復が見られるのは数カ月後という。脳梗塞の症状を完全に治すことはできないが、生き残った神経細胞の保護や血管の再生を促すことで脳機能の促進が期待される。(平成絵19年1月12日 産経新聞) 紅茶で心臓病の予防 紅茶には心臓病を防ぐ効果があるとされているが、その効果もミルクを入れて飲むとなくなることが、ベルリン医科大付属病院(ドイツ)の研究で分かった。 欧州心臓学会の専門誌(電子版)に9日、掲載される。 研究チームは、更年期を過ぎた健康な女性16人を対象に、何も加えない紅茶と、脱脂乳のミルクを10%加えた紅茶とを500ミリ・リットル飲んでもらう実験を行った。 飲む前と2時間後に、腕の動脈を超音波で調べ、血管の弾力性を示す指標「FMD」を計測した。 FMDは、血管内皮の機能を反映し、低い数値は心臓病の兆候につながる。 実験の結果、ミルクなしの紅茶を飲んだ後は約4・3%向上したが、ミルク入りだとほとんど変化がなかった。 ネズミの細胞を使った実験でその原因を分析したところ、ミルクに含まれる様々なたんぱく質の中でも特にカゼインが、紅茶の有効成分と結合してしまうことがわかった。(平成19年1月9日 読売新聞) 入院医療費、定額に 厚生労働省は入院医療を対象に、病気やケガの種類が同じなら検査・投薬の数量や日数にかかわらず医療費を入院1回あたりの定額とする新制度を導入する検討に入った。過剰診療を減らして医療の効率化を促し、欧米より長い入院日数を短縮する狙い。2008年4月の診療報酬改定で導入を目指す。現在の医療費は入院・外来にかかわらず投薬や検査など診療行為ごとに決めた報酬単価を積み上げて算定する「出来高払い」が原則。 診療行為をすればするほど医療機関が受け取る報酬が増えるため、必要性の低い検査をするなど過剰診療になりやすい面がある。(平成19年1月9日 日本経済新聞) 脳梗塞、起こしやすい遺伝子 日本人に多い脳梗塞発症に関係する遺伝子が、九州大学大学院医学研究院と東京大学医科学研究所の共同研究で分かった。DNA塩基の個人差で、動脈硬化と密接に関係するたんぱく質ができ、発症率に2.8倍の違いが出た。九大が1961年から福岡県久山町で行っている生活習慣病の疫学調査で集めた健常者と、九大病院などの脳梗塞患者(それぞれ1126人)の遺伝子を比較。DNA上の塩基配列の個人差(一塩基多型=SNP)を調べたところ、「PRKCH」と呼ばれる遺伝子のSNPが脳梗塞と関係していることが分かった。このSNPにはアデニン(A)と、グアニン(G)という塩基があり、人にはAA、GA、GGの3タイプがある。脳梗塞患者は健常者に比べ、Aを持つ人が1.7倍多かった。また、88年に久山町で行った健診受診者約1600人を追跡調査。健診後、脳梗塞を発症した人の遺伝子を調べた結果、AAのタイプの人は、GGの人より脳梗塞発症率が2.8倍高かった。脳梗塞などの生活習慣病は、複数の関連遺伝子と、生活・環境因子の影響で発症するため、Aの塩基を持っているからといって脳梗塞を起こすわけではないが、発症にかかわる遺伝子を解明することで、治療薬の開発や発症予防につながるという。九大などの研究グループは、高血圧や糖尿病など他の生活習慣病のほか、かいよう性大腸炎についても関連遺伝子の研究を進める方針。 九大大学院医学研究院の清原裕教授は「脳梗塞の関連遺伝子は他にもある。発症メカニズムを明らかにして治療法や予防法を確立したい」と話している。(平成19年1月8日 毎日新聞) 羊水から万能幹細胞 体のさまざまな細胞に分化する能力を持つ胚(はい)性幹細胞(ES細胞)に似た幹細胞を、人間の子宮の羊水から取り出すことに成功したと米ウェークフォーレスト大の研究チームが米科学誌ネイチャーバイオテクノロジー(電子版)に7日、発表した。 ES細胞は、病気などで機能を失った組織を人工的につくって移植する再生医療への応用が期待されているが、受精卵を壊さないと得られないという倫理的な問題が研究推進の障害になっている。 だが、今回見つかった羊水由来の幹細胞は通常の医療行為から得られるので、倫理的な問題は少ないという。(平成19年1月8日 中国新聞) アルツハイマー病DNAワクチン 東京都神経科学総合研究所は、アルツハイマー病の治療にDNAワクチンが効果がある仕組みを解明した。 ワクチンの作用でできた抗体に、原因とされるたんぱく質がくっつき、それを脳内の細胞が除去していたという。効果の高いワクチン開発に生かせるとみている。脳にたまってアルツハイマー病を起こすとされるたんぱく質、アミロイドベータのDNAに改良を加え、DNAワクチンにした。このワクチンを注射すると生体内でアミロイドベータができ、同時に免疫システムによってアミロイドベータにくっつく抗体も作られる。(平成19年1月9日 日経産業新聞) 皮下脂肪から肝臓細胞を作製 国立がんセンター研究所と国立国際医療センターの研究チームが、人体の皮下脂肪から、肝臓細胞を作製することに成功した。肝炎や肝硬変など国内に350万人以上いる肝臓病患者の肝臓を修復する再生医療の実現に近づく成果として注目されそうだ。 チームは「数年以内に臨床応用を検討したい」という。同研究所は、皮下脂肪に含まれている「間葉系幹細胞」という細胞に着目した。さまざまな臓器や組織の細胞に変化する可能性を秘めており、皮下脂肪の細胞の約10%を占める。研究チームは、国際医療センターで腹部の手術を受けた患者7人から皮下脂肪を5グラムずつ採取、この幹細胞を分離し、成長を促す3種類のたんぱく質を加えて約40日間培養したところ、ほぼすべてが肝細胞に変化した。得られた肝細胞の性質を調べてみると、血液の主成分の一つであるアルブミンをはじめ、薬物代謝酵素など肝臓でしか合成されないたんぱく質が14種類以上検出された。人工的に肝機能不全に陥らせたマウスに、この肝細胞約100万個を注射で移植したところ、上昇していたアンモニア濃度が1日で正常レベルに低下した。皮下脂肪から再生した細胞は、乳房の修復などにも用いられているが、肝臓の持つ複数の機能が確認されたのは世界で初めて。再生医療の研究では、胚(はい)性幹細胞(ES細胞)が有名だが、受精卵を壊して作るため批判を受けやすい。皮下脂肪を使えば倫理的な障害は少なく、患者自身から採取した細胞なので拒絶反応も起きないという利点がある。落谷室長は「皮下脂肪から作製した肝細胞は、機能などの点からみると、合格点ぎりぎりの60点程度。より本物に近い機能を持った肝細胞を作製したい」と話している。(平成19年1月6日 読売新聞) 心臓病治療に「心筋シート」 重い心臓病の治療で、患者自身の筋肉の細胞から「心筋シート」を作り心臓に張って心筋再生を図るという、世界でも例のない臨床研究を、大阪大や東京女子医大のグループが実施する。対象には、補助人工心臓を着けて心臓移植を待っている患者6人を予定。重い副作用がなく人工心臓を外せるようになるなど安全性と効果が確認できれば、より多くの患者に広げるという。大阪大病院未来医療センター長の澤芳樹教授(心臓血管・呼吸器外科学)らが計画。医学部の倫理委員会と、同センターの審査評価委員会の承認をすでに得ている。対象は、拡張型心筋症の70歳以下の患者。同症は心筋が弱って薄く伸び、心臓内の空間が広がって血液がうまく送り出せなくなる。重症になると心臓移植しか治療法はなく、患者は補助人工心臓を着けながらドナーからの提供を待つ。具体的には、まず患者の太ももから5〜10グラムの筋肉を摘出。筋芽細胞という、筋肉が損傷を受けた時に分裂、分化して損傷を補う細胞を探し出す。その細胞を特殊な培養液で24時間培養して増やし、直径3〜4センチ、厚さ50マイクロメートルのシートを10枚ほど作る。これを3枚重ねにして、左心室の表面に張る。 イヌなどの動物を使った実験では、心筋が再生され、心臓のポンプ機能が回復することが確認されている。 筋芽細胞を培養し、そのまま心筋内に注入する臨床研究は、欧米ですでに実施され、大阪大も取り組んでいる。一定の効果も報告されているが、欧米では注入した細胞の一部しか機能しないうえ、重い不整脈などの副作用も指摘されている。澤教授は「シートは、弱った心臓を覆うように張れるので効果も広く期待できる。シートを作る技術も確立している。慎重に研究を進めて結果を分析し、ほかの心臓病にも広げたい」と話す。(平成19年1月2日 朝日新聞) 喫煙で女性の心筋梗塞の危険性8倍 日本人女性が心筋梗塞になる危険要因のトップは喫煙で、たばこを吸う人は吸わない人より8倍も危険性が増すことが、熊本大などの研究グループによる調査で明らかになった。男性でもたばこを吸う人の方が危険性が4倍高く喫煙は高血圧に次ぐ要因だった。 02年に急性心筋梗塞を初めて発症した全国の患者1925人(平均67.7歳、男性1353人、女性572人)と、年齢と性別の割合を患者に合わせた健康な2279人のデータを解析。高血圧や喫煙などの危険要因が、それぞれ単独でどのくらい大きいかを調べた。男性では、高血圧の人はそうではない人と比べて4.80倍発症し、続いて喫煙が4.00倍、糖尿病が2.90倍。女性では喫煙が8.22倍で、糖尿病が6.12倍、高血圧が5.04倍だった。喫煙リスクが女性の方が男性より高い理由について、河野宏明・同大助教授は「はっきりしないが、体質的なものに加え、女性の方が体が小さく影響が大きいのかもしれない」という。欧米では、喫煙と、高コレステロール血症などの脂質代謝異常が2大危険要因とされる。今回の研究では、高コレステロール血症は、日本人男性で1.52倍と他の要因に比べて低く、女性では1.10倍だが統計上の明確な差は出なかった。(平成19年1月1日 朝日新聞) |