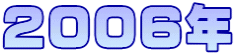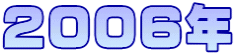|
75歳以上の外来医療、「定額制」を導入へ
厚生労働省は75歳以上のお年寄りの外来診療について、医師の治療を1カ月に何回受けても医療機関に支払われる診療報酬を一定にする「定額制」を導入する方針を固めた。寝たきりの在宅患者への往診など、高齢者向け医療の一部ではすでに定額制が導入されている。厚労省はこれを外来医療へと拡大して医療費の抑制を図る考えだ。高齢者に対して、必要度の高くない医療が過剰に行われているとされる現状を改善する狙いだが、患者の受診機会の制限につながる可能性や、医療機関がコストを下げようと必要な医療まで行わなくなる危険もあり、今後、適用する疾病の範囲や条件を慎重に検討する。06年の医療改革で、75歳以上を対象にした新しい保険制度を08年に創設することが決まっている。厚労省は来年3月までに、ここに盛り込む独自の診療報酬体系の基本方針を出す予定で、外来診療の定額制導入はその柱となる。患者は、高血圧や心臓病、関節障害など、特定の慢性疾患の医療機関をあらかじめ選ぶ。そこで一定回数以上受診すると、それ以上は何回受診して投薬や検査を受けても医療機関が健保組合から受け取る報酬は定額とする方法などが検討される見込みだ。現在の診療報酬は、個別の診察や検査、投薬について細かく料金が設定され、それを積み上げて治療費が決まる「出来高払い」が基本。患者に多くの治療を行うほど医療機関の収入が上がる仕組みで、高齢者の外来医療では「過剰な診療で、医療費の増加や病院・診療所のサロン化を招いている」との指摘もある。75歳以上の医療費(04年度)は9兆214億円で、医療費全体の28%を占める。患部を温める簡単な治療を受けるため患者が1カ月に20回以上診療所に通うなどのケースもある。厚労省は、医療の質を保ちつつ定額制を導入することは可能とみるが、患者は選んだ医療機関に一定期間は通い続けることが求められ、いつでもどの医療機関でも受診できる自由が一部制限される。受けられる治療の回数が減ったりすることも考えられ、反発が予想される。また、同じ病気について患者が同時期に複数の医療機関を受診すれば、逆に医療費がふくらむ恐れもあり、重複受診を防ぐ仕組みも必要となりそうだ。(平成18年12月29日 朝日新聞)
後期高齢者の初期診療、登録主治医に制限を
2008年度から75歳以上の「後期高齢者」に適用する新しい診療報酬制度に関する提言を発表した。高齢者全員が地域の診療所から主治医(かかりつけ医)を選び、初期診療は登録した主治医だけが担う内容。主治医が受け取る診療報酬はその診療所を登録した高齢者の人数に応じた定額払い方式とすることを求めた。現行の医療制度では患者は医療機関を自由に選ぶことができるため、軽度の患者まで大病院に集中し、病院が入院医療など本来の役割に集中できない問題が生じている。提言では後期高齢者の初期診療を診療所に限定し、患者が事前に選んだ主治医が病状に応じて専門医がいる病院に患者を紹介する仕組みとする。(平成18年12月25日 日本経済新聞)
骨髄採取、痛み軽減
関西医科大のグループが、「灌流法」と呼ばれる新しい骨髄採取法の国内初の臨床試験に成功した。採取される人の負担が軽く痛みも軽減される。骨髄採取時の負担の重さは骨髄移植普及を阻む壁の一つになっており、画期的な方法として注目される。従来の骨髄採取は、直径約1.5ミリの針を患者の腰骨の約100カ所に刺し、計0.5〜1リットルの骨髄液を吸い出す。健康な骨髄提供者でも、痛み止めの投与を受けながら3、4日の入院が必要だった。灌流法は2本の針を同時に刺し、片方から生理食塩水を注入、他方からあふれ出る骨髄液を採取する。効率よく採取でき、吸引しないのが特長。免疫機能を担う末しょう血内のリンパ球の混入が少なく、他人に移植して白血球の型が合わなくても、リンパ球が患者の体を攻撃しない利点もある。(平成18年12月25日 毎日新聞)
細菌性髄膜炎、日本もワクチン承認へ
重症率が高い乳幼児の病気、細菌性髄膜炎の主原因であるインフルエンザ菌b型(Hib)ワクチン(商品名アクトヒブ)を承認する方針を固めた。Hibワクチンは世界100カ国以上で承認されており、先進国で未承認なのは日本だけだった。厚労省などによると、細菌性髄膜炎の約6割はHibが原因。国内では年間、5歳未満の乳幼児1万人に1人程度がHibによる細菌性髄膜炎にかかると推定される。このうち5%が死亡し、25%に聴覚障害、てんかんなどの後遺症が残るという。初期診断や治療が難しいため、予防効果が高いワクチンが80年代後半から欧米を中心に承認され始めた。98年には世界保健機関(WHO)が乳児への定期接種を推奨する声明を出し、現在は、90カ国以上で公費負担などによる定期予防接種が実施されている。米国では予防接種の導入後、罹患率が100分の1にまで減ったという報告もある。重い副作用は実質的にない。 日本では罹患率が欧米の数分の一とされ、ワクチンの必要性がなかなか広まらなかった。(平成18年12月24日 朝日新聞)
白血球に血管再生促す働き 千葉大の研究で確認
腕から採血して集めた白血球の一種に、血管や心筋の再生を促す働きがあることが、千葉大の研究でわかった。 血管が詰まる病気で、脚の切断を迫られた患者の治療に使ったところ、症状が改善し切断を免れた人が少なくなく、心機能が回復した例もあった。新たな再生医療の方法につながる成果だ。再生医療では、骨髄の幹細胞が「血管を作ったり心筋細胞に分化したりする」と期待され、臨床研究が進められている。だが、最近、骨髄幹細胞には分化能力がないか、あっても治療に使えるほど効率的ではない、などと報告され、期待ほどの成果が出ていない。今回使った白血球の仲間は、単核球と呼ばれ、細菌などが体内に入った際にやっつける役割を担っている。この単核球を集め、筋肉に注入すると骨格筋細胞が増え、それが血管新生を促す物質を出して血管ができていくことを基礎実験で突き止めた。そこで、脚の血管が詰まる閉塞性動脈硬化症や炎症などで同様の症状を起こすバージャー病の患者約50人に対し、腕の静脈から3時間かけ採血。取り出した単核球を1時間かけ脚に注入した。数週間後、痛みが和らいだり潰瘍が小さくなったりするなど7割の人で症状が改善し、26人が足首やひざから下を切断せずにすんだ。さらに13人は心臓の血流もよくなり、血液を送り出すポンプ機能の回復も確認できた。骨髄の幹細胞を採取しないですめば、患者に大きな負担をかける全身麻酔を使わないで、治療が可能になる。(平成18年12月23日朝日新聞)
視力1.0未満、小学生の3割
視力が「1・0未満」の子供が、小学校で3割近く、中学校では2人に1人に上ることがわかった。子供の視力低下は20年以上続いており、「テレビゲームやパソコンの影響ではないか」とみている。 調査は、今年4〜6月に健康診断を受けた全国の幼稚園児と小中学生、高校生から、計約336万人分を抽出して集計した。 それによると、視力が「1・0未満」の小学生の割合は、昨年度比0・7ポイント増の27・2%。視力が調査項目に加わった1979年度以降で最も高くなった。79年度は17・9%だった。「0・3未満」の小学生も6・1%と、やはり過去最高。79年度の2・7%の2倍以上の割合になった。同じ傾向は中学生でも見られ、「1・0未満」は昨年度比2・3ポイント増の50・1%で、「0・3未満」は同0・7ポイント増の20・4%。 79年度は、「1・0未満」が35・2%、「0・3未満」が13・1%だった。文科省では、小型ゲーム機や携帯電話の普及も視力低下の要因になったとみている。幼稚園児の「1・0未満」は24・0%、高校生は58・7%だった。一方、ぜんそくの子供は、幼稚園で2・4%(昨年度比0・8ポイント増)、小学校で3・8%(同0・5ポイント増)、中学で3・0%(同0・3ポイント増)で、いずれも過去最高を更新。また、今年度から新たに調査項目に加わったアトピー性皮膚炎の子供は、幼稚園で3・8%、小学校で3・6%、中学で2・8%、高校で2・2%だった。(平成18年12月22日 読売新聞)
毛髪再生、マウスで実験に成功
東京大学発のベンチャー企業は、マウスの毛根から採取した細胞を毛の生えていない別のマウスの皮膚に移植し、毛を生やさせる実験に成功した。まだ基礎的な段階だが、将来は人の毛髪を再生できるようになる可能性があるという。移植したのは毛乳頭細胞。毛髪の付け根の皮膚組織の中にあり、発毛を促す成分を分泌している。黒い毛のマウスから毛乳頭細胞を採取し、無毛のマウスであるヌードマウスの皮膚組織の中に特殊な注射器で移植したところ、四週間後には注射した部分から約8割の率で毛が生えてきた。(平成18年12月22日 日本経済新聞)
肥満、腸内細菌で決まる?
動物の腸の中にすむ細菌が太りやすさに関係していることを米ワシントン大のチームが突き止めた。人間など哺乳類の腸内には、1000種類以上の細菌がすみ、消化吸収の補助などに役立っている。ほとんどの細菌が、バクテロイデス(B)類かファーミキューテス(F)類のいずれかのグループに属している。研究チームが、太ったマウスとやせたマウスの腸内細菌について、B類とF類の割合を比べたところ、太ったマウスは、B類が50%以上も少なかった。人の場合も、太った人ほどB類が少なかった。カロリー制限で体重を減らすとB類が増え、F類が減った。さらに、無菌状態で育てたマウスに、肥満マウスと、やせたマウスの腸内細菌を与えて影響を比べた。2週間後の体脂肪増加率は、肥満マウスの腸内細菌を与えた場合は約47%だったが、やせたマウスの腸内細菌を与えた場合は約27%にとどまった。研究チームは、B類が減ってF類が増えると、食事からのカロリー回収率が高まり、体重増につながると推測。腸内細菌の状態を変えることで、肥満を治療できる可能性があると考えている。(平成18年12月21日 読売新聞)
便秘と大腸がんは無関係
便秘と大腸がんは関係ありません。便に含まれる有害物質が腸に長くとどまるため、古くからあった「便秘がちな人は大腸がんになりやすい」という俗説が、厚生労働省研究班の疫学調査で否定された。調査は全国6地域に住む40〜69歳の男女約6万人を対象に93年から実施。開始時に便通の頻度などを聞き、平均8年間、追跡調査して大腸がんを発症したか調べた。その結果、便通が「週2〜3回」しかない便秘の人たちは、「毎日1回」「毎日2回以上」する人たちと比べても、大腸がんを発症する危険度は変わらなかった。また、普段の便の状態との関連では、「下痢」の人は、大腸がんの一つである直腸がんのリスクが高い傾向が出たが、対象人数の少なさなどが影響した可能性もあり、今後も検討が必要という。(平成18年12月20日 朝日新聞)
胃がん手術後の抗がん剤「有効」
進行胃がんで胃を切除した患者は、手術後にTS―1(ティーエスワン)という経口抗がん剤を服用した方が、手術単独に比べて死亡の危険性が3割低くなることが、千人以上を対象とした国内の臨床試験で明らかになった。胃がん手術後の抗がん剤治療の有効性が大規模な試験で証明されたのは初めて。今後、この方法が進行胃がんの標準治療になるのは確実だ。試験の対象は、がんの進み具合を表すステージ(1が最も早期、4が最も進んだ段階)が2と3の進行がん患者で、胃を手術で切除した1000人余。このうち約半数の患者には手術後に何もせず、残りの半数にはTS―1を1年間服用してもらった。その結果、抗がん剤治療を受けた群は、手術後3年の生存率は80・5%で、手術単独群の70・1%を10ポイント上回った。死亡の危険性は手術だけの群より32%低かった。副作用は食欲不振が最も多く(6%)、重いものは少なかった。(平成18年12月15日 読売新聞)
抗うつ剤、服用24歳以下で自殺行動
米食品医薬品局(FDA)は12日、日本でも販売されている「パキシル」などの抗うつ剤すべてで、服用すると自殺のリスクが高まるとの添付警告の対象を、現行の「小児と思春期の患者」から24歳以下に拡大するよう精神薬の諮問委員会に提案した。FDAがパキシルやプロザック、ゾロフトなど11種の抗うつ剤に関する372件の治験データ(計約10万人分)を調べたところ、18〜24歳の患者で偽薬を服用した場合に比べ、自殺や自殺未遂、自殺願望を持った事例が有意に多かったという。(平成18年12月14日 毎日新聞)
カロリー制限による減量、骨密度が減少
カロリー制限をして体重を落とすと骨密度が減少するのに対して、運動で体重が減っても骨密度に変化がないことが、米ワシントン大学の研究グループの調査で分かった。ダイエットなど食事制限で減量すると骨粗しょう症になりやすいとしている。女性30人と男性18人(平均年齢57歳)を「カロリー制限をした食事をするグループ」「カロリー制限せず運動をするグループ」の2集団に分けて調査した。カロリー制限したグループは1年後に体重が平均8.2キログラム減少し、骨密度も同2.2%減っていた。運動をしたグループでは体重が6.7キログラム減ったものの骨密度に変化はなかった。(平成18年12月13日 日経産業新聞)
高齢で3センチ以上身長縮むと危険、心臓病など死亡率増
20年間で身長が3センチ以上縮んだ高齢者は、それ未満だった人に比べ、心臓病などで死亡する恐れが高いことが英国ロンドン大学などの研究でわかった。身長の縮みと死亡率との具体的な因果関係は明らかにされていないが、研究チームは「身長の低下は、骨密度に関係する。生活習慣などで骨が弱くなり、それが病気につながった可能性はある」としている。研究チームが調査対象としたのは、1978〜80年に、身長や生活習慣、疾病の有無などをチェックした40〜59歳の男性4213人。年齢が60〜79歳になった20年後にも同様の項目を調べた上で、その健康状態をさらに2005年まで追跡した。04年までに確認された死者計760人について、「3センチ以上」「1センチ以下」といった具合に身長の縮み具合でグループ分けして、それぞれの死亡率を分析したところ、3センチ以上縮んだ人は、1センチ以下だった人に比べ、がん以外の心疾患、呼吸器疾患などで亡くなる割合が64%も高かったという。なお、一般に加齢とともに身長は縮むとされているが、20年間にわたる今回の調査でも、平均1・67センチ縮んだことが確認された。(平成18年12月12日 読売新聞)
医療、薬剤噴霧で癒着防止
手術後に患部と皮膚や臓器がくっついてしまう癒着を防ぐ新技術を東京大病院などの研究グループが開発した。傷口や臓器に2種類の薬剤を噴霧するだけでよく、ウサギを使った実験では、癒着の発生量を7割以上減らすことに成功した。癒着が起きると、腸閉塞や慢性的な痛みが生じることがある。東大病院の倫理委員会に臨床試験を申請する準備を進めており、数年後には実用化したいという。研究グループは、傷口にゼリー状の膜を作る癒着防止剤、術部以外の臓器などには保水作用のある糖類のトレハロースをそれぞれ噴霧する新手法を考案した。(平成18年12月11日 毎日新聞)
更年期障害ホルモン療法 乳がんリスク6割減
女性の更年期障害の治療に「ホルモン補充療法(HRT)」を実施しても乳がんになるリスクは上がらず、逆に6割ほど下がることが、厚労省の調査でわかった。HRTは、米国の臨床試験で「乳がんのリスクを高める」とされて以来、国内でも敬遠されがちだったが、研究班は「更年期障害に悩む日本人にとっては、利益の方が大きい」としている。大阪府立成人病センターなど全国7施設で、過去10年以内に乳がんの手術を受けた45〜69歳の女性(3434人)と、がん検診を受けに来た人で、乳がんでなかった同年代の女性(2427人)の2グループに対し、HRTの経験など21項目をアンケートした。その結果、乳がん患者グループではHRT経験者が5%で、もう一方のグループは11%。統計上、HRT経験者の方が、乳がんになるリスクは57%低かった。女性ホルモンのエストロゲンを単独で使った場合と、エストロゲンと黄体ホルモンを併用した場合ではリスク差はなく、HRT経験者の半数近くは、期間は1年未満だった。経口薬などで女性ホルモンを摂取するHRTは、欧米では一般的な治療法。だが、米国国立衛生研究所が91年から15年計画で始めた大規模臨床試験で、乳がんや脳卒中などのリスクが高まることが指摘され、02年に試験も中止された。 日本国内では更年期障害の治療は普及しておらず、HRTに関する大規模な調査もなかった。米国での試験中止以降は副作用を恐れる人も多く、現在、HRTを受けている人は数%とされる。日本人の乳がんリスクが低かった原因について佐伯教授は、米国人と異なり乳がん発症のピークが閉経前の45〜49歳にあること、HRTを何年も続ける米国人に比べて、使用期間が短いことなどを挙げている。 「欧米のように閉経後の乳がんが増えれば、状況は変わるかもしれない。HRTを受けたから乳がんにならないというわけではなく、同時に検診を受けることが必要だ」と話している。(平成18年12月10日 朝日新聞)
アルツハイマーMRI診断
アルツハイマー病の原因タンパク質である「ベータアミロイド」に結合し、磁気共鳴画像装置(MRI)による診断をしやすくなる試薬を滋賀医大と滋賀県工業技術総合センターが開発した。コンピューター断層撮影(CT)や陽電子放射断層撮影(PET)と違い、放射線被ばくがなく、治療効果の判定や症状の観察にも使えるという。同様に開発された試薬の5倍以上の感度があるといい、「Shiga−X」と名付けた。アルツハイマー病は脳にベータアミロイドが蓄積し老人斑と呼ばれるシミができ、細胞死が起きる。MRIで撮影しやすくするようフッ素を加え、アルツハイマー病のモデルマウスの静脈に注射すると、2、3時間でアミロイドに結合、MRIで観察すると白く光る様子が確認できた。(平成18年12月5日 中国新聞)
外出しないと歩行障害4倍
ほとんど家を出ない高齢者は毎日外出する人たちに比べ、歩行が不自由になるリスクが4倍。認知機能が落ちるリスクが3.5倍もあることが、東京都老人総合研究所などの調査でわかった。もともとの健康状態とはかかわりなく、外出しないこと自体が危険性を高める。同研究所と新潟県与板町内65歳以上の約1500人の健康状態と、MMSEというテストで認知機能を調べ、健康状態を分析した。1キロの距離を歩けないか、階段を上れない場合を「歩行障害あり」として、そうした状態になるリスクを「1日に一回は外出する」人たちと比較した。年齢や健康状態が同じになるように調整したうえで比べると、「2〜3日に一回」の人は1.8倍、「週一回かそれ以下」の人では4倍という結果だった。認知機能が一定以上下がるリスクも、「2〜3日に一回」で1.6倍、「週一回かそれ以下」は3.5倍になった。調査の結果、歩行障害を抱えても、外出する機会が多ければ、回復する可能性が高い。 社会活動に参加するなど、外に出る習慣をぜひ保ってほしい。(平成18年12月2日 朝日新聞)
大酒飲みは「自殺要注意」
「大酒」は自殺リスクを高めるらしいことが、名古屋市立大の大規模疫学調査で分かった。酒量を調べた中高年男性のその後を追跡調査したところ、「1日3合以上飲む人」の自殺率は「時々飲む人」の2.3倍に上った。厚生労働省研究班として90〜93年に飲酒状況を聞いた全国の40〜65歳の男性約4万5000人を、その後約8年半にわたって調べたところ、168人が自殺。全体では毎年約2200人に1人が自殺したことになる。酒量に応じ、全く飲まない人から1日3合以上飲む人まで6グループに分けて比べると、酒量が増えると自殺率が上がり、酒量が最も多く自殺率も最も高い1日3合以上のグループでは、毎年約1600人に1人の割合で自殺していた。全く飲まない人の自殺率も1日3合以上グループとほぼ同じだったが、自殺の危険性を高める重病を持ち、酒を飲めなかった人が含まれていたことが考えられるという。飲酒と自殺については、ソ連時代のロシアとベラルーシで、85〜89年の禁酒政策時代に自殺がそれぞれ約3割減ったと報告されるなど、以前から関連が疑われていた。国内でも都道府県の住民1人当たり飲酒量と自殺率の間に強い相関関係がみられる。国立病院機構・久里浜アルコール症センターは「依存症の人は自殺率が高いという調査はあったが、飲酒と自殺の関係を大人数の追跡調査で実証した意義は大きい。自殺への歯止めが利かなくなるほか、飲酒がうつを引き起こしたり悪化させたりすることも考えられ、今後解明が必要だ」と指摘する。(平成18年11月28日 朝日新聞)
寝酒でかえって不眠誘発
寝酒をすると夜中に目が覚める可能性が高くなる。眠ろうと思って酒を飲むことは、かえって不眠を誘発する可能性が示唆される。20歳以上の男女計約2万5000人分の睡眠やストレスに関するデータを解析した。 1週間に1回以上寝酒をする習慣がある人は男性48%、女性18%。寝酒をする人の割合が最も高いのは男性は55−59歳、女性は40−44歳だった。「寝付けない」「夜間に目が覚める」「早朝に目が覚める」といった不眠の症状と、寝酒との関係を多変量解析と呼ばれる方法で調べたところ、「夜間に目が覚める」と寝酒との間に有意な関連があることが分かった。うつ状態と睡眠時間との関連についても調査。睡眠が「7時間以上8時間未満」が最もうつ状態の人の割合が低く、7時間より短くなればなるほど、8時間より長くなればなるほど、うつ状態の人の割合が高かった。(平成18年11月29日 産経新聞)
炭素系新素材が変形性関節症の進行抑制に効果
炭素系新素材「フラーレン」が、変形性関節症の進行を抑える効果がある。従来は痛みなどへの対症療法が中心で、進行を抑える効果が確認できたのは画期的という。フラーレンはサッカーボール状の炭素同素体で、化粧品などにも使用されている。変形性関節症は年齢とともに軟骨組織が衰え、国内には約1000万人の患者がいる。フラーレンをウサギのひざに注入したところ、関節の変形の進行が注入しないケースの半分以下に抑えられたという。(平成18年11月27日 毎日新聞)
免疫効果高めるエイズワクチン
経口投与を繰り返すと、着実にエイズに対する免疫力が高まる新しいエイズワクチンの開発に、順天堂大や近畿大などの共同研究グループがマウスを使った実験で成功した。よく効くエイズワクチンの開発は世界的な課題で、将来の臨床応用が期待される。このワクチンは、天然痘の予防接種に使われていた安全な種痘ウイルスに、エイズウイルスの遺伝子の一部を組み込んだもの。投与するとエイズウイルスのたんぱく質が作られ、それをもとにエイズウイルスへの免疫ができる。エイズウイルスは増殖時に変異しやすいため、それに対抗できる免疫を複数回の投与でつけることが望ましいが、これまでの研究では、1〜2回投与すると種痘ウイルスに対する免疫ができてしまい、エイズウイルスに対するワクチン機能が低下する欠点があった。順天堂大医学部は、種痘ウイルスを生体物質の薄い膜で包んだ。すると、種痘ウイルスに対する免疫ができにくくなり、その結果、投与回数を増やすことでエイズウイルスに対する免疫力を高めることに成功した。(平成18年11月26日 読売新聞)
健康食品の「副作用」検証
市場の拡大とともに健康被害の報告が増えている健康食品について、厚生労働省は被害事例を検証する検討会を年内にも設ける方針を固めた。医師や薬剤師ら15人ほどの専門家を委員とし、被害実態の把握や摂取との因果関係の分析を進める。ケースに応じて商品名なども迅速に公表し、被害の拡大を防ぐという。薬には副作用を検証する仕組みがあるが、健康食品では初めて。健康食品は、滋養強壮や美容、ダイエット、がん予防など多種多様な目的で売られ、年間の市場規模は1兆2000億円とも1兆5000億円ともいわれる。厚労省が一定の効能を認めた「特定保健用食品(トクホ)」、ビタミンやミネラルなどを一定量含む「栄養機能食品」などの表示が認められているものもあるが、それら以外は安全を担保する基準はない。厚労省によると、被害報告は毎年、全国の保健所から50件前後寄せられ、肝障害や発疹ができるアレルギー、下痢などを訴える内容が多い。しかし、もともと病気の人が摂取しているケースも多く、症状が食品によるものかどうか、判断が難しいという。これまで厚労省は被害報告があるたび、専門家を探して意見を聞いてきた。今後は、肝臓や腎臓、皮膚科、産婦人科などの専門医と、漢方薬の原料となる生薬に詳しい薬剤師らを委員とする検討会を設けておき、被害内容に応じて委員を招集。分析の結果、因果関係が認められれば、ホームページで直ちに商品名などを公表する。疑わしい場合は、動物実験や文献調査などもしてさらに詳しく調べるという。(平成18年11月25日 朝日新聞)
たばこも酒も習慣、食道がんリスク10倍
喫煙するのに加えてほぼ毎日飲酒する男性は、どちらの習慣もない人たちと比べて食道がんになるリスクが9〜11倍あることが、宮城県の約2万7000人を対象にした調査でわかった。たばこの関与が特に大きく、患者の約7割は喫煙しなければ、がんにかかるのを避けられた計算になるという。84年に約9000人、90年に約1万8000人のいずれも40歳以上の男性に食生活などを尋ね、それぞれ9年間と7年7カ月間追跡したところ78人が食道がんになっていた。そこで喫煙や飲酒、緑茶を飲む習慣が食道がんのリスクとどうかかわるかを調べた。たばこを吸う人のリスクは吸わない人と比べて5倍、ほぼ毎日飲酒する人のリスクはほとんど飲まない人と比べて2.7倍あった。緑茶を1日5杯以上飲む人は飲まない人と比べて1.7倍リスクがあった。理由ははっきりしないが、研究チームは「緑茶を熱い状態で飲む人が多かったのかも知れない」と推測する。熱い飲食物は、食道がんの危険を高めるとされている。こうした個別の解析とは別に、「たばこを吸わず、お酒も緑茶もほとんど飲まない」人たちのリスクを1として計算すると、喫煙と飲酒の習慣がある人ではリスクが9.2、さらに1日3杯以上の緑茶を飲む習慣も加わると11.1になった 食道がんと診断されるのは年に1万5000人ほどとされ8割以上を男性が占める。今回の調査をまとめた栗山進一・東北大助教授は「食道がんは生活習慣で予防できる代表的ながん。禁煙が何より大事で、酒を飲みながらのたばこは最悪です」としている。(平成18年11月1日 朝日新聞)
卵と心筋梗塞
卵を食べる頻度と心筋梗塞にかかる割合は特に関係がないとの結果が、厚生労働省研究班の9万人規模の追跡調査で出た。コレステロールが高い人は、心筋梗塞予防の一環として卵の摂取を避けるよう指導されることが多いが、研究班は「心筋梗塞予防のために卵を制限する根拠は得られなかった」と結論づけた。調査は全国の40〜69歳の男女に卵を食べる頻度を尋ね、計9万735人から回答を得た。そのうち約3万3000人は血中の総コレステロールの値も調べた。卵を食べる日が「週に1日未満」と答えた人が心筋梗塞を起こした率は、「ほぼ毎日食べる」人の約1.2倍で統計的には同等の範囲だった。総コレステロールの値が「220」以上と高い人の割合は、「ほとんど毎日食べる」が27.5%で、「週1日未満」は33.5%とやや多かった。 (平成18年11月28日 毎日新聞)
がん死の原因、男性たばこ4割
がんで死亡した男性の約4割、女性の5%が、たばこが原因と考えられるとする推計を厚生労働省の研究班がまとめた。年間約8万人がたばこでがん死したことになる。対象は調査開始時40〜79歳の男性13万9974人、女性15万6796人の計29万6770人。調査開始時の喫煙経験率(たばこを吸っている人と過去に吸っていたがやめた人の割合)は男性79.5%、女性10.5%。平均9.6年追跡した結果、がんで死亡したのは男性6503人(うち喫煙経験者5668人)、女性3474人(同499人)。年齢を調整して解析した結果、喫煙経験がある人は、ない人に比べ、男性で1.79倍、女性で1.57倍、死亡率が高かった。食事や運動など喫煙以外のリスクが同じと仮定すると、がんで死亡した男性の38.6%、女性の 5.2%がたばこが原因となった。人口動態統計にあてはめると、年間に男性約7万4000人、女性約7000人がたばこが原因でがん死した計算になる。男性では、吸ったことがない人に比べ、調査開始時に喫煙していた人の死亡率は1.97倍、過去に吸っていたがやめた人は1.5倍で、禁煙の効果もうかがえた。(平成18年11月15日朝日新聞)
脊髄再生、ラットで成功
かびから取り出された物質をラットに投与し、切断された脊髄を再生させることに、慶応大と大日本住友製薬の共同チームが成功した。交通事故などによる脊髄損傷患者は国内に10万人以上おり、治療薬につながる可能性があるという。中枢神経の脊髄が損傷すると、損傷部分より下部の脚などがまひし動かなくなる。脊髄の神経線維は一度切れると伸びないためで、「セマフォリン3A」というたんぱく質が再生を妨げる物質の一つと考えられている。同製薬は十数万種類の化合物を調べ、地中のかびの一種から、このたんぱく質の働きを抑える物質を見つけた。01年から慶応大と共同で研究を開始。ラットの脊髄を背中で切断し、後ろ脚をまひさせた状態にして、切断部位にチューブでこの化合物を1カ月注入した。注入ラット20匹は約3カ月後に、神経組織の1割程度が再生して部分的につながり、後ろ脚のひざなどすべての関節が動くようになった。注入しなかったラット20匹は後ろ脚がまったく動かないままだった。この物質による副作用はラットでは見られず、再生を妨げるたんぱく質も人間に共通している。慶応大の岡野栄之教授は「サルなど大型の動物で安全性や有効性を確認したい。症状が慢性化している患者の場合、神経幹細胞移植と組み合わせることなどが必要かもしれない」と話している。(平成18年11月13日 毎日新聞)
"男性"骨粗鬆症が増加の一途
最近、増加の一途を辿っている男性骨粗鬆症の実態が第8回日本骨粗鬆症学会で報告された。「骨粗鬆症は女性の病気」と捉えられ、男性骨粗鬆症はあまり注目されてこなかった。しかし、男性骨粗鬆症の予後は女性よりも悪いと言われ、年間2万5000人程度の新規罹患者が発生している。骨粗鬆症の疫学調査としては、代表的な骨粗鬆症性骨折である大腿骨頚部骨折に関して、1987年から5年ごとに4回にわたって全国調査が行われている。2002年に行われた厚生労働科学研究班の調査によると、大腿骨頚部骨折発生数は11万8000人と、過去3回の調査結果よりも新規発生患者が増えていることが示された。各年代別の危険度をみると、男性は女性に比べて約半数で、特に高齢者ではその差が明らかだった。また、患者数を見ても女性の方が圧倒的に多く、いずれの調査でも男性は女性の約3分の1以下と考えられている。しかし02年の調査では、年間2万5300人の男性が新たに大腿部頚部骨折を起こしていた。これは15年前に比べて約2倍の増加に当たる。そうした疫学調査結果をもとに、最も頻度が高い脊椎椎体骨折について40〜79歳の各年代50人ずつ計400人を選んでレントゲン撮影を行った。日本骨代謝学会の診断基準を判定法として脊椎椎体骨折の有病率を性別、年齢別にみたところ、40〜49歳で男性4%、女性2%、50〜59歳で男性15%、女性10%、60〜69歳で男性22%、女性14%と、60歳代までは男性の方が女性よりも高かった。一方、70〜79歳では男性18%、女性45%と、高齢女性になると脊椎椎体骨折の有病率が急上昇し、さらに複雑骨折の割合が増加することが分かった。この集団を追跡して10年目に調査に参加した299人に関して、新規骨折の累積発症率を年代別にみたところ、男性では40歳代2.9%、50歳代10.3%、60歳代13.2%、70歳代30%との結果で、女性では40歳代2.1%、50歳代6.5%、60歳代23.1%、70歳代42.3%と、60〜70歳代の女性で明らかに累積発生率が高くなっていた。このことから、脊椎椎体骨折についても、男性の発生率は女性より少ないものの、決して楽観できる成績ではないとした。(平成18年11月7日 薬事日報)
メタボリック症候群と血圧
メタボリックシンドロームであっても、生活習慣で血圧が正常に保たれていれば動脈硬化のリスクは上がらない。そんな傾向が東京大病院循環器内科の調査で浮かんだ。同シンドロームは生活習慣病の危険を高め、心臓病や脳卒中を招く動脈硬化につながるとして注目されるが、同シンドロームの有無だけにとらわれず、生活の中で個々の危険因子に注意する必要性が示される結果だ。都内の病院で約8000人の血圧や血中脂質の値などを分析したほか、首の動脈に軽度の動脈硬化が起きていないかどうか、超音波装置で調べた。このうち、血圧がやや高めだが正常範囲である「上140未満、下90未満」の約6000人を対象に、同シンドロームの有無と動脈硬化のリスクの関係を調べてみた。 女性の場合、同シンドロームがある人の動脈硬化のリスクは、ない人に比べて2.7倍高かった。だが、女性のうち、同じ血圧でも降圧剤に頼っていない人の動脈硬化のリスクは、同シンドロームがあってもなくても、変わらなかった。血圧が同じでも、薬を飲んでいる人のリスクが高くなっているらしい。薬に頼らないと正常な血圧を保てないこと自体がリスクを高めている可能性が考えられるという。男性はいずれの場合もリスクに違いはなかった。(平成18年11月3日 朝日新聞)
神経細胞、伸ばすたんぱく質発見 まひ患者などに朗報か
長いもので1メートル以上もある神経細胞が伸びていくのに必要なたんぱく質を、九州大生体防御医学研究所が突き止めた。神経移植が成功すれば、事故で神経が切れた半身まひ患者などの治療に役立つが、動物実験では移植しても神経はなかなか伸びない。このたんぱく質の働きを活発にできれば、解決につながる可能性があるという。神経細胞は普通の細胞と違い、核のある細胞体から、ひも状の神経突起が長く伸びている。足を踏まれて痛いのは、踏まれた刺激が神経突起を通して脳に伝わるためだ。神経突起が出来る際には、細胞膜に含まれる脂質が細胞内でいったん集まり、一方向に運ばれる。そこで中山教授らは神経細胞に特有で、細胞膜内の物質輸送に関係するとみられるたんぱく質の一種に着目した。これを子宮の細胞に加えて実験すると、細胞は神経のように突起を伸ばした。さらに、神経細胞を操作しこのたんぱく質をほとんど作らせなくすると、本来は一方向に伸びてひも状になるはずの細胞膜が、すべての方向に伸びてしまい、細胞が全体として広がった。 中山教授らはこのたんぱく質が突起形成に重要だと結論付け、「突起が伸びる」という意味の英語から「プロトルーディン」と命名した。中山教授は「遺伝的に両足が動かなくなる病気の患者には、プロトルーディンを作る遺伝子が変異している場合がある。正常なプロトルーディンを補えば治療につながるかもしれない」と話している。(平成18年11月4日 毎日新聞)
タミフルと異常言動の関連性はなし
抗インフルエンザウイルス薬オセルタミビル(商品名タミフル)の服用者が異常言動で死亡した例などが報告されているが、「小児のタミフル服用と異常言動の関連性は認められなかった」という研究結果が厚生労働省の研究班の調査で分かった。異常言動は、インフルエンザの合併症として多く発生する脳症の前にも出るとされるが、タミフルの服用が影響しているのか注目されていた。調査は昨年度、全国12都県の小児科医を通して行い、2846件(99.5%が0歳から15歳まで)の回答を得た。発熱後7日間の服薬状況や肺炎や中耳炎の併発、けいれんや意識障害、幻覚やうわごとなどの異常言動があったか答えてもらった。調査対象の患者の9割がタミフルを服用していた。服用した患者の異常言動発生率は11.9%。一方、服用しなかった患者の異常言動の発生率は10.6%だった。統計学的に意味がある差ではなかったという。医師への調査とは別に、患者の親らにも調査票を配って調べたところ、2545件の回答があった。こちらもタミフル服用による異常言動の発生率の上昇はみられなかった。厚労省によると、01年の販売開始から今年6月末までに、タミフル服用後に異常言動などで死亡した16歳以下の患者は15人。医薬品による副作用被害に救済金を支給する国の制度に申請した例もあるが、これまでのところ、副作用と認められたケースはない。タミフルは、鳥インフルエンザが変異して起きるとされる新型インフルエンザの治療薬としても期待され、国や自治体が備蓄を進めている。(平成18年10月29日 朝日新聞)
若年者の虚血性心疾患リスクが明らかに
肥満と運動不足が危険因子、夏季に多いのも特徴
若年者の虚血性心疾患は増加傾向にあるとされるが、中高年に比べると、肥満と運動不足が発症の重大な危険因子であり、狭心症より心筋梗塞の割合が高いことが分かった。第54回日本心臓病学会学術集会で、信州大保健学科内科学教授の本郷実氏が発表した。調査対象は、1992年から2002年の間に長野県で虚血性心疾患を発症した40歳以下の若年患者101人と50歳以上の中高年患者94人。それぞれの冠動脈病変、代謝危険因子4項目、生活習慣危険因子3項目などを、カルテと独自に作成した調査票に基づき比較検討した。その結果、中高年の虚血性心疾患患者ではBMI
25以上が37%だったのに対し、若年者では57%、喫煙者の割合も中高年の64%に比べ、若年者では80%と、それぞれ若年者の方が有意に高かった。また、若年者では運動習慣が発症リスクを減らすことも分かった。一方、中高年では60%が高血圧を合併していたものの、若年者は31%で有意に低かった。「今回の調査の詳細を調べてみると、若年者では肥満でも小児期からのものが多く、喫煙者は発症後も禁煙できないケースが多いことが分かった」。また調査では、両群の虚血性心疾患の発症時期も調べており、若年者では中高年に比べ、夏季の発症が有意に多いことが分かった。この点に関し本郷氏は「発汗による脱水と喫煙習慣が、凝固能を亢進させて虚血性心疾患のリスクを高めているのではないか」と考察。「予防のためには、リスク因子を排除することが早急に必要」と警鐘を鳴らした。同氏は、「今後は若者や保護者に向けた、早期からの生活習慣病の予防教育が重要だ」とし、現在、生活習慣を反映した検査や測定項目を長野県下の中学生の学校健診に導入し、保護者への指導にも乗り出している(平成18年10月30日 Nikkei Medical
)
ボケ防止には野菜をたくさん
野菜を多く食べている高齢者ほど「認知力」が衰えにくいことが米シカゴのラッシュ大の研究グループの調査でわかった。とくにホウレンソウやキャベツ類などの葉野菜を多く食べている場合に顕著だった。年をとると記憶力が衰えたり、思い出すのに時間がかかったりするようになる。グループは65歳以上の約3700人を対象に、こうした「認知力」の衰えぶりと、野菜や果物を食べる回数などとの関係を調べた。1日に食べる野菜、果物の種類や回数を答えてもらったうえで認知力を調べる試験を実施。3年後と6年後にも同様の試験をして比較した。その結果、野菜を多く食べる人たち(1日2.8回程度)は、最も少ない人たち(同0.9回)より、認知力低下の度合いが40%も低かった。年齢にして、5歳分、若返ったことになるという。ただ果物にはこうした効果はみられなかった。グループのマーサ・モリス博士は「果物より野菜に多く含まれるビタミンEが関係しているのかもしれない」としている。(平成18年10月28日 朝日新聞)
トゥレット症 20%が不登校
トゥレット症候群になった子どもの20%が不登校を経験していたことが、本人や家族で作るNPO法人「日本トゥレット協会」の会員への調査で分かった。この症候群は、まばたきや顔しかめ、首振りなどの「運動チック」と、せき払いや鼻すすり、叫び声などの「音声チック」が、ともに1年以上続く疾患。回答した会員106人のうち、20%が発症後に「学校に通っていない」または「通ったり通わなかったりを繰り返した」。 理由は「症状が重く、肉体的に通えないか勉強についていけなくなった」(85%)、「学校で症状をからかわれた」(65%)が多かった。当事者が困っている症状は、チックなどの症状が54%で、「ADHD(注意欠陥・多動性障害)」「睡眠障害」など併発する病気による症状も46%と多かった。初診時に適切な診断・治療が受けられずに病院を替えた人は66%にのぼり、医師から「くせ」と言われた人も5%いた。同協会は「学校や医療現場で、この病気への理解を深めてほしい」としている。(平成18年10月27日 読売新聞)
納豆効果
生活習慣病の発症にかかわるコレステロールや中性脂肪の値の高い人が、納豆を1か月間、毎日食べることで、それぞれの数値が改善したことが国立循環器病センター(大阪府吹田市)、ヒュービットジェノミクス社などの共同研究でわかった。納豆が生活習慣病予防に有効であることが改めて示された。研究チームは今年1月、血液検査の数値が高めのメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の境界領域にいる佐賀県有田町の住民52人(平均年齢65歳)を対象に、1パック(30グラム)の納豆を毎日の朝食時に4週間食べてもらい、試験の前後で数値を測定した。コレステロール値が高い(220以上)、中性脂肪値が高い(150以上)場合、それぞれ数値が7・7%、12・9%改善した。 もともと正常な人では、ほとんど変化はなかった。また、52人中、便秘症状があるとした25人(男性5人)に、摂取後の便通について聞いたところ、80%に当たる20人が、症状が改善したと回答。 男性は全員、便通が良くなった。納豆摂取による副作用はなかった。(平成18年10月27日 読売新聞)
睡眠、7〜9時間が適切
睡眠時間が7〜9時間より長いか短い子どもは、精神状態が悪いという傾向のあることが、日本大医学部の板佳孝講師(公衆衛生学)らによる10万人規模の調査で分かった。兼板講師は「7〜9時間が適切な睡眠時間だと示すデータ」と説明している。富山市で開かれている日本公衆衛生学会総会で26日発表する。厚生労働省の研究班(主任研究者、林謙治・国立保健医療科学院次長)が04年12月〜05年1月に、中学校131校、高校109校を全国から無作為抽出し、在校生に過去1カ月の睡眠状況や精神的健康度に関して質問。 回収した9万9668人分のデータを解析した。精神的健康度は、行動の際に「いつもより集中できましたか」など12問に対する回答を点数化して測定。4点以上(12点満点)で不健康とした。解析によると、精神的に不健康だったのは全体の44%。不健康な子どもの割合は、睡眠時間が8〜9時間で33.2%と最も低く、7〜8時間で33.7%、6〜7時間で42.2%、5〜6時間で50.9%、5時間未満で58.3%と、短くなるほど高くなった。逆に、9時間以上は40.8%で、7〜9時間よりも不健康の割合が増した。また、寝付きの悪さと健康度には大きな関連があり、「常に悪い」と答えた子どもの74.7%が不健康で、逆に「全くない」と答えた子どもでは31.5%だった。兼板講師は「この研究では分からないが、睡眠が短くて精神状態が悪くなるのと、精神状態が悪くて睡眠が短くなるのと、どちらも考えられる」と話している。(平成18年10月26日 毎日新聞)
肺がん、CT検査による早期発見が「有効」
米コーネル大学を中心に東京医科大学などが参加する国際チームは、コンピューター断層撮影装置(CT)検査で肺がんを早期に発見・手術すると延命効果が高いことを大規模な患者調査で初めて確認した。検査と治療を受けた患者が10年後も生きている確率(生存率)は9割以上で、国際チームはCT検査が肺がん治療に有効なことを裏付けたとみている。成果は米医学誌ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに26日発表する。(平成18年10月26日 日本経済新聞)
治る早期乳がん、発見増加 X線検診の普及で
「超早期乳がん」と呼ばれる「非浸潤性乳管がん(DCIS)」と診断されて手術を受ける人が増え、乳がんの総手術件数に占める割合がこの4年間で5割増えたことが、主な医療施設へのアンケートで明らかになった。 乳房X線撮影(マンモグラフィー)検診の広がりで早期発見が可能になったことなどが背景にある。日本の乳がん死亡率は上がっているが、DCISの段階で治療すればほぼ完治する。診断率がさらに上がれば死亡率減少につながるとして、専門医は検診の重要性を訴えている。アンケートは、聖路加国際病院(東京都中央区)など、先進的に乳がん治療に取り組む全国の約20施設でつくる「乳癌(にゅうがん)カンファレンス」が02年から実施している。これらの施設で行われた乳がん手術は02年が2429件、05年は3656件。うちDCISが占める割合は8.7%(212件)から13%(476件)に増えた。この調査と一緒に、NPO法人が国内50施設を対象に実施したアンケートでも05年に10%を超えていた。乳がんには「非浸潤性」と「浸潤性」がある。DCISは進行度でいうと「ステージ0」で治療すればほぼ100%治る。 ただ、がんが乳管の中にとどまっていてしこりがないため触診ではわからない。放っておくと周囲の組織にがんが広がり浸潤性に進行する場合もある。DCISの手術が増えたのは、検診制度が04年度に見直されマンモグラフィーが普及したほか、針でがん組織を吸引して調べる「マンモトーム生検」が同年度に保険適用され、見つけやすくなったためとみられている。
乳がん患者の死亡率は欧米で下がりつつあるが、日本では上昇している。 検診の受診率が低く、DCISの発見率が低いためという指摘もある。調査を担当した同院の中村清吾・乳腺外科部長は「米国でのDCISの手術割合は20%近い。マンモグラフィー検診の普及とともに、医療施設の正確な診断と治療が必要だ」と話している。(平成18年10月25日
朝日新聞)
フィセチン、大量含有のイチゴで記憶力向上!
野菜や果物に広く含まれるフラボノイドの一種「フィセチン」を摂取すると、記憶力が向上することを、武蔵野大(西東京市)と米ソーク研究所の共同チームが動物実験で確認し、16日付の米科学アカデミー紀要電子版に発表した。フィセチンはイチゴに多く含まれているが、「人への効果はこれから調べる」としている。記憶をつかさどるのは、大脳の奥にある「海馬」だ。海馬に入ってきた情報は「長期増強」という仕組みで記憶として定着する。武蔵野大薬学研究所の赤石樹泰助手と阿部和穂教授は、認知症に効果のある物質を探す過程で、フラボノイドの一種フィセチンに注目した。フラボノイドは強い抗酸化作用があり、老化防止への効果が知られるポリフェノールの代表的な物質。ラットの海馬を取り出して生きた状態に保ち、フィセチンの水溶液を細胞にかけると、長期増強を担う分子が活性化した。次に生きたマウスを使って実験した。2個の物体を健康なマウスに記憶させ、24時間後、2個のうち1個を別のものにすり替えて再び見せる。前日、物体を見せる前にフィセチンの水溶液を飲ませたマウスは、すり替えた物体にだけ興味を示した。しかし、この水溶液を飲まなかったマウスは、どちらの物体にも均一に興味を示し、前日に見たことを忘れていた。(平成18年10月18日 毎日新聞)
肺がん発生率 "家族に発症歴"で倍に
家族に肺がんになった人がいると、そうでない場合に比べ約2倍の人が肺がんにかかっていることが、厚生労働省研究班(主任研究者=津金昌一郎・国立がんセンター予防研究部長)の大規模調査でわかった。家族に共通する体質や生活習慣が影響しているとみられる。調査対象は、全国の40〜69歳の男女約10万人。両親や兄弟姉妹に肺がん歴があるかを聞いたうえで、2003年までの11年間、肺がんの発生状況を追跡調査した。それによると、肺がん歴がある家族を持つ人は全体の2%で、11年間に791人(男性584人、女性207人)が肺がんを発症。家族に肺がん歴があるグループは、ないグループに比べて約2倍の人が肺がんになっていた。性別では男性が1・7倍、女性が2・7倍で、女性にこの傾向が強かった。本人の喫煙や職場での受動喫煙などの影響はあらかじめ除かれているため、研究班は、家族に共通する体質や何らかの生活習慣が肺がんの危険性を高めたとみている。(平成18年10月11日 読売新聞)
寝過ぎの高校生は持久力が劣る
1日8時間以上睡眠をとる高校生は、6時間未満の人より持久力で劣る傾向がある。文部科学省が公表した2005年度の体力・運動能力調査で、こんな結果が出た。持久力と生活習慣との関係では、朝食抜きやテレビの見過ぎも影響するらしい。6〜17歳については持久力をみるため、20メートル区間を徐々にペースを速めながら走って折り返せた回数と、睡眠時間などとの相関関係を分析した。その結果、睡眠時間が「8時間以上」と答えた高校生(15〜17歳)は男女とも、「6時間未満」の高校生より回数が少なかった。その差は15歳男子と16歳女子で約13回だった。一方、小学生(6〜11歳)は男女とも「8時間以上」の方が好成績で、中学生(12〜14歳)もほぼ同じ傾向だった。朝食については男女とも、「毎日食べない」と答えた方が「毎日食べる」より回数が少なかった。ただし、その差は7歳男子で約3回、12歳男子で約11回なのに対し、15歳男子では20回強と年齢が上がるにつれて開きが大きくなっていた。テレビゲームを含めたテレビの視聴時間との関係でも同様で、17歳男子では「3時間以上」と答えた方が「1時間未満」より約14回少なかった。調査・分析に携わった順天堂大の内藤久士・助教授は「寝過ぎやテレビの見過ぎが直接の要因というよりも、そうした子供たちには規則正しい生活習慣が確立されていないからではないか」と分析している。このほか、青少年層全体(6〜19歳)では、走る・跳ぶ・投げるの基礎的な運動能力と握力で、85年前後から続く低下傾向は今回も変わらなかった。 一方、20〜64歳の成年層は、敏捷(びんしょう)性をみる反復横跳びが緩やかに向上、全身持久力をみる急歩は低下した。(平成18年10月10日 朝日新聞)
早食いの子、肥満度が高い
食べ物を早食いする子供は、ゆっくり食べる子供に比べて肥満度が高いことが、東京歯科大とライオン歯科衛生研究所の共同研究で明らかになった。研究グループは5年前、早食いするサラリーマンほど肥満度が高いとする調査結果を公表していたが、小学生でも同様の傾向があることが浮き彫りになった。調査は食生活が激変しているとされる沖縄県八重山地区の小学5年生256人(男子137人、女子119人)を対象に、食生活など生活習慣を尋ねるとともに、身長と体重を測定。子供の肥満度の指標であるローレル指数(標準は116〜144)を使って、双方の関係を調べた。その結果、他人よりも食べるのが「はやい」と答えた子供の肥満度は平均141で、標準でも太り気味に近かった。一方、「ゆっくり」と答えた子供は平均125だった。また、一口で食べる量が「多い」と答えた子供の肥満度は平均139で、「少ない」と答えた子供の平均129よりも高かった。 反対に、「おやつの回数」や「夜食の有無」「運動する頻度」といった、一般には肥満との関連が指摘されている生活習慣は、今回の調査では、関連性がみられなかった。同大千葉病院の石井拓男病院長(社会歯科学)は「ゆっくりとよくかんで食べるといった、正しい食習慣を早くから身につけさせることが必要だ」と話している。(平成18年10月7日 読売新聞)
幹細胞で脳梗塞治療
札幌医大の研究グループは、患者本人の骨髄の幹細胞を使って脳神経細胞の再生を促す国内初の脳梗塞の治療を実施する。この治療は受精卵を壊してつくる胚性幹細胞(ES細胞)と比べ倫理的に問題も少なく、拒絶反応が起きない利点がある。一方、改善効果の詳しい仕組みなど解明されていない点もある再生医療だけに臨床結果が注目される。治療は脳梗塞の患者の骨盤から骨髄液を採取し、幹細胞を抽出。この幹細胞を数週間かけて培養し、腕に点滴で戻す。脳に達した幹細胞から放出されたタンパク質の一種「サイトカイン」が血管や神経の再生を促すという。脳梗塞を発症して2週間後のラットに、幹細胞を移植した結果、運動機能が回復。移植しないラットに比べ約2、3割速く走った。実験では脳梗塞発症直後のラットほど効果があったという。採取した幹細胞を培養して増殖する過程で細菌やウイルスに感染する危険性もあるが、研究グループは「培養した幹細胞を体内に戻す前に検査を十分行うので安全性は確保できる」と話している。(平成18年10月10日 日本経済新聞)
肝炎治療もオーダーメード
感染者が300万人に上るといわれるB型、C型肝炎対策として、厚生労働省は来年度から、患者一人ひとりの遺伝子などを分析し、それに基づいた治療法を探る「オーダーメード治療」に取り組む。同じ症状なのに治療薬が効く人と効かない人がいたり、強い副作用が出たりする仕組みを解明し、新薬の開発などにもつなげるのが狙いだ。ウイルス感染が原因のB型、C型肝炎の治療では、インターフェロンなどの薬でウイルスを駆除したり、治療薬で肝がんの発症を抑えたりするのが主流。しかし、効果は個人差があり、現在の治療で完治できるのはC型で約6割、B型で約4割といわれる。発熱や貧血などの副作用もあり、薬が使えないケースも出ている。このため、同省は来年度から3年計画で、「オーダーメード治療」に着手。 肝炎治療に熱心な医療機関の協力を得て患者の血液を採取し、遺伝子情報などを収集する。さらに、ウイルスのタイプも解析し、09年度をめどに、病状などの臨床情報と合わせて少なくとも数百人規模の統一的なデータベースをつくる。 遺伝子のどの部分が治療薬の効果や副作用などに影響を与えているかなどを調べる。その原因が分かれば、新薬開発の研究にも役立つという。オーダーメード治療は、患者の遺伝子情報から、体質や病状などに応じた医薬品や処方を選ぶ手法。治療効果が高まるほか、無駄な医薬品の使用が減るため、副作用だけでなく医療費の削減効果もあるという。がん治療などの分野が先行している。
肝炎は「国民病」ともいわれ、同省の推定では、発症していない感染者はC型で150万〜190万人、B型で110万〜140万人。加えて、肝がんや肝硬変などの患者はC型で約52万4000人、B型で約9万7000人(いずれも02年10月時点)。潜伏期間が数十年に及ぶケースもあり、感染を知らない人が多いことが問題になっている。
国立感染症研究所の脇田隆字・ウイルス第二部長は「ウイルスのデータ収集や研究は行われていたが、患者側のデータの蓄積はなかった。患者の遺伝子とウイルスの情報、副作用や病状変化などの臨床情報を積み上げて活用できれば、きめ細かい治療ができるようになる」と期待している。(平成18年10月5日 朝日新聞)
多発性硬化症、血液検査で再発予測
国立精神・神経センターの研究グループは、免疫に関係する病気「多発性硬化症」の再発を血液検査で予測する技術を開発した。「症状はないが、再発が心配で旅行に行けない」といった患者も多かったが、新技術で患者の生活環境の改善につながりそうだ。多発性硬化症は脳や脊髄に炎症が起きる病気で、国内の患者数は1万人以上といわれる。若い人や女性に多い。症状が安定してから再発するまでの期間は1カ月―数年とばらつきがあり、予測する方法がなかった。研究グループは患者の血液中にある免疫細胞「NK細胞」の「CD11c」というたんぱく質を調べた。症状の安定した23人の患者のうち、たんぱく質の測定値が低い患者は4カ月以内の再発率が15%だったが、値が高い10人では60%が再発し、予測に応用できることが分かった。研究グループではCD11c以外の分子を利用する方法も開発中で、予測率の向上をめざす。(平成18年10月4日 日本経済新聞)
内視鏡で1ミリの食道がんも発見
昭和大学横浜市北部病院の井上晴洋助教授らは、早期発見が難しいとされる食道がんを直径1ミリの初期段階で見つけることができる手法を開発した。病巣部を拡大して見る内視鏡を使い、がんになると特徴的に表れる毛細血管の形状変化を観察、がんかどうか判別する。食道がんは進行してから見つかることが多いが、早期発見できれば治るケースが大幅に増える。食道がんは食道の内面を覆う粘膜の表面にある上皮から発生する。 上皮には先端部がループ状になった毛細血管がいくつもある。井上助教授は食道がんの病変部を詳しく観察し、がんが発生すると同時に、毛細血管の形状が微妙に変化することを突き止めた。がんの進行度に応じて、血管が特徴ある形を示すことも分かった。(平成18年10月3日 日本経済新聞)
抗肥満物質、食欲抑制のたんぱく質発見
群馬大大学院の森昌朋教授らの研究グループは、摂食やエネルギー代謝を制御する脳の視床下部に直接働きかけて食欲を抑制するたんぱく質「ネスファチン1」を発見した。動物実験で既に、皮下脂肪型と内臓脂肪型の両方の肥満の解消効果を実証しており、「メタボリック・シンドローム解消の切り札として、できるだけ早く臨床での使用を目指す。正常体重の人の場合、脂肪細胞が分泌するたんぱく質「レプチン」の食欲抑制作用から肥満になりにくい。だが、肥満状態の人には、レプチンが作用しないことは以前から知られていた。森教授らは、脂肪細胞だけでなく、脳細胞で分泌する九つのたんぱく質から、レプチンと同様に視床下部に作用して食欲を抑制させる別のたんぱく質があることを発見し、「ネスファチン1」と名付けた。レプチンの作用しない肥満状態のネズミの脳髄液中にネスファチン1を注射して実験したところ、投与しないネズミと比べ、1日の摂食量は約30%減少、11日後の皮下脂肪は約20%、内臓脂肪は約30%減少させることが確認された。 今後、臨床使用までに、毒性実験など人体への副作用の有無を解明するなど課題は残っている。森教授は「同様の作用をするたんぱく質はこれまでにも数種類発見されているが、レプチンと同等の食欲抑制作用を有するものは、ネスファチン1だけ」と話している。(平成18年10月2日
毎日新聞)
大腸ポリープ、和食で発生率が2〜3割減少
肉をなるべく魚に替え植物油の摂取量を減らし、旧来の和食を食べるよう指導を受けた人は、そうでない人に比べ、大腸ポリープの発生率が2〜3割程度減ることが、名古屋市立大の徳留信寛教授らの研究で分かった。 食事改善の効果が出るには2年程度かかり、徳留教授は「継続した取り組みが大切」と訴えている。横浜市で開催中の日本癌学会で28日に発表した。徳留教授らは96年から04年までに、同大で大腸ポリープを切除された50代から70代までの男女計206人を、くじで二つに分けた。片方の104人には、肉はなるべく魚に替える、てんぷらなどの揚げ物を避けるなどの指導を3カ月おきに繰り返した。残りの102人には食事の脂肪を減らすよう一般的な指導をした。最初の指導から2年後に検査すると、一般的指導のグループでは検査を受けた74人中27人(36%)にポリープが再発していたが、魚を多く食べるなどの指導を受けたグループでは91人中26人(29%)にとどまった。検査を受けなかった人も含めて推計すると、魚食などでポリープが2〜3割減らせたとの結論が出た。ポリープを調べると、一般的指導の方が、悪性度が高くがんに近いポリープの割合が高かった。ただ、1年後の検査ではポリープの率に差がなかった。大腸がんの多くはポリープからできるため、徳留教授は「適度な運動と食事改善で、大腸がんを半減できるのではないか」と話している。(平成18年9月29日 毎日新聞)
前立腺がん細胞にザクロが劇的効果
果物のザクロに、前立腺がんの細胞を死滅させる成分が含まれていることが、名古屋市立大の朝元誠人助教授らの研究で分かった。朝元助教授らは、人間の初期の前立腺がん細胞を培養し、濃度5%のザクロ果汁の溶液に入れて影響を調べた。すると、わずか30分で激しい反応を起こし、がん細胞が死滅した。前立腺がんにこれほど強く作用する天然物質は例がないという。他のがん細胞には効果がなかった。また、前立腺がんのラットに、5%濃度のザクロジュースを飲ませたところ、がん縮小効果がみられた。ザクロの何の成分が効いているかは不明。朝元助教授は「普通の食品に、こんな作用があるのは珍しい。成分が分かれば、前立腺がんの予防や治療への応用が期待できる」と話している。(平成18年9月29日 読売新聞)
神経まひ性角膜障害、点眼で回復
神経まひ性の角膜障害に対し、神経伝達物質などから作った成分の点眼によって、治癒を促進させることに、山口大眼科の西田輝夫教授のグループが世界で初めて成功した。神経まひ性角膜障害は、三叉神経痛の手術後やヘルペス感染、コンタクトレンズ障害、糖尿病による神経障害などのせいで、角膜に潰瘍や欠損が生じる。従来の治療は、抗菌薬の点眼などをしながら角膜の自然治癒を待つにとどまり、重症の場合は視力を失うこともある。西田教授らは、サブスタンスPと呼ばれる神経伝達物質と、インスリンに似た物質のインスリン様成長因子(IGF―1)の創傷治癒効果に着目し、それぞれ四つのアミノ酸からなるペプチドを特定。動物に投与して効果を確認した後、人での臨床研究を行った。1日4回点眼し、角膜上皮欠損の20人中19人で治癒した。治療日数は最短3〜89日で、平均11日だった。脳腫瘍や聴神経腫瘍の手術後に起きる角膜障害の場合は、再発することが多いため、西田教授は「再発予防のため長期の点眼継続も検討する必要がある」と話している。(平成18年9月29日 読売新聞)
30代の女性は乳がん・子宮がんの発症が2倍に急増
日本人女性は20代後半から乳がんや子宮がんの発症が急増し、30代のがん罹患率は同世代の男性の2倍以上とした分析結果を、厚生労働省研究班がまとめた。10代後半から30代のがんは、比較的治療成績が良いため死亡データなどから把握しにくく、詳しい罹患傾向が分かっていなかった。育児や働き盛りの世代の実態が明らかになったことで、社会的損失を減らすためのきめの細かいがん対策が可能になるのではと指摘された。研究班は、大阪府など15府県が1993年から2001年まで、地域がん登録で集めた約137万人の患者データを解析した。1年間に新たにがんと診断される人は、年齢が上がるとともに増加。男性では30代前半は人口10万人当たり27人、同後半は50人だったのに対し、女性は30代前半に67人、同後半が115人となっていた。これに伴い30代では、女性の罹患率は男性の2・3−2・5倍だった。乳がんや子宮がんが20代後半から急増しているためで、30代では女性がかかるすべてのがんのうち乳がんと子宮がんが約60%を占めていた。45歳以降は、たばこや食生活などと関連が深い胃がんや肺がんが増加傾向となり、がん全体の罹患率は男性が上回った。(平成18年9月29日 中国新聞)
母乳・ヨーグルト含有たんぱく質、大腸ポリープを抑制
母乳やヨーグルトなどに含まれるたんぱく質「ラクトフェリン」に、大きくなるとがん化する可能性がある大腸ポリープを縮小させる効果があることが、国立がんセンターがん予防・検診研究センターの調査で分かった。ラクトフェリンは、人間の母乳、特に初乳に多く含まれる。牛乳などにも含まれるが、量が少なく熱に弱い欠点がある。今回の研究では、牛乳から分離、精製したラクトフェリンの錠剤を使用。同センター中央病院で、すぐには内視鏡切除の必要がない直径5ミリ以下の腺腫が見つかった104人に協力を求め、1日3グラム、あるいは1・5グラムを摂取する群と、ラクトフェリンを含まない偽薬を摂取する群の計3群に分けて、1年後に腺腫の変化を比較した。その結果、偽薬の群では直径が平均6%増大したのに対し、1・5グラム摂取群では2・1%の増大にとどまり、3グラム摂取群では4・9%の縮小が認められた。また、3グラム摂取群では、血中のラクトフェリン濃度が高く保たれ、免疫細胞の一種であるNK細胞が活性化することも分かった。 腺腫を縮小させる食品成分が見つかったのは初めて。ラクトフェリンの摂取で、腺腫の増大が抑制できるのであれば、大腸がんの予防効果も期待できると期待。(平成18年9月26日 読売新聞)
がん「最初にたんぱく質損傷」発症メカニズムで新説
がんは遺伝子の変異が積み重なって起きるとされるが、それ以前に、たんぱく質が損傷することで、細胞が「がん」特有の性質を持つとする新たな説を、渡辺正己・京都大学原子炉実験所教授らがまとめた。がん細胞は死なずに無限に増殖する。がんの原因を遺伝子の変異と考えた場合、変異の頻度と、細胞が"不死化"する頻度は比例するはずだ。しかし両者は一致しない場合が多い。渡辺教授らも以前、ハムスターの細胞に放射線を当てたが、不死化する頻度は、遺伝子変異の頻度より500〜1000倍も高かった。渡辺教授らは、遺伝子以外の、放射線で傷ついた部分に謎を解くかぎがあると考え、放射線照射後の細胞を詳しく調べた。その結果、染色体を安定させる役割を担うたんぱく質や、細胞分裂で染色体の動きを誘導するたんぱく質に多くの異常が見つかった。染色体数も増えており、不死化する頻度は遺伝子変異の頻度の1000倍以上だった。たんぱく質を傷つけるのは、放射線など様々な要因で細胞内にできる有害物質「ラジカル」とされる。渡辺教授らは、寿命の長いタイプのラジカルを培養細胞から化学的に除去。すると細胞が不死化する頻度が減り、関連が示唆された。渡辺教授は「がんの大半は、染色体にかかわるたんぱく質が傷つき、染色体が異常化して細胞分裂が正常に行えない細胞から生まれると考えた方が矛盾がない」と話している。(平成18年9月26日 読売新聞)
糖尿病にかかると、がんリスク3割増
糖尿病にかかっていると、がんを発症する危険が2〜3割高まるとする結果を、厚生労働省の研究班が約10万人を対象に調べた研究からまとめた。90年から94年にかけて、40〜69歳の男性約4万7000人、女性約5万1000人にアンケートし、糖尿病の有無や生活習慣などを聞いた。その後の経過を03年まで追跡すると、男性で3907人、女性2555人が何らかのがんにかかっていた。糖尿病になっていた人ががんを発症するリスクを糖尿病でない人と比べると、がん全体では男性で27%、女性でも21%上回っていた。 男性では、糖尿病の人はそうでない人と比べて肝臓がんで2.24倍、腎臓がんで1.92倍、膵臓(すいぞう)がんで1.85倍とリスクが高まっていた。 女性では肝臓がんで1.94倍、胃がんで1.61倍だった。
一般的な糖尿病では、病気が進む過程でインスリンが過剰分泌状態になる。この状態だと、細胞の増殖が刺激され、がんにつながりやすいことが実験で知られている。ただ、肝臓がんを招く慢性肝炎などを抱えていることが、逆に、糖尿病の危険を高めている可能性も考えられるという。(平成18年9月26日 朝日新聞)
歯垢を分解する糖類、果物やワインに
果物やキノコ、ワインなどに含まれている糖類の一種「エリスリトール」に、虫歯や口臭の原因となる歯垢を分解しやすくする働きがあることを、花王の研究者らが見つけた。歯ブラシやうがいの水流程度でも、歯垢がはがれやすくなるような効果が期待できるという。口の中には虫歯につながる病原菌と、いわゆる善玉の細菌などが混在する。こうした細菌が増えて、食べかすなどをエサにして絡み合い、歯につくと、取れにくい歯垢となる。 唾液の清浄作用が細菌の増殖を抑えることは知られているが、詳しい仕組みは分かっていないという。唾液の働きを研究していた花王ヘルスケア研究所の研究員らは、メロンやナシなどの果物や、しょうゆ、みそ、ワインなどの発酵食品に含まれるエリスリトールが、唾液と同じように細菌同士の結合をゆるくする働きを持つことを見つけた。再現した歯垢にエリスリトール水溶液をかけると、歯ブラシが触れなくても、ブラシが起こす水流を再現した超音波があたるだけで、歯垢がはがれるようになった。エリスリトールを使わずに超音波をあてるのに比べ、歯垢は約3分の1まで減っていた。(平成18年9月23日 朝日新聞)
カルシウム多量に取ると大腸がんリスク3割減
牛乳や小魚に含まれるカルシウムを毎日たくさん取ると、大腸がんになる危険性が約30%低下することが九州大学と国立国際医療センター研究所の大規模な疫学調査で分かった。大腸がんは欧米型の食生活が浸透し国内でも患者が急増、毎年約9万人が発病し、約4万人が死亡する。がんの部位別死亡数で見ると女性でトップ、男性だと第4
位。明確な予防効果が確認された食物はこれまでなかった。調査は2000年から03年にかけ、福岡市と近郊にある8病院に入院中の大腸がん患者840人と同地域で暮らす健康な住民833人を対象に実施した。普段食べている食品の種類と量を聞き取り、カルシウムやそのほかの栄養素の摂取量と大腸がんとの関係を調べた。(平成18年9月23日 日本経済新聞)
食べるワクチン動物で効果 アルツハイマー病
アルツハイマー病の原因物質とされるタンパク質「ベータアミロイド」の遺伝子をピーマンに組み込み、その葉を食べさせることで脳に蓄積したベータアミロイドを約半分に減らすことに、東京大の石浦章一教授らがマウスで成功した。
葉の中にできたベータアミロイドが腸から吸収されることで、体内の抗体が増える仕組み。
ベータアミロイドを直接注射する人間の臨床試験では髄膜炎が出た例があるが、今回のものは経口ワクチンで、副作用は出なかったという。人間で安全性と効果が確かめられれば「食べるワクチン」開発につながる可能性がある。アルツハイマー病は、脳にたまったベータアミロイドが神経細胞を死滅させ、記憶や認知障害などの症状が出ると考えられている。石浦教授によると、ベータアミロイドの精製は難しいため、ピーマンに遺伝子を導入して作らせるようにした。育った葉を細断し、家族性アルツハイマー病のマウス6匹に週1回、3カ月間食べさせたところ、脳のベータアミロイドは、食べさせなかったマウスに比べて平均で約半分に減少。血液中の抗体の量は、食べる前より増えていた。石浦教授は「自然に老化したマウスにも効けば、アルツハイマー病では患者が最も多い原因不明の孤発性にも効果が望める」と話している。(平成18年9月23日 中国新聞)
リウマチ発症に4倍の差 遺伝子のわずかな違い
関節リウマチに関係があると思われていなかった遺伝子が発症に関係し、わずかな構造の違いで発症の確率が4倍以上違うとの研究結果を板倉光夫徳島大教授らがまとめた。構造の違いは、遺伝子の塩基配列が1つだけ異なる一塩基多型(SNP)で、これを調べれば、リウマチになりやすいかどうかを診断できるとしている。 板倉教授らは、関節リウマチに関する遺伝子があると考えられていた14番染色体に注目。リウマチ患者とそうでない人950人ずつの塩基配列を比べ、細胞内の情報伝達に関係することが知られていた「PRKCH」という遺伝子の特定のSNPが最も違いが大きいことを突き止めた。 さらに周辺の3カ所のSNPの組み合わせで、最もリウマチになりやすい場合は最もなりにくい場合の4倍以上発症しやすいことが分かった。板倉教授は「治療薬開発につながるので、この遺伝子の機能解明を目指したい」と話している(平成18年9月22日 中国新聞)
注射嫌いの子も大丈夫、鼻からワクチン
注射が嫌いな子どもには鼻にひと吹き。東京大学医科学研究所の清野宏教授らがインフルエンザなどのワクチンを鼻から簡単に投与できる技術を開発した。液を鼻の中に吹きつけたり垂らしたりするだけで済む。動物実験に成功、5年後の実用化を目指す。一般にワクチンは注射でないと病気の発症を抑える免疫の抗体が十分できないため、他の投与法は難しい。新技術は、抗体ができにくい半面、副作用の心配が少ない利点がある不活化ワクチンというタイプで可能にしたのが特徴だ。(平成18年9月22日 日本経済新聞)
学習は午前中に、記憶妨げる物質の発生が少い
北海道大の伊藤悦朗客員研究員らが貝を使って学習の実験をした結果、記憶形成を妨げるタンパク質は午後よりも午前中の方が少ないことが分かった。伊藤研究員は「このタンパク質は人間にもある。午前中の学習は記憶形成を妨げるタンパク質を減らすのに効果が期待できる」と話している。実験では脳の神経細胞数が人間に比べ数十万分の1と単純で解析しやすいヨーロッパモノアラガイを使用。記憶形成にかかわることが知られるタンパク質が学習でどのように変化するかを調べた。実験は午前と午後に分け、それぞれ約80匹の貝を使用した。好物の砂糖水と苦手な塩化カリウムを15秒間隔で交互に10回繰り返し与えた後に砂糖水を与えた。 その結果、午前中に実験した貝のすべてが次に塩化カリウムが与えられることを学習して何も口にしなくなった。午後に実験した貝で口に入れなくなったのは7、8割だった。(平成18年9月16日 日本経済新聞)
拒食症の小児患者26人死亡
病院の小児科を受診した拒食症(神経性無食欲症)の患者が昨年は944人おり、過去に衰弱や自殺などで26人が死亡している。調査を担当した宮本信也筑波大教授は「かなり多く驚いた。受診者数も多いと言える。 予防のための健康教育が必要だ」としている。拒食症は、重度の体重減少に、体重が増えることへの恐怖などの精神症状が伴い、小学生の患者など低年齢化が進んでいるという。調査は、総合病院など小児科医を育成するための小児科研修病院569施設を対象に実施、294施設が回答した。昨年受診した拒食症患者は、初診が358人、再診が586人の計944人だった。「これまでに拒食症の死亡例の経験がある」と答えたのは24施設で、計26人。死因は衰弱や致命的な不整脈、心不全、自殺などだった。また、低身長や脳の委縮などの後遺症の恐れもある初潮前の女児患者は、過去に386人が確認された。病院側が苦慮している点は、鼻に入れた管や点滴による強制栄養療法を実施するかどうかの判断や、患者が隠れて嘔吐するなどの問題行動であることも分かった。今回の調査では、受診者、死亡者の年齢や性別は調べておらず、学会は発症のきっかけや治療経過、死亡の詳細について2次調査を近く始める。(平成18年9月19日 中国新聞)
便のDNA検査で大腸がん発見、確率8割
大腸などの消化管の壁からはがれ、便に含まれる細胞のDNAを調べることで、がんを効率よく発見する方法を松原長秀岡山大助手らが開発した。松原助手によると、米国の統計では、現在の便潜血反応検査で見つかる大腸がんは最大2割程度。この方法は8割程度になると期待できるという。松原助手らは、大腸など消化器がんの患者らの細胞を調べ、がん細胞では遺伝子に特定の分子がくっつくメチル化という現象が起きていることを突き止めた。大腸がんの場合は、6カ所でメチル化が起きているケースが多かった。(平成18年9月16日 日本経済新聞)
キムチでお通じ効果 脂肪増えずに筋肉増
キムチに排便を促す効果があるという女子大生を対象にした実験結果を、桃屋研究所の吉田睦子研究課長らがまとめた。吉田課長らは2005年9─12月、18─22歳の学生37人の協力を得て、キムチを漬け込むために使うトウガラシやニンニクなどの薬味成分を1日に10グラム、鍋料理や納豆に混ぜて食べてもらった。 2週間後の検査で、24人(65%)は排便の量が平均23%増え、軟らかくなった。23人(62%)は体重が増加。うち21人は、体脂肪は増えずに骨量や筋肉量が増えた。悪玉コレステロール(LDL)は23人(62%)で減少。生活習慣病のリスクがある基準値以上だった8人のうち4人は基準値以下になった。(平成18年9月15日 中国新聞)
メタボリックで胃がんリスク高まる
内臓の周りに脂肪がたまる内臓脂肪症候群(メタボリック・シンドローム)に陥ると、動脈硬化や糖尿病だけでなく、胃がんのリスクも高まることが、東大腫瘍外科の北山丈二講師らの研究でわかった。肥満解消が、がんの予防や再発防止にもつながる可能性を示す成果と言えそう。北山講師らの研究チームは、脂肪細胞から分泌される「アディポネクチン」というホルモンに着目した。脂肪の燃焼を助ける働きなどをするが、内臓脂肪症候群になると、分泌量が減り、血液中の濃度が下がる。チームが突き止めたのは、アディポネクチンに強力な抗がん作用があること。ヒトの胃がん細胞を移植したマウスにこのホルモンを投与すると、腫瘍が最大で9割も減少した。さらに、胃がん患者75人の血液中のアディポネクチン濃度を調べたところ、がんの進行した患者ほど濃度が低かった。このホルモンは、胃がん細胞と結合しやすい構造をしており、結合したがん細胞を殺す働きがあるとみられる。抗がん作用は、血液1ミリ・リットルあたりの量が0・03ミリ・グラムを超えると強まる。内臓脂肪症候群の人の濃度は、その5分の1〜6分の1という。がん増加原因として、脂肪の過剰摂取が挙げられるが、がんを引き起こす仕組みは十分に解明されていない。(平成18年9月19日 読売新聞)
急増の慢性閉塞性肺疾患、ビタミンC不足と喫煙で発症
東京都老人総合研究所と順天堂大学の研究チームは13日、高齢者に多い肺の病気「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」が、ビタミンC不足と喫煙で起こると、発表した。これまでもたばこの吸い過ぎが原因の一つと考えられていたが、ネズミの実験で確認したのは初めて。COPDは初期のころは息苦しさが目立ち、進行すると呼吸困難となって死に至る。最近患者が急増しており、今回の実験結果は予防法の確立に役立ちそうだ。老人研の石神昭人主任研究員と順大医学部の瀬山邦明助教授らのチームの成果で、米国胸部疾患学会雑誌に報告した。ネズミは本来ビタミンCを体内でつくれるが、研究チームはビタミンCを作れないようにしたネズミに、たばこの煙を吸わせた。肺を調べたところ、約2カ月でCOPDを発症した。煙を吸わせなかったネズミは6カ月で発症した。(平成18年9月16日 日本経済新聞)
突発性難聴にゼラチン療法
耳が突然聞こえなくなる「突発性難聴」に対して、京都大の伊藤壽一教授と田畑泰彦教授らのグループが、薬を特殊なゼラチンに混ぜ、鼓膜の奥にある内耳にくっつける新しい治療法を開発、動物実験で効果を確かめた。 内耳は手術が難しく、服薬や点滴では薬がほとんど届かないが、新治療法ではゼラチンから薬が少しずつ溶け出す。突発性難聴は毎年3万5000人が受診しているとされ、多くは、何らかの原因で音を電気信号に変えて脳に伝える内耳の神経機能が低下していると考えられる。ステロイドを大量点滴する治療法があるが、ステロイドが使えなかったり、効かなかったりすることも多い。これまで内耳の神経細胞を活性化させる薬が見つかっても、患部に届ける方法がなく、有効な治療法は確立していない。そこでグループでは、田畑教授らが開発した体の中で少しずつ溶けて薬を放出する特殊なゼラチンを利用。ゼラチンに、神経細胞の成長を促す働きのあるメカセルミンという薬を混ぜ、小さな塊を人工的に難聴を起こしたラットとモルモットの内耳の膜にくっつけた。すると2週間後には大部分のラットとモルモットで、聴力が正常に近い状態に戻り、内耳の神経細胞が働きを取り戻していた。ゼラチンをくっつけるのは中耳と内耳の境にある膜で、鼓膜に小さな穴を開けて通す。伊藤教授は「内視鏡を使えば安全に治療が可能」と話している(平成18年9月13日 朝日新聞)
皮膚がんを高熱で狙い撃ち
磁場をかけると発熱する酸化鉄の微粒子を使い、がん細胞だけを焼き殺す手法を、信州大と中部大の共同研究グループが開発し、マウスで皮膚がんを大幅に縮小させる実験に成功した。家庭に普及している電磁調理器と似た原理で、副作用が少なく、抗がん剤が効かない患者でも効果が期待できるという。信州大の松本和彦助教授は「早ければ来年にも皮膚がんの一種、悪性黒色腫(メラノーマ)を対象に小規模な臨床試験を始めたい」と説明。(平成18年9月13日 中国新聞)
毎日5杯、緑茶で長寿…脳こうそく死亡率が大幅低下
緑茶を1日5杯以上飲む人は脳こうそくなど循環器疾患による死亡率が顕著に低く、長寿の傾向があることが栗山進一・東北大助教授らの調査でわかった。ただ、がん死亡を防ぐ緑茶の効果は確認されなかった。研究チームは1994年に40〜79歳だった宮城県内の4万530人(男性1万9060人、女性2万1470人)を、1995年から11年間にわたって追跡調査。1日に飲むお茶の量によって四つのグループに分け、死因などを分析した。1日に5杯以上飲むグループの死亡率は、1杯未満のグループに比べ、男性で12%、女性で23%低かった。特に、動脈硬化が原因となる脳こうそくでは、お茶を多く飲むと男性で42%、女性で62%も死亡率が低下した。研究チームは、男女の死亡率の差は、喫煙によるものと考えられるとしている。栗山助教授は「緑茶を飲む量とがんの死亡率には関連が無かったが、緑茶を飲むと長生きの傾向があるとは言えそうだ」と話している。(平成18年9月13日 読売新聞)
人間ドック受けた270万人、88%に何らかの異常
日本人間ドック学会は、2005年に人間ドックを受けた人の約88%に何らかの異常が見つかった、とする調査結果を公表した。このうち70%くらいは医療の必要がなく、生活習慣を変えるだけで改善できる。調査は、同学会などが指定する全国の病院や施設で人間ドックを受診した約270万人が対象で、「異常なし」は12.3%で、87.7%の人で何らかの異常が見つかった。異常があった項目で最多は肝機能異常で26.6%、これに高コレステロール、肥満が続き、生活習慣に関係の深い項目が目立った。また、がんが発見されたケースは5887件あり、内訳は胃がん31.7%、大腸がん18.1%、肺がん9.1%など。胃がんの割合は20年前の調査に比べ半減した一方で、前立腺がんや乳がんが増加した。(平成18年9月9日 日本経済新聞)
ジュースでアルツハイマー病のリスク軽減
フルーツジュースや野菜ジュースをよく飲む人は、アルツハイマー病の発症リスクが大幅に低いことが示された。ジュースを週1回未満しか飲まない人に比べ、週3回以上飲む人ではアルツハイマー病の発症率が76%低く、週1〜2回飲む人でも16%低いという。この知見を報告したバンダービルト大学医学部助教授によると、これは抗酸化物質の中でも特に強力であるポリフェノールによる効果だという。ポリフェノールは果物や野菜の皮の部分に含まれ、実を丸ごと絞ればジュースにも含まれる。どのジュース、どのポリフェノールが特に高い効果をもたらすのかについては、さらに研究を重ねる必要がある。(平成18年9月7日 日本経済新聞)
膵がん、血液で早期診断へ
国立がんセンター研究所のグループが、患者から採った1滴の血液で、膵がんの有無を診断する方法を開発した。膵がんの有効な早期診断法はなかったが、90%以上の精度で見つけることができるという。3年後をめどに人間ドックなどでの応用をめざす。日本では、膵がんで年間2万2000人が死亡。がんの死因の第5位で、がん全体の約7%を占める。しかも最近20年間で膵がんは2.5倍と急増する傾向にある。初期には身体症状が出にくいため早期診断が難しく、このため5年生存率は、国立がんセンター中央病院97〜99年の患者で4.2%と低い状態が続いている。膵がん患者と健康な人の計142人の血液から、患者に特異的に増減するたんぱく質を分析。4種類のたんぱく質を調べる方法で、膵がんがあるかないかが判断できることを突き止めた。この方法で別の患者78人のデータを解析したところ、91%の正しさで診断できた。膵がん患者に特異的に表れる腫瘍マーカーで調べる方法も併用すれば、より完全に近い診断もできそうだという。(平成18年9月6日
朝日新聞)
くも膜下出血「血管内治療」も有効
脳卒中の一つ、脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血の治療で、手術せずに行う「血管内治療」は、治療1年後以降の長期成績が、「開頭手術」と同等とする結果を、米国の研究者らが発表した。脳動脈瘤は脳血管にできるこぶ状の膨らみで、血管内治療は、血管を通してコイルをこぶに入れる。従来は、頭部を切開し、破れた部分をクリップでとめる開頭手術が一般的だった。米カリフォルニア大サンフランシスコ校など9施設は、1996年から3年間に、くも膜下出血の治療を受けた1010人(血管内治療299人、開頭手術711人)を調査した。その結果、治療から1年後、こぶが再び破れる再破裂率は、血管内治療で0・11%、開頭手術が0%で、ほとんど差がなかった。再治療が必要となった割合は血管内治療が7・7%、開頭手術で1・7%だった一方、再治療時に死亡したり、合併症で障害が残ったりした割合は、それぞれ11%、17%だった。米国の研究者は「二つの治療法とも、再破裂率は非常に小さい。再治療率は血管内治療の方が高いが、開頭手術は再治療時に後遺症が残る割合が高いので、長期成績は総合的に同等と言える」としている。(平成18年9月1日
読売新聞)
がんの痛み緩和治療に重点
3人に1人の死因となっているがん。患者側から要望の強い痛み緩和治療に、厚生労働省が来年度から本格的に乗り出すことになった。末期はもちろん早期にも起こる痛みを和らげるため、モルヒネなどの使用方法を医師に研修してもらい、患者の相談にのる支援センターを都道府県ごとに設置する。欧米ではモルヒネなどの医療用麻薬を使った緩和ケアが早くから普及し、末期だけでなく初期のがん患者にも積極的に処方されている。厚労省の05年調査では、がんの死者数が32万人を超えて過去最多となり、81年以来、死因のトップとなっている。がん治療に携わる医師の10人に1人が、医療用麻薬を痛み止めとして使うことに「躊躇する」と答えた。このため、がん治療に携わる医師に、早期の患者にも使えるように緩和治療の正しい知識を身につけてもらうため、専用のマニュアルを作るほか、医療用麻薬についても専門医による講習会を各地で開き、使い方などを学んでもらう。一方、入院せずに通院し、緩和ケアを受けながら自宅での治療を希望する患者も増えている。このため、各都道府県に「在宅緩和ケア支援センター」(仮称)を設置し、医師や看護師が、在宅治療を望む患者や家族の相談に答えて助言をするなど体制作りを急ぐ。日本は医療用麻薬の使用量が米国の20分の1に過ぎず、緩和治療が極端に遅れている。背景には、医師側が根治療法ではないために意識が向かず、対策が後手にまわってきたこともある。今回、厚労省が本格的に対策に乗り出したことは遅すぎた感はある。医師だけでなく、これから医師になる学生に対しての教育こそ必要。(平成18年8月28日 朝日新聞)
不妊治療助成、20万円に倍増
厚生労働省は来年度から、体外受精など保険が適用されない不妊治療費への助成を現在の年間10万円から20万円に倍増することを決めた。助成の対象となるのは「特定不妊治療」といわれる体外受精と、顕微鏡を使い精子を卵子に注入して受精卵を子宮に戻す顕微授精。現在は年間10万円が上限で、夫婦あわせた年収が650万円未満の場合に通算5年間、助成を受けることができる。しかし、不妊治療には平均でも年間30万〜50万の費用がかかるとされており、経済的負担の軽減が課題となっていた。このため、助成額を現在の倍の20万円に増額。所得制限についても「夫婦で年収920万円未満」に引き上げ、対象を広げることを検討している。(平成18年8月28日 朝日新聞)
筋肉の数に個人差、大阪外大助教授が調査
トレーニングで筋肉は鍛えられるが、筋肉の数や付き方は、個人によって生まれつきかなり異なることが、大阪外国語大の研究でわかった。筋肉を詳しく調べることで、天性のスポーツエリートの発掘に役立ちそうだ。 例えば"力こぶ"は上腕二頭筋の名前の通り、二つの筋肉で構成されるのが一般的だが、分析では三つある人が14〜20%、四つある人が1〜4%いた。こうした特徴を持つ人は、ひじや指の筋肉の数も多くなるなど、特徴が1か所にとどまらない傾向があった。筋肉にかかる力に耐えるため、こうした特徴が現れるとみられるが、腕、指の筋肉が多いと、柔道などで、相手の動きを押さえる引き手に有効だと考えられる。また、太ももの裏側のハムストリングスは、筋肉がY字状にくっつくが、この位置や長さにも個人差があり、ひざや腰の動きの差につながっているとみられた。一方、アキレス腱の筋組織が、かかとの骨までついている人とついていない人がおり、体操選手のゆか運動での瞬発力や、けがに対する強さなどに関与しているとみられる。 (平成18年8月26日 読売新聞)
ビール1杯で顔真っ赤 食道がん8倍以上
ビール1杯で顔が赤くなる人は、普通に酒が飲める人と比べ、食道がんになるリスクが少なくとも8倍以上にのぼることが、国立病院機構大阪医療センターの研究グループの調査で明らかになった。飲酒時に顔が赤くなる「フラッシング反応」は、アルコールから代謝されたアセトアルデヒドが原因。アセトアルデヒドを分解、無毒化するアルデヒド脱水素酵素の正常型をもつ日本人は半数程度で、完全に解毒できない欠損型をもつ人との間で差が生まれる。東京と大阪の食道がん、頭頸部がん患者約400人、健常者約1400人を調査。その結果、正常型の人が少量飲酒した場合に比べ、8.84倍もの食道がんの発生リスクがあり、さらに1日3合以上飲酒すると、実に114倍ものリスクがあることが判明した。辻仲科長が、経験から指摘する「食道がんにかかる典型的な例」は、営業職などに配属され、酒が弱いのに、接待など付き合いで無理に飲むようになり、次第に普通に飲めるようになるケースという。(平成18年8月26 日産経新聞)
ストレスにより脳が萎縮
ストレスにより脳細胞が萎縮し、免疫システムの老化が早まるということを示した研究米国精神医学会で報告された。 ラットに繰り返しストレスを与えると、脳のニューロン(神経細胞)の萎縮を示す徴候が認められたという。過去の研究で、ストレスによって脳海馬の神経細胞が萎縮し記憶力が障害されること、意思決定や注意力に関わる前頭前皮質と呼ばれる部位でも萎縮が起きることが明らかにされていた。今回の研究では、ストレスを与えられたラットは、餌の場所が変わったときに同じ手掛かりを別の方法で利用する能力が失われたという。ストレスを与えられた脳は、不安が大きくなり、注意力、学習能力、記憶力などが低下する。しかし、脳は回復力が極めて高いため、心理療法、認知行動療法および薬剤を組み合わせることにより正常な状態に近づけることができるという。また、脳の損傷は時間の経過によっても癒やされ、運動にも極めて大きな効果があることが明らかになってきている。また、ストレスが免疫システムを破壊することも示された。ストレスによって細胞内の染色体末端部のDNAが短くなり、適切に働かなくなるという。この部分のDNAは、靴ひもの先端のほつれを防止するプラスチックキャップのような役割をもつ。 健康な女性を対象とした研究の結果、心理的ストレスがこの末端部の短縮に関わり、免疫システムの老化を早めることがわかった。この問題への対処法は、「十分な睡眠、活動的であること、健康的な食生活など、慢性疾患の予防法してすでに知られていることを守ることだ」と述べている。(平成18年8月17日 日本経済新聞)
認知症の専門知識もつ、認定看護師
認知症ケアの専門知識や技術をもつ、初めての「認知症高齢者認定看護師」が誕生する。日本看護協会が新設するもの。同協会によると、認知症の患者は診療科にかかわらずいる。だが、看護師は所属する科の知識はあっても、認知症の理解が不十分で、コミュニケーションに戸惑うケースも少なくないという。このため、認知症に詳しい看護師を育成しようと、昨年4月から研修を始めた。定員15人に対して全国から19人の応募があった。1年間、基礎知識の講習を受けて実習を終え、5月の認定試験に10人が合格した。今年4月からは2期生が研修中だ。
認定看護師は、認知症の患者への対応だけでなく、家族のサポートや、退院後に利用する訪問看護ステーションとの連携を調整する役割を担う。同協会は「どんなケアが必要か見極め、医師や介護職といったスタッフ間の橋渡しも期待したい」としている。同協会はこれまで、救急や糖尿病など12分野で1700人以上の認定看護師を育成している。(平成18年8月8日 朝日新聞)
足の切断を防ぐ再生医療
埼玉医科大学は重度の糖尿病患者などの皮膚にできる潰瘍の新しい治療法を開発した。患者から骨髄液を採取し、この液に浸したコラーゲン製人工皮膚を患部に張り付ける。臨床研究では9割以上で回復し、足の切断を免れた。厚生労働省の先進医療に申請済みで、難治性潰瘍の簡単な再生医療として普及を目指す。糖尿病や足の動脈硬化(閉塞性動脈硬化症)、床ずれなどが原因で足や腰などにできる重い潰瘍を放っておくと、皮膚や筋肉組織が壊死(えし)する。現在、国内に糖尿病患者は740万人いるが、1.4%が皮膚の潰瘍を経験し、そのうち2割が足や指を切断しなければならない。埼玉医大の市岡滋・助教授らが開発した新治療法は、まず患者の腰のあたりから骨髄液を採取して、やけどの治療などに使うコラーゲンからできた人工皮膚に浸す。壊死した部分を取り除いた潰瘍に人工皮膚を張り付けると、骨髄の成分が血管や皮膚の再生を促し、3―4カ月で治る。(平成18年8月7日 日本経済新聞)
C型肝炎インターフェロン治療、医療機関で大きな違い
C型肝炎患者のインターフェロン治療に関する考え方が、医療機関によって大きく違うことが久留米大などの調査で分かった。肝臓専門医がいる病院では70歳以上の高齢者の患者にも勧めていたが、専門医がいない診療所では「高齢」を理由に勧めていなかった。また、インターフェロン治療に対し、患者の側には「副作用が心配」との見方が強いことも分かった。久留米大と日本製薬工業協会医薬産業政策研究所が、九州のある地区の1病院と7診療所に通う患者254人の治療法などについて患者・医師双方に尋ねた。肝臓専門医がいる病院では90%の患者にインターフェロン治療を勧めていたが、専門医がいない診療所では39%だった。その差は高齢の患者で特に大きく、診療所で勧めない理由も「高齢のため適さない」が47%で最も多かった。
一方、この治療を勧められながら同意しなかった患者では、「副作用が心配」(75%)が最大の理由だった。
結果について、佐田教授は「高齢者ほど肝がんのリスクがあるので、専門医は高齢者にもインターフェロンを使っている。病院と診療所の連携が必要だ」と言う。C型肝炎の患者・感染者は国内に約200万人いるとみられ、慢性肝炎から肝硬変や肝がんに至るリスクがある。肝がんの約8割はC型肝炎ウイルスが原因とされる。
だが近年、C型肝炎ウイルスを抑える注射薬インターフェロンの改良が進み、抗ウイルス薬との併用治療法が効果を上げている。肝がん発生を抑えることもできる。最近普及してきた方法では、週1回の注射を半年〜1年続ける。最初の2週間は入院が勧められ、その後は通院で治療できる。(平成18年8月6日 朝日新聞)
たばこ、一本でダイオキシン摂取基準200倍相当
たばこの煙に含まれる物質が、細胞内でダイオキシンと似た働きをし、1本分の煙が、1日の摂取基準を約200倍上回るダイオキシンに相当することを、山梨大大学院生の河西あゆみさんや、北村正敬教授(分子情報伝達学)らが突き止めた。米国のがん専門誌「キャンサーリサーチ」に論文が掲載された。ダイオキシン類は、細胞内の「ダイオキシン受容体」と結合し、活性化させて毒性を発揮する。たばこの煙は微量のダイオキシンを含むと分かっていたが、他に約5000種類の化学物質も含むため、総合的にどれだけ同受容体を活性化するかは不明だった。研究チームは市販のさまざまなたばこ1本分の主流煙を、溶液に溶かして抽出液を作った。一方で、同受容体が活性化すると特殊なたんぱく質を分泌する細胞を、遺伝子操作で作成。この細胞に抽出液を加え、活性化の程度を調べた。タール10ミリグラムを含む平均的なたばこの場合、活性化の程度は、ダイオキシン3万9300ピコグラム(ピコは1兆分の1)が受容体と結びついたのに相当した。体重60キロの人なら、国が定めるダイオキシンの1日耐容摂取量(体重1キロ当たり4ピコグラム)の164倍に当たる。タールの多いたばこでは200倍以上に達した。さらに、同受容体の活性化で特殊なたんぱく質を作るマウスを作成。主流煙を直接吸わせる実験や、周囲に流して受動喫煙と同じ状態にする実験をした。いずれもマウスの血中でたんぱく質が増え活性化が確認された。北村教授は「受容体は今回、主にダイオキシン以外の物質で活性化したとみられ、大量のダイオキシンを浴びたのと同じ害が出るわけではない。だが、遺伝子操作でこの受容体を常に活性化させたマウスは、がんや免疫異常を起こす。喫煙者も同様の心配がある。喫煙させたマウスでは、活性化が4日続いた」と警告している。(平成18年8月4日
毎日新聞)
腹部大動脈瘤にステント治療
腹部大動脈瘤に対して、血管の内側から治療する筒状の器具、ステントが初めて承認され、先月、慈恵医大で治療が行われた。腹部大動脈瘤は動脈硬化に伴って発生し、直径が4〜5センチを超えると、命にかかわる破裂の危険が高まる。このため大きい場合は、開腹して人工血管を埋め込む手術が行われてきた。国内では年間約1万1000件を数える。しかし、高齢の患者が多く、全身麻酔で行われる手術は、心臓病や肺気腫(しゅ)など別の病気を持っていると、危険が高い。そのため、欧米では腹部動脈瘤は約10年前から、開腹手術ではなく、ステント治療が広がり、現在、米国では半数を占めている。足の付け根の動脈から、人工血管の代わりに、金属の網が埋め込まれたポリエステルの筒を挿入して、腹部大動脈に留置する。局所麻酔でも行われる。 先月、日本でも腹部大動脈瘤治療用のステントが承認され、アメリカで経験を積んできた同大血管外科の大木隆生教授が60歳代の男性患者に実施。2日後に退院した。ステント治療は、東京医大、奈良県立医大、三重大、山口県立総合医療センターでも始まる。(平成18年8月4日 読売新聞)
ALS治療に新手法、米教授ら進行抑制ラットで成功
全身の運動機能が麻痺する「筋委縮性側索硬化症(ALS)」の症状の進行を遅らせることに、米カリフォルニア大サンディエゴ校のドン・クリーブランド教授らが動物実験で成功した。研究チームは、SOD1という酵素が異常だと、これが脊髄(せきずい)にあるミクログリアという免疫細胞を傷つけ、ALSの症状の進行につながることを解明。この酵素の生成に働く特殊なRNA(リボ核酸)を阻害する物質(アンチセンス)を合成した。アンチセンスを、ALSの症状を人工的に発症するようにしたラットの脳に生後 65日で注入したところ、ラットは生後95日でALSを発症した。 通常は平均で発症27日後に死亡するにもかかわらず、アンチセンスを注入した場合は、症状の進行が遅く、平均で37日後まで生き延びた。(平成18年7月31日
読売新聞)
多発性硬化症の発症を抑えるリンパ球発見
脳や脊髄の神経を自らの免疫が攻撃し、傷付ける自己免疫疾患の一種「多発性硬化症」の発症を抑えるリンパ球を、国立精神・神経センター神経研究所の山村隆部長らが発見した。新たな免疫疾患の予防、治療法開発につながる成果で、31日付の科学誌「ネイチャー・イムノロジー」電子版に発表する。多発性硬化症の患者数は現在、国内に約1万人。過去30年間に20倍以上増えたとされる。山村部長らは、この背景に食生活など生活習慣が関与していると予測し、腸の粘膜だけに存在し、その働きが未解明なリンパ球の一種に着目。このリンパ球の量を変えたマウスに多発性硬化症のモデルとされる脳炎を発症させた。その結果、リンパ球が多いマウスほど、病状が軽く、リンパ球を全く持たないと病状が極端に悪化することが分かった。逆に脳炎のマウスに、リンパ球を注射すると症状が緩和した。(平成18年7月31日
読売新聞)
非ステロイド性抗炎症薬における防御因子増強剤の予防効果は不十分
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)による胃潰瘍など胃粘膜傷害を防ぐために、多くのケースで胃粘膜を保護する防御因子増強剤が併用されているが、奈良県立医科大学などの研究チームが日本人を対象に臨床試験を行った結果、予防効果は不十分であることが明らかになった。試験では、胃酸の分泌を抑えるH2ブロッカーの方が胃粘膜傷害を有意に改善する結果だった。医学専門家として試験計画の助言などを行った島根大学医学部の木下芳一教授は、「現在の治療を見直す必要がある」と指摘し、NSAIDsによる胃粘膜障害にH2ブロッカーの使用を促している。
臨床試験は、GCPに準拠し、関節リウマチなどでNSAIDsを使用している日本人患者の胃粘膜傷害の発症頻度と、保険適用範囲内での胃粘膜傷害の対処法を検討した。奈良県立医大の整形外科教授の高倉義典、同大第3内科教授の福井博の両氏が試験調整医師となって行われた。261人の患者を対象に実施した発症頻度の検討では、63%の患者に潰瘍や胃炎といった胃粘膜傷害が発現していることが判明。 自覚症状がない188例でも58%に傷害が見つかった。
薬剤別の発現率は、ジクロフェナク投与患者(36例)では83%。胃に比較的やさしいと言われ最もよく使われるロキソプロフェン(94例)でも58%、メロキシカムとエドトラク(42例)という新しいNSAIDsでも55%に上った。胃粘膜傷害を防ぐため、防御因子増強薬は96%に投与されていたが、62%の患者に傷害があり、同薬は傷害発生を防ぐには不十分であることが示された。その上で、傷害に対する対処法については、胃粘膜傷害があり(潰瘍患者は除外)、試験に同意した129人を対象に、防御因子増強薬のレバミピド(1日300mg)とH2ブロッカーのファモチジン(1日20mg)を無作為で割り付け、4週間投与して比較。傷害の程度が悪いほど高い値となる「LANZAスコア」を用いて評価した。
投与前は両群とも中程度のスコア2.4だったが、投与後はレバミピド群が2.2とほとんど改善しなかったのに対し、ファモチジン群は1.3と有意に改善。両群間の差も有意だった。傷害が完治したことを示すスコア・ゼロとなった患者は、レバミピド群が18.2%に対し、ファモチジン群は45.6%に上った。副作用は重篤なものはなく、発現頻度も両群同程度だった。
試験結果を受け、島根大の木下教授は「出血性潰瘍を起こした場合、2カ月の治療で約40万円かかる。比較した両剤とも薬価は1日60円程度で済むことを含め、治療の効果の高いH2ブロッカーの使用が奨められる」とした。昨年出版された胃潰瘍診療ガイドラインでも,日本で市販されている多くの胃粘膜防御系薬剤が,潰瘍治癒率からみてその使用根拠が不明確であるとされているが、胃潰瘍診療ガイドラインへの試験結果の反映については、「他の試験を含めた検討になる」とし、課題だとした。
さらに同教授は、自覚症状がなくてものみ続ける予防的投薬も提案したが、いつまでのみ続け、傷害が完治した場合の服用の継続の要否については、別途試験が必要だとした。(平成18年7月31日 薬事日報)
子宮温存がん治療で出産
子宮頸がんの治療で、腹腔鏡を使った手術で子宮を温存し、妊娠、出産させることに倉敷成人病センター産婦人科グループが国内で初めて成功した。子宮頸がんは近年、若い女性に増えており、出産を望む若い子宮がん患者の選択肢の一つとして注目されそうだ。子宮がんには、入り口部分(頸部)にできる子宮頸がんと、奥の袋状の部分(体部)にできる子宮体がんがある。子宮頸がんは、ごく早期に発見されれば、がんの部分だけを切り取る手術で済むが、進行すると子宮やその周囲を広く摘出しなければならない。今回行われた「広汎子宮頸部摘出術」は、やや進行した患者を対象に、子宮頸部と周囲の組織だけを切り取り、子宮体部を残す方法。 数年前から国内数か所の大学病院で開腹手術によって試みられている。この治療を開腹ではなく、腹腔鏡手術で実施。おなかに5〜10ミリの穴を5か所開け、小型カメラを入れて見ながら、がんを切除した。患者はその後、妊娠し、今春、妊娠34週で約1900グラムの健康な女児を出産した。(平成18年7月28日 読売新聞)
平均寿命が6年ぶり低下・男78.53歳、女85.49歳
厚生労働省は25日、2005年の日本人の平均寿命が男女とも6年ぶりに前年を下回ったと発表した。男性は0.11年短い78.53歳に、女性は0.1年短い85.49歳になった。インフルエンザの流行が原因とみられる。この結果、男性は主要国・地域で2位から4位に後退。女性は21年連続で世界一を維持した。平均寿命は、その年の年齢別の死亡率が今後も続くと仮定した場合、ゼロ歳の人が生きる平均年数。 簡易生命表として年齢、男女別にはじく。低下の背景を死亡原因別にみると、肺炎と心臓病の影響が大きい。いずれも05年3月に増えた。厚労省は猛威を振るったインフルエンザが関係しているとみる。自殺の増加も響いた。 一方、がん、脳卒中、交通事故による死亡は改善した。平均寿命を主要国・地域の直近の統計と比べると女性は香港の84.7歳を引き離し世界一を維持。アイスランドに次ぎ2位だった男性は香港、スイスに抜かれた。
(平成18年7月26日 日本経済新聞)
心筋梗塞に関与する遺伝子型を発見
心筋梗塞の発症に関与する遺伝子の型を理化学研究所などの研究グループが見つけた。特定の型の人は他の型に比べて1.45倍、心筋梗塞を起こしやすかった。リスクの高い人には特に生活習慣に気を使ってもらうなど、個人に応じた病気予防に役立つ成果という。3459人の心筋梗塞患者と3955人の一般人から同意を得て、遺伝子の違いを調べた。その結果、PSMA6という遺伝子を構成する部品(塩基)1個の違いで、心筋梗塞になりやすい型(GG型)とそうでない型に分かれることがわかった。GG型の割合は一般人で8.9%だが、患者では12.4%と多く、この型の人は心筋梗塞のリスクが1.45倍高くなるという。この遺伝子の働きを抑える実験をしたところ、炎症作用が抑制された。心筋梗塞は心臓の血管の炎症との関連が指摘されている。遺伝子の型で炎症の起きやすさに違いが出てリスクの差につながったと田中さんはみる。田中さんらはこれまでも、心筋梗塞関連の遺伝子の型の違いを見つけていて今回が三つ目。三つを組み合わせることで、一般人に比べ約3.5倍という特に高リスクの人がわかるという。(平成18年7月17日
朝日新聞)
がん・糖尿病治療の専門知識備えた看護師を養成
厚生労働省はがんや糖尿病に詳しい看護師を養成することを決め、痛みの緩和や生活習慣改善など、臨床研修の内容を盛り込んだ実施要綱を全都道府県に通知した。「国民病」と言われるがんや糖尿病は、治療が長期化するケースが多く、医師よりも患者と接する機会が多い看護師が果たす役割は大きい。今年度は約700人が研修を受け、看護の質の向上を図る。厚労省によると、研修は都道府県に委託して実施。ある程度の勤務経験があり、主に地域の中核病院に勤務する看護師を対象とする。身分を勤務先の病院に置いたまま、都道府県がん拠点病院など、がんや糖尿病の専門的な治療を行う病院で原則40日間、実践的な研修を受ける。がんの研修では、激しい痛みを「心のケア」を含めて取り除く疼痛緩和をはじめ、化学療法を受けた患者や末期の患者に対する話し方や、病状を説明する際の資料の使い方など、がん看護に必要な内容を一通り学習する。一方、糖尿病の研修では、食事療法や運動療法、薬物療法、生活指導のほか、足に血流障害を起こさないためのケアについても学ぶ。初年度となる今年度は、がん研修は全国の25病院、糖尿病研修は10病院で、1カ所当たり約20人を対象に実施。各病院が、地域の中核病院から1人か2人ずつ受け入れる。日本看護協会が認定した専門看護師や認定看護師を講師として活用。 研修で得た知識や技術を、勤務先の病院に戻って臨床現場で活用してもらう。厚労省は、研修の成果を点検したうえで、来年度以降に研修を行う病院を拡大。なかでも、がん看護については、全都道府県で最低1カ所ずつ行うようにしたい考え。(平成18年7月17日 産経新聞)
歯周病の人ほど脳血管障害に
歯周病による炎症で歯周組織(歯肉や歯を支える歯槽骨など)の破壊が進んでいる人ほど、自覚症状がほとんどない脳血管障害(無症候性脳血管障害)を起こしやすいことが分かった。無症候性脳血管障害を繰り返すと、認知症になりやすいとされ、歯周病の予防が認知症の予防にもつながる可能性がある。昨年秋、岩手県大迫町在住の55歳以上の男女で、頭部外傷や脳卒中の既往歴がない156人を対象に調査した。このうち、過去も含め歯周病による歯周組織の破壊の程度が確認できた129人について、MRIで脳を撮影し、病変の有無を分析した。その結果、脳の血流が悪くなっていることを示す病変が見つかった人は、歯周組織の破壊が軽度だった72人では11%(8人)だったが、破壊が中度・重度の57人では28%(16人)に上った。年齢や喫煙の有無、血圧などを考慮した結果でも、歯周組織の破壊が進んだ人ほど無症候性脳血管障害を起こしやすかった。介護保険法の改正で今年4月に導入された介護予防サービスでは、口腔ケアも対象になっており、口の中の健康への意識をもっと高めてほしい」と話している。(平成18年7月17日 毎日新聞)
生活習慣病防ぐ運動量
生活習慣病の予防に必要な1週間の運動量の目安を示した指針「エクササイズガイド2006」を、厚生労働省の運動指針小委員会がまとめた。スポーツだけでなく掃除や階段の上り下りなど、日常生活での活動も対象にして、内容ごとに具体的な時間をあげており、運動習慣のない人でも活用できるのが特徴。指針は「エクササイズ」という運動量の単位を設定し、例えば軽い筋力トレーニング、バレーボールなどの運動や、歩行、床掃除といった活動は、20分行えば1エクササイズとした。内容がきつくなるほど時間は減り、ゴルフ、速歩、自転車、子どもと遊ぶなどは15分、軽いジョギング、エアロビクス、階段の上り下りなら10分、ランニング、水泳、重い荷物を運ぶなどは7〜8分で1エクササイズとなる。生活習慣病を防ぐには、これらを組み合わせて1週間に計23エクササイズ以上行い、うち少なくとも4エクササイズは運動とすることを目標とした。また、内臓脂肪型肥満に高血圧などが重なったメタボリック症候群と、その予備軍の人たち向けに、運動の目標を設定する方法も紹介。ウエストを1センチ減らすには、7000キロカロリー分の運動や食事制限が必要となるが、ジョギングと歩行を計20分行った場合、70キロの人では123キロカロリーの消費になる―などと分かりやすくアドバイスしている。(平成18年7月15日 産経新聞)
認知症の4割が事故を経験
認知症で運転免許証を持つ患者83人のうち4割が、接触や追突などの交通事故を起こしていた。こんな結果が高知大医学部の精神医学の研究でわかった。1995〜2005年に高知大病院などを受診した83人(平均70.7歳)を調べた。
その結果、34人(41%)が58件の事故を起こしていた。うち人身事故は14件だった。 また認知症の原因によって事故の傾向が異なっていた。
アルツハイマー病では、駐車する時にぶつけたり、自分がどこを走っているかわからなくなって事故を起こしたりする例があった。
前頭側頭葉変性症(FTLD)では、追突や赤信号を無視した右折、人にぶつかってそのまま走り去るなどの事故が含まれていた。また、調査した患者83人のうち42人が運転免許の更新手続きを取り、全員が成功していた。
道路交通法の改正で、運転に支障がある認知症の人は公安委員会が免許を取り消すことができる。 だが、自己申告などを元に判断しているため、処分は年間数十件にとどまる。警察庁は判断能力を検査するシステム作りを検討している。(平成18年7月1日 朝日新聞)
中・高生の23%が不眠
中学・高校生の4人に1人が不眠を訴えていることが、日本大医学部の研究で分かった。10万人規模の調査で思春期の子どもの不眠の実態が明らかになるのは初めてで、不眠の割合は大人を上回った。2004年12月〜2005年1月に、全国の中学131校、高校109校を無作為に抽出し、在校生に睡眠状況や生活習慣、精神的健康度を質問した。不眠としたのは(1)なかなか寝付けない「入眠障害」 (2)夜中に目が覚める「夜間覚醒(かくせい)」 (3)朝早く目覚めて再び眠るのが難しい「早朝覚醒」のうち一つ以上が当てはまった場合で、入眠障害は14・8%で、成人の8・3%より6・5ポイントも高い。逆に、夜間覚醒は11・3%(成人15%)、早朝覚醒は5・5%(同8%)で、成人より低かった。(平成18年6月30日毎日新聞)
リハビリ期間上限撤廃
診療報酬改定でリハビリの上限撤廃を求めて厚生労働省に約44万人の署名を手渡す。今年4月の診療報酬改定で、医療保険で受けられるリハビリの期間が疾患別に上限が設けられた問題で、全国の患者らでつくる「リハビリ診療報酬改定を考える会」が30日、上限撤廃を求める約44万人の署名を厚生労働省に提出し、「期限を設けず、患者が必要なリハビリを医療保険で受けられるようにしてほしい」と訴えた。同会は上限設定で、長期のリハビリ医療を必要とする多くの患者が保険診療の対象外になり、「患者が切り捨てられる」と主張。5月から上限設定に反対する署名活動を展開していた。今回の診療報酬改定では、厚労省の研究会で「長期にわたって効果が明らかでないリハビリが行われている」などと指摘されたことを受け、●脳卒中など脳血管疾患180日 ●骨折など運動器150日 ●肺炎など呼吸器90日 ●急性心筋梗塞など心大血管疾患150日などと保険適用の上限を設定した。また、「改善が期待できる場合」という条件付きで、失語症や高次脳機能障害、重症筋無力症、スモンなど一部の疾患は上限規定から除外した。しかし、患者からは除外疾患の基準や改善の定義があいまいという批判が出ており、疾患別ではなく、必要なリハビリを受けられるようにすべきだとの声が上がっていた。(平成18年6月30日 毎日新聞)
腹圧性尿失禁
せき、くしゃみなどで腹部に力が入った際に尿が漏れる「腹圧性尿失禁」の患者に対し、本人の筋肉から採った細胞を培養後、尿道の筋肉へ注入して症状を改善することに、米ピッツバーグ大のM・チャンセラー教授と吉村直樹・准教授らが成功した。トロント大(カナダ)と共同で実施した臨床試験は、同大の40〜60代の女性患者7人が対象。まず太ももの筋肉から細胞を採取し、これを約4週間培養した後、それぞれの尿道の筋肉へ注入した。このうち尿道の筋肉の浅いところに注入した2人は効果が見られなかったが、深いところに注入した他の5人は症状が改善。注入は外来治療で済み、副作用も特に報告されていないという。腹圧性尿失禁は、尿道を締める筋肉が弱まるのが原因。出産を経験した中年女性に多い。研究グループは「培養細胞には幹細胞が含まれる。それが新しい筋線維に分化し、尿道周辺の筋肉の働きを強めたのだろう」と推測。 「米国だけで1300万人が尿失禁に悩んでおり、今回の成績には、非常に勇気づけられる」としている。(平成18年6月30日 読売新聞)
記憶に重要な働きのある、たんぱく質を発見
京都大学などの研究グループは、記憶に重要な働きをしているたんぱく質を新たに突き止めた。脳の海馬という部分の神経細胞の機能に欠かせず、ネズミを使った実験では、このたんぱく質がないと記憶力が低かった。認知症の新しい治療法の開発に役立つ可能性がある。海馬の神経細胞は1度活動した後、次の活動に備えて休む仕組みになっている。京大の竹島浩教授と東北大学の森口茂樹助手らは、休み状態を作り出すように働く3種類のたんぱく質がうまく連携するために、「ジャンクトフィリン」と呼ぶたんぱく質が必要なことを見つけた。ジャンクトフィリンを持たないネズミを作って実験したところ、数分間の短期でも数日間の長期でも、記憶力が通常のネズミより低かった。(平成18年6月27日 日本経済新聞)
肥満治療薬
アベンティスは抗肥満薬「アコンプリア」(一般名:リモナバン)の承認をEU加盟全25カ国で取得し、7月の英国を皮切りに順次発売していくことになった。同剤は、脳神経組織に存在するカンナビノイド1(CB1)受容体を阻害することで食欲などを抑制する。適応は、同社によると「2型糖尿病や脂質代謝異常といった肥満に関連した心血管及び代謝性疾患のリスク因子を持つ肥満の患者さん(BMI値30以上)、過体重(同27以上)の治療で、食事療法や運動療法の補助療法として使用される」。20mg錠を1日1回投与する。世界4500人の患者を2年間に渡って調査した臨床試験「RIO」では、体重、ウエスト径、糖尿病の指標となるHbA1c、中性脂肪を有意に減らした。それらデータに基づいて承認となった。7月に英国で発売し、今年後半からデンマーク、アイルランド、ドイツ、フィンランド、ノルウェーで販売を始める計画。米国では承認申請中、日本ではPIIbにある。(平成18年6月27 日薬事日報)
「無呼吸症候群」メタボリック・シンドロームにご用心
寝ているときに呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群」の男性患者の半数、女性では約3割が、脳卒中や心筋梗塞の引き金になる「メタボリック・シンドローム」を合併しているとの研究結果を、愛知医科大病院睡眠医療センターがまとめ、日本高血圧学会誌に発表した。どちらかの診断を受けた場合は、もう一方の合併の可能性も考慮する必要がありそうだ。同センターの塩見利明教授らは、精密検査で睡眠時無呼吸症候群と診断された819人(男性719人、女性100人)を対象に、内臓脂肪の蓄積などで起きるメタボリック・シンドロームの合併状況を調べ、同症候群ではない男性59人、女性30人と比べた。その結果、同症候群の男性のメタボリック・シンドローム合併率は49・5%で、同症候群ではない男性(22・0%)の2倍以上。女性の合併率は32・0%で、同症候群ではない女性(6・7%)の約5倍だった。 さらに、メタボリック・シンドロームの診断基準(腹部肥満、高血圧、高血糖、高脂血症)のうち、女性の血糖値を除いたすべての項目で、症候群の集団の方が、そうでない集団より数値が悪いこともわかった。(平成18年6月25日 読売新聞)
「初期がん」から緩和ケア
厚生労働省は、末期のがん患者の痛みや心労を取り除く「緩和ケア」を、初期がんを含むがん治療の全段階に導入するため、新しい医療体制を整備することを決めた。全国135か所の拠点病院に、2年以内に緩和ケア対応医療チームを設置するよう求めると共に、モデル地区から選んだがん患者5000人に対し、緩和ケアを組み込んだ試験的な医療を開始する。緩和ケアの普及を目的とした基本計画を5年以内に策定することを目指す。国内でのがん発症者は、年間約60万人。がんと診断された患者は、早い段階から、死への不安を抱えたり、がんや治療による苦痛を感じたりしている。 だが、国内の医療現場は、手術でがんを取りきるなど根治を重視しているため、終末期を迎えるまで、ほとんど緩和ケアは行われていない。 今月成立したがん対策基本法には、緩和ケアについて「早期から適切に行われるようにする」と明記されている。緩和ケアの普及は、患者に優しいがん医療体制づくりの第一歩となる。現在、地域のがん診療の中核となる拠点病院が、全国で135施設選ばれている。厚労省は、拠点病院に対し、緩和ケアを医師、看護師、医療心理の専門家によるチーム医療とすることを義務づけ、ホスピスだけでなく、一般病棟や外来のがん患者にも、継続して施療できる院内体制の整備を求める。拠点病院への新規指定を希望する医療機関に対しても、緩和ケアの充実を指定条件にする。 さらに、緩和ケアを全国に普及させる具体策を研究するため、年内に経験豊富な研究者を公募し、選抜する。選ばれた研究者は、拠点病院を中心にモデルとなる地区を選定、5000人の患者を対象に研究を進める。 具体的には、ケアに必要な知識や技術を各医療機関に広める教育プログラムを作り、地域内の患者が必要とするときにすぐ緩和ケアを受けることが可能な医療体制のあり方を探る。 在宅での緩和ケアプログラムも作成し、末期がん患者の自宅療養を増やす。 緩和ケアの利用率は、欧米の3割に対し、日本は1割未満。 痛みを和らげるモルヒネの1人当たり使用量は、日本はカナダの10分の1との統計がある。モデル地区では、緩和ケアの利用率を2倍に高めることを目標とする。(平成18年6月25日 読売新聞)
BSE潜伏期間が最長50年超す
牛海綿状脳症(BSE)の牛を食べて発病するとされる変異型クロイツフェルト・ヤコブ病は、感染から発病までの潜伏期間が、長い人で50年を超す可能性があるとの推定を、英ロンドン大などのチームがまとめ、24日付の英医学誌ランセットに発表した。従来は長くて20年程度との推定もあったが、チームは長期的な監視が重要と訴えている。根拠は、BSEやヤコブ病と同様に異常プリオンが原因とされるクールー病。 死者への敬意を表す手段として人の脳を食べる習慣があったパプアニューギニアの一部に残る疾患で、潜伏期間は平均12年とされてきた。チームは比較的最近死亡した患者11人の中に、潜伏期間が50年以上とみられる例を複数発見。こうした人に共通した遺伝的特徴も見つけ、潜伏期間は個人の遺伝的特徴に左右される可能性があると推定した。変異型ヤコブ病でも患者に共通する遺伝的特徴があることなどから、現在の変異型患者は潜伏期間が特に短い人であり、牛から人へ種をこえた感染の影響を考えると、50年よりさらに長い期間を経て患者が増える可能性があると結論づけた。(平成18年6月25日 毎日新聞)
ES細胞からヒト血液成分
あらゆる組織や臓器に成長できる「胚性幹細胞(ES細胞)」から、人間の血液成分を作り出す研究成果が相次いでいる。東京大学の二つの研究グループが、血小板と赤血球をそれぞれ作ることに成功した。量産できれば、不足している輸血用血液を献血に頼らなくても済むようになる。 感染症を起こす新たなウイルスが献血に混入する問題を回避できる可能性もある。
東大の中内啓光教授、江藤浩之助手らは、出血を止める役割を持っている血小板を世界で初めて作製した。国産のES細胞にたんぱく質を加えながら培養して成長させた。 できた血小板には、集まって固まるという血小板特有の性質があることを確認した。 現在は作製効率が低いため、研究グループは今後、大量の血小板を一度に作る技術の開発に取り組む。(平成18年6月25日 日本経済新聞)
脊髄損傷患者に神経細胞の再生治療を実施
関西医科大を中心とするグループが、事故などで首を骨折して半身不随になった脊髄損傷の患者に自身の骨髄細胞を移植して神経細胞の再生を促す日本初の臨床研究を実施、24日、大阪府内で経過報告をした。 実施例はまだ1例で、副作用はなく、症状の改善もみられたが、責任者の中谷寿男・同大教授(救急医学)は「現時点では移植による治療効果かどうかはわからない」としている。
報告によると、3月上旬に転落事故で首を骨折して同大病院に運ばれた30代の男性に対して、12日後に移植を実施した。 背骨を固定する手術の際に骨髄を採取、専用の施設で培養した後、腰から注射した。 これまで副作用はなく、移植前に両腕のひじが動かせなかったのが、少し曲げ伸ばしができるようになったという。 ただ、同程度の脊髄損傷では、多くの場合は改善が望めないが、機能が回復する例もある。今回が治療効果かどうかは判断できないという。
この臨床研究は、事故直後の患者が対象で、グループでは23例を目標にしている。 今月、2例目の患者に治療を試みたが、細胞培養がうまくいかずに中止したという。(平成18年6月24日 朝日新聞)
ES細胞、分化神経細胞移植で運動能力回復
米ジョンズホプキンス大の研究チームは20日、脊髄が麻痺したラットに胚性幹細胞(ES細胞)から分化させた神経細胞を移植し、運動能力を回復させることに成功したと発表した。 移植した細胞が成長し、神経回路を再生した。 将来的には筋萎縮性側索硬化症(ALS)や脊髄損傷の治療への応用の可能性もあるという。 研究チームは、ラットのES細胞に、筋肉を制御する信号を伝える神経細胞(運動ニューロン)への分化を促す化学物質などを加えて培養。 ウイルスの感染で運動ニューロンを失い、脊髄がまひしたラットに移植した。 神経細胞の成長を促す物質を分泌する細胞も合わせて移植し、別の化学物質も皮下注射した。 移植から3カ月後に数百本の運動ニューロンが下肢を動かす筋肉に接続しているのが確認された。 半年後には15頭中11頭が足を動かすなどの運動ができるようになった。
一方、ES細胞を移植したものの、比較のため一部の物質しか与えられなかったラットでは運動能力の回復は見られなかった。 今夏にはヒトES細胞とブタで実験し、同様の効果が大型の動物で見られるかを確認する。 研究を主導した同大のダグラス・カー博士は「神経を再接続する手順を示すことができた」と話している。(平成18年6月21日 毎日新聞)
自然な眠りを導く脳内物質を確認
脳を覆うくも膜でつくられる睡眠物質「プロスタグランジンD2(PGD2)」が、自然な眠りを調節する「睡眠ホルモン」として働いていることを、早石修・大阪バイオサイエンス研究所理事長らのグループがラットの実験で確かめた。副作用の少ない睡眠薬や居眠り防止薬の開発につながる成果で、京都市で開催中の「国際生化学・分子生物学会議」で21日に発表した。
PGD2は脳脊髄(せきずい)液中に分泌される。早石さんらは82年、微量で強い睡眠作用を持つことをラットの実験で発見した。今回は脳内での働きをさらに詳しく調べた。PGD2が脳に働く量を減らすと、睡眠が抑制されることがわかった。(平成18年6月21日 朝日新聞)
アルツハイマー病に新ワクチン
東京都神経科学総合研究所などのチームは、アルツハイマー病の予防や治療に有効なワクチンを開発した。 副作用がないことを動物実験で確認した。1年半後にも臨床試験を始める。開発したのはDNA(デオキシリボ核酸)ワクチン。脳にたまってアルツハイマー病を起こすとされるベータアミロイドのDNAが入っている。 新ワクチンを注射すると細胞がアミロイドを作る。すると体の免疫機構が働きアミロイドの作用を抑えるたんぱく質(抗体)ができる。アルツハイマー病を発病するマウスで効果を調べた。生後3―4カ月で発病前のマウスと、同12カ月でアミロイドが脳にたまり始めて発病したマウスに注射。どちらも同18カ月の時点で脳のアミロイド量はワクチンを注射しなかったマウスの半分以下だった。過剰な免疫反応や髄膜脳炎などの副作用は起きず、研究チームは新ワクチンが予防や治療に有効とみている。(平成18年6月14日 日本経済新聞)
アルコール性肝硬変、コーヒー1杯で8割に減少
飲酒量が同じの場合は、コーヒーを多く飲む人ほどアルコール性の肝硬変になりにくいことが、米カリフォルニア州での大規模な疫学調査で確認された。調査を実施した研究者は、1日1杯のコーヒーで発症の危険性は8割に減るとしながらも、予防には「お酒の飲み過ぎを避けるのが先決」と、くぎも刺している。調査は、医療保険などを運営する「カイザー・パーマネンテ」研究部門のアーサー・クラツキー医師らが、保険加入者12万5580人を対象に実施。1978〜85年の時点で尋ねておいた各自の生活習慣と、その後の病気発症状況との関連を分析した。それによると、2001年までにアルコール性肝硬変を発症していたのは199人。 喫煙など他の要因が影響しないように配慮して分析を試みたところ、明確に浮かび上がったのがコーヒー効果。 飲まない人に比べ、1日に4杯以上飲む人の発症リスクは2割、1〜3杯の人でも6割にとどまった。(平成18年6月13 日読売新聞)
変形性膝関節症、50歳以上女性4分の3発症
膝の関節がすり減る変形性膝関節症の人の割合は、50歳以上の女性で75%に及ぶとみられることが、東京大「22世紀医療センター」の調査で示された。男性でも54%にのぼり、国内で計3000万人以上が患っていると推定できた。研究グループは今後、股関節なども含めた関節症の発症や進行のメカニズム解明を目指す。
同センター関節疾患総合研究講座の吉村典子・客員助教授らは昨春以降、東京都板橋区と和歌山県日高川町の住民約2200人に協力を得て、関節の状態をX線撮影で調べた。
その結果、50歳以上では女性の74.6%、男性の53.5%に関節の軟骨のすり減りなどが見つかり、変形性膝関節症と診断できた。50歳以上の国民に当てはめると、女性1840万人、男性1240万人が該当する計算になる。変形性膝関節症は、痛みがひどいと人工関節が必要になることもある。高齢者の生活の質を低下させる病気だが、発生率や有病率はこれまでよくわかっていなかった。グループは、今回調査した2カ所に別の地域も加えた計5000人について生活習慣などを調べ、発症とのかかわりをみていく。すでに発症した患者5000人も追跡し、症状の変化についても調べる。(平成18年6月12日 朝日新聞)
帝王切開20年で倍増
出産時に、帝王切開手術で赤ちゃんを取り上げられる割合が、約20年で倍増している。高齢出産が増えているほかにも、医師不足や医療ミスを避けようとする医師の心理など、社会的事情の変化が背景にある、との指摘もある。厚生労働省統計によると、分娩における帝王切開の割合は84年に7.3%だったが、90年には10.0%と年々高まり、02年には15%を突破した。産科医院と病院の別でみると、医院では11.8%なのに対し、病院は17.9%にのぼる。帝王切開は、難産や逆子、胎児の心拍が落ちた場合などに行われる。
リスクの高い高齢出産の増加が、帝王切開手術増加の背景にあるといわれる。妊婦が35歳以上の分娩は、90年には8.6%だったが、04年には15.2%まで上がった。だがほかにも、医師不足や医療過誤の回避、妊婦の意識変化といった社会的要因もあるとする専門家は少なくない。名古屋大付属病院とその関連病院計約40施設の年間1万5000〜1万9000件の分娩を調べると、91年に12%だった帝王切開手術は01年に20%、04年には24%に上昇していた。以前ならまず自然分娩を試みていた逆子のケースなどで、最初から手術予定を組む例が増えた。人手不足の中で、医療事故を避けたいという医師側の心理もある、とみる。 05年の最高裁統計によると、医療訴訟の約1割を産婦人科分野で占める。予定手術なら30分から1時間程度で、昔より安全性も高い。また妊婦側も「陣痛が怖い」「双子で不安」などと手術を希望する人が多くなっているという。「医師にとって、帝王切開は精神的にも、肉体的にも楽。少しでも分娩リスクがあって、妊婦が望めば、医師から『経膣(けいちつ)分娩でがんばってみましょう』とは言わなくなっています」と井上医師。
不必要な帝王切開が増えている、と感じているのは、母子愛育会総合母子保健センター愛育病院(東京都港区)の中林正雄院長も同じだ。勤務医らの激務が、安易な手術選択につながっている、とみる。
だが、安全になったとはいえ帝王切開は外科手術で、危険性もある。「そのリスクも知って欲しい」と中林院長。
母親らにも、安易な帝王切開を戒める声がある。千葉県習志野市の主婦、細田恭子さん(41)はインターネット上に帝王切開を経験した母親たちが話し合う掲示板を開設。自身も3人の娘を帝王切開で産んだ。術後3日は傷が痛んで歩けなかった。傷跡がケロイド状に残る恐れもある。精神的な負担もある。「楽をして産んだという偏見はまだ根強く、母乳をすぐに与えられなかったという罪悪感を抱く人もいる。最も幸せなはずの出産後に悩む母親が多いことを、医師は知って欲しい」。(平成18年6月10日 朝日新聞)
子宮頸がんに予防ワクチン
米食品医薬品局(FDA)は8日、米医薬品大手メルクが開発した世界初の子宮頸がん予防ワクチン「ガーダシル」の販売を承認した。対象は9〜26歳の女性で、半年間に3回、注射で接種する。FDAによると、子宮頸がんは世界で毎年、47万人が発症し、23万人が死亡している。臨床試験では極めて高い予防効果が確認できたといい、発症が大幅に減らせると期待されている。子宮頸がんのほとんどはヒトパピローマウイルス(HPV)に感染することで発症し、性交渉を通じて広まるとされる。ガーダシルは子宮頸がんの原因の70%を占めるHPV16型、同18型など計4種類のHPV感染について、がんにつながる病変の発症を防ぐ。
米国などでの約2万人対象の臨床試験で、ウイルスに感染していない女性に100%近い予防効果があることが確認され、申請後約半年の審査でスピード承認された。
しかし、ウイルス感染後に接種した場合には効果がみられなかった。このためFDAは、性的交渉が活発になる前の9歳からの使用を認めた。(平成18年6月10日 朝日新聞)
ニンジン煮て美肌、ベータカロチン摂取が「生」の1.6倍
ニンジンは、ゆでて食べると、色素「ベータカロチン」の体内への吸収率が高まることが、伊藤園中央研究所などの研究でわかった。ベータカロチンは紫外線から肌を守る効果があるとされ、これからの季節、有効な調理法といえそうだ。 研究グループでは、24〜41歳の男性8人を対象に、生のニンジンとゆでたニンジンをそれぞれ200グラム食べてもらい、ベータカロチンの血中濃度を調べた。その結果、ゆでたニンジンだと、生の場合に比べ摂取後6時間で平均1・4倍、8時間で1・6倍に達していた。また、ゆでたニンジンを基に作った野菜果汁を飲んで、肌の状態を調べた別の実験では、摂取後8週間で、13人の対象者全員のシミの面積が減少することが確認された。 提坂裕子・同研究所副所長は「ニンジンは、油で調理してもベータカロチンの吸収率は上がるが、油の取りすぎはいけない。ゆでて食べることを、積極的に考えてほしい」と話している。(平成18年6月9日 読売新聞)
胃がん、リンパ節広く取る手術と標準手術に差なし
進行胃がんの治療で、胃の周囲のリンパ節を広く切り取る「拡大手術」と、一定範囲の切除にとどめる標準的な手術(D2郭清)では、治療効果にほとんど差がないという結果を、日本の国立がんセンターがまとめた。報告した同センター中央病院の笹子三津留・副院長は「リンパ節を多くとったことで、患者の状態を悪化させている可能性もあるのではないか。標準治療はD2郭清と考えるべきだ」と話した。
同センター中央病院など全国の24医療機関が共同で調べた。がんの進行度(4段階)が2〜4の進行胃がん患者で、95〜01年に拡大手術をした260人と、D2郭清をした263人について、治療効果を比べた。その結果、3年生存率はともに76%。5年生存率は拡大手術が70%、標準的な手術は69%で、ほとんど差はなく、「延命上の利点はない」(笹子副院長)としている。
日本胃癌(がん)学会の治療ガイドラインは、進行度2〜3の患者については基本的に「胃の3分の2以上の切除とD2郭清」を標準治療とし、拡大手術の実施は、がんの転移が進んだ進行度4の患者などに限っている。(平成18年6月7日 朝日新聞)
骨粗しょう症薬、乳がん抑制にも効果
世界最先端のがん研究成果を報告する米臨床腫瘍学会で、米研究グループが、特定の骨粗しょう症治療薬が乳がん抑制にも効果を発揮したとの実験結果を発表した。年末までに乳がん抑制剤としても承認申請する方針を明らかにした。骨の代謝を促す体内のエストラゲンという物質は、不足すると骨粗しょう症にかかりやすいが、乳腺に対してはがん発生のリスクを高めるマイナス効果もある。閉経後の骨粗しょう症の女性に、治療薬として塩酸ラロキシフェンを投与すると、骨に対してエストラゲンの働きを高める一方で、乳腺への作用は抑制する効果もあることが分かった。発表した米研究グループによると、5年間投与した治験結果では、進行がんの抑制効果はがん専門薬とほぼ同等で、副作用の面でも大きな差はみられなかった。(平成18年6月6日 日本経済新聞)
ディーゼル排ガス、胎児に影響、自閉症発症の可能性
ディーゼル自動車の排ガスを妊娠中のマウスに吸わせると、生まれた子供の小脳にある神経細胞「プルキンエ細胞」が消失して少なくなることが、栃木臨床病理研究所と東京理科大のグループによる研究で分かった。自閉症では小脳にプルキンエ細胞の減少が見られるとの報告もある。ディーゼル排ガスが自閉症の発症につながる可能性を示す初めての研究として注目を集めそうだ。研究グループは、妊娠中のマウスに、大都市の重汚染地域の2倍の濃度に相当する1立方メートル当たり0.3ミリグラムの濃度のディーゼル排ガスを、1日12時間、約3週間浴びせた後に生まれた子マウスと、きれいな空気の下で生まれた子マウスの小脳をそれぞれ20匹ずつ調べた。その結果、細胞を自ら殺す「アポトーシス」と呼ばれる状態になったプルキンエ細胞の割合は、ディーゼル排ガスを浴びた親マウスから生まれた子マウスが57.5%だったのに対し、きれいな空気の下で生まれた子マウスは2.4%だった。また、雄は雌に比べ、この割合が高かった。人間の自閉症発症率は男性が女性より高い傾向がある。 さらに、プルキンエ細胞の数も、排ガスを浴びたマウスから生まれた子マウスに比べ、きれいな空気下で生まれた子マウスは約1.7倍と多かった。菅又昌雄・栃木臨床病理研究所長は「プルキンエ細胞の消失などは、精神神経疾患につながる可能性がある。 ヒトはマウスに比べ胎盤にある"フィルター"の数が少ないため、ディーゼル排ガスの影響を受けやすいと考えられる。現在、防御方法を研究中だ」と話している。橋本俊顕・鳴門教育大教授(小児神経学)の話:最近約10年間で先進国では自閉症が増えているとみられており、海外の研究報告では生まれる前の要因が強く疑われている。 その研究報告と今回の研究は一致しており、候補の一つを特定できた点で高く評価できる。 今後は、ディーゼル排ガスで動物に自閉症の行動特徴が起こるのか調べる必要がある。
「自閉症」
言葉の発達の遅れや対人関係を築きにくいなどの特徴がある一方、特定の分野で大変優れた能力を発揮する人がいる。脳の機能障害があるとされるが、はっきりした原因は分かっていない。典型的な自閉症は日本に約36万人、広汎性発達障害なども含めると約120万人いると推定されている。(平成18年6月4日 毎日新聞)
HIV感染最多
1日1.14人。東京都内でエイズがじわじわと増えている。 昨年1年間にエイズウイルス(HIV)に感染した人と、エイズを発症した患者の合計数は、過去最多の417人。15年前に比べて8倍に増えた。一方、感染の有無を調べる検査の受診者数は、伸び悩みぎみ。危機感を抱く都は、今年から始まった「検査普及週間」(1〜7日)に合わせ、啓発に力を入れる。
「感染者は、実際には報告数の4〜5倍はいる。エイズ患者が増え続けているのは先進国では日本だけ。爆発的な流行につながるおそれがある」
新宿駅南口にある都南新宿検査・相談室で、10年近く検査に携わる医師の山口剛氏(73)は指摘する。
都内で検査を受け、感染や発症が明らかになった人は年々増え続け、90年の51人から昨年は417人になった。すでに感染が分かっている人も加えると計3938人で、全国の感染者の累計約1万1000人の4割になる。
一方、検査そのものの受診者数は、社会問題化した92年に3万1千人以上だったのが、昨年は2万2千人。 休日に検査をしたり、即日で結果が分かる検査も実施したりするなど様々な工夫が奏功し、ここ数年、増加傾向にはある。 ただ、「手は尽くし、頭打ちになりつつある」と都の担当者は懸念する。
HIVの増殖を抑える薬物治療の進歩で、エイズは致死的な病気ではなくなった。それだけに早期発見が重要だが、山口氏は「安心してしまっているのか、関心は薄れている」と嘆く。
昨年、新たに感染が分かった人の9割は日本人男性。6割が外国人だった92年から状況は大きく変わった。感染源は同性間の性的接触が目立つ。
年齢別では20代、30代が72%を占め、HIV感染の危険性が高まるクラミジアなどの性感染症の若者が増えていることも懸念材料だ。一方、全国では昨年1年間にHIV感染832人、エイズ患者367人が新たに報告された。 合わせて過去最高の1199人となり、2年連続で千人の大台を超えた。(平成18年6月3日 朝日新聞)
BCGより1千倍効く結核新ワクチン
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター(堺市)と自治医科大のグループが、DNAワクチンと呼ばれる新しいタイプの結核ワクチンを開発、ネズミの実験で有効性を確認した。 単独接種でBCGの1000倍、BCGとの併用で1万倍の効果を示した。 BCGの効果が見込めない高齢者向けに特に期待される。
新ワクチンは、結核菌が持つ特定のたんぱく質と免疫力を高める働きのあるインターロイキンを作る遺伝子(DNA)を注射する。細胞内に取り込まれる工夫があり、強い免疫反応が誘導されるという。
大人のマウスに新ワクチンとBCGをそれぞれ接種した後、結核菌を感染させ、5週間後の結核菌の数を調べた。 新ワクチンを接種したマウスの菌数は、BCG接種のマウスの約1千分の1で、発症を抑えられる程度だった。 一方で、あらかじめBCGを接種してから新ワクチンを打つと、菌数は約1万分の1まで抑えられた。 今後、サルで効果を確かめ、臨床試験に移る準備をする。
日本では乳児期のBCG接種を推進しているが、予防効果は10年間程度しか続かず、大人への接種は効果が期待できない、とされている。 また、結核は感染しても若くて免疫力のあるうちは発病しないが、年をとって病気などで免疫力が下がると、休眠していた結核菌が活動を再開し、発病する場合が多い。
世界では毎年900万人が結核にかかり、200万人が死亡。 日本でも年間3万人の結核患者が報告され、約6割が60歳以上だ。(平成18年6月5日 朝日新聞)
ホヤにアルツハイマー予防効果
海に生息するホヤなどに含まれる脂質の「プラズマローゲン」がアルツハイマー病を防ぐ効果を持つ可能性が高いことが、東北大大学院農学研究科の宮沢陽夫教授(食品学)らの研究でわかった。 動物実験で証明できたことから、来年にも錠剤の健康食品として発売する。 ひどい物忘れなどを引き起こすアルツハイマー病は、脳の神経細胞が死ぬことが原因と考えられている。これまで、患者の脳内ではプラズマローゲンが通常より3割程度減少していることがわかっていたが、その働きは明らかにされていなかった。 宮沢教授らは、細胞の培養実験の結果、プラズマローゲンに神経細胞死を防ぐ効果があることを突き止めた。 さらにアルツハイマー病を発症させたラットにプラズマローゲンを食べさせ、迷路を経て餌にたどり着かせる実験をしたところ、記憶・学習能力の低下を防ぐことができた。 プラズマローゲンは牛の脳にも含まれるが、BSE(牛海綿状脳症)感染の恐れがある。そこで手に入りやすい海産物を調べ、ホヤやカキ、ウニなどに含まれていることを発見。 とりわけ、ホヤの場合は廃棄する内臓への含有率が約0・1%と高く、有効活用できるという。 宮沢教授らは昨年8月、ベンチャー企業を設立。ホヤからプラズマローゲンを抽出する方法も開発している。 また、4〜5年をかけて患者への効果を確かめ、医薬品などの開発に結びつけたいとしている。 宮沢教授は「ホヤは宮城、岩手両県の三陸沿岸が産地。 先進各国では高齢化が進んでおり、日本だけでなく世界で需要が高まれば、東北の新しい産業に結びつく可能性がある」と話している。(平成18年6月1日 読売新聞)
精子の数、日本最下位
日本人男性の精子数は、フィンランドの男性の精子数の約3分の2しかないなど、調査した欧州4か国・地域よりも少ないことが、日欧の国際共同研究でわかり、英専門誌と日本医師会誌5月号に発表した。 環境ホルモンが生殖能力にどう影響するか調べるのが目的。 精巣がんが増えているデンマークの研究者が提唱し、日本から聖マリアンナ医大の岩本晃明教授(泌尿器科)らが参加した。 神奈川県内の病院を訪れた、20〜44歳の日本人男性324人(平均年齢32.5歳)の精液を採取した。年齢などの条件は各国でそろえ、禁欲期間の長さの違いによる影響が出ないよう補正して、各国男性の精子数を統計的に比較した。 日本人男性は他国の男性よりも禁欲期間が長く、日本人の精子数を100とすると、フィンランドが147、スコットランド128、フランス110、デンマーク104で、日本が最低だった。 ただ、環境ホルモンの関与が疑われる精巣がんや生殖器の異常の発生率は、日本人男性では非常に低く、研究チームは「精子数の違いは栄養や生活習慣、人種差などが関係しているのではないか」としている。(平成18年5月31日 読売新聞)
認知症予防に「運動・栄養・昼寝」
よく運動し、栄養に気をつけて、昼寝した方が認知症の発症率が下がることが、厚生労働省の研究班(主任研究者=朝田隆・筑波大教授)の研究でわかった。 生活習慣の改善による認知症予防の成果が確認されたのは初めてで、注目される。 研究は、茨城県利根町の65歳以上を対象に2001年から2005年にかけて行われた。 希望者約400人に運動や栄養、睡眠の改善を指導し、指導しなかった 1500人と比較した。 具体的には、週3〜5回、1回20〜60分、音楽に合わせてステップを踏む簡単な有酸素運動を行った。 また魚の脂質に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)などを含む栄養補助剤を毎日取るとともに、30分以内の昼寝をした。 その結果、生活習慣を指導したグループでは認知症の発症率が3・1%だったのに対し、しなかったグループは4・3%にのぼった。また、記憶能力のテストでも、指導したグループの成績が約16%向上した。 今後さらに統計的分析を進める。 認知症予防については、海外でさまざまな研究がなされており、魚を食べたり運動をしたりすることなどが望ましいとされてきた。 しかし、生活習慣改善を行う「介入研究」ではなく、生活習慣を観察し、数年にわたって認知症の発症率などを見る「観察研究」が主だった。(平成18年5月27日 読売新聞)
メタボリックシンドローム、「腹囲」健診で測定
平成20年度から40歳以上の人が受ける新しい健康診断の検査項目と判定基準が26日、固まった。内臓脂肪の蓄積に高血圧や高脂血、高血糖が重なり生活習慣病の危険性が高まる「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」の考え方を導入したのが特徴で、これまで実施していなかった腹囲(へそ回り)の測定を必須とする。 健診の結果「要治療」とならなくても、生活習慣病の「危険度」に応じて受診者を3つのレベルに分類。 生活習慣の改善などをきめ細かく指導する仕組みを取り入れる。 新しい健康診断は、厚生労働省が20年度から、健康保険の運営者に対して、40歳以上の加入者への実施を義務付けるもの。 検査項目や判定基準は26日、有識者でつくる検討会に示され、基本的に了承された。 検査項目には従来と同様の身長や体重、血圧などに加え、腹囲や尿酸の測定を追加した。 これらは「基本健診」として受診者全員に実施。 一方で尿検査や心電図検査などは「精密健診」として医師が必要と判断した場合に実施することにした。 内臓脂肪症候群は、腹囲が「男性85センチ、女性90センチ以上」で、さらに高血糖、高脂血、高血圧のうち2つ以上に当てはまる場合。それぞれが定められた数値以上に悪ければ治療のため医療機関の受診を勧めるが、数値が低くても内臓脂肪症候群の該当者や、生活習慣病の危険度が高いと判断した人は「積極的支援レベル」と判定し、3―6カ月間、生活改善や禁煙、運動などの保健指導をする。 それに次ぐ危険度の人は「動機づけ支援」として生活改善などの指導を1回実施し、それ以外の受診者には生活習慣病に関する情報を提供する。 厚労省は今秋以降いくつかの都道府県で準備事業を開始、20年4月から本格導入する予定だ。(平成18年6月27日 産経新聞)
抗がん剤、病巣だけ治療 大阪府立大が微小カプセル開発
がんができた部位を体外から温めることで、病巣だけに抗がん剤を働かせることができる微小カプセルを、大阪府立大の河野健司教授(生体高分子化学)らの研究グループが開発した。 抗がん剤が正常な組織も傷つけてしまう副作用を減らすことができるという。 24日から名古屋市で開かれる高分子学会で発表する。 カプセルは直径100ナノメートル(ナノは10億分の1)で、生体内にもあるリン脂質とコレステロールでできている。 温度に反応しやすい高分子を表面に組み込み、40度以上になるとカプセルが壊れるようにした。 がんができた部位の毛細血管は、正常な部位の血管に比べ、血液中の物質が血管の外に漏れ出しやすい性質がある。 このため、体内に入った微小カプセルは、毛細血管から漏れ出てがん細胞の周辺にだけたまる。 がんを外から温めてやると、カプセルが壊れて抗がん剤が放出される仕組みだ。 河野教授らは、後ろ足にがん組織を移植したマウスで効果を調べた。 カプセルの投与から12時間後に、高周波加温機で体外からがんを45度で10分間温めたところ、8日たってもがんはほとんど成長しなかった。 一方、温めなかったりカプセルを投与しなかったマウスでは、がん組織の体積は5倍以上になった。 河野教授は「医療の分野と連携し、がん組織だけを攻撃する治療の実現を目指したい」としている。(平成18年5月22日 毎日新聞)
MRSAに効く新抗生物質を発見
院内感染の原因となる細菌の中でも最も恐れられているメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)やバンコマイシン耐性腸球菌(VRE)などを殺す強力な抗生物質を発見したと、米製薬大手メルクの研究チームが、18日付の英科学誌ネイチャーに発表した。
研究チームは、25万種に及ぶ天然物質の抽出物の殺菌力を調べ、南アフリカの土壌から採取した放線菌が作る低分子化合物が強い殺菌力を持つことを突き止め、プラテシマイシンと名づけた。 MRSAに感染したマウスで試したところ、効果が確認でき、副作用もなかったほか、VRE、肺炎球菌などに対しても強い殺菌作用を示した。 さらに、この物質が働く仕組みを調べたところ、細胞の脂質合成にかかわる酵素を阻害することが判明。既存の抗生物質と仕組みが似ていると、耐性菌が出現しやすいが、この物質のように、脂質合成を阻害する抗生物質は例がないという。 薬剤耐性菌に詳しい国立感染症研究所細菌第2部の荒川宜親部長は「MRSAなどに有効な抗菌薬は少なく、治療は手詰まり状態で新薬が期待されていた。 この抗生物質は、全く新しい仕組みらしく画期的だ。 毒性も低く、臨床的にも期待できる」と話している。(平成18年5月18日 読売新聞)
関節リウマチ薬とがん
関節リウマチの治療で高い効果が知られる「生物学的製剤」が、悪性リンパ腫など、がんのリスクを高める可能性が指摘されていることから、日本リウマチ学会は長期の安全性調査に取り組むことを決めた。 これらの薬をめぐっては17日、がんのリスクが約3倍高まるという米英グループの新たな報告が米医師会雑誌に掲載された。
関節リウマチは免疫細胞が信号物質を過剰に出すことで、全身の関節の痛みや骨の破壊を招く。 「TNF」という信号物質の働きをじゃまする生物学的製剤は、国内では2剤が販売され、2万人ほどが使っている。
約9割の患者で効果がみられる一方、免疫力にかかわるTNFを抑えることで、感染症やがんになる確率が高まることも心配されている。 「関節リウマチ自体ががんのリスク要因」との報告もあり、結論は出ていない。
学会調査の中心になる宮坂信之・東京医科歯科大教授は「海外とは薬の用量も異なり、米英の報告をそのまま国内にあてはめることはできない。 やはり日本人でのデータが必要だ」と話す。(平成18年5月18日 朝日新聞)
赤ちゃんのアレルギー性鼻炎、親の喫煙でリスク3倍
煙の漂う室内で育った赤ちゃんは、親がアレルギー体質だった場合、1歳までにアレルギー性鼻炎を発症する割合が3倍に増えることが、米シンシナティ大(オハイオ州)の研究で分かった。 同大のG・レマスターズ教授らが、欧州の専門誌「小児アレルギー・免疫学」電子版に17日発表した。 調査の対象としたのは、親がアレルギー体質の乳児633人。 喫煙状況も含めて各家庭の室内環境などを調べ、 1歳までに表れた呼吸器系症状との関連を分析した。 その結果、室内での1日の喫煙本数が20本以上という家庭の乳児は、家族が全くたばこを吸わない家庭の乳児に比べて鼻炎の発症が倍増、特にアレルギー性鼻炎の発症は3倍に上った。 なお、今回の調査では、兄や姉が多いほど、鼻炎の発症が減る傾向がみられたという。これまでも、細菌などに感染する機会が増えると、アレルギーを抑える免疫細胞が活発になるという説が唱えられてきたが、「兄や姉の効果を0歳児で確認したのは初めて」としている。(平成18年5月18日 読売新聞)
乳がん手術後の乳房を再建
九州中央病院(福岡市)は12日、乳がん手術後に乳房を再建する新手法の臨床研究を始めると発表した。患者自身の脂肪を採取し、一部含まれる脂肪などに成長する未熟な細胞を濃縮してから移植する方法で体に定着しやすくする。 従来は背中の筋肉などを使っていたが、脂肪は採取しやすく、患者の肉体的な負担を軽減できるとみている。
(平成18年5月13日 日本経済新聞)
心臓ペースメーカー、X線撮影でも誤作動の恐れ
胸部X線撮影など比較的被曝線量が少ない場合でも心臓ペースメーカーに不要な電流が流れ、誤作動を起こす恐れがあると、大阪市であった12日の日本医科器械学会で発表された。 被曝線量の多いCT(コンピューター断層撮影)では特定のペースメーカーが誤作動を起こすため、厚生労働省が昨年から指導を始めていた。広瀬稔・北里大助教授(臨床工学)らが、3機種のペースメーカーに胸部撮影などに使っているX線を当てて影響を調べた。 その結果、内部回路にX線が当たると、不要な電流が発生。 それが心臓からの信号と誤認され、誤作動になる場合があると分かったという。
X線を当てる方向や強さによって誤作動は、起きたり起きなかったりした。 実験に使った3機種のうち、1機種は誤作動を起こさなかった。
広瀬さんは「医療現場や健康診断でも、鉛でペースメーカーを守ったり、深刻な誤作動に備えたりすることを考えてほしい」とリスクを減らす努力が必要だとしている。
ペースメーカー使用者は国内に約30万人いるとされる。製造会社などでつくるペースメーカ協議会は「通常のX線撮影で影響が出た実例は聞いていないが、必要があれば業界として対応したい」と話している。
厚労省は昨年5月、CTでX線を当てないように製品に表示するようにメーカーを指導。 その後、医療機関には、ペースメーカーを使う患者にCTで5秒以上のX線照射をしないように呼びかけていた。(平成18年5月13日 朝日新聞)
抗体併用で"大型がん"消滅
免疫の働きを強める3種類のたんぱく質を組み合わせた「カクテル免疫療法」で、大型の固形がんを高率で消滅させることに、順天堂大医学部の奥村康教授(免疫学)らのチームが成功した。 マウスの実験だが、人間への応用も期待できる成果で、8日付の専門誌「ネイチャー・メディシン」電子版に発表する。 奥村教授らは、がん細胞に結合すると、これを自滅させる「アンチDR5抗体」と呼ばれるたんぱく質を人工的に作成した。 ただ、この抗体は一部のがん細胞にしか結合できないため、単独では効果が小さい。 このため、体内にもともとある免疫細胞が、がん細胞を見つけやすくする「アンチCD40抗体」と、免疫細胞の攻撃能力を高める「アンチCD137抗体」を併用したところ、強力な抗がん作用を発揮させることが分かった。 マウスを使った実験では、5ミリ・メートル角の乳がんや腎臓がんが、10匹中7匹で消滅した。人間だと、握り拳大のがんが消滅したことに匹敵するという。 奥村教授は「がん細胞を移植したマウスを治療したのでなく、『自家がん』と呼ばれる自然に近いがんを消滅させた点で、意義は大きい。 これらの抗体の作用は人間でも同じと考えられるため有望だ」と話している。(平成18年5月8日 読売新聞)
骨粗しょう症を抑える作用発見
九つのアミノ酸が結合した「W9ペプチド」という炎症抑制作用を持つ物質が、骨粗しょう症などの際に骨が減少する作用も抑えることを、東京医科歯科大の青木和広助手(硬組織薬理学)らが発見した。
骨粗しょう症だけでなく、炎症から骨の破壊を招く関節リウマチや歯周病の治療薬への応用も期待される。生物の骨では常に形成と破壊が繰り返されている。
健康なときはこのバランスがとれているが、カルシウム不足などになると破壊が進む。 青木助手らは、W9ペプチドが骨を破壊する細胞ができるときに必要な分子と結合して、破壊細胞の生成を抑えることを発見。
さらに普通の餌を与えたマウスと、カルシウム量を10分の1にしたマウスで実験した。
10分の1マウスのすねの断面積中に骨の占める割合は2日後、4.4%で、正常マウス(9.7%)の約半分までに減少した。
一方、10分の1マウスのうちW9ペプチドを投与したマウスは10.3%で、正常マウスとほぼ同じ状態を保った。
W9ペプチドを大量に投与しても肝臓、腎臓の異常は認められなかったという。 青木助手は「炎症と骨減少を抑える二つの働きを同時に持つ、副作用の少ない関節リウマチなどの薬剤の開発につながる」と話している。(平成18年5月5日 毎日新聞)
軟骨の病的な骨化を抑制 マウスの特定タンパク質
軟骨が骨になる「骨化」を促すタンパク質カーミネリンの働きを抑えると、変形性関節症による軟骨の病的な骨化を抑制できるとするマウスでの実験結果を、東京大医学部の川口浩・助教授らのグループが8日、米医学誌ネイチャー・メディシン(電子版)に発表した。正常な骨化には影響しないという。 軟骨の骨化は、骨の成長や骨折の治癒の際に起きる正常な現象。 関節の軟骨が変性する変形性関節症の患者では、関節の周りで病的な骨化が起きて痛み、まひの原因となり、高齢者で大きな問題となっている。 カーミネリンや同様の物質が人で見つかれば、治療法開発につながる可能性がある。(平成18年5月8日 中国新聞)
人工関節向け新素材を開発
千葉大学は人工関節向け新素材を開発した。セラミックスと金属を複合した材料で、通常の金属に比べて100倍以上摩耗しにくく、セラミックスに比べても割れにくい。細胞への毒性がないことも確かめた。 材料の物性を調べた段階だが、今後、実際に人工骨の構造を作製し、長期間使用しても問題ないかどうか調べていく。
人工関節にはチタンなどの合金やセラミックス、プラスチックなどを組み合わせて使う。人工股関節の場合は、骨盤側に超高分子量ポリエチレンというプラスチック、大腿骨側にコバルトクロム合金やセラミックスが使われることが多い。プラスチックや合金は関節面の動きによって摩耗し、摩耗で出た粉末が炎症を起こして人工関節の土台となる周囲の骨が破壊される問題があった。 また、セラミックスは割れることもある。人工関節がゆるんだり、割れたりすると再手術が必要で、患者への負担が大きかった。(平成18年5月8日 産経新聞)
がんワクチン臨床研究
大阪大グループが進める「WT1がんワクチン」の臨床研究が、年内にも全国20医療機関に広がる見通しになった。 がんワクチンでは過去最大規模だ。 肺がんや脳腫瘍(しゅよう)などを対象にした安全性試験で、現在まで目立った副作用がなく、がん縮小などの効果が見られているためで、今後効果が確認されれば、実用化に向け大きく前進する。
WT1は、細胞増殖にかかわり、様々な種類のがん細胞に多く現れるたんぱく質。 杉山治夫・大阪大教授(機能診断科学)らのグループはWT1の特定の断片(ペプチド)が、免疫反応の目印になることを発見。 がん細胞にWT1が見つかった患者であれば、人工的に合成したこのペプチドを注射することで、患者の免疫系にがん細胞を攻撃させることができると考えた。
大阪大病院で01〜04年に、主に安全性確認の目的で実施した20人(白血病10人、乳がん2人、肺がん8人)では、3人でがん組織が小さくなったり、進行が止まったりしたほか、9人でがん細胞の指標とされる腫瘍マーカーの値が下がった。
その後、対象のがんを拡大。 04年に始めた脳腫瘍でもがん組織が小さくなったり、進行が止まったりする例が確認された。 白血病の一部で白血球や血小板が減る症状が認められたが、それ以外に目立った副作用は確認されていない。
拡大臨床研究には東北から九州までの20医療機関が参加予定で、大阪大病院、高知大病院、愛媛大病院、広島赤十字原爆病院、大阪府立母子保健総合医療センターではすでに始めている。(平成18年5月3日 朝日新聞)
がん医療の中核拠点、都道府県ごとに指定
厚生労働省は今夏をめどに、がん診療の中核となる医療機関を各都道府県ごとに指定する。各地域にあるがん医療機関の医師や看護師の研修拠点にするほか、診療データの分析・評価機能を持たせる。昨年から始まったがん医療の「第3次対がん10か年総合戦略」に基づいて実施するもので、指針を満たす医療機関を厚生労働省が指定する。がん医療の地域間格差を解消し、患者が全国どこでも質の高い医療サービスを受けられるようにするのが狙い。厚生労働省は「がん診療連携拠点病院の整備指針」を改定。これまで、各都道府県の主要都市などを中心にがん医療拠点の整備を進めてきたが、新指針は都道府県単位でより高度ながん診療の拠点を置くことにした。指定を受けた医療機関は各都道府県内のがん医療機関のとりまとめ役となり、他の医療機関からの患者の病状相談にも応じる。データ分析などを手掛ける専門組織も設置する。(平成18年2月2日)
パーキンソン病遺伝子治療
自治医大病院は、運動障害を伴う難病パーキンソン病に対する国内初の遺伝子治療臨床研究を厚生労働省に申請した。パーキンソン病は、脳内の物質ドーパミンが不足して引き起こされる難病。脳内でドーパミンに変化する薬剤を内服する治療が有効だが、症状の進行に伴い、薬をドーパミンに変える体内の酵素が減少し、その効果が、薄れるという事態が避けられなかった。申請した治療法は、この酵素を作る遺伝子を特殊なウイルスに組み込み、脳に注入するというもの。(平成18年2月2日 読売新聞)
大豆イソフラボン、妊婦さん取り過ぎ注意
骨粗鬆症やがんの予防効果があるなどとして人気のある「大豆イソフラボン」について、食品安全委員会の専門調査会は、過剰摂取に注意を促す報告書案をまとめた。ホルモンのバランスを崩す恐れがあるとして、通常の食生活に加え特定保健用食品などで1日に追加的にとる安全な上限量を30ミリグラムとした。特に、妊婦や乳幼児に対しては「追加摂取は推奨できない」としている。専門調査会は、02年の国民栄養調査などから、大豆イソフラボンの摂取量は、国民の95%が70ミリグラム以下であり、健康被害が出ていないことなどから安全な摂取量の上限を1日70〜75ミリグラムとした。さらに通常の食生活をしている女性を対象に、イソフラボンの錠剤などを飲んでもらい内分泌系への影響をみた調査から、男女ともに1日30ミリグラムを追加で取れる上限値とした。
30ミリグラム以上含まれている健康食品のドリンク剤や錠剤もあることから、これらを取る際の注意にもなっている。
ただ妊婦や胎児、乳幼児などに対しては、「追加摂取する場合の安全性は科学的に判断できない」とし、通常の食事以外からの摂取は勧めないとした。(平成18年2月1日 朝日新聞)
カプセル内視鏡画像
カプセル内視鏡をのみ込んで撮影した胃や十二指腸、小腸、大腸など消化管の画像を短時間で再生、診断する方法を八木康史大阪大教授(視覚情報処理学)らが開発した。カプセルが滞留しているときは高速、一気に動いた場合は低速で再生し、無駄な時間を省くと同時に見落としをなくすことができるという。八木教授によると、カプセル内視鏡は約8時間かけて体内で1秒間に2枚ずつ、計約6万枚の画像を撮影し、体外に排出される。現在、診断する医師は画像の早送りと巻き戻しを繰り返し、約2時間かけて、がんやかいようなど異常がないかを判断している。(平成18年1月31日 中国新聞)
新型インフルエンザ対策
新型インフルエンザ出現に備えて、国立感染症研究所と国内のワクチンメーカー4社は、人に感染した鳥インフルエンザウイルス(H5N1)をもとにしたワクチンの臨床試験を月内にも始める。新型インフルエンザが発生してからでないと、新型ウイルスをもとにしたワクチンは製造できない。感染研では、鳥インフルエンザワクチンでも、効果はある程度期待できるとみており、国の新型インフルエンザ対策の行動計画に基づいて、緊急時には医療関係者などに優先的に接種できるよう備蓄を進める。順調に進めば、来年、国の製造承認が出る。ワクチンの製造設備は、通常のインフルエンザワクチンを生産する4月〜9月は使えないため、メーカーは承認に先行して、秋から備蓄用ワクチンの製造準備に入る。インフルエンザウイルスは変異しやすいため、備蓄用ワクチンのウイルスは、臨床試験で使うベトナムのウイルスと型は同じH5N1でも、より新しいインドネシアのウイルスを使う予定だ。新型インフルエンザ用ワクチンは、新型が出現してから接種できるまでに1年はかかるとされ、流行の第1波には間に合わず、第2波以降の対策に使われる。(平成18年1月29日 読売新聞)
子どもの救急
夜間や休日の診療時間外に病院で受診するかどうかの判断の参考になる「こどもの救急」というホームページを、日本小児科学会が開設した。小児医療を担ってきた同学会の「公式」サイトとして、最新の知見を更新するなど内容の充実を図る予定で、小さい子どもを持つ家族の強い味方になりそうだ。生後1カ月から6歳までが対象。発熱、けいれん・ふるえ、吐き気、下痢、誤飲など19の「気になる症状」から選択し、どんな状況かあてはまる項目をチェックすると、救急車をすぐに呼ぶべきか、タクシーなどで病院に行くべきか、準備するものや医師に伝えるべき項目、注意事項などが示される。家で様子を見る場合も、看護のポイントや控えるべき薬剤などがわかる。
例えば、「誤飲」は吐かせてはいけない場合や牛乳を飲ませてはいけない場合があり、対応の仕方を細かく示した。病気ごとの皮膚のブツブツの様子や、健康な便の見分け方なども写真でわかりやすい。小児救急の現場では過酷な労働環境が指摘されている。厚生労働省研究班の調査(04年)では、時間外受診が増えているが、28%が受診不要だった。同学会理事の中澤誠・東京女子医大教授は「急いで病院に行くべきか迷う時に、家族が判断をする上での目安にしていただきたい。緊急時は混乱する場合もあるので、ふだんも見ていただければ」と話す。(平成18年1月30日 朝日新聞)
鳥インフルエンザワクチン開発
アジアや欧州で猛威をふるっている鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)がニワトリやマウスに感染するのを100%阻止する新型ワクチンを米ピッツバーグ大の研究グループが開発した。 今後は人間でも有効かどうかを臨床試験で確かめる方針だ。ピッツバーグ大学医学部のアンドレア・ガンボット助教授らは、鳥インフルエンザウイルスの表面を覆うたんぱく質の遺伝子を風邪の原因ウイルスであるアデノウイルスの遺伝子に人工的に組み込むことに成功した。
こうして作った改造ウイルスは動物や人間の体内に入っても増殖する力はない。 しかし体内の免疫細胞はウイルス表面に現れた鳥インフルエンザたんぱく質を認識して、これを攻撃する抗体を作ることが可能になる。 つまり改造ウイルスがワクチンとしての役割を果たすことになる。 ニワトリやマウスでの動物実験では、ウイルスの感染をほぼ100%食い止めたという。(平成18年1月28日 日本経済新聞)
インスリン投与、初の吸入型
ファイザー製薬は糖尿病の治療に使う世界初の吸入型インスリンを米食品医薬品局(FDA)から承認された。 これまでインスリンは注射器などで体内に注入する以外なく、患者の苦痛を伴う難点があった。吸入型は今後、治療の主流になるとみられ大型新薬に成長するとの見方も出ている。吸入型のインスリン「エクスベラ」は粉末状で、専用の吸入器を使い肺に送り込む。今年半ばにも使用可能になる見込み。FDAは当初、肺機能に与える影響を懸念したが、試験結果から機能低下は限定的と判断した。ただ、ぜんそく患者や喫煙者は使用すべきではないとしている。米には糖尿病患者が2000万人近くいるとみられ、各医薬品メーカーが吸入型インスリンの開発を競っている。ファイザーは欧州でも26日に承認を得た。(平成18年1月28日 日本経済新聞)
HIV感染者・患者、2年連続で1000人突破
2005年の1年間に新たに報告されたエイズウイルス(HIV)の感染者、発症した患者の合計は1124人で、2年連続で1000人台となったことが厚生労働省の集計(速報値)でわかった。4月に発表される05年の確定値は速報値よりも増えるとみられ、過去最多だった04年(1165人)とほぼ並ぶ見通し。同省は「同性愛者や青少年に対する予防啓発活動をさらに進める必要がある」としている。
05年の感染者数の速報値は778人で、過去最高だった04年の確定値(780人)を更新するのは確実とみられる。発症した患者数の速報値は346人。 04年の確定値(385人)よりも39人少なく、発症患者数は1998年以来7年ぶりに減少に転じる可能性があるという。(平成18年1月28日 日本経済新聞)
花粉、平年の3〜8割
環境省は25日、今春のスギ、ヒノキの花粉の飛散量が「平年の3〜8割程度にとどまる」とする花粉総飛散量予測の確定版を発表した。 昨年7月の気温や日照時間が平年を下回った影響で花芽の数が少なかったためで、観測史上最大の飛散となった昨年に比べると、飛散量は1〜4割程度。 スギの開花は平年より数日程度遅れる見通し。 地域別の飛散量では、「北海道が平年並み、東北は平年と比べて6割、関東甲信越で同3割、北陸・東海が同8割、近畿・中国・四国・九州で同4〜6割程度」と予想している。(平成18年1月26日 読売新聞)
新型インフルに備え、ウイルス1600種公開
新型インフルエンザの発生に備え、理化学研究所は約1600種のインフルエンザウイルスのデータベースを作り、インターネットで公開した。ウイルス増殖に必要なたんぱく質の立体構造を解析したもので、その形から鍵穴をふさぐカギのような化合物が見つかれば、新薬開発につながる。理研は「国内外の製薬会社、研究者に使ってもらい、治療薬の開発を促したい」という。たんぱく質の立体構造は、米国立保健研究所(NIH)に登録されているインフルエンザウイルスの情報をもとにコンピューターで予測、解析した。05年にベトナムで死者が出たH5N1型の鳥インフルエンザウイルスや過去の人インフルエンザウイルス、その変異体などが含まれている。理研の横山茂之さんは「タミフルなど既存の治療薬が効かないウイルスも出ており、ほかの治療薬の開発を急ぐ必要がある」という。(平成18年1月21日 朝日新聞)
花粉飛散、昨年の2割
日本気象協会は19日、今春の花粉飛散予報を発表した。スギ、ヒノキの花粉飛散量は、平年より少なく、大量だった昨年の2割前後のところが多い見込み。飛散の開始も平年並みか、遅くなりそう。一方、北海道のシラカバの花粉飛散量は平年並みか、やや多い。環境省も昨年12月、今春のスギ、ヒノキの花粉飛散量について、平年並みか、その半分程度になるとの予測を発表している。(平成18年1月20日 読売新聞)
神経結合の目印を発見 再生治療に貢献も
複雑な脳の神経回路の中で、神経細胞同士がお互いを見つけ出して結合する際に目印となるタンパク質を、東京大や理化学研究所発生・再生科学総合研究センターなどのチームがショウジョウバエを使った実験で発見、19日付の米科学誌ニューロンに発表した。チームの能瀬聡直東大助教授は「目印を使って脳の神経回路を形成する仕組みは人間を含めて共通と考えられる。将来的には損傷した神経を再生治療する方法の開発に役立つかもしれない」としている。神経回路は、発生の過程で、神経細胞が決まった道筋に沿って正しい相手と結合して形成されるが、多数の細胞が密集している脳では、神経細胞がどのように特定の相手を探し出すかが、分かっていなかった。(平成18年1月19日 中国新聞)
カレー粉成分に前立腺がん抑制作用
米ニュージャージー州立大学の研究グループは、カレー粉に含まれるターメリックと、カリフラワーなどの野菜に含まれるPEITCという化合物に前立腺がんの増殖を抑える作用があることを発見した。動物実験で確認した。前立腺がんは全米の男性のがん死亡者数の2位を占める。放射線治療や化学療法と同時にターメリックやPEITCを摂取すれば、がん治療成績が上がるのではないかとみている。
米国に比べ、ターメリックや野菜の摂取量が多いインドで前立腺がん患者が少ないことに着目した。人の前立腺がんの細胞を移植したマウスにターメリックとPEITCを注射したところ、がん細胞の増殖を抑える効果があったという。(平成18年1月18日 日経産業新聞)
心臓病予防、やはり魚に効果
魚を多く食べる人はあまり食べない人に比べて心筋梗塞になるリスクが6割前後低いことが、約4万人を対象にした厚生労働省研究班の調査で分かった。魚の心臓病予防効果は欧米の研究などで指摘されてきたが、日本人で大きな効果があることが大規模調査によって初めて裏付けられた。17日付の米医学誌サーキュレーションに発表される。研究をまとめたのは磯博康・大阪大教授(公衆衛生学)ら。岩手、秋田、長野、沖縄の4県で成人住民約4万人の協力を得て、食事アンケートをし、90年以降11年間の発症を追跡調査した。
心筋梗塞や狭心症といった虚血性心疾患になるリスクは、魚を食べる量が最も少ない人たち(1日20グラム程度)に比べて、最も多い人たち(1日180グラム程度)は37%低かった。 診断確実な心筋梗塞に限れば、56%も下回った。
魚に心臓病予防効果があるのは、油成分のエイコサペンタエン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA)が血栓を作りにくくし、動脈硬化を防ぐ働きがあるためとされている。 EPAやDHAはイワシやサバなどの青魚に多い。たとえば、マイワシ100グラムに含まれるEPAとDHAは計2.5グラム程度だ。
食べた魚の種類からEPAとDHAの合計摂取量を計算したところ、摂取量が最も少ない人たち(1日0.3グラム程度)に比べ、最も多い人たち(1日2.1グラム程度)は虚血性心疾患のリスクが42%、診断確実な心筋梗塞で65%低く、効果がはっきり出た。
磯教授は「日本人でも魚をよく食べる人のリスク低下がはっきりした」と話している。(平成18年1月17日 朝日新聞)
医療費一定の「包括払い」、対象病院を大幅増加へ
政府は16日、医療費の支払いを病気や治療法により一定額とする「包括払い」方式の対象病院を2006年度から大幅に増加させる方針を固めた。既に導入している大学病院など82病院に加え、試行中の62病院も対象とするほか、新たに協力を得られる病院を積極的に募る。将来は全病院への導入も視野に入れている。現在は原則、治療、投薬を行った分だけ医療費を払う「出来高払い」方式が採用されており、「検査漬け、投薬漬け」医療につながっているとの指摘がある。包括払い方式では、投薬や検査回数が増えても医療費は一定額しか払われない。厚生労働省は、この方式が増えれば病院運営が改善され医療給付費の抑制につながると期待している。厚労省は03年度、包括払い方式を全国約9000病院の約1%の82施設で導入。04年度からは、検証データを提供できる62病院でも試行している。ただ、包括払い方式は、必要な治療をしなくても支払額が同じなため、「手抜き、過少医療につながる」との批判が日本医師会などにある。昨年末の厚労省調査では、包括払い方式での患者の平均在院日数は02年の20・37日から05年の17・56日に短縮された。一方で、同じ病気での再入院者が2・54%から4・26%へ増える弊害も見られた。(平成18年1月17日 読売新聞)
薬剤耐性、インフルエンザ治療薬2種を使用中止
米疾病対策センター(CDC)は14日、現在米国で流行中のインフルエンザ(H3N2型)に対し、2種の治療薬「アマンタジン」「リマンタジン」がほとんど無効と分かったとして、医師らに処方しないよう呼び掛けた。CDCによると、検査したウイルスの91%が二つの薬に耐性を示した。両薬への耐性ウイルスの割合は前年の11%から急増したという。日本で広く使われている「タミフル」や、「リレンザ」は有効だとしている。アマンタジンは比較的安価なことから発展途上国などで多く使われており、日本でも承認されている。(平成18年1月16日 毎日新聞)
がんセンターに「対策情報センター」設置へ
厚生労働省は今秋、国立がんセンター(東京都中央区)に「がん対策情報センター」を設置、全国135カ所の「地域がん診療拠点病院」とネットワークで結ぶ体制を整える。患者や家族、地域の医療機関にがんに関する情報提供を行うのが目的。がん治療は専門性が高く、地域間の医療技術格差が問題になっているが、情報の共有によって格差の是正を目指す。同省は06年度予算案にシステム整備費など15億3000万円を計上。拠点病院に順次、患者や家族の相談窓口となる「相談支援センター」を新設するほか、拠点病院を最終的には360カ所に増やす方針だ。情報センターは相談支援センターで、がん治療に関する指針や医療機関の治療成績などの情報を提供。国立がんセンターの専門医が、ネットワークを通じて送られてくる画像を診断したり、拠点病院の医師らの研修、国内外の抗がん剤に関する情報収集も行う。13日に国立がんセンターを視察した川崎二郎厚労相は「がん治療の水準は知事にとっても大きな課題。 国立がんセンターが蓄えてきたノウハウや医療技術を情報センターを使って地方に伝えていきたい」と語った。(平成18年1月16日 毎日新聞)
自治体病院、自力で黒字はわずか8%
全国の自治体病院のうち、補助金などに頼らず実質的な営業黒字を確保しているのは、全体の8%程度しかないことが、日本政策投資銀行の分析でわかった。補助金を含めて経常黒字を確保している病院は4割近くまで増えるが、累積赤字は増加傾向だ。自治体病院は「へき地医療など民間ではできない分野を担っている」(総務省)だけに、経営の効率化が求められそうだ。
政策投資銀が03年度に1000あった自治体病院について、地方公営企業決算をもとに分析したところ、実質的に営業黒字なのは82病院しかなかった。大半が診療報酬など本業の収入では、必要経費をまかなえない状況だ。03年度の地方公営企業決算によると、自治体や国からの補助金で経常黒字の病院は389と4割近くまで増えるが、6割はなお赤字。病院事業全体の経常赤字額は合計で1400億円近くに達する。 補助金に当たる病院事業会計への他会計からの繰入金は、全体で5451億円だった。
政投銀は、自治体ごとの一般財源の規模を表す「標準財政規模」に対する繰入金の比率も分析した。平均では3.4%になり、高い自治体では15%に達するところもあった。 公共事業や福祉など全体の行政活動に必要な財源のうち、病院事業支援のためだけに15%を割いていることになり、財政負担が大きいことを示している。
診療報酬の引き下げや地方財政改革による補助金の削減が進めば、「自治体病院の経営はさらに厳しさを増す」(政策投資銀政策企画部)と見ている。(平成18年1月15日 朝日新聞)
「胆汁酸」やせる効果
肝臓でつくられ、食事のときに腸に流れ出る胆汁の成分が、エネルギーの消費を活発にさせる働きを持っているという研究結果を、仏ルイ・パスツール大の渡辺光博研究員らが動物実験などで示し、英科学誌ネイチャー電子版で発表した。新しいやせ薬の開発につながる可能性も考えられる。渡辺さんらが注目したのは胆汁の主な成分である胆汁酸。脂肪分の多いエサと一緒にマウスに与えると、与えないマウスと比べて体重の増加が抑えられた。体の組織を比較すると、褐色脂肪でエネルギーを盛んに消費していた。遺伝子操作したマウスなどを使ってさらに分析すると、胆汁酸は褐色脂肪細胞の中にある酵素に働きかけるなどして、エネルギー消費などにかかわるホルモンの働きを活発にしていた。人の筋肉の培養細胞で調べると同じ働きが見られた。
胆汁酸はコレステロールを材料につくられ、小腸で脂肪を吸収する働きを助けている。胆汁酸そのものを人が摂取すると、悪玉コレステロールの値が上がってしまうので、直接、薬にするのは難しいが、渡辺さんは「胆汁酸と同じような働きをする物質を特定できれば、肥満を防ぐ薬につながる可能性がある」と話す。(平成18年1月13日 朝日新聞)
診療報酬、心臓移植など公的医療保険の適用対象に
厚生労働省は11日、06年度診療報酬改定方針を中央社会保険医療協議会(中医協)に示した。医療技術の評価に関し、心臓移植、脳死肺移植、脳死肝臓移植、膵臓移植を新たに公的医療保険の適用対象とするとともに、臓器提供施設での脳死判定や脳死判定後の患者の医学的管理について、診療報酬の対象とする方針を盛り込んだ。脳死移植に関し、97年に臓器移植法が施行されて以降、通常の医療として普及が進んだと判断した。 また、移植を行う医療機関、移植を受ける患者の双方の経済的負担を少なくし、移植の普及をはかる狙いも込められており、厚労省は今後、高度先進医療専門家会議の議論も踏まえて検討を進める考えだ。臓器移植のうち、現在医療保険の対象となっているのは腎臓移植、生体肝移植、眼球移植に限られ、他の移植は原則として全額が患者の自己負担となっている。厚労省によると、例外的に混合診療を認めている「高度先進医療」で心臓移植を受けた場合、患者の自己負担分は約300万円だが、医療保険が適用されれば自己負担額は約90万円以下に収まる見通しだという。厚労省はこのほか、高齢者の入院日数を短縮し、在宅医療を推進するため、「在宅療養支援診療所」(仮称)制度を創設する方針も打ち出した。地域の診療所が病院と連携し、24時間体制で往診や訪問看護を可能とする体制を整えた場合、診療報酬を手厚くする方針だ。(平成18年1月12日 毎日新聞)
薬局に行かず薬受け取り、在宅医療推進へ
厚生労働省は、自宅で治療を受けている患者やその家族が薬局に出向かなくても薬を受け取れるよう制度を見直す方針を固めた。今の仕組みでは、薬をもらうには一度は薬局に行かないとならないが、医療費抑制をめざす厚労省が在宅医療促進のために見直すことにした。早ければ06年度中に実現する見通しで、体が不自由な患者や家族にとっては便利になりそうだ。薬剤師法は、販売や譲り渡しを目的とした薬の調剤ができる場所を原則として薬局に限っている。調剤には処方箋の確認が含まれるとされている。通院が難しい患者には、医師の指示の下、患者の家での服薬指導などが認められているが、処方箋の確認は薬局でないとできないため、結局は患者や看護する家族が薬局に行かなければならないのが実情だ。このため、厚労省は薬剤師法か関連省令を改正して、薬局以外でも処方箋の確認を認める考え。ただし、薬の調合作業は衛生上の観点からこれまで通り薬局のみで扱うこととする方針だ。見直されれば、例えば、往診した医師に書いてもらった処方箋を患者が薬局にファクスで送ると、薬剤師が薬局で調合した薬を持って患者宅を訪問し、処方箋の原本を確認して薬を渡すことができるようになる。医師や薬剤師の指導による薬物療法が自宅でも受けやすくなることで、がんなど終末期医療のあり方が変わる可能性もある。また、在宅医療に限らず適用される方向のため、一人暮らしで重い風邪をひいたり、家族全員がインフルエンザにかかったりした場合にも、医師による診察から薬の受け取りまで、外出せずに受けられるようになる。
現在、薬剤師が患者宅を訪問しての服薬指導は医療保険の対象だが、交通費は患者が負担。患者宅で処方箋の確認を認めた場合の費用負担のあり方は今後検討する。
厚労省は、医療費の伸び抑制のほか、患者の生活の質(QOL)向上のため、在宅医療の環境整備を進めており、今回の見直しもその一環だ。(平成18年1月12日 朝日新聞)
在宅サービス使う障害者 増加の見通し
入所施設から在宅への移行を促す障害者自立支援法が今年4月に施行されるのに伴い、ホームヘルプや作業所などの在宅生活を支援するサービスや、グループホームの利用者数が増える見通しだ。推計では、障害者の自宅をヘルパーが訪ねて介護する「訪問系サービス」、就職支援や自立訓練を行う作業所などの「日中活動系サービス」、入所施設のほか、障害者が共同生活を送るグループホームやケアホームなどからなる「居住系サービス」に分けて、2011年度の利用者を見積もった。障害者によっては、2種類以上のサービスを利用するケースもある。訪問系サービスの利用者数は、今年度の9万人から16万人に、日中活動系サービスも、30万人から47万人にそれぞれ増加する。居住系サービスは、グループホームとケアホームの利用者が計3万人から9万人へ増える一方、施設入所者は22万人から16万人に減る見通しだ。厚労省は近く、将来推計を踏まえ、基盤整備の基本指針を策定する方針。指針に基づき、各都道府県、市町村も来年度中に障害福祉計画を作り、サービス供給体制を整える。(平成18年1月11日 読売新聞)
新型インフルエンザ、満員電車の通勤が感染加速
新型インフルエンザが出現した場合、満員電車での通勤が感染の広がりを速くし、患者数も増やすとのシミュレーション結果を11日、東京大生産技術研究所と国立感染症研究所の研究者が共同で発表した。通勤電車の運行を停止すれば、感染者数が3割程度減るとの結果も出ており、発生時の対策をどうすべきかの参考になりそうだ。新型インフルエンザの広がりについては、多くのシミュレーションがあるが、通勤の影響を調べたのは初めてという。合原一幸・東大教授らは、国勢調査結果に合わせ、満員電車で通勤する会社員や、学校へ通う子供などが住む、人口約80万人の都市を想定。新型インフルエンザは、通勤電車内と職場、学校、家庭などで他人にうつると仮定し、感染が広がる日数や患者数などを試算した。その結果、通勤電車の影響を考えなければ、最初の患者が出てから1日あたりの患者数が最大となるまでには約50日かかり、延べ患者数は四十数万人になると推計された。ところが、通勤1回で感染する確率を、仮に「10万分の5」と見積もると、感染は加速して、1日あたりの患者数は十数日でピークに達し、延べ患者数は50数万人に増えた。患者数が人口の1%に達した時に満員電車の運行を禁じると、ピークまでの日数は変わらないが患者数は30数万人まで減るとの結果も出た。感染拡大の期間が長いほど余裕を持って対策がとれるため、期間の推定は重要だとされる。合原教授は「電車の運行停止は実現できないかもしれないが、今回はそうした政策判断のための基礎資料を示した。時差通勤や、電車内の換気の改善などでも一定の効果は出ると思う」と話している。新型インフルエンザに関し厚生労働省は、最悪の場合、国民の25%が感染し、1300万人から2500万人が医療機関で受診すると予測している。(平成18年1月11日 毎日新聞)
足の付け根圧迫、1日1キロ歩けば筋力アップ
足の付け根をベルトで圧迫(加圧)し、1日わずか1キロ・メートルほど歩くだけで、3週間後には足腰の筋力が10%も上昇することが、首都大学東京の安部孝教授(身体運動科学)らの研究でわかった。高齢者の効率的なトレーニングとして期待できそう。米国応用生理学誌2月号に掲載される。加圧によるトレーニング法開発者の佐藤義昭氏らとの共同研究で、教授らは大学生18人を2グループに分けた。一方は、足の付け根を幅5センチほどのベルトで圧迫し血流を制限した状態で、もう一方は何も付けずに、休憩をはさみながら10分程度、毎日2回歩いた。歩行は大またで、時速約3キロ・メートルのゆっくりしたペース。3週間後、ベルトを締めたグループの太ももの周囲は2センチ増加。太ももの筋肉量、筋力はそれぞれ6%、10%増加した。血液を調べると、運動の強度に比例して増える成長ホルモン量が、血液1ミリ・リットル当たり1ナノ・グラムから13ナノ・グラムに上昇。激しいトレーニング後の成長ホルモン量の30ナノ・グラムと比較して極めて効率的であることが確認された。安部教授は「50歳を超えると足の筋力は若者と比べ30%以上減る。筋力を維持するには、強い負荷をかけて鍛えるのが一般的だが、加圧トレーニングならその必要がない」と話している。(平成18年1月11日 読売新聞)
がん治療に遺伝子診断
乳がん患者に使う抗がん剤の効果や、白血病の治療薬の副作用を、遺伝子診断で事前に予測できることがわかり、財団法人癌研究会有明病院(東京都江東区)が患者の個性に合ったがん医療を今年から本格的に進める。 ヒトの遺伝子と薬の効果に関する研究は進んできたが、確実なデータは少なく、がんでの臨床応用は全国的にも先駆的なものになる。同会癌研究所の三木義男・遺伝子診断研究部長らは、乳がん患者51人の協力を得て、治療前に少量のがん細胞を取り出して約2万1000種類の遺伝子の働き方を網羅的に調べた。乳がん用に広く使われる抗がん剤パクリタキセル(商品名タキソール)が15人で良く効き、36人は効果が低かった。
分析の結果、3種類の遺伝子の働き方を調べれば、効くかどうかを51人全員で判定できることがわかった。判定の確実性が高いため、臨床応用に適しているという。事前判定ができると、抗がん剤でがんを小さくして手術をするという治療方針が立てやすい。効かない人には別の抗がん剤を使うなど選択肢がある。また、慢性骨髄性白血病の治療薬イマチニブ(商品名グリベック)についても、血液中の二つの遺伝子の型を調べれば、白血球の一種の好中球が減少する副作用が出やすい人を事前に予測できることがわかった。三木部長らは、がんが転移しやすいかどうかの予測などに遺伝子診断を使う研究も進めている。これらの成果をもとに有明病院では遺伝子診断を応用したがん治療に取り組む。まず、乳がんの抗がん剤の効果予測について約100人の患者の協力を得て、正確な診断のための検証を進める。遺伝情報を扱うことに倫理的問題もあるため、遺伝相談に詳しい医師も配置している。有明病院の武藤徹一郎院長は「研究と臨床を結びつけて患者さんに合った医療を進めたい」と話している。(平成18年1月10日 朝日新聞)
77人過去に感染? 茨城、埼玉の鳥インフルエンザ
高病原性鳥インフルエンザ問題で、厚生労働省は10日、茨城、埼玉両県の養鶏場の従業員ら計77人が過去に感染していた可能性があると発表した。毒性の弱いH5N2型で発症者はいなかった。体内にウイルスが残っている段階で通常のインフルエンザウイルスと混じり合うと、新型インフルエンザに変わる可能性も否定できないため、厚労省は「通常のインフルエンザにかかった場合は養鶏場での作業を避けてほしい」と呼びかけている。中国やカンボジアなど海外では毒性の強いH5N1型で鶏から人に鳥インフルエンザが感染した例が相次いでいるが、毒性が弱く発症しにくいH5N2型については、実態はあまり知られていなかった。国立感染症研究所は「H5N2型の人への感染の可能性が報告されたのは世界で初めて」としている。鶏の感染が確認されている茨城と埼玉の養鶏場34カ所の従業員ら353人の血液を採取し、鶏との接触などがない茨城県職員31人と比べたところ、茨城の従業員ら70人、埼玉の従業員7人は血液中の抗体値が高く出た。ただ、ウイルスは検出されておらず、感染を断定することはできないという。厚労省では今回の調査結果から、H5N2型は人に感染しても、健康上の影響は小さいとみている。(平成18年1月10日 朝日新聞)
脳腫瘍手術に新技術
がんだけに集まる色素をレーザー光で光らせて、脳腫瘍の取り残しを可能な限り小さくする新しい外科手術法を、東京医科大学の秋元治朗講師(脳神経外科)らが開発した。脳腫瘍の再発を防ぐ手法として期待される。 脳腫瘍は外見上、脳の正常細胞と区別しにくい。がんの取り残しが少なくなく、再発のおそれがつきまとう。 一方で、正常細胞を傷付けると、言語や運動機能などの後遺症が出る懸念があった。そのため、がん細胞だけを正確に切除する方法が求められていた。新手法は、がん細胞に代謝されず、蓄積しやすい葉緑素由来の色素「レザフィリン」を、手術の12時間前に患者に注射。赤色レーザー光を照射するとがん細胞だけが赤く光る。 光った部分のみを切除していく。肉眼に頼っていた従来の方法に比べ、がん細胞の取り残しが少ない。直径が4〜7センチと大きい脳腫瘍患者13人を、この手法で手術したところ、10人は社会復帰が可能となった。 3人が術後7か月までに亡くなったが、うち2人は再発した患者で治療が難しい症例だった。(平成18年1月8日 読売新聞)
たんぱく質解析、実用重視へ、病気に直結の数百種に絞る
文部科学省は、来年度からがんやアレルギーなど病気の発症に深くかかわり、医薬品開発などに結びつくたんぱく質の立体構造の解析を本格化させることを決めた。これまで約2700種類のたんぱく質の基本構造を単純なものから解明してきたが、今後は病気に直結する重要たんぱく質の解析に絞る。数百種類を5〜10年で解析し、競争の激しいこの分野で世界をリードしたい考えだ。生物のたんぱく質は約30万種類と言われるが、類似物質も多く、基本的な構造は約1万種類。日本は、このうち3000種類の解析を、2002年度から年間約100億円を投入し、5年計画で目指してきた。病気と関連の深いたんぱく質には、解析の困難なものも多い。来年度からの新計画では、こうしたたんぱく質に狙いを定める。現在の解析の主力となっている核磁気共鳴装置(NMR)や放射光施設(スプリング8)を改良して、分析能力を増強する。解析の対象は、医薬の専門家らが病気にかかわるたんぱく質として抽出した2800種類の中から数百種類に絞り込む。食品開発など、医学以外の分野でも、実用に結びつくたんぱく質を選び出し、解析を加速させる。また、病気の原因となるたんぱく質に結びついて薬効を発揮する化合物を探索しやすくするため、たんぱく質の構造と化合物の構造を比較するデータベースを整備。探索時間を数年から数日に短縮する。化合物自体も10万種類を保管し、企業などに活用してもらう。基本構造の解析で日本に後れを取った米国は、2005年6月から、病因たんぱく質に狙いを定めた解析に取り組んでいる。
*たんぱく質:生命の設計図とされる遺伝子の情報をもとに生体内で作られ、生命活動を支えている。筋肉を動かしたり、食べ物を消化したりするのも、たんぱく質の働きだ。病気に関係するたんぱく質の構造がわかれば、その働きを調節する薬の設計に道が開けると期待されている。(平成18年1月8日 読売新聞)
生活習慣病、保健指導を民間に委託
厚生労働省は来年度から、健康診断で生活習慣病のリスクが高いと判断された人に対する個別の保健指導を民間事業者に委託する方針を決めた。生活習慣病対策は、食事や運動など生活改善が不可欠だが、保健所などの保健師だけでは数が不足し十分な指導が行えないため、民間の管理栄養士や健康運動指導士に委ねる。専門家による検討会を設置し、委託先の事業者の基準を作成する。生活習慣病の中で、特に肥満症、糖尿病、高血圧症、高脂血症を放置すると脳卒中や心筋梗塞などに進展する可能性が高く、早い段階でリスクの高い人を発見し、生活習慣を改善してもらう必要がある。しかし、20歳以上の健康診断受診率は約6割にとどまり、さらに受診しても事後の指導につながっていないケースが多い。同省の対策はこうした事後の指導に重点を置くもので、医師にかかる患者は別枠。来年度予算案に1億8420万円を計上し、試行的に5都道府県で、20〜39歳の約5万人を対象に問診票による健康チェックを実施し、リスクが高い人には健康診断を受けてもらう。「予備群」とされた場合、民間の病院やフィットネスクラブの管理栄養士、健康運動指導士、スポーツプログラマーらが食生活の改善や運動を指導する。同省によると、生活習慣病有病者数(推計)は、糖尿病が約740万人、高血圧症が約3100万人、高脂血症が約3000万人。個別指導を行う保健師は全国に約4万人しかおらず、都市部は特に不足している。03年度の医療費総額31兆5000億円のうち、生活習慣病が約3割を占めており、同省は今回の取り組みによって中長期的な医療費の抑制を目指す。(平成18年1月8日 毎日新聞)
国保保険料、年金から天引き
厚生労働省・社会保険庁は2008年度から、公的年金の受給者が国民健康保険に加入している場合、国保の保険料を年金から天引きして徴収する仕組みに変える。年金を受け取った後、国保の保険料を改めて納める仕組みでは加入者の手続き忘れなどで未納が起こりやすいためだ。年金から直接天引きし、拡大する未納を減らし、医療保険の財政悪化を防ぐ。政府は医療制度改革の一環として08年度から75歳以上の高齢者が入る新医療制度を作り、その保険料を加入者の年金から天引き徴収する。これに合わせて、新制度の対象とならない74歳以下の国保加入者に対しても年金からの保険料天引きを始める。老齢年金だけではなく障害・遺族年金を受け取っている加入者も対象とする。(平成18年1月7日 日本経済新聞)
感染症専門の薬剤師を認定へ
薬剤耐性菌の発生など、医療現場で切実な問題となっている感染症に対応するため、医療機関に勤務する薬剤師でつくる日本病院薬剤師会(全田浩会長、会員約3万4000人)が、「感染制御専門薬剤師」の認定を始める。耐性菌を発生させにくい抗菌薬の使い方などを熟知し、医師に助言できる人材を育てる狙い。15日に初の認定試験を行い、年度内には専門薬剤師が誕生する。入院患者は病気や手術などで体力が低下しているため、耐性菌などが広がると重症化して死亡する恐れも高い。また、3年前に世界で流行した新型肺炎(重症急性呼吸器症候群=SARS)は、病院内から感染が広がった。新型インフルエンザの発生が世界で警戒される中、院内感染対策は国内の病院にとっても最重要課題の一つとなってきた。感染制御専門薬剤師には、抗菌薬の適正使用や医療器具の消毒など、院内感染を防ぐための知識や技術が求められる。高い水準を維持するため、認定の有効期間は5年とし、同会などが開く講習会で所定の単位を履修しないと、更新が認められない。15日の初試験には193人が挑む予定。同会では「毎年100〜200人を認定し、10年後には、必要な病院には一人ずつ配置できるようにしたい」(尾家重治・山口大病院助教授)としている。同会は今後、がんやHIV(エイズウイルス)などの専門薬剤師の認定も開始する予定。高度化・細分化を続ける医療現場で、高い専門性を持った薬剤師の育成を目指す。(平成18年1月7日 読売新聞)
少子化対策、3歳まで育児手当、6歳児まで医療費無料検討
政府は4日、少子化対策の一環として、3歳までの子どもを持つ保護者を対象とする育児手当制度を新設し、さらに6歳児までの医療費を全額無料化する方向で検討に入った。育児手当は月額1万5000円を軸に調整する方針。経済力の低い若年夫婦層に重点を置き、財政支援により少子化に歯止めをかけたい考えで、猪口邦子少子化担当相を中心に財務、厚生労働両省と調整を進める。同制度が設けられれば、乳幼児・児童への助成制度としては1972年の児童手当以来となる。育児手当は、現行の児童手当(第2子まで月額5000円、第3子以降同1万円)に加えて助成するもので、児童手当制度を参考に所得制限を設ける意向。児童手当は来年度から、支給対象を小学3年以下から同6年以下に広げ、所得制限も一般のサラリーマン家庭で860万円未満(現行780万円未満)に引き上げる予定になっている。一方、医療費の病院での窓口負担は現在、3歳未満が2割、3歳以上が3割。乳幼児医療費については地方自治体が独自に助成制度を設けているケースも多いが、この本人負担分を国が全額助成する考えだ。政府の試算では、育児手当制度に年5400億円、乳幼児医療の全額助成に同3000億円の計8400億円の財源が必要となる。ただ、新たな財政支出に対し財務省が難色を示し、育児手当については、乳幼児医療費への負担が減る地方自治体に一定の財政支出を求める案も浮上。今後、関係省庁で調整し、07年度からの導入を目指す。昨年12月に公表された05年の人口動態統計(推計値)と国勢調査の速報値で、日本の人口が初めて減少していることが判明し、政府は危機感を高めているが、少子化対策に「即効薬はない」(小泉純一郎首相)として決め手を欠いているのが実情だ。一方で、国の社会保障給付費全体に占める児童・家族関係給付費の割合は4%程度と少なく、新たな財政支出による対応策を模索していた。(平成18年1月5日 毎日新聞)
指導医、研修制度に「満足」1割
04年度に導入された卒後臨床研修などにより、研修医の待遇に対する満足度が大幅に改善していることが全日本医学生自治会連合(医学連)の調査でわかった。新しい制度について研修医の約半数は「満足」としている。しかし、研修医を指導する指導医には「満足」が約1割にとどまるなど不満が強く、医学連は「指導医が十分な指導に取り組める体制整備が必要」としている。全国約200の医療機関の研修医と指導医を対象に昨年7〜11月、アンケートを実施。研修医712人、指導医925人から回答を得た。研修医の収入は手取りで月平均28万円。5年前の前回調査では0〜10万円が7割以上を占め、「アルバイトで研修に集中できない」などの声が出ていた。研修医に一定収入を保証した新制度の効果が裏付けられた形だ。「忙しすぎて休養がとれない」と答えた人も前回は約4割いたが、今回は5%程度に減った。一方、指導医は、勤務医としての業務のかたわら研修医を教えているが、指導のため通常業務が軽減されるなどの「業務保障」があるかどうかについては、8割以上が「まったくない」と答えた。「指導する時間は十分か」の問いにも「不十分」が6割に達した。「指導医に対する経済的な補償」についても「不十分」と「まったくない」と回答した人が、合わせて全体の8割を超えた。(平成18年1月5日 朝日新聞)
認知症予防の効果立証 写経で脳イキイキ
認知症の改善や防止策として、脳を活性化するのに最も効果が高いのは「写経」であることが、川島隆太・東北大学教授と学研の共同研究で分かった。川島教授らのグループが、平成15年から翌年にかけ、仙台市内の高齢者延べ1000人を対象に、オセロゲームなど脳を活性化させるのに役立つとされる160種類を実験し、大脳の血流量の変化を計測。作業中に、前頭葉の左右と、頭頂葉の左右の変化を調査した。作業前の平穏時を基準とし、脳が最高に活性化しているプラス3から、脳がリラックスしたマイナス3までの11段階で判断した。その結果、写経の作業中に、前頭葉、頭頂葉の左右で、いずれも最高値のプラス3を記録。オセロゲームは、頭頂葉に変化がなく、前頭葉にマイナス3の値が出て、リラックスグッズであることが判明した。学研は、実験結果を冊子にして、特別養護老人ホームなどに配布。今年からは東京都府中市の高齢を対象に、研究成果を活用しながら予防効果の調査に乗り出す。(平成18年1月4日 産経新聞)
ビフィズス菌、インフルエンザ予防に効く!
ビフィズス菌を多めに取る高齢者は、免疫機能が高まり、インフルエンザウイルスに感染しにくいという研究結果を、森永乳業栄養科学研究所(神奈川県座間市)がまとめた。今年3月に開かれる日本農芸化学会大会で発表する。茨城県内の介護老人保健施設に入所している高齢者27人(平均年齢86歳)に2004年11月から毎日、ビフィズス菌の一種「BB536」を1000億個含む粉末(2グラム)を飲んでもらった。インフルエンザ流行のピークが過ぎる昨年3月末まで飲み続けたグループ(13人)には、飲む前に比べて、白血球の殺菌機能が高まる傾向が見られ、インフルエンザ発症者がいなかった。一方、1か月半で飲むのをやめたグループでは、14人中5人が発症した。光岡知足、東大名誉教授は「免疫力の下がった高齢者にとって、インフルエンザにかかりにくくなる効果が期待できる。ただ即効性はないので、流行の1か月以上前から飲み続けることが望ましい」と話している。(平成18年1月4日 読売新聞)
65歳以上の介護保険料、4月から月1000円負担増
65歳以上の高齢者が支払う毎月の介護保険料が2006年4月の改定で、全国平均で1000円程度引き上げられる見込みであることが厚生労働省の調べで分かった。全国平均は現行の3293円から4300円程度となり、約3割負担が増す。高齢者の増加などで介護サービスの利用が増えたためで、引き上げ率は前回の03年度改定の13%を大きく上回る。介護保険は利用者負担(1割)を除いた給付費の50%を公費、32%を40―64歳の保険料、18%を65歳以上の保険料で賄っている。このうち、65歳以上の人が払う保険料は要介護者への介護サービスの提供量に応じ3年ごとに見直すことになっており、市町村ごとに異なる。(平成18年1月1日 日本経済新聞)
|